#紅い血液の悪魔
Photo

Devil of Scarlet Blood
#illustration#touhou project#touhou fanart#flandre scarlet#touhou flandre#gouyoku ibun#submerged hell of sunken sorrow#東方#touhou#東方project#フランドール・スカーレット#フラン#フランドール#剛欲異聞#devil of scarlet blood#紅い血液の悪魔#7月4日はフランドールの日#flandre day#vampire girl#石油の海#sea of oil
138 notes
·
View notes
Quote
相沢 友子(あいざわ ともこ、1971年5月10日 - )は、日本の脚本家。脚本家以前はシンガーソングライター、女優として活動していた。血液型はB型。東京都出身。
略歴・人物
高等学校在学中より文化放送でコンサート・リポーターを務め、詞を書いていたところソニーミュージックのスタッフに歌うことを勧められ、1991年3月、19歳の時にシングル「Discolor days」にて歌手デビュー[1][2]。その後、ホリプロ所属の女優としても活動しながら、4枚のアルバムを発表している。シンガーソングライターであり、加藤いづみとも親交が深く、アルバムにも楽曲を提供している。
デビューから長らく歌手兼女優であったが、ソニーとホリプロとの契約を解消し、フリーとなる。フリー直後に、ホリプロ時代のマネージャーに「小説を書き、賞を狙ってみては?」と勧められ、1999年に第15回太宰治賞の最終候補作に小説『COVER』がノミネートされた[2]。当時、相沢は「その当時は藁にもすがる思いでした。音楽の道がうまくいかなくて、事務所との契約が切れて、本当に一時期何もしてない時期があって。私はほぼ歌詞しか書いていなかったので、やれることといったら書くことだなと思って、小説『COVER』を書いた」と述懐している[2]。その結果をもって、前述のマネージャーの紹介で共同テレビジョンの小椋久雄に脚本執筆の指導を受け[1]、2000年に『世にも奇妙な物語』で「記憶リセット」で脚本家デビューした[2]。
2003年にアメリカ合衆国で発生した大停電を題材とするドキュメンタリー『ニューヨーク大停電の夜に』(NHKハイビジョン、構成・源孝志)で語りを務める[3]。その後、同事件をエピソードとして、2005年に源孝志と共同で映画『大停電の夜に』の脚本を手がけた[4]。
2009年に放映された『重力ピエロ』の脚本を手がけたきっかけについて、相沢がパーソナリティーを務めていたラジオ番組の常連リスナーで、伊坂幸太郎の担当編集者から、「素晴らしいからぜひ読んでほしい」と小説を送付され、即座に相沢が映像化を申し入れたとしている[5][注 1]。相沢によれば、「物語の肌触りは軽やか。けれど、世の中的な常識に人が流れされて生きていることへのロック魂が隠されていることに共感した」という[6]。伊坂は映像化に積極的でなかったが許諾し、最大の魅力を損なうことなく小説のコンテクストをそのまま映像に置換しようと努めたという[5]。なお、『読売新聞』の福永聖二は、「異論もあるだろうが、伊坂作品の精神を尊重しつつ、より自然な流れを作った」と評している[7]。
2013年に放送された『ビブリア古書堂の事件手帖』について相沢は、「ていねいに話を積み上げてファンタジックに作っていきたい」とし、古書業界の用語を各所に挿入するなどして、作品の世界観を伝えようとしたという[8]。また、剛力彩芽がキャスティングされたことについて、「たしかに栞子とは外見のイメージが違いますが、剛力さんは黙ってじっとしているとミステリアスなムードを持っている」とし、「彼女の“静”の部分を出すと新鮮なものになると確信できたので、栞子を剛力さんのイメージに近づけるのではなく、剛力さんが物語に寄り添っていけるような脚本を心がけ」たと述べている[8]。
2015年に放送された『私の青おに』について相沢は、「人の温かさが伝わるストーリー。高畠町の持っている風景の力強さを伝えたい」としている[9]。なお、主演で辻村莉子役を演じた村川絵梨は、「脚本を読んだ時から、すごく自分と重なる部分があって。そういう意味ではとても自然に莉子という役に向き合うことができました」と述べている[10]。
リアルサウンドのインタビューによれば、相沢はト書きに「私はうるさいぐらいに、『ここで相手を見る』とか、『ここで顔を上げる』とか、目の動きまで書く」とし、「あとは現場で好きにしていただいて構わないですけど、私のイメージはできる限り伝えよう」と演出に一任しているという[2]。また、以心伝心と言えるほど、互いに分かりあう役者や監督・演出家と仕事ができると嬉しいとし、『恋ノチカラ』で主演を務めた深津絵里に関して「天才的な役者さんですけど、びっくりするぐらい汲み取って返してくれて。自分の想像を超えてくるお芝居を役者さんがしてくれることもたくさんあります。お互いに響き合って、奇跡的に合致したときは感動しますね」と述べている[2]。
アーティストの友人に、加藤いづみや相馬裕子などがいる。
主な脚本作品
テレビドラマ
1999年
DG TV DI:GA「UNIVERSE」「SNOW KISS」「Love Things」
2000年
世にも奇妙な物語 春の特別編「記憶リセット」[11]
悪いこと「盗む」
やまとなでしこ[注 2][12]
2001年
17年目のパパへ[13]
ココだけの話「不機嫌なめざめ」
私を旅館に連れてって[注 3][14]
江國香織クリスマス・ドラマスペシャル「温かなお皿」[注 4]
2002年
世にも奇妙な物語 秋の特別編「昨日の君は別の君 明日の私は別の私」[15]
LOVE & PEACE(DVD)「君がいるだけで特別な街、特別な場所」「Thanks」
恋ノチカラ[5][16]
2003年
天国のダイスケへ〜箱根駅伝が結んだ絆〜[17]
いつもふたりで[16]
エ・アロール[18]
2004年
めだか[19]
2007年
秋の特別編「48%の恋」[20]
2008年
鹿男あをによし[5]
2010年
ギルティ 悪魔と契約した女[注 5][21]
2012年
鍵のかかった部屋[注 6][22]
2013年
ビブリア古書堂の事件手帖[注 7][8]
女と男の熱帯[23]
2014年
鍵のかかった部屋 SP[24]
失恋ショコラティエ[注 8][注 9][25]
2015年
紅雲町珈琲屋こよみ[26]
私の青おに[9]
2017年
人は見た目が100パーセント[27]
龍馬 最後の30日[28]
龍馬 最後の遺言
2019年
トレース〜科捜研の男〜[29]
2022年
ミステリと言う勿れ[30]
2023年
セクシー田中さん[注 10][30]
映画
2000年
世にも奇妙な物語 映画の特別編「結婚シミュレーター」[31]
2005年
大停電の夜に[注 4][4][32]
2009年
重力ピエロ[5][6]
2010年
東京島[33]
2011年
プリンセス トヨトミ[23]
2015年
脳内ポイズンベリー[34]
2017年
本能寺ホテル[35]
2021年
さんかく窓の外側は夜[36]
2023年
ミステリと言う勿れ[37]
配信ドラマ
僕だけが17歳の世界で(2020年、AbemaTV)[38]
金魚妻(2022年、Netflix)[注 8][39]
ラジオドラマ
LOVE = Platinum 恋愛パズル(2010年)[33]
相沢友子 - Wikipedia
3 notes
·
View notes
Text
街とその不確かな壁/君たちはどう生きるか/ジブリ・春樹・1984
最初のジブリの記憶は『魔女の宅急便』(1989年)だ。母がカセットテープにダビングした『魔女の宅急便』のサントラを幼稚園の先生に貸していたから、幼稚園の頃に見たのだ。
まだ座席指定の無い映画館に家族で並び、私は映画館の座席で親に渡されたベーコン入りのパンを食べていた。4・5歳の頃の記憶だ。
その夜、私は夢の中で魔女の宅急便をもう一度見た。私は親に、夢でもう一度映画を見たと伝えた。
『おもひでぽろぽろ』(1991年)も映画館で見たが、あまりよく分からなかった。『紅の豚』(1992年)も映画館で見た。帰りにポルコ・ロッソのぬいぐるみを買ってもらい、縫い付けられたプラスチックのサングラスの後ろにビーズで縫い付けられた黒い目があることを確認した。
『平成狸合戦ぽんぽこ』(1994年)『耳をすませば』(1995年)までは両親と一緒に見たと思う。
父はアニメに近い業界にいたため、エンドロール内に何人かの知人がいたようだった。アニメーターの試験を一度受けたそうだが、他人の絵を描き続けることは気が進まなかったらしい。
家のブラウン管の大きなテレビの台の中にはテレビ放送を録画したVHSテープが並び、ジジやトトロの絵とタイトルを父が書いていた。テレビ放送用にカットされたラピュタやナウシカを私は見ていて、大人になってから初めて見たシーンがいくつかあった。
“家族で映画を見る”という行事はジブリと共にあった。ジブリ映画の評価は今から見て賛否両論いくらでもあればいいと思うが、批評も何も無い子ども時代に、母がとても好きだった魔女の宅急便や、戦争は嫌いだが戦闘機が好きな父と紅の豚を見られたことは幸福な年代だったのだと思う。
評価が何も確定していない映画をぽんと見て、よく分からなかったり面白かったりする。
親は『おもひでぽろぽろ』を気に入り、子どもにはよく分からない。父からは昔の友だちが熱に浮かされたように「パクさんは本当に凄いんだよ」と言い続けていたと聞かされた。
※
大人になった私は『ゲド戦記』(2006年)を見て「面白い映画に必要なものが欠けているこの作品を見ることにより今までに見たジブリ映画のありがたみが分かった」とぐったりし、『崖の上のポニョ』(2008年)を新宿バルト9で見て、全然楽しめず、新宿三丁目のフレッシュネスバーガーで「神は死せり!」と叫んでビールを飲んだ。
2020年には『アーヤと魔女』の予告編に驚愕し、『モンスターズ・インク』(初代、2001
年)からずっと寝てたのか!?と罵倒した(見ていない)。
私が持っていたジブリという会社への尊敬は過去のものになり、多彩な才能を抱えていたにもかかわらず明らかにつまらないものばかり作る血縁にしか後任を託せない状況にも嫌悪感を抱いた。
期待値は限りなく低く、『君たちはどう生きるか』を見ようかどうか迷っている、とこぼしたら「見て文句も言えるからじゃあまあ一緒に行く?」という流れになり、見た。
あまりにも期待値が低かったため、文句を言いたくなるような作品ではなかった。私は2023年、もっともっとつまらない映画を何本も劇場で見ている。つまらない映画を劇場で見ると、もう2度と見なくて良いという利点がある。
『君たちはどう生きるか』の序盤、空襲・火災・戦火で街が焼ける場面、画面が歪で、不安で、安定感がなく、私はホッとしていた。綺麗に取り繕う気のない、表現としての画面だった。
複数の場面に対してセルフ・パロディーであるというテキストを読んでいたが、私にはあれらはオブセッションに見えた。小説家でも芸術家でも脚本家でも、何を見ても何度も同じことを書いているな、という作家に私は好感を持っている。少なくとも、いつも結局テーマが同じであることは減点の理由にはならない。
『君たちはどう生きるか』になっても高畑勲の作品に比べればどうにも女性の人格が表面的で、天才はこんなにもご自身の性別をも超えて何もかもわかり物語に落とし込めるのかと感激した『かぐや姫の物語』(2013年)に比べてしまうと胸の打たれかたが違うのだけれども、でも私は取り憑かれたテーマがある作家のことが、いつも好きだ。
スティーブン・スピルバーグは『フェイブルマンズ』(2022年)でもう大人として若い頃の母親を見つめ直せていたように思うが(フェイブルマンズで取り憑かれていたのは別のものだ)、
宮崎駿は小さい頃に一方的に見つめていた母に取り憑かれ、母の内面には踏み込めないまま、少年・子どものまま母を見つめ続け、自分が老年の大人として若い母親を見つめ直す気は無い。
そして、母親の方を少女にして映画の中に登場させる。しかも「産んでよかった」という台詞を創作する。
貴方は大人なのにずっと子どものままで母親に相対したいのですか、と思いはするものの、子どものままの視線で母を見つめ続けたいのなら、それがあのように強烈ならば、それがオブセッションなら全くかまわないことだと思う。
最初に屋敷に出てきた7人のおばあちゃんがあまりにも妖怪じみているので驚いたが、あれは向こうの世界とこっちの世界の境界にいるかた達という理解で置いておいてあげよう。
それにしてもアオサギが全く可愛くもかっこよくも無いことに最後まで驚いていた。頭から流れる血液も、赤いジャムも気持ちが悪い。途中途中、激烈に気色が悪い。世界や生き物は気持ちが悪く、性能の良い飛行機みたいに美しくは無い。カエル、内臓、粘膜、血液、食物もグロテスクだ。嫌悪ではない、全部生々しい。生々しく、激烈だ。その生々しさを必要としたことに胸をうたれた。
塔の中のインコについて、愚かな大衆だとかジブリはもう人が多すぎてしまったんだとか商業主義的な人間の表現だというテキストも読んだのだけど、私はあのインコたちがとても好きだった。
インコたちは自分達で料理をして、野蛮で、楽しそうだった。終盤、緑豊かな場所にワッセワッセと歩いていくインコさんが、「楽園ですかねぇ」「ご先祖さまがいますねぇ」と言ったようなことを言うシーンが面白く、可愛らしく、インコたちの賑やかな生活(時に他者に攻撃的であっても)を想像した。
私は水辺の近くをよく散歩していて、大きな渡り鳥が飛来してまた消えていくのをじっと見つめている。鳥たちがある日増えて、いなくなる。国を越えて飛んで行き、地球のどこかには居続けているのがいつも不思議だ。
映画の中で、鳥やカエルはあのように生々しく、実体をつかんでアニメーションに残すことができるのに、全てを生々しく捉える気が無い対象が残っている。どうしてもそれを残すことが寄す処なら、それはそのままでかまわない。
※
小説では、村上春樹の『街とその不確かな壁』を読んだ。
私の父は村上春樹と同い年で高校卒業後に東京へ出てきたので、『ノルウェイの森』で書かれている、まだ西新宿が原っぱだった頃を知っている。その話を友人にしたところ、『西新宿が原っぱだったというのは春樹のマジックリアリズムかと思っていた』と言っていた。
私が村上春樹を読み始めたのは及川光博が「僕はダンス・ダンス・ダンスの五反田君を演じられると思うんだけど」と書いていたの読んだのがきっかけだ(曖昧だけれども、1999年くらいか?)。
『風の歌を聴け』は家にあったので、そのまま『1973年のピンボール』『羊をめぐる冒険』『ダンス・ダンス・ダンス』を読み、その後短編集をあるだけと、『ノルウェイの森』『世界の終わりとハートボイルドワンダーランド』を読み、『ねじまき鳥クロニクル』は途中途中覚えていないが一応読み、『スプートニクの恋人』(1999年)を高校の図書館で読んだがあまり面白くないと感じた。
最近ではイ・チャンドン監督の映画『バーニング』(2018年)が素晴らしかったし、濱口竜介監督の『ドライブ・マイ・カー』(2021年)も面白かった。
『ドライブ・マイ・カー』の原作(短編集『女のいない男たち』収録)は映画を見た後に読んだが、反吐が出るほどつまらなく、気持ちが悪い短編だった。
イ・チャンドン監督も、濱口竜介監督も、「今見たらその女性の描写、気持ち悪いよ」を意識的に使っていたのだろう。『バーニング』は『蛍・納屋を焼く・その他の短編』時期の初期春樹、『ドライブ・マイ・カー』はタイトルこそドライブ・マイ・カーだけれども、ホテルの前の高槻の佇み方はダンス・ダンス・ダンスの五反田君であろう(港区に住む役者である)。
村上春樹のことは定期的にニュースになるのでその度に考えているのだけど、2023年に、フェミニズムのことをある程度分かった上で過去作を読むのはかなり厳しい気もしている。
次から次にセックスをしているし、主人公はガツガツしていない風なのに何故かモテているし、コール・ガールを呼びまくっている。
『ダンス・ダンス・ダンス』に出てくるユキは13歳の女の子で、ユキの外見・体型に関する記述はそこまで気持ち悪くはないのだが、『騎士団長殺し』に出てきた未成年の女性に対する描写はとても気持ちが悪かった(はず。売ってしまったので正確ではないのだが、あまりに気持ちが悪くて両書を比較をした)。
いくら今「この人は世界的巨匠」と扱われていても、作品を読んで気持ち悪いと思えばもう読む価値のない作家であるので、まだ読んだことがない人に読むべきとは全く思わない。
けれども、20年前に読んだ村上春樹は面白かったし、『ダンス・ダンス・ダンス』に書かれる母娘の話に私は救われたのだと思う。
最近友人に会い、「村上春樹は読んだことないんだけど、どうなの?」と聞かれたので、「春樹の物語は色々な本で同じモチーフが多い。主人公がいて、どこかへ行って、帰ってくる。戻ってきた世界は同じようでいて少し変わっている。私たちが現実だと思っている世界は世界の一部分に過ぎず、どこかでみみずくんが暴れているかもしれないし、やみくろが狙っ���いるかもしれないし、誰かが井戸の底に落ちたかもしれない。だけど主人公は行って、戻ってくる。どこかで何かが起こっていても、行って戻ってくる。一部の人は行ったっきり、帰ってこられない。」
「この世では 何でも起こりうる 何でも起こりうるんだわ きっと どんな ひどいことも どんな うつくしいことも」は岡崎京子の『pink』(1989年)のモノローグだけれども、何でも起こりうる、現実はこのまま永遠に続きそうだけれども、ある日小さなズレが生じ、この世では何でも起こりうるんだわ、という小説を次々に読みながら大人になったことを、私は愛している。日常を暮らしていると現実の全てに理由があるかのように錯覚してしまうけれども、「何でも起こりうる」世界には、本当はあまり理由がない。何か理由があると錯覚し過ぎてしまうと、公正世界仮説に囚われて、善悪の判断を間違ってしまう。
「主人公が、行って、帰ってくる」形は数えきれないほどの小説・映画の構造なので特徴とも呼べないところだけれども、『君たちはどう生きるか』もそうだし、『ダンス・ダンス・ダンス』も、『世界の終わりとハードボイルドワンダーランド』も、昔読んだ『はてしない物語』だって勿論そうだし、『オズの魔法使い』もそうで、『君の名は。』もそうだったような気がする。
『はてしない物語』の書き方はわかりやすい。
「絶対にファンタージエンにいけない人間もいる。」コレアンダー氏はいった。「いけるけれども、そのまま向こうにいきっきりになってしまう人間もいる。それから、ファンタージエンにいって、またもどってくるものもいくらかいるんだな、きみのようにね。そして、そういう人たちが、両方の世界を健やかにするんだ。」
※
『街とその不確かな壁』は春樹の長編も最後かもしれないしな、と思って読み始めたが、半分を超えるまで全然面白くなく、半分を超えてもちょっと面白いけどどう終わるんだろうこれ、の気持ちだけで何とか読み終わった。
17歳の少年のファーストキスの相手の音信が突然途絶えようと、『世界の終わりとハードボイルドワンダーランド』の世界の終わり側の話をもう一度読まされようと、どうしてそれを45歳までひっぱり続けるのか、読んでいて全然情熱を感じなかった。
イエロー・サブマリンのパーカを着た少年が何のメタファーなのかは勿論書かれていないが、春樹は昔に還りたいんだろうか?何故か「あちらの世界」から物語がこちらに、鳥に運ばれてきたみたいにするすると現れ世界を覗けたあの頃に?活発な兎が息を吹き返すように?
※
宮崎駿のオブセッションや視線は今も跳ね回っており、村上春樹の滾りは、もう私にはよくわからないものになった。
私は昔『ダンス・ダンス・ダンス』を何ヶ月もずっと読み続け、どのシーンにどんな形の雲がぽつんと浮かんでいるかも記憶していた。欲しいものだけ欲しがればいいし、くだらないものに対してどんなことを友だちと言い合いビールを飲めば良いかを知った。
岡崎京子に「幸福を恐れないこと」を教えてもらったみたいに。
4 notes
·
View notes
Text

Twitterリアタイ企画「悪魔のゾートロープ」
参加キャラクター

キャラクター概要
▽プロフィール
周防ヨシキ
誕生日…11/15
年齢…21歳
身長…186cm
体重…75㎏
血液型…B型
髪色…黒髪 インナーカラーをよく変える
瞳…ブルーグレー
出身…埼玉県
職業…大学生。心理学専攻
部活…中高は陸上部だった
好きな食べ物…おにぎり、味噌汁、卵焼き。やっぱりこれだね。
飲み物…紅茶、白湯
好きな服…綺麗めシャツやジャケット。柔らかい素材のパンツ
得意なこと…相手の表情を読む。共感する。
苦手なこと…球技が意外とダメ
音楽…なんか今どきの大学生っぽい浮ついたやつじゃないですかね?
映画…邦画とかじゃないですか?MCUは全部観てる
趣味…髪を染める、知らない食べ物を食べる。
色…青緑、白
▽性格など
・常に落ち着いた口調で感情が顔に出ないので何を考えているかわからないとよく言われる。
・本人は楽しい事好きで好奇心旺盛なので自分は明るい性格だと思っている。
・ボードゲームやリアル脱出ゲームが好き。
・自分の知らないジャンルに興味があるので、様々な職業の人に話を聞きたがる。初対面の相手でもよく話す。
・オススメされたものはその場でチェックする。勧められた本や映画もすぐ観るので重宝されている。
▽本編では
・11月の中旬、多額の借金を隠していた父が線路に飛び込み自殺。母は自暴自棄になりその日に一人で荷物も持たず家を出た。心中しようと包丁を向けてきた妹に反撃して刺し殺した後、風呂場でゆっくり息をつき「死にたくないな、」と呟き城に導かれる。
・一連の一家離散の捜査中周防は行方不明だったため、妹の殺人には関与していないと認識されている。
・妹を殺したことに罪悪感が無いわけではないが、殺人ではなく”一連の出来事”と考えておりほぼ事故や事件のつもりでいる。
妹を刺したことは有耶無耶に辛い過去として他人に話し同情を煽って自分の責任の所在を薄めている。
・結婚後は妻思いで子煩悩。本当に優しい父になりたいと思ってる。本気で。
・大学卒業後はスクールカウンセラーとして働いている。
▽関係
涼乃聖蘭(呼び→聖蘭さん)
嫁さん
▽本編
11/23

11/30
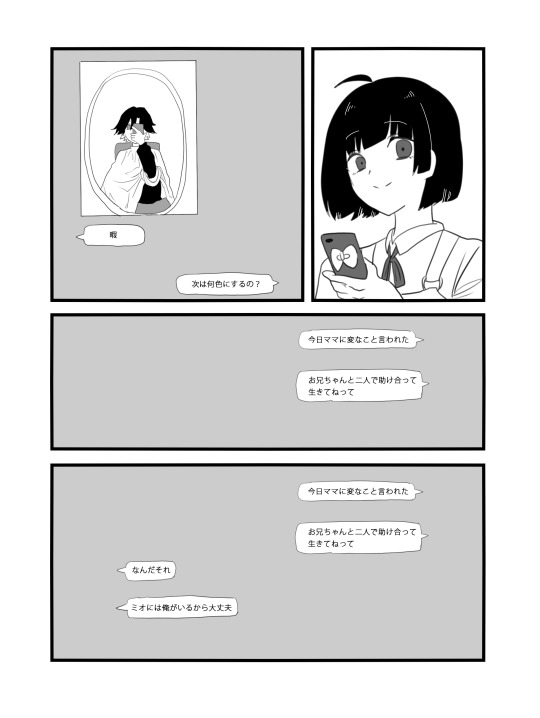

12/1



12/3

12/9

12/18




12/25



1/1






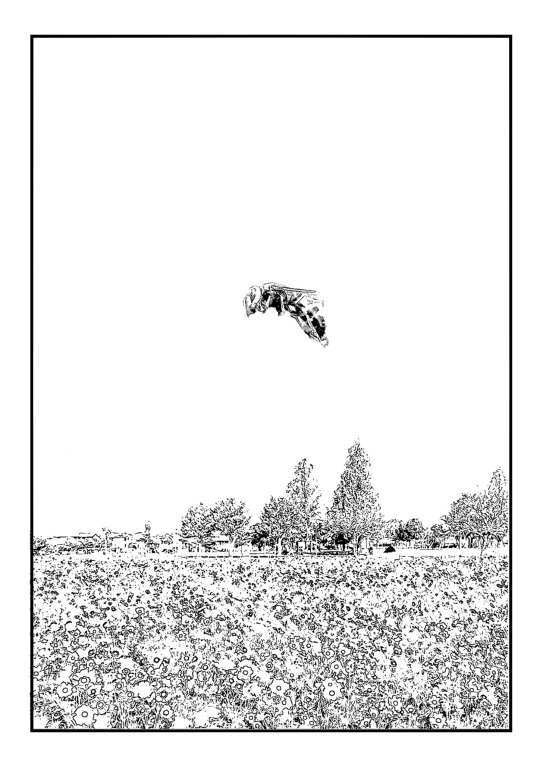

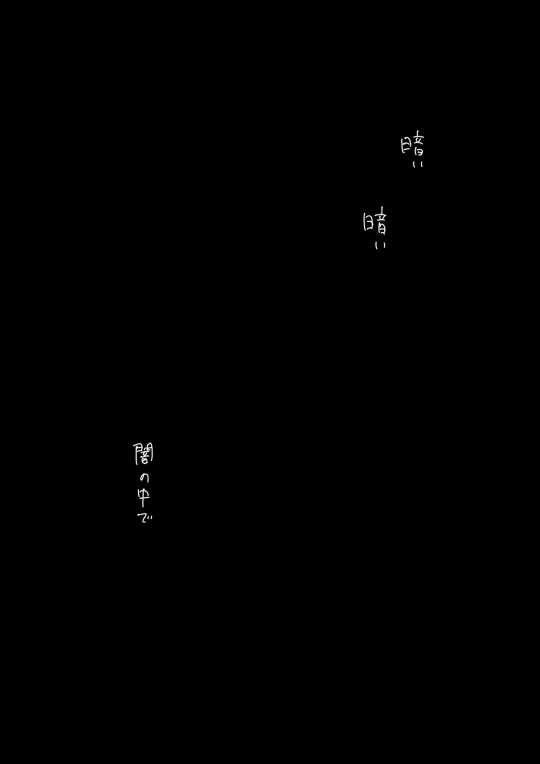
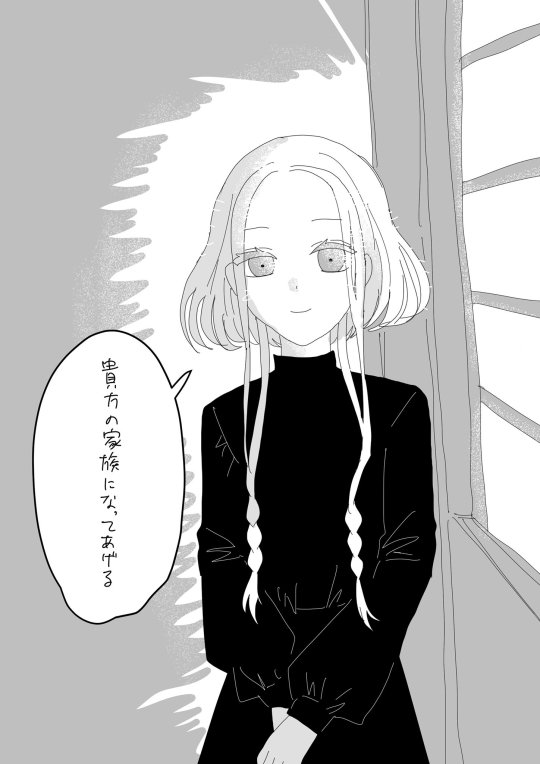
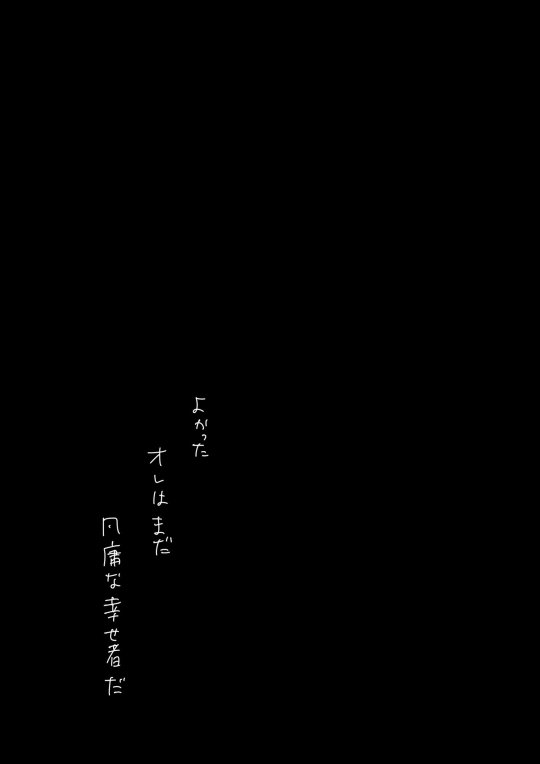
こいつ結婚してハッピーエンドってまじかよ
0 notes
Text
☆プロトタイプ版☆ ひとみに映る影シーズン3 第六話「悟りの境地」
☆プロトタイプ版☆
こちらは無料公開のプロトタイプ版となります。
段落とか誤字とか色々とグッチャグチャなのでご了承下さい。
→→→☆書籍版発売までは既刊二巻を要チェック!☆←←←
(シーズン3あらすじ)
謎の悪霊に襲われて身体を乗っ取られた私は、
観世音菩薩様の試練を受けて記憶を取り戻した。
私はファッションモデルの紅一美、
そして数々の悪霊と戦ってきた憤怒の戦士ワヤン不動だ!
ついに宿敵、金剛有明団の本拠地を見つけた私達。
だけどそこで見たものは、悲しくて無情な物語……
全ての笑顔を守るため、いま憤怒の炎が天を衝く!!
pixiv版 (※内容は一緒です。)
དང་པོ་
アラビアンナイトに、漁師と魔人という寓話がある。壺に閉じ込められていた魔人の封印を解いてしまった漁師が、「お前なんかこんな小さな壺に入る事すらできないだろう」と煽って魔人を再び封じ込める話だ。グリム童話や西遊記にも似たような物語がある。
「貴様は終わりだワヤン不動、金剛の有明が訪れる前に亡き者にしてくれる!」
この間抜けもそうだ。わざわざ暴風吹き荒れる高度三千メートルの塔外空中庭園に出て、最上の姿とやらになるため分散していた全黒煙を一身に集中させた。煙として漂い私達の体や霊魂を汚染させる方が圧倒的に恐ろしい力なのに、頭に血が上った本人は気付いていないんだ。
最上形態の金剛愛輪珠如来は十二単に似た複数人種の生皮ドレスローブと、ラスタカラーに輝く狸の毛皮の襟巻きで着飾っている。背中に千手観音のように多色の腕を生やし、その顔つきは……私の和尚様。ムナル様のご遺体から奪った物だ。
「やれやれ、悔しさに言葉もないか? ほら、ワヤン不動。我らを裏切った貴様の師匠の顔だぞ」
知ったことか。その人は既にこの世から逝去した。ていうか勝手に髪の毛生やしてるし、もはや課金のしすぎでゴチャゴチャになったアバターみたいで和尚様感ゼロだし。
「御託は不要だ。かかってこい、ケツ穴糞野郎(オンツァゲス)」
影影無窮! 私は影体を練り、自身の腕を四本に増やした。右上腕から長斧(ティグク)、神経線維塊(ドルジェ)、羂索(キョンジャク)、倶利伽羅龍王剣(プルパ)を持つ。今までこいつに破壊された物や、さっき粛清した龍王も含めた私の全法具だ。かつてない程慎重に、そして確実にこいつを滅ぼす!
ヴゥン! 先制して如来の顔面に目くらましの神経エネルギーを放った。すかさずティグクを振るうが、如来は回避。なるほど。死体を継ぎ合わせて作ったあの体は所詮器に過ぎず、奴は目でなく煙体で物事を感じ取っているんだ。
「カハハハ、ならばこうだァ!」
指先で小さな影と神経を練り、高速連続射出! チュタタタッ! これも如来は人間離れしたバック宙返りで回避。しかし奴が体制を整えようとしたその瞬間、私は既にゼロ距離で龍王剣を構えている!
「ピギャアァーーーーーッ!!!」
刺突ゥ! 如来の胸部を貫いた龍王剣が絶叫、炎を吹き上げながら奴の体内を燻製窯に変えた! 開祖バドゥクン・サンテットとの戦いで得た奥義、影縫いだ!
「ほう……」
如来は涼しい表情のまま、胸部の風穴から大量の黒煙を噴出。一方こうなる事を予習済みの私も、煙を吸わないよう息を止めたまま、影体を後部へ滑らせた。
「やれやれ、少しは賢くなったようだな。どれ、他の連中とも遊んでやろう」
如来の背後を彩る千手が、ボトボトと数本剥がれ落ちる。それらは黒煙を纏うと、生を得たような人型に膨張。私の後方目がけて走り出した!
「光君、イナちゃ……」
「貴様の相手はこの私だ!」
ズズゥッ……周囲一帯の空気が吸引されるような音。仲間の心配をして���る暇はないようだ。
「龍王!」
「へ!?」
全身猛毒の奴の攻撃を生身で受け止めてはまずい。私は自動制御型法具キョンジャクの先に龍王剣をくくり、めいっぱいブン回す! 瞬間、如来が大量の汚染黒煙を噴出!
「ギヘエエェェェエエーーーー!!?」
黒煙を扇風機(サイクロン)効果で全て吹き飛ばした! 猛回転と毒に酔った龍王は悲鳴を上げながら影炎吐瀉!
「オゴゴボォーーーーッ!!!」
「ぐわっ!」
龍王剣爆発! 衝撃波を食らった私は後方へ吹き飛び全身を強打。しかし黒煙を散々吐き散らかした如来もやつれてきている。武器を二つ失った対価は大きいぞ!
「よし、トドメを……うっ!?」
ティグクを構えた瞬間、私は突如背骨の辺りに激痛を覚える。振り返るとそこには……杭のような形状で私を貫く、固形化黒煙!?
「うガッ!」
血管に汚泥を流されたような鈍痛! 視界がチカチカと明滅し、手足の力が抜けていく。
「ゼェ、ゼェ……ふふ。トドメを……どうすると?」
一転、舐め腐ったような表情で近寄ってくる如来。私は満身創痍でティグクを振るう。しかし斧の柄がみぞおちに当たり、私は胃液を吐き出して自滅転倒!
「ぐはっ!」
「ハッハハ! やぁれやれ、やはり邪道に金剛の有明は訪れぬようだな!」
亡布録装束(ネクロスーツ)に刻まれた死者達にケラケラと歪な笑い顔を作りながら、この世で最もおぞましい外道野郎がにじり寄る。
「だが貴様も女よ。最後の情けとして、この私の接吻で邪尊の因果から解き放って殺してやろう……」
如来は黒煙を吐きながら私に顔面を近付ける。キショい! 和尚様の顔でどうやったらここまで気色悪い所作ができるんだ!?
「ひぃぃぃーーー!」
しかしその時!
「グオォォルアアァ!!!」
ズドゴオオォン! 如来の横っ面を突如巨大な発光体が吹き飛ばした!
「ガッ! ……かはっ……き、貴様ァァ……!」
塔の壁面に大の字でメリ込んだ如来が、ベリベリと顔を剥がしながら振り返る。睨みつけた先には……御戌神、光君だ!
「僕の一美ちゃんに触るな」
「何故だ。貴様如き、分身で十分汚染できたはず……!?」
如来が目を見開く。光君の足元には、ただの腕と化した亡布録が転がっていた。それどころか、私も含めた彼の周囲の黒煙がみるみる消滅していく。
「ま、まさか!」
「カハハッ……何の対策もなしにお前に挑むわけがなかろう? 塔を上っている間に、お前の特徴は仲間と共有済みだ」
黒煙が生物を死に導く力と、光君をずっと蝕んでいた滅びの光。その特性はどこか似ている。ならば、そう。こいつは滅びの光と真逆の、生き物が発する命の輝き……すなわち、『赤外線』を当てまくれば消毒できる!
「ぐああああっ! 馬鹿なァァ!」
「効果は既に亡布録ゾンビで検証済だ! カァァーーッハハハハァァーーー!!!」
パァァァ! 光君を中心に、大晦日の寒空を強烈な赤外線の熱波が撫でた! 周囲一帯の体感温度が急激に上昇し、風をももろともせず滞っていた黒煙はたちまちオレンジ色に輝きながら消滅!
「おのれ……見くびるな、亡布録の法力はいかなる光も通さぬわァァ!」
如来が立ち上がり、再び背中から二本の腕をもぎ取った。それに黒煙を充填すると、腕は二対のガトリングキャノンと化す!
「たかが天部や明王如き、生身の戦いで十分! 捻り潰してくれるわぁ!!」
ズダガガガガガガ!!! 硬化した皮膚片を乱射! やはりこいつは馬鹿だ。
「ステゴロで如来部が明王部に勝てるかボケがァァーーーッ!!」
ヴァダダガガガガガァン!! 無数の神経線維弾が爆ぜ、皮膚片は全て分解霧散! 棒立ちの如来にティグクを叩き込む!!
「うおおおおおーーーーッ!」
頭を真っ二つに割られて吹き飛ぶ如来! 物理肉体に身を包んでいる奴はそのまま、謎の力で浮く空中庭園から放り出された。
「おのれ! おのれェ! 亡布録よ、魂と骸の抜け殻よ!! 我が血肉となれえええぇぇ!!」
自由落下しながら絶叫する如来。すると塔の亜空間からボトボトと亡布録や黒煙が飛び出し、再び如来の装束を蘇らせる!
「フハーーーッハッハッハァ! やれやれ、ここまで手こずらせてくれるとは!」
再び法力を得た如来は地面スレスレで再上昇! 背中の千手に黒々とした巨大煙玉を抱えて上空に迫る! 迫る!!
「この私は何度でも甦えぅええぇぇえ~~~!!?」
しかし高度三千メートルに達した時……如来と煙玉が、謎の飛行物体に吸い込まれた!
「な!? な!!?」
突然の事に何が起こったか理解できない如来。しかしその飛行物体を、その創造者を、私は知っている……
「アブダクショォン!」
たった今、如来が塔から吸い上げた亡布録。その一体が奴から反抗するように、未確認飛行物体から舞い降りた。彼女の名はリナ。私が生まれて初めて作った『自我を持つタルパ』の……宇宙人リナだ!
「やれやれ。まんまと罠にはまたネ、愛輪珠如来!」
イナちゃんが駆け寄る。そう。私はここに来る途中、彼女に『亡布録の中に、髭の生えた女の皮(リナ)がいたら理気置換術をかけてほしい』と依頼していたんだ。如来は私を乗っ取りに来た時、家の結界を突破するためリナを亡布録に変えていたから。
「有り得ぬ、抜け殻が自我を取り戻すなどと……くそ、ここから出せ!」
如来はリナが生成したタルパUFOの中で狭そうにもがく。
「ふっ……やれやれ。言うことを聞けぬなら、この飛行物体ごと亡布録に変えてやる!」
煙玉破裂! 船内に黒煙が充満し、UFOの外観が次第に色褪せていく……
「させるか! スリスリマスリ!」
シュッ! イナちゃんが射出した理気置換術の波動がUFOの丸窓を通して何かに命中した。すかさず船内に、ふわりとラスタカラーの糸のようなものが光る。
「ぐあぁ!?」
如来は繭状になった糸に拘束される。更に、自らの首を飾っていた狸の毛皮が奴を締め上げる。彼も……あの化け狸もまた、如来に命を奪われた魂の抜け殻だ。
「フ……フフ! だがワヤン不動、貴様に私が倒せるかな?」
「?」
「亡布録は所詮、死者の抜け殻。このまま私を倒せば、この宇宙人と狸も消滅する。そして貴様の師匠である金剛観世音菩薩の亡骸も、永遠に消え失せるのだ!」
ほぼ敗北を悟った如来は、最後の脅しにかかっているつもりらしい。だが、それがどうしたというんだ。
「オモ? こいつ何言ってるの。リナちゃんも狸さんも、もうこの世にいないヨ?」
「……へ?」
「それは私が理気置換術で操ってるだけ。お前と同じやり方で、しかえししたんだヨ! ゲドー野郎!」
「なっ……なっ……!」
ゴォッ。光の獣と影の明王が火柱を噴き上げ、天に二色の螺旋を描く。
「や、やめろ……」
死の残滓には、命の輝きを。生命の営み、男女結合の境地……両尊合体(ヤブユム)を。
「よせ! もう間もなく、金剛の有明は訪れるのだ! それを拝めずに、き、消えたくない……」
全ての因果を斬る漆黒の影体、全ての外道を焼き尽くす真紅の後光輪。ワヤン不動・輝影尊(フォトンシャドウフォーム)爆誕!
シャガンッ! 世界が白一色の静寂に染まる。この領域は私であり、私はこの領域そのもの。中に存在する異物は、金剛愛輪珠如来のみ。さあ、
「やめろおおおォォォーーーーーーーー!!!!」
神影繰り(ワヤン・クリ)の時間だ!
༼ 南摩三満多哇日拉憾唵焼雅蘇婆訶! ༽
幾多の仲間が散り、師は逝去された。ここからは、私自身が我が道を歩んでいく。
༼ 一名來自沙漠盡頭的精靈僧官將其救起精霊曰吾乃悪魔神視不食其力而乞為悪是故將汝等糧食交之於吾僧官曰生存乃自然之道既然如此佛祖不会介意您便拿去吧! ༽
金剛愛輪珠如来は外宇宙の理力により死を超越した残滓。だがこの地球上に衆生を蔑ろにする仏など不要だ!
༼ 精霊曰神不容受施于神外之物是故命汝等崇敬於吾僧官曰如果您施恩予我我將感激不盡既然如此佛祖不会介意您大可放心! ༽
もはや外道の如来も、邪尊もこの世からは消え失せる。ここにいるのは憤怒の化身、外道を滅ぼし衆生を守る輝影尊のみ!
༼ 精霊曰神不容爾等試探其之���心是故吾便在此自殺僧官曰您死後我便會恭敬的悼念您既然如此佛祖便不会介意您大可放心! ༽
案ずるな、呪われた黒煙よ。死者の肉と魂は素粒子に分解霧散し、また地球の糧として巡るもの。
༼ 精霊曰吾中意之佛道是故汝接受吾之心臓將其食用於是乎精霊感到十分満意帶著愉悅的心情離世了而僧官則吃了精霊的心臓成為了守護其衆生的赤紅影尊ヌアァァアアア!!! ༽
その輪廻から逃れられる悪徳など、この世には存在しないのだから。私はそれを知っている。邪尊でも、祟り神でも、たとえそれが悪魔でも……
༼ 唵! 皮! 影! 維! 基! 毘! 札! 那! 悉! 地! 吽ーーーーーーッ!!!!! ༽
……さまよえる全ての者に、抜苦与楽の永眠を与えん。
གཉིས་པ་
暗転、赤転、明転。全てを出し切った私と光君は、素っ裸で並んで得体の知れない空間に横たわっていた。そこは真冬とは思えないほど心地の良い朝日が差し込む、あたたかな森の中……
「……って、まだ終わっちゃだめじゃん! 光君も起きて!」
「そ、そうだ! ここまで来たら、ちゃんと金剛滅ぼさにゃ!」
私達は慌てて腰を上げる。いけない。戦闘後にマッタリしちゃういつもの癖が出かけたけど、まだ大魔神を倒していなかった!
『ふふふ……仲睦まじい新婚夫婦、素敵ですのね』
「!」
見知らぬ声の方には、色とりどりの花で彩られた棺があった。覗き込むと、中にはドレスを着た女性が眠っている。
「あなたは?」
『私は平良鴨カスプリア。全知全脳の女神……いえ。ただの豚ですわ』
「ぶ、豚ぁ?」
するとポッと短い電子音を立てて、森に小さな魔女……悟さんのアバターが現れた。そうか、ここは例の白雪姫なんとかってゲームの世界だ。
「そうよ、そいつは私の白豚ちゃん! ほら、おどき!」
絵本の白雪姫なら、棺で眠っている姫は王子様のキスで目覚める。ところが悟さんは、カスプリアさんに容赦なく四季砲(フォーシーズンズ・キャノン)をブッ放した!
「ひゃあん!」
可愛らしい悲鳴を上げて、女神様は棺から放り出された。しかしその表情はなんともご満悦そうだ。
「ふむ、両肘下と十二指腸、左脚がまだ未完成のようね。それとも私が今フッ飛ばしちゃったかしら? おほほほ!」
「滅相もございませんわ悟様! 私めの肉体はまだまだ未完成ですもの。本日は紅ご夫妻様のために、私カスプリア。魂だけ覚醒致しましたの!」
……つまり、色々と作りかけのこの女性は女神カスプリア。人類に金融アルマゲドンとかいう試練を引き起こし、悟さんに見事ハートをかっさらわれた奥様というわけだ。
「この度は、私めと同じ『カオスコロル』がとんだご迷惑をおかけ致しました。私めも今はお力になれず、本当に申し訳ありませんの」
「カオスコロルとは?」
ああ、光君には伝えていなかったか。
「混沌色(カオスコロル)。例の外宇宙……創造主様の世界から降ってきた、謎の粒子だよ」
「じゃあ、カスプリアさんは大魔神や神の子さんと同じで?」
「ええ。あちらの領域……そうですわね、いわゆる外宇宙から参りましたの」
カスプリアさんが一瞬言い淀んだ。
「あまり人間様にあちらのお話はしない方が良いんですの。なにせ時の王様に記憶を封印された私め自身、全知全脳の自我を取り戻したとたん人格がゲシュタルト崩壊してしまったのですもの」
「げ、げしゅたると崩壊……」
って、自分が誰だかわからなくなって発狂するとかいう、あれだよね……?
「でも一人だけ。生きたままたった一人であちらに到達されて、お心に異常をきたさず帰られた人間様がいらしたわ」
「え?」
「ゴータマ・シッダールタ。初代、仏様ですわ!」
「そうなんですか!?」
まさか、それが悟りを開くって言葉の真の意味!?
「ええ! そして一美様、光様。あなた方がワヤン不動輝影尊として大魔神と戦われるのなら、同じ悟りの境地に至っていなければ勝ち目はありません。なぜなら大魔神は、いわゆる創造主を強制的に人に見せつける力がございますの!」
「人間が見たら発狂する神を、強制的に!?」
そういう事か。もし私達がこのまま大魔神ロフターユールと対決し、奴に宇宙の事を見させられたら発狂して負けてしまうんだ。だから今この場で、悟りを開くしかないようだ。
「ドマルの時から思ってたけど……やっぱり精神に見合わない力は、身を亡ぼすんですね」
「そういう事ですの。私めが今からあなた達に、この宇宙の真理をお見せしますわ。創造主を目視した人間は一瞬で無限の情報に脳を焼かれてしまうので、本来よりもゆっくり……さくさくっとお見せしますわね」
なにそれ怖い。
「大丈夫よ、あんたら二人一緒なんだから! 私だって一人で見たけど大した事なかったわよ!」
悟さんの魔女アバターがコロコロと笑う。……って、え!? 悟さん見た事あるの!?
「それでは……行ってらっしゃい! ですの~!!」
「「え、ちょ、���ええええぇ~~~!!?」」
そして私と光君の視界は、ゲーム空間から異次元へ飛び去った……。
གསུམ་པ་
そこから私達は、目まぐるしく地球史を遡った。気になる歴史上の出来事や人物に少しでも集中すると、そこで起きた運命、無数の人々のひしめき合う感情、喜び、悲しみ、痛み、安らぎ、食べるもの、食べられるもの……ありとあらゆる感覚と本能が、ハチャメチャに押し寄せてくる。私も光君も、深入りしかける度にお互いの手をぎゅっと握って耐えた。
三大禁忌で隠匿されていた話は、概ね本当だった。学校で習うような一般常識を思い出した後で改めて見ると、とんでもない話だ。
現代では謎に包まれたシュメール文明。それは外宇宙へ繋がる『塔』を建てた、神々と人類が手を取る国だった。しかし彼らは創造主の片鱗を目の当たりにして、人類が二度と外に夢を見ないようそっと衰退した。その物語はやがて、現代の人々も信仰する世界一有名な聖典を生み出すきっかけとなった。
その後、地球に降り注いだカオスコロル。そりゃあ神の子と名乗るのも納得だ。彼は人類が二度と創造主に近寄らないよう、奇跡の力で生涯慈善事業を行いながら、ひっそりと人類から霊感を奪っていった。
そして第二のカオスコロル。霊能者と合体して大預言者に変身した彼は、中東に当時まだ残っていた異教徒が呼び出した外宇宙生物を倒し、それまで以上にめちゃくちゃ厳しい一神教を作った。彼はもはや唯一神の名前を呼んだり、イメージで偶像を作る事まで頑なに禁じた。それでも現代でも、人類の三分の一ぐらいの人達が彼の言いつけを守っているのはとてつもない偉業だ。
第四のカオスコロル……カスプリアさんは、時の王様の隠し子に宿った。だけど霊能者であった王様は、カスプリアさんの記憶が完全になくなるまで彼を地下に幽閉し、人間の言葉や生活を何一つ教えずに育てた。そのせいでカスプリアさんはやがてゲシュタルト崩壊して、脳を卵に変えて自らを封印。それを戦時中ナチスドイツに発掘され、今に至る。
人類とカオスコロル達が、ここまでして長年隠し通してきた『外宇宙』。いま、その実態は私達の目前にある。
「……ここまでは、大丈夫ですの? 準備ができましたら、いっせーのーせで創造主をチラ見せいたしますわ」
「わかりました。光君、大丈夫?」
「ゼェ、ゼェ……うぷっ。なんとか」
私はいい、まだ仏であるドマルの記憶や精神が根幹にあるからこのくらいは平気だ。しかし光君は今に至るまで、既に何度か分解霧散しかけている。
「じゃ、じゃあいくよ……本当に平気!?」
「ど、どうにかするから! 大丈夫。一美ちゃんを残して、僕は絶対に壊れたりなど!」
「わかった。いっ……」
「「せーのーせっ!」」
私達の合図と共に、カスプリアさんは外宇宙の景色を解放した。
བཞི་པ་
「ロフター。ロフターや、イラクサを刈ってきておくれ」
穏やかな森の中。腰の曲がった老魔女グリーダが、大鍋をかき混ぜながら使い魔を呼ぶ声。
「おいおい、イラクサですって? 僕の肉球が膨れ上がってパンになっちまいますよぉ」
現れた使い魔は、嗄れた声で二足歩行の猫。彼は虎のように大柄だけど、身長二メートル半もある魔女と並ぶと丁度よい体格差だ。
「文句を言うんじゃないよ。あたいの叔母のナブロク手袋を使いな。叔母さまはどんな毒や火傷からもあんたを守ってくれるよ」
魔女に促されるまま、猫は引き出しから人皮の手袋を取り出した。それは丁寧になめされて、甲に金色のルーンが刺繍されている。
「おやおや、こんなに薄いのに随分とあったかいんですなあ。それに……おお。確かに、イラクサに触ってもチクチクしないですよ。こりゃあグリーダの叔母さんは随分と良い人だったんでしょうね」
「ヒッヒッヒ! そうさ。あたい達魔術師はね、古くからノースの神々と共にヴァイキングを支えるこの国の英雄なのさ。最近は神が一人ぽっちしかいないなんて訳のわからない事を言う外人さんもよく来るけど、あんな偏屈な考え方はこの辺りにゃ向いていないね!」
「にゃははは! 全くその通りですなあ。わはははは!」
ལྔ་པ་
魔女と猫の、幸せそうな束の間の時間。外宇宙の創造主……本当にそう呼んでいいのか……を見た私と光君の脳裏には、その光景が過っていた。
「こんな物のために」
光君の唇が震える。
「こんな物の尊厳を守るために、あの魔女は裁判に?」
魔女裁判。実は土着信仰の根強いアイスランドでは、ヨーロッパほど熾烈な魔女裁判は行われていない。しかし森の魔女グリーダは拷問の上で惨殺されてしまった……カオスコロルである、ロフターユールを庇って。
「こんな物の尊厳を守るために、いまだ世界中で戦争が??」
「そうですわ」
創造主を背にしたカスプリアさんの目が、玉虫色に光る。この『神』を三次元の物体として落とし込むと、確かに似たような色をしている。
創造主について言葉で例えるのは難しい。あえて言うならそれは、どこまでも無限に広がり、うねり続ける複雑な波だ。波の先をよく拡大してみても、見えなくなるほど無限に同じ形の小さな波が連なっているだけ。どれだけ全景を見渡そうとしても、見えなくなるほど無限に同じ形の波が連なっているだけ。その全貌は途方もなく壮大で、その片鱗は手の中に握りつぶせるほどちっぽけで無価値な存在。それが創造主という概念だと思う。
「僕は認めない! 神様ってヤツは、もっと偉大で立派で……こう、ひげもじゃのお爺さんなど! みんなが尊敬できるお方でねえと! なのに、こんな心があるかどうかもわからない場所が……神様など……」
光君の頬を涙がつたう。こうなるのも当然だ。だって私達は、つい今しがたまで人類の全ての歴史を追体験したばかりだから。神に祈りながら死んでいった人々、神について争い命を奪い合う人々、神を騙る人々……その全てを、見てきたから。
「一美ちゃんは、どうしてそんな平気ので……?」
「……」
私って、薄情な女なのかな。ただ……
「平気、かどうかは何とも言えないけど……私は正直、こんなもんかなって思った」
「どうして?」
「だって……創造主って、人類だけのものじゃないでしょ」
「!」
そう。私達は、人類の全てを見てきた。けど、それだけじゃない。動物、植物、惑星、この宇宙の全てを経てここに来たじゃない。
「人のための神様なら、確かに人型じゃないと変だと思う。けど太陽系には、犬とか葉っぱとか、石とか、ミトコンドリアとか。色々な存在があるでしょ? その全員のお母さんだってんなら、こんなわけのわかんない形だったのも納得がいくよ」
「人間以外……まさか一美ちゃん、さっきの遡りで、人類以外にも目を……!?」
「い、いやいや、ちょっとずつだよ!? そこまで精神のキャパないし! ……あ、でも」
人間をここまで魅了する神様、といえば……
「……よく見るとこの波の形、仏様っぽくない? お釈迦様の螺髪(パンチパーマ)、ほら、あのへんの出っ張りを真似したのかも!」
「は、はは……」
光君は膝を打った。
「……これが、不動明王(ホトケさま)か」
དྲུག་པ་
かくして全てを悟った私達は、カスプリアさんの力でゲーム空間に意識を帰還させた。
「さすが……お二人共、よくご無事でお帰りなさいましたわ。ですが、それができたのは、お二人が今まで幾多の試練を乗り越えてきた神仏だったから。普通の人間は創造主を直視するだけでショック死ですのよ」
「わ、わかってます! あんなのバレたら文明がめちゃくちゃになっちゃいますよね!」
というか、目がチカチカして卒倒するのが先かも。
「ええ。ですが、それこそ金剛が企てる楽園計画ですの」
そう、私達はロフターユールの過去も見てきた。彼は魔女狩りで大切な人を失い、一神教を……過去のカオスコロル達が築き上げてきた秩序を、憎んでる。
金剛有明団の真の目的は、全人類が失った霊感を再び蘇らせ、この地球上から『創造主への幻想』を破壊する事だったんだ。
1 note
·
View note
Text
私の神様
2016年2月10日、13時59分。
私は、宮本フレデリカを殺した。
いや、その表現は必ずしも正しくない。この国で人を殺せるのは医師だけだ。正確に言うならば、彼女の飲んでいたカフェオレに睡眠薬を混入させ、意識の消失を確認した後に致死量の麻酔薬を点滴注射し、心肺を停止させた。肉体の、生命活動の停止を死と言うのであれば、先述した時間に彼女は死んだ。法的な意味での死が必要であれば、私がその資格を持たない以上は無意味だが、呼吸心拍の停止と走行反射の消失を確認した現在、2016年2月10日の14時1分に宮本フレデリカは死亡した。私が殺した。
彼女の散大した瞳孔は光を捉えない。季節が巡るように留まることを知らなかった唇は、もう言葉を発さない。笑わない。歌わない。
私が何を感じているか。それを語るのは全くの欺瞞でしかないだろう。また、現在の自己に言及するだけの能力を私は持たず、そうする意味を見出すこともできない。同様に、私がなぜそうしたか、つまり彼女を殺害したのかを語ることも無意味だ。空が青くとも、金銭目当てにも、夢を叶えるためにも生きるためにも、人は人を殺し得るのだから。
だが、それでも私はそうしようと思う。
始まりがそうであったように、私たちの日々がそうであったように、彼女のコバルトグリーンの虹彩は死して未だ私の脳幹を揺らして止まないのだから。
私と彼女の出会いは、ひどくありふれたものだったことを覚えている。忘れようもない。私はアメリカでの退屈な生活と先の見えた研究を捨てて、この国へ戻ってきた。アイドルになるとを決めたことに特別な意味はなく、瞼を塞ぐ退屈の氷を僅かでも融解させられればと考えていただけだった。スカウトを受けたその足で向かった事務所で、私は彼女と出会った。後に彼女はこの出会いを運命と(何度も)称したが、彼女は私が潰し踏みにじったその果実を前に何を思うだろうか。聞いてみたいが、その相手はもういない。私が殺した。
「あたし、宮本フレデリカー。ママはフランス人パパは日本人のハーフなんだー。志希ちゃん、これからよろしくねー仲良くしようねー」と、その日出会った彼女は私に言った。改めて文字にすれば、なんて凡庸なのだろう。しかし、彼女の声が、瞳が、表情が持つ情報量は、いつだって私の処理能力を上回っていた。
彼女の言葉は、言葉である以上に音楽だった。声音はキャラメルパンケーキに似ていたが、抱擁にも近い。高く跳ね上がった語尾は、大気中でステップを刻んで私の平衡感覚を揺さぶった。かと思えば、彼女の視線は磁力か重力それ以上の引力で私の視界を奪う。網膜に雪崩れ込んだ光は像を結び、像はイメージとなり、また一秒たりとも同じ形を見せない彼女の表情は凪いだ日の海と透明な朝日が生み出す光の乱反射に似ていた。
しかし���彼女を表すべく選ばれた全ての表現は、言語というツールの有限性に束縛されている。たとえ私の体を構成する細胞と同じだけの言葉を結んだとしても、一本の毛先ほども彼女を表現できないことだろう。
よって、時は進む。私たちは、彼女の言葉をそのまま借りて良いのであれば「仲良く」なった。
私たちは波長が合った。呼吸が合った。リズムが合った。やはりいくら言葉を重ねても足りることはないが、逆にそれを一言に集約するのであれば、楽しかった。彼女は私の言葉をよく理解し、心を上手に読解した。振り回されることも、手を引かれることも、また振り回し手を引くことも、二人でいる時間に退屈は存在しなかった。瞼を閉じている時間が減った。一人でいる時間が減った。研究に費やす時間は減り、笑っている時間が増えた。
彼女と居る間だけ、私はただの十八歳の少女でいられた。
そうして二人でいつも遊んでいたら、ユニットを組めと言われた。レイジー・レイジー。だら・だら。全く本質から逸れた名前だとは思ったが、その響きだけは嫌いではなかったし、二人でいる理由になるのであれば形は問題ではなかった。
名前とは対照的に、私たちの活動は精力的だった。社会的な評価にも恵まれ、二人でいるほどに二人でいる時間は増えていった。指数の曲線をたどって増大していく幸福の中で、私たちはステージが終わっても、醒めない夢の中で永遠に続くワルツを、ルンバを、フラメンコを踊っていた。
永遠などありはしない。
そんな簡単なことさえ、彼女は私から忘れさせた。
終わりは、日常の内側から訪れた。種子を蒔いたのは私で、培地を作ったのも私。そこに、熱を湿気を与えたのは彼女。二人で大切に育てた終わりの芽吹きは、蒸し暑く煙った夏の夜だった。ライブを終えた夜、私たちは(いつものように)打ち上げを早々に抜け出して近場の公園で一千の瞳に曝された熱を放出していた。話しては歌い、話しては踊り、また話す。月明かりはビルに遮られ、ビルの照明は落とされ、私たちを見ているのはわずか二本の街灯、を揺らして雨が降り始める。ぬるま湯のような、けだるい雨。あーあ、と帰ろうとする私の手を彼女が引き止める。熱を帯びた指先、陽の光を全て飲み込んだような瞳の輝き、強まっていく雨と、背中越しに街灯のハレーション。
黄金の色をした残像を網膜に焼き付けながら、私は踊る。私たちは、踊る。水銀のような豪雨が体にまとわりつき、反比例して、肉体は軽くなっていく。跳んだ足は地を踏まず、驚き見下ろせば変わらずそこにある。背中に生えた翼は、光と水滴が生んだまぼろし。世界を構成する音楽、リズムは私たちのステップ、メロディは私たちの歌声、雨粒のオーケストラ、街灯はステージライト。時間の速度を追い越して、流星群のように流れる景色を背負って、彼女の像は圧倒的な存在感で私の脳を支配し続けた。その最良の時間は、一瞬たりとも色褪せることなく、今も私を衝き動かして止まない。
どちらが先だったか、やがて私たちは疲れ果て地面に座り込んだ。紅潮した頬。開け放した喉。肺は換気を繰り返し、酸素が急速に全身を循環する。手についた砂粒。小刻みに震える脚。それまで私たちを満たしていた言葉さえ、雨が洗い流していた。
理性の活動はひどく散漫で、だから、同時に立ち上がった私たちの行動は脳幹の仕業なのだろう。おぼろ気な、蜃気楼を目指す旅人のような足取りで私たちは近づく。視線には互いだけを映している。大きな眼に雨粒が降り注いでも、彼女は瞬くことさえない。私の視界では、溶融が始まっている。熱した赤銅のようにどろりと溶けていく風景の中で、黄金やコバルトグリーン、山桜、真珠、夜の海、彼女を構成する色だけが狭窄した視野を満たす。
荒れた呼吸、唾液を飲み込み、唇を開く、彼女の心音さえ聞こえるほどの距離にあって私は、夢から醒めた彼女の瞳の中に、泥のような欲望で濁っていく私を見た。
最悪は、最良のすぐ後に訪れる。
その後何が起き、それから私たちがどう変容を遂げたのか。仔細に語ろうとは思わない。ただ、始まりはその夜にあった。彼女を殺そうと、不定形な意志が私に生まれたのは確かにその夜だった。その意志は時を重ねる毎に、私たちが触れ合う毎に形を確かにし、そして今日という日に現実となった。
後悔をしているか。きっと、私はしていない。仮にこの私を構成する原子が無限に近い時を経て再び私を繰り返したとしても、私は私の意志で何度でも彼女と出会い、彼女を殺すだろう。彼女は私の全てだった。殺害という行為さえ含めて、私の世界の全てだった。
彼女は、どうだろうか。最期まで、私には彼女の心がわからなかった。その上でこう言うのは全くの欺瞞に過ぎないのだが、彼女も同じなのではないだろうか。回帰する命において、彼女は何度でも私と出会い、私に殺される。これは願望でしかないが、確信に似ている。しかし、証明できない以上は無為な信仰でしかない。
無為。そう、無為が多すぎた。この手記の基本的な意義は、私たちの死後誰かの目に触れ、私が明確な意志を以て宮本フレデリカを殺害したと証すことにある。だとすればあまりに余分が多い、が、もういい。私の理不尽な殺意は、十分に記述されている。
左腕に注射針を刺す。テープで固定を施す。針から伸びた管の先には、彼女を殺したものと同じだけの麻酔薬と輸液。クレンメをひねり、液が落ち、私は彼女と同じかたちで死んでいく。苦もなく。眠るように。
さようなら、宮本フレデリカ。私の、黄金の花冠。コバルトグリーンの魔法。素粒子の配列の奇跡。空を舞う自由意志。あなたは、確かに、私の(以下、解読不能な文字が僅かに続き、手記は途切れている。一ノ瀬志希が所持していたガレージからは手記にある通りの医療器具が見つかり、注射針からは二人分の血液が採取されたが、一ノ瀬志希及び宮本フレデリカの遺体は発見されなかった)
0 notes
Text
【Piano perfetto】
遡ること 23年前
とある少女はある施設へ預かることになった
なんの変哲もない保育施設
彼女は両親の共働きもあり
3年の間は預かるという施設になる
そこで不自由ながらも生活していく
ある日の夜
悪夢を見た
周りの同じ年の子達が
理性を失い
『先生』に飛びかかっていく姿
そこで目が覚めた
泣いている少女は嫌な予感がしていた
「ごめんねM 今日もこのまま部屋で遊んでてね」
そう言って男はドアを閉めると鍵を掛けた
まるで牢獄みたいだ
外で大人たちが大声で何かを発している
怖い、ここから出たい
そう思った
こんなところに居たらいつか私もこうなると
怯えながら暮らした
また夢を見た
そこで一緒に暮らしてた友達が
息をしていなかった
いや、夢じゃない
母さんが言っていた
お別れだって
2度と会えないお別れだって
折角仲良くなれたのに
悲しい…悲しい…?
私って何でこんなにも考えてる?
まだ私って五歳だよ?
こんなにも思考が感情が満たされてるの
普通じゃない
私も何かされた?
「今日のご飯だよ」
また『先生』がご飯を持ってきてくれた
ハンバーグだ 美味しそう そんなことよりも
「先生、みんなどうしちゃったんですか?」
「みんな?」
「ここでともだちになったみんな」
「具合が悪くなっちゃってね」
「…嘘だよね?」
少女は急に口調を変えた 五歳の発言ではなくなった
「みんなしんだんでしょ!?変なことしてるのは先生達だ!こんな所にずっと閉じ込めてて何をしてるの!?」
感情が高ぶる
「落ち着いて!落ち着いて!」
「いやだぁ!!」
次の瞬間肩を掴まれた少女は
『先生』を投げ飛ばした
「あっ…」
『先生』は動かなくなってしまった
頭を強く打ったみたいだ
「M!!何をしてる!!」
見たことない人がこちらに来た
でも先生達と同じ服装している
近づくと 小声で
「父さんから話は聞いた 今すぐ帰ろうって」
「父さんの友達?」
「そうだ。行こう」
状況的に飲み込めないのが普通の幼少期だろう
彼女は既に実験台にされていた
PH試作品を投与されていたのだ
この試作品は未知なウイルスと言ってもいいだろう
身体能力、脳の活発化、将来的な特殊な能力の取得 の効果を付与できる らしいが
殆どは理性の崩壊 言語能力の低下 食欲旺盛といった ゾンビのような変貌を遂げてしまった。彼女だけが、何も起こらなかった
いやもう既に起きていた
大人一人を投げ飛ばし
思考回路が一気に上昇され
実際のところ、ずっとウイルスを投与されていたということだ
寝ている間に
さて、彼女は両親の友達と外に出る準備をしている
無機質な白い廊下を走り続ける
向こうから二人向かってくる
「誰だ!!」
一人が叫び警棒を取り出す
「くっ…まずいな」
隣に居た少女は
壁を蹴って飛び、ライダーキックのように
相手の頭へ飛びかかった
「!?」相手の一人と一緒に居た彼も驚いた
それもそうだ 相手からしてみれば、実験台にしていた少女が 大人と一緒に行動し、跳躍しているところを見てしまったのだから
「お前…成功し…つっ!!!???」
警棒を持った男は助けに来てくれた彼に右ストレートを喰らって倒れた
「とんでもない能力だ…このまま行ける?」
「早くここから出たい」
「よし、止まらず行こう」
施設の非常口
やっと出れる
ドアを開けると
「孝!!無事か!?」
「おう!この子も大したもんだぞ!!」
「助かる!飛ばしていくぞ!」
車に飛び乗って
初代4ドアインプレッサが大地を蹴り
山の中に消えていく
その一年後
密かに暮らしていた家族は脱走した少女の為に名前を、籍を変えることになった
高梨 魔理 彼女の新しい名前
これで安心して暮らせる…そう思っていたのだが
魔理は倒れてしまった
精神的に追い込まれてしまったのか
病院へ運ばれる
そこである事実が判明した
「この子は…人間…だったんですか?」
「どういうことです…?」
父親が医者へ問いかける
「構造、血液、脳と調べていきましたが、六歳の体ではありません。まるで完璧な体、倒れたのはウイルス性の肺炎ですが…もう治りそうです。私達が手を入れるまでもなく」
「魔理に…何が…?」
「私にもわかりません ただ、これだけは言えます。この子は狙われる これだけのウイルス耐性と治癒能力、充分な理由です。」
父親は息を呑む また狙われるのかと
「今回の検査結果はすべて破棄します。そうでもしないと、命の危険だってありますから。このまま帰って大丈夫です。」
そう言うと医者は書類をシュレッダーにかける
「ありがとうございます」
「いえいえ、それとお代も結構です。貰っては履歴が残ってしまいますから」医者は苦笑いをした
月日は流れ…
場所:ニューヨーク ブルックリン区
ガレージに置かれた深紅のストラトス
離れたところにソファが置いてあり
腰掛けるツインテールの女性
「…全く…またこんなのを送ってきて…」
手に持っているのは父親から��られてきた食料と…『完璧な人間計画』とイタリア語で書かれた書類だった
「人類の新たなステップアップとして幼少期に試作品を投与するも…失敗に終わる…か…」
書類はクリアファイルに入れて大きなツールボックスの引き出しへしまう
「あれで何人も亡くなったし、流石に企業として動いてないでしょうに…」
ドアの開く音
「あら?ご新規さん?いらっしゃい」
「『我ら南十字星の騎士なり』…でしたか?」
黒人の大男が紳士に話す
「そっちのご新規さんか…ようこそ
Southern Cross Engineeringへ
お荷物はどちらへ?」
0 notes
Text
08280005
.........だから、俺がもし大通りで通り魔殺人をするなら、きっと最初に狙うのは腹の大きな女だ。子供が狙い目だと思われがちだが、案外そうでもない。もう生まれてしまった子供は親が必死になって守るから、むしろ普通の人間よりも狙いにくい部類だろう。くだらないが、それを無理矢理狙って殺すのは至難の技だ。両親が揃っているなら尚更。
俺の目の前でベビーカーを押す女が楽しそうに旦那に話しかけて、旦那は嬉しそうに目を細め子供をあやしている。ああ、世界共通の幸せの絵だ。反吐が出る。
幸せ、ってなんだ?他人から見て、己が幸せな姿に映ることか?いや、違う。幸せは、自分の置かれている状況について何も不平不満を抱かず、我慢を強いられることなく、全て俺の意のままに遂行されることだ。そうに違いない。幸せ、幸せ。ああ、俺は幸せになりたい。ずっと子供の頃からの夢だった。幸せになることが。幸せになることこそが。
他人の幸せに対して恐ろしく心が狭くなったのは、きっと今俺の置かれている状況が著しく幸せから遠いから、だろう。社会の中での立ち位置も、持って生まれた時点で腐っていた神様からのギフトとやらも、白痴付近を反復横飛びする出来の悪い頭も、見てくれの悪さも、全てだ。
自ら遠ざかったつもりはない。人の幸せを妬んで、それで、手に入らないことには気付いていて、そして、そして、?
?ん、あぁ、覚める、ダメなやつだ、これ、と、思考が曖昧になって、見えていたものも、匂いも、温度も、何もかもが遠ざかって、そして、何も見えなくなった。
極めて自然に、目蓋が開いた。手探りで掴んだスマホの画面を見れば、時刻は朝の5時を少し回ったところだった。曜日表示は土曜。どちらにせよ早すぎる。
"彼"の中途半端に病んだ思考が俺の頭と同期して、混ざろうとしているのが分かって吐き気を覚えた。やめろ。混ざるな。のそり、重たい身体をベッドから引きずり起こして、ふらふらと冷蔵庫に縋り付き、冷えたミネラルウォーターを喉へ流し込んだ。水の通り道が冷えていって、そして胃の辺りがじんわり冷たくなる。物理的にはあり得ないが、その温度は首の後ろを通って、脳へと伝わり、思考が少し、冷めていく。
何が通り魔だ。情けない。俺の夢を支配して、外に出たがったくせにやりたいことがそんなバカの憂さ晴らしだなんて興醒めもいいところだろう。しかも、やる前のウジウジした感情から見せるなんて。はっ。しょうもない。どうせなら血溜まりの中の回想にでもしてくれていれば、今頃、小話くらいには昇華出来たものを。
奴の目線から見えていた短い指と、くたびれ皺の寄ったスーツとボロボロの革靴、己を嘲笑っているように見える周りの視線と話し声、やけに煩いメトロの到着メロディ、喧騒、咽せるようなアスファルトの油の匂い、脳天に刺さる日差し、それら全てを戦後の教科書の如く黒塗りで潰して、そして、深呼吸ののち頭の中のゴミ箱へと入れた。これで、俺は、俺に戻れる。もう一眠りしよう、と、布団に潜り込み、俺は柔らかい綿人形を抱き締めて、眠るための定位置へと着き直した。
物書きで飯を食える、などという夢を抱く間もなく、敷かれたレールに乗って模範囚の如く社会の、それも下の方の小さな歯車の一つに成り果てた俺。チャップリンのように笑えたらいいんだろうが、生憎笑えない現状の片手間で書いている小説、そんな大層なものではないが、もう200を超えただろうか。詳しく数を数えてはいない。数字を重ねることに、大して意味はない。ただ増えていくソレを見るよりも、彼ら、彼女らの過去、未来に想いを馳せる方がよっぽど大事だ。俺は、彼らの人生を文字に変え、束の間の虚無を忘れている。
俺は、自分の力では、小説を書けない。
一昔前に流行ったゴーストライターではなく、どこかの小説の盗用でもない。人から詳細を聞かれたら、「主人公達が動くのを見て書いてる」と答えて誤魔化しているが、俺は、自分の夢を小説にしていた。いや、自分の夢でしか、小説を書けない。
夢の中で、俺は俺じゃない誰かとなって、違う人生の一部を経験する。なった誰かの感情と共に。そしてその夢は、嫌に鮮明に、必ず完結して終わる。
そのおかげで、俺はまるで自らが体験したように、綿密な話が書ける。不思議と夢を忘れることはなく、内容によっては自ら夢を捨て、今朝のように半ば不快感を持って目覚める。そして、その夢の記憶はじきに消える。
そうして俺は眠り、夢を見て、出てくる彼らの物語を文字に認めて、満たされず空虚な、平々凡々な自分の人生を今日も狂気で彩る。
ある日偶然君の皮膚片を食べた時、世界にはこんなにも美味しいものがあったのかと感嘆し、感動のあまり失禁したことを思い出した。
目が覚めた瞬間、これよりいい書き出しは無い、と思った。思考は溶けた飴のように彼のものと入り混じっていて、はっきりと覚醒はしない。恐らく、俺の思考は殆ど死んでいるんだろう。今こうして無心で手を動かしているのは、確かに生きていた彼だ。口内には口にしたこともない見知らぬ女の皮膚片の味がこびりついて、舌の上がまだぬるぬると滑る感覚、しょっぱい味が残っていた。食べたことのない味。ああ、書かないと、無心で筆を走らせる。書く瞬間、俺は俺でなくなり、彼が俺を使って脳を動かしているような感覚に陥る。戻ってこられなくてもいい、そのまま彼に身体を明け渡しても後悔なぞしない。と、俺は諦め身体の主導権を彼らに手渡している。
ふと気が付いたときには、もう小説は書き上がっていた。軽く誤字を確認して、小説掲載サイトにそれを載せる。人からの反応はない。別に必要はない。
サイトを閉じ、ツイッターを開く。現れたアカウントでただ一人フォローする彼女のアイコンを見て、そしてDMを開いて、青い吹き出しが羅列される様をざっと見て、心が幸せに満たされていくのを感じる。じわり、と湧き出たのは、愛情と、快楽と、寂しさと、色々が入り混じったビー玉みたいな感情だった。
彼女は、ネットの中に存在する、美しく気高く、皆から好かれている人気者。そんなのは
建前だ。彼女は、まさしく、
「おれの、かみさま。」
そう呟いて画面をなぞる。ホワンと輪郭がぼやけたケーキをアイコンにしているあたり、ここ最近どこかへケーキを食べに行ったのかもしれない。俺が彼女について知ってることは、声を聞く限り恐らく女性で、恐らく俺よりも歳が下で、俺のことなど認知すらしていない、ということだ。
別に悲しくなんてない。彼女はただここにいて、俺に愛されていてくれれば、それでいい。拒絶されない限り、俺の幸せは続く。好きだ、好きだ、今日も彼女が好きだ。
彼女のツイートは食べたスイーツのこと、日常のほんの些細ないいこと、天気のこと、そんなささやかな幸せに溢れた温かいものばかり。遡る度、何度見ても心が溶かされていく。
どこで何をしているのか、どんな服を着て誰と笑うのか、そんなの��知らない。どうでもいい。得られないものを欲しがるほど俺は子供じゃない。そばで幸せを共有したいなど、贅沢が過ぎて口にした日には舌でも焼かれそうだ。
『今日も、好きだよ。』
また一つ増えた青い吹き出しをなぞり、俺は不快感に包まれる頭を振り、進めかけていたゲームの電源を入れた。時刻は午後の2時。窓の外では蝉がけたゝましく鳴いており、心の底から交尾を渇望しているらしかった。
触れ合えないことを、惜しいと思わない日はない。彼女の柔肌に触れて、身体を揺さぶって一つになることが、もし出来るのなら、俺は迷わず彼女を抱くだろう。幾度となくそんな妄想で、彼女を汚してきた。俺の狭い部屋のベッドの上で、服を雑に脱ぎ散らかし、クーラーでは追い払い切れない夏の湿気と熱気を纏った彼女が、俺の上で淫らに踊る様を、何度想像したか分からない。その度に俺は右手を汚し、彼女への罪悪感で希死念慮が頭を擡げ、そしてそんな現実から逃げるように夢を伴う惰眠を貪る。
彼女を幸せにしたいのか、彼女と共に幸せになりたいのか、彼女で幸せになりたいのか、まるで分からない。分からない、と、考えることを放棄する俺の脳には、休まる時はない。
俺の中の彼女は最早、彼女本人からはかけ離れているのかもしれない。俺が見る夢の種類は大まかに分けて二つ、目を覆いたくなるような凄惨な感情の入り混じるものと、急に凪になった海をただ眺めているような穏やかなもの。後者に出会った時、俺は必ずと言っていいほど相手の人格を彼女に当てはめる。彼女は右利きで、俺の左に立つのが好きだ。彼女は甘党で、紅茶に詳しくダージリンが特に好み。彼女は子供が好きで、時折自身も無邪気に遊びまわる。彼女は、彼女は、彼女は。どれも、ツイートからじゃ何も読み取れない、俺が付与した彼女のあるべき姿だ。起きて、文章を仕上げて、そして心には虚しい以外の感情が浮かばない。
分かりやすく言うなら、花を育てる感覚に似ている。水を注ぎ、栄養をたっぷり与え、日の光と風を全身に浴びさせて、俺が花から得る物理的なものは何もない。花の子孫繁栄の手助けとしてコマとなり動いたに過ぎない。花側から見ても、ただ育った環境が良かったという認識にしかならないだろう。それでいい。俺はただ目の前で、花が咲くのを見られたらそれで良かった。植物と違って人間は枯れない。根腐れもしない。メリットがあれば、大切に大事に育てれば、半永久的に、花を咲かせ続けてくれる。これほど幸せなことはないだろう。自らの手で育つ様を、永遠に見られるなんて。
ああ、今日も彼女が好きだ。
恋は病気で愛は狂気。言い得て妙だ。病気、狂気、これはまさしく狂気だろう。まごうことなき、彼女への愛なのだから。世間で言う正しい愛じゃないことくらい、まだ正気を保ってる俺の脳は理解してる。が、正しさが必ずしも人を幸せにするわけではない。しかし、正しくない、道が外れている、本当の愛ではない、そう声高に叫ぶ内なる自分がいるのも確かで、結局俺は世間よりも何よりも、俺に足を引っ張られて前に進めないまま、深く深く沈んでいく。ただ一つ言えるのは、どんな形であれ、俺が彼女に向ける愛は狂気であり、すなわちそれが愛ということだ。
純粋な愛からなる狂気ならどれほど良かっただろう、と、目覚めた瞬間トイレに駆け込み僅かばかりの胃液を吐き出しながら考えていた。つい先日の思考を巻き戻して、何処かに齟齬があったかと必死に辿るが吐き気に消されて頭の中が黒に塗り潰される。
違和感を感じたのは夢が始まってすぐのことだった。視界が、進み方が、現実と大差ない。変だ。いつもなら若干の浮遊感から始まる夢が、地に足ついた感覚で、見える手や腕も自身のもので恐らく間違いない。なぜだ。初めてのパターンに内心は動揺しているが、夢の中の俺は平然としている。俺は黙々と愛車を運転し、車は山道を奥へ奥へと進んでいく。ガタゴトと揺れる車に酔いそうになりながらも、ナビを切りただ道なりに進んで、そして暫くしてから、脇道へと入った。脇道といっても草は生え放題、道未満のその木のないエリアを少し走ってから車を止めた俺は、車内のライトをつけ、行儀悪く身を乗り出して後方座席へ移動し、転がっていた黒い巨大なビニール袋を破いた。
キツく縛られまるで芋虫のような姿で袋から出てきたのは、紛れもない、何度夢想したかわからない、愛おしい彼女だった。俺は、彼女の着ている薄いワンピースの感触を楽しむように掌で撫で、身体のラインを触れて覚えていく。凹凸、滑らかな生肌を想像しながら身体を撫で回し、スカートの裾を少しずつたくし上げていく。彼女が噛んでいる猿轡には血が滲んでおり、嫌々、と首を振っては綺麗な涙をぱたぱた散らす。そのリスのような丸い目に映る俺はきっと、この世の誰よりも恐ろしい化け物に見えているだろう。身体を暴く手は止まらない。胸を、局部を、全てあらわにし、下着を一度抱きしめてから破り捨てる。そして、現れた汚れなき場所へ、手を、口を寄せ、そして、俺は、彼女と、一つになった。頭の中が気持ちいい、暖かい、柔らかい、という白痴のような感想で埋め尽くされる。彼女に埋まった俺の身体の一部が溶けてしまう、気持ち良さで脳が溶けてしまう、身体の境界も全て失ってただ善がる概念になってしまう。ああ、ああ、と、感嘆する声が漏れて、俺は目の前の柔い身体を撫で回し、噛み、舐めしゃぶり、全身で味わった。涎が溢れて止まらない。彼女の柔らかい腹にぼたぼたと泡混じりで落ち溜まっていく。鼓膜に己の荒い呼吸音だけが響いて、車外の虫の声も彼女の呻き声も、何も聞こえない。ただただ車はギシギシと揺れ、彼女の目尻から絶えることなく涙が溢れて、俺の心から絶えることなく多幸感が溢れて、彼女の中に彼女と俺が混ざり合った生き物の種が植え付けられた。
死んだと見間違う目をした彼女へ、俺は口を寄せて一言、囁く。
『今日も、好きだよ。』
そこで目が覚めた。
吐くものが無くなってもまだ喉がひくりひくりと痙攣していた。苦しい。買い溜めしておいた水の段ボールを引き寄せて、無造作に掴んだ一本を雑に開け胃へと流し込む。零れた水が首を伝ってTシャツを濡らした。ぜえぜえと喉が鳴る。頭を振り払って、絞り出した声は驚くほど情けないものだった。
「そんな、はずはない、あんなの、俺じゃ、俺じゃない、っ、ぅ...」
逆流する胃液に応戦するように水を飲む。喋ると逆効果なのは分かっているのに、誰に主張したいのか、言葉は止まらない。今話しているのは俺か、誰か、分からない。
「俺はそんなこと望んでない!!!!っ、くそ、ふざけんな...っ、クソ...」
込み上げた涙は悔しさ故。浅ましい己の脳がどうにも恥ずかしく、憎らしく、それに縋って自尊心を保っていた己が卑しく、そして何よりも己の夢の特性に殺意が湧いた。
一度、目を覆っても嫌になるような凄惨な夢を見た。それは、簡単に言えば理不尽な男がバールで一家をぐちゃぐちゃに叩き潰す話だった。書くべきなのか、と筆が止まり、彼の人格を放置したまま俺は1日過ごして眠り、そして、同じ夢を見た。次の日も、次の日も、むせ返るような血の匂いと足を動かすたびにびちゃりと鳴る足音と、頭部を殴った拍子に転がり落ちた眼球を踏んだ足裏の感触と、その後彼の同居人が作ったハンバーグの味が消えないまま1週間が経ち、俺は書かなければ夢に殺されると自覚して、筆を取った。
夢を使って自分を満たす以上、逃げることは許されない、ということか。忌々しい。まだ治らない吐き気に口元を押さえ、放り投げていたスマートフォンを手に取った。仕事を休んでも夢に囚われ続ける。ならば、書くしかない。時刻は朝の4時半過ぎを指し示していた。
そして、彼女を好き放題貪った話がスマートフォンの中に出来上がった。満員電車で誤字チェックをすると、周りの乗客の視線がこちらに向いている気がした。フラフラするが、仕事からは逃げられない。あの夢も、俺の偽物もこれで消えた。今日は眠れる。
楽観視、だったんだろう。巣食う闇の深さは思った以上だった。俺は翌日も吐き気で目覚めトイレに駆け込み、脳内をぐるぐると駆け回る、四肢に残る彼女の感触と、膣内の締め付けと湿り気、背中に走る絶頂感と共に噛みちぎった喉笛のコリコリとした食感、口に溢れる鉄臭い鮮血の味、そして、恍惚とした表情で俺に抱かれたまま絶命した彼女の顔を、振り解いて捨てようとしては目眩に襲われた。
「分かった、書くから、分かったから...俺じゃない、あれは俺じゃない、俺の皮を被った偽物だ、」
彼女の夢を見始めてから、ツイッターを覗かなくなった。
彼女は、毎日俺の夢に出てくるようになった。最悪の気分で夢に無理矢理起こされ、時折吐いて、震える手でなんとか夢を文字で起こして、溜まっていくそれらはメモを圧迫していく。救えない。先が見えない。
そして夢で彼女を殺し始めてから、今日で3日が経った。もう、うなされることも跳ね起きることもない。静かに目を開けて、見慣れた天井を認識して、重い胃を抑えて起きるだけだ。よくもまああんなに楽しんで殺せるもんだ。と、夢の内容を反芻する。
彼女の膨らんでいた乳房も腹も尻も太ももも、鋭利なサバイバルナイフでさっくりと切り取られていた。カケラはそこかしこに散らばって、手の中には乳房があった。俺は生暖かい開かれた彼女の腹に手を探り入れて、挿入していた愚息を膣と、そしてその先に付いた子宮の上から握りしめた。ないはずの脈動を掌で感じるのは、そこが、命を育む大切な部屋だから、だろうか。暖かい、俺の作られた場所。彼女の作られた場所。人間が、人間になる場所。ああ、気持ちいい。無心で腰を動かせばがくがく揺れる彼女の少ない肉が、小さく蠢いているように見えた。動きがてら肋骨あたりを弄れば、つまみ上げた指の間で蛆虫がのたうち回っている。気味が悪い、と挟み殺して、彼女の内臓に蛆虫の体液をなすりつけた。目線を彼女の顔までやって、いや、そういえば頭は初日に落としたんだった、と、ベッド脇の机に鎮座した彼女を見遣る。目線を腹に戻す。食いちぎったであろう子宮の傷口からは血と、白濁の体液が流れ出て腹膜を彩っていた。芸術には疎いが、美しいと感じる色彩。背筋に快楽が走る。何時間でもこうしていられる。ああ、ああ、嗚呼......
こんなはずじゃなかった。彼女と見る夢はもっと暖かくて、綺麗で、色とりどりで、こんな狭い部屋で血肉に塗れた夢じゃなかったはずだ。どこで何を、どう間違えたのか、もはや何も分からない。分からないまま、夢に囚われ、俺は今日も指を動かすんだろう。
スマートフォンを握った瞬間、部屋のチャイムが鳴った。なんだ、休日のこんな朝早くに。宅配か?時計を見て顔を顰め、無視の体勢に入ろうとした俺をチャイムの連打が邪魔してきて更に苛立ちが増す。仕方なく、身体を起こして彼女の眠るベッドから降りた。
床に降り立つ足裏に触れる無数の蠅の死骸の感触が気持ち悪い。窓は閉め切っているのに片付けても片付けても湧いてくるのはなぜなんだろう。追い討ちをかけるように電子音が鳴り響く。休日にも関わらずベッド脇の机に鎮座し勘違いでアラームを鳴らす電波時計にも腹が立つ。薙ぎ払えば一緒に首まで落ちて気分は最悪だ。クソ、クソクソクソ。ただでさえ変な夢を見て気分が悪いのに。鳴り止まないチャイム。煩いな、出るよ、出るっつってんだろ。俺は仕方なく、着の身着のままで玄関のドアを開けた。
3 notes
·
View notes
Text
金曜日はカレー

前の日記にミニシアター・エイド基金が始まったので、リンクを追加しておきました。ご興味のある方はぜひ!私は何コースにしようか検討中です。
最近は家で大人しく過ごしていますが、夫もだいぶ前からテレワークになったので「家庭内天下一武道会」が開催されないよう気をつけたいです。上は最低限の買い物に出たついでに献血していただいたもの。(血液が不足しているそうなので)除菌ウェットティッシュなのがご時世。血を抜いていると、つい「アカギ」の鷲巣麻雀が浮かんできてしまいますね・・・。

ずっと家にいると曜日の感覚がなくなりがちなので、海上自衛隊方式で金曜日はカレーにすることに。上はわりと近くの紅茶専門店がスリランカ料理を出していてテイクアウトしてきたもの。パイナップルのカレーが予想外に辛くて美味しかったです。ご飯も玄米でヘルシー。

ついでにたまっていたカレー写真をまとめて。ハモニカ横丁からキチムに移転した「ピワン」。前より広くなったので、行きやすくなって嬉しい。チキンと黒胡麻坦々のハーヘンハー。生姜の佃煮が大好きでいつも頼んでしまいます。今はテイクアウトをやっているみたいなので、お近くの方はぜひ。

新宿紀伊国屋地下といえば「モンスナック」。定番のシャバシャバカレーもいいけど、私はいつもカレーバターライス一択。添えられたタンドリーチキンも美味しい。結構ボリュームあるのでお腹空いている時にどうぞ。

経堂の「スリマンガラム」。この日はタミル・ナードゥ州の収穫祭ポンガルを祝う特別メニュー。どんどんよそわれた順から食べていく方式だったので、食べかけ写真ですが・・・。写っていないけれど、お祝いの時に食べるというチャッカライ・ポンガルという甘いお粥が珍しかったです。

調布の「かれんど」という喫茶店のキーマオムカレー。キーマの下に玉子が隠れています。たまにテレビで紹介されたりしている人気店。スパイスの効いたカレーうどんも美味しいのでおすすめ。

高田馬場「ブラザー」のサバキーマカレー。サバカレーは家でもたまに作るのですが、ここは山椒が効いているのがいい。真似しよう。

錦糸町「生駒」の麻婆カレー飯排骨のせ。いわゆる町中華のカレーですね。カロリーの暴力!私は皿台湾を食べたので一口もらったけど悪魔的な美味しさでした。麻婆とカレーって合うよね。
また楽しく外食できる日々がはやく戻ってきますように・・・。
4 notes
·
View notes
Text
異邦人の庭(お試し版)

1.
逃げねばならない。娘はひたすら盗んだ馬に乗って駆け���。うだるような夏を何日も繰り返すたびに食料は尽きた。夜闇に紛れて忍び込んだ村々から水を盗み、家畜の餌を喰らい、そのまま逃げ続けた。やがて馬が死んだので、その血を啜り、肉を喰らい、腹を壊しながら先に進む。
メシュエは逃亡者であった。小領同士の争いで村は焼けた。敵領に戦利品として捕らえられた若い娘が辿る運命などたかが知れている。
敵領に仕える者らの慰み者として弄ばれ捨てられる運命はまっぴらであった。虜囚の身から成りあがることが出来るほどの幸運と美貌、狡猾さと図太さが己にあるとは思えなかった。故に、攫われて行った侍女らの悲鳴と、更に遠くから聞こえる強制されたかのような喘ぎ(あえぎ)声を聞きながら、彼女は己を犯そうとした男を、隠し持っていた短剣で刺し殺して逃げ出した。焼けた故郷を背に、誰のものとも分からぬ馬を走らせ、死体から拾った十四の娘にはいささか重い剣を腰に佩(は)いて。
行くあてはなかった。領は落ち、どこへ行けども敵地。安息の地など見つかりそうになかった。彼方から来た黎明(れいめい)女王(じょおう)を祖とする光の王朝が滅びて久しい。各領は争いに明け暮れ、互いの小さな土地を喰らいあっている。夜闇から魔物らが這い出てきた、などという噂もある。二つ頭の人喰い鬼や影を駆ける六本足の犬、それに、黎明女王の敵であった死を知らぬ夜の娘、名を消された魔女王(まじょおう)が蘇ったとも言われている。
メシュエは物陰でひそやかに語られてきた恐ろしい物語の数々を思い出す。黎明女王が身にまとった光輝(こうき)と威厳(いげん)によって、永遠に封じられた怪物。魔にその身を捧げた者。血まみれの圧政者。血と骨で塔を築き上げ、そこから冷酷に世界を支配しようとした恐るべき悪鬼。
生ぬるい風に乗って、正体のつかぬ何かのうめき声がする。砂と土埃広がる荒野には隠れられそうな場所はない。夏の暑さは夜になっても引くことはない。熱で枯れ果てた草を踏みしだきながらただ遠くへと行く。口は渇き、飢えは続く。メシュエは逃げなければという動物的な本能に駆られて逃げている己と、誰も知らない場所ですべてを終わりにしたい、と望む自分がいることに気付いていた。どちらにせよ、逃げなければならない。生き延びるにせよ死ぬにせよ、結末は自分で決めたかった。
カダール領ルス村の代官の娘であるメシュエは、良家の子女にふさわしく学問や芸術を仕込まれてこそいたが、一番の得手は剣の扱いであった。父似らしく、背は成長期の少年達を追い抜かんばかりの勢い。痩せぎすな体には幾ら食べても娘らしい丸みはつかず、目は厳しすぎた。やがて、見た目の愛らしさとは程遠いメシュエには、良縁を見つけてやるより得意の剣の技で身を立てさせたほうが良いだろうと、両親らは諦める。そのような訳で、メシュエは名高い剣士の一人を師につけられ、適度に放置されて育った。
村の同世代の少年らがメシュエの性を意識するようになってからは孤独であった。同世代の娘らは少年のようなメシュエを畏怖とも恐怖とも、憧れとも嫌悪感ともつかぬ複雑な感情で見ていた。代官の子であるが故に大っぴらに嫌われてはいなかったが、村の娘らは逃げ水のようにメシュエから距離を置いていた。
結果、透けるほどに薄く青白い肌を闘志で薄紅に染めながら、師と打ち合うのが日課となる。実戦こそ知らなかったが、貴族が挨拶のように行う会話の如き優美な剣技ではなく、攻防一体の実用的な剣技はメシュエの中に叩き込まれて行った。それが何に使われるのか、意味する所をぼんやりとしか理解されぬままに。メシュエが剣の意味を知ったのは、村が襲われてからだった。奪うための武器と奪うための技法をずっと学んできたのだ。そう思うと、気持ちが悪くなる。
夜通し歩き続ける。疲れ果てた時に気絶するように眠り、痛みを伴う後悔を覚えながら目覚める。それを繰り返す。メシュエが歩いているのは住む者の少ない荒野であった。段々村の数も減り、ここ数日は獣すら見ていなかった。メシュエはただ突き動かされるままに逃げていた。自分が今どこにいるかは皆目(かいもく)見当もつかなかった。
日は昇り、落ちる。
疎らに生えている棘の多い木を剣で切り、そこから液体を啜る。僅かな苦みの混じる青臭い味が口の中に広がる。毒があるか、そのようなことに構っていられなかった。生きているのに疲れたが、飢えで死にたくはなかった。
――どこかに行けば、雇ってもらえるだろうか。
故郷なき流れ者となった己のことをふと思う。メシュエの村を襲った兵士らの中には同じ年の程の者もいた。年経た大人の中には女戦士もいた。正規の兵ではなく、雇われ戦士だとメシュエを犯そうとしていた男は言っていた。男はメシュエの兄と同じような年頃に見え、それがたまらなく気持ち悪かった。雇われ戦士になる未来をメシュエは放り投げる。もう一人のメシュエをどこかで生み出すのは嫌だった。人を踏みにじる獣に堕す(だす)己を想像すると、また空になった胃が焼けるように痛くなり、腰に佩いた剣を邪魔に感じる。人を刺し殺すのはあっさりとしており、それにためらいも感じぬ己を思い出すたびに吐きそうになる。
――どこに行っても、同じ。
故郷のない者を誰も信用しない。故郷のない者は、雇われ戦士になるか、それが出来なければ森へ逃げて追剥(おいはぎ)まで身を落とすかしかない。どこかに所属していないものに住む地はないことを、代官の娘としてのメシュエは知っていた。父が苦い顔で締めだした逃亡者に芸人、流浪(るろう)の民達。「居つかれたら、何を持ち込むか分かったものではない――」そう、父は言っていた。
今やメシュエは面倒の種だ。そう思うと、逃げて生き延びたいという欲求は、自分の望んだ瞬間に死にたい、という諦めの混じった思いに塗り替えられる。
何時しかサンダルは壊れ、メシュエは乾いた大地の上を、足を引きずりながら歩いていた。爪は割れ、足の所々から血が滲(にじ)んでいる。夜明けの薄い月が見える。空は青みがかった黒から淡い紫へと変わりつつある。冷えた風は何度も繰り返されたように、これから暑くなるだろう。
大岩を見つけ、メシュエはもたれかかる。もう限界であった。空腹の感覚は馴染みのあるものになりすぎて、実感がなくなっていた。渇いた喉を潤せそうな木はどこにもない。
目を閉じれば蛮行(ばんこう)の記憶が火傷のようにメシュエを苛む。
眠りに落ちれば、僅かな間は痛みから逃れられる。
――願わくば、次は目覚めませんように。
あてのない祈りを胸に、気絶するようにメシュエは眠りに落ちた。
2.
澄んだ心地よい音がする。
――水の音……。
メシュエは朦朧(もうろう)とした記憶の中から音の正体を思い出し、それにつられて目が覚め、胸から広がる突き上げるような痛みにうめき声が出る。
涼しい風が肌を撫でる。嗅いだことのない華やかな香りが鼻をくすぐる。ぼんやりと開いた目に映ったのは、沢山の花びらが重なりあった見たこともない花。炎を思わせる赤、輝くばかりの黄色。一点の穢(けが)れもない白……単色の花もあれば、二色三色が斑のように混じりあったものもある。それらが細い道を作るかのように、几帳面(きちょうめん)にまっすぐに植えられている。メシュエの周りは色こそ違えど、ひらひらとした香り高い花でまとめられているようであった。
――ああ、とうとう死んだのね。
メシュエは思う。しかし、話に出てくる死後の国はこのように色鮮やかなものではなかった。白い石で出来た道と灰色の空が延々と続いているはずの死後の国にしては、メシュエがいる場所は生気に溢れていた。美を争うように咲き乱れる花達は、暗い死後の国には似つかわしくない。そもそもメシュエの飢えも渇きも残ったままだ。胸に手を当てる。鼓動(こどう)はある。まだ、生きているのかもしれない、とメシュエはぼんやりと思う。
――魔に騙されているの? それとも、妖精に?
どちらにせよ喉の渇きは限界だ。のろのろと立ち上がり、水の音を辿る。道こそ話で聞いた死後の国と同じく白い石で出来ていたが、石の上には花びらがいくつも落ちていて、さしずめ絵のよう。空は朝ののどかな光で溢れていて、どこまでも青い。
やがて、花びらが重なりあった香り高い花の道は途切れ、一気に目の前が開ける。白い石で作られた装飾の多い階段から、広場が続いている。花壇にはやはり見たことのない花が沢山。見たことのない木にはたわわに様々な種類の果実が実り、やはり同じく白い石で作られた小さなあずま屋が木陰に一つ。中央にはきらきらと水を噴き上げている大きな石作りの泉があった。
メシュエは水場を見つけた動物的な喜びに突き動かされ、力を振り絞って泉に駆け寄り、水に口を付ける。
喉を冷たいものが通りすぎ、カラカラになった喉に、胃に、心地よい痛みが走る。
ひたすら我を忘れて飲み続ける。生への執着心がここにきて一気に噴き出したかのように。冷たい、冷たい、冷たい……。
水を飲み終わったメシュエは、石造りの広場の上でごろんと横になる。石の床も、ひんやりと冷たい。
――そういえば、大人達が言っていたっけ。この世のどこかでは、善き仙女や妖精が暮らしていて、時折手助けしてくれるって。
何時から生まれたか分からぬ物語は、メシュエの心の中に救いのように広がる。もしかしたら、仙女が助けてくれたのかもしれない。
メシュエは再び眠りに落ちようとする。今度は、ただひたすらに安堵(あんど)の思いに包まれて――。
瞬間、遠くからぱたぱたと駆けてくる足音が聞こえた気がした。いや、足音は近づいている。無理やり甘い疲労感から意識を呼び戻せば、目の前には年のあまり違わぬであろう少���が一人。苛立(いらだ)ちを顔に浮かべてメシュエをじっと見ている。
「ちょっと、どこから入って来たの――」
少女は座り込み、メシュエの顔を検分するように顔を近づけて覗き込む。少女の肩につくかつかないかの暗褐色(あんかっしょく)の髪の毛がメシュエの顔にかける。あまりにも暗いので、黒と見間違いそうになるような髪色であった。様々な花を束ねたような甘い芳香がふわりと広がる。覗き込んできた瞳もまた黒と見間違いそうになる暗褐色。少女の色味の強い肌や奇妙な短い衣とズボンもあいまって、メシュエは東からくる放浪の民の姿を連想した。話で聞く仙女は色白く、波打つ髪の毛を持つ大人の女性だった。少女ではない。
「あなたは、仙女様の小間使(こまづかい)?」
やっとのことでメシュエは問いを口にした。何日ぶりか分からない他者との会話であった。
少女は肩をすくめ苦々しい顔になる。一番聞きたくない言葉を聞かされた人のように。しかし、数拍の後疲れたような諦めを顔に浮かべ、メシュエに手を差し出した。労働を知らなそうな、染みも傷も一つもない綺麗な手であった。
「生憎、わたしは仙女でもその小間使でもないから。あえて言うなら、ただのぐうたらな引きこもり庭師(にわし)。……つかまって。家に連れてくよ」
少女は吐き捨てるように言う。敵意とは違う、無関心でいて欲しいと言いたげな棘のある態度ではあったが、ここから追い出すつもりはまだないらしい。メシュエは差し出された少女の手を掴もうとするが、力が入らず手は見当外れの方に弧を描いた。それを少女は目ざとく捕まえ、メシュエを立たせようとする。しかしメシュエの足は疲れ果てたと立ち上がることを完全に放棄していた。腰に佩いた剣の重みも忘れていた。故に、体勢を崩し、少女が引っ張られる形になる。結果出来上がったのは、メシュエの上に奇妙な格好で乗っかった少女の図。
「んあああああもうっ! ゲームの最中だったのに! わざわざ来てやったのに! どうして全部上手く行かないのかな!」
メシュエはあまりにも子どもじみた少女の様子に思わず笑いだし。
気が緩み。
眠気が襲い掛かり。
「あーあーちょっと待ちなさい眠るなっ……」
意識が遠ざかる。
ぼんやりと、少女が何かを呼ぶ声が聞こえたような、そんな中でメシュエは今度こそ眠りに落ちて行った。
再び、メシュエは目覚める。天井は木で作られていて、灯りがぶら下がりながら、こちらを照らしていた。嗅いだことのない、それでもどこか美味しそうな匂いが鼻をくすぐる。起き上がろうとすれば、柔らかな寝台(しんだい)に体が沈んで行く。それ以前に、メシュエの体は動くことを拒否していた。両手両足に力が入らない。力を入れようとじたばたした後に結局諦め、メシュエはぼんやり天井と、僅かに揺れる灯りを見た。
「起きた?」
少女の声が聞こえる。刺々しさは減っていたが、不思議と万事投げやりな感じを持つ声であった。見れば、少女は陶器(とうき)の皿に銀色の匙を持ち、白くつぶつぶとした何かに茶色い汁をかけたものを持ってきていた。料理なのだろう。
「面倒だから、レトルトで済ませた。でも、味は確かだから。ああ、素晴らしきかな文明……離れて久しいけど」
寝台の側の棚に皿を置き、少女は宙を睨み手を大きく振る。何もない場所からいくつかのクッションがメシュエの目の前に落ちてくる。どれも色鮮やかで、新品のようで、見るか���に柔らかそうだ。
それから少女はああ面倒くさい、とぶつぶつ言いながらメシュエの体を起こしにかける。見た目よりも力があるようで、ぐい、と起こされたメシュエはいきなりのことに少し咳き込んだ。少女はそれにもお構いなしで片手でメシュエの体を支えながら、次々にクッションを彼女の背と寝台の後ろにぎゅうぎゅうと詰め込んで行く。
「ほら、これでちょっとは体を起こせるでしょ。ほんとの所、布団は白いから、カレーなんて何かあったらめんどいんだけど。どうせ汚れたらシーツごと捨てればいい訳だし」
ぶつぶつとメシュエには意味の分からぬ言葉をこぼす少女。メシュエは渡されるがままに陶器の皿を受け取り、どうしたらいいか分からぬままに、嗅ぎ慣れぬ匂いの間に僅かに肉汁の香りが混じった料理を匙でつんつんと突く。
「食べ方説明してなかった。白いのと混ぜて。辛かったら水を持ってくるから」
言われるがままに白い粒と茶色い汁を匙(さじ)で混ぜ、口に運ぶ。辛い? その言葉と共に燃えるような辛みが口の中を走り、メシュエは咳き込む。肉の味がほんのりとし、コクと酸味のある茶色い汁は最初の一口こそ美味だったが、ひたすらに辛かった。食べ物をいきなり得てしまった空腹の胃からも痛みが走る。
「あー、こっちの文化じゃスパイスが一般的じゃないのを忘れていたわ……一応中辛選んだんだけどな……」
また少女は意味の分からない言葉を呟いた。一応はメシュエに気を使ってくれた、のだろうか。
「待ってて、今クリームシチュー辺り温めて来るから」
「いえ、いいです、食べられなくはないので……美味しいので……」
慌ててメシュエは銀色の匙で辛い食事をかき込んだ。粘り気のある白い粒と茶色い汁は辛みこそ非常に強かったが、慣れれば食べられないこともなかった。その上、正体不明の少女の機嫌を損ねるのはまずい、と思ったのもある。代官の娘にふさわしい礼儀も何も投げ捨てて、辛みに耐えながら一心不乱に食べるメシュエ。その姿を、少女は珍しいものを観察するように眺めていた。
「水、置いといたから。むせる前に飲んで」
水はいかにも高価そうで澄んだガラスの盃に入っていた。メシュエは手を伸ばして盃を掴み、飲む。冷たい水が喉を一気に通り、辛みが一瞬和らぐ。また食べる。それを繰り返しているうちに辛さにも段々慣れる。
――あ、これ。案外美味しいかもしれない。
そう思い始めた頃には、皿の上は空になっていた。空腹と安堵がメシュエの体を満たす。
「御親切に、ありがとうございました」
「……どうも」
少女は感謝を言われ慣れていない人のように、メシュエから視線をそらした。
「あなたは、一体」
仙女ではない、と己を称する少女は不思議な料理を持ってきて、目の前で何もない場所からクッションを降らせ、貴人ですら滅多に持っていないようなガラスの盃を当たり前のように扱っていた。
「ぐうたら庭師だよ、ここから出られず、出る気もなく、何となく生きているだけの……」
自嘲(じちょう)するような様子から、メシュエは本当のことを隠している人特有の後ろ暗さを感じた。
「そうだ、あの子の一族……きみ達に言わせれば黎明女王だっけか――は、まだ元気? ここにいると時間の感覚がなくて」
少女はまるで知り合いのように伝説の中の存在と、それに繋がる血筋のことを口にする。どう考えても本人が言うようなぐうたら庭師ではない。もしくは目の前の少女は、何でもない人間であることを演じるのを楽しんでいるのかもしれないとメシュエはいぶかしむ。
「輝ける女王陛下とそのお血筋の方々は、皆、身罷(みまか)られました」
一瞬少女の暗い色の瞳に驚きが走ったのをメシュエは見逃さなかった。それから、少女はまた先ほどのような万事投げやりな様子に戻る。
「そっかー、くたばったか。何事もハッピーエンドとは行かない訳だね。あの子の人生はそれなりにハッピーだっただろうけど」
「ハッピー?」
聞きなれぬ単語をメシュエは復唱する。
「お幸せ、ってことさ。悪い魔女王を退治して、主人公になれて、皆に慕われてさ……あの子は昔っからそうだった」
吐き捨てるような少女の様子は、どこか痛々しかった。
「知り合い、なのですか?」
「知り合いも知り合い、幼馴染だよ。それを嬉しく思ったことは、一度もないけれど――」
少女は、投げやりな様子の中に、謎めいた笑みを少しほど混ぜた表情を浮かべた。どこか、不気味さを感じさせるような、年とはちぐはぐの笑みを。
「とりあえず、ここから先はわたしの暇つぶしで独り言だ」
少女は寝台の側にあった椅子に腰かけ、ぶらぶらと足を揺らす。
「昔々の話、黎明女王がただの少女で、わたしもきみと同じただの少女だった頃。昔々、本物の十四才だった頃の話」
ふとメシュエは部屋の中が薄暗くなってきたのを感じた。灯りがゆらゆらと揺れる。宵闇が近づいてきていた。
*
という訳で入稿しましたので、お試し版を! 本当は出るはずだった文フリにあわせて5月6日通販開始します。気になった方はどうぞどうぞ!
*
追記: 事前通販型イベント【Text-Revolutions Extra】に参加することとなりました。そのため5月6日からの通販ではなく、そちらでの新刊として頒布することになりました。二転三転してすみません。どうか皆さまの元に届きますように!
1 note
·
View note
Text
第35話 『旧き世に禍いあれ (3) - “猟犬の追尾"』 Catastrophe in the past chapter 3 - “Tracking hounds”

その黒い犬は、長い舌を口からだらしなく垂らしていた。太く曲がりくねったそれは、舌というよりも針のように尖っている。
褐色の闘犬に似た四肢を持っているが、頭の部分は妙にぼやけて見える。形がなく、いくつかの鋭い触手のようなシルエットのひとつが、長い舌のように見えてうねっていた。
その全体的に鋭利なシルエットは、狩猟犬を連想させた。
「何だこいつは……」
ゴットフリートの声だったのか、自分の声だったのか、それともふたりの声か。臭気と混乱で、フィリップには判断が出来なかった。
猟犬、なのだろうか。4つ足の黒い影はその太い四肢で地面にしっかりと立ち、周囲の様子を探っているように見えた。その異様な姿は生理的な嫌悪感が込み上げてくるものだったが、目を逸らすことができずにいた。こいつは一体何者なのか? どこから来た? 何故ここに? 仮にこいつが猟犬なのだとしたら、一体何を狩るためのものなのか。 何一つわからないにも関わらず、なぜか「こいつの狙いは自分だ」という説明不能な確信が強まっていく。
猟犬はゴットフリートには見向きもせず、フィリップの位置を見定めると、迷わず飛び掛かって来た。
やはりこちらに来たか、と心中で考える間もなく猟犬の舌先は首元まで迫っていた。先程受けたゴットフリートの攻撃より速い。
フィリップは即座に短距離のテレポートを行う。吐き気が込み上げるが、避ける方法は、フィリップの持つ術ではこれしかない。連続して転移を行って、魔力を使い過ぎた。
空間のブレが収まり視界が明瞭になった瞬間、フィリップは激しい痛みに苦痛の声を上げる。
「なっ!?」
確かに転移は成功したはずだった。
痛む左腕を見れば、注射針のような舌が刺さっている。
猟犬が傍らに突き立った最初とは別の盾から這い出てきている。長い舌は盾から半身だけを乗り出した猟犬の胴体から繋がっている。
フィリップはそれを引き抜こうと腕を振り回すが、抜けない。
攻撃をかわすために数歩距離を取って転移したのに、転移先の足元ですでに待ち構えていたかのような……。
猟犬は両足で地面をしっかりと捉え、頭部を振るってフィリップを引っ張る。
ゴットフリートは離れたところから、目と口を開けて呆然とその様子を見ている。
(まさか……こいつも短距離転移したのか?)
猟犬の下肢は傍の盾の影から伸びているように見えた。斜めに地面に突き刺さった盾の影から、隠れていた下肢の先が這い出してくる。
テレポートしたため、ゴットフリートとフィリップの間にはかなりの距離がある。
この距離をただ跳躍してきたとは思えない。この一瞬でそんな動きをしていたら、正確に左腕を狙う事もできそうにないし、その勢いでそのままフィリップに体当たりした方が早いだろう。人型ではない魔物で、転移術を使えるものはほとんどいないはずだ。覇王の軍勢の中でも、そんなやつは見たことがなかった。
転移でなければ説明がつかない。
(追尾するように転移して、土の地面と盾の間の空間から這い出てきた……? そんな、まさか……)
フィリップが振りほどけず、まごついている間に、舌を突き刺された左腕の変化がはじまった。
舌が刺さった周囲から、どんどんと左腕がしなびはじめたのだ。
「く、クソ……ッ!」
信じられないことの連続でパニックになりかけたが、フィリップはぐっと奥歯を噛みしめて正気を保つ。
ベルトのホルダーからナイフを取り出し、その舌を思い切り切り払った。舌は容易に切れ落ち、断面から暗い青灰色の液体がぼたぼたと垂れ落ちた。
すかさず後ずさって距離を取る。舌を切り落とされて喘いでいるように見えた猟犬は、今度は距離を保ったまま、すぐにこちらに飛んでくる様子はない。刺された左腕は、もう原型をとどめていなかった。
(腕が……なくなった……!?)
舌が抜けた後も左腕は、ミイラのように乾燥しながらどんどん細くなっていく。
ミイラというには、元の骨を無視した縮み方だった。水気を失いカラカラに乾いた野菜カスのようになっているが、内側の骨まで同様に萎縮したとしか説明がつかない。
痛みはない。すでに左腕の感覚は全くなくなっていた。かえってそれが異様に恐ろしく、フィリップは額に噴き出した冷や汗を袖で拭った。
あの舌はなんだ? 一体、何が起きた? 何かを吸われたのか? あの猟犬はどうやって足元に移動してきた? 左腕は諦めるしかないか? ぐるぐると脳をたくさんの言葉が駆け巡る。
(逃げろ……)
本能が叫ぶ。その通りだ。
逃げるしかない。ゴットフリートでさえ手に負えないのに、突然現れた襲撃者は、それ以上に危��な存在だった。この場に留まって状況を解決する術など、自分は何も持ってはいない。
じり、とフィリップがさらに後じさると、猟犬がそれを見て体を低くした。
再び、先ほど感じた刺激臭が強くなる。
ぼうっと青黒い煙が、あちこちに落ちている遺品の盾や剣、鎧といった角のあるものから幾筋も立ち上る。それぞれが凝って、どれもが同じように猟犬と同じ形状を取り始めた。左腕を奪ったはじめの一頭よりはいずれも小さいものの、やはり姿はそっくりで、姿を成すや、すべてがフィリップに敵意を向けて周囲を取り囲み始める。
(何だこれは……)
フィリップは頭の中で今まで読んだすべての文献や図録の記憶をひっくり返す。こんな怪物は、見たことも聞いたこともない。神話の類にもこのような存在が示唆された試しもなかった。
とにかく、とにかく逃げなければ。だが、どうやって?
すっかりと左腕は、押さえた右手で隠せるほど小さくなってしまった。
フィリップが駆け出す。同時に猟犬たちが地を蹴る軽い足音が響く。
「――……どうやら、てめえの飼い猟犬じゃなさそうだな」
低く太い声。
絶体絶命か。これほどの生物を前にして、さらにゴットフリートまで相手にする事など、不可能だ。
だが、ゴットフリートは、フィリップを追撃しようとする猟犬たちのいる方に剣の切っ先を突きつけて、がははと無遠慮に笑った。非常に愉快そうにその瞳の奥に紅蓮の炎が立ち上る。
「魔術師なんかよりも、数段面白そうじゃねえか! 猟犬!」
咆哮に近い怒号を上げ、剣を振りかざした。
その剣圧は風を切り裂く音を伴い、猟犬に襲い掛かる。離れたところにいたフィリップまで風圧が迫るほどの力強さ。
ゴットフリートの剣先は猟犬の一頭を切り裂く。それをはじまりにいくつもの猟犬を切り飛ばして、はじめに現れた個体に向かって行く。
猟犬たちはフィリップを追う邪魔をされて、すぐさま別方向に跳ねた。
ゴットフリートはその動きを読んでいたように、振り下ろした剣を真横に一閃する。
切っ先がかかりそうになるも、猟犬が避ける方が紙一重で早い。
大股に踏み込み、ゴットフリートが今度は大きく剣を突き出す。
小型の猟犬が何体も切り裂かれ、霧のように消える。逃げ惑う猟犬たちは、最大の個体を守るようにゴットフリートを取り巻く。群れの鼻先は、すでにその全てがフィリップから逸れてゴットフリートに向けられていた。
一閃、二閃、迫る取り巻きの小型を次々なぎ倒し、首を落とされた小型の胴を蹴り飛ばして、大型の猟犬の腹部に強かに打ち込む。大型はその衝撃によろめき、間髪入れずゴットフリートは蹴り抜いた足を踏み込み、大剣の先が轟音を立てて唸る。
「おらぁ!!」
怒号。
最後に残った猟犬は、すんでのところで体勢を整え、身を翻してゴットフリートに飛び掛かる。ゴットフリートは構わず迫る猟犬の頭部目掛けて大剣を振り抜いた。
一瞬の、そして突然の静寂。猟犬がいない。すっかり気配までなくなった。息遣いすらも。
歴戦の猛者であるゴットフリートでさえ、大剣が命中する直前に突然姿を消した猟犬を目で追うことはできなかった。
「ああ? 犬っころめ! どこに行きやがったぁ!」
夜の雪山に、野太い声が響く。
ゴットフリートは消えた猟犬たちを探すために、見開いた眼で周囲を見渡す。そこには、膝をついたフィリップとゴットフリートの姿しかない。
けれど、ゴットフリートは警戒を解かない。手応えがなかった。これで退く相手ではないと彼は理解していたし、フィリップも同様に理解していた。
「ふんっ」
気合を入れなおし、ゴットフリートは柄を握る手に力を込めた。どこから飛び出してきても、一振りで仕留める。その巨躯と同じほどの丈の剣を、それだけの速さで振るえる者は、トラエに彼を置いて他にはいない。
辺りを窺っているゴットフリートの背後から、突然現れた大型が飛びかかる。ゴットフリートは殺気のみからその出現を察知し、反転して剣を振り抜く。
反応されることを予期してか、猟犬は剣先の手前で空を蹴って退き、振り抜かれた剣先をやり過ごしてから再び地を蹴ってゴットフリートに向かって飛ぶ。
それに応じ、振り抜いた剣の勢いに任せて回転、跳躍し、飛来する猟犬に自ら飛び込んで二撃目を狙う。
満月の空に、飛び掛かる猟犬と剣を構えた英雄の影が浮かび上がる。
「これで決まりだ!」
猟犬の尖った舌と、ゴットフリートの剣先が交差する。
猟犬は何も貫くことなく着地した。
さきほどまでゴットフリートが立っていた場所に、そっくりと足の跡があるだけだった。
突然、目の前から獲物がいなくなり、墓石の影から小型の仲間たちもそろそろと出てきた。全頭が戸惑ったかのように辺りを見渡し歩き回る。
本来の獲物であった筈のフィリップも、邪魔をしてきたゴットフリートの姿もなかった。
今度は雪の上に、奇妙な猟犬たちだけが取り残されていた。
周囲をしばらくうろついたあと、鼻をクンクンを動かす。
静かに、一頭が墓石の影に消えていく。
また一頭、また一頭とその後に続き、やがて全ての猟犬が、戦場から姿を消した。
残されたのは、戦死者たちを覆う雪だけだった。

猟犬の頭をたたき割るために剣を振るったその刹那、世界が光に包まれた。
直後に、体の重心がブレた感覚に襲われ、ゴットフリートは反射的に目をつぶった。
1秒と経たずに体の重心が元の位置に戻り、目を開ける。
猟犬はいなかった。
まるで夢だったかのように、自分ひとり、小汚い部屋の中心に立っていた。
肩当てには、剣圧で舞い上げて浴びた雪が、まだ薄く積もっていた。剣先にも、あの薄気味悪い生き物の返り血がこびりついたままだ。
「……ったく、興が冷めるぜ」
満月の照らす雪の斜面ではなく、見慣れた兵舎の中だ。誰かが置き忘れたであろうシャツで剣の血を軽く拭い、鞘に戻す。兵舎は狭すぎる。抜身の剣を手に歩けるほどの幅もない。
久々に、心の底の方から沸き立つような敵と相対した興奮は、まだ体の底にくすぶっていた。
「やってらんねえな!」
ゴットフリートは、転がっていた誰かの飲み残しの木製ジョッキを蹴り飛ばした。ジョッキは棚に当たり、耳障りな音を立てる。何もかもが苛立たしく、やり場のないフラストレーションがゴットフリートの内に燻っていた。
「助けたつもりかよ、あの野郎め……俺は勝ってたッ」
兜を小脇に抱えてバリバリと頭を掻いて、フンと大きな鼻息を吐いた。
また酒保にでも行くか、今日の分はもう飲んだけど若ぇ奴の分をふんだくるか、などと考えながら歩きはじめたゴットフリートは、異変に気が付いた。
「んだぁ? うるせえなぁ」
遠くから音がする。建物の外か。すぐにそれが何か、感づき、目を見開く。
この音を、ゴットフリートは知っている。身近でずっと聞き続け、その中を走り抜けてきた。
戦の気配。命を奪い合う者たちが放つ、独特の気配。ゴットフリートが生きる場所だ。魔術師、猟犬。次々降って湧いた獲物を前におあずけを食らって行き場をなくした”飢え”が、再び首をもたげた。
にやりと口角を上げて、ゴットフリートは胸を張った。
「仕事の時間か」
扉を蹴破り開けて飛び出す足取りは、子供のように無邪気だった。

(自分がしたことは、本当に許されることなのだろうか……)
スヴェンは何度も何度も繰り返した疑問に、自ら押しつぶされそうになっていた。
とんでもない過ちを犯したのではないだろうか。
真実は追い求めてきた。時空を遡行するという研究の真相に魅せられた心はまだ輝きを失っていない。
だが、それはあくまで自分の手で引き寄せたかった奇跡のはずだ。自らが完成してこそ意味を持った奇跡だったのではないか。
それでも、自分の人生で成し遂げられないというのなら、せめて知りたいと願ってしまった。
スヴェンは泣きたいような叫びたいような、複雑な心を噛みしめた。
ぶんぶんと首を振る。
「これでいいのだ……吾輩が自分で決めたことだ……」
そう思いながらも、机の上の本を開くことは出来なかった。
フィリップから、警備の情報と引き換えに得た本。
真実を目にしてしまえば、知る前には戻れない。
(未来からもたらされた知識……)
本来は今、ここには存在しないはずの知識を、自分が詳らかにしてしまってもよいのか。自分のためだけに使うのであれば、問題はないと言えるのか。意図せず自身のものとして世界に放り出されてしまわないか。自問する言葉はいくらでも心の底から浮かび上がってくる。
「……しばらく何か違う本でも読もう……」
再び窓の外を見ると、兵士たちが駆け出し、叫び合う声がした。敵襲……? 今、敵襲と言っていなかったか? 背中を汗が伝う。
窓の外に身を乗り出して、メガネを押し上げる。目を細め必死で夜闇を見た。
斜面を敵がやってくる。しかし、何か妙だ。あの集団はどうしたことか、どいつもこいつも大きく頭を左右に振り、各々が方方によろめき歩いて、統率が取れていないように見える。雪に足を取られ倒れる、しかしその横から、また別の兵士が立ち上がる。そうして、起き上がった者が列に加わり、数が見る間に増えていっている。ラウニやソルデの進軍にしては、不自然過ぎる集団だ。
「あれは……?」
深いため息を漏らし、背後の物音にスヴェンは振り向いた。
室内に、フィリップが立ち尽くしていた。昼間に姿を消した時とは打って変わってげっそりと痩せこけた印象で、左肩を押さえている。
「おお……」
「ここはもう危険だ」
フィリップは微かに震えた声でスヴェンに告げた。
「何が起きてるんだ?」
「襲われた。ゴットフリートに出くわして、その後どこからか猟犬のようなものが現れた」
「ゴットフリートと?!」
スヴェンは思い出した。ゴットフリートは酒を飲んでは城外を機嫌よく散歩することがある。そんなに頻繁ではないので失念していが、まさか、今日に当たるとは……。伝えなかった事に対する罪悪感がほんの一瞬だけ芽生えたが、すぐにそれは顔を隠した。
スヴェンを見つめて、フィリップは右手を離した。その下には、あるべきものがない。
「腕、が……」
切断されているわけでもない。ただ、不自然なほど委縮し、形を変えていた。
恐ろしくて息を飲む。
「分からない。猟犬に刺されたあとで、こうなった」
スヴェンは目を白黒させて、カチャカチャとメガネを直した。
「刺されたんだ。あの長い舌で……肘の上の辺りをやられたと思ったら、腕がこうなった」
「し、知らない!そんなおかしな犬がこの雪山に出るなんて聞いた事がない!私は知らなかった事だぞ!? ご、ゴットフリートの事だって…!」
スヴェンは必死に、大げさな身振り手振りで弁明した。
フィリップは探るようにスヴェンを見ていたが、やがて息を吐いて項垂れた。
「……ゴットフリートの方に猟犬の注意が向いて、その隙に長距離転移の準備が出来た。今頃、ゴットフリートも城塞のどこかに移せたと思う」
「なんてことだ……今、外が大変なことになっているようだ。君が何かしたわけではないのか?」
スヴェンのどこか切羽詰まった様子に、フィリップは首を傾げた。それを見て、スヴェンは腕を突き出して、研究室の窓の外を指差した。
フィリップは、山の斜面から兵士たちの屍体が起き上がる光景を目にした。
そして、慄いた。
遠くから音がする。うめき声が重なり合い、波のように城塞に押し寄せている。
「これ、は……」
「信じられないだろうが、ここから見る限りでは、斜面の戦死者が起き上がっているように見える。そうとしか思えん。雪の下から出てきて、城塞に向かってくる……お前がやったんじゃなかろうな?」
「……屍体が、起き上がった……? それは…」
スヴェンは不服そうにメガネを押し上げた。
「死体が起き上がって、この城を攻めてきている」
スヴェンの言葉を聞きながら、フィリップも窓の外に身を乗り出した。
信じられない。
さきほどまでフィリップは、ゴットフリートとあの猟犬と共に斜面にいた。猟犬に襲われ、命からがら城塞まで転移してきた。
しかし……、斜面からやってきているものは、猟犬ではない。先程雪の下から掘り出した兵士の屍体と同じ防具を着込んでいることが、月明かりに照らされて垣間見える。
「外で何があった? 一体何が起きている!? 未来から来たのなら、この城塞の歴史は知っているのだろう? 何があったのだ、あれはなんなんだ、このあと何が起きる!?」
「そんな…… 知らない、こんな事、僕は…」
城内では悲鳴まで上がり始めている。
フィリップは真っ直ぐと城塞に向かう屍者の群れを見る。ひとつひとつ小さな点に見えるが、それが幾千も動き始める。
ありえない。
だが、フィリップは屍者がひとりでに動くことがある前例を知っている。
世界の秩序が崩壊した日から、覇王の呪いを受けた屍者たちが立ち上がり、人々を襲い始めた。フィリップとグレーテルは、その屍体たちとこれまで戦ってきたのだ。
全てが始まったあの日の情景によく似ている。
ただ、ありえない。フィリップが知っている歴史では、この時期は人間同士の小競り合いこそあったが、まだ覇王は目覚めていなかったはずだ。屍者たちも、まだ起き上がってきてはいなかったはずだ。
だから、今こうして屍者がひとりでに動くなんてことは起こりえない。
「どうして……」
フィリップは言葉を飲み込んだ。
間違いない――あれは覇王の呪いを受けた者達だ。始めこそふらつきながら斜面を這い上がってきてた屍者たちの動きは見る間に活性化されていき、兵士たちの数倍も速く、そして生身の人間では考えられない力強さで兵士たちを易易となぎ倒す。兵士たちは木の葉のように簡単に弾き飛ばされていく。ただの屍者操作、ゾンビの類でできる芸当ではない。Buriedbornesの術を受けた者だけに見られる、人間を超えた動き。
屍者には感情がない、痛覚もない。限界を超えて動き、破壊され動けなくなるまで何度でも立ち上がる。
人間は疲弊する。今までの戦場とはかけ離れている事態に混乱している。倒れても何度でも起き上がる怪物に対して抱かれる感情は、恐怖でしかない。訳も分からず、城の者達は圧倒的な力を持った屍者たちに蹂躙されていく。悲鳴がブラストフォート城塞を支配している。
これは、あの日と同じではないか。
忘れることのできないあの日に。
「フィリップ、何が起きているんだ!」
「僕には分からない、何も知らない」
狼狽し、迫るスヴェンを突き放した。よろめき驚いて目を見開いたスヴェンに、フィリップは胸が痛んだ。まだ何も確信はないが、他に理由が考えられない。これは覇王の呪いだ。フィリップたちが立ち向かっている困難とあまりにも酷似している。
まさか、自分がここに来たことで、自分が受けている呪いをこの時代に広めてしまったのではないか?
それをどう伝えれば良い?また伝えたところで、何ができる?
「……ん? 何か臭わないか?」
スヴェンが怪訝そうに声を上げた。
フィリップは、心臓の鼓動が跳ねるのを感じた。
この臭いを、フィリップは一度嗅いでいる。
咄嗟に周囲を見渡して、机の角から青黒い煙が細く漏れ始めたのを見つける。
(いけない……! あの猟犬がくる!)
フィリップは確信した。これ以上、この時代にいることはできない。
全ての謎に、この場で答えを出す時間はもうない。閉鎖時空間を開く呪文の詠唱を始める。
「フィリップ!」
発生させた時空の”扉”に、自ら飛び込んだ。
「これから何が起こるかだけでも…!」
スヴェンの悲痛な叫び声がこだましたが、最後まで耳にする事はできなかった。
――何かを考えている暇もなかった。
フィリップには、スヴェンを置き去りにし、現在へ逃げ帰る以外の選択肢はなかった。

~つづく~
原作: ohNussy
著作: 森きいこ
※今回のショートストーリーはohNussyが作成したプロットを元に代筆していただく形を取っております。ご了承ください。
旧き世に禍いあれ(4) - “悔恨”
「ショートストーリー」は、Buriedbornesの本編で語られる事のない物語を補完するためのゲ��ム外コンテンツです。「ショートストーリー」で、よりBuriedbornesの世界を楽しんでいただけましたら幸いです。
2 notes
·
View notes
Text
iFontMaker - Supported Glyphs
Latin//Alphabet// ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789 !"“”#$%&'‘’()*+,-./:;<=>?@[\]^_`{|}~ Latin//Accent// ¡¢£€¤¥¦§¨©ª«¬®¯°±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ Latin//Extension 1// ĀāĂ㥹ĆćĈĉĊċČčĎďĐđĒēĔĕĖėĘęĚěĜĝĞğĠġĢģĤĥĦħĨĩĪīĬĭĮįİıIJijĴĵĶķĸĹĺĻļĽľĿŀŁłŃńŅņŇňʼnŊŋŌōŎŏŐőŒœŔŕŖŗŘřŚśŜŝŞşŠšŢţŤťŦŧŨũŪūŬŭŮůŰűŲųŴŵŶŷŸŹźŻżŽžſfffiflffifflſtst Latin//Extension 2// ƀƁƂƃƄƅƆƇƈƉƊƋƌƍƎƏƐƑƒƓƔƕƖƗƘƙƚƛƜƝƞƟƠơƢƣƤƥƦƧƨƩƪƫƬƭƮƯưƱƲƳƴƵƶƷƸƹƺƻƼƽƾƿǀǁǂǃDŽDždžLJLjljNJNjnjǍǎǏǐǑǒǓǔǕǖǗǘǙǚǛǜǝǞǟǠǡǢǣǤǥǦǧǨǩǪǫǬǭǮǯǰDZDzdzǴǵǶǷǸǹǺǻǼǽǾǿ Symbols//Web// –—‚„†‡‰‹›•…′″‾⁄℘ℑℜ™ℵ←↑→↓↔↵⇐⇑⇒⇓⇔∀∂∃∅∇∈∉∋∏∑−∗√∝∞∠∧∨∩∪∫∴∼≅≈≠≡≤≥⊂⊃⊄⊆⊇⊕⊗⊥⋅⌈⌉⌊⌋〈〉◊♠♣♥♦ Symbols//Dingbat// ✁✂✃✄✆✇✈✉✌✍✎✏✐✑✒✓✔✕✖✗✘✙✚✛✜✝✞✟✠✡✢✣✤✥✦✧✩✪✫✬✭✮✯✰✱✲✳✴✵✶✷✸✹✺✻✼✽✾✿❀❁❂❃❄❅❆❇❈❉❊❋❍❏❐❑❒❖❘❙❚❛❜❝❞❡❢❣❤❥❦❧❨❩❪❫❬❭❮❯❰❱❲❳❴❵❶❷❸❹❺❻❼❽❾❿➀➁➂➃➄➅➆➇➈➉➊➋➌➍➎➏➐➑➒➓➔➘➙➚➛➜➝➞➟➠➡➢➣➤➥➦➧➨➩➪➫➬➭➮➯➱➲➳➴➵➶➷➸➹➺➻➼➽➾ Japanese//かな// あいうえおかがきぎくぐけげこごさざしじすずせぜそぞただちぢつづてでとどなにぬねのはばぱひびぴふぶぷへべぺほぼぽまみむめもやゆよらりるれろわゐゑをんぁぃぅぇぉっゃゅょゎゔ゛゜ゝゞアイウエオカガキギクグケゲコゴサザシジスズセゼソゾタダチヂツヅテデトドナニヌネノハバパヒビピフブプヘベペホボポマミムメモヤユヨラリルレロワヰヱヲンァィゥェォッャュョヮヴヵヶヷヸヹヺヽヾ Japanese//小学一年// 一右雨円王音下火花貝学気九休玉金空月犬見五口校左三山子四糸字耳七車手十出女小上森人水正生青夕石赤千川先早草足村大男竹中虫町天田土二日入年白八百文木本名目立力林六 Japanese//小学二年// 引羽雲園遠何科夏家歌画回会海絵外角楽活間丸岩顔汽記帰弓牛魚京強教近兄形計元言原戸古午後語工公広交光考行高黄合谷国黒今才細作算止市矢姉思紙寺自時室社弱首秋週春書少場色食心新親図数西声星晴切雪船線前組走多太体台地池知茶昼長鳥朝直通弟店点電刀冬当東答頭同道読内南肉馬売買麦半番父風分聞米歩母方北毎妹万明鳴毛門夜野友用曜来里理話 Japanese//小学三年// 悪安暗医委意育員院飲運泳駅央横屋温化荷開界階寒感漢館岸起期客究急級宮球去橋業曲局銀区苦具君係軽血決研県庫湖向幸港号根祭皿仕死使始指歯詩次事持式実写者主守取酒受州拾終習集住重宿所暑助昭消商章勝乗植申身神真深進世整昔全相送想息速族他打対待代第題炭短談着注柱丁帳調追定庭笛鉄転都度投豆島湯登等動童農波配倍箱畑発反坂板皮悲美鼻筆氷表秒病品負部服福物平返勉放味命面問役薬由油有遊予羊洋葉陽様落流旅両緑礼列練路和 Japanese//小学四年// 愛案以衣位囲胃印英栄塩億加果貨課芽改械害街各覚完官管関観願希季紀喜旗器機議求泣救給挙漁共協鏡競極訓軍郡径型景芸欠結建健験固功好候航康告差菜最材昨札刷殺察参産散残士氏史司試児治辞失借種周祝順初松笑唱焼象照賞臣信成省清静席積折節説浅戦選然争倉巣束側続卒孫帯隊達単置仲貯兆腸低底停的典伝徒努灯堂働特得毒熱念敗梅博飯飛費必票標不夫付府副粉兵別辺変便包法望牧末満未脈民無約勇要養浴利陸良料量輪類令冷例歴連老労録 Japanese//小学五〜六年// 圧移因永営衛易益液演応往桜恩可仮価河過賀快解格確額刊幹慣眼基寄規技義逆久旧居許境均禁句群経潔件券険検限現減故個護効厚耕鉱構興講混査再災妻採際在財罪雑酸賛支志枝師資飼示似識質舎謝授修述術準序招承証条状常情織職制性政勢精製税責績接設舌絶銭祖素総造像増則測属率損退貸態団断築張提程適敵統銅導徳独任燃能破犯判版比肥非備俵評貧布婦富武復複仏編弁保墓報豊防貿暴務夢迷綿輸余預容略留領異遺域宇映延沿我灰拡革閣割株干巻看簡危机貴揮疑吸供胸郷勤筋系敬警劇激穴絹権憲源厳己呼誤后孝皇紅降鋼刻穀骨困砂座済裁策冊蚕至私姿視詞誌磁射捨尺若樹収宗就衆従縦縮熟純処署諸除将傷障城蒸針仁垂推寸盛聖誠宣専泉洗染善奏窓創装層操蔵臓存尊宅担探誕段暖値宙忠著庁頂潮賃痛展討党糖届難乳認納脳派拝背肺俳班晩否批秘腹奮並陛閉片補暮宝訪亡忘棒枚幕密盟模訳郵優幼欲翌乱卵覧裏律臨朗論 Japanese//中学// 亜哀挨曖扱宛嵐依威為畏尉萎偉椅彙違維慰緯壱逸芋咽姻淫陰隠韻唄鬱畝浦詠影鋭疫悦越謁閲炎怨宴援煙猿鉛縁艶汚凹押旺欧殴翁奥憶臆虞乙俺卸穏佳苛架華菓渦嫁暇禍靴寡箇稼蚊牙瓦雅餓介戒怪拐悔皆塊楷潰壊懐諧劾崖涯慨蓋該概骸垣柿核殻郭較隔獲嚇穫岳顎掛括喝渇葛滑褐轄且釜鎌刈甘汗缶��冠陥乾勘患貫喚堪換敢棺款閑勧寛歓監緩憾還環韓艦鑑含玩頑企伎忌奇祈軌既飢鬼亀幾棋棄毀畿輝騎宜偽欺儀戯擬犠菊吉喫詰却脚虐及丘朽臼糾嗅窮巨拒拠虚距御凶叫狂享況峡挟狭恐恭脅矯響驚仰暁凝巾斤菌琴僅緊錦謹襟吟駆惧愚偶遇隅串屈掘窟繰勲薫刑茎契恵啓掲渓蛍傾携継詣慶憬稽憩鶏迎鯨隙撃桁傑肩倹兼剣拳軒圏堅嫌献遣賢謙鍵繭顕懸幻玄弦舷股虎孤弧枯雇誇鼓錮顧互呉娯悟碁勾孔巧甲江坑抗攻更拘肯侯恒洪荒郊貢控梗喉慌硬絞項溝綱酵稿衡購乞拷剛傲豪克酷獄駒込頃昆恨婚痕紺魂墾懇沙唆詐鎖挫采砕宰栽彩斎債催塞歳載剤削柵索酢搾錯咲刹拶撮擦桟惨傘斬暫旨伺刺祉肢施恣脂紫嗣雌摯賜諮侍慈餌璽軸叱疾執湿嫉漆芝赦斜煮遮邪蛇酌釈爵寂朱狩殊珠腫趣寿呪需儒囚舟秀臭袖羞愁酬醜蹴襲汁充柔渋銃獣叔淑粛塾俊瞬旬巡盾准殉循潤遵庶緒如叙徐升召匠床抄肖尚昇沼宵症祥称渉紹訟掌晶焦硝粧詔奨詳彰憧衝償礁鐘丈冗浄剰畳壌嬢錠譲醸拭殖飾触嘱辱尻伸芯辛侵津唇娠振浸紳診寝慎審震薪刃尽迅甚陣尋腎須吹炊帥粋衰酔遂睡穂随髄枢崇据杉裾瀬是姓征斉牲凄逝婿誓請醒斥析脊隻惜戚跡籍拙窃摂仙占扇栓旋煎羨腺詮践箋潜遷薦繊鮮禅漸膳繕狙阻租措粗疎訴塑遡礎双壮荘捜挿桑掃曹曽爽喪痩葬僧遭槽踪燥霜騒藻憎贈即促捉俗賊遜汰妥唾堕惰駄耐怠胎泰堆袋逮替滞戴滝択沢卓拓託濯諾濁但脱奪棚誰丹旦胆淡嘆端綻鍛弾壇恥致遅痴稚緻畜逐蓄秩窒嫡抽衷酎鋳駐弔挑彫眺釣貼超跳徴嘲澄聴懲勅捗沈珍朕陳鎮椎墜塚漬坪爪鶴呈廷抵邸亭貞帝訂逓偵堤艇締諦泥摘滴溺迭哲徹撤添塡殿斗吐妬途渡塗賭奴怒到逃倒凍唐桃透悼盗陶塔搭棟痘筒稲踏謄藤闘騰洞胴瞳峠匿督篤凸突屯豚頓貪鈍曇丼那謎鍋軟尼弐匂虹尿妊忍寧捻粘悩濃把覇婆罵杯排廃輩培陪媒賠伯拍泊迫剝舶薄漠縛爆箸肌鉢髪伐抜罰閥氾帆汎伴畔般販斑搬煩頒範繁藩蛮盤妃彼披卑疲被扉碑罷避尾眉微膝肘匹泌姫漂苗描猫浜賓頻敏瓶扶怖附訃赴浮符普腐敷膚賦譜侮舞封伏幅覆払沸紛雰噴墳憤丙併柄塀幣弊蔽餅壁璧癖蔑偏遍哺捕舗募慕簿芳邦奉抱泡胞俸倣峰砲崩蜂飽褒縫乏忙坊妨房肪某冒剖紡傍帽貌膨謀頰朴睦僕墨撲没勃堀奔翻凡盆麻摩磨魔昧埋膜枕又抹慢漫魅岬蜜妙眠矛霧娘冥銘滅免麺茂妄盲耗猛網黙紋冶弥厄躍闇喩愉諭癒唯幽悠湧猶裕雄誘憂融与誉妖庸揚揺溶腰瘍踊窯擁謡抑沃翼拉裸羅雷頼絡酪辣濫藍欄吏痢履璃離慄柳竜粒隆硫侶虜慮了涼猟陵僚寮療瞭糧厘倫隣瑠涙累塁励戻鈴零霊隷齢麗暦劣烈裂恋廉錬呂炉賂露弄郎浪廊楼漏籠麓賄脇惑枠湾腕 Japanese//記号// ・ー~、。〃〄々〆〇〈〉《》「」『』【】〒〓〔〕〖〗〘〙〜〝〞〟〠〡〢〣〤〥〦〧〨〩〰〳〴〵〶 Greek & Coptic//Standard// ʹ͵ͺͻͼͽ;΄΅Ά·ΈΉΊΌΎΏΐΑΒΓΔΕΖΗΘΙΚΛΜΝΞΟΠΡΣΤΥΦΧΨΩΪΫάέήίΰαβγδεζηθικλμνξοπρςστυφχψωϊϋόύώϐϑϒϓϔϕϖϚϜϞϠϢϣϤϥϦϧϨϩϪϫϬϭϮϯϰϱϲϳϴϵ϶ϷϸϹϺϻϼϽϾϿ Cyrillic//Standard// ЀЁЂЃЄЅІЇЈЉЊЋЌЍЎЏАБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯабвгдежзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюяѐёђѓєѕіїјљњћќѝўџѢѣѤѥѦѧѨѩѪѫѬѭѰѱѲѳѴѵѶѷѸѹҌҍҐґҒғҖҗҘҙҚқҜҝҠҡҢңҤҥҪҫҬҭҮүҰұҲҳҴҵҶҷҸҹҺһҼҽҾҿӀӁӂӇӈӏӐӑӒӓӔӕӖӗӘәӚӛӜӝӞӟӠӡӢӣӤӥӦӧӨөӪӫӬӭӮӯӰӱӲӳӴӵӶӷӸӹӾӿ Thai//Standard// กขฃ���ฅฆงจฉชซฌญฎฏฐฑฒณดตถทธนบปผฝพฟภมยรฤลฦวศษสหฬอฮฯะัาำิีึืฺุู฿เแโใไๅๆ็่้๊๋์ํ๎๏๐๑๒๓๔๕๖๗๘๙๚๛
see also How to Edit a Glyph that is not listed on iFontMaker
#FAQ#ifontmaker2#Symbols#Dingbat#Cyrillic#Greek#Coptic#thai#character set#character sets#list#language
4 notes
·
View notes
Text
シートベルトを外して、しかし滑らかに次の動作へ続けることが出来なかった。
ガレージに停めた愛車の運転席。すでにエンジンは完全に静まり、シャッターも降り切って、あたりには静けさがあった。
帰着の物音は家内にも届いているはずで。
であればグズグズとためらってはいられない。初手から、弱みを見せるわけにはいかない。
フウッと、深い息をひとつ吐いて、逡巡をふり払う。
助手席に置いた鞄を引き寄せながら、ルームミラーを見やる。一瞬だけ視線を止めて、映った貌をチェックする。それは習慣通りの行為、それだけのこと。
ドアを開け、怜子は車から降り立った。
今日の装いは、銀鼠色のスーツに黒の開襟シャツ。いわば定番の仕事着姿だったが、シックな色合いが豊かな身体つきを際立たせるのもまた、いつものごとく。黒いストッキングのバックシームが艶やかだった。
ヒールを鳴らして歩き出せば、もうその足取りに迷いはなかった。
エントランスの柔らかな灯り、見慣れた光景が、この家の主を迎える。いつものとおりに。
そう、なにも臆することなどない。我が家へと、自分の城へと、帰ってきたのだ。
リビングから微かにテレビの音が聞こえる。
いつも通り、直接キッチンへと入った。
「ああ、おかえりなさい」
ソファに座った志藤が、明るい声をかけてくる。テレビを消し、こちらへと向き直って、
「帰ってきてくれたんですね」
嬉しそうに言った。礼儀のつもりなのか、立ち上がって。
「……ええ」
これも習慣のとおり、鞄を食卓の椅子へと置きながら、素っ気なく怜子は返した。“なにを、そんなに喜ぶことがあるのか”という冷淡さを、志藤を一瞥した視線にこめて
志藤は、そんな義母の態度も気にする様子はなく、ゆっくりと歩み寄りながら、
「お食事は? ビーフシチューがありますけど」
などと、心遣いをしてくる。
確かにコンロには鍋があり、あたりにはその匂いも漂っていた。今夜は帰らぬという英理が作りおいていったものに違いない。その献立も、温めるだけという簡単さと、食べ残しても問題がないものをという配慮からの選択だろう。例によって行き届いたことだとは思いながら、娘のそんな主婦としての熟練ぶりに、素直に感心することが出来なかった。いまは。
「僕は、もう済ませてしまったんですけど。すみません、もしかしたら、お帰りにならないかと思ったんで」
「……構わないわ。私も済ませてきたから」
別に謝られる筋合いのことではない、と疎ましさをわかせながら、志藤に返した言葉は、嘘ではないが正確でもない。急に入った商談のために、昼食をとったのが夕方近くになってからだった。いま空腹を感じていないのは事実だった。とにかく、英理の用意していった絶品の(と呼ぶべき味わいであることは知っている)シチューを食べる気にはならなかった。
ならば、すぐに自室へと引き上げてもよかったのだが。
キッチンに佇んだ怜子は、リビングとの境のあたりに立った志藤を見やった。
改めて、その背の高さを認識する。170cmを実は少し越える怜子に見上げる感覚を与えてくる相手は、普段の生活の中でそう多くはいない。その長身ぶりに見合った、軟派な雰囲気からはやや意外な、がっしりとした肉づき。
いまの志藤は、仕事帰りの装いから上着とネクタイを取り去った姿だった。いつものように湯上りの姿で迎えられるかと身構えていて、そうでなかったことには密かな安堵を感じた怜子だったが。二つ三つボタンを外したワイシャツの襟元から覗く硬そうな胸板へと吸い寄せられた視線を、すぐに逸らした。
上着とネクタイは、ソファの上に雑に脱ぎ捨てられてあった。常にはないことだ。夕食をひとり先に済ませていたことや、入浴もせず着替えもしないまま寛いでいたらしき姿から、本当に怜子が今夜は帰宅しないと考えていたようにも思えて。
微かな憤慨を覚える。それは、自分がこの突発的な状況から逃げるものと決めつけていたのか、という憤り――であるはずだったが。
そんな怜子の思考の流れは、時間にすればごく僅かな間のことだった。そうですか、と頷いた志藤は、
「じゃあ、お酒に付き合ってもらえませんか?」
そう言った。なんの屈託もない調子で。
「たまには、いいじゃないですか。ね?」
「…………」
「じゃ、乾杯」
杯を掲げてみせる志藤を無視して、グラスを口に運んだ。
志藤も、特に拘ることなく、ひと口飲んで、
「ああ、美味い。上等な酒は、やっぱり違うな」
そう感心してみせる。大袈裟にならぬ程度の言い方で。そのへんの呼吸が、この若者は巧みだった。
ソファで差し向かいのかたちになっている。テーブルに置かれた氷や水は、すべて志藤が用意した。チーズとナッツを小皿に盛った簡単なつまみまで。その並びの中のボトルに目をやって、
「社長は、スコッチがお好きなんですね」
と、志藤は言った。
「あの、初めて付き合ってくれた夜も、同じものを飲まれてましたよね? 確か、銘柄も同じものを」
「……そうだったかしら」
冷淡に、ではなく、不快さを隠さずに怜子は答えた。よくも、しゃあしゃあと“あの夜”のことを口にするものだ、という怒りがわいて、
「……違うわよ」
と、つい洩らしてしまう。
え? と聞き返す志藤の間抜けな顔に、さらに感情を逆撫でされて、
「スコッチでも、銘柄は違うと云ってるの」
結局、そう指摘することになる。最初の返答の、“もう、そんなことは覚えていない”というポーズを、自ら無意味なものにして。
「ああ、そうでしたか。こりゃ、恥ずかしいな。知識もないのに、わかったふりなんてするもんじゃないですね」
「…………」
頭なぞ掻いてみせて、実のところ恥じ入るふうでもない志藤の反応を目にすれば、揚げ足をとってやったという快味など生じるはずもなく。逆にまんまと乗せられたという苦さだけがわいて。
「昔の話は、おやめなさい」
「ああ、すみません」
居丈高に命じて、志藤に頭を下げさせても、その苦味は消え去ることなく。
それを流し去り、気を鎮めるために、怜子はまたグラスに口をつける。
飲み慣れた酒の味わいが、今夜は薄かったが。それでいいのだ。
上質のモルトを水と氷で薄めているのは、無論のこと警戒心からだった。怜子は、いまだスーツの上着も脱がず、まっすぐ背を伸ばして座った姿勢も崩そうとはしない。
そうしてまで、この場にあらねばならない理由がある。怜子は、そう思っている。この機会に、志藤に、この娘婿に、言っておかねばならないこと、質しておかねばならないことがある、と。ことに、今夜のこの突然な状況について。
それを、どう切り出したものか、と思案したとき、
「……社長」
と、志藤が呟いた。呼んだのではなく、ひとりごちるようにそう言ってから、
「いえ、つい以前からのクセで、社長と呼んでしまうんですが。本当は、“お義母さん”と、お呼びすべきですよね? ただそれも、どうも慣れない感じで。どちらがいいですか?」
「……どちらでも、いいわよ」
嘆息まじりに返したぞんざいな答えには、しかし呆れよりも苛立ちがこもった。そんなどうでもいいことで、また思考を妨げられた、と。
率直に云うなら、“社長”も“お義母さん”も、どちらの呼び方も不快だったが。
「……慣れないというなら、無理に変える必要もないでしょう」
数拍の間をおいて、そう付け加える。不機嫌に。そちらのほうが、まだマシだ、と。
苛立ちが記憶を呼び起こす。いつも、この調子だったと思い出させる。
このふざけた若い男は、いつもこんなふうにのらりくらりとした言動で、怜子のペースを乱してきた。それは怜子の周囲の人間の中で、志藤だけが容易くやってのけることで。相性が悪い、とはこういうことかと怜子に感じさせたものだったが。いまはそんな苦い記憶を噛みしめている場合でもないと、
「なにを企んでいるの?」
直截に、そう問い質した。鋭く志藤を睨みつけて。
「企む、ですか? そりゃあ、また穏やかじゃないですね」
空っとぼける志藤の反応は予測どおりだったから、
「慎一を連れだして。英理は、どういうつもりなのかと訊いているのよ」
「それは、姉弟の親睦を深めようってことじゃないですか? ずっと、じっくり話す機会もなかったみたいですし」
「…………」
じっと疑念と探りの目を向ける怜子を見返して、志藤は“ああ”と理解したふうに頷いて、
「英理が、我々のことを慎一くんに話すつもりなんじゃないかって、社長はそれを案じてらっしゃるわけですね? なるほど」
「……なにか聞いているんじゃないの?」
「いえ、それについてはなにも。確かに英理は、いずれ慎一くんにも“真実”は伝えるべきだとは考えているみたいですけど」
「必要ないわ、そんなこと」
「ええ。僕もそう思うんですけどね」
微かに苦笑を浮かべて。“自分に言われても”と言いたげに。
「とにかく僕が英理から聞いてるのは、久しぶりに姉弟ふたりだけの時間を持ちたいって意向と、それによって、僕と社長にも、ゆっくりとふたりで話す機会が作れるだろうって見込みです。それだけですよ。で、見込みのほうは、僕としては、どうかな? って半信半疑だったんですけど。結果として、こうして社長とお酒を酌みかわせてるわけですから、英理の考えが正しかったってことですね」
そう云って、今度は邪まな笑みのかたちに口許を歪め、怜子へと向ける視線をねっとりと粘ついたものに変える。どちらも意識的にそうしたに違いなかった。
「それで。こういう状況になれば、僕も思惑が生じてくるわけですよ。企む、っていうなら、いまこの場になって、いろいろと考えを巡らせてるところです。このあと、どうやって怜子社長と“昔”のような親密さを取り戻そうかって」
カランと氷が鳴った。怜子が手にしたグラスの中で。
またひと口あおった、そのグラスをテーブルに置いて、
「……笑えないわね」
と、怜子は云った。
「そうですか? じゃあ、何故帰ってきたんです? 待っているのは僕だけだと知りながら」
「だから、それは、」
「英理の真意を突きとめるため、ですか。けど、それだったら直接英理に電話して訊くべきでしょう。英理の暴走を危ぶみ、止めたいと思うなら、なおさらそうすべきですね。でも、それはしてないんでしょう?」
「……ここは私の家よ。帰ってくることに、なんの問題があるというの?」
低く抑えた声に、微かにだが苛立ちがこもっていた。
「もちろん問題なんてないですよ。最初から、それだけの話なら。ただ、ついさっきまでは、不本意ながら帰ってきたって言い方だったでしょう? こうして、酒の誘いには応じてくれながら、ピントのズレた理由を口にしたり。ひとつひとつがチグハグで矛盾していて、どうにも明晰な怜子社長らしくもない。だから、僕はこう考えるわけです。その矛盾を突き崩してあげることこそが、いま僕に期待されてることなんじゃないかと」
「……馬鹿ばかしい」
嘆息とともに、怜子は吐き捨てた。
「なにを言うのかと思えば。自惚れが強くて、都合のいい解釈ばかりなのは変わってないわね」
きつい口調できめつけながら、その目線は横へと逸らされていた。
「そうですかね? まあ、願望をこめた推測だってことは否定しませんが」
志藤は悪びれもせずに。
怜子は、顔の向きを戻して、
「あなた、いまのお互いの立場を本当に解っているの?」
そう難詰した表情は険しくこわばり、声にももはや抑えきれぬ感情が露わになっていた。憤りと、切羽詰った気色が。
「義母と娘婿、ってことですかね。まあ、世間一般の良識ではNGでしょうけど、僕たちの場合、ちょっと事情が特殊ですからね」
ぬけぬけとそう云って、そのあとに志藤は、「ああ、そうか」と声を上げた。
「そこが、最後の引っかかりですか。英理が僕の妻だってこと、いや、僕の妻が英理だってことが。なるほど」
なにやら言葉遊びのような科白を口にして、しきりに頷くと、グラスを手に立ち上がった。テーブルを回って、怜子の隣りに腰を下ろすと、わざわざ持ち運んだグラスはそのままテーブルに戻して。やにわに腕をまわして、怜子の身体を抱きすくめた。
「やめてっ」
怜子の抵抗は遅れた。唐突な志藤の行動に虚を突かれて。しかし抗い始めると、その身もがきは激しく本気なものとなって。大柄な男の腕の中で、豊かな肢体が暴れた。それでも強引に寄せようとした志藤の顔を、掌打のような烈しさで押し返すと、両腕を突っ張り精一杯に身体を離して。眉を吊り上げた憤怒の形相で叫んだ。
「英理を選んでおいてっ」
叫んで。自ら発したその言葉に凍りつく。厚い封印を一気に突き破って臓腑の底から噴き上がった、その感情に。
打たれた顎の痛みに顔をしかめながら、愕然と凝固する怜子の貌を覗きこんだ志藤は、納得したように肯いて。そして耳元に囁いた。せいぜい優しげな声音で。
「あれは、社長より英理を選んだってことじゃあなかったですよ」
「…………」
無責任な、身勝手な、傲慢な。人として、母親として、さらなる憤激を掻きたてられるべき台詞。
なのに、怒りも反発も、どうしようもなく溶け崩れていく。ぐったりと、総身から力が抜け落ちていく。
そして、そうなってしまえば。身体にまわされたままの固い腕の感触が、そこから伝わる体温が。鼻に嗅ぐ男の体臭が。酩酊にも似た感覚の中へと、怜子の心身を引きずりこんでいく。
ああ、駄目だ……と、胸中に落とした嘆きには、すでに諦めがあった。わかっていた、と。こうなってしまえば、もう終わりだということは。
志藤が再び顔を寄せてくる。
怜子は、ゆっくりと瞼を閉じた。
接触の瞬間、反射的に引き結ばれた唇は、しかしチロリと舐めずった舌先の刺激に、震えながら緩んだ。
すかさず舌が侵入する。歯列を舐め、口蓋の粘膜をひと刷きしてビクリとした反応を引き出すと、その奥で竦んだ女の舌を絡めとった。
抗うことなく怜子は口舌への蹂躙を受け容れた。馴染みのある、だが久しいその刺激に、意識より先に感覚が応えて。結び合った口唇には押し返す力がこもり、嬲られる舌がおずおずと蠢きはじめる。流しこまれた男の唾液を従順に嚥み下せば、喉奥から鳩尾へとカッと熱感が伝わって胴震いを呼んだ。一気に酩酊の感覚が強まる。
無論、端然と座していた姿勢はしどけなく崩れている。スリッパを落とした片脚はソファの上へと乗り上がり、斜めに流したもう一方の脚との間に引き裂けそうに張りつめたスカートは、太腿の半ばまでたくし上がっていた。両手は志藤のシャツの腹のあたりをギュッと縋りつくように握りしめている。
その乱れた態勢の肢体を志藤の手が這いまわる。よじった脇から腰を、背中を、腕を、スーツの上から撫でさする掌のタッチはまだ軽いものだったが。触れていく箇所に粟立つような感覚を生じさせては、怜子の脳髄を痺れさせるのだった。泣きたくなるような懐かしさを伴って。
ようやく口が離れたときには、怜子の白皙の美貌は逆上せた色に染まって、うっすらと開けた双眸はドロリと蕩けていた。ハッハッと荒い息を、形のよい鼻孔と、涎に濡れて官能的な耀きを増した紅唇から吹きこぼして。
その兆しきった義母の貌を、愉快げに口許を歪め、しかし冷徹さを残した眼で眺めた志藤は、
「感激ですよ。またこうして、怜子社長の甘いキスを味わえて」
甘ったるい囁きを、血の色を昇らせた耳朶に吹きこんだ。
ゾクッと首筋を竦ませた怜子は、小さく頭を横にふって、それ以上の戯言を封じるといったように、今度は自分から唇を寄せていった。
さらに濃密なディープ・キスがかわされる。荒い鼻息と淫猥な唾音を響かせながら、怜子は娘婿たる若い男の舌と唾液を貪った。その片手はいつしか志藤の腰から背中へとまわり、もう片手は首を抱くようにして後ろ髪を掴みしめていた。より密着した互いの身体の間では豊かな胸乳が圧し潰されて、固い男の胸板を感じとっていた。
背徳の行為に耽溺しながら淫らな熱を高めていく豊満な肢体を愛撫する志藤の手にも、次第に力がこもっていく。指を埋めるような強さで、くびれた腰を揉みこむ。さらによじれた態勢に、豊熟の円みと量感を見せつける臀丘を、やはり手荒く揉みほぐす。かと思えば、たくし上がったスカートから伸びる充実しきった太腿の表面を、爪の先で軽く引っ掻くような繊細な攻めを繰り出す。どの動きにも、この熟れた肉体がどんな嬲りに反応するかは知り尽くしているというような傲岸な自信が滲んでいて。実際、その手の動きの逐一に鋭敏な感応を示しながら、怜子の豊艶な肢体は発情の熱気を溜めこんでいくのだった。
上着の中に入りこんだ志藤の手が、喘ぎをつく胸乳を掴みしめ、ギュッとブラジャーのカップごと揉み潰せば、怜子は堪らず繋いでいた口を解いて、ヒュッと喉を鳴かせて仰け反った。
グッタリとソファにもたれ、涎に汚れた口から荒い呼吸を吐く。常には決して見られぬしどけない姿を愉しげに見下ろした志藤は、
「シャワーを浴びますか? それとも、このまま部屋に?」
優しい声で、そう訊いた。
「…………」
怜子は無言で首を横に振った。
ソファに落としていた腕をもたげて、志藤のシャツを掴んだ。脱力しているかに見えたその手にグッと力がこもって、志藤を引っ張るようにして、
「……このまま……ここで……」
乱れた息遣いの下から、怜子はそう云った。
「それはまた、」
思わずこみ上げた笑いをこらえて、志藤の表情が奇妙なものとなる。そこまで切羽詰っているのか、と。だが怜子の言葉には続きがあった。
「一度だけよ。それで、なにもなかったことにするの」
志藤を睨みつけて、有無をいわせぬといった口調で宣言した。淫情に火照った貌では、その眼光の威力は大幅に減じていたと言わざるをえなかったが。必死の気概だけは伝わった。
「……なるほど」
僅かな間を置いて返した志藤の声には、呆れとも感心ともつかぬ心情がこもった。
つまり、行きずりとか出会いがしらの事故のように“こと”を済ませるということだ。だから、シャワーを浴びて準備などしないし、ベッドへと場所を移したりもしない。
それが、せめてもの英理への申し訳なのか、己が“良識”との妥協点がそこになるということなのか。
いずれにしろ、よくもまあ思いつくものだ、と胸中にひとりごちる。まさか、事前に考えていたわけでもあるまいに。さすがは切れ者の須崎怜子社長、と感嘆すべきところなのか?
しかし、その怜子社長をして、このまま何事もなく終わるという選択肢は、すでにないということだ。そこまで彼女を追い詰めたのは、今しがたのほんの戯れ合いみたいな行為ではなくて、一年の空白と、この二ヶ月の煩悶。
つまりは、すべてこちらの目論見どおりの成り行きということだが。
それでも、
(やっぱり、面倒くささは英理より上だな)
改めて、そう思った。その立場や背景を考慮すれば仕方のないところだし、それだけ愉しめるということでもある。
「わかりました」
だから、志藤は真面目ぶった顔で頷いてみせる。ひとまずは、怜子の“面倒くささ”に付き合って、そこからの成り行きを楽しむために。
まずは……“一度だけ”という自らの宣言を、その意志を、怜子がどこまで貫けるか試させてもらう、といったところか。
志藤はソファから立って、スラックスを脱ぎ下ろした。
引き締まった腰まわりを包んだビキニ・ブリーフは、狭小な布地が破れそうなほどに突き上がっている。なんのかんの云っても、久しぶりに麗しき女社長の身体を腕に抱き、芳しい匂いを鼻に嗅いで、欲望は滾っていた。
その巨大な膨張を一瞥して、すぐに怜子は顔を横に背けた。肩が大きくひとつ喘ぎを打って、熱い息を密やかに逃した。
“このまま、ここで”と要求しながら、ソファに深くもたれた姿勢を変えようとはしなかった。スーツの上着さえ脱ごうとはしない。
なるほど、と納得した志藤は、テーブルを押しやって空けたスペースに位置をとると、怜子の膝頭に手を掛けた。しっとりと汗に湿ったストッキングの上を太腿へと撫で上げると、充実しきった肉づきには感応の慄えが走って、怜子の鼻からはまた艶めいた息が零れた。ゆっくりと遡上した志藤の手は、スカートをさらにたくし上げながら、ストッキングのウエスト部分を掴んで引き剥がしにかかる。怜子は変わらず顔を背けたまま、微かに臀を浮かせる動きで志藤の作業に協力した。
白い生脚が露わになる。官能美に満ちたラインを見せつけて。
むっちりと張りつめた両腿のあわいには、黒い下着が覗いた。タイト・スカートはもう完全にまくれ上がって、豊かな腰の肉置に食いこんでいるのだった。ショーツは瀟洒なレースのタンガ・タイプ。
「相変わらず、黒がよく似合ってますね」
率直な感想を口にして、“ちょっとおとなしめで、“勝負下着”とまではいかない感じだけど”とは内心で付け加える。まあ、急な成り行きだから当然かと、ひとり納得しながら、手を伸ばした。
やはりインポートの高級品であるに違いないそのショーツの黒いレース地をふっくらと盛り上げた肉丘に指先を触れさせれば、怜子はビクリと首をすくませたが、即座に頭を振って、志藤の手を股間から払いのけた。懇ろな“愛撫”なぞ必要ない、親密な“交歓”の行為などする気はないという意思の表明だった。
「……わかりましたよ」
怜子の頑なさに呆れつつ、志藤は戯れかかる蠢きを止めた指をショーツのウエストに引っ掛けて、無造作に引き下ろした。あっ、と驚きの声を上げる怜子にはお構いなしに、荒っぽい動作で足先から抜き取ったショーツを放り捨てる。
これで怜子は、下半身だけ裸の状態になった。
横へと背けた頸に、新たな羞恥の血を昇らせながら、反応を堪えようとする様子の怜子だったが、
「ふふ、怜子社長のこの色っぽい毛並みを見るのも久しぶりですね」
明け透けな志藤の科白に耐えかねたように、片手で股間を覆った。隠される前に、黒々と濃密な叢の形が整っていることまで志藤は観察していた。処理は怠っていないらしいと。
まあ、これも淑女としての身だしなみってことにしておくか、と内心にひとりごちながら、志藤はビキニ・ブリーフを脱ぎ下ろす。解放された長大なペニスが隆々たる屹立ぶりを現す。
その気配は感じ取ったはずだが、怜子は今度はチラリとも見やろうとはしなかった。ことさらに首を横へとねじって。隆い胸を波打たせる息遣いが、深く大きくなる。
怒張を握り、軽くしごきをくれて漲りを完全なものにすると、志藤は怜子へと近づく。ワイシャツはあえて残した。半裸の姿の怜子に釣り合わせ、その意思に応じるといった意味合いで。
上半身には全ての着衣を残しながら、腰から下だけを剥き出しにした女社長の姿は、どこか倒錯的な淫猥さがあって、これはこれで悪くないという感興をそそった。スカートすら(もはや全く役目は果していないが)脱がず、ストッキングとショーツという、交接に邪魔な最小限のものだけを取り去った姿で、いまでは義理の母親たる女は待っているのだ。すり寄せた裸の膝と、股間に置いた手に、最後の、いまさらな羞恥の感情を示して。
志藤は両腕を伸ばして、腰帯状態になっているスカートを掴むと、重みのある熟女の身体をグイと引き寄せた。巨きな臀を座面の端まで迫り出させて、
「横になりたくないって云うなら、こうしないとね」
窮屈で、よりはしたない態勢へと変えさせた怜子に、そう釈明する。こちらは、あなたの意思に応えているんですよ、といった含みで。怜子は顔を背けたまま、なにも言わなかった。
次いで、志藤は怜子の両膝に手をかけると、ゆっくりと左右に割っていった。抵抗の力みは一瞬だけで、肉感的な両の腿は従順に広げられて、あられもない開脚の姿勢が完成する。
「手が邪魔ですね」
「…………」
簡潔な指摘に、数秒の間合いを置いて、股間を隠していた手が離れる。怜子は引いた手を上へと上げて、眼元を隠した。じっとりと汗を浮かべた喉首が、固い唾を嚥下する蠢動を見せた。
「ちょっと、キツイかもしれませんよ」
中腰の体勢となって、片手に怜子の腰を���さえ、片手に握りしめた剛直を��めながら、志藤が警告する。それは気遣いではなく、己が肉体の魁偉さを誇る習性と、それを散々思い知っているはずなのに入念な“下準備”を拒んだ怜子の頑迷さを嘲る意図からの言葉だった。“だったら、改めて思い知ればいい”という、残虐な愉楽をこめた脅しだった。
視界を覆っていた手の陰で、怜子の瞳が揺動する。まんまと怯えの感情を誘発されて、指の間から見やってしまう。
だが、その怖れの対象をはっきりと視認するだけの暇も与えられなかった。
熱く硬いものが触れた、と感じた次の刹那には、その灼鉄の感覚は彼女の中に入りこんで来た。無造作に、暴虐的に。
「ぎっ――」
噛みしめた歯の間から苦鳴を洩らして、総身を硬直させる怜子。秘肉はじっとりと潤みを湛えていたが。規格外の巨根を長いブランクのあとに受け入れるには、湿潤は充分ではなかった。
構わず志藤は腰を進めた。軋む肉の苦痛に悶える怜子を、“それ見たことか”という思い入れで眺め下ろしながら、冷酷に抉りこんでいった。
やがて長大な肉根が完全に埋まりこめば、怜子は最奥を圧し上げられる感覚に深く重い呻きを絞って、ぶわっと汗を噴き出させた喉首をさらして仰け反りかえった。裸の双脚は、巨大な量感に穿たれる肉体の苦痛を和らげようとする本能的な動きで限界まで開かれて、恥知らずな態勢を作る。
「ああ、相変わらず、いい味わいですよ」
志藤が満悦の言葉を吐く。未だ充分に解れていない女肉の反応は生硬でよそよそしさを感じさせたが、たっぷりと肉の詰まった濃密な感触は、かつて馴染んだままで。長い無沙汰を挟んで、またこの爛熟の肉体を我が物としたのだという愉悦を新たにさせた。
「でも、こんなものじゃないですよね? 怜子社長の、この熟れたカラダのポテンシャルは」
という科白に、すぐにその“本領”を引きずり出してやるという尊大な自信をこめて動き出そうとすると、
「ま、待ってっ、」
反らしていた顎を懸命に引いて、難儀そうに開いた眼を志藤へと向けた怜子が焦った叫びを上げた。この肉体の衝撃が鎮まるまでは、といましばしの猶予を乞うたのだったが、
「待てませんね」
にべもなく答えて、志藤は律動を開始した。ぎいっ、とまた歯を食いしばり、朱に染まった顔を歪めて苦悶する怜子に、
「こういうやり方が、お望みだったんでしょう?」
と皮肉な言葉を投げて、長く大きなスラストで責め立てていく。接触は、繋がり合った性器と、太腿に掛けた手だけという、即物的な“交接”の態勢を維持したまま。
頑なに、懇ろな“情交”を拒んだことへの懲罰のような暴虐的な行為に、怜子はただその半裸の肢体をよじり震わせ、呻吟するばかり……だったのだが。
単調な抽送のリズムを変じた志藤が、ドスドスと小刻みに奥底を叩く動きを繰り出すと、おおおッと噴き零した太いおめきには苦痛ではない情感がこもって。
どっと、女蜜が溢れ出す。まさに堰を切ったようなという勢いで湧出した愛液は、攻め立てられる媚肉に粘った音を立てはじめる。
あぁ……と、怜子が驚いたような声を洩らしたのは、その急激な変化を自覚したからだろう。
「ようやくカラダが愉しみ方を思い出してきたみたいですね」
「ああああっ」
そう云って、それを確認するように志藤が腰を揺すれば、怜子の口からは甲走った叫びが迸り出る。ぐっと苦痛の色が減じた、嬌声に近い叫びが。満たし尽くされたまま揺らされる肉壷が、引き攣れるように収縮した。
(……ったく。結局こうなることは、わきりきってるってのに)
内心に毒づいて、じっくりと追い込みにかかる志藤。ようよう、絡みつくような粘っこさにその“本領”を発揮しはじめた熟れ肉の味わいを愉しみながら。あえて性急さは残した動きの中に、知悉しているこの女体の勘所を攻め立てる技巧を加えていく。
怜子は尚も抗いの素振りを見せた。唇を噛みしめて、吹きこぼれようとする声を堪える。窮屈な態勢の中でのたうつ尻腰の動きも、志藤の律動を迎えるのではなく、逆に少しでも攻めを逸らし、肉体に受け止める感覚を減じようとする意思を示した。
「ふふ、懐かしいな」
と、志藤が呟いたのは、そのむなしい抵抗ぶりに、ふたりの関係が始まった頃の姿を想起したからだった。長い空白が生んだ逆行なのか。或いは、やはり義理とはいえ親子の間柄になったことが、この期におよんでブレーキをかけるのか。それとも……長く捨て置かれた女の最後の意地なのか。
いずれにしろ、甲斐のない抗いだった。こうして深く肉体を繋げた状態で。
両手に掴んだ足首を高々と掲げ、破廉恥な大開脚の態勢を強いてから、ひと際深く抉りこんでやれば、引き結ばれていた怜子の口は容易く解けて、オオゥと生臭いほどのおめきを張り上げた。そのまま連続して見舞った荒腰が、もたがった厚い臀肉を叩いて、ベシッベシッと重たく湿った肉弾の音を立て、それにグチャグチャと卑猥な攪拌音が入り混じる。ますます夥しくなる女蜜の湧出と、貪婪になっていく媚肉の蠢きを明かす響きだった。
「ああっ、ひ、あ、アアッ」
もはや抑えようもなく滾った叫びを吐きながら、怜子が薄く開けた眼で志藤を見やった。その眼色にこもった悔しさこそが、心底の感情だったようだが。その恨みをこめた一瞥が、怜子が示しえた最後の抵抗だった。
「アアッ、だ、ダメぇっ」
乱れた髪を打ち振って、切羽詰った叫びを迸らせ、腰と腿の肉置をブル…と震わした。と、次の刹那には弓なりに仰け反りかえった。
「……っと。はは、こりゃあすごい」
動きを止めて、激烈な女肉の収縮を味わいながら志藤が哂う。脳天をソファの背もたれに突き立て、ギリギリと噛みしめた歯を剥き出しにして、硬直する怜子のさまを見下ろして。
「もったいないなあ」
と、呟いた。怜子に聞こえていないことは承知だから独り言だ。
筋肉を浮き上がらせてブルブルと震える逞しいほどの太腿を両脇に抱え直して、志藤は律動を再開した。
「……ぁああ、ま、待って、まだ、」
忘我の境から引き戻された怜子が重たげな瞼を上げて、弱い声で懇願する。まだ絶頂後の余韻どころか震えさえ鎮まっていない状態で。
「駄目ですよ」
しかし今度も志藤は無慈悲な答えを返して、容赦なく腰の動きを強めていく。
「久しぶりに肌を重ねての、記念すべき最初の絶頂を、あんなに呆気なく遂げてしまうなんて、許せませんよ。ここはすぐにも、怜子社長らしいド派手なイキっぷりを見せてもらわないと」
「あぁ……」
怜子の洩らした泣くような声には、敗北と諦めの哀感がこもった――。
どっかとソファに腰を落とすと、志藤はテーブルのグラスを取って、ひと口呷った。
氷は半ば以上溶けて、上等なスコッチの味は薄まっていたが。“ひと仕事”終えて渇いた喉には丁度よかった。
ふうと息を吐いて、額に滲んだ汗の粒を拭った。深く背を沈めて、改めて眼前の光景を眺める。
志藤はもとの席に座っている。だから、その前方には、たった今まで烈しい“交接”の舞台となっていたソファがあって。そこに怜子が横たわっている。
グラスの中の氷は完全には溶けきっていない。経過した時間はその程度だったということだが。その間に怜子は三度、雌叫びを上げて豊かな肢体を震わした。性急な激しい交わりだった。
いまの怜子は横臥の姿勢で倒れ伏している。三度目の絶頂のあと、志藤が身を離したときに、ズルズルと崩れ落ちた態勢のまま。しどけなく四肢を投げ出して。
半裸の姿も変わっていなかった。最後まで志藤は怜子の腰から上には手を触れなかった。抱えた裸の肢を操り、微妙に深さや角度を変えた抽送で怜子を攻め立て続けた。最後は、その豊かな肢体を折りたたむような屈曲位で最奥を乱打して、怜子に断末魔の呻きを振り絞らせ、彼岸へと追いやったのだった。その刹那の、食い千切るような媚肉の締めつけには一瞬だけ遂情の欲求に駆られたが。ここは予定の通りに、とそれを堪えて。激烈な絶頂の果て、ぐったりと脱力した怜子から剛直を抜き去った。
だから今、僅かに勢いを減じて股間に揺れる肉根をねっとりと汚しているのは、怜子が吐きかけた蜜液だけということになるのだが。そんな汚れた肉塊を丸出しにして、いまだ上半身にはシャツを残した間抜けな格好で、悠然と志藤は酒を注ぎ足したグラスを口へと運んだ。美酒の肴は、無論、たったいま自分が仕留めた女の放埓な姿だ。
乱れたブルネットの髪に貌が隠れているのは残念だったが。横向きに伏した姿勢は、膝から下をソファから落とした剥き出しの下半身、ムッチリと張り詰めた太腿から肥えた臀への官能的なラインを強調して、目を愉しませる。なにしろ、先刻までの忙しない“交接”では、その肉感美を愛でることも出来なかったのだから。いまの状態も、豊艶な熟れ臀を眺めるのにベストなポージングとも視点ともいえなかったが。なに、焦る必要はない。この艶麗な義母の“ド派手なイキっぷり”を見たいという欲求が、まだ充分には叶えられていないことについても同じく。最後の絶頂の際に、怜子はついに“逝く”という言葉を口走りはしたが、それは振り絞った唸りのような声で。彼女が真に快楽の中で己を解放したときに放つ歓悦の叫び――咆哮はあんなももではない、ということを志藤は経験から知っているのだったが。それもまあ、このあとの楽しみとしておけばいい。まだ、ほんの“口開け”の儀が終わったばかり。夜は長いのだ。
と、そんな思索を巡らせていると、向かいで怜子の身体が動いた。
思いの他、早い“帰還”だった。完全に意識を飛ばしていたのではなかったらしい。深い呼吸に肩を上下させて、のろのろと上体を持ち上げる。垂れ落ちた髪に、顔は見えなかった。膝を床に落とし膝立ちになってから、ソファに手を突いて、よろりと立ち上がった。数瞬、方向に迷うように身体を回してから、出入口を目指して歩きはじめる。少し、ふらついた足取りで。途中、床に投げ捨てられてあったストッキングとショーツを拾い上げて。リビングを出る直前になって、ようやく腰までたくし上がったスカートに気づいて引き下ろす動作を見せながら、廊下へと姿を消した。最後まで志藤には顔を向けず言葉も掛けなかった。志藤もまた無言のまま見守り見送った。
ほどなく、遠く聞こえたドアの開閉音で、浴室に入ったことがわかった。
なるほど、と志藤は頷いた。浴室へと直行して、肌の汚れとともにすべてを洗い流すということか。そうして、この一幕をなかったこととする。確かに、それで首尾は一貫するわけだが。
もちろん、志藤としては、そんな成り行きを受け容れる気はなかった。受け容れるわけがないことは、怜子も理解しているはずで。だったら、やるべきことをやるだけだ、と。
それでも、グラスの酒を飲み干すだけの時間を置いてから、志藤は立ち上がった。半ばの漲りを保った屹立を揺らしながら、ゆっくりと歩きはじめる。浴室へと向かって。
熱いシャワーを浴びれば、総身にほっと蘇生の感覚が湧いて。
だが、そうなれば、冷静さを取り戻した思惟が心を苛む。
胸元に湯条を受けながら、宙を仰いだ怜子の貌には憂愁の気色が浮かんだ。
悔恨、罪悪感。しかし一番強いのは、慙愧の想い、己が醜態を恥じる感情だった。
――“英理を選んでおいてっ”。
志藤の腕の中で叫んでしまったその言葉を思い返すと、死にたいような恥辱に喉奥が熱くなる。自らの意志で関係を絶った男に向けるのは理不尽で身勝手な恨み。ずっと心の奥底に封じこんで気づくまいとしていたその感情を吐き出してしまった瞬間に、怜子は自身の意地も矜持も裏切ることになったのだった。
あとは、ただ崩れ流されただけだった。その済し崩しな成り行きの中で、怜子が示した姑息な抵抗、場所を移すことを拒み、裸になることを拒み、愛撫の手を拒んだことなど、無様に無様を重ねるだけの振る舞いだった。いまになって振り返れば、ではなく、即時にその無意味さ馬鹿馬鹿しさは自覚していたのだったが。
それでも尚、こうして浴室へと逃げこんで。肌を汚した淫らな汗を流すことで、辻褄を合わせようとしている。
そうしながら、しかし怜子の手は、己が身体を抱くようなかたちをとったまま動こうとしないのだった。最前までの恥知らずな行為の痕跡を洗い流すことで全てを消し去ろうとするのなら、真っ先に洗浄の手を伸ばすべき場所に向かってはいかないのだった。
そこに蟠った熱い感覚が、触れることを憚らせる。燠火を掻き立てる、という結果を招くことを恐れて……?
結果として怜子は、その豊満な裸身を熱く強いシャワーに打たせて、ただ佇んでいた。
……なにをしているのか、と、ぼんやりと自問する。無意味な帳尻合わせの振りすら放擲して。心に悔しさや恥ずかしさを噛みしめながら、身体ではついさっきまでの苛烈な行為の余韻を味わっているかのごとき、この有様は、と。
だが、長くそんな思いに煩う必要はなかった。
浴室のドアの向こうに足音と気配が近づいてきた。磨りガラスに人影が映る。
ちらりと横目に、その長身の影を認めて。もちろん怜子の顔に驚きの色は浮かばなかった。
断りも入れずガラス戸を開け放って。志藤はしばしその場で眼前に展けた光景に見惚れた。
黒とグレーのシックな色合いでまとめられた、モダンなデザインのバスルーム。開放的な広さの中に立つ、女の裸身。
まるで映画のワン・シーンのような、と感じさせたのは、その調った舞台環境と、なによりそこに佇立する裸体の見事さによるものだ。
フックに掛けたままのシャワーを浴びる怜子を、志藤は斜め後ろから眺めるかたちになっている。今夜はじめて晒された完全な裸身を。
四分の一混じった北欧の血の影響は、面立ちではなく体格に顕著に表れている、と過去にも何度か抱いた感想をいままた新たにする。優美なラインの下に、しっかりとした骨格を感じさせる肢体は、どこか彫刻的な印象を与えるのだった。高い位置で盛り上がった豊臀の量感、その中心の深い切れこみの悩ましさも記憶にあるままだったが。腰まわりは、英理が評していたとおりに、以前より少し引き締まっているだろうか。
怜子は振り向かなかった。志藤の来襲に気づいていないかのように、宙を見つめたまま。さっきまでは止まっていた手がゆるゆると動いて、肩から二の腕を洗う動きを演じた。いかにもかたちばかりに。
暖色の柔らかな照明の下、立ち昇る湯気の中、濡れていっそう艶やかに輝く豊艶な肢体を、志藤はなおもじっくりと眺めた。一年と二ヶ月ぶりに目の当たりにする、いまでは義理の母親となった年上の女の熟れた裸身に、ねっとりとした視線を注ぎ続けた。
すると堪えかねたように怜子の裸足の踵が浮いて膝が内へと折れた。重たげな臀が揺れる。執拗な視線を浴びせられる肌身の感覚までは遮断できなかったようだった。
その些細な反応に満足して、志藤は浴室の中へと足を踏み入れる。ピシャリと音を立ててドアを閉めれば、閉ざされた空間の中、立ち昇る熱気に混じった女の体臭を鼻に感じた。深々と、その甘く芳しい香りを吸いこむと、股間のものがぐっと漲りを強めた。
ゆっくりと回りこむように、豊かな裸体へと近づく。それでも怜子は振り返ろうとしなかったが。
自分もシャワーの飛沫の中へと入った志藤が、背後から抱きしめようと両腕を広げたとき、
「もう終わりといったはずよ」
冷淡な口調でそう云った。顔は向こうへと向けたまま。
「まさか」
軽く受け流して、志藤は腕をまわした。怜子は後ろから抱きすくめられた。
その瞬間、身体を強張らせ首を竦めた怜子が、
「……やめなさい」
と、掣肘の言葉を繰り返す。感情を堪えるような抑えた声で。
しかし、志藤はもう拒否の答えさえ返さずに、
「ああ、感激ですよ。こうしてまた、怜子社長の柔らかな身体を抱くことが出来て」
陶然とそう云って、ぎゅっと抱擁を強めた。裸の体が密着して、怜子の背は男の硬い胸を感じ、腰のあたりにも熱く硬いものが押しつけられる。
ね? と、志藤が耳元に囁きかける。
「一度だけって約束だと言っても、僕はまだ、その一度も終わってはいないんですから」
「……それは、貴方の勝手な…」
怜子の反駁、素気なく突き放すはずの科白は、どこか漫ろな口調になって、
「やっぱり、あんな落ち着かないシチュエーションではね。最後までという気にはなれなかったですよ。一年あまりも溜めこんだ怜子社長への想いを吐き出すには、ね。でも、本当は怜子社長も同じ気持ちなんじゃないんですか?」
甘ったるい口説と問いかけに、違うと怜子は頭を振って。そっと胸乳に滑ろうとした志藤の手を払いのけた。
と、志藤は、
「それは、葛藤されるのは当然だと思いますけど」
口調を変えてそう切り出した。
「いまだけは、余計なことは忘れてくれませんか? もう一度、貴女の本音を、本当の気持ちを聴きたいですよ」
「……やめて…」
と零した怜子の声は羞恥に震えた。もう一度と志藤が求めた“本音”“本当の気持ち”が、彼女のどの言葉を指したものかは自明であったから。
羞辱に震えて、そして抗いと拒絶の気配が消える。
やはりそれは、取り返しのつかない発言、発露だったと噛みしめながら。
怜子は、再び胸乳へと滑っていく男の手を、ただ見やっていた。
剥き身の乳房に今宵はじめて志藤の手が触れる。釣鐘型の巨大な膨らみを掌に掬い乗せ、その重みを確かめるようにタプタプと揺らしてから、広げた指を柔らかな肉房に食いこませていった。
ビクッと怜子の顎が上がる。唇を噛んで零れようとする声を堪えた。それに対して、
「ああ、これ、この感触。相変わらず、絶品の触り心地ですよ」
志藤の感嘆の声は遠慮がなく。その絶品の触り心地を味わい尽くそうというように、背後から双の乳房を掴みしめた両手の動きに熱がこもっていく。柔らかさと弾力が絶妙に混淆した熟乳の肉質を堪能しつつ、そこに宿る官能を呼び起こそうとする手指の蠢き。
ねちこく懇ろな愛撫、リヴィングでは拒んだその行為を、いまの怜子は抵抗もなく受け容れていた。抱きしめられたときに志藤の腕の中に折りこまれていた両腕は、いまは力無く下へと落ちて。邪魔がなくなって思うがままの玩弄を演じる男の手の中で、淫らにかたちを歪める己が乳房を、伏し目に薄く開いた眼で見つめながら。唇は固く引き結んだまま、ただ鼻から洩れる息の乱れだけに、柔肉に受け止める感覚を示していたのだったが。
「……痛いわ…」
ギュウッと揉み潰すような強い把握を加えられて、抗議の言葉を口にした。寄せた眉根に苦痛の色を浮かべて、視線は痛々しく変形する乳房へと向けたまま。
「ああ、すみません。つい、気が逸ってしまって」
そう謝って、直ちに手指の力を緩めた志藤だったが、
「まだ、早かったようですね」
と付け加えた科白には含みがあった。すなわち、もう少しこの熟れた肉体を蕩かし官能を高めたあとでなら、こんな嬲りにも歓ぶのだろう、という。
そんな裏の意味を、怜子がすぐに理解できたのは、過去の“関係”の中で幾度もその決めつけを聞いていたからだった。その都度、馬鹿げたことと打ち消していた。
いまも否定の言葉を口にしようとして、しかし出来なかった。わざとらしいほどにソフトなタッチへと切り替わった乳房への玩弄、やや大ぶりな乳輪をそうっと���先でなぞられて、その繊細な刺激に思わずゾクリと首をすくめて鼻から抜けるような息を洩らしてしまう。さらに硬く尖り立った乳首を、指の腹で優しく撫で上げられれば、ああッと甲走った声が抑えようもなく吹きこぼれた。
「なにせ、さっきはずっとお預けだったのでね。不調法は、おゆるしください」
なおも、くどくどと連ねられる志藤の弁解には、やはり皮肉な響きがあった。むしろ、“お預け”をくらって待ち焦がれていたのは、この熟れた乳房のほうだろう、と。玩弄の手に伝わる滾った熱、血を集めて硬くしこった乳首の有りさまを証左として。
怜子は悔しさを噛みしめながら、一方では安堵にも似た感情をわかせていた。志藤の言動が悪辣で下卑たものへと戻っていったことに。
赤裸々な己が心の“真実”などを追及されるよりは、ひたすら肉体の快楽に狂わされるほうがずっとましだ、と。そんな述懐を言い訳として、肉悦へと溺れこんでいく自らをゆるす。
「ああ、アアッ」
抑制の努力を捨てた口から、悦楽の声が絶え間なく迸りはじめる。熱く滾った乳房を嬲る男の手は、執拗さの中に悪魔じみた巧緻がこもって。久方ぶりに――どうやっても自分の手では再現できなかった――その攻めを味わう怜子が吹き零すヨガリの啼き声は、次第に咽ぶような尾を引きはじめて。
胸乳に吹き荒れる快楽に圧されるように仰け反った背は、志藤の胸に受け止められる。女性としては大柄な体の重みを、逞しい男の体躯は小揺るぎもせずに支えて。その安定の心地も怜子には覚えのあるものだった。
背後の志藤へと体重を預けて、なおも乳房への攻めに身悶えるその態勢を支えるために、床を踏みしめる両足の位置は大きく左右に広がっていた。ムッチリと肥えた両の太腿が、あられもない角度に開かれて。
そうであれば、ごく当たり前に、次なる玩弄はそちらへと向かっていく。
志藤の片方の手が、揉みしだいていた乳房を離れ、脇腹をなぞりながら、腿の付け根へと達する。
濡れて色を濃くした恥毛を指先が弄ったとき、ビクッと怜子の片手が上がって、志藤の手首のあたりを掴んだが。それはただ反射的な動きで、払いのけるような力はこもらなかった。
愉悦に閉ざしていた双眸をまた薄く開き、顎を引いて、怜子は下を、己が股間のほうを見やった。いつの間にか晒していた大股開きの痴態も気にするどころではなく、濡れた叢を玩ぶ志藤の指先を注視する。
うっ、と息が詰まったのは、無論のこと、指がついに女芯に触れたからだった。
「アアッ、だ、ダメッ」
甲高い叫びを弾けさせて、くなくなと首を打ち振る。引いていた顎を反らし、志藤の肩に脳天を擦りつけるようにして。はしたなく広げた両腿の肉づきを震わして。
もちろん、女芯を弄う指の動きは止まらない。怜子の叫びが、ただ峻烈すぎる感覚を訴えただけのものであったことは明らかだったし。
(……ああ、どうして……?)
目眩むような鮮烈な刺激に悶え啼きながら、怜子は痺れた意識の片隅に、その問いかけを過ぎらせていた。
やわやわと、志藤の指先は撫でつけを続けている。その触れようは、あくまで繊細で優しく、しかしそれ以上の技巧がこもっているようには思えないのに。
なのに、どうしてこんなにも違うのか? と。
乳房への愛撫と同じだった。どれほど試してみても、その感覚を甦らせることは出来なかった。
そう、そのときにも怜子はその言葉を口にしたのだった。“どうして?”と。いまとは逆の意味をこめて。
深夜の寝室で、ひとり寝のベッドの上で。もどかしさに啜り泣きながら。
「ふふ、怜子社長の、敏感な真珠」
志藤が愉しげに呟く。その言いようも怜子には聞き覚えがあった。宝石に喩えるとは、いかにもな美辞なようで、同時に怜子の秘めやかな特徴を揶揄する含みのこもった科白。実際いま、充血しきって完全に莢から剥き出た肉豆はぷっくりと大ぶりで、塗された愛液に淫猥に輝くさまは、肉の“真珠”という形容が的確なものと思わせる。そしてその淫らな肉の宝玉は、くっきりと勃起しきることで“敏感な”女体の泣きどころとしての特質も最高域に達して、いよいよ巧緻さを発揮する男の指の弄いに、つんざくような快感を炸裂させては総身へと伝播させていくのだった。
「ヒッ、あっ、あひッ、アアアッ」
絶え間なく小刻みな嬌声をほとびらせながら、怜子は突き出した腰を悶えうねらせ続けた。自制など不可能だったし、その意思も喪失している。股間を嬲る志藤の腕にかけた片手は、時おり鋭すぎる刺激にキュッと爪を立てるばかりで、決して攻め手の邪魔だてはしようとせずに。もう一方の手は、胸乳を攻め続ける志藤の腕に巻きつけるようにして肩口に指先をかけて。より深く体の重みを男へと浴びせた、全てを委ねきるといった態勢となって、その豊艶な肉体を悶えさせていた。否応なしに快感を与えられ、思うが侭に官能を操作されて、指一本すら自分の意思では動かせないようなその心地にも、懐かしさを感じながら。
「ヒッ、ああっ!? ダ、ダメッ、それ、あ、アアッ」
嬌声が一段跳ね上がったのは、ジンジンと疼き狂う肉真珠を、ピトピトと絶妙な強さでタップされたからだったが。切羽詰まった叫びは、数瞬後に“うっ!?”と呻きに変わる。急に矛先を転じた指が、媚孔へと潜りこんだからだった。
熱く蕩けた媚肉を無造作に割って、男の指が入りこんでくる。息を詰めて、怜子はその感覚を受け止めた。
「さすがに、ほぐれてますね」
志藤が云った。それはそうだろう、この浴室へと場所を移す前、リヴィングではセックスまで済ませている。熟れたヴァギナは、今夜すでに志藤の魁偉なペニスを受け入れているのだ。
だが今、怜子は鮮烈な感覚を噛みしめるのだった。男らしく長く無骨とはいえ、その肉根とは比ぶべきもない志藤の指の蹂躙に。
リヴィングでの交わりは、やはりどうにも性急でワンペースなものだった。怜子がそう望んだのだったが。結果として、久しぶりに迎え入れた志藤の肉体の逞しさ、記憶をも凌駕するその威力に圧倒されるうちに過ぎ去った、というのが実感だった。短い行為の間に怜子が立て続けに迎えた絶頂も、肉悦の高まりの末に、というより、溜めこんだ欲求が爆ぜただけというような成り行きだった。
いま、こうして。裸体を密着させ、乳房を嬲られ女芯を責められて、羞ずかしくも懐かしい情感を呼び覚まされたあとに改めての侵略を受ける女肉が、歓喜して男の指を迎え入れ、絡みつき、食い締めるのを、怜子は感じとった。そして、深々と潜りこんだ指、その形にやはり憶えがある指が、蠢きはじめる。淫熱を孕んだ媚肉を、さらに溶け崩れさせるために。そのやり方など知り尽くしている、といった傲慢な自信をこめた手管で。
「ああっ、ん、おおおっ」
また容易く官能を操られれば、怜子の悶えぶりも変わる。口から洩れる声音は、囀るような嬌声から低く太いおめきへと変じて。尻腰は、媚孔を抉り擦りたてる志藤の指のまわりに円を描いて振りたくられるのだった。その豊かな肉置を揺らして。
グッチュグッチュと粘った濡れ音を怜子は聴く。しとどな潤みにまみれた女肉が男の硬い指に掻きまわされて奏でる淫猥な響き。実際には、いまもまさにその下腹のあたりに浴び続けるシャワーの音に隠れて聞こえるはずはなかったのだが。耳ではなく身体を通してその淫らな音を怜子は聴いて。湧き上がる羞辱の感情は、しかしいっそう媚肉粘膜の快美と情感の昂ぶりを煽って、脳髄を甘く痺れさせるのだった。
「アアッ、ダメッ、そこ、そこはっ」
蹂躙の指先が容赦なく知悉する弱点を引っ掻けば、早々と切迫した叫びが吹き上がった。あられもなく開かれた両腿の肉づきにグッと力みがこもったのは、叫びとは裏腹に、迫り来るその感覚を迎えにいこうとするさまと見えたのだったが。
しかし、ピークは与えられなかった。寸前で嬲りを止めた指がズルリと後退していけば、怜子は思わず“あぁっ”と惜しげな声を零して。抜き去られた指を追って突き上げる腰の動きを堪えることが出来なかった。
両脇に掛かった志藤の手が、仰け反った態勢を直し、そのまま反転させる。力強い男の腕が、豊満な肢体を軽々と扱って。
正対のかたちに変わると、志藤は至近の距離から貌を覗きこんできた。蕩け具合を確認するような無遠慮な視線に、顔を背けた怜子だったが、優しくそれを戻され口を寄せられると、瞼を閉じて素直に受け入れた。
熱いキスが始まれば、怜子の両腕はすぐに志藤の背中へとまわって、ひしとしがみつくように抱きついていった。白く豊満な裸身と浅黒く引き締まった裸体が密着する。美熟女の巨大な乳房は若い男の硬い胸に圧し潰され、男の雄偉な屹立は美熟女の滑らかな腹に押しつけられる。その熱にあてられたように白い裸身の腰つきは落ち着かず、シャワーを受ける豊臀が時おりブルッブルッと肥えた肉づきを震わした。
と、志藤が怜子の片手をとって、互いの腹の間へと誘導した。もちろん即座にその意図を悟っても、怜子の腕に抗いの力はこもらず。
口づけが解かれる。密着していた身体が僅かに離れた。怜子の手に自由な動きを与え、そのさまを見下ろすための隙間を作るために。
涎に濡れた口許から熱い息を吐きながら、怜子はそれを見やった。長大な剛直を握った自分の手を。己が手の中で尊大に反り返った隆々たる屹立を。
逆手に根の付近を握った手に感じる、ずっしりとした重み、指がまわりきらぬほどの野太さ、強靭な硬さ、灼けるような熱さ。一度触れてしまえば、もうその手を離せなくなって。見てしまえば、視線を外せなくなった。
深い呼吸に胸を喘がせながら、怜子は凝然と見つめ続けた。
そんな怜子の表情を愉快げに眺めていた志藤が、つと肩に置いた手に軽い力をこめて、次の動きを示唆する。
怜子は、視線を下へと向けたまま、一度は首を横に振ったが、
「おねがいしますよ」
「…………」
猫撫で声のねだりとともに再度促されると、詰るような眼で志藤の顔を一瞥して。
ゆっくりと膝を折って、その身体を沈みこませていった。
濡れた床に膝をつけば、その鼻先に、雄渾な牡肉が鎌首をもたげるというかたちになって。怜子は我知らず“……あぁ”とあえかな声を洩らして胴震いを走らせた。
改めて端近に眺める、その魁偉なまでの逞しさ、凶悪なフォルムは、直ちに肉体の記憶と結びつく。今夜すでに一度その肉の凶器を迎え入れ、久方ぶりにその破壊力を味わわされていた怜子だったが。このときにより強く想起されたのは、もっと古い記憶だった。突然の英理の介入によって志藤との関係が途絶する直前の頃の。ずるずると秘密の逢瀬を続ける中で否応なくこのはるか年若な男の欲望に泥まされ、長く眠らせていた官能を掘り起こされて。毎度、酷烈なほどの肉悦に痴れ狂わされていた頃の。
結局……自分は、その記憶に呪縛されたまま。それを忘れ去ることが出来ず、逃れることも出来ずに。
その呪縛のゆえに、愚かな選択を重ね、醜態を繰り返して。無様さを上塗りしつづけて。
挙句、こうしてまた、この男の前に跪いている。いまや娘の夫となった男の前に。
救いがたいのは、そんな自責を胸に呟いて、しかしそこから脱け出そうという意志が、もう少しも湧いてこないことだった。自ら飛びこんだ、この陥穽の底にあって。無益で無様なばかりの抗いを捨て去ることに、開き直った落ち着きさえ感じて。
こんなにも――自分の堕落ぶりは深かったのだと、思い知ってしまえば。
「……これが…」
恨めしさを声に出して呟いて、眼前の巨大な肉塊を睨みつける。すべての元凶、などとはあまりに下卑た言いようだし、またぞろな言い訳になってしまうようだが。まったくのお門違いでもないだろう。その並外れた逞しさを見せつける男根が、須崎怜子を、有能な経営者たる才女を、破廉恥な堕落へと導いた若い牡の力の象徴であることは間違いなかったし。
ギュッと、握り締めた手指に力をこめる。指を跳ね返してくる強靭さが憎らしい。その剛さ、逞しさが。
その奇怪な感情に衝き動かされるように、顔を寄せていった。そのような心理の成り行きでは、まずは唇や舌で戯れかかる、という気にはならずに。切っ先の赤黒い肉瘤へと、あんぐりと大開きにした口を被せていく。
「おっと。いきなりですか」
頭上から志藤の声が降ってくる。がっつきぶりを笑うという響きを含ませて。
そんなのじゃない、と横に振られる首の動きは小さかった。口に余るようなモノを咥えこみながらでは、そうならざるを得ない。そして意識はすぐに口内を満たし尽くすその肉塊に占められていく。目に映し手指に確かめた、その尊大なまでの逞しさ凶悪な特長を、今度は口腔粘膜に味わって。
浴室に闖入してきてから、ほとんど怜子の身体ごしにしかシャワーを浴びていない志藤の股間には、微かにだが生臭いような匂いが残っていた。リヴィングでの慌しい交わりの痕跡。それを鼻に嗅いでも怜子に忌避の感情は湧かず、ただその身近な質の臭い、鼻を突く女くささを疎ましく感じて。別の臭気を嗅ぎ取ろうとするように鼻孔をひくつかせながら、首を前後に揺らしはじめる。
やはり一年数ヶ月ぶりの口戯。往時の志藤との関係においても、数えるほどしか経験しなかった行為だ。狎れを深める中で、執拗な懇請に流されるという成り行きで、幾度かかたちばかりにこなしたその行為を、いまの怜子は、
「ああ、すごいな」
と、志藤が率直な感嘆を呟いたほどの熱っぽさで演じていた。荒く鼻息を鳴らし、卑猥な唾音を響かせて。まさに、咥えこむなり、といった性急さで没入していって、そのまま熱を高めていく。抗いがたい昂ぶりに衝き動かされて淫らな戯れに耽溺しながら、その激しい行為が口舌にもたらす感覚にまたいっそう昂奮を高めるという循環をたちまちのうちに造り上げて。
いっぱいに拡げた唇に剛茎の図太さ強靭さをまざまざと実感すれば、甘い屈従の情感に背筋が痺れた。張り出した肉エラに口蓋を擦られると、やはり痺れるような快美な感覚が突き上がった。えずくくらいに呑みこみを深くしても、なお両手に捧げ持つほどの余裕を残す長大さを確かめれば、ジンと腹の底が熱くなって、膝立ちに浮かせた臀をうねらせた。唾液は紡ごうと意図するまでもなく止め処もなく溢れ出て、剛茎に卑猥な輝きをまとわせ、毛叢を濡らし、袋にまで垂れ流れた。唾の匂いと混じって色濃く立ち昇りはじめる牡の精臭を怜子は鼻を鳴らして深々と嗅いで、朱に染まった貌に陶酔の気色を深くした。
シャワーは志藤の手で向きをずらされ、ふたりの身体から外れて、空しく床を叩いている。その音を背景に、艶めいた息遣いと隠微な舐めしゃぶりの音がしばし浴室に響いて。
うむ、と快美のうめきを吐いた志藤が手を伸ばして、烈しい首ふりを続ける怜子を止めた。そして、ゆっくりと腰を引いて、剛直を抜き出していく。熱い口腔から抜き取られた巨根が、腹を打つような勢いでビンと反り返った。
野太いものを抜き去られたかたちのままぽっかりと開いた口で、新鮮な空気を貪るように荒い呼吸をつきながら、怜子は数瞬己が唾液にまみれた巨大な屹立を見つめて。それから、上目遣いに志藤の顔を見やった。
「このままだと、社長の口の中に出してしまいそうだったんで。素晴らしかったですよ」
「…………」
賞賛の言葉を口にして、そっと頬を撫でてくる志藤を、疑いの目で見上げて。また、鼻先に揺れる肉塔へと視線を戻す。
確かに……若い牡肉はさらに漲りを強めて、獰猛なまでの迫力を見せつけてくる。
(……ああ……なんて…)
畏怖にも似た情感に、ゴクと口内に溜まった唾を呑みくだして。そのさまを見れば、志藤が自分の口舌の行為にそれなりの快美を味わったというのも事実なのだろうが、と思考を巡らせて。
そこでやっと、その懇ろな愛撫の褒美のように頬を撫でられているという状態に気づいて、はっと顔を逃がした。それから、これも今さらながらに、夢中で耽っていた破廉恥な戯れを突然中断された、そのままの顔を見られ続けていたということに思い至って。俯きを深くして、乱暴に口許の涎をぬぐった。
やはり、そういうことなのだ、と悔しさを噛みしめる。これも、この男の悪辣な手管のひとつなのだ。我を忘れた奔騰のさなかに、急に自意識を呼び覚まさせる。意地の悪い、焦らし、はぐらかしだった。
と、理解して。しかしその悔しさが、反発や敵意に育ってはいかない。ズブと、また深く泥濘へと沈みこんでいくような感覚を湧かせて。
そも、その中断を、焦らされた、はぐらかされた、と感ずること自体が、志藤の手に乗っているということだった。ジリジリと情欲を炙られ続けるといった成り行きの中で。
涎を拭った指先は、そっと唇に触れていた。そこに宿った、はぐらかされたという気分――物足りなさ、を確かめるように。そして、横へと逃がされていた視線は、いつしか前方へと舞い戻っていた。魁偉な姿を見せつける牡肉へと。
そんな怜子のさまを愉しげに見下ろしていた志藤が、つと腰をかがめ、両手を脇の下に差しいれて立たせようとする。その腕に体の重みを預けながら、怜子はヨロリと立ち上がった。
立位で向かいあうかたちに戻ると、志藤は怜子のくびれた腰から臀へと、ツルリと撫でおろして、
「このままここで、ってのも愉しめそうですが」
「…………」
「やっぱり、落ち着かないですね。二階に上がりましょう」
怜子の返答は待たずにそう決めて。シャワーを止めた。この場での一幕を伴奏しつづけた水音が止む。
さあ、と片手をかざして、志藤が怜子を促す。次の舞台への移動を。
「…………」
無言のまま、怜子はそれに従って、ドアへと向かった。
脱衣所に出て。
おのおの、バスタオル――英理によって常に豊富に用意されている清潔なタオル――で身体を拭いて。
しかし着替えまでは用意されていない。今夜の場合は。怜子の着衣一式、皺になったスーツとその中に包みこまれた下着やストッキングは、丸めて脱衣籠に放りこまれてあった。
仕方なしに、もう一枚とったタオルを身体に巻こうとした怜子だったが、
「必要ないでしょう」
そう言った志藤にスルリと奪い取られてしまった。
「今夜は、僕らふたりきりなんですから。このままで」
「…………」
一瞬、詰るように志藤を睨んだ怜子だったが。微かな嘆息ひとつ、ここでも指示に従って。素足を踏んで、裸身を脱衣所のドアへと進めて。
そこで振り返った。湯上りの滑らかな背肌と豊臀の深い切れこみを志藤へと向けて、顔だけで振り向いて、
「今夜だけよ」
そう云った。せいぜい素っ気ない声で。
「ええ。わかってますよ」
志藤が答える。失笑はしなかったが、笑いを堪えるという表情は隠さずに。
それが妥当な反応だろう。怜子とて、その滑稽さは自覚しないわけがなかった。この期におよんで。こんな姿で。
それでも彼女としてはそう言うしかなかった。どれだけ無様な醜態を重ね、ズルズルと後退を続けたあとだろうと、すべてを放擲するわけにはいかないではないか、と――。
薄笑いを浮かべる男に、怨ずるような視線を送って顔を戻すと、怜子は脱衣所のドアを開け放った。
ひんやりと殊更に大きく感じた温度差に竦みかかる足を踏み出して、廊下に出た。
裸で共用スペースに出るなど、かつて一度もしたことのない振る舞いだった。家にひとりきりのときにも。羞恥と後ろめたさに胸を刺されながら、覚束ぬ足取りで玄関ホールへと進む。ペタリペタリと、湿りを残した足裏に床を踏んでいく感触に不快な違和感を覚えながら、より明��い空間へと。高い天井からの柔らかな色の照明が、このときには眩いような明るさに感じられて。その光に照らし出されたホールの景色、日々見慣れた眺めを目にした怜子が思わず足を止めたのと、
「ああ、ちょっと、そのままで」
少し距離を置いて後をついてくる志藤がそう声を掛けたのは、ほぼ同時だった。
日常のままの家内の風景の中(それも玄関先という場所)に、一糸まとわぬ裸身を晒しているという非現実感が怜子の足を止めさせた。志藤の指示は、無論その異常な光景に邪まな興趣を感じて――なにしろ、豊艶な裸身を晒しているのは、平素はクール・ビューティーとして知られる辣腕の女社長であり、この家の女主人なのだ――じっくりとその珍奇な絵図を鑑賞しようとする意図からだった。
そんな思惑は見え透いていたから、怜子はそれを無視して歩みを再開し、階段へと向かった。
指示を黙殺された志藤も、特に不満を言うこともなく後を追った。怜子が西側の階段、自室へと向かうルートを選んだことにも、別に異議はなかった。多分、そうなるだろうと思っていた。足取りを速めたのは、もちろん階段を昇り始めた怜子を、ベストな位置から眺めるためだった。
「……おお…」
急いだ甲斐があって、間に合った。狭く、やや急角度な階段を上がっていく怜子の姿を、数段下のまさにベスト・ポジションから仰ぎ見て、感嘆の声を洩らした。
どうしたって、まず視線はその豊臀へと吸い寄せられる。下から見上げる熟れた巨臀は、さらにその重たげな量感が強調されて、弩級の迫力を見せつけてきた。そして、はちきれんばかりの双つの臀丘は、ステップを踏みのぼる下肢の動きにつれて、ブリッブリッと扇情的に揺れ弾んで、そのあわいの深い切れこみの底の暗みを覗かせるのだった。
陶然と志藤は見上げていたが、その絶景を味わい尽くすには階段はあまりに短かった。粘りつく視線を気にした様子の怜子が途中から動きを速めたので、鑑賞の時間はさらに短縮された。その分、セクシーな双臀の揺動も派手になったけれど。
ああ、と思わず惜しむ声をこぼして、志藤も後を追った。足早に階段を昇りきった怜子の裸の足裏の眺めに目を引かれた。働く女として長年高いヒールを履き続けている影響なのか、怜子の踵はやや固くなっているように見えて。今さらのようだが、その些細な特徴に気づいたことも、またひとつこの美貌の女社長の秘密に触れたってことじゃないか、などという自己満足を湧かせながら。
階上に上がって、通路の奥の怜子の私室へと向かう。手前の慎一の部屋の前を行きすぎるとき、怜子は顔を逆へと背けた。志藤は、無論なんの感慨もなく、今夜は無人のその部屋の前を通過する。
逃げこむ、というような意識があったのだろうか、自室に辿りつくと怜子は逡巡もなくドアを開けて中へと入った。志藤も悠然とそのあとに続いて。
入室すると、やけに慎重な、確実を期すといった手つきで、ドアを閉ざした。閉じられた空間を作った。
間接照明に浮かび上がった室内を見回して、
「社長の部屋になってから入るのは、初めてですね」
と云った。同居の開始以前、ここがまだ英理の部屋だった頃に一度だけ入室したことがあった。
入れ替えが行われて、当然室内の様相は、そのときとは変わっている。置かれているインテリアもすべて移動したものだし。物が少なく、すっきりとまとめられているところは似通っているが。
なにより、はっきりとした違いは、
「怜子社長の匂いがしますね。当たり前だけど」
広くとられた空間を、うろうろと裸で歩きまわりながら、志藤が口にしたその点だろう。両手を広げ、うっとりとその馥郁たる香りを吸いこんで。
「…………」
その香りの主は、むっつりとそんな志藤を見やっていた。壁際に置かれたドレッサーの側らに佇んで。暖色の照明が、その見事な裸体に悩ましい陰影を作って。その肢体を、三枚の鏡がそれぞれの角度から映している。チラリと、その鏡面に怜子の視線が流れた。
「ああ、さすがにいいクッションだな」
志藤が言った。断りもなく怜子のベッドに触れながら。セミダブルのサイズのベッドは、簡単に整えられた状態、怜子が今朝部屋を出たときのままだった。同居が始まってからも、この部屋の掃除は(立ち入りは)無用だと、英理には通達してある。
志藤が、大きく上掛けをめくった。現れ出たシーツは皺を刻んで、さらにはっきりと怜子の昨夜の痕跡を示す。その上に、志藤が寝転がる。ゴロリと大の字に。
その傍若無人な振る舞いに眉をしかめても、怜子に言うべき言葉はなかった。裸の男を部屋に招じ入れておいて、ベッドに乗られたと怒るのは馬鹿げているだろう。
志藤が仰向けのまま腰を弾ませて、マットの弾力を確かめる。恥知らずに開いた股間で、やはり恥知らずに半ばの漲りを保った屹立が揺れる。滑稽ともいえる眺めだった。
うん、と満足げに頷いて。顔を横に倒して、深々とピロウの匂いを嗅いだ志藤は、
「ああ、怜子社長の香りに包まれるようだ」
と、またうっとりと呟いた。
「向こうの、いまの僕らの部屋にも、最初の頃はこの香りが残ってたんですがね。いまでは、さすがに消えてしまいましたが」
そう続けて、首を起こして怜子を見やった。先ほどからの志藤の行為と科白に、不快げに眉根を寄せている怜子にもお構いなしに、
「その最初の頃に、英理が“残っているのは、香りだけじゃないわ”って云うんですよ。香りだけじゃなくて、怜子社長の、この一年間の……そのう、色々な感情、とか」
言い出しておいて、途中から奇妙に言いよどむ様子を見せる。その志藤に、
「……だいたい、想像がつくわ」
冷ややかな声で怜子はそう云って。
それから、傍らのドレッサーを見やった。体をまわし上体を屈みこませて、鏡に映した顔を覗きこんだ。ベッドの志藤のほうに、剥き身の臀を向ける態勢で。化粧の崩れを確認する。
本当は、部屋に入ってきたときから、それをしたかったのだ。タイミングを探していた。いまの志藤とのやりとりが切欠になったというなら、自分でも不可解だったが。
さほど酷い状態にはなっていなかった。常に控え目にと心がけているメイクは、見苦しいほどに崩れてはいない。ルージュだけは、ほとんど剥げ落ちてしまっていたが。
そもそも……シャワーを浴びたといっても、顔は洗っていなかった。髪も濡れているのは毛先だけだ。
なんのことはない、という話になってしまう。志藤の来襲までに、それをする時間がなかったわけではないのだから。
結局、唇に残ったルージュを拭い、鼻や額を軽くコットンではたいただけで、手早く作業を終えた。見苦しくなければそれでいい、と。
態勢を戻して、振り向く。愉しげに観察していた志藤と目を合わせて、
「……この一年の、私の恨みや後悔が残っている、部屋中にしみついている、って。そんなことを、あの子は言ったんでしょう?」
やはり、冷淡な声で怜子はそう訊いた。
「ええ? すごいな。さすが母娘ってことですかね」
志藤が感心する。一旦は言いよどんでおきながら、あっさりと怜子の推測が正解だと認めて。
「わかるわよ」
不機嫌に怜子は答える。同居を始めてからの英理の言動を思い出せば、そのくらいは容易に察しがつくと。“さすが母娘”などと、皮肉のつもりでないのなら、能天気に過ぎる言いようだ、と。
だが、意地悪くか、ただ無神経にか、持ち出された英理の名が、怜子の心に水を差し制動をかけたかといえば……そんなこともなかったのだ。改めて、いまの英理がどんな目で自分を見ているのかを伝えられ、この二ヶ月間に繰り返されてきた挑発的行動を思い返せば、現在のこの状況への罪悪感は薄れていく。
そもそも、その状況、今夜のなりゆき自体が、英理の企みによるものであるのならば――と、弁解じみた呟きを胸におとす。その前提を確認すれば、疎ましさと反発が湧き上がったけれど。
「実際、どうなんです? この寝心地のいいベッドは、怜子社長の哀しみや寂しさを知ってるんですか? この部屋にも、」
「知らないわ」
まくしたてられる志藤の言葉を遮った声には、不愉快な感情が露わになった。
「ああ、すみません。はしゃぎすぎましたね」
志藤が上体を起こして頭を下げた。居住まいを正す、というには、股間をおっぴろげたままの放埓な姿勢だったが。
「こうして、社長の部屋に入れたのが嬉しくて、つい。以前は殺風景なホテルの部屋ばかりでしたから」
「……当然でしょう、それは」
「そうなんですけど。だからこそ念願だったわけでね。いつか、怜子社長のプライベートな空間で愛しあえたらっていう思いが。それが叶って、はしゃいでしまったんです」
「……それはよかったわね」
冷ややかに。志藤の大袈裟な喜びぶりに同調することはなく。それでも、そうして言葉を返すことで、会話を成立させてしまう。
この狎れ合った雰囲気はなんなのか、と怜子は胸中にひとりごちる。この部屋に入った瞬間から、それまでの緊迫した感情が消えてしまったことに気づく。それは、裸で家中を歩かされるという破廉恥な行為の反動でもあったのだろうが。
同じような心理の切り替わりを過去にも経験していた。一年以上前、志藤との密やかな関係が続いていた頃だ。周到に人目を警戒した待ち合わせからホテルに到着し、“殺風景な部屋”に入ってドアを閉ざすと、怜子はいつもフッと張り詰めた緊張が解けるのを感じたものだった。どれだけ、はるか年若な男との爛れた関係に懊悩と抵抗を感じていようと、その瞬間には、ほっと安堵の感情を湧かせていた。無論それは、なんとしても事実を秘匿せねばならないという思いの故だったわけだが。
そう、当時とは状況は変わってしまっている。もはや、閉ざしたドアに、守秘の意味はないというのに。
「それに、あの頃と違って、今夜は時間を気にする必要もないわけですからね。朝まで、たっぷりと愉しむことが出来るんですから」
「…………」
愉しげな志藤の科白に、体の奥底のなにかが忽ちに反応するのを感じる。“朝まで、たっぷりと”という宣告に。かつての限られた時間の中の慌しい行為でも、毎回自分に死ぬような思いを味わわせたこの剛猛な牡が、と戦慄する。
つまりは、肉体の熱は少しも冷めてはいないのだった。浴室での戯れに高められたまま、裸での行進という恥態を演じ、この部屋での志藤の振る舞いに眉をひそめ、不愉快な会話に付き合うという中断を挟んだあとにも。
であれば、この部屋に入ってからの奇妙な心の落ち着きも、単に最も私的な空間へ逃げこんだという安心感によるのではなくて。ついに、ここまで辿り着いたという安堵がもたらしたものということになるのではないか。迂遠な、馬鹿馬鹿しいような段階を踏んで――クリアして――ようようこのステージに到着したのだ、という想いが。あとは、もう――――。
さあ、と志藤が手招く。ベッドの上、だらしなく脚を開いて座ったまま。その股座に、十全とは云わぬが屹立を保った肉根を見せつけて。
「……我が物顔ね…」
詰る言葉は、どこか漫ろになった。双眸に、ねっとりとした色が浮かんで。
ざっくりと、ブルネットの髪を手櫛で一度掻き上げて、怜子は足を踏み出す。豊艶な裸身を隠すことなく、股間の濃い叢も、重たげに揺れる巨きな乳房も曝け出して。ゆっくりと、娘婿たる男が待ち構えるベッドへと歩み寄った。
乗せ上げた裸の膝に、馴染んだ上質の弾力がかえってくる。スウェーデン製のセミダブルのベッドは、六年前の離婚の際に買い換えたものだ。だから、このベッドが怜子以外の人間を乗せるのも、二人分の重みを受け止めるのも、今夜が初めてということになる。
抱き寄せようとしてきた志藤の手をかわして、腕を伸ばす。その股間のものを掴んで、軽くしごきをくれた。
「おっ?」
「……続きをするんでしょう…」
そう云って、体を低く沈めていって、握りしめたものに顔を寄せた。
「なるほど。再開するなら、そこからってわけですか」
そう言いながら、志藤の声にはまだ意外そうな気色があった。そんな反応を引き出したことは小気味よかったが、それが目的だったわけではない。
先の浴室での行為で知りそめた口舌の快美、突然の中断につい“物足りない”と感じてしまった、その感覚を求めて、というのも最たる理由ではなかった。
あのときに怜子が飽き足りぬ思いを感じてしまったのは、“このままだと、口の中に出してしまいそうだったので”という志藤の言葉が、まったくのリップサービスであることが明白だったからだ。
当然な結果ではあった。そのときの怜子は、ひたすら己が激情をぶつけるばかりで、男を喜ばせようという思いもなかったのだから。だが、たとえ奉仕の意識が生じていたとしても、繰り出すべき技巧など、彼女にはなかった。無理もないことだ、数えるほどの、それも形ばかりにこなしたという経験しかなかったのだから。
もし……過去の志藤との関係が途絶することなく続いていたなら、違っただろう。最初の峻拒から、済し崩しに受け容れさせられたという流れの延長線上に。怜子は徐々に馴致を受けて、男への奉仕の技巧を身につけることになっただろう。
その練達の機会を逸してしまったことを、まさか惜しいとは思わない。思うはずがなかった、のだが。
だったら……と、怜子は考えてしまったのだった。自分が無我夢中で演じた狂熱的な行為にも悠然たる表情を崩さない志藤を見上げたあのときに。瞬間的に、直感的に。
だったら……その時間を――自分が思いもかけぬ成り行きで、この男と訣別してからの一年間を、彼のそばで過ごしたあの子は。日々の懇ろな“教育”を、過去の自分とは比ぶべきもない熱心さで受け入れたであろう、あの子は。いまではどれほどの熟練した技巧を身につけたのだろうか? と。
さぞかし……上達したことだろう、と確信する。こんな男に、それだけの期間、じっくりと仕込まれたならば。
そう、じっくりと。ふたりだけの濃密な時間の中で。自分が、ひとり寂寥を抱いて過ごしていた間。
か黒き感情が燃え立つ。ずっと、この発露のときを待っていたというように腹の底で燃え上がって、怜子を衝き動かす、駆り立てる。
鼻を鳴らして、深く牡の匂いを嗅いで。舌を伸ばしていく。長い脚を折って、志藤の両脚の間に拝跪するような形になって。
赤黒い肉瘤の先端、鈴口の切れこみに舌先を触れさせる。伝わる味と熱にジンと痺れを感じながら、舌を動かしていく。我を忘れてむしゃぶりつくだけの行為にはしたくないのだ、今度は。
ああ、と頭上で志藤が洩らした快美の声、それよりもググッと充実ぶりを増していく肉根の反応に励まされて、怜子は不慣れな舌の愛戯を続けていく。たちまち漲りを取り戻した巨根は、再び多量の唾液に塗れて、淫猥な照りと臭気を放った。
懸命に怜子は舌を蠢かせた。少しでも、競合相手との“差”を縮めたくて。なればこそ殊更に拙劣に思えてしまう己が行為に、もどかしさを噛みしめながら。
志藤が怜子の髪を掻きあげて、顔を晒させる。注がれる視線を感じても、怜子は“見ればいい”という思い入れで、いっそう行為に熱をこめていった。
はしたなく伸ばした舌で男性器を舐めしゃぶる痴態、初めて見せるその姿の新奇さを味わうのであろうと。普段の取り澄ました顔と、いまの淫らな貌とのギャップを愉しむのであろうと。娘婿のペニスにしゃぶりつく義母、という浅ましさを嗤うのだろうと。とにかく、この姿態を眺めることで志藤が味わう感興が、自分の稚拙な奉仕を少しでも補うのであれば、という健気なほどの思いで。
それなのに。
「ああ、感激ですよ」
と志藤は嬉しげに云って。それまではよかったのだが、
「でも、どうしたんです? 以前は、あんなに嫌がっていたのに」
今さら、そう訊いて。さらには、
「もしかして……他の誰かの、お仕込みですか?」
「…………」
舌の動きを止めて、怜子は志藤を見上げた。
「いや、そうだとして、別に僕がどうこういう筋合いじゃないですけど。ただ、もしそうなら“部屋やベッドに怜子社長の寂しさが染みついてる”なんて、とんだ見当違いな言いぐさだったな、って」
志藤は言った。拘りのない口調で。
「………さあ。どうかしらね」
曖昧な答えを、不機嫌な声で返して。怜子は視線を落とした。知らず、ギュッと強く握りしめていた剛直に目を戻して。
あんぐりと大開きにした唇を被せていった。ズズッと勢いよく半ばまで呑みこんで、そのまま首を振りはじめる。憤懣をぶつけるように。
「おお、すごいな」
聴こえた志藤の声は、ただ快感を喜ぶ気色だけがあった。追及の言葉を重ねようともせずに。
そもそも、さほど本気の問いかけでもなかったのだろう。怜子の変貌ぶりを目にしてふっと湧き上がった、疑念というよりは思いつきを口にしただけ。だから深刻な感情などこもらず。
それが怜子には悔しかったのだった。疑われたことが、ではなく、ごく気軽にその疑惑を投げかけられたことが。“他の誰か”と云った志藤の口ぶりに、嫉妬や独占心の欠片も窺えなかったことが。
自分は常に志藤の向こうに英理の存在を感じては、いちいちキナ臭い感情を噛みしめているというのに――。
“僕がどうこういう筋合いじゃない”などと、弁えたような言いぐさも気に入らなかった。正論であれば余計に。今さら、この期におよんで、と。
悔しさ腹立たしさを、激しい首振りにして叩きつける。突っ伏した姿勢で、シーツに圧しつけた巨きな乳房の弾力を利用するようにして。
口腔を満たし尽くす尊大な牡肉。灼けつくような熱と鋼のような硬さ。たとえ悔しまぎれに歯を立てようとしても、容易く跳ね返されてしまうのではないかと思わせる強靭さが憎たらしい。
憎くて、腹立たしくて、悔しくて。どうしようもなく、肉が燃える。
いつしか、苛烈なばかりだった首振りは勢いを減じて。怜子の舌は、口中で咥えこんだものに絡みつく蠢きを演じていた。
えずくほどの深い呑みこみから、ゆっくりと顔を上げていく。ブチューッと下品な吸着の音を響かせながら、肉根の長大さを堪能するようにじわじわと口腔から抜き出していって。ぷわっと巨大な肉笠を吐き出すと、新鮮な呼吸を貪るいとまも惜しむようにすかさず顔を寄せていった。多量に吐きかけた涎が白いあぶくとなって付着している肉根に鼻頭を押し当てて直に生臭さを嗅ぎながら、ヴェアアと精一杯に伸ばし広げた紅舌を剛茎へと絡みつかせていくのだった。淫熱に染まった瞼の下、半ば開いた双眸に、どっぷりと酩酊の色を湛えて。
「ああ、いいですよ。怜子社長の舌」
熱烈な奉仕を受ける志藤はそんな快美の言葉を吐きながら、己が股座に取りついた麗しい義母の姿を眺めおろして。豊かな肢体を折りたたむようにした態勢の、滑らかな背中や掲げられた臀丘を撫でまわしていたが。
やがてゆっくりと、股間は怜子に委ねたまま、上体を後ろに倒していって、仰臥の姿勢に変わった。
「僕からも、お返ししますよ。そのまま、おしりをこちらにまわして、顔を跨いできてください」
「…………」
意図を理解するのに時間がかかった。
いわゆるシックスナインの体勢になれと志藤は指示しているのだった。それも、女が上になったかたちの。
「……いやよ」
短く、怜子は拒絶の言葉をかえした。かつての志藤との関係の中でも経験��ない行為だった。その痴態を思い描くだけでも、恥ずかしさに首筋が熱くなる。
「今さら恥ずかしがらなくてもいいじゃないですか、僕と社長の間で。やってみれば愉しめますよ、きっと。社長の熱い奉仕の御礼に、僕の舌でたっぷり感じさせてあげますよ」
ペラペラとまくしたてて、長く伸ばした舌の先で、宙に8の字を描いてみせる。その卑猥な舌先の動きに、怜子は目を吸い寄せられた。
「英理も、このプレイが好きなんですよ。愛を交わしてるって実感が湧くと言って。だから、怜子社長もきっと気に入りますよ」
「……なにが“だから”よ」
そう呟いて。しかし、のろのろと怜子の身体は動き始める。淫猥な舌のデモンストレーションと、科白の中に盛りこまれた気障りなひとつふたつの単語と、より効果を及ぼしたのは、どちらであったか。
突っ伏していた裸身がもたげられ、膝が男の脚を跨ぎ越して。そのまま、下半身を志藤の頭のほうへと回していく。
顔を跨ぐ前には躊躇をみせたが、さわりと腿裏を撫でた志藤の手に促されて、思い切ったように片脚を上げた。オス犬のマーキングのごとき恥態を、ニヤニヤと仰ぎ見る志藤の眼にさらして、
「ああっ」
淫らな相互愛撫の体勢が完成すると、怜子は羞辱の声をこぼして、四つ這いに男を跨いだ肢体の肉づきを震わした。
「ああ、絶景ですよ」
大袈裟な賛嘆の声を志藤が上げる。怜子の、はしたなく広げた股の下から。
「ふふ、大きな白い桃が、ぱっくりと割れて」
「……いやぁ…」
弱い声を洩らして、撫でさすられる臀丘をビクビクと慄かせる。戯れた喩えに、いま自分が晒している痴態を、分厚い臀肉をぱっくりと左右に割って秘苑の底まで男の鼻先に見せつけているのだということを、改めて突きつけられて。
「こんなに濡らして。おしゃぶりしながら、社長も昂奮してくれてたんですね?」
「……あぁ…」
「ああ、それにすごい匂いですよ。熟れたオンナの濃厚な発情臭、クラクラします」
「ああっ、やめて」
ネチネチとした言葉の嬲りにも、怜子はやはりか弱い声をこぼして、頭を揺らし腰をよじるばかり。志藤の意地悪い科白が、しかし偽りではなく、観察したままを述べているのだと判ったから。自覚できたから。
そして、恥辱に身悶えながら、怜子はその恥ずかしい態勢を崩そうとはしなかった。ひと通りの約束事のように言葉での嬲りを済ませた志藤が首をもたげて、曝け出された女裂へと口を寄せるのを察知すると、アアッと滾った叫びを迸らせて。男の顔を跨いだ逞しい太腿や双臀の肉づきをグッと力ませる。
息吹を感じた、その次の瞬間には、ピトリと軟らかく湿ったものが触れてきた。あられもない開脚の姿勢に綻んだ花弁に柔らかく触れた舌先が、複雑な構造をなぞるように這いまわって、纏わる女蜜を舐めずっていく。まずは、と勿体をつけるような軽い戯れに、
「……あぁ…」
怜子は蕩けた声をこぼして、涎に濡れた唇を震わした。男を跨いだ四肢から身構えの力みが消え、ぐっと重心が低くなっていく。
クンニリングスという行為自体が、これまでほとんど味わったことがないものだった。無論、怜子が拒んでいたからだったが。なれば、いま破廉恥な態勢で無防備に晒した秘裂に受ける男の舌の感触は、新鮮な刺激となって、すでに淫熱を孕んだ総身の肉を蕩かす。指とも違った優しく柔らかな接触が、ただ甘やかな快美を生んで、気だるく下肢を痺れさせるのだった。
だが、そのまま甘ったるい愉悦に揺蕩っていることを許されはしなかった。
ヒイッと甲走った叫びを上げて顎を反らしたのは、充血した肉弁を舐めずり進んだ舌先が女芯に触れたからだった。やはりぷっくりと血を集めた大ぶりな肉芽を、根こそぎ掘り起こすように、グルリと舌を回されて。峻烈すぎる感覚に、咄嗟に浮かし逃がそうとした臀の動きは、男の腕力に封じこまれて。容赦ない舌の蹂躙に、怜子はヒイヒイと悶え啼くばかりだったのだが。つと、志藤は、真っ赤に膨れ上がった肉真珠から舌先を離して、
「お互いに、ですよ」
と、優しげな声で言った。
云われて、難儀そうに眼を開く怜子。その眼前に、というより、男の股間に突っ伏した顔のすぐ横に、相変わらず隆々と屹立する長大な男根。ふてぶてしく、尊大に。獰悪な牡の精気を放射して。
両腕を踏ん張り体勢を戻して、大きく開いた口唇を巨大な肉瘤に被せていく。途端に口腔を満たす熱気と牡臭。反射的に溢れ出す唾液と、剛茎に絡みついていく舌。
「そう、それでいいんです」
傲岸にそう告げて、自身も舌の動きを再開する志藤。忽ち、怜子の塞がった口中で弾ける悦声。
ようよう、その態勢にそぐった相互愛撫が始まって。しかしそれは、拮抗したものにはならない。互いの急所に取りつきながら、攻勢と守勢は端から明らかで。
この娘婿の、女あしらいの技巧、女のカラダを蕩けさせ燃え上がらせる手管のほどを、怜子はまたも存分に思い知らされることになった。緩急も自在に秘裂を嬲る志藤の舌先は、悪辣なまでの巧緻さを発揮して。ことに、ひと際鋭敏な肉真珠に攻めが集中するときには、怜子は健気な反撃の努力さえ放棄して野太い剛直を吐き出した口から、はばかりのない嬌声を張り上げるのだった。そうしなければ、肉の悦楽を叫びにして体の外へ放出しなければ、破裂してしまうといった怖れに衝かれて。
そして、受け止めきれぬほどの快楽に豊満な肢体を悶えさせ、嫋々たる啼泣を響かせながら、怜子はその胸に熱い歓喜の情感をも湧かせていた。“愛を交わしてる実感”と、英理がこの痴戯を表したという言葉を思い起こし噛みしめて。確かに、互いに快楽の源泉を委ねあって口舌の愛撫を捧げあうこの行為には、そんな感覚に陥らせる趣向があった。懇ろな、志藤の舌の蠢きには“愛”とはいわぬまでも、確かな執着がこもっていると感じられて、怜子の胸に熱い感慨を掻き立てるのだった。
そんな心理のゆえだったろうか、
「……ああ……いい……」
ねっとりと、舌腹に包みこむように、また肉珠を舐め上げられたとき、怜子は快美をはっきりとした言葉にして吐き出していた。我知らず、ではなく、意識的に。
フッと、臀の下で志藤が笑う気配があって、
「言ったとおり、気に入ってくれたみたいですね」
愉しげにそう云って、
「ここも凄いことになってますよ。いやらしい蜜が、後から後から溢れ出して。ほら」
ジュル、と下品な音を立ててすすることで、溢出の夥しさを実証して、
「ああ、極上の味わいですね。濃厚で、芳醇で。熟成されてる」
「……あぁ…」
大仰で悪趣味な賞賛に、怜子は羞恥の声を返して。ブルリと揺らした巨臀の動きに、またひと滴の蜜液を、志藤の口へと零した。
淫情に烟った双眸が、鼻先にそそり立つ肉塊へと向けられる。赤黒い肉傘の先端、鈴口の切れこみからトロリと噴きこぼれた粘液に。
あなただって、と反駁の言葉を紡ぐ前に、口が勝手に動いていた。先端に吸いつき、ジュッと吸い上げる。その瞬間に鼻へと抜ける濃厚な精臭に酩酊の感覚を深めながら、剛茎を握った手指にギュッと力をこめて扱きたてる。もっと、と搾り出そうとする。
志藤が洩らした快美の呻きが怜子の胸を疼かせ、淫猥な作業にいっそうの熱をこめさせた。だが、そのすぐ後には、またジュルリと蜜汁を吸われる刺激に、喉奥でくぐもった嬌声を炸裂させることになる。
互いの体液を、欲望の先触れを啜りあうという猥雑な行為に耽りながら、怜子はまた“英理の言葉は正しい”という思いを過ぎらせていた。悔しさとともに。“あの子は、この愉悦を、ずっと――”と。そんな想念を湧かせてしまう、己が心のあさましさは、まだ辛うじて自覚しながら。そのドス黒い感情に煽り立てられて、いっそうの情痴に溺れこんでいく己が心と体を制御することまでは、もう出来ずに。
ともに大柄な体躯を重ね合った男女の姿を、壁際のドレッサーが映していた。汗みどろの肌を合わせ、互いの秘所に吸いつきあって、ひたすら肉悦の追求に没頭する動物的な姿を。
白く豊艶な肢体を男の体に乗せ上げた女が、また鋭い叫びを迸らせる。甲高い雌叫びの半ばを咥えていた巨大な屹立に直に吐きかけ、半ばを宙空に撒き散らした。隠れていた面が鏡面に映る。この瀟洒な化粧台の鏡が毎日映してきた顔、しかしいまは別人のように変わった貌が。淫情に火照り蕩け、汗と涎にまみれた、日頃の怜悧な落ち着きとはかけ離れたその様相を、鏡は冷ややかに映し出していた。
「……あぁ…」
男の顔の上で、こんもりと高く盛り上がった臀丘にビクビクと余韻の痙攣を刻みながら、怜子は弱い声を洩らした。
幾度目か���快感の沸騰をもたらして、志藤の舌はなおも蠢きを止めない。息を継ぐ暇も与えられず、怜子は目眩むような感覚に晒され続けた。これほどの執拗な嬲りは、かつての関係の中でも受けた記憶はなかった。当時のような時間の制限のない今夜の情事、“朝まで、たっぷりと”という宣告を志藤はさっそく実践しはじめたのだ、と理解して。どこまで狂わされてしまうのか、という怯えを過ぎらせながら、怜子は中断や休息を求める言葉を口にはしなかった。
爛れた愛戯に、際限なく高められていく淫熱、蕩かされていく官能。だが、その中心には虚ろがあった。
肉芽を嬲り続ける舌先は、しかしその攻めによって発情の蜜液を溢れさせる雌孔には触れようとしない。浴室での戯れ合いでそこに潜りこみ掻きまわした指は、悶えを打つ双臀を掴んだまま。
であれば、怜子の肉体に虚ろの感覚はいや増さっていくばかり。表層の快感を塗り重ねられるほどに、内なる疼きが際立っていって。無論すべて男の手管であることは承知しながら、怜子は眼前に反り返る尊大な剛肉に再び挑みかかっていくしかなかった。また唇に舌に味わう凶悪な特徴に、さらに肉の焦燥を炙られることまでわかっていても。その獰悪な牡肉こそが、それだけが、我が身の虚ろを満たしてくれるものだと知っていれば。
そうして、健気な奮戦は、あと数度、怜子が悦声を振り絞り肢体を震わすまで続いて、
「……ああっ、も、もうっ」
そして予定通りに終わった。ついに肉の焦燥に耐え切れなくなった怜子が、べったりと志藤の顔に落としていた臀を前へと逃したのだった。混じりあった互いの汗のぬめりに泳ぐように身体を滑らせて、腰に悩ましい皺を作りながら上体をよじり、懇願の眼を向ける。快楽に蕩けた美貌に渇望の気色が凄艶な迫力を添えて。
「いいですよ」
口許の汚れを拭いながら、志藤が鷹揚に頷く。頷きながら動こうとはせずに、迎えるように両腕を広げて。
その意味を理解すると、即座に怜子は動いた。反発も躊躇もなく。横に転がるように志藤の上から下りると、向きを変えて改めてその腰を跨いだ。示唆のとおり、騎乗位で繋がろうとする態勢になって。あられもなくガニ股開きになった両腿を踏ん張って、巨大な屹立へと向けて腰を落としていく。差し伸ばした手にそれを掴みしめ、照準を合わせるという露骨な振る舞いも躊躇なく演じて。灼鉄の感覚が触れたとき、半瞬だけ動きが止まったが、グッと太腿の肉づきを力ませて、そのまま巨臀を沈めていった。
「ああッ」
ズブリと巨大な先端を呑みこんで滾った声を洩らした、その刹那に、
(――たった、これだけのこと)
そんな言葉が脈略もなく浮かび上がってきた。
「……あ……おお…」
沈みこませていった臀が志藤の腰に密着し、魁偉な肉根の全容を呑みこむと、怜子は低い呻きを吐いて。次いで、迫り上げてきた情感を堪えるために、ギッと歯を食いしばった。
臓腑を圧し上げられるような感覚。深く重い充足の心地。
身体を繋げるのは、今夜二度目だ。すでにリヴィングで、この長い夜の始まりの時点で情交を行い、怜子は絶頂にも達していた。
それなのに、いま“やっと”という感慨が怜子の胸を満たす。
と、志藤が、
「ああ。ようやく、ひとつになれたって気がしますね」
と云ったのだった。実感をこめた声音で。
「ああっ」
怜子が上げた声は歓喜の叫びだった。重たげな乳房を揺らしながら前のめりになって、両手を志藤の首にしがみつかせて、
「誰とも、してないわ」
泣くような声で、そう告げた。それは、さきの志藤の問いかけへの答えだった。“他の誰か”などという無神経な問いへの。そのときには、憤慨のままに返した曖昧な答えを、いまになって怜子は訂正したのだった。懸命な感情をこめて。
「嬉しいですよ」
志藤が笑む。そんなことは先刻承知といった顔で、
「ずっと、僕のことを待っていてくれたってわけですね」
傲慢な問いかけに、怜子は乱れた髪を揺らして頭を振った。縦にとも横にともつかず曖昧に。そのまま誤魔化すようにキスを求めた。
だが志藤は軽く唇を合わせただけで顔を逸らして、体を起こしていく。繋がったままの体位の変更、強靭な肉の楔に蕩けきった媚肉をゴリッと削られて、ヒッと喉を反らした怜子の身体を片手に抱きとめながら、対面座位のかたちをとる。やや不安定な態勢への変化に、怜子はさらに深く腕をまわして志藤の首にしがみつき、より強くなった結合感に熱い喘ぎを吐いた。志藤が顔を寄せれば、待ちかねたようにその口にむしゃぶりついていく。
卑猥な唾音と荒い鼻息を鳴らしての濃密なキスの最中に、志藤が大きく腰を弾ませた。上質なマットレスの反発を利した弾みは、直ちに繋がりあった部分に響いて、
「アアッ、ふ、深いぃっ」
生臭いようなおめきを怜子に振り絞らせる。
「ふふ、悪くないでしょう?」
愉しげに言って、志藤は両手に抱えこんだ巨臀を揺らし腰を跳ね上げて、深い突き上げを送りこむ。
「ん、ヒイッ、お、奥、刺さってっ」
「ええ、感じますよ。怜子社長の一番奥。オンナの源」
生々しい実感の吐露に、さらに煽り立てる台詞をかえして。双臀を抱えていた両手を、背と腰に撫で滑らせて、
「それに、このかたちだと、より愛しあっているって実感がわくでしょう?」
「ああっ、志藤くんっ」
歓喜に震える叫びを放って、ぎゅっと抱きついた腕に力をこめた。志藤が口にしたその実感を確かめるように抱擁を強くして、巨きな乳房を圧しつけ、背中や肩を愛しげに撫でまわす。若い男の逞しい体躯や硬い筋肉を、総身の肌を使って感じ取ろうとしながら、また口付けをねだっていく。
美しい義母の熱い求めに応じながら、志藤は“その呼び方も久しぶりだな”などと冷静な思考を過ぎらせて。熱烈に口に吸いついてくる怜子の頬越しに、壁際のドレッサーへと視線をやった。
鏡面に白い背姿が映し出されている。豊満で彫りの深い裸の肢体。ねっとりとした汗に輝く背中に乱れた髪を散らして。くびれた腰からこんもりと盛り上がる巨きくて分厚い臀が、淫らな揺れ弾みを演じている。男の腰を跨いだ逞しい両腿を踏ん張って、あられもなく左右に割った双臀の肉づきを、もりっもりっと貪婪な気色で歪ませながら、女肉を貫いた魁偉な牡肉を食らっている。不慣れな体位でありながら、淫蕩な気合を漲らせた尻腰の動きには、もう僅かにもぎこちなさは見受けられず。
戯れに、志藤が抱え直した巨臀をグリリとまわしてやれば、怜子の涎にまみれた口唇から音色の違った嬌声が噴きこぼれて。そして忽ちに、そのアクセントを取り入れていくのだった。鏡に映る熟れ臀の舞踊が、いっそう卑猥で露骨なものになっていく。ドスドスと重たげな上下動に、こねくるような円の動きを加えて。
「ああっ、いいっ」
自らの動きで、グリグリと最奥を抉りたてながら、怜子が快美を告げる。ギュッと志藤の首っ玉にしがみつき頬を擦りよせながら。
「僕もたまりませんよ。怜子社長の“中”、どんどん甘くなっていって」
偽りのない感覚を怜子の耳朶へと吹きかけながら、志藤は自分からの動きは止めていた。交接の運動はまったく怜子に任せて、その淫らな奮戦ぶりと溶解っぷりを眺め、実際にどんどん旨みを増していく女肉の味わいを堪能していた。
だから、
「――ああっ、ダメ、も、もうっ」
ほどなく、切迫した声を洩らして、ブルと胴震いを走らせはじめた怜子のさまを“追いこまれた”と表するのは適切ではなかっただろう。
「いいですよ。思いっきり飛んでください」
鷹揚に許しを与えて、だが志藤はそれに協力する動きはとらない。最後まで怜子ひとりの動きに任せて。
男の胡坐の中に嵌りこんだ淫臀の揺動が激しく小刻みになる。ひたすら眼前に迫った絶頂を掴みとろうとする欲求を剥き出しにして。そして、予兆を告げてから殆んど間もなく、
「あああっ、イクわ、イクぅッ――」
唸るような絶息の叫びを振り絞って、怜子は快楽の極みへと飛んだ。喉を反らし、汗に湿ったブルネットの髪を散らして。爆発的な愉悦、まさに吹き飛ばされそうな感覚が、男の体にしがみつかせた四肢に必死の力をこめさせた。
志藤もまた快美の呻きを吐きながら、熟れた女肉の断末魔の痙攣を味わっていた。この夜ここまでで最高の反応、蕩け爛れた媚肉の熱狂的な締めつけを満喫しながらであれば、ギリギリと背肌に爪を立てられる痛みも、腰を挟みこんだ逞しい両腿がへし折らんばかりの圧迫を加えてくるのも、愉快なアクセントと感じられた。ついに“本域”のアクメに到達した艶母が曝け出す悶絶の痴態、血肉のわななきと滾りを堪能して。
そして、その盛大な絶息の発作が鎮まりきらぬうちに、大きく腰を弾ませて突き上げを見舞った。
ヒイイッと悲鳴を迸らせて、志藤の腕の中で跳び上がるように背を伸ばした怜子が、
「アアッ、ま、待って、まだ、イッて、待ってぇッ」
「いいじゃないですか。何度でも」
くなくなと頭を揺らして、しばしの休息を乞うのには、声音だけは優しく冷酷な答えを返して。膂力にものをいわせて、抱えた巨臀をもたげては落としを繰り返した。
無慈悲な責めに、忽ちに怜子は追い詰められた。ほぼ連続しての絶頂に追い上げられ、獣じみた女叫びを振り絞り、総身の肉置を痙攣させた。それからガクリと、糸が切れたように脱力して、志藤の肩に頭を落とした。
そこでようやく志藤は攻め手を止める。怜子の乱れ髪の薫りを嗅ぎながら、荒い喘ぎに波打つ背中を労うように撫でて。重たくなったグラマラスな肢体を、丁重に後ろへと倒させていく。半ば意識を飛ばした怜子は、されるがままだったが。背中がベッドを感じると安堵したような息を吐いて、さらに身体を虚脱させた。
態勢の変化に浅くなった結合、そのまま志藤は剛直を抜き取った。その刹那、朦朧たる意識の中で艶めいた微妙な色合いの声を洩らした怜子を愉しげに見下ろしながら、その膝裏に手を差し入れ、長く肉感的な両肢を持ち上げ、さらに腹のほうへと押しやる。
大柄で豊かな裸身が屈曲位の態勢に折りたたまれて、情交直後の秘苑が明かりの下に開陳される。濃密な恥毛は汗と蜜液にベットリと絡まり固まって肉土手にへばりついていた。熟れた色合いの肉弁は糜爛の様相でほどけ、その底まで曝け出している。媚孔は寸前まで野太いモノを咥えこんでいたという痕跡のままにしどけなく拡がって。そこから垂れ零れる淫蜜の夥しさと白く濁った色が、この爛熟の肉体の発情ぶりとヨガリっぷりをあからさまにしていた。まるですでに男の射��を受け止めたかのような有様だが、立ち昇る蒸れた臭気には、熟れきった雌の淫猥な生臭さだけが匂って。
「……あぁ…おねがい、少し休ませて…」
窮屈な態勢に、ようよう彼岸から立ち戻った怜子が懇願の言葉を口にした。薄く開いた双眸で志藤を見上げて。
「まだまだ。これからじゃないですか」
軽く怜子の求めをいなして、志藤が浮かせた腰を前へと進める。無論のこと、隆々たる屹立を保ったままの剛直を、開陳された女苑へと触れさせる。貫きにかかるのではなく、剛茎の腹で秘裂をヌラヌラと擦りたてながら、
「ようやく怜子社長のカラダもエンジンがかかってきたってところでしょう? 僕だって、まだ思いを遂げてませんしね」
「……あぁ…」
辛そうな、しかしどこか漫ろな声を零して。そして、怜子の視線はどうしようもなくそこへと、卑猥な玩弄を受けている箇所へと向かう。はしたない態勢に、これ以上なくあからさまにされた秘裂の上を、ヌルッヌルッと往還する肉塊へと。
「……すごい…」
思わず、といったふうに呟きが洩れた。その並外れた逞しさを改めて目に映し、淫らな熱を孕んだ部位に感じれば、つい今さっきまでの苛烈なまでの感覚も直ちに呼び起こされて。
「今度は僕も最後までイカせてもらいますよ」
「…………」
そう宣言した志藤が、片手に握った怒張の切っ先を擬して結合の構えをとっても、怜子はもう休息を求める言葉は口にしなかった。
膝裏を押さえつけていた志藤の手が足首へと移って、さらに深い屈曲と露骨な開脚の姿勢を強いた。羞恥と苦しさにあえかな声を洩らしながら、怜子の視線は一点に縫い止められていた。
真上から打ち下ろすような角度で、志藤がゆっくりと貫きを開始する。怜子はギリッと歯を噛みしばって、跳ね上がりかける顎を堪え、懸命に眼を凝らして、巨大な肉塊が己が体内に潜りこんでいくさまを見届けようと努めるのだったが。
休息を求めた言葉とは裏腹、ほんの僅かな中断にも待ち焦がれたといった様子で絡みついてくる媚肉の反応を味わいながらじわじわと侵攻していった志藤が、半ばから突然に一気に腰を叩きつけると、堪らず仰け反りかえった喉から獣じみたおめきをほとびらせて、
「ふ、深いぃッ」
生々しい実感を、また言葉にして吐き出した。宙に掲げられた足先が硬直して、形のよい足指がギュッとたわめられる。
「ええ。また奥まで繋がりましたよ。ほら」
そう言って、志藤が浮き上がった巨臀の上に乗せ上げた腰を揺する。それだけの動きに、またひと声咆えた怜子が、やっと見開いた眼で傲然と見下ろす男の顔を見やって、
「んん、アアッ、深い、ふかいのよっ、奥、奥までぇっ」
そう振り絞りながら、片手で鳩尾のあたりを掴みしめる。そこまで届いている、とは流石にありえないことだったが、それが怜子の実感であり。それをそのまま言葉にした女叫びには、その凄絶��感覚をもたらす圧倒的な牡肉への礼賛の響きがあった。そして、それほどに逞しく強靭な牡に凌される我が身への満悦、牝の光栄に歓喜するといった気色も滲んでいたのだった。忙しく瞬きながら、男の顔を仰ぎ見る双眸には、甘い屈服の情感が燃え立っていた。
そんな怜子の負けこみぶりを愉しげに見下ろして、志藤は仕上げにかかる。
最奥まで抉りこんだ剛直をズルズルと引き抜き、硬い肉エラで熱く茹った襞肉を掻き擦られる刺激に怜子を囀り鳴かせてから、ひと息に貫き通して、低く重い呻きを絞り出させる。べしっべしっと厚い臀肉を荒腰で打ち鳴らして、改めて肉根の長大さを思い知らせるような長い振幅のストロークを見舞えば、昂ぶりつづける淫熱に見栄も恥も忘れた義母はヒイヒイとヨガリ啼きオウオウと咆えながら、窮屈な姿勢に極められた肢体を揺らし、溶け爛れた女肉をわななかせて、必死に応えてきた。
だが、志藤の攻めが、深い結合のままドスドスと奥底を連打するものに切り替わると、
「アアッ、ダメ、私、またぁ」
もろくも切迫した声を上げて、もたげられた太腿の肥えた肉づきをブルブルと震わしはじめた。
と、志藤は抽送を弱めて、
「もう少し我慢してください」
そう言って、怜子の両脚を下ろし屈曲の態勢を直させて、体を前へと倒した。正常位のかたちに身体を重ねて、すかさず首を抱き唇を寄せてくる怜子に軽く応じてから、
「僕も、もうすぐなんで。一緒にイキましょう」
「……アアッ」
耳元に囁かれた言葉に、怜子は滾った声を放って、志藤の首にまわした腕に力がこもった。腰が震え、媚肉がキュッと収縮して咥えこんだモノを食い締めた。
だが志藤は、怜子が総身で示した喜びと期待に直ちに応えようとはせずに、
「ああ、でも、どうですかね」
と、思案する素振りを見せて、
「もちろん、いつものピルは用意してますけど。でも、いまや義理とはいえ母親になった女性に……ナカ出しまでしてしまうってのは、さすがに罪が深いかな?」
「ああっ」
と、怜子が上げた声は、今度は憤懣によるものだった。この期におよんでの見え透いた言いぐさ、底意地の悪さに苛立ったように頭を揺らして。そうしながら、素早くその身体が動いている。腕にはさらに力みがこもって、男の硬い胸を己が胸乳へと引き寄せ。解放されてベッドへと落ちていた両脚は、志藤の下半身へと絡みついていって、尻の後ろで足首を交差させたのだった。がっし、と。決して逃がさぬ、という意思を示して。
「わかりました」
志藤が頷く。すべて思惑どおりと満悦の笑みを浮かべて。
抽送がまた苛烈なものへと戻っていく。女を攻め立てよがり狂わせる腰使いから、遂情を目指したものへと気配を変じて。その変化を感じ取った怜子が高々と歓喜の叫びを張り上げて、
「来て、来てェッ」
あられもない求めの言葉を喚き散らした。娘婿たる男の精を乞いねだって、激しい律動へと迎え腰を合わせ、ぐっと漲りを強めた剛根を疼き悶える媚肉で食い締めるのだった。
「一緒に、ですよ」
ようよう昂ぶりを滲ませ、息を弾ませた声に念を押されれば、ガクガクと首を肯かせながら、
「は、早くぅっ」
切羽詰まった叫びを振り絞った。ギリギリと歯を食いしばって、臨界寸前にまで追い上げられた情感を堪える。男に命じられたから、ではなく、怜子自身の欲求、なんとしてもその瞬間を合致させたいという切実な希求が、僅かな余力を振り絞らせた。その必死の尽力が間断なく洩れ続ける雌叫びを異様なものとした。瀕死の野獣の唸りに、渾身の息みに無様に鳴る鼻音まで加わって。
平素の理知の輝きなど跡形もなく消失した狂態は、それほど長くは続かなかった。遂情を兆しているという志藤の言葉は偽りではなかったのだ。怜子の懸命の努力は報われ、願望は叶えられた。
低く重い呻きと同時に、最奥まで抉りこんだ剛直が脈動する。熱い波濤が胎奥を叩いて、その刹那に怜子が迸らせた咆哮は、やはり野獣じみて獰猛ですらあった。遠吠えのように長く長く尾を引いた。志藤の体にしがみつかせた両腕両脚が筋を浮き立たせて硬直する。
今夜ここまで欲望を抑えてきた志藤の吐精は盛大だった。熱狂的な雌孔の反応がさらにそれを助長した。揉みしぼるような女肉の蠕動を味わえば、志藤もまた“おおっ”と獣声を吐いて肉根を脈動させ、その追撃が怜子にさらなる歓悦の声を上げさせる。そんな連環の中に、こよなき悦楽を共有しあって。
やがて、ようやく欲望を吐き出し終えた志藤が脱力した体を沈ませた。重みを受けた怜子が微かな呻きを吐いて、男の背にまわした腕に一度ギュッと力がこもり、また弛緩していった。両脚も力を失って、ベッドへと滑り下りていった。
汗みどろの裸身を重ね、今度はしばし虚脱と余韻のときを共にして。
「……最高でした」
乱れ散らばったブルネットに顔を埋めたまま志藤が呟いた。率直な実感をこめた声で。
応えはない。
首を起こして見やれば、熱情に火照り淫らな汗に濡れた義母の面は、瞼を閉ざして、形のよい鼻孔と緩んだ唇を荒い呼吸に喘がせている。意識があるのかどうか判然としなかったが。
つと、その眦からこめかみへと、滴が流れた。
口を寄せ、チロリとその涙の粒を舐めとれば、ビクと微かな反応がかえって。
「これまでで、最高でしたね」
「…………」
今度は問いかけにして繰り返せば、うつつないままにコクと肯いた。
そっと唇を重ねる。強引な激しさも悪辣な技巧もない、ただ優しく触れるキスを贈れば、艶やかな唇は柔らかく解けて。
いまだ肉体を繋げたまま、義理の母親と娘婿は、快楽の余韻を引いた吐息を交わし合った
英理の特製ビーフシチューは今日も絶品の出来だった。
形ばかり志藤に付き合うつもりが、口をつければ空腹を刺激されてしまった。
「……こんな時間に食べてしまって」
結局少量とはいえ取り分けたぶんをほぼ食べ切って、日頃の節制を無にする行動だと後悔を呟く。
「いいじゃないですか。たっぷり汗をかいたあとだし」
「…………」
こちらは充分な量をすでに平らげた志藤が、ワインを飲みながら気楽に請け合う。いかにも女の努力を知らぬ男の無責任な言いぐさだったが。
不機嫌に睨みつけた怜子の表情は、志藤の言葉によって呼び起こされた羞恥心の反動だった。
たっぷりと激しく濃密なセックスに耽溺し、汗をしぼり体力を消耗して。そのあとに、空腹を満たすべく食事を(量はどうあれ、濃厚な肉料理を)摂っている。まるで動物の行動ではないか、と。欲求の充足だけを原理とした。
いまは、その爛れた媾いの痕跡を洗い流し、一応の身なりを整えていることが、せめてもの人がましさといえるだろうか。食事の前に再びシャワーを使って、いまはともにバスローブ姿で食卓についていた。
「……英理は主婦として完璧ね」
卓上に視線を落として、怜子はそう云った。美味しい料理は英理が作り置いていったもの。身にまとう清潔で肌触りのいいローブも英理が用意したものだ。
「そうですね」
「あなた、幸運だわ」
「それはもう、重々わかってますよ。いつも英理に言われてますから。こんな出来た嫁を手に入れた幸せを噛みしめろって。才色兼備で家事も万能、その上――」
ニッと、志藤は愉しげな笑みを浮かべて、
「美しくてセクシーな母親まで付いてくるんだから、と」
「…………」
「今夜こうして、その幸運を確認できたわけで。僕は本当に果報者ですよ」
ぬけぬけとそう言い放って満悦の表情を見せる志藤を、怜子はしばし無言で睨んで。ふうっと息を吐いて、感情を静めて、
「……今夜のことは」
軋るような声で言い出した。いま、やや迂遠な切り出しから告げようとしていた言葉を。
「弁解する気もないし、あなたを責める気もないわ。性懲りもなく、また過ちを犯した自分を恥じるだけよ。でも、こんなことは今夜かぎりよ」
「どうしてです? これは英理も望んでることなのに」
だから、別に“不義”を犯しているというわけでもない、と。
「……おかしいわよ、あなたたち」
「そうですかね? まあ、多少特殊な状況だとは思いますけど」
「……もう、いいわ」
嘆息まじりにそう言って、怜子は不毛な議論を打ち切った。
とにかく、告げるべき言葉は告げた、と。今夜の成り行きを、志藤との関係の再開の契機にするつもりなどないということ、志藤と英理の異常な企みに乗る気などないということは。
志藤は軽く首を傾げて、考える素振りを見せたが。その表情は、あまり真剣なものとは見えなかった。怜子を見つめる眼には、面白がるような、呆れるような色があった。
仕方がない、とは納得できてしまった。今夜、自分がさらした醜態を振り返れば。なにを今さら、と嘲られることは。
だが、他にどんな決断のしようがあるというのか? 狂乱のときが過ぎて、理性を取り戻したいまとなっては。
「本当にそれでいいんですか?」
志藤が訊いてくる。優しげな、気遣うような声で。
目顔で問い返しながら、その先の言葉はおよそ察しがついた。
「いえ、久しぶりに怜子社長と肌を合わせて、離れていた間に貴女が抱えこんでいた寂しさを、まざまざ感じとったというつもりになったもので。また明日から、そんな孤独な生活に戻ることを、すんなり受け容れられるのかな、って」
あくまで慇懃な口調で。いかにも言葉を選んだという婉曲な表現で。
「…………」
怜子は無言で侮辱に耐えた。やはり、受け止めるしかない屈辱なのだと言い聞かせて。志藤の挑発を無視することで決意を示そうとした。
志藤は、しばし怜子の表情を観察して、
「……そうですか」
と、嘆息して、
「それが怜子社長の意思なら仕方ないですが。僕としては残念だな。今夜あらためて、カラダの相性の良さを確認できたのに」
「……それが、決まり文句なのね」
怜子は言い返していた。沈黙を貫くはずが。声に冷笑の響きをこめはしたけれど。
かつての関係の中でも、幾度となく聞かされた台詞だった。それも、この男の手管のひとつなのだろうと怜子は理解していた。その圧倒的な牡としての“力”で女を打ち負かしたあとに、僅かばかり自尊心を救済して。そうすることで、よりスムーズに“靡き”へと誘導する。きっと、これまで攻略してきた女には決まって投げかけてきた言葉なのだろうと。
「そんなことはありませんよ。本当に、これほどセックスが合う相手は他にいないと思ってるんです」
「…………」
「だから、今夜かぎりってのは本当に残念ですけど。まあ、仕方ないですね」
そう云って、グラスに残ったワインを飲み干した。その行動と気配に、次の動きを察した怜子が、
「もう終わりにしてちょうだい」
と、先回りに頼んだ。
「もう充分でしょう? 私、疲れきっているのよ」
「まさか。夜はこれからじゃないですか」
あっさりと受け流した志藤が壁の時計を見やる。時刻は0時を三十分ほど過ぎたところ。
まだそんな時間なのか、というのが怜子の実感だった。この数時間のあまりに濃密な経緯に。
「シャワーを浴びてリフレッシュもしたし、お腹を満たしてエネルギーも補充できたでしょう? やっぱり時間の制約がないのはいいですね。こうしてゆっくりと愉しめるのは」
そう言って笑う志藤の逞しい体躯からは、若い雄の獰猛な精気が発散されはじめていて。
「もう無理よ、これ以上は」
その気配に怖気を感じて、怜子は懇願の言葉を続けた。
「本当に、クタクタに疲れ果てているのよ。若いあなたに激しく責められて……何度も……恥ずかしい姿をさらして……」
そう言ってしまってから、こみ上げた悔しさに頬を歪めた。それは自分の無惨な敗北ぶりを認める科白であったから。転々と場所を変えながらの破廉恥な戯れのはて、辿り着いた寝室で立て続けに二度、志藤の欲望を受け止めたという成り行きの中で、その行為の苛烈さだけでなく、それによって味わわされた目眩むような快楽、幾度となく追い上げられた凄絶な絶頂が、心身を消耗させたのだと。
だが表白することで改めて噛みしめた悔しさ惨めさが、何故か怜子を衝き動かして、
「わかってよ、志藤くん。私、若くはないのよ。……英理とは違うのよ」
そんな言葉を吐かせた。わざわざ、英理の名まで持ち出して。
「そんな弱音は怜子社長らしくないですね」
気楽に志藤は云って、
「英理は意外にスタミナがないんですよ。いつも、割と早々に音を上げてしまうんです。比べたら、怜子社長のほうがずっとタフだと思いますよ。相性がいい、セックスが合うというのは、それもあるんですよ」
「……なによ、それは」
それで賞賛のつもりなのか、と。単に、自分のほうが英理より淫乱で貪欲だと云っているだけではないか、と志藤を睨みつける。
つまり、戯言だと撥ねつけられずに、受け取ってしまっているのだった。妻の英理よりも義母である自分とのほうが肉体の相性がいい、などという不埒な娘婿の言葉を。
「御気に障りましたか? 率直な気持ちなんですが」
悪びれもせずに、志藤は、
「それを今夜かぎりと言われれば、名残を惜しまずにはいられませんよ。また後日って約束してもらえるなら、話は違いますけど」
「しつこいわよ。聞き分けなさい」
にべもない答えを返して。そうしながら、腕組みして考えを巡らす様子の志藤を、怜子は見やっていた。
「……やっぱり、なにか気障りなことを言っちゃいましたかね?」
窺うように志藤はそう訊いて、
「“美人の母親が付い��くる”なんて、確かに失礼な言いぐさでしたね。でもそれは、英理らしい尖った言い回しってだけのことですよ。もちろん僕は、怜子社長を英理の余禄だなんて思ってません。思うはずがないじゃないですか」
「……どうでもいいわよ、そんなことは」
深い溜め息とともに。どうしようもなくズレていると呆れ果てて。
だが、まるで見当違いの角度から宥めすかして、かき口説こうと熱をこめる志藤のしつこさを、疎ましいものとは感じなかった。
そも、それはまったく的外れな取り成しだったか? 件の英理の言葉を聞かされたとき、その逸脱ぶりに母親として暗澹たる思いをわかせつつ、女としての憤りを感じたことは事実。たった今の志藤の弁明に、その感情が中和されたことも。
……不穏な心理の流れであることは自覚できた。だから怜子は、
「ねえ、明日には、あの子たちも帰ってくるのよ。英理はともかく、慎一には絶対に気取られるわけにはいかないわ」
あえて、その名前を口に出した。今夜ここまで、考えまい思い浮かべまいとしてきた息子の名を。
遠く離れた場所で、姉弟がどんな時間を過ごしているのかは、今は知りようがない。怜子としては、慎一を連れ出した英理の行動が、ただ自分に対する“罠”を仕掛けるためのものであったことを願うしかなかった。まさか、慎一にすべてを明かすなどと、そこまでの暴挙には出るまい、と祈る思いで。
とにかく、明日――日付としては、もう今日だ――帰宅した慎一に、異変を気づかれることだけは絶対に避けなければならない。たとえ……帰ってきた慎一が、すでに“事実”を知らされていたとしても。いや、そうであれば尚更に、今夜自分が犯した新たな過ちまで知られるわけにはいかない。すべての痕跡を消して、何事もなかった顔で、息子を迎えなければ。これ以上、際限もない志藤の欲望に付き合わされては、それも困難になってしまうだろう。
なんて、ひどい母親か、と深い慙愧の念を噛みしめる。性懲りもなく過ちを繰り返さなければ、こんな姑息な隠蔽に心をくだく必要もなかったのだ。
「ああ、慎一くん。なるほど」
名を出されて、存在を思い出したといったふうに志藤は呟いて、
「確かに、彼には今夜のことは知られたくないですよね。ええ、もちろん僕も協力しますよ」
と、軽く請け負って。
すっと立ち上がった。テーブルを回って怜子の傍らに立つと腕を掴んで強引に引き上げた。
ほとんど、ひと呼吸の間の素早い動きだったが。唐突な行動とは云えまい。先ほどから志藤は、しばしの休息を終えての情事の再開を求めていたのだから。
「放してっ」
振り払おうとする怜子の抗いは、男の腕力を思い知らされただけだった。
「まあまあ。ふたりが帰ってくるにしても、午前中ってことはないでしょう。まだもう少し愉しめますよ」
「ダメよっ」
“もう少し”などという約束を信じて、ここで譲ってしまえば。この獰猛な牡獣は、朝まででも欲望を貪り続けることだろうと正確に見通して。なにより、そんな予見に怯えながら、瞬く間に熱を孕んでいく我が身の反応が怜子には怖ろしかった。腰にまわった強い腕に引き寄せられ、さらに体熱と精気を近く感じれば、熱い痺れが背筋を這い上がってきて。その自らの身中に蠢き出したものに抗うように身もがき続けたのだったが。その必死の抵抗���あしらいながら顔を寄せた志藤が、
「いっそ、英理にも秘密にしましょうか?」
耳元に吹きかけた言葉の意外さに、思わず動きを止めて、その顔を見上げた。志藤はニンマリと愉しげに笑って、
「今夜は、なにも起こらなかった。怜子社長は普段通り帰宅したけれど、僕からのアプローチは断固として撥ねつけられて。その身体には指一本触れることが出来なかったって。明日帰ってきた英理にそう報告するんです」
「…………」
まだ意図が掴めず目顔で問い返す怜子に、志藤はさらに笑みを深め、声をひそめて、
「そうしておいて。僕らは、また秘密の関係を復活させる。どうです?」
「――なに、をっ」
瞬時、率直な驚きを浮かべた貌が、すぐに険しく強張る。睨みつける視線を平然と受け止めた志藤は気障りな笑みを消して、
「怜子社長は考えたことはありませんか? もし、あのとき英理に気づかれなかったら、あんなかたちで英理が介入してこなかったら。いまの僕と貴女の関係はどうなっていたかって」
「…………」
「僕は何度も考えましたよ。考えずにはいられなかったな。だって、本来僕が、なんとしても手に入れたいと望んだ相手は、須崎怜子という女性だったわけですから」
それは、この夜の始まりに口にした言葉に直結する科白だった。一年前の成り行きは、けっして怜子を捨てて英理を選んだということではなかった、という弁明に。静かだが熱のこもった声で、真剣な眼色で。だが繰り返したその表白に、いま志藤がこめる思惑は、
「だから、また貴女とあんな関係に戻れたらって。思わずにはいられないんです」
つまりは、改めて密かな関係を築こうという恥知らずな提案なのだった。怜子が、英理からの“招待”をどうしても受ける気がないというのであれば。その英理を除外して、またふたりだけの関係を作ろうじゃないか、と。
ぬけぬけと言い放った志藤の眼には、身勝手に思い描いた未来への期待の色が浮かぶように見えた。またその口ぶりには、それならば英理の構想する“三つ巴”の生活よりはずっと受け容れやすいだろう、という極めつけが聞き取れた。
「……呆れるわね」
短い沈黙のあとに怜子が吐き捨てた言葉には、しごく真っ当な怒りがこもった。どこまで節操がないのか、と。志藤を睨む眼つきが、さらに強く厳しいものになって。
しかし、その胸には混乱も生じていたのだった。英理への背信というべき提案を持ち出した志藤に。この若い夫婦は、自分を陥れ取り込むために結束していたのではなかったか。
無論、その厚顔な告白を真に受けるなど馬鹿げている、と心中に呟きながら、怜子は志藤へと向けた剣呑な視線の中に、探る意識を忍ばせてしまうのだった。冷淡な義母の反応に微かな落胆の息をついて、
「でも、それが僕の正直な想いなんですがね」
「…………」
尚もそう重ねた娘婿の瞳の奥に、その言葉の裏付けを探そうとしてしまうのだった。
志藤が口を寄せた。ゆっくり近づいてくるその顔を、怜子は睨み続けていた。唇が触れ合う寸前になって顔を横に逃がそうとしたが、意味はなかった。唇が重なりあってから、怜子は瞼を閉じた。
優しく丁重なキスを、ただ怜子は受け止めた。舌の侵入は許しても、自らの舌を応えさせはしなかった。
急にその息を乱させたのは、胸元から突き上げた鋭利な刺激だった。バスローブの下に潜りこんだ志藤の手が、たわわな膨らみを掬うように掴んでジンワリと揉みたてたのだった。
「は、離してっ」
「無理ですよ。もう手が離れません」
身をよじり、嬲りの手をもぎ離そうとする怜子の抵抗など歯牙にもかけずに、志藤が答える。弱い抗いを封じるように、ギュッと強く肉房を揉み潰して、怜子にウッと息を詰めさせると、またやわやわと懇ろな愛撫に切り替えて、
「この極上の揉み心地とも、今夜かぎりでまたお別れだなんて。どうにも惜しいな」
そうひとりごちて、せめてもその極上の感触を味わい尽くそうというように、手指の動きに熱をこめていく。
怜子はもう形ばかりの抵抗も示せずに、乳房への玩弄を受け止めていた。繊細な柔肉の、それにしても性急に過ぎる感応ぶりが抗いの力を奪っていた。瞬く間に体温が上昇して、豊かなブルネットの生え際には、はやジットリと汗が滲みはじめている。豊かな乳房の頂では、まだ直截の嬲りを受けない乳首がぷっくりと尖り立っていた。クタクタに疲れ果てていると、志藤に吐露した弱音は嘘偽りのない実感からのものだったが、疲弊した肉体の、しかしその感覚はひどく鋭敏になっていることを思い知らされた。
そんな我が身の異変に悩乱し、胸乳から伝わる感覚に背筋を痺れさせながらも、怜子は、
「でも、正直自信がないですよ。明日からまたこれまで通りの生活に戻っていけるかは」
半ば独り言のように喋り続ける志藤の声に、耳をそばだてていた。
すでに仕掛けている淫らな接触のとおり、これで解放してくれという怜子の懇請は完全に黙殺していたが。しかし、今夜かぎりにすることは受け容れた言いようになっている。つい先ほどまで“英理に隠れてでも”と関係の継続を迫ってきた位置から、あっさりと引き下がって。その唐突な距離の変化が怜子を戸惑わせ、耳を傾けさせるのだった。なにか……割り切れぬような尾を引いて。
「今夜、あらためて身体の相性のよさも確認できたっていうのに。それを、一夜だけの夢と納得しろだなんて。切ないですよ」
「…………」
志藤も、じっくりと聞き取らせようとするのだろう。乳房への嬲りを緩めた。そうされずとも、思惑は察することが出来たが。しかし口上を制止する言葉が出てこなかった。
身体――セックスの相性のよさ。この不埒な若い男の手に触れられただけで――たった今がそうであるように――情けないほどにたやすく燃え上がり蕩けていった己が肉体。淫猥な攻めの逐一に過剰なほどに感応して、振り絞った悦声、吹きこぼした蜜液。そして……かつてのこの男との記憶さえ凌駕してしまった、凄絶な情交――。
「だって、これからも僕らは、この家で一緒に暮らしていくわけですからね。怜子社長……いや、もう弁えて、お義母さんと呼ぶべきかな。とにかく、貴女の姿がいつもすぐそばにあるわけで。それじゃあ、今夜のことを忘れることなんて、とても」
「…………」
そう、同居生活は続いていく。今夜、なにもなかったと方をつけるなら、同居暮らしも何事もなく続いていくしかない。“ただの”娘婿に戻った志藤は、これまでのように妻である英理との仲睦まじさを見せつけるのだろう。その傍らにいる自分には、あくまで慇懃な態度で接し、“お義母さん”という正しい呼称もすぐに口に馴染ませて……。
「お義母さんが不在のときだって、同じことですよ。リビングのソファに座っていても、シャワーを使っていても、玄関ホールに立って、あの階段を見上げるだけでも、思い出さすにはいられないでしょう」
「……やめて」
やっと振り絞ることが出来た。
転々と、場所を移しながら繰り広げた痴態。我が家のそこかしこに刻んでしまった記憶。それを明日からの生活に引き摺っていかねばならないのは、無論志藤ひとりではない。
数瞬だけ志藤は黙って。そして付け加えた。
「まあ、お義母さんの寝室だけは、僕は二度と立ち入ることはないでしょうけど」
「…………」
そう。その場所は、また怜子だけのスペースになる。何処よりも濃密な記憶が蟠る、あの部屋は。
毎日の終わりに、たとえば湯上りの姿で戯れ合う志藤と英理を階下に残して、或いはすでにふたりが夫婦の寝室に引き上げたあとに。怜子はひとり階段を上り、あの部屋へ、あのベッドへと向かうのだ。
毎晩、ひとりで。
もちろん志藤は自らの嘆きを口にするというふりで、怜子に突きつけているのだった。頑なに拒絶を貫くのであれば、そんな毎日が待っているんですよ、と。
怜子はなにも言えなかった。並べ立てられた状況、情景のすべてが、あまりにも生々しく思い描けてしまって。
「僕にも、怜子社長のような強い意志が持てればいいんですけど。見習うのは難しいですね」
気まぐれにまた呼び方を戻して、やはりそちらのほうがよっぽどマシだと怜子の耳に感じさせながら、志藤は念を押してくる。その意志の強さ、矜持の高さによって、この一年あまりの時間を耐え抜いてきた怜子だが、その“実績”には感服するが。明日からも同じようにそれを続けていくことが本当に出来るのか、と。今夜を越えて、この一夜の記憶を抱えて。
と、志藤は無言で立ち竦む怜子の腰を強く引き寄せた。身体を密着させ、ローブ越しに硬く勃起した感触を押しつけて怜子に息を詰めさせ、乳房を揉み臀を撫でまわしながら、
「やっぱり、考え直してもらえませんか? ふたりだけの関係を再開すること」
未練を露わにした口調でそう問いかけた。またも突然に距離を詰めて。
「ダ、ダメよ」
荒々しい玩弄に身悶えながら、怜子は忽ちに弾む息の下から、
「英理に気づかれるわ」
そう口走って、即座に過ちに気づいた。違う、そうじゃない、と頭を振って、たった今の自分の言葉を打ち消そうとする。
だが志藤は、その怜子の失策に付け入ろうとはせずに、
「……そうですか」
ふうっと嘆息まじりにそう言って、両手の動きを止め、抱擁を緩める。密着していた腰も離れた。
「だったら、未練な気持ちが残らないように、このカラダを味わい尽くさせてもらいますよ」
今度こそ割り切って切り替えたといったような、どこか冷静な響きをたたえた声でそう言った。
「……ぁ…」
そんなふうに言い切られてしまうと、奇妙に切ないような情感が胸にわいて。怜子は無意識に伸ばしかけた手を力なく下へと落とした。
乳房と臀から離れた志藤の手がバスローブの腰紐を解くのを、怜子は沈黙のまま見下ろしていた。次いで、襟にかかった手が、肩を抜いて引き下ろしていくのにも抵抗しなかった。
ローブが床に落ち、熟れた見事な裸身が現れ出る。今度はダイニングを背景に、食卓を傍らに。その状況を意識せずにはいられないのだろう、怜子は羞恥の朱を上らせた顔を俯け肘を抱いて膝を擦り寄せるようにしていたが。その挙措とは裏腹に、爛熟した豊かな肢体は、迫り出すような肉感を見せつける。照明に照らされる白磁の肌には憔悴の陰りは窺えず、むしろ精気に満ちて艶やかな輝きを放つように見えた。
その義母の艶姿へと好色な目を向けながら、志藤は自分も脱いでいった。裸を晒すには、こちらもローブ一枚を取り去ればよかった。深夜の食卓で、そんな姿で義母と娘婿は向き合っていたということだ。
露わになった精悍な裸形へと奪われた視線をすぐに逸らした怜子だったが。すでに半ば以上の力を得た肉根を揺らしながら、志藤が再び腕を伸ばしてくると、
「ここではいやよ」
そう云って、後ずさった。もはや解放を願おうとはしなかったが、これ以上こんな場所で痴態を演じるのは嫌だと。
「じゃあ、部屋へと戻りますか」
あっさりと聞き入れて、さあ、と怜子を促しながら、志藤は唯一足元に残ったスリッパを脱ぎ捨てる。怜子も、裸にそれだけを履いた姿の滑稽さに気づいて、そっとスリッパから抜いた素足で床を踏んで。促されるまま踵をかえし歩き出して。ダイニングから廊下へと出かかったところで歩みを止め振りかえると、僅かな逡巡のあとに、
「……今夜だけ、よ…」
結局その言葉を口にした。まるでひとつ覚えだと自嘲しながら、あえてその台詞を繰り返したのは、志藤より自分自身に言い聞かせようとする心理だったかもしれない。その一線だけは譲ってはならないと。
それとも……まさか“今夜だけ”なのだからと、朝までの残された時間の中で自らのあさましい欲望を解放しきるための口実、免罪符として、という意識が働いたのか。
そんなはずはない、と打ち消すことは、いまの怜子には出来なかった。己が肉体に背かれるといったかたちで、無様な敗北を重ねた今夜のなりゆきのあとでは。
或いは――と、怜子は思索を進めてしまうのだった。自分の中の暗みを、奈落の底を覗きこんで。この期におよんでも自分からは放棄できないその防衛線を、圧倒的な牡の“力”で粉砕されることこそを、実は自分は望んでいるのではないか、と。
どうあれ、志藤には失笑されるだろうと思っていた。だが違った。志藤はじっと怜子の目の奥を見つめて、
「ええ」
と簡潔に頷いたのだった。その口許に、不敵な笑みを浮かべて。
眼を合わせていられずに、怜子は顔を戻した。己が鼓動を鮮明に感じた。
廊下に出る。再び怜子は、そこを裸の姿で往くのだ。二階の自室へと向かって。一度目と違ったのは、志藤がぴったりと隣りに寄り添ってきたことだった。横抱きに義母の腰を抱いて。歩きながら、その手が腰や臀を撫でまわしてくるのにも怜子は何も言わず、させておいた。すると志藤は、怜子の片手をとって、ブラブラといかにも歩くには邪魔くさそうに揺れている股間の逸物へと誘導した。怜子は抗わなかった。視線も前に向けたままだったが、軽く握るかたちになった己が手の中で、男の肉体がムクムクと漲りと硬さを増していくのは感じ取っていた。ほんの一、二時間前の二度の吐精など、この若い牡の活力には少しも影響していないことを確認させられて、忍びやかな息を鼻から逃がす。撫でまわされる臀肌がジワリと熱くなる。
かつての関係においての逢瀬は、裏通りのラブホテルの“ご休憩”を利用した、時間的に忙しないものだった、いつも。だから、この先は怜子にとって未知の領域だ。今から朝が来るまでの長い時間、若い英理でさえ音を上げ半ばでリタイアしてしまうという志藤の強壮ぶりに自分はつき合わされて、その“本領”を骨の髄まで思い知らされることになるのだ。中年女である自分には、到底最後までは耐え切れぬだろうが。それとも……英理よりもタフだろう、という志藤の無礼な見立てが、正しかったと証明してしまうことになるのだろうか?
胡乱な想念を巡らせているうちに、玄関ホールを通りすぎ階段に辿り着いた。腕を離した志藤が、先に上るように促す。確かに、ふたり並んで上るには窮屈ではあったが。
前回と同様に背後を気にしながら上りはじめた怜子の悩ましい巨臀の揺れ弾みを、今度はより近い距離から見上げていた志藤だったが、
「ああっ!?」
「堪りませんよ、このセクシーなヒップの眺め」
階段の途中で、やおらその揺れる双臀を両手で鷲掴んで怜子を引き止めると、滾った声でそう云って、スリスリと臀丘に頬を擦りつけた。
「な、なにっ!? いやっ、やめなさい……ヒイッ」
前のめりに態勢を崩して、上段のステップにつかまりながら、後ろへと首をねじった怜子が困惑した叫びを上げる。唐突な、志藤らしくもないといえる狂奔ぶりに驚きながらの制止の言葉が半ばで裏返った声に変わったのは、深い臀裂に鼻面を差しこんだ志藤が、ジュルッと卑猥な音を鳴らして秘芯を吸いたてたからだった。
「アッ、ヒッ、い、いやよ、やめてっ」
「怜子社長がいけないんですよ、あんなに悩ましくおしりを振って、僕を誘うから」
双臀のはざまから顔を上げ、かわりに揃えた二指を怜子の秘肉へと挿し入れながら、志藤が云った。
「ふ、ふざけないで、アアッ、イヤァッ」
「ふざけてなんていませんよ。ホラ、こんなにここを濡らして。この甘い蜜の匂いが僕を誘惑したんです」
そう言って、実証するように挿しこんだ指先をまわして、グチャグチャと音を立てる。
「ああ、いやぁ、こ、こんな場所で」
段差に乳房を圧し潰した態勢で、上段のステップにしがみついて、なんとか狼藉から逃れようとする怜子だったが。その身ごなしはまったく鈍重だった。掻きまわされ擦り立てられる媚肉から衝き上がる快美と、耳に届く淫猥な濡れ音が煽りたてる羞恥が、身体から力を奪うのだった。すでにそんなにも濡らしていたのだと、ダイニングでの手荒い玩弄も、また素っ裸でここまで歩かされたことも、自分の肉体が昂奮の材料として受け容れていたのだと暴き立てられることが。
やがて、秘肉を嬲る指の攻めが知悉した泣きどころに集中しはじめれば、怜子はもう形ばかりの逃避の動きさえ放棄して、ヒイヒイとヨガリの啼きに喉を震わせていた。ただ怜子は途中から、唇を噛んで声が高く跳ね上がるのを堪えようとした。こんな開けっ広げな場所で、という意識が手放しに嬌声を響かせることをはばからせたのだった。家内にはふたりだけという状況において無意味な抑制ではあったのだが、惑乱する心理がそうさせた。だがその虚しい努力によってくぐもった啼泣は、逆に淫らがましい響きを帯びて、妖しい雰囲気を演出していた。そして、悦声を堪える代わりといったように、裸身ののたうちは激しくなっていく。捧げるように高くもたげた巨臀を淫らに振りたくり、抉りたてる指のまわりに粘っこく回し、ボタボタと随喜の蜜汁をステップに垂れ零して。重たく垂れ落ちて揺れる乳房、時折段差に擦れる乳首から伝わる疼痛が、状況の破廉恥さを思い出させても、もうそれが燃え上がる淫情に水を差しはしなかった。裸で階段にへばりつき、むっくりと掲げた臀の割れ目から挿しこまれた男の手に秘裂を嬲られ淫らな蜜液をしぶかせている、といまの自分の狂態を認識することで、昂奮と快感はどこまでも高まっていくのだった。
だから、
「……ああ、部屋で、部屋に…」
嫋々たる快美の啼きにまじえて怜子が洩らしたその言葉には、さほどの切実さもこもらず。せいぜいが、はや迫りきた絶息の予感によって掻き起こされた理性の燃え滓の表出、といった程度のものだった。実情とすれば、怜子はもうこのままこの場でアクメの恥態を晒すことも――それを指ではなく、志藤の魁偉な肉体によって与えられることさえ、受け容れる状態に追いこまれていたのだったが。しかし、
「……そうですね」
ほとんどうわ言のような怜子のその言葉を、待っていたというように志藤はそう応じて。そして、彼女の中に挿しこんでいた指をスルリと引き抜いてしまったのだった。
ああ!? と驚愕の声を発して振り返った怜子に、照れたような顔を向けて、
「つい、ガキみたいに血気に逸ってしまいました。すみません」
そう謝ると、上げた足を突っ伏した怜子の体の横に突いて、そのままトントンと段飛ばしに、身軽に怜子の傍らをすり抜けて階段を上がった。
忙しく首をまわして怜子が見上げた先、数段上で振り向いて、
「さあ、早く部屋へ行きましょう。僕はもう待ち切れないんですよ」
朗らかにそう言って、とっとと階段を上っていく。怜子を助け起こしもせずに。こちらは硬く引き締まった尻を怜子に向けて。
「……あぁ……待って……」
呆然と虚脱した表情のまま、怜子は弱い声を洩らして。ようやくノロノロと動きはじめる。両手を突いたまま、這うようにして階段を上っていく。前腕や脛には赤くステップの跡がついて、逆に臀を掲げていたあたりのステップには転々と滴りの痕跡が残っていた。
また玩ばれたのだ、とは無論ただちに理解して。しかし今は怒りもわいてこなかった。怜子の感覚を占めるのは、燠火を掻き立てられて放り出された肉体の重ったるい熱さだけだった。意識には、仰ぎ見る視点のゆえに殊更に逞しく眼に映った志藤の裸身だけがあった。力の入らぬ足腰を踏ん張り態勢を起こしても、片手はステップに突いたまま、危うい足取りで上っていく。志藤のあとを追って。
志藤は待たない。速やかに階段を上りきると通路を進んで、最後に一度振り向き、クイクイと手招きしてみせて。そのまま部屋の中へと入っていった。
ようよう二階まで上がった怜子が、���け放たれたドアを目指し、のめるような足取りで進んでいく。追いたてられるのではなく追いかけて、自分の寝室へと向かっていく。
白く豊艶な裸身が室内へと消えていき、その勢いのままに引かれたドアがバタンと不作法な音を立てて閉ざされた。その場は、束の間、深更の静かさを取り戻した。閉ざされたドアの向こうから、艶めいた音声が洩れ聴こえはじめるまでの僅かな間――。
4 notes
·
View notes
Link
大虐殺の爪痕は残り、100万人のウイグル人が消えた…民族浄化の最終段階に入った東トルキスタン。習近平が進める「文革2期」は、最先端技術が管理・支配する反理想郷を生み出した。
2000人が殺傷され、1万人以上の行方不明者を出したウルムチ大虐殺から9年。今年も7月5日に世界各国でジェノサイドを実行した中共への抗議活動が行われた。
多くの亡命ウイグル人が暮らすトルコの最大都市イスタンブールを始め、ブリュッセル、パリ、キャンベラ。そして我が国では5日に前後して新宿と六本木の都内2箇所でデモ行進が相次いだ。
▽豪・キャンベラの抗議活動7月5日(WUC)
「中華人民共和国は、やがては滅びる世界最悪の帝国主義国家です。今の21世紀にも18・19世紀のような植民地主義を公然と実行しているのは、この中華人民共和国だけです」
7月7日の六本木デモでは出発前の集会で、国際政治学者の藤井厳喜氏が、そう訴えかけた。ウイグル問題の核心を突いた発言。遠い未来であっても、中共の衰亡はソ連と同じく歴史の必然と説く。
��出発前にスピーチする藤井厳喜氏7月7日(撮影筆者)
「アジアの癌である中国共産党の政権から自由を勝ち獲るまで、私達が頑張って行くしかない」
拓大のペマ・ギャルポ教授は、1日の新宿デモに駆け付け、檄を飛ばした。塗炭の苦しみに喘ぐチベットと東トルキスタン。尖閣を巡り、中共の侵略は我が国にとっても遠い国の悲劇ではなくなっている。
▽集会で挨拶するペマ・ギャルポ教授7月1日(YouTube)
我が国での東トルキスタン支援は、ウルムチ大虐殺の直後、欧米各国に先駆けて活発化した。既に10年近い実績になるが、今年の9周年デモは大きく様変わりした。
我が国に居住する大勢のウイグル人が集まったのだ。新宿デモでは、100人に迫る人数に上ったという。初めて参加したウイグル人男性は、こう理由を語る。
▽新宿デモに参加したウイグル男性7月1日(ch桜)
「今、ウイグルが置かれている状況は、死ぬか生きるかしか選択の道がない。中国の弾圧が耐えられない所まで来たので、これからはもっと増えるのではないか」
ウイグル人をめぐる状況は、この1年で急激に悪化した。9年前のジェノサイドも、その後の大量拘束事件すらも「最悪の事態」ではなかったのだ。
【海外にも弾圧の恐怖が忍び寄る】
日本ウイグル連盟のトゥール・ムハメット会長がスピーチを始めて間もなくの出来事だった。デモ出発地点の六本木・三河台公園に数人の屈強な男が乱入。隠し持っていた横断幕を広げた。
突然、集会場に現れた妨害者。警備の警察官が速やかに排除し、大きな混乱には至らなかったものの、演説は一時的に罵声で掻き消された。中共による海外監視網の広がりを感じさせる実力行使である。
▽六本木デモに現れた中共の駄犬7月7日(撮影筆者)
乱入者のうち2人は典型的な漢族の人相だったが、「地獄に堕ちろ」などと意味不明の言葉を叫んでいた男は発音から日本人の可能性が高い。不逞支那人だけがウイグルの敵ではないのだ。
大規模な7月1日の新宿デモに中共指導部が危機感を募らせたのか、在日工作機関が独自に動いたのか、詳細は判らない。だが、在外ウイグル人を標的にした弾圧は確実に強化されている。
昨年7月、エジプト在住のウイグル人留学生ら60人以上が一斉拘束され、強制送還される事件が起きた。中共の指示を受け、エジプト政府が不当な摘発に乗り出したのだ。
タイやカンボジアに続き、中共指導部の在外ウイグル人狩り指令は、イスラム諸国にまで及び始めた。正に査証なき惑星。そして、我が国で暮らすウイグル人にも魔の手は延びている。
▽六本木のデモ行進7月7日(撮影筆者)
日本ウイグル連盟によると、大手企業に勤務するウイグル人ら少なくとも10人が一時帰国した後、戻れなくなっているという。ムハメット会長は、こう事態の深刻さを語る。
「自由な海外生活をしていれば、独立運動や政府による民族弾圧の情報にも触れやすいので海外に居る全てのウイグル人が疑われている」
▽出前に挨拶するムハメット会長7月7日
ウイグル人という理由だけで監視・摘発の対象となる…地球規模の民族弾圧。日本政府が真剣に身の安全を守るべき在日外国人は、政治力を持った反日朝鮮人等ではなく、こうした普通の人々である。
各国で抗議活動に参加するウイグル人は、マスク姿がデフォルトになりつつある。これは、本人が自らの安全をはかる為だけの措置ではない。抗議に参加したことを理由に祖国の家族が危険に晒されるのだ。
▽EU本部前で呼び掛けるウイグル人3月(AFP)
「私の親戚3名が収容所に送られています」
新宿デモを終え、インタビューに応じた男性は、力無い声で、そう話した。意を決して抗議に参加したウイグル人の中には、既に家族や親族が中共当局に捕らわれた者も少なくないのではないか…
祖国・東トルキスタンでは、海外の熱心な支援者ですら想像し得なかった凄惨な事態が進行している。
【絶望収容所に消えた100万人】
「100万人のウイグル人を収容所から解放しろ」
これまでになかったシュプレヒコールが副都心に響いた。100万人という膨大な数のウイグル人が強制収容所に押し込められ、殆どが無事の帰還を果たせずにいるのだ。
▽新宿デモ先導するイリハム氏7月1日(撮影:真さん)
収容施設の急増と次々に消えるウイグル人の存在は、エジプト送還事件後に浮かび上がった。最初に告発したのは、米政府系メディアRFA(ラジオ・フリー・アジア)だ。
「帰国しなければ、代わりに母親が『再教育』を受ける」
RFAの記者は、そんな脅迫めいたメッセージがSNS経由で各国のウイグル人に相次いで届いている事実をキャッチした。再教育とは何か…中には「収容所」という単語が記されたケースもあった。
▽EU本部前で訴える亡命ウイグル人7月5日(WUC)
現地からの断片的な情報を慎重に照合した結果、中共当局が東トルキスタン全域に強制収容所を新設している実態が判明。それらは表向き「技術研修センター」「再教育センター」を名乗っていた。
そして今年初め、亡命ウイグル人が運営するイスタンブールのネットメディアが流出した公的資料などを根拠に拘束者数を約90万人と推計。人数は今も増え続け、120万人に達するとの見方も出ている。
▽収容所と見られる施設の開所式(RNS)
「当局は何も教えてくれない。家族は愛国者になる為の訓練を終えたら戻って来ると言うだけだ」
大規模な強制収容所送りの実態は、ウイグル人の妻を持つ外国人ルートからも浮き彫りになった。東トルキスタンに暮らす家族と連絡が取れなくなった者が相次いだのだ。
また著名なウイグル人サッカー選手や民謡歌手、慈善活動家らが消息を絶ち、今年2月には聖典の翻訳者として知られるイスラム学者の獄中死が判明。亡命ウイグル人社会に大きな衝撃を与えた。
▽拘束40日後に獄死したサリヒ師(RFA)
更に今年7月、世界ウイグル会議のドルクン・エイサ総裁の母親が強制収容所に送られら末、帰らぬ人となったことが明らかになる。10代から高齢者まで問答無用で押し込まれる絶望収容所だ。
獄中でどのような拷問が行われているのか、詳らかではない。生還者が限られ、全体像を把握することは困難を極める。若い収容者の場合は無言の帰宅すら叶わず、臓器狩りの可能性も指摘される。
【文革の第2期が始まった】
RFAの後塵を拝する形で、欧米の通信社も僅かながら報じ始めた。ただし中共当局の受け売りに近い「再教育キャンプ」という紹介は論外。「政治犯収容施設」というネーミングも不適切だ。
連行対象者はテロリストやその予備軍ではない。海外に親族が居るなど「自由な情報」に触れることが可能なウイグル人がメーンと見られる。政治犯とは程遠い一般の東トルキスタン国民である。
▽カシュガルのモスク前行進する公安’17年(AFP)
海外に亡命したり、難民として暮らすウイグル人は多い。しかし、中央アジア諸国への出稼ぎが厳しく制限されて以降、国外の安全圏に逃れる者は激減した。その中で、100万人超という人数は多過ぎる。
子供にムスリムの伝統名を付けたことで収容所送りになった夫婦もいる。長い髭やベールの着用禁止、未成年のモスク礼拝制限。個人の信仰に起因して連行されるケースも多いだろう。
▽中共スローガン掲げたモスク’17年(RFA)
こうした宗教規制だけでも許されざる弾圧だが、更に恐ろしい「思想改造」が全域で進んでいる疑いも濃い。愛国教育というレベルではなく、共産党崇拝の強制である。
中共が死の収容所に掲げる「再教育」がキーワードだ。東トルキスタン各地では、共産党に忠誠を誓う地域集会が活発に開かれ、子供を含む集落の人々が出席を強要されている。
▽各地で催される党マンセー集会(file)
AFP通信によると、中共当局が“規律違反”と決め付けた行為・風習は約100項目。「工作組」と呼ばれる私兵集団が、党の目や耳となって摘発に勤しみ、住民が丸ごと消え去った村もあるという。
参照:AFP5月15日「不穏分子」を毎日訪問、中国・新疆ウイグル自治区でさらなる弾圧』
▽騒動の現場を捉えた流出写真’17年1月(RFA)
東トルキスタン国内で撮影されたトラブル現場の写真。黒い制服に赤い腕章を付けた漢族は何者なのか。「工作組」とは断定できないが、武警や特警または公安とも違う。まるで紅衛兵ではないか。
同様の弾圧に苦しむチベットでは、当局による僧院の破壊や乗っ取りを「プチ文革」と呼んで蔑む。だが、東トルキスタンの実情を垣間見ると、現地で進行しているのは本格的な文革の続きだ。
【光彩を奪われたウイグル人】
かつての文革は、沿岸部や漢族地域とは比較にならない大きな傷跡をチベットなどの植民地に残した。末期の頃、半ば制御不能になった紅衛兵の武闘派を送り込み、好き勝手に暴れさせたのである。
それから約40年、21世紀の文革2期は、暴漢が直接手を下す分かり易いバイオレンスよりも、陰湿で凄惨だ。最新のIT機器を用いて特定の民族を徹底管理・監視し、見えない鉄条網で取り囲む。
▽共産党旗を担いで歩くウイグル人'17年(CNN)
中共当局はウイグル人が持つ全てのスマホに対し、「百姓安全」というアプリのインストールを義務付けた。スマホの中身を盗み見て、行動を監視するスパイウェアだ。
公安や特警が街中で抜き打ち検問を行い、アプリのインストを確認。手持ちのガジェットに接続し、内部をチェックする。特定の単語などが検出された瞬間、連行される。
▽カシュガル市内の検問所’17年11月(AP)
雑用係の公安が特殊なガジェットを携帯しているのか…現地からの情報も一部の報道も、疑問符を付けざるを得ない。だが、英BBCのウルムチ潜入取材で、実在することが判明した。
▽特殊機器で��マホを検査する公安(BBC)
検問所ではなく施設の中だが、黄色い服装の公安が問題のガジェットを手にしている。摘発対象になるのは、宗教的なコンテンツだけではないだろう。
またスパイアプリには、特定の人物が自宅から300m離れた際、感知して追跡するシステムも組み込まれているという。追尾して行き先を特定するのが、街中に大量設置された監視カメラだ。
▽カシュガル中心部にある監視カメラ群(RFA)
拙ブログがウルムチ市内に増殖する監視カメラに言及したのは、8年前のことだ。以降、カメラは指数関数的に増え、都市部の裏通りや貧しい住宅街から、鄙びた集落にまで進出している。
参照:H22年7月7日『消えた1万人のウイグル人…民兵が徘徊する絶望都市』
過去に類例のないハイテク監視社会。例えスマホを持たなくとも、顔認証技術で特定個人の行動は記録される。そして今や当局がデータ化し、把握しているのは、全ウイグル人の「顔」だけではない。
▽侵略国の旗に覆われた裏路地’17年(RFA)
昨年末、中共当局は東トルキスタン全域で、強制的な“健康診断”を実施。ウイグル人口の9割が受診を強いられ、指紋や血液から光彩に至る生体データを採取された。
なぜ幼い子の光彩までデータ化し、党が管理する必要があるのか? 既に常人には理解も想像も及ばない領域。何か、暗黒を極める壮大な実験が着々と進んでいるようにも見える。
▽五星紅旗を振るウイグルの子供’17年11月(AP)
人口の1割以上が絶望収容所に送られ、外の居住区も監獄化。DNAサンプルも光彩も奪われた。大規模弾圧、民族浄化、恐怖政治…ありきたりの表現では、現状を正確に伝達できない。
中央アジアの片隅に誕生したのは、独裁政党が特定の民族全員をハイテク管理・支配するディストピアだ。
〆
最後まで読んで頂き有り難うございます
クリック1つが敵に浴びせる銃弾1発となります
↓
参考動画:
□YouTube『【総集編】2018.7.1【フリーウイグル!中国政府の人権弾圧糾弾デモ】日本ウイグル協会@新宿駅周辺』
□YouTube『2018年7月7日ウルムチ虐殺9周年記念デモ出発前の集会』
□BBC2月1日『「いっそ妻と母を撃ち殺してくれ」亡命ウィグル男性』
□YouTubeチャンネル桜7月8日『【ウイグルの声#14】もう耐えられない…在日ウイグル人が100万人強制収容にNO!』
参考記事:
□ZAKZAK7月6日『【有本香の以毒制毒】77歳の老母を収容所送りにする中国と「友好」か 世界ウイグル会議・ドルクン氏の「悲しみと苦闘知ってほしい」』
□ニューズウィーク6月15日『サッカー選手もアイドルも ウイグル絶望収容所行きになった著名人たち』
□AFP5月15日「不穏分子」を毎日訪問、中国・新疆ウイグル自治区でさらなる弾圧』
□ニューズウィーク5月18日『イスラム教徒に豚とアルコールを強要する中国・ウイグル「絶望」収容所』
□産経新聞4月26日『中国の人権弾圧を非難「他の民族を同じ目に遭わせたくない」世界ウイグル会議総裁』
□ニューズウィーク3月13日『ウイグル絶望収容所の収監者数は89万人以上』
□ニューズウィーク2月16日『ウイグル「絶望」収容所──中国共産党のウイグル人大量収監が始まった』
□ロイター5月14日『コラム:中国ウイグル族を苦しめる現代版「悪夢の監視社会」』
□AFP2月28日『ビッグデータで「危険人物」特定、中国・ウイグル自治区 人権団体が指摘』
□ニューズウィーク2017年7月26日『中国、ウイグル族にスパイウエアのインストールを強制』
□大紀元2017年12月15日『中国当局、新疆で1900万人のDNA採集 「無料の全民検診」実施』
□大紀元2017年11月1日『中国公安部、声紋バンクを設立 音声通話も監視か』
6 notes
·
View notes
Text

2021/12/26
今日はコスメの断捨離しました。主にリップ類。↑が捨てた物。結構たくさんあるわ。リップ好きなのにコロナで全然消費できなかった…なのに劣化して臭くなるし。
空っぽor劣化シリーズ



目薬は空っぽなのになぜか捨てずに取っておいたやつw
カスッカスなCHANELのリップグロス(しかも異臭がする)。Jillのグロスも変色&異臭残りも少ない。catriceのリキッドシャドウもカスッカスだしリキッドなので明らかにやばい。紫のグロスも一見普通に残っているように見えるが、カスッカスでチップに乗らない。ちなみにJillのチャームは外してプリンセスセレニティのがま口ポーチに付けました。↓6月の誕生石のムーンストーンがセレニティのイメージぴったりだわ。ちなみに白いファーのポンポンはArianaの香水からのチャーム。元々付いてたのは銀水晶のチャームだけでした。

日本で買ったマスカラシリーズ。今髪色暗いから(毛先のみブリーチ)眉マスカラいらないしとにかく古すぎて使える気がしない。ドーリーウインクのはパケ可愛いから置いといただけwでも明らかいらんよな。
色みが好きじゃないものシリーズ




Winnersでつい衝動買いしてしまったものがほとんど。
Too facedのラテックスリップの質感が嫌い。すんげーべたべた。マスクしてるときにつけれた代物ではない。wetnwildのはメタリックカラーの黒に近いブラウン系の発色��んだけどもハロウィンぐらいにしかつかえないwハロウィンには黒リップを別に買えば良いと思っています。
色付きリップクリームたち。リップクリームだけど保湿性がクソ。LOLのリップクリームに至っては水色が唇に乗るので血色も悪くなるし。ポルジョ風のパケのはダイソーで買った物なので別に躊躇せず捨てれる。色味は好きだったけど、保湿具合は良くないので…plumpグロスはスースーして気持ちよくてお気に入りったけど、白みピンクのラメがすごく似合わないし、液漏れがひどくてリップクリームがわりにも使えないので。
MANNA KADERのリップはMLBBって感じの色合いだけども、これをつけても気分は上がらない。実際コロナ前も全然使ってなかったしな。これを豆に塗り直すぐらいだったら、もうマットな赤リップを軽めにつけて、元々唇が赤い人っぽく見せた方が盛れる。
ティント類。基本的に色味がダメダメです。マットリップの方がよっぽど良い。マリリンモンローのやつは真っ赤な方は気に入りってるので残しますがピンクは微妙。韓国コスメのティントはオレンジピンクって感じであんまり好きな色味ではない。essenceのクリアの方はティントじゃないのか?っていうくらい発色しないし、かといって保湿力があるわけでもない。ラメも付かない。色づくわけでもなく保湿するわけでもない謎の棒を塗ってる気分になるので処分。ピンクの方が良いけども、すぐ落ちる。
残しておくもの

左から。マリリンモンローのリップクリーム(ほんのり色付き&ラメ付き)は最近買った物だからとりあえず残しておきます。まあ一年後には処分の対象になるだろうけども。
マリリンモンローの真っ赤なティントは塗りたては濡れたような真っ赤なんだけども、乾いてくると濃いピンクになる。右端のCHANELのグロスと口紅のように。だからこれを家で使って、そのシャネルをお直し&保湿用として持ち歩こうかな?って感じです。
中央のtoofaced、catrice、udのラメグロスはほとんど発色しないけども、保湿力があるのでリップ下地or保湿に使えると思って。udは大好きなスースーするタイプなので。
とりあえず来年はこの辺のリップを使いきって行こうと思います。それまで新しいリップ買わないことを目標にします。ほんまはアイシャドウの整理もしたほうが良いんだろうけど、アイシャドウは粉物で基本あんまり劣化しないし、もし劣化でのアレルギー反応でたら捨てようって思ってるから、まあ気長に使っていこうと思う。アイシャドウも来年は買わないようにしよう…とにかくコスメの情報とか見ないようにしなきゃなあ。マスカラとルーセントパウダーぐらいは買っても良いことにして。来年はスキンケアやダイエットに力をいれようかな。
https://ameblo.jp/okou8888/theme-10108727123.html
たまたま見つけた記事だけども、この人はコスメを少しでも意識して使い切るように一週間同じメイク用品を使うという一週間チャレンジっていうのをやっているみたい。まあ私はファンデとか全く持ってなくて、toofacedのコンシーラーくらいしか持ってない(もう古すぎるしシミのカバーするにも厚塗りになりすぎるから、代替品が買えたら処分しようかと思ってる)から関係ないんだけども、チークとかアイシャドウパレットとかリップとかは一週間同じものを使うように意識するっていうのはアリかなと思った。
チークは何気に4個も持ってる。CHANELの定番のチーク(ピンクオレンジ系)、同じくCHANELのチーク&リップ(コーラルピンク系)、セーラーマーズのリップ&チーク(赤)、essenceのパックマンコラボの4色チーク(ブラウン、オレンジ、コーラル、青みピンク)リップ&チークはブラシなしで指でぼかせばいいから好き。旅行用に使おうかなって感じ。やっぱ普段は粉物チークのCHANELとパックマンを交互に使うのがいいかも。
あとアイシャドウパレットはnyxのPhoenix(赤系)、ccolorのGolden palette(ブラウンゴールド系緑系)、essenceのパックマンコラボ(定番の赤茶系)、hottopic(ヌードカラー系)、ANNA SUI(ベージュ×ブラウン×ターコイズ)、Jill Stuartの2017年限定パレット(白×ショッキングピンク×ブラウン系+グリッター)、w7(ブリックカラー系)という感じでどれも多少の捨て色はあるけど充分使えるからなあ。
チークとアイシャドウパレットとリップを週の初めにあみだくじで決めて、それを一週間どうにか使う(アイシャドウパレットは単色アイシャドウの併用可能)というルールでやってみようかな。リップは一週間固定で。
昨日クリスマスにもらったピアス(太め)をつけるために、年末まで太めのピアス付けっぱなしにしとこう。軽く拡張。右が完全に縮んでる感じだから、とりあえず普通のピアス(でも少し太め)を付けっぱなしにしてる。海外のピアスって基本的に太いんだってね。ぐぐるとエルメスやティファニーなどの高級価格帯のものでも太めで1mmぐらいあるらしい。日本の市販のピアスは0.7〜0.8とからしいからどれだけ太いかって話。ホールをプチ拡張しないと入らんわ。
なんか昔男友達がやたらとピアスのゲージ数を気にしていたけども、普通の人は自分のピアスのゲージ数がどのくらいか具体的に知らんよな。ボディピアスならその知識があるのもわかるけどさ。普通に耳たぶに開けてるような人は市販のピアスが入ればどうでもいいもんな。その友達はイキリたいのか拡張希望だったみたいだけども、結局社会人になってピアスをほとんどしなくいから閉じてきちゃってるみたい。あれから10年だもんなあ。そりゃイキリの二十歳の男の子もさすがに大人になるわ。私も右のピアスホールがあんまり綺麗に空いてないからいっそのこと閉じたほうがええんかも。それか少し拡張した方が誤魔化せるんかな?女性は一粒ピアスしてても何にも言われないけども、男はいろいろ言われるよな。むしろ女性はピアスもマナーのような感じ。結婚式ではピアスかイヤリングつけるし、お葬式でもシンプルなパールのピアスなら付けても良いというかパールのネックレスかピアスをつける方がむしろマナー的には正解らしい。まあ女性は化粧がマナーみたいなもんだから、ピアスもその一つなのかもね。海外ではピアスはまだ幼い女児が開けてるし、まあピアスってよっぽどでかいジャラジャラしたモチーフでもないと邪魔にならないアクセサリーだもんな。私もピアスのそこが好き。つけっぱなしにしなきゃいけないなら、ネックレスは寝るときには首閉まりそうで怖いし、指輪もごくシンプルなものでないと邪魔だし、腕輪やアンクレットはいくら可愛くてみ邪魔だし。大河ドラマに出るとかいうわけでもない一般人だと、ピアス空いてる方がなんだかんだで便利だわ。イヤリング可愛いのもいっぱいあるけども、イヤリングほんまにすぐ落として無くすからなあ。ピアスも時々無くすけど、そもそも落としにくいからなくなりにくいんだよな。
0 notes
Photo

【甘い物も食べてます】 こんまりコンサルタント @miki.konmari さんに、誕生日LINEチケット頂いてて、 チャイラテにしました❣️ ありがとうございます😊 みきさんの ヨガ週1レッスン参加してます。 clubhouseでこんまり流片付けをテーマを軸に、アラフォー(私アラフィフ誕生日)���女性の興味ある雑談も交えつつお話ししてます。 水曜日夜22:30からです。 mikiさんのアドバイスで、 巻き型対応ストレッチと筋トレを取り入れました。 巻き型猫背なんですよねー私。 姿勢も直して代謝上げていきまーす。 糖質制限もゆるーくしてる方向けにハーブテント養生はオススメです。 肥満度2まで行ったのです(T . T)3月に…健康に良いからと腸内環境に良い発酵食品の取りすぎでした… 4月から酢の物系の血液サラサラ食材、高タンパク低GI値意識してる程度です。 ⭐️私の半年10キロダイエット作戦成功の秘訣の考察。 固太りの筋肉緩める (ハーブテント) 腸内環境内臓の炎症を抑えるとタイハーブ魔女のティウ先生に言われたのと、エビデンスもある、モリンガパウダーを2ヶ月目終わりくらいから浮腫改善を感じました。 食生活は、水キムチベースのお野菜とゆで卵、納豆、豆腐とかに炭水化物を半分くらいかな。 パンはやめましたよー。 1〜3月で太った原因はどー考えても糖質過多な発酵食品のわたしのとりすぎ(笑)また年齢も重ねて代謝悪し。 血液サラサラ系の、酢の物発酵食品、水キムチ、酢キャベツ、酢玉ねぎ、薬草料理多用❣️採用…薬味ですね!薬味ダイエットに近いかな! スイーツ投稿なのに減量話でした。 身体が軽くなって楽しみです! 停滞してる減量作戦。 突破作戦を今月から変えました〜。 冬には冬養生に変更しまーす(笑) 興味ある方は @薬草てらこや Facebook秘密のグループに招待しますのでDMくださいねー♪ #薬草料理 #薬草 #薬草紅茶 #タイハーブ #ハーブティ講座 #2拠点生活 #自然農 #更年期 #PMS #温活 #アラフィフ #野間大池 #オンラインサロン #ユーファイ #発酵よもぎ蒸し #ハーブテント #ハーブボール講座 #ハーブ講師 #ハーブ #薬草てらこや #薬草講座 #タイハーブ #モリンガ #健康 https://www.instagram.com/p/CWfhV_5vmmv/?utm_medium=tumblr
#薬草料理#薬草#薬草紅茶#タイハーブ#ハーブティ講座#2拠点生活#自然農#更年期#pms#温活#アラフィフ#野間大池#オンラインサロン#ユーファイ#発酵よもぎ蒸し#ハーブテント#ハーブボール講座#ハーブ講師#ハーブ#薬草てらこや#薬草講座#モリンガ#健康
1 note
·
View note