Text
フェイク
後ろから見ている。
私の肩に手を置いてゆっくりと振り向かせると彼は首をねじって下から覗き込んで笑いながら私の名前を呼ぶとけたたましい金属音と共に煙になって舞い上がった。
私は彼が誰なのかも知らないのでその名を呼んでやることもできずに風に流され消えていく彼であった煙の尾をじっと眺めそしてそれがすっかり消えてしまうと背筋を寒くして彼の肉肉しい笑みを思い出すのだった。
私の肩は彼が掴んでいた所だけ異様に重く感じられてもはや何処にもいない彼の存在を私にだけしつこく教えてくれるばかりか時折やはりまだ彼が私のそばで私の肩を掴んでいるようにさえ思わせるため日頃から肩を震わせては後ろを振り返るようになってしまった。
0 notes
Text
アリスト10
扉を開けてはっとした。部屋の中は、また少し温度が上がったように思える。井戸でもたつかなければ良かった、と内心で舌打ちをした。
今ではクリスティアンの顔は苦しげに歪み、唇の間からは時折唸る声と、何かしらの呟きが聞こえてきている。出かける前に長く話をしすぎたせいだろうか、それとも傷が酷くなってしまっているのだろうか。帰ってきたと声をかけるのも忘れ、クリスティアンの布団を剥いで服をめくり傷の具合を確かめる。
「閣下、遅くなって申し訳ありません。今、薬、塗りますね」
解熱剤と共に手に入れてきた化膿止めを包みから取り出して、タライを引き寄せてクリスティアンの身体を拭いてやってから塗る。少しだけ、表情が和らいだように、アリストには見えた。傷の方は、清潔にしてこれから切らさず化膿止めをぬるしかない。疲れが出てしまったのだ、ここに少しの間とどまって安静にするべきなのだろう。どちらにせよ熱が引かなければ出発は無理だ。幸い、必要な物の収穫はアリストの満足に足りる量であった。
包みから解熱剤を取り出し、クリスティアンの顔を窺う。唇が微かに動いている。何か呟いているようだ。起こして、起きてくれるだろうか。何かがアリストを躊躇わせている。しかしこのまま熱に浮かされている状態はきっと良くない。起こして薬を飲ませるべきだ。起こそう。一度自分に頷いて枕元の水差しの隣に薬と包みを置き、クリスティアンを小さく揺さぶる。
「閣下。クリスティアン閣下。アリストですよ」
小さな唸り声だけで、他の反応はなかった。
「薬を、お持ちしました。クリスティアン閣下、一度起きて、飲みましょう」
何かを呟いている。
「クリスティアン閣下、アリストが戻りましたよ」
唇がわずかに開いた。しかしそれだけで、起きる気配はない。しばらくの間その隙間をじっと見つめていたが、息をついてタライを抱えて部屋を出る。扉に手をかけると、
「父上」
ころり、石が転がるように口から零れたのは、クリスティアンが呼んだのは、アリストの名前ではなかった。
訳もなくどっと吹き出す冷や汗が背中を流れる。
ゆっくりと、振り返る。
汗が目に入ったのだろうか、クリスティアンの目尻にはうっすらと涙のようなものが滲んでいる。
辛いだろう。この高熱だ。
どうなるかも行く先の見えない、勝手の分からない土地での立ち往生だ、心細いだろう。
いまだ自分たちが追われているかも、定かではない。不安だろう。
しかし、だからと言ってその名前を呼ぶのだろうか。
吸った空気が喉を詰まらせる。自然と、息が浅くなった。苦しい。
その人を呼ぶべきではないはずだ。
例え何の夢を見ていようと、クリスティアンの口から出てきて許されるものではない。
アリストは朦朧とするクリスティアンの口が動くのを待った。今にもその人物を否定する言葉が出るに違いない。一歩、一歩と扉から離れて側に立つ。
ぷつ、ぷつ、額に新しい汗の玉が浮かんでくるのを、拭ってやることも惜しい。すがる思いですらあった。早く、早く次の言葉がでないものか。
新たに額から一筋、汗が流れていった。
「・・・・・・父上・・・・・・」
瞬間、タライの水を全て流し込んでしまったように腹が重くなる。
ゆっくりと、クリスティアンの額を汗の粒が流れていく。
否定された。
アリストは否定された。
否定されたのだ。
そのようにしか思えなかった。哀れな、この元王子に。この期に及んで、だ。
タライの水に写るものが呆然とアリストを見上げている。その視線が煩くて睨みつけると、震える声でタライは言った。
「だめだったのかな」
そっと右手を開いてみる。赤く濡れているような気がしたからだ。
「あの男を、殺しては、いけなかったのかな」
目を見開いてじっとアリストを見つめるその者に、そんなことはない。そう言い返そうとして喉に息が引っかかって声が出てこなかった。目の前がくらくらする。
群衆と広場。首が晒された壇上の側で、膝をついて動こうとしない、動けなくなっているクリスティアンの姿を思い出したのだ。
殺してはいけなかったと言うのだろうか。
アリストは、自分があの首を落としたことをうっすらと覚えていた。不思議なことに、クリスティアンと別行動をとっていた時の事が記憶に薄いのだ。それでも、あの男の首を落としたのはこの手であるということは覚えている。それを誰かに言うことは無かったが。あれは仮にも王族だ、不敬の大罪という言葉は元騎士のアリストに幾らかの用心を持たせていて、その用心はクリスティアンに対しても働いていた。それとも何か別の気がかりがアリストにそうさせていたのかもしれない。そうでなくとも、用心がなくともアリストは、不敬の大罪をクリスティアンには明かさなかっただろう。アリストは通すべき義を通したまでで、それをクリスティアンに褒めてもらおうなどとは思��ていなかったのだ。
なぜ殺してはいけなかったのか。
タライの中もその答えは寄越してくれなかった。熱にうなされるクリスティアンのみが、それに応えてくれるのだろうか。
向こうは国を見捨て民を見捨て臣を見捨てクリスティアンを見捨てたというのに。それでもあの時剣を突き立ててはいけなかったというのだろうか。
ころりと、また石が転がるような呟きがクリスティアンの口から零れる。目尻から静かに、雫が流れていった。
開いた右手に溢れるような赤色が湧いて、指の間から零れていく。そんな物さえ、見えた気がする。
あの時手放した剣は、アリストが首を落としたから手のひらから逃げていったのか。
しかし、しなければならない事をしたのだ。
あの男を追わなければいけなかった。
首をはねなければいけなかった。
心臓に刃を突き立てなければいけなかった。
右手から溢れた赤色は瞬く間に部屋に浸って息を奪っていった。おびえたタライの中が視線をさまよわせて助けを求めてくる。その目はアリストの足がよろけたせいで揺らいでゆがんだ。
そして、彼は波紋の中に消えた。
アリストは息をのんだ。
「ああ!」
いけなかったのだ!
「クリスティアン閣下・・・・・・!」
タライが、アリストの腕から逃げるように傾いた。
いけなかったのだ、殺しては。
少なくとも、この手では殺してはいけなかったのだ。
クリスティアンには、憎らしくとも必要だったのだ。
間違ってしまった。
間違ってしまった。
もう戻れない所で、アリストは間違えてしまったのだ。
タライが手から抜け出して抗議するように大きな音を立てて落ちる。床にはねた水が、クリスティアンの頬にも飛び散った。音が頭の中で反響し、アリストを責め立てている。どうしろというのだ。今更、自分が父親の仇だと明かせばいいのか。ここで、けじめを付けて見せればいいのか。何をしろというのだ。もはやアリストとクリスティアンしかいない部屋で、立っていることもできず膝から崩れ落ちる。アリストの事を、クリスティアンは許しはしないだろう。それはアリストを窒息させるに十分だった。
「閣下・・・・・・!」
ぴくり、瞼が動いた。
「申し訳ございませんクリスティアン閣下、俺は、俺は、俺は、俺は、クリスティアン閣下、すいません、申し訳ございません」
うすく目を開けて見上げるとすぐ側で、ぽとぽと、ぽたぽた、真っ青な顔のアリストがひざまづいて涙をながしている。食いしばった歯の隙間から押し出されるうわずった声が何度も自分を、クリスティアンの事を呼んでいた。自分の顔が塗れているのは、取り落としたのだろうタライの水がかかったのだろうか。それともアリストの涙であろうか。
「どうした、アリスト」
呼びかけても、頭を振って名前を呼び謝るだけだ。その声は王城から一度目の脱出を図った時に聞いた絶叫をおもいださせる。
「どうした、アリスト」
あの抜け道を戻るとき、アリストには随分と堪えることをしてしまったのだ、もうあんな思いをさせたくはない。熱のためか頭がぼうっとして言葉を聞き取れない中、努めてゆっくりと、取り乱したアリストを落ち着かせるように口を開く。クリスティアンの声は掠れていた。
「なに、気にしないよ」
「申し訳ございません、俺は、どうしようもなく、もう戻れないことを」
錘でもぶら下げていると勘違いしてしまいそうな程重い腕をそっと上げ、指の腹で涙を払ってやった。泣きじゃくりその手を取って胸に抱え込み、アリストは嗚咽をもらす。何を感情的になっているのか、たまにそう言うところがある男だ。タライひとつ、何と言うことはない。それとも、クリスティアンを起こしたことを焦っているのだろうか?
「大丈夫さ、大丈夫だよアリスト」
あまりに泣くものだから、哀れにさえ思う。
「謝らなくていいよ、気にしないから」
顔をくしゃくしゃにして、涙はまだぽたぽたと流れ落ちている。はっきりしない頭でそれを眺めていた。
そうか、気づいてやるべきだった。
やはり、アリストにとって世に不正を働くことは、辛かったに違いない。なんと声をかけたら良いのだろう。もうやらなくて良いと、言ってやることは、きっとできない。罪悪に苦しむアリストを、どうしたら楽にしてやれるのだ、罪悪の元になっている自分自身が。
あまりのふがいなさに、重たかった首の後ろがいっそう重たくなった。身体に力が入らない。このままうなじから溶けだして、何物でもない形のない物になってしまいたい。
それでもクリスティアンは言って安心させてやりたかった。私が一緒に罪を被っている、と。おまえの良心でおまえ自身を攻撃する事はない、と。
「違うのです、違うのですよ、クリスティアン閣下、俺は、俺は、本当に、申し訳ない、申し訳ないのです」
「アリスト、私を見ろ」
「だめです、申し訳ありません、違うのです、俺は、俺は、閣下、俺は」
「アリスト、アリスト、落ち着け、私を見ろ」
抱えた腕を痛いほどに締め上げ、アリストは大きく首を振った。目元から散った涙がクリスティアンの頬にぶつかって砕ける。
「アリスト、大丈夫だから、お前は何も悪くないから」
ぜいぜいと、息の上がっているのはアリストの方だ。
「アリスト、お前は何も悪くないのだから」
何度も何度も、アリストはクリスティアンを呼んだ。
たとえ何万回の人生を巡りあの場に立ったとしても、この手はあの男の首を落とすだろう。何がどうあっても殺す。疑いもなくあの男は殺すべきで、殺すならこの手であるべきなのだ。クリスティアンにした仕打ちを考えるのなら、それは正である。ただ、そうだとしてもクリスティアンにはあの男が必要であったのだ。今生の別れとしても。アリストは巡ってくることのない何万回の分まで謝り倒す必要があった。懺悔ができない代わりに。浅ましいのは分かっている。それでも、謝らずにはいられない。それによってクリスティアンが宥めようとかける言葉が、多少でもアリストの救いになるからだった。
「アリスト、顔をお上げ」
やっと上げた顔を、アリストは歪ませた。玉座での冷え冷えとした双眸とは対称の、クリスティアンの安心させるような穏やかな顔。その顔に、実は真実さえもが許されるのではないかと誘惑されている気分になった。
「お前も疲れている。休みなさい、私は大丈夫だから」
涙の跡が薄明かりを受けて光っている。アリストは小さく鼻をすすった。
クリスティアンは、知ればきっと許さないだろう。アリストへの信頼も絶ち得る話だ。そうに違いないのだ。もう一粒流れていく涙を手の甲で拭い、下唇を強く噛む。ただアリストを落ち着かせる為に使われた許しの言葉を、本当の物として受けとりたかった。
全てを打ち明けたくなる口を制しながら、この場を辞する言葉を探す。
「・・・・・・タライを、片づけてきます」
ああ、と言う声はかすれてアリストに届かなかっただろう。
自分で水差しを取り、アリストが用意してくれた薬と一緒に、言葉も水も流し込む。「少し眠るよ」クリスティアンはゆっくり目を閉じた。
もうしばらくすれば薬も効いて、数日後にはまた進むことができるだろう。
「はい」
部屋を出て扉に寄りかかる。また少し、目から涙が落ちていく。
クリスティアンを、どうすれば良かったのだ。空のタライにぽたぽたと音が響く。これから、どうすればいいのだ。
言うべきではないことは、明白だ。
アリストは頷いた。それは今までと、変わらない。そうだ、今までと同じに接していれば、決して明るみに出ることはないのだ。イスへたどり着くまで隠し通せれば、その後はクリスティアンにとって目まぐるしい日々がしばらく続くだろう、その間に忘れてくれはしないだろうか。そうなってはくれないだろうか。ぐっと抱え込んだタライに多い被さるようにして呟く。
「俺が、殺した。殺したんですよ、閣下。」
言葉は誰の耳にも入らず、タライの中へ落ちていく。
「俺は、殺していないんだ」
アリストはもう一度頷いた。話題にさえ、上げなければいい。そうすれば、嘘などつく必要もないのだ。大丈夫、大丈夫だ。ゆっくりと背筋を伸ばす。イスへ。そうすれば、状況も環境も変わる。
「俺は、ただ側にいればいい。そうでしょう」
副官の、闊達とした返事が聞こえた気がした。クリスティアンも、気にするなと言葉を掛けてくれたではないか。アリストは大きく息を吸って顔を上げる。
決意してからの道のりは、多少の息苦しさを除いて概ね順調であった。クリスティアンの熱が下がり、長居してしまった街を出て数日、歩みも捗っている。病み上がりを気遣ってアリストは馬車を用意しようか悩んだが、それはクリスティアンから断られてしまった。歩けば馬車分の金が浮く。クリスティアンはクリスティアンで、どうにかアリストの負担を減らしたいと思っているのだろう。あの宿で泣いて取り乱してからというもの、時折クリスティアンはいやにアリストに甘い。そのたびにやり辛さを感じない訳でもないが、隠している罪悪からくる肩の重さは多少軽くなる。どうせなら、ありがたく受け取っておくべき贈り物と、思うことにしていた。
「閣下」
先を行くアリストが弾んだ声を丘に響かせる。クリスティアンは短く返事をして顔を上げた。王城で革命軍と戦っていたあの日のように空のてっぺんまで青く風通しの良い日だ。アリストの碧い両目も空のように広く、太陽を照り返している。豊かな金髪がよく似合う男だ。目を細めたクリスティアンは、丘の向こうから吹き下ろしてくる風に混じって潮の香りを嗅いだ。
「アリスト」
つられて声を上げながら小走りに丘を登る。海だ。港だ。遠くに港が見える。あのどこかに、どうにかアリストが席を用意したクリスティアンたちの船があるだろう。大きく息をつく。ここまで、よく来られたものだ。後ろを振り返る。探しても、王城の尖塔の先すら、城壁のいっぺんすらない。最後に見たのはいつだっただろうか。クリスティアンは、日にちを数える事すら止めていた事に気がついた。
「少し、休んでいきませんか」
丘に腰を下ろしてアリストは笑いかけた。緩く頷いて横に座り、二人で港を遠くに眺める。まだ見たことのないイスを近くに感じ、なぜか後ろを確かめた。
城壁は見えない。
しがらみなど、もう無いはずなのだ。
城壁も、騎士団の宿舎も、食堂も、王城の冷たい地下室も、緋色の敷物も、天井の高い玉座の間も、石畳の城下の広場も、もうクリスティアンの人生にはないのだ。二度と。
クリスティアンは、意味もなく母の最期の様子を思い出していた。そして王城でのアリストとのやりとりを。それらは、随分と昔のことのように思えた。
ふと、隣から、アリストの声がする。それは歌だった。うろ覚えに、その歌詞を知っている。
「聞いたことがあるな」
照れたようにアリストは笑った。
「前に、お教えしましたよ」
長い旅路を経て、故郷へ帰る歌だった。アリストからしてみれば、イスへ向かう歌なのだろう。第二の故郷だと以前に言っていた事を思いだす。綺麗な声だ。王城でしゃがれてしまった喉も元に戻っている。しばらく聞き入っていたクリスティアンは、合わせてゆっくりと歌い出した。声は自分の背中に向けて、玉座に放った指輪に届けと。クリスティアンの右手には、未だ紫の噛み跡がある。跡を指先でなでながら、父の顔を思い出そうとした。
思い出せたのは、広場で晒された首であった。
これからも褪せる事は無いであろう黒く質量のある熱湯が腹でさざ波を立て、それを押さえる為に声を、少し大きくする。
いつか凪いだ気持ちで、歌のようにこの国へ再び訪れる事は、できるだろうか。ただの一人の人間として。今、クリスティアンを絡め取るしがらみは確かに無くなり、思いと郷愁だけが残った。噛み跡も、決して消えることはないだろう。玉座の間でのアリストのやりとりをまた思い出しながら、自分はとんだ馬鹿者だと頬をゆるめる。
「いきましょうか」
「ああ、イスへ」
二人は立ち上がり、丘を降りていった。
イスへ。港は、待ち受けるように徐々に大きくなっていく。
おわり。
***********************************************************
1年止めたり半年止めたりしてちょっと話がつながらなくなったけども、
アリストとクリスティアンの脱出劇、生還ルートでした。
後書きとしては、ちょっとすれ違い起こして空気悪いけど、書きたい所を書けてすごく楽しかったです。クリスティアンは結局父親のしがらみからは、自覚しない所で解放されていないまま生きていくんじゃあないだろうかと思ったので、最終的にこうなりました。
イスにたどりつく所まで書きたい気持ちもあったのですが、そうするとイスにいる人たちの事も書きたくなるだろうし、まとまらなくなりそうなので、港を出る前で終わりにしようかなあと。
0 notes
Text
アリスト9
うなだれて肩を落とし、宿へ戻ってくる頃には夜も深くなっていた。薬はまだ手に入らない。 アリストが長くクリスティアンを一人にすることなど出来るはずもなく、とりあえず戻ってきてしまった。宿の主人にタライと手ぬぐいを借り、井戸から水を汲んで部屋に向かう。ノックをしても返事はなかった。 「クリスティアン閣下、戻りましたよ」 扉を開けると、狭く暗い部屋に熱がこもっている。ぎょっとして側へしゃがみ額に触れると、出かける前よりも熱いではないか。うなされているのか、時折聞き取れない声で何か呟いているようだった。あたりを見回した。がらんとした部屋になにもないのは分かっている。解熱剤でもあれば少しは楽にしてやれるのだが、宿には生憎置いていないようだった。早急に必要なものがひとつ増えてしまった。 布団を剥いで腹の傷に手を当て、頬や首元の温度も確認する。じっとりと汗をかいていて、小さく開いた口の隙間から乾いた呼吸が掠れた音とともに聞こえる。餌を求める鯉のようだ。眉尻を下げてクリスティアンの様子を見つめていたアリストは近くに置いたタライを引き寄せ、濡らした手ぬぐいで身体を拭いてやり、最後に冷やすために額に置いてやる。しかしきっと、しばらくもしない内にぬるくなってしまうだろう。 「クリスティアン閣下、起きられますか。アリストが戻りましたよ。閣下、水でも、飲まれてください」 何度か声をかけてやっと、薄く目を開ける。この暗い部屋が頭の中から引き出すのか、嫌な、不快な夢を見ていた気がする。 「起きあがれますか、水、飲みましょう」 ゆっくりとした瞬きだけの返事をして、クリスティアンは背中を支えられながら上半身を起こした。喉がからからだ。 アリストは少しずつクリスティアンに水を飲ませながら、異常に熱いその身体を険しい思いで見つめた。早く、早く、薬がいる。 「何か、食べられますか。食欲はありますか」 持ち合わせている物はとても病人が食べる物ではない。しかし風邪で喉が腫れている訳でなないのだから、食欲さえあれば食べれないこともないだろう。それに、頼めば宿の主人に粥くらいは作ってもらえるのではないか。 「いい。今は、まだ」 「分かりました。水、置いておきますね。俺はまた少し出かけますが、なるべくこまめに飲んでください。もう少ししたら、きっと楽になります」 「ああ」 どこへ、などと分かり切った言葉はかけられず、扉の向こうへ消えるアリストの背中を苦い思いで見送る。 「アリスト」掠れた声も、届かないだろう。クリスティアンは強い自責の念に駆られた。あの隠し通路で、アリストに、酷なことをしたのだと。 閉じた扉が、思い出したように勢いよく開く。 「閣下、呼びましたか。どうしました?」 アリストだ。 身体が弱ると心も弱るのだろう、それをクリスティアンは実感した。応えがあるだけで何か、助かったような気がしてくるのだ。それでも言いたい言葉だけは喉の奥に張り付いて出てこない。大きな目を瞬きさせて扉から振り返るアリストに、柔く微笑んだ。 「すまない。迷惑を」 「いいえ!なにを言いますか。あなたの生きるは、我々の、俺の願いなのですから。」 ニッと笑ってみせるアリストを、目を細めながら眺める。疲れているだろうに。ここが、この宿が自分の最後の寝台になるなら、アリストだけでも安全な国外へと抜けられるのではないか。少なくとも足は速くなり肩も軽くなるはずだ。もうすでに何者でもないクリスティアンを必死に逃がすよりか、生産性を大きく感じる。今までに何度も去来しては重たく粘着質な水を残していくその思いは、熱で回らなくなった頭を容易に浸し始めていた。 ここを最後にしないとしても、一人はここで具合が治るのを待ち、もう一人は先を行くという方法もあながち悪いやり方でもないのではないだろうか。先を急ぎたがるアリストに比べ、クリスティアンは自身の怪我の具合を差し引いても、大して急ぐそぶりを見せていなかった。それは、王城の地下、革命軍に捕らえられていた時に持ちかけられた取引があったからだ。不本意とはいえ、クリスティアンは全てを捨てて国を出ようとしているのだ。革命軍が提示した条件通りに。一度反故にはしてしまったうえ安易な考えではあるが、根拠のない確信がクリスティアンを納得させていた。そもそも、父の首の代わり以外に、あの場でのクリスティアンの役目など誰からも期待されていないのだから。 「そうか」 心なしか肩を落として返事をしたクリスティアンに、アリストは未だ伝えていないことを明かすことにした。本当は後にとっておきたかったのだが。 「クリスティアン閣下。まだ内緒にしていたのですが、ここぞと言うときに伝えたかったのですけど、俺たちの向かっている先は、俺の、二つ目の故郷と言いますか、小さい頃に世話になっていた所なんです」 扉を後ろ手に静かに閉め、寄りかかる。 「そうだったのか」 表情は見えないが、少しだけクリスティアンが首を傾けたのは分かった。 「ええ。あの街にはいろいろな人間がいます。俺のいた家なんかは、特に。閣下一人が加わっても、違和感もなにもありませんし、初めて見るもの聞くもの、あるでしょう。仕事もきっとあります。しばらくは俺のいた家にいて、落ち着いたら身の振りを決めれば良いんです。そのくらいは話せば分かってもらえる、そんな所なのです。俺たちは今、国に追われて、ただの名前としての名前と身体と、この小さな荷物以外なにも持っていませんもの、しがらみだって。だから、何にでもなれますよ。天気が良ければ海へ船を出してみてもいいし、街を散策してもいい。雨の日は家にいて、住んでいる人たちの身の上を聞いてみてください。1日や2日では足りない話が山ほどあります。慣れるまではきっと、驚くことがたくさんあって退屈しませんよ。俺の幼なじみも二人、紹介しましょう。よく出かけて遠くへ行く奴らなので、都合良く居合わせるかは分かりませんが、そしてちょっと癖があると言えばあるのですが、良い奴らなんですよ。それで、暮らしが落ち着いたら手頃な家を用意してもいい。クリスティアン閣下、ね、良いでしょう?」 アリストの目は、丸い。夜の暗がりのこの部屋からどうやって光を得ているのだろうか、まぶしいのだ。 「ああ、楽しみだ。こんな熱、さっさと下げて早く訪れてみたいものだな」 「ふふ、ね、そうですよ」 部屋の影がクリスティアンの顔を隠してしまっているため見えないが、少しは気が晴れただろうか。考えていたよりも話しすぎてしまいアリストは気まずそうに下を向いて扉に手をかけた。そのまま出ようとして、歯の後ろでもたついていた言葉が気まずいついでに、不用意に口から漏れ出る。 「閣下。」 「うん?」 「もし、もしですよ」 「ああ」 「もしも、俺に何か負い目を感じるのなら、感じてしまうと言うのなら」 アリストは眉尻を下げて笑った。 「最後、家へ着いたときに、頂戴したい物があるのです。これは俺のエゴです。なので、どうするかは閣下にお任せします。ただの、冗談だと思ってください。でも、もし頂けるなら、最後の終わりに一言、よくやったと、それだけを」 クリスティアンが返事をする前に扉が閉じてアリストを隠し、足音が急ぐように遠ざかる。 黙ったままの扉がアリストの背中の様な気がしてクリスティアンは小さく笑い声をもらした。アリストはアリストで、そういった不安を抱えていたと言うことだ。 「覚えておくよ」聞く者もいない扉の裏側にそう声をかけて横になる。身体の調子はまったく良くはなっていない。どっと押し寄せるだるさに抵抗する事も出来ず瞼をとじた。もう一眠りするしかない。 首尾良くアリストは薬を手に入れられるだろうか、無事だろうか。 そう心配しながらクリスティアンが眠りに落ちていく頃、アリストはやっとの思いでそれを成している所だった。 暗闇がかすかな衣擦れの音をも吸い込んでしまうのか、それとも静かな無音がわずかな光をも隠してしまうのか、アリストは頼るものも無いままそれでも最善の細い道を違えずに進むことができていた。信頼する仲間に背中を預けているような感覚さえある。 誰かに見られることもなく、したがって不要で不本意な乱暴を働くこともなく。懐に収まる成果の包みを赤子の様に抱えながら、裏路地を縫い歩く。こんなことにも慣れ始めている、自分が不思議である。 部屋へ向かい、タライの水を替える為にクリスティアンの側へ膝をつく。また、うなされているようだった。 小さく息をついて井戸で水を替え、ついでに自身の身体も濡れた手ぬぐいで拭いておく。安宿には当然、風呂はない。濡れた手ぬぐいを首にかけたまま、新しいものをタライに浸した。クリスティアンにもしてやらねば。井戸の縁に寄りかかる。懐から出した口糧を加えて自分たちの使っている部屋の窓に目を向け、また小さく息をつく。 糧食も工面しなければならない項目のひとつであった。アリストは早い段階で、最終的に船を使わなければいけないことに気づいていたし、さすがに密航を成す自信はない。クリスティアンから預かった限りある路銀のほとんどを、それに当てるつもりであった。薬を探すとき、食料を調達するとき、集めるべき余剰を加味していた。早くにそうしていたのが良かったのだろう、このまま続けて行けば金銭の面では何とかなりそうではあった。あとは、クリスティアン次第である。 アリストが部屋を出る前のあの会話。未だクリスティアンの中で、何かわだかまりがあるようだった。もともと思慮深い人である。考えてしまう多くのことが時として重荷になるのだろう。しかしそれは、今の状況では足枷になりかねない。 足下に置いたタライをつま先でこづく。宿の裏手にあたるこの水場は、井戸の周りだけ石畳で、はき掃除だけはこまめにやっているようだ。ただ石畳の隙間からは細かく雑草が伸び、宿の軒下などには背の高いものが好き放題に育っている。夜の落とす影がそれらを黒々と浮かび上がらせているのを見やって、そしてまた部屋の窓に目を移す。 もし、イスにたどり着いたとして、全て済んだとして、クリスティアンの中にわだかまりが残ったとしたら。 首を振ってため息をつく。 窓の向こうには、うなされているクリスティアンがいる。早く、戻ってやらねばならない。中の水をこぼさないようにタライを持ち上げる。 アリストは、クリスティアンに「よくやった」などという言葉を求めたことを激しく悔やみ始めていた。クリスティアンの意志のままに、死にたいと言うのなら死なせてやりたいと心に決めたはずだったのだ。ゆらゆらとたゆたうクリスティアンを良いことに、この状況はクリスティアンの意志のままなのだと、アリストは刷り込んでいるのではないだろうか。 「よくわかってる。自覚してる。分かってるんだよ」 腹に食い込むほどきつくタライを抱え込む。 「でも、何も言わないじゃないか。あの広場で、この手を取ったじゃないか。何か違うか?最善と思うようにしろと、あの口で言ったじゃないか。違うのか?」 この憤りを、誰かのせいにしたかった。 ***** ***** ***** ***** ***** 次くらいで終わるはず......!ガンバレアリスト君!!!!頑張れクリスティアン閣下!!!!
0 notes
Text
アリスト8
王の首をもって革命の完遂を民に知らせたのだから、身体に鞭を打つように逃げる足を急がせることはしたくなかった。王族狩りも収まったと思いたい。傷の重いクリスティアンがいるのだから尚のこと。それでも追われている様な予感がして、アリストの気は急いていた。追われてはいなくとも、触れくらいは出回っていておかしくないだろう。その思いから着いた先の街で宿を取ることすら、安易に出来ることではなかった。 クリスティアンはと言えば、よく従順にアリストに着いてきている。このまま誰にも見つからずに逃げ切りたいものだ。 「次の街で、宿を取りましょう。化膿止めの薬をもう数日前から切らしていますし、食料もギリギリです。あと、進捗で言えば、俺たちは中々順調ですから」 痛々しさはそのままで、まだまだ化膿止めが必要ではあるが、クリスティアンの腹の傷は少しずつ良くなってきている。この逃避行の大きな懸念はまさに、その傷であった。普通であれば捗る平坦な道も、傷が開かないように、クリスティアンが苦しくないように休み休み行かなければならない。今では小間実に綺麗にして薬を塗るのを怠らなかったおかげで、初めよりも日に進める距離が長くなった。アリストの怪我も随分と良くなっていて、肩も、奇しくも革命軍に治療されていたおかげで綺麗に塞がりかけているのだ。 「2、3日くらい、薬がなくても大丈夫だよ、アリスト。そんなに急ぐことはないからね」 「はい」 ひどくしゃがれていたアリストの声も元に戻り始めている。クリスティアンは、先を行くアリストの背中を見ながら、ゆっくりと目を細めた。元のアリストに戻るだろうか、と。今では薄れてきているが、やはり離れる前の彼とは何か違和感を、時折感じるのだ。水筒の縁を睨むように覗き込んだまま考えにふける様を見ていると、どこか不安を覚える。 さらにクリスティアンの気を重くしているのは、金の問題であった。 城から持ち出してきたずた袋の中に路銀は入っているのだが、クリスティアンとアリストの怪我を治す為の薬や、これほど長い行程の路用分��賄えないはずなのだ。それでも未だにやって来れているということが不思議でしょうがない。どこからどうやって金を捻出しているのか、何度が聞こうとしてやめた。 あのアリストが、あのアリストが、世に対して不正を働いているかもしれないと問いつめることを、クリスティアンにはどうしても出来なかったのだ。働いていたとして、生きたままこの国から逃げ切るにはそれを止めるように言えない。指示はしていなくとも、それをやらせているのは、クリスティアンなのだろうからだ。 街道の側の木陰で二人休憩しながら空を見上げる。首を巡らせて王城のあった方を見やるが、なにも見えない。 アリストの、時折見せる表情は、罪悪かそれに近い物から生まれてくるのだろうか。再会したときから感じる違和感を思えば、広場で合流する前にも大きな転換の期があったに違いない。 「アリスト」 「はい」 「そろそろ、行こうか」 「ええ」 立ち上がり荷物をとると、各自怪我の状態を軽く確認して歩き出す。時折思い出したように会話をする以外は無言で、ただただ土や草を踏む音の他、風とすれ違う音のみがしている。頭を巡る様々な事柄も次第に白く薄れてなにも浮かばなくなり、クリスティアンもアリストも今は昔となってしまった行軍を何となく思い出すのであった。 夕暮れ前、ア、とアリストが声をあげる。遠くを眺めていたクリスティアンが声をかけると小走りに駆けだして街道の脇に立ち、振り返った。足下には杭の様な物が一本、打ち込んである。しゃがんで見れば朽ちかけた標識で、次の街までは後1日足らずだと書いてあった。 腹を静かにさすって、安堵の息をもらす。 「やっと街ですね」 安宿でもベッドがあると無いとでは、やはり違うものだ。この旅でアリストとクリスティアンはそれを嫌と言うほど再認識していた。顔を見合わせて微笑み合う。もうひと頑張りだ。疲れ始めている身体を励まして太股を軽く叩いた。 しかし、その無理が祟ったのだろう、街に入った頃にはクリスティアンの傷は熱を持ち、それが全身に回ってしまった。傷口から良くない物が入ってしまったに違いない。 そしてこういう時に限って宿は見つからないものである。路地裏にやっと空き部屋のある寂れた宿を見つけ、あまり寝心地の良さそうではないベッドに眉をしかめる。 「クリスティアン閣下、申し訳ありません、このような所しか見つからず」 ベッドの縁に腰掛けながら重たい頭を振り、クリスティアンは礼を言う。今までが順調といえば順調であったため、一気に気分が焦り始めていた。 「アリスト、すまない」 「気にしないでください。俺は薬を探してきますので、どうか少しでも楽なように休んでください」 億劫に頷きながら横になる。身体が、腹が、傷が、熱い。アリストの肩は大丈夫だろうか。同じく熱を持ったりはしていないだろうか。言葉をかけようとして、声がでなかった。扉が閉まる。薬を、どこから調達するつもりだろう。アリストに本来のアリストのままでいてほしいと思っているのにも関わらず、こうしてクリスティアンが不正を強いているのではないか。 暗い日の当たらない部屋は、王城の地下を思い出させた。 「は、は」 そうだ、国からすれば、クリスティアンの生命自体が不正なのだ。 「は」 目を閉じた。ひとまず、寝よう。一人の時はろくなことを考えない。 右手の甲に唇をよせて指の噛み痕を新しくする。それはもはや、クリスティアンの癖になっていた。 ***** ***** ***** ***** ***** 本当は8で全分終わらせる予定だったけどちょっとだけ長くなりそうなのでここで分断 そろそろリベンジアリスト終わりの予定
0 notes
Text
アリスト7
アリスト7
ひしめく民衆の最前列へ、ぬるりとアリストが出る。
人々の雄叫びともつかない歓声が、数本の矢が壇上に刺さったときには悲鳴に変わっていた。いっせいに惑い始める群衆とは対照的に、壇上の台に視線を釘付けにされたクリスティアンが力なく膝をついたまま固まっている。広場が襲われている事にも気がついていないようだ。
自分のすぐ側まで来た足音にも反応することなく、腕を捕まれ強引に立たされてやっと首級から目を離し、揺れる瞳を自分の前に向ける。
首元に、刃。
剣を向けるその者は顔のほとんどを布で覆い、おまけに外套を目深に被っているせいで表情が分からないが、空色の目が厳しくクリスティアンを睨みつけ、どこか、アリストを思わせた。似ているにしても、こんな目をする男ではなかったのではあるが。
剣から男の目へ視線を移すと、さらに目を厳しく細めながら、汚いしゃがれた声を男は出した。
「選べ」
男からその後ろへ気を向けると、どういったことか、もはや興味すら抱かないが、悲鳴や怒号が飛び交っているではないか。「城に待機させている奴らを呼べ!全員とらえろ!」と、遠くに革命軍を指揮して混乱を治めようとしている頭の姿もある。ひきつったその顔に、悦を、微かに覚えた。
「なにをだ」
「ここで首を飛ばすか、それとも走り出すか、選べ」
通りの陰から、家々の屋根から、矢が降ってくる。この場を乱している者たちは矢を射るとサッと身を翻して逃げていき、またどこかから革命軍を狙うようだった。城下の土地勘がなければここまで攪乱することは到底できまい。
壇上を見上げ、そこに未だ黙ったままぴくりとも動かない首を眺めた後、男に言う。
「誰とも存せぬが、お前の最良と思うようにしてみなさい」
アリストに言ってやるのだった、と思わなくもないが、こうなると誰が予想できたろう。しゃがれ声はひどく動揺したように瞳を揺らがせて剣先を離すと逡巡の後に手を差し出した。その手のひらを見つめ、またアリストを思い出す。
「この手を取ることをお勧めします」
「それがお前の最良というのなら」
手を取ると、痛いほどに握り男は走り出す。つられてクリスティアンもバタバタと足を動かした。怪我も相まってここ数日ろくに動いていなかったものだから、手を引かれていなければこの人混み、すぐにはぐれてしまっただろう。頭の中は止まったままで、混乱に乗じてクリスティアンはぐんぐん広場から遠ざかっていった。革命軍が背中を追ってきてはいるものの、逃げまどう人々に隠され追いつかれずにいるのだ。
追っ手を振り切りある程度進むとしゃがれ声は大通りの横道に滑り込み、角を折れに折れ、城下の外ではなく城の方へ足を向けた。このあたりの道はクリスティアンもよく知っている。騎士団の若い連中が城下へ無断で出かける時に隠れて使う、抜け道があるのだ。迷うことなく男はその抜け道を進み始め、揺れる外套のせいで輪郭の分かりにくい彼の背中をいぶかしんで観察していると、どうしてやはり、アリストのように思える。父の事があったのだ、この背中がアリストでも今更驚きはしない。どうせ、万事はクリスティアンを裏切るのである。今、鈍い思考の中で父の首だけが鮮明であった。
今度こそ今生の別れ。広場の方を振り返り、ふつふつと胸の奥に湧いてくる思いを持て余しながら、王城で見送った背中を思い出す。今まで父と子としての会話も、思いやりも、それらしい関係は皆無であった。ただ、惨めにも期待していた自分がいた、それだけだ。そっと、右手の噛み跡をなでて息を吐いた。
終わったのだ、父とのしがらみは、きっと。
そう思い定めながらも右手の甲を口元へ持って行き、噛み跡を新しくした。それは無意識のうちに行われ、前を行くしゃがれ声の男は当然見ていなかっただろう。彼は彼で、時折出くわしそうになる革命軍を避けながら隠れて進む事に苦心していてクリスティアンの手指に気を払っているどころではなかったのだ。
革命軍の出払った城内にやっとの事で入り込むと外套と顔の覆いを少しばかりずらし、男は彼がアリストであることを明かした。やはり、とクリスティアンは独りごちたが、目の下のくまも、血走った目も、どこか違和感を感じる表情も、離ればなれになる時は見受けられなかったはずだ。よくよく似ている、他人とさえ思ってしまいそうになる。
「お前、その酷い声はどうしたんだ」
「そのうち治りますよ」
そっけなくそう言い、アリストは用心深く辺りを見回すとクリスティアンの間近に詰め寄り不躾に顔をのぞき込む。
「クリスティアン閣下、ご無事で何よりでございます。あれ以来、ほかにお怪我などは」
「ない」
「安心しました。俺はこのままあなたをどうにか、革命軍の手の及ばない所へお連れしたいと思っておりますが」
「先ほど言ったとおりだ。最良と思うようにしなさい」
アリストの瞼がぴくりと動いたのを、クリスティアンは見逃さなかった。やはり、この男はどこか変わったように思える。間をおいてアリスト、
「申し訳ありませんが、閣下、俺が王城へあなたをお連れしたのは、また同じ手を使おうと考えたからなのです。城門を目指すよりははるかに、と、思うのですが」
注意深くアリストを観察しながら同意し、クリスティアンは先に立ってまだ誰にも使われていないだろう城外への隠れた道へ案内し始めた。その後ろを、焦れるでもなく、浮き足立つでもなく、アリストはついてくる。
背中に感じる視線に居心地の悪さを覚えながら、無事で良かったのはお前もだ、と声を掛ける機会を逃したことを思い出し、しかし口にするのは今でもないような気がした。お互い黙ったまま、数日前がそうであったように騒がしい王城の外の音を聞きつつ、人気のない王城の中を進むだけである。もう見ることもないだろうと思っていた王城は革命軍が踏み込んだせいで土っぽく、緋色の敷物も泥で汚れていた。見るともなく周りを見渡して足早に進んでいく。
くらくら時折眩暈が襲ってくるが、クリスティアンは一度も立ち止まることなく抜け道へたどり着くことができた。陰気で、かび臭く、暗い。様相はアリストと通ったあの道とほぼ同じで、その時と同じくアリストはランタンを掲げクリスティアンの前に立って用心深く歩き出した。響く足音を聞きながら、観念した心持ちで出口を目指す。アリストも、二度目はないと知っているのかクリスティアンを疑うそぶりもない。あの時はこの長い抜け道を行く間に考えを巡らせ、様々な自分と戦ったものだ。右手の噛み跡に手を這わせる。戦い、そしてこの男を逃がすという腹を決め、そのようにした、はずだった。はずだったのだ。恨むなら、いったい誰を恨めばいいのだろう。あの物言わぬ首にしろ、何にしろ。
暗い道に不安を覚える頃に、既視感のある行き止まりに突き当たった。
薄い壁をはがさなければ。クリスティアンはアリストの横に立って鞘ごと剣を腰からはずすと壁に突き立てたが、隣の動く気配はなく、
「アリスト?」
呼びかけてみるが、じっと壁を見上げたまま口を一文字に結んでいる。
不信ではない。幻滅でもない。この場にあっても、アリストがクリスティアンに向けているのは忠誠であった。しかし、処理しきれず持て余している何かがあることも、また確かなことではある。壁に剣を突き立てたクリスティアンがこちらを見ている事に気がついて、つい、口を開いた。
「クリスティアン閣下」
「何だ」
頭を振って、微笑む。言葉にはなりそうもない。口に出せばそれは恨み言のように聞こえるだろう。
「この壁を壊して外へ出たら、もう国外へ逃れ国を捨てることになりますが、それでも?」
後ろを振り返れば、通ってきた暗闇の中に、父の背中が消えていくように見えた気がした。あ、と声を出しそうになるものの、壇上の失意が即座にクリスティアンの息を詰まらせる。半歩引いて、乗り出しかけた身をごまかす。
「もう、いい」
黙ってうなずき、アリストはやっと剣を腰から外し壁に突き立てた。二度目だからだろうか、漆喰の壁が見えるようになるまでにはそう時間はかからず、クリスティアンとアリストは二人で外に出ることができた。大きく息を吸い込み、吐く。クリスティアンはもう一度城を振り返り見上げた。騒ぎはどうも広場から遠のいて、城門の方へ移ったようだ。煙が城門の方から上がっている。
広場を乱した者たちもアリスト同様顔を隠してはいたが、クリスティアンが自分の部下たちの動きを見間違うはずがなかった。気を重くしながら、アリストを見る。
「広場のあの者たちは、どうなる?」
「彼らですか」
ここまでアリストとはどこか別人のようにも思えた男が久々に、らしくない、あるいはクリスティアンのよく知るアリストのように、言いよどむ。
「彼らは、俺たちと道を違えています。申し合わせはしましたが、もう、会うことはないでしょう」
酒場を後にし、他に身を潜める場所を探そうという時に、彼らのうち一人が追いかけてきたのだ。どちらにせよ自分たちも逃げねばならない事、クリスティアンの処刑で革命軍の警備が広場に集中するであろう事、少しの陽動くらいなら手を貸すというのも可能である事、そして、クリスティアンが助かろうが処刑されようが自分たちはもうクリスティアンについて行く気がないと言う事。彼は困ったようにアリストを窺い、「アリスト、お前がどう思うかは分からないが、俺たちは一度閣下を切り捨てようとしたんだ。だもんで、もう、閣下を上にいただく事なんてできないよ。処刑が始まったら言う暇さえないだろうから先に言っておく。さよならだ、閣下にも伝えておいてくれ。この国で、貴方の下で剣を握れたこと、何にも代え難い宝であったと」そう言って去っていった。それから二度ほど、それぞれ別の者と陽動の打ち合わせを終えた頃に広場での処刑の噂が聞こえ、彼らは酒場の店主の手引きで武器を得、この日に臨んだ。
事のあらましを伝えると、城壁に隠され見えない街並みを見透かすように目を細め、いったいいくらが生き残るのであろうな、ぽつり、クリスティアンが言う。
「それは我らも同じです。さあ、急ぎましょう。追いつかれては彼らの陽動も無駄と言うものです」
アリストは先を促そうとしたが、クリスティアンは立ち止まったまま王城を眺めている。もう、そこには居場所などない、そう言ってしまいそうになるのを思いとどまり、クリスティアンの袖を引く。
「すまん」
驚いたのか、ぱっと腕を引っ込めてクリスティアンはアリストに向き直った。
「すまん、アリスト、ぼうっとしていた」
不自然に袖を払う仕草をして見せてクリスティアンは、依然がそうであったように抜け道の入り口に隠されていたいくらかの物資が入ったずた袋を腰にくくり、やっと歩き始める。それを見送り、今度はアリストがいぶかしんで背中を見つめる番であった。
*****************************************
脱出は成功しましたがもう少しだけ続きます!
0 notes
Text
アリスト6
ああ暗い、と思った。暗い。静かに目を開けてみたが、それでもやはり暗かった。暗い。そうだ、当たり前だ、死んだのだ。馬鹿みたいに可笑しく感じられて声を出して笑うとすぐに咳こみ、そして腹の痛みに顔をしかめる。衛生兵がくれた麻薬の葉は、どこにやっただろうか。そうだ、廊下の端に吐き捨てたのだ。父が角を曲がり姿を消したときに。気休めでしかなく、痛みを和らげてはくれなかったが、捨てなければ良かった。違う、指揮に戻らなければ。何だというのだ、あの憎らしい男に何を命令されたからといって、クリスティアンは任された軍の指揮に戻らなければいけない。陛下から位を譲渡されたのが何だというのだ。窓の外には、そうだ、愛しい、大切な部下たちが命をとして戦っているではないか。戻ろう。いいや、戻ってどうするというのだ。良いじゃないか、陛下は逃げると言った、私に代わりになれと、位を譲渡したじゃないか、今まで下された命令をすべて、されてもいない期待通りに、時には空っぽの期待以上にやり遂げてみせたじゃないか、やってやろう、見捨てればいいのだろう部下たちのことも。そうだ、陛下は、この国の王だ、政治すら顧みないのだ、クリスティアンのことを顧みるはずがない。ああ、革命は、こうして起こったのだ。逃げればいい、呪われろ。やってやろう、どちらにせよこの革命は成るのだ、ならば、私も革命軍に荷担しよう、彼らに同じ気持ちだ、この国は、王家は、倒れてしまえばいいのだ。王の首で、この首で、それを成してやろう。
「起きたか」
寝台の、上。暗い部屋の中でこちらを覗き込む二つの顔をクリスティアンは凝視した。見覚えがある。誰だと問うと、彼らは顔をみあわせた。こめかみを擦り、なぜか痛む腹を押さえるとそこには包帯が巻かれているではないか。がちゃがちゃ、頭の中でそのような音が聞こえた気がした。
そうだ、こいつらを、クリスティアンは玉座の間で待っていたのだ。しかし扉を開けたのはアリストで、アリストは、アリストは、
「アリストはどこだ?」
玉座の間、違う、クリスティアンは最後王城の中をさまよい、そして倒れたのだった。そうだ。抜け道が見つかったとき玉座の間から誰かが逃げたのだとすぐに知られないように、少しでも攪乱になればと王城を歩き回っていたのだ。そうして力尽きて倒れていたところを捕らえられ、その場で首をはねられるとも思っていたのだが、城下の広場において民衆の前でそれは行われるらしく、クリスティアンが立つのもままならないと知ると革命軍は王城の地下にクリスティアンを入れ手当をさせたのであった。
上体を起こし、こめかみを擦る。クリスティアンの眉間の皺を見て二人のうち枕元の椅子に腰掛けているひょろりとした体格の男が気遣わしげに覗き込んできた。
「大丈夫か」
そ��顔に唾でも吐きかけてやろうか、と唇を噛みながら曖昧に返事をする。大丈夫か、だと。この者たちには、どうやら腹の傷は見えないようで、そして王城を落としたことも忘れてしまっているのだろう。
ひょろりとした男はクリスティアンに敵意は向けていないようであったが、後ろに立っている尊大な態度の男は厳しい顔をしたままこちらを睨みつけていて、それがまたクリスティアンの気を逆撫でしていた。今まで守ってきた民衆が、今はこのような顔を向けてくるのかと思うとどうにもやるせなく、いいや民衆にこのような顔をさせるようにしてしまったのは紛れもなく王族の責任であるのだ。父よ、あなたの成した事、成さなかった事をこの顔が物語っているのだ。それを見ることも放棄し背負うことも放棄し野に走った王の、その外皮を被る事を了承した自分は、あの王よりも誇りなどなく、この地下室こそお似合いだとため息をつく。しかし、クリスティアンのような役回りも必要なのかもしれない。仮にも王族の末席に名前を連ねるのなら、たとえ継承権がなくとも。王城の腐敗を看過してしまっていた罰として。
クリスティアンは、もうやらねばならない事もなく、したい事もない。それならば、王族の最後の仕事として後は来るべき刃を受けるだけだ。ここ数日で負うことになった様々な思いも既に重さがなくなり、クリスティアンの胸の中に収まり始めている。一時アリストにかき乱された心中も穏やか。父に対するくすぶる思いと目の前の二人が気に入らない事は除外して、すべて感情は平坦になりつつあった。
「処刑はあとどのくらいで執行される」
父の逃亡がどうなったのかは分からないが王族狩りが終わっているのなら、クリスティアンが起きたので今日か明日にでも執行されるのではないだろうか。しかし、クリスティアンの問いに二人は気まずそうに顔を見合わせ、ひょろりは居心地悪そうに両手をすり合わせている。都合がつかない、そういう返答だった。
二人に分からないように寝台のシーツを握りしめ、緩んでしまいそうになる口元を引き結ぶ。ざまあない、父が簡単に捕まる訳がないのだ、すべてを捨てて逃げ出せるほどの男だ、革命軍などに捕まる訳がない。いざとなったら、あのいけ好かない側付きをも捨てていくだろう。ざまあない。王族狩りの追跡を撒いて、とうに遠くへ、行ってしまったに違いない。反吐が出そうな気分だ。この無能め、二人に聞こえないように口の中でそう呟く。なぜだか肩の強ばりがほぐれた気がして、煮え返るような腹の気持ち悪さの反面、胸がすっとする。後は、自分が刃を受ければ、それですべてが終わるのだ。
こいつはすべて諦めて、自棄になっているのでは。わずかに頷いただけのクリスティアンを見てひょろりの後ろに立つ尊大な態度の男はそう思った。男は、ひょろりの方も、クリスティアンの生い立ちくらいは知っていたので、彼に同情しないわけでもない。愛されなかったばかりか、捨て駒にされているのだから。
「処刑のことだが」
連れているひょろりとした男やほかの幹部と共に依然話し合っていた話題を切り出す。王族の中にあって、クリスティアンは王族らしからぬ仕打ちを受けていた。それらしい権力もなく、横柄でも、横暴でもなく、横領もせず、実直に役割に務め、人に見えるところでは必ず誠実であった。おおよそ、あの王族らしからぬほどに。民は王族の陰口は言いはするものの、取り立てて言うこともないクリスティアンについては何も不満という不満も、意見という意見も持っていないのだ。これを王族として首を落とすことに、はたと躊躇いを覚えるほどである。
「それを行う前にいくつか聞きたいことがある」
言いにくそうに口を開いた男に一瞥を投げて、私が親切に答えるとでも、クリスティアンは苛立たしげに返す。寝起きにこの二人を見てからずっと抱いていた気に入らない思いが、二人と話しもしたくないとクリスティアンにそう言わせたのだ。あとは死ぬだけだというのに何故そっとしておいてくれないのか。
短気そうだと踏んでいたが、男は驚いた後すぐに腹の底に響くような声をにじませて笑い出した。
「別に、答えなくてもいい。そういった分かりやすい態度の方が、良心の呵責もないというものだ。ああ胸くそわるい、俺は、俺の親切が踏みにじられるのを、快く笑っていられるほど出来た人間じゃない、お前など、王族などは、さっさと首を切ればいいのだ」
そう言うと最後は睨むようにクリスティアンにぐいと顔を近づけて、そして踵を返し部屋から出ていく。出て行く背中に、おい、と呼びかけるひょろりが盛大にため息をもらした。部屋の扉に向けていた視線をひょろりに移す。手をすり合わせるのは癖らしい。
仮にも王城の守護を最後まで果たした騎士団の指揮官と二人きりになろうとは、この革命軍の甘さというのだろうか、奥歯を噛んでひょろりを睨めつける。たじろいだのも一瞬、ひょろりは手をすり合わせながらクリスティアンの目をしっかりと見た。
「答えていただきたい。俺たち革命軍は、腐敗した王族から民を解放する事が使命だ。あなたは、王族の血をその身に流してはいるが、しかし、継承権もなく、そして腐敗もしていない。どうだろう、地位も名前も国も捨てるのなら、処刑を免れる事が、あなたになら許されるが」
窺うような、気遣うような物をひょろりの瞳のなかに認める。耐え難いものだ。クリスティアンは尊大な態度の男のように低く笑う声をもらした。
「答えてやろう」
拳を、ひょろりの肩めがけて振り抜いた。椅子から転げ落ちる音が暗い地下室に響くなか、寝台から足を下ろしてひょろりの前に立つ。
「答えてやろう。この国は陛下の物だ。私は王族で、王子で、この国を担う義務と権利がある。それを恐れ多くも不当に踏みにじったのはお前たちだ。私は生き続ける限りこの国から出ていく気は無いし、お前らが城内を汚すのを許すつもりもない」
一言、話す度に一歩踏み出し、尻餅をついたまま後ずさるひょろりの間近に寄る。
「答えたぞ。いかがか」
熱い、氷の熱が碧眼からあふれ、身を炙られている錯覚に陥った。王城で見つけだしたときは弱々しく倒れていた男が、先ほどまでも青ざめた顔をしていた男が、一歩自分に寄るたび喉の奥が熱くひきつる。目の前にある冷ややかなこの目は今、力をもって自分を地面に押さえつけているのではないか。あきらかな憎悪の色が、ひょろりの顔に浮かぶ。食いしばる歯の間から、
「処刑以外の、道を、示してやったのに、なんだ、それは」
そう唸ると力を込めてやっと立ち上がり、お前の処分は決まったぞ、扉を叩きつけるようにして出て行った。その扉をひとしきり睨みつける。
不意に、頬が緩んだ。くつくつ、押し殺した笑いが部屋の暗闇に吸い込まれていった。
怪我が痛む。
声を殺すことに耐えられなくなり、次第に大きくなっていく自分の笑い声が部屋いっぱいに響いて、それが聞くに堪えられず掻き消すように腕を伸ばしむんずと椅子を掴むと扉に投げつけた。大きな音こそすれ、どちらも壊れない。その事に腹を立ててよろめきながら椅子を拾い上げると何度も扉を殴りつける。耳の中に残る、先王の言葉や先ほどの二人の申し出を振り払うように、腹の傷を気にも掛けず。
「誰が憐れめなどと言った!誰が命乞いをした!何も知らないくせに!私が何を願った!馬鹿にするのも、いい加減にしろ!」
クリスティアンのどこにそんな力が残っていたのか、椅子は鈍い音を立て砕け頭上に降りかかり、我に返ると腹を押さえてその場にうずくまる。
どこが痛いのだろうか、もはや分からない。部屋の暗闇は外から、痛みは中からクリスティアンに何かを訴えているように思えて煩わしいくらいにうるさい。しかし耳をふさいでも無駄である。先ほどまでの平穏さはどこへ。視界がぐらつき手を床に着くと、椅子の破片で皮が切れたのか、薄く血がにじんだ。
「アリスト…」
身体に血が足りていないからか目眩と共に視界が真っ白に点滅している。この身体を引きずって遠くへなど、行けるはずがない。行きたくもないのだ。それでも、たとえクリスティアンを思った利己心からの行動であっても、その美しさに応えてやらないことに罪悪を感じないわけにはいかなかった。
「アリスト、ごめんなあ」
次に革命軍の何者かがこの部屋に来るときはきっと、あそこまでクリスティアンが言ったのだから、処刑の日取りが決まった時であろう。予定通りさ、と口の中で呟くと目を閉じた。石の床は冷たく体温を奪い、クリスティアンはそのままべったりと泥が地面に這うように倒れ伏し身体を伸ばして意識を失っていった。
知らないうちに運ばれたのか、意識を取り戻した時には寝台の上であった。クリスティアンは力が抜けたように日がな一日ほとんど起き上がることなく寝台に横たわり、暗闇なのか天井なのか分からない物を見上げて過ごしていた。腹の傷は未だにじくじくと痛み、しかしその痛みに耐えようとしているおかげで余計な事を考えなくて済んでいるのかもしれない。今はただ、処刑を待てばいいだけなのだ。
代々国王に継がれるあの指輪を手にはめてから自分の首が飛ぶという覚悟はできていた。その覚悟を揺らがせたアリストは、今は遠くにいるだろう。それだけが、何もかも気に入らない今の状況の中で唯一、クリスティアンの救いだった。あの殊勝な男を生き延びさせる事ができたのだから。
右手を掲げると、指輪を玉座に放ったままにしていたことを思い出し、目を閉じてため息をつく。
国王の証でもあるあの指輪は、今この右手にはまっていなければいけない。先王が王族狩りから逃れたのなら、いよいよ必要とされる首として、クリスティアンがその役割を担うことになるだろう。ならば、証くらいは、持っているべきだ。億劫にベッドから下りると廊下に繋がっているだろう扉を騒々しく叩く。
「陛下の指輪が無いんだが、玉座から誰ぞ拾ってきてくれないか。陛下の指輪だ。陛下の指輪を、ここに持ってきてくれ。陛下が私に下賜してくださったものなんだ、指輪を」
返事はなかった。それからしばらく、力いっぱいに扉を叩き続けたが憎たらしいほどに扉の向こうは沈黙を守っている。
「陛下の指輪を」
何���も何度もそう喚いているうちに、ふと暗い通路の向こうからクリスティアンの名前を血の混じった声で呼び続けるアリストを思い出して黙る。今はどうしているだろう。遠くへ行ってしまってくれただろうか。まさかクリスティアンを助け出そうと城壁を越える手立てを考えようとしているのだろうか、それともまだあの丘の麓でクリスティアンの名前を呼び続けているのだろうか。それもあながち無い話ではないだろうと背筋がぞっとする。だがしかし、あそこで置いていかなければ二人して野たれ死ぬことは明白であったはずだ。どうして先王のようにさっさと逃げてくれないのだろう。軽く頭を振るとベッドへ座り、右手を眺める。見捨てないでください、という言葉はまだ耳の中に残っていた。アリストはクリスティアンが見捨てたのだと思ったのだろうか。
右手の甲を口元に持っていくと指の根元を噛む。紫色に歯形が付き、クリスティアンは満足そうに眺めた。
「指輪だ」
或いは、その顔は自嘲に満ちているのかもしれない。仰向けに倒れ込むと右手を掲げたまま呟く。
「私は結局、いつもこうなんだ。最後までこうだとは、さすがに思わなかったが」
あの男は今平野のどのあたりを逃げているのだろうか。ひどく怯えたままの顔で、あの忌まわしい側付きと共に命惜しさ、そのためだけにせっせと足を動かしているのだろう。全身を巡る血が普段よりもゆったりと流れている気がして気持ち悪くなり、目を閉じると天井に吸い込まれるような錯覚と共に眠りに落ちていく。クリスティアンは自分が少し緊張している事をよく感じ取っていた。後は死ぬだけ、という所でこうも焦らされると落ち着かないものなのか。
再び目が覚めたのは扉の向こうから騒々しい足音が響いてきたのを聞き取ったからだった。王城内で革命軍に捕らえられた時を思い出しにわかに込み上げてきた笑いを押し殺すと、指の根元をもう一度きつく噛んだ。
「クリスティアン王子。もうお覚悟はできていると思うが」
「ああ、連れて行ってくれ、反逆者諸君」
革命軍の者たちは気分を害したように低く唸ったが、その顔すら愛おしく思えてくる。武装した者たちに挟まれて暗い廊下を歩いていき、どうやら処刑の行われる広場まで護送されるようだった。
久しぶりに浴びる太陽の光はクリスティアンには眩しすぎ、視界いっぱいを真っ白な色に塞がれ、たたらを踏む。早く歩け、と立ち止ったクリスティアンを後ろから誰かが小突いた。
汚い馬車、それを囲む騎乗した兵、見栄えは軍そのものであったが練度は騎士たちのそれに及ばない。こんなものの前に国軍は倒れたのかと思うと、王家が腐りきっていたのもよく頷ける。この革命は正しいのだ。
馬車の前に革命軍の頭であろうものが無言で立っていた。クリスティアンは足を止めて彼と見つめ合い、そして逸らすと黙ったまま慇懃に馬車へと乗り込む。右手の指の根元に左手を這わせた。馬車が走りだしたときに頭が大きな声で呼びかける。
「最後だ、よくこの街を見ておけ」
返事はせず、鷹揚に外を窺うとすれ違う民は皆疲れ少しの不安を抱いてはいるがどこか希望に満ちた、晴れ晴れとした顔をしている。馬車が広場に着く間、その人々の表情を眺めつつ右手の噛み跡を撫でていた。
人だかりはいよいよ、この階段を上ればそこで見た景色がクリスティアンの今生最後の景色になるのだろうと思うと緊張で目眩が収まらない。人々がざわめく声すら耳には届かず、詰めいていた息を思い出したように少しだけ吐いた。
先に到着していた革命軍の頭がなにかを民衆に向けて語っているのが遠くに聞こえ顔を上げると、ちょうど壇上の前に設けられた台に被せられた布に手を掛けている所だった。
「やめろ」
とっさに叫ぶ。その布の下に何があるのか、知りはしなかったが分かってしまった。見たくない。
クリスティアンの声は広場に集まる民衆のざわめきと革命軍の頭の演説にまぎれて誰に聞かれることもなく、布は、落ちた。
ぶつん。耳の中で音が聞こえる。
「陛下」
その首を見て、民衆は空気が割れんばかりの雄叫びをあげる。クリスティアンにはともかく雄叫びに聞こえたが実際は歓声なのか悲鳴なのかまったくわからなかった。膝から力が抜け、その場に崩れるクリスティアンを支える者はいない。
ぐらぐらと、陽炎のように壇上の台に置かれた王の首が歪んで見える。隣には側付きの首もあるようだ。
今生の別れを、あの廊下ではたしたのに。物も言わぬ首が、クリスティアンに背を向けながらじっと台の上に居座っているではないか。
「逃げたくせに、逃げたくせに、どうしてそこにいるのです陛下、私にすべて投げてよこして、遁走したのではなかったのですか」
いやに長引く歓声なのか怒声なのか悲鳴なのか分からない物が音量をまして処刑台を包み、吐き気がする。
「あなたはそうやっていっつも、私に応えてくれないのですね、私の功績を、いつも台無しにする、私は、私がどれだけ、あなたのために、それでもここにきてもこれが最後だったのに応えてくれなかったあなたのために私はここに残ったのにあなたが生きたいと言うから、なのに、どうして、そこにいるのです」
腕を振り上げて歓声をあげる民衆が憎かった。首だけの父が憎かった。地下室であの二人が話した、都合がつかない、とは、遁走の成功の事ではなかったのだろうか。
首級から目を離すことができず、崩れ落ちたクリスティアンのその姿を遠くから見つけた者がいた。外套のフードを目深にかぶり、布で顔のほとんどを覆い、いまだ血走っている空色の目は探していた姿を見つけるとわずかに見開かれ、クリスティアン閣下、としゃがれた声をあげる。
アリストは広場の人だかりをかき分けて進み始めた。
*****************************************************
クリスティアン閣下のパートでした。彼の思考がぐちゃぐちゃしてるのは半分は仕様です。
1 note
·
View note
Text
お前たちが俺を呼んだのか。静かに水をたたえる場所で、虫たちのみが囁くこの場所で! 少しの狂いも許されないお前たちよ! 私を起こして願おうとしたのか、常軌を逸した者たち。お前たちはいつもそうする。
0 notes
Text
アリスト5
後をつけられていないかを十分に注意しながら裏路地へと入る。
騎士団の何人かが懇意にしていた酒場があったはずだ。アリストと交流があった者たちが逃げ集まるのならそこであろう。その予想の通りに、店の扉をくぐると店主が目を丸くして駆け寄ってきた。さすがに客はほとんどおらず、しかしそのためアリストが扉をくぐると視線をこちらに向けてきたが、革命軍に怪我が怪我を手当してくれた時に汚れた服を新しくしてくれたおかげで、アリストは店の客に怪しまれることもなく、店主に小声で用向きを話すと彼は微かにうなずき、裏の勝手口から酒場の地下へアリストを通してくれた。そこは酒蔵になっていて、樽の間に身を潜めるようにしてくたびれた騎士団の者たちが数人、ちょうど話し合っている所であった。
樽の影に外した装備を重ねて積んで、戦いの汚れをろくに落としもせず固まっている彼らと目が合うと、何日も会っていなかったという訳ではないのに、その者たちの顔を見て、アリストは懐かしいという思いを感じた。目を丸くしてアリストを見る騎士団崩れたちは、確かめるようにアリストに触れる。そうして初めて、目の前に立つ者がアリストで間違いないのだと納得したのだった。アリストはそれほどに厳しい面持ちで、皆の記憶するアリストとは違っていた。
「生きていたのか、お前も」
わずかに頷く。
「城門が閉ざされて、外に出られないと聞いた。残党狩りから逃れるなら、この酒場に何人かは集まるだろうと踏んだんだ」
ぐるりと見回すと騎士団の者たちも同じ考えで集まったようであった。アリストは皆から外の新しい状況の説明を頼まれ、手短に説明する。すっかりしゃがれてしまったアリストの声が皆を心配させたのか、途中何度も水を飲まされた。
残党狩りは依然として続いている事。国王が逃亡の末に殺された事。その他の王族は捕らえられた事。その中にクリスティアンも含まれる事。ただし、王を殺したのは、この手である、という事だけは伏せておいた。さすがに、騎士の前で不敬の大罪を報告することはできない。そのくらいの冷静さは今のアリストでも持ち合わせている。
クリスティアン存命と捕縛の知らせは、集まっている騎士団崩れの者たちを動揺させるには十分であったようだ。彼は最後、指揮もせずにどこかに居たからである。酒蔵にいる者の内いくらかは、眉間に皺を寄せた。自分の耳障りなしゃがれ声以外の音が聞こえない酒造をぐるりと見回し、アリストは低く唸る。
「閣下は生きておられる」
それぞれの眉間の皺を睨みながら、それらの目が良い色を返さないことを見て取る。喜びこそすれ、そんな顔をしている場合ではないだろうに。
「アリスト、アリスト、お前はそのために来たのか」
そう言った者の目を真っ直ぐに見つめて、そうだ、と一言返した。
「助力を」
深く息をつく音がどこかからか聞こえる。
「閣下は」
騎士団崩れの内の、疲れた顔の男がアリストに一歩あゆみ寄った。
「閣下は、俺たちを見捨てたじゃないか。怪我で後退されたのは知っている。しかし、手当の後姿を消したと聞くぞ。そして、捕まったんだろう?逃げて、捕まったんじゃないのか?」
ひやりとしている酒蔵の温度が、更に下がったように思えた。疲れた顔の男とアリストから視線を逸らす者もいる。アリストが何も言わずに睨みつけていると、男は続けて言った。
「閣下のあとを、副官殿が務めたぞ。あの方は立派に、俺たちに散る手本を見せてくれた。閣下は、クリスティアン閣下は、ああ、さすがに王族だな、陛下と同じ道を、選ばれたのだろう?」
間髪入れずにアリストは男のうめき声を聞いた。自分の両手が男の首を締め上げている。血走ったアリストの両目は男を食い殺さんばかりだ。
副官のあの男が、何のために、何を思って散る手本とやらを披露したのか、うめき声をあげる男の耳元で怒鳴ってやりたい。クリスティアンが首を縦に振らないのを、俺が無理を言って城外へ連れようとしたのだ。そうして、クリスティアンはクリスティアンの内の父親に惑わされて結局引き返してしまったのだ。クリスティアンは、自分たち騎士団を見捨てるどころかクリスティアン自身を見捨てていたのに、そして、アリストのことも見捨てたのに、この男はいったい何を気にしているのか。男が口の端に泡を吹き始め、周りにいた者たちは急いで二人を引きはがし距離を取らせる。視線の多くはアリストへ、戸惑いの色を示していた。空色の目は血走って赤く、いつもはゆったりと微笑むはずの口元は歪められ荒い息を吐いている。
「クリスティアン閣下が、陛下のもとでどんな仕打ちを受けていたか、王家をどれだけ憂いていたか、俺たちは知っているだろう。俺たちの事をどれだけ大切に、閣下が思っていてくれたか、俺たちは知っているだろう。それを、それを、なんだ。陛下と同じだと。同じだと。お前、よくも」
疲れた顔の男も、目の前のアリストによくよく似た男を顔をゆがませると共に凝視していた。何人かが二人の間に入りなだめすかして水を飲ませる。頭に血が上ったせいだろうか、アリストは頭痛に顔をしかめた。
二人の間に入った者のうち一人が控えめにアリストを窺う。なぜそんな風に怯えを見せるのか分からない。自分の名前を呼んだその者にアリストは視線だけをやって返事をした。
「なあ、アリスト、閣下が俺たちを見捨てたかどうか、それを抜きにしても、今、俺たちが閣下を助けに行くなんて、考えてくれよ、どう考えても、出来やしないさ。なあ、アリスト、俺たち、この城下の外に行かなきゃ生きていけないぞ、残党狩りがすぐにここを見つけるだろ、それをどう出し抜いて、閣下を助けろってんだ、俺たちだって下手すりゃ殺されるんだ、逃げられたって、ここから逃げられたって、俺たち、なあ、アリスト、生きるなら、国を捨てて、国を捨ててさ、行かなきゃ、いけないんだぞ」
国を捨てて、と絞り出すように最後にもう一度言うとその者は俯いて歯ぎしりをした。その様子を呆然と見て、次いであたりに目をやると誰もがその者の言葉を、奥歯を噛みしめて、自分たちの境遇の辛さを耐えるように聞いている。疲れた顔の男さえも力なくうな垂れ、アリストは周りの人間たちにぞっとする思いで一歩引いた。
訳が分からない。
クリスティアンを助ける事の困難さをアリストが分かっていないとでも思っているのだろうか、この者たちは。分かっているからここに、例え少ししか得られないのだとしても助力を求めに来たのではないか。
クリスティアンを助ける事に、国を捨てるという事の何が関係すると言うのだろうか。クリスティアンがどうにかして暮らしていくには、もちろんこの国の中ではそれは成されないということは分かり切ったことではないか。傷心に浸り時間を食う余裕すらあるくせに、一体何が、この者たちの足を逡巡させるのだろう。頭痛がぐらぐらと視界を揺らしはじめ、手渡されていた水の入った器を覗き込む。そこに映る者は酷く気分を害されたかのようにぶっきらぼうにアリストへ視線を返すだけで、何も言わない。
「少し、休もう。アリスト、お前もだ。顔色が悪い。怪我をしているんだろう、何か食わなきゃ動けないぞ」
「俺はいいよ、体調はすこぶるいいんだ、休めば顔色もすぐ良くなる」
先ほどのやりとりのせいか、声をかけてきた男はどこか距離をとりつつアリストを伺い、しかしそれに対してアリストはあまり気にかけず何も言ってこない水面の者から視線を外さずそれだけを返した。どうやらここにいる者たちの助力は得られそうにない。当てが外れたせいで、この状況からどうクリスティアンを助け出せばよいのか、より難しくなってしまった。水面の者は随分と黙ったままであったが、皆が背中を丸めて休憩しおえ、再び城下からどう脱出するかの話し合いをアリスト抜きで始めた頃に一言だけ、この命尽きるときはクリスティアン閣下のお側で、と呟いた。まだクリスティアンは生きているのだ。もしかしたら、助け出せるかもしれない。けれど、その場にいたってまだ逃げたくない、死にたいというのなら、アリストはどうするべきなのだろうか。副官の男の、俺の代わりにあの人の側で死んでくれ、という最期の会話がふと胸の内に浮かび、黙祷をするように、あの男の冥福を思った。
「閣下はとんだ分からず屋だ。こんなにも生きていてほしいと望まれているのに、閣下はとんだ分からず屋で、おまけに柔らかいふりをしているとんでもない頑固者だ」
水面の者は片眉をあげてアリストを見ている。
「それでも、そうだ、あの人が死ぬと言うのなら、その側で俺も果てようじゃないか。そうだ、どうして忘れていたんだろう、王城から脱するときに、そう約束したじゃないか」
誰にも聞こえないような声でそう呟くと、水面の者は鷹揚に頷きながらも口の端を持ち上げ、杯の底へと沈んでいく。アリストは顔を上げた。なんとしてもクリスティアンの元へ行こうじゃないか。その末そこで二人で果てようとも、クリスティアンの側に、アリストはいるべきなのだ、少なくとも今は。そう思い至るとがばりと立ち上がり、驚いてこちらを振り返る騎士団崩れの者たちをぐるりと見回し、毅然と口を開く。
「どうも、俺はここにいても邪魔になる。俺は行くよ。どうか、その余裕があったら俺と、そして閣下の寿命が長くなることを祈ってくれ。俺も、ここに集った大切な仲間たちの人生が少しでも長く、平穏なものになると祈ろう。では、共に戦った愛しい戦友たちよ、今しばしの別れに涙はいらない、道が開ける祈りが必要だ!」
誰も声を掛ける事ができず、アリストは一息に話し尽くすと爛々とする目の光を残し、どこか洋々と酒蔵を後にした。酒場にいる店に声を掛け、そして路地へと消えていく。
----------------- もうすでにしょうもないけどここからもっと捏造度がアップします。Bボタンはいつもあなたのそばに! でも割りと王道な道を行こうと思ってるのではらはら度は低いかと!
0 notes
Photo
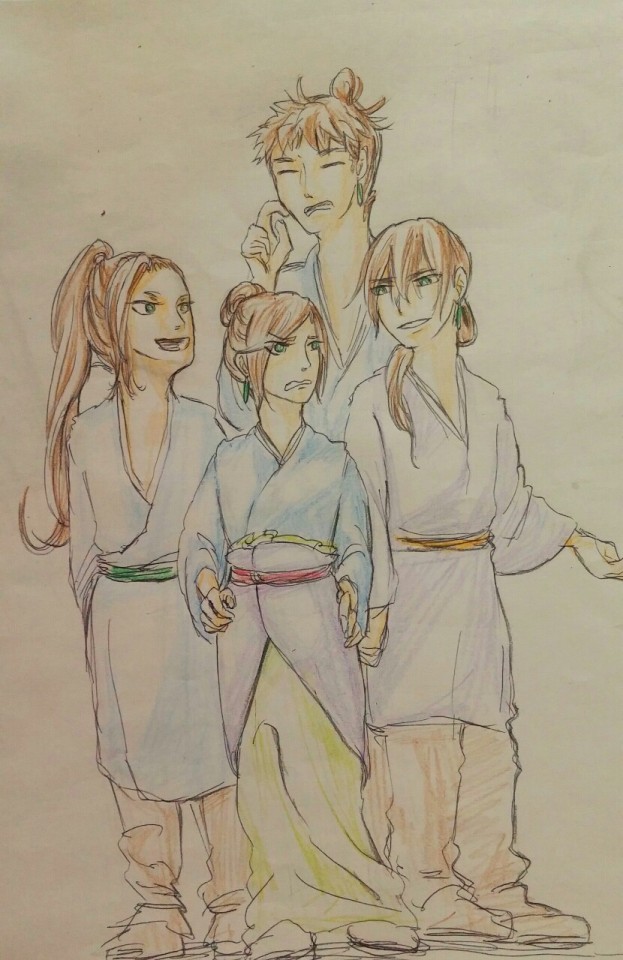
「お前いつの間にそんなに伸びたんだ」 「成長期ですもの、まだまだ伸びるはずです」 「いいなあ、俺なんかもう伸びないし、どこまでいくか楽しみだな」 「いいや、俺がお前の歳の頃はまだ伸びてたぞ」 「先生は例外ですって」 「ほんと、拳ひとつ分で良いから分けてほしいな」 ........ 身長さ的な。主人公
0 notes
Photo



最近甥っ子が脳内でエンジョイしてるけどこんなにガツガツしたキャラじゃないよって思い出した。 彼はもっとネクラであんまり表情も動かなくて眉毛とまつげが多いんだたしか当初の予定ではと思い出した。
0 notes
Text
胸がつまるようなその音を見たか。 延々とした、ただの広がりを切り裂くように、 沈殿の影底から覚めるように、 お前の喉を裂くその音を見たか。 あるいは打ち付ける拳のような、鼓膜を裂いて脳を揺らすような、 脳裏に張り付いて剥がれない彼の光を聞いたか。
0 notes
Conversation
せっ○○しないと出れない部屋
リュー:致さないと出れないんですって、エン。どうしましょうか。
エン:じゃあ出なくていいわ。そのうちリル殿たちが救出しに来てくれるかもしれない。
リュー:果たして、来てくれるでしょうか。
エン:仲間を信じるのは大切なことだ。
リュー:まあ、ここにずっといるでも構いませんけどね。エンと俺だけの、世界なんてのも悪くありません。むしろそうですね、一生いたって構いませんよ。
エン: ....。
リュー:ずっといると決まれば、エン、あなたは、俺もそうですが、一人の時間が無いと辛いタイプでしょう?お互いのスペースを用意しましょうか。仕切りも何もない部屋ですから、仕方ない、部屋の端にお互いが寄るしかないですが、よろしいですか?何かあれば、というか普段は真ん中辺りで過ごしましょう?
エン: ....。
リュー:エン?どうしました?
エン:切実に外に出たいわ。
リュー:え?外に?出たいですか?分かりました、出ましょう?いますぐ、出られますからね、エン!
エン:いや、近寄るなし。
リュー:へ?外に出るためには、だって。
エン:ほんと、近寄るな。一歩でも近づいてみろ、殴るからな。
リュー:エン?あなたが出たいと言うなら、俺はすぐにでもその為に動きます、今、すぐにです。実は言うと俺も外に出たいです。さあ、エン!
エン: ....。(リル殿、あんたの家系って本当にしょうもないな....)
リュー:!?がふっ!!!
ーーーーーーーーー
リル:いやあ、二人とも救出できて良かったよ。
エン:ご迷惑かけて申し訳ない。助かりました。
リル:ふふふ、いいっていいって。ね、ね、それよりさ。
エン: ....。なんでしょうか。
リル:リューとは?
エン:....。ご覧の通りですが。
ゴウ:リュー....ほら、氷持ってきたから、冷やしなさいよ。
0 notes






