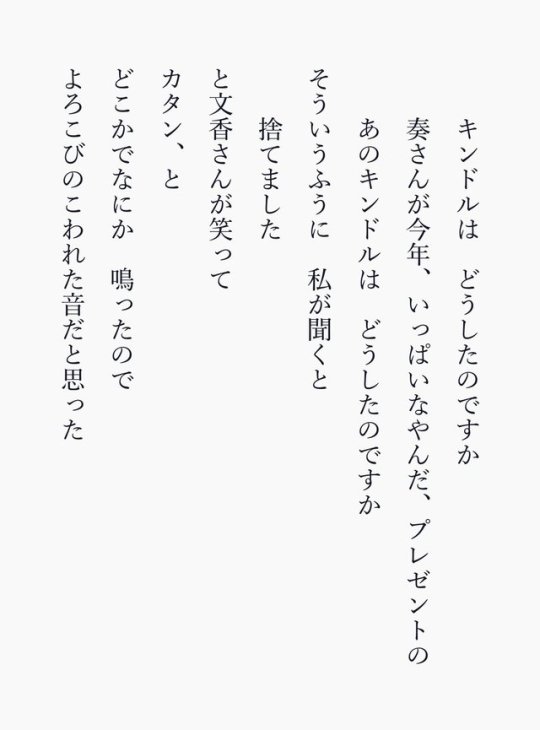Text
まくら / 奏周子
「家が燃えたの」と奏ちゃんは玄関先で言った。濃いブラウンのグラサンの裏で、薄い色の瞳がさっきまで涙で濡れていたのがあたしには手にとるようにわかった。あたしはグラサン、あほみたいにでかいトランク、その上のケイト・スペード、グラサンを順番に見たあと、「何回目や」ときいた。もちろんあたしはその回数を覚えている。あたしはキッチンの灰皿から吸いさしのマルボロを拾い、奏ちゃんがリビングでスカートをすとんと落とすのを眺めながら「襲うぞ」とひとりごとを言った。換気扇がごうごう鳴ってあたしの声をかき消した。
奏ちゃんが並べ立てる文香ちゃんの凄まじい悪口を聞きながら夕食を食べ終わったあと、あたしたちは別々の布団に入った。でもけっきょく彼女はいつもみたいにあたしのベッドに潜り込んできた。元カノのおなかを枕にするためにちょくちょくやってくるくらいなら、結婚なんてしなければいいのにと思ったけど、口には出さなかった。
あたしは何も言わない。もちろん奏ちゃんを襲ったりもしない。
「文香のばか」と彼女は寝言を言った。あたしのたいらなおなかは涙と鼻水でぐちゃぐちゃに濡れていた。そのありえなさに急な笑いの発作が起きて、「くは」と息が漏れた。く、く、と小刻みにおなかの上で揺れる奏ちゃんを眺めながら、あたしは笑った。
「奏ちゃんの、あほ」とあたしは言った。奏ちゃんは顔をしかめて眠り続けていた。
1 note
·
View note
Text
あるいは同時に / しきフレしゅーこ
その日あたしがノーベル賞級にめずらしく時間通りに事務所にたどりつくとフレちゃんがひとりで泣いていた。談話室のいつものテーブルには彼女が作った涙のみずうみがあった。あたしが口をひらく前に「なんでもないの」とひとこと言ってフレちゃんは顔を上げた。彼女が抱えていた鉢植えはエアコンの風に揺れてさわさわ鳴った。
「周子ちゃん、なんでもなくはないでしょって言ってるよ」とあたしは言った。
「テキトーすぎ」とフレちゃんは笑った。
蛍光灯の光を反射している葉が照り返され、フレちゃんの頬のかがやきはあまりにもあおかった。私はしばらく黙ったあと、「木にしてあげるよ」とフレちゃんに言った。
「フレちゃんも木にしてあげるよ。たぶん三ヶ月もまじめに研究したら作れると思う」
「誘惑イビルはどうなっちゃうの」とフレちゃんは言った。
「三人中二人が植物になったら、まあ解散だろうね」
「シューコちゃんが人間に戻ったときに、イビルがなくなってたらかわいそうだよ」
フレちゃんは三回くらい、かわいそうと繰り返した。限りなくやさしい人だった。あたしは身体の中心で渦巻く嫉妬で狂いそうになり、それからにこっと笑ってひざまずいた。「なんで笑うの」とフレちゃんは笑いながら言った。あたしは返事をしないで微笑み続けていた。きっとあたしたちは三人同時に木になってしまえればよかったのだ。
0 notes
Text
テ蝶(リライト)
愛をうたがうことは過去のものになった。もはやそれは輝かしく、うつくしく、目に見えるのだから。
最後のロングトーンが終わると同時に、私たちはステージの中心で天高く手を掲げた。凄まじい轟音で鳴っていた羽音ははるか遠くへと去り、今や心地いい余韻となって汗だくの私たちを包んでいた。
そして三人の呼吸が静寂の中にひとつだけ響いた。
次の瞬間にはアリーナを埋め尽くしたひとびとの歓声が雷のように鳴った。激しく上下する肩をぎゅうっとお互いに抱きながら、私たちは最初のたった三曲で合同ライブの成功を確信して、顔いっぱいに浮かべた笑みを見合わせた。
そして、空から蝶が降りてくる。
一万枚をはるかに超える数の電子的な羽が擦れている。
私たちの鼓膜はそれで満たされて、ほかに何も聞こえなくなる。
「ありがとう! みんなありがとう!」
「ありがとうございます!」
フミとシヅコがお客さんに向かって叫ぶと、その声は激しい歓声を呼んだ。客席ではサインライトの海が激しくうねり、地鳴りとなった足音がごうごうと轟き続けた。桃色と橙色の空飛ぶ光は、彼女たちの呼びかけに応じて爆発するように増えた。
「ありがとう!」
私は全身の力を振り絞るようにして叫んだ。アリーナの端から龍のように生まれた青色の光の連なりは、ほかのふたつと舞台の上で交わり、三色に音を立てて花開いた。
空気が震えていた。
狂い飛んでいた。風が巻いていた。
私たちに向けられたアリーナいっぱいの愛を、その一匹一匹が示していた。
『テ蝶』を使うと、誰かに向けた好意がきらめく蝶として拡張現実に描画される。
視聴覚の電子的拡張がオープンプラットフォーム化され、人間の感情に対するセンシングの精度が向上すると、ありとあらゆる人々が拡張現実アプリケーションを公開した。テ蝶は最初、そういったサービスのうちの一つの、さらに単なる一機能だった。
『向かいに座っている異性が自分に好意を持っているかどうかわからなければ、大抵のひとはただ話しかけることもできないでしょう』
運営母体のフーディエ社を創業した中国系の女性は、存在しない蝶を視界にぼんやりと描くことの価値について聞かれて自信ありげにこたえた。ライブのオリエンテーションにマネージャーから渡された補足資料として、私はシヅコとフミと三人でそのインタビューを見ていた。
『この蝶がいれば、そうですね……勇気が、得られる。ひと続きの空間を共有しているその人が、未来の共有さえも��しているのだという、気づきが得られるのです。そういった一種のフレーミングは……関係性における最初の確信は、ひとの生き方を変容させると私は考えています。蛹から生まれる蝶のように』
日本でサービスインしたとき、それはモテ蝶という名前だった。みんな恥ずかしくてそれをテ蝶と呼んだ。テ蝶はバーやクラブに広がっていき、すぐに都市部のあらゆる住民が知った。そして私たちは今日、世界で初めてテ蝶をパフォーマンスに取り入れたアイドルグループになった。
「さて次は〜?」
『この曲です!』
三人で声を揃えて叫ぶと次のグループの新曲のイントロが始まり、青白い蝶たちがはらはらと雪のように舞い降りるのが見えた。今日の合同ライブに参加するそれぞれのアイドルグループのために、カスタムされたテ蝶がフーディエ社から提供されていた。私たちはそれを振り切ってスポットライトの外に逃げた。
暗い通路でイヤモニを外しながら、あまりの興奮にあははと身体を折り畳んで笑った。出番が近い二人とハイタッチをすると、フミは「リラックス!」と言いながら彼女たちの背中をぽんぽん叩いた。興奮に満ちたまま私たちは早歩きで衣装替えへと急ぐ。
「すごかったですね!」
「やーほんと圧倒的! レイの青い蝶、かんっぺき海だね。溺れたかと思ったよー」
「あはは、それを言ったらシヅコなんか、ほんものの桜の木みたいだった」
私はシヅコと見つめ合い、彼女とはじめて会ったときを思った。彼女とグループを組むとわかったあの春の、生きる道がはっきりと切り替わったような、出会いの瞬間。
「本当に……本当に、すごくきれいだった」
シヅコは私に満点の笑顔を咲かせたあと、それをフミに向けた。
「フミちゃんは炎の中に立ってるみたいでした! こう、ぼおお〜って感じの〜」
「それ、私燃えつきて死んじゃうよ」
フミがけらけら笑ったので、シヅコもごめんなさい、と楽しそうな顔のまま謝った。
「レイもさすがにテ蝶嫌い、直ったんじゃない? まだ一回も使ってないんでしょ。蝶をつくる、アクティブモード」
私は笑みを浮かべ、「それはどうだろ」と、フミを軽くいなしたつもりになる。
「ハイハイわかってるわかってる、レイが好きな人バレるのすんごくイヤがってるの、わかってるよ〜。まったく純真なんだから〜」
「ちょっと、違うってば! アイドルなのに常時アクティブにしてるのフミぐらいでしょ」
私が怒ったふりをすると、「運命の出会いを逃したくないのはフツーだっつーの!」とかなんとか適当なことを言いながらフミは逃げ出した。数歩で彼女を捕まえて、軽く頭を叩いた。すぐにあははと笑って、もたれあった。シヅコも追いつきながら微笑んで、
「でもほんと、何も聞こえませんでしたね。ちょうちょの柱の、中は」
「うん、すごかった。ひどい嵐の中、一人きりで立ちすくんでいるみたいな——」
ざあ、という音が小さく聞こえた気がして、私は言葉を切った。三人でほとんど同時に立ち止まった。
「聞こえた?」
フミが真面目な顔をして言ったので、私は、
「聞こえた、かも……シヅコは?」
シヅコはしばらく黙っていた。逃げ場のない暗くて狭い廊下にいることが急に不安になった。
「……えっと……何も聞こえないと、思いますけど——」
そのとき、私たちを怪訝そうに見ていたシヅコが、内蔵をまき散らしながら爆発したように私には見えた。ぎらぎら光る桃色の蝶の群れがもの凄い勢いでシヅコを包み込み、次の瞬間には私たちを飲み込んだのだった。洪水に流されたときのような激しい轟音が私を包み込んだ。羽音以外は何も聞こえなかった。ひらけた空間で蝶に包まれる快感とは違う、ただ密度の濃い恐怖にすべてが満ちた。私自身のあああという身体の中に響く叫び声と、鼓膜に直接叩きつけられるような昆虫同士のこすれる音があたりを埋め尽くしていた。口の中に何匹か入って、咀嚼してしまうような感覚があった。私はそれが現実のものではないとわかっているのに、嘔吐しそうになりながら唾を何度も吐いた。
耳元で誰かが声を上げていた。肩を揺さぶりながら、彼女は「……切って!! レイ!!」と叫んだ。
私はフミの声にはっとする。右耳の後ろを押さえて、集中し、視聴覚の拡張を切った。耳障りな轟音は斧で叩き切られたように一瞬で姿を消し、視界を覆っていた蝶は跡形も無くなった。
目の前には私の肩をぎゅうっと押さえているフミがいた。彼女は私から手を離して素早く立ち上がると、シヅコに駆け寄った。
「誰か、誰か!」
シヅコは叫び声を上げて、床に転がっていた。さっきまでの私みたいに、唾液を何度も床に吐いていた。フミがシヅコを抱きしめて、さっき私にしたのと同じように「拡張を切って! 早く!」と叫んだ。私は必死にシヅコの耳の後ろを親指で押しながら「シヅコ!」と呼びかけた。
「切れない、切れないの、切れない、切れない……」
シヅコは自分でも何度も耳の後ろに触って、弱々しく繰り返しながらうずくまった。床に肘をついて、たべたものをげえ、と吐いた。
「……助けて……助けてえ、レイちゃあん」
それからしばらく、助けて、と言いながら、繰り返し私の名前を呼んで、段々反応が薄くなったシヅコは気を失い、廊下にははあはあ言う二人分の荒い呼吸だけが満ちて、私はそれでもずっと震える手で彼女の耳の後ろをぎゅうぎゅう押していた。
激しいブレーキ音を立てて、救急車が停止した。「前の車、どいてください!」というスピーカーからの声が響いたあと、ゆっくりとまた走り始める。
「麻倉シヅコさん、年齢は二十二」
「はい」
「コンサートの終了直後に拡張現実の昆虫に全身を覆われて、それが消せなくなり、倒れた、と」
「まだです」
「はい?」
「……公演は、まだ終わっていないんです。冒頭の出番が終わった時に」
「ああ」
失礼、と言いながら、救急隊員は横目でシヅコのバイタルを確認した。彼は一瞬だけ耳に手をやり、拡張現実をオンにして顔をしかめた。
「……この昆虫は合法なものと、先ほど伺ったのですが」
「テ蝶です、フーディエという会社の——」
「テ蝶? あれがこんなに」
「公演の演出に使ったんです。ステージから降りたら、消えるはずが」
救急隊員は沈黙して、シヅコの全身を包んだ衣装をまじまじと見た。
私はマネージャーに病院名を連絡する。「何かあったら」と出がけに押しつけられたフミの車の鍵が手の中で温まっていた。必死に頭を下げたら、マネージャーとフミは私を彼女の付添に送り出してくれた。出番はみんなで埋めるから安心しろと、フミは言い切った。
シヅコの指がぴくりと動いた。私はそれを手にとって握りしめた。
蝶の夢を見ていなければいいなと思った。
「拡張現実が消えなくなることは、あまり知られていませんが、よくあることです」
シヅコを担当した救急外来の若い医師はそう説明した。
「その多くは薬物との併用によります。認識に作用するインターフェースのスイッチは身体感覚上に実装されることが多いので——」
とん、と彼は耳の後ろを触って、
「——その感覚が正常に取得できない状態になると、スイッチが焼き付くんです」
私は傍らのベッドで寝ているシヅコに目をやった。アイマスクとイヤーマフ、マスクで覆われ、点滴で鎮静剤を投与されている、彼女の痛々しげな全身を見た。汚れたステージ衣装は脱がされて、簡素なシャツとジャージを身にまとっていた。
「テ蝶に包まれた興奮が、シヅコをこうしたってことですか」
「私も先ほど拝見しましたが、十分な要因になると思います。違法に改造された拡張現実単体でもまれに見られることです。拡張の性質と、焼き付いたスイッチ。その二つが今の状況を生んでいます」
私はシヅコのつめたい二の腕にそうっと触った。
「フーディエに対策してもらうのを待つしかないと思います。それまで、気分を落ち着ける投薬を行いましょう。サポートに連絡は?」
「事務所がしています。公演がプロモーションも兼ねていたので、ホットラインがあって」
「問題の程度と比べて対応が遅いですね」
私は沈黙する。医師はデータベースを操作しながら、「入院をおすすめします」とひとこと言った。
「……レイちゃあん」
私はシヅコの呻くような声にはっとして、医師を見た。彼は看護師に指示して、イヤーマフを片耳だけそっと外させた。う、と唸って、耳を抑えた震えるその手を、私はやさしく取って、はっきりとした大きな声で「シヅコ」と呼びかけた。
シヅコは、ぐす、と鼻をすすって「もういやだあ」と何回も言った。
「おうちに帰りたいです」と言った。
そのあとは私が何度呼びかけても泣くばかりだった。私はイヤーマフを戻して、彼女の腕に額をつけた。
「……彼女を連れて行きたいところが、あるんですが」
「あの蝶を引き連れて帰宅ですか? 救急車も事故を起こしかけた。あまりおすすめできませんが」
私は彼の目をまっすぐに見て、「家だけじゃないんです。お願いします」と言った。
「私は反対です。周囲はともかく、シヅコさんの状態が――」
「ひらけた場所なら、問題ないでしょうか」
「……ええ、おそらく。密度が薄くなれば」
ちり、と、ポケットの中で鍵が鳴った気がした。
えへへ、とシヅコが弱々しく笑うのを見て、私はほっとした。出発してしばらくしてから片手でアイマスクを外してやると、シヅコはのろのろとイヤーマフとマスクを自分で取った。
「……レイちゃん」
「なに」
「ありがとう、ございます」
「お礼ならフミに言ってよ」
私たちは自動運転で病院までやってきたフミの車に乗り込んで、首都高の複雑な分岐をパトカーに先導されていた。わずかに吹き込む冷たい風が心地よかった。拡張をオンにしてみると、雲のような桃色の光が細かく点滅しながら私たちの後ろを少し遅れてついてきているのがわかった。
「フミの車がオープンカーで良かった」
「ふふ……フミちゃんがこの車を買ったとき、レイちゃんあほっぽいって言って怒られてたのに」
「あれは鎌倉の桜並木に行ったときに撤回したから、もう忘れた」
シヅコは笑い終わると、はあ、とかわいく息を吐いた。
「ライブ、どうなりました?」
「わからない。聞かなかった」
「……そうですか」
それでシヅコは黙った。
ハイウェイを照らす照明は規則的に私たちの車に差し込んで、パーカーに半分隠された私の衣装のスパンコールに跳ね返った。ダッシュボード、ドアの内側、シヅコの横顔がきらきら光った。蝶の羽が起こす反射のようだった。
「……テ蝶、ぜったいに使いたくなくなったね」
シヅコはこたえずに黙っていた。出口の標識が見えて減速すると、ざあ、という音が遠く聞こえはじめた。シヅコは耳の後ろを何度も押していた。
「消えた?」
「消えません……私、これからどうなるんでしょう」
「大丈夫だよ、いつか直る」
一般道を進むと、シヅコの蝶はどんどん増えていった。桃色の輝きで人目を引く彼女に、一瞬の恋心が次々と向けられて、それらも消えないのだった。
「私はテ蝶、消しちゃうの、いやです」
「なんで?」
「……フミちゃんと同じです。ほんとうの愛があらわれたら、逃したくない」
車が赤信号で止まって、私はシヅコに向き直った。「ほんとうの愛」と私は囁いた。私たちはそのあと数秒の間、声もなく見つめ合った。
そして「だって私はアイドルだから――」とシヅコが呟いたとき、蝶の雲は私たちに追いついた。
激しい羽ばたきの音とともに鱗粉が見る間にダッシュボードに積もりはじめた。私は目を閉じて、ゆっくりと息を吐きながら拡張を切った。シヅコは俯いて、アイマスクとイヤーマフの中へと戻っていた。
青信号を見上げると、フーディエ社の入っているビルが遠くに見えた。
無人の受付を操作すると、すぐに白人の男性がやってきて「こんにちは、本社で開発を担当しているエドと言います」と頭を下げた。
「本来ならコミュニティマネージャの林か、あるいは営業担当者が話をするべきでしょうが、少しだけ今回の障害に詳しい僕が黒木さんへの説明に呼ばれました。会議室にご案内します」
「夜分遅くにすみません。でも説明はいいんです。ただ、見て欲しくて」
私は男性を促して、エレベーターホールへ戻る。彼は一瞬、どうするか迷ったようだが、結局小走りになって私に追いついた。
「バタフライが消えなくなった原因は、一時的な過負荷です」
「過負荷」
「はい。私たちのサービスは常時一千万人を超える接続ユーザ数を誇っています。一方で、バタフライの時間単位の増減はゆったりしたもので、特に一人のユーザにバタフライが集中するような状況はこれまで起きていませんでした。社会システムの成り立ちを考えれば、物理的時間的に縛られる我々のシステムがそう言った特徴を持つのは、当然のことです」
彼は言葉を区切って、説明を私が理解しているかどうか確認するような視線を向けた。エレベーターが開き、私は地下の駐車場階を押す。それで、と言うように私は彼を見た。
「つまり、その特徴を無視した瞬間的な負荷が、今回あなたがたのステージによって我々のシステムにかかった、ということです。事前の想定をはるかに超えた負荷です。それは愛の結実です。本当に素晴らしいことだと思います。しかし、結果として運悪くシステムのストレージが部分的に破壊されました。残ったキャッシュがごく一部のユーザに——」
「エドさん、拡張はオンにしていますか」
「拡張? はい。業務に使うので」
かすかな音がエレベータシャフトを抜けて聞こえていた。それは近づき、どんどん大きくなり、ぽおん、という間抜けな音がしてエレベーターの扉が開くと、私たちの小さな四角い部屋へと避けようのない洪水のように入り込んだ。地上のあらゆるものを破壊する災厄のまんなかにひとりきりで取り残されたシヅコの苦痛を、私は一瞬だけ味わった。顔にぶつかり続けるまぼろしの蝶にあきらかな痛みを感じて、自分の拳を強く握りしめた。
私は彼らをまっすぐに睨みつけた。
やがてドアは自動的に閉じ、蝶たちの濃さは薄くなった。拡張を切ってフーディエ社の階を押すと、エレベーターはゆっくりと動き出した。
「あの中に、私の大切なひとがいるんです」
エドさんはエレベーターの隅で、壁にもたれ掛かるようにして立っていた。かみさま、と彼が呟くのを私は聞いた。
「直して下さい」と私が言うと、彼は雷に打たれたように直立し、私をまっすぐに見ながら「必ず直します」とこたえた。
シヅコの寝室の扉と窓は完全に開け放たれていた。カーテン越しに淡い光がひそやかに差していて、はるか遠くを電車がかたかたと走っているのがわかった。
帰宅してからずっと、シヅコはベッドの端に座ったまま壁の本棚から一メートルぐらい横の空間をぼうっと見ていた。あるいは部屋にいっぱいの蝶を見ているのかもしれなかった。アイマスクは外されて、イヤーマフとマスクだけがシヅコを覆っていた。
その感覚のほとんどは、器具と投与された薬剤によって遮断されているはずだった。
私は彼女を見つめたまま後ずさり、緩慢な動作で洗面所に歩いて行った。真っ白なタオルに水を含ませて固く絞った。彼女の家で何度もパーティをしたことがあるから、どこに何があるのかすぐにわかった。戸棚に隠れた電子レンジを使って、濡れたタオルを短く温めた。
シヅコはずっと同じ姿勢で蝶を見ていた。どこかそれに魅入られているかのようだった。
一度広げたタオルを指先で撫でて温度を確かめ、シヅコの額にそうっと押しつけた。マスクを外し、その顔をやさしく拭って、それから服を脱がせた。そうして私は汗にまみれた彼女の身体を拭いた。
それが終わったとき、シヅコは目を閉じていた。眠っているのかいないのかわからないその寝顔に、私はベッドにもたれ掛かり見入った。うっすら濡れた額に張り付いた彼女の前髪を、何度か払った。
寝室の扉をそのままにしてリビングに戻り、私は拡張現実をつけた。蝶たちがシヅコの部屋から漏れ出る気配はなかった。ひらかれた窓のせいかもしれなかった。私はテキストチャットを立ち上げ、フーディエ社のインシデントログをひらいた。エドさんがそこのリードオンリーなアクセス権限をくれたのだった。数分前にエンジニアの一人が『彼女を対象とした新規のバタフライが生まれないようロックした』と報告しているのを見つけた。
私はそっとテ蝶を立ち上げると、新規ユーザー向けのガイドを全部無視して、トン、とアクティブモードを起動した。
そして私の身体から一匹の蝶も生まれないのを確認した。
「見たかったな、一度くらい」と私はひとりごとを言った。
目を覚ますと、最初に視界に入ったのはそのほとんどを覆う光だった。私は思わず顔の前に手をかざし、それがひらかれた巨大な窓から差し込む昼の太陽だと知った。九月も半ばを過ぎていると言うのに、室内はじりじりと焼けつくように暑かった。
光が強すぎて、すべてのものが白か黒に見えた。
「シヅコ」
シヅコはベランダに立っていた。
痛がっていつもサンダルを履いていたその床の上を、裸足で歩いていた。デッキチェアをよいしょと持ち上げて、その上に乗り込みやすいように位置を変えていた。
彼女は私にすぐに気づいた。手を振って、笑顔のまま、その手すりの上に、のそのそと登って腰掛けた。
私は嘘みたいにあかるい空を背にしたシヅコを見上げる。
「蝶、消えたの?」
「そうみたいですね」
「フーディエが消してくれたのかな」
「全部消えちゃいました」
手すりの上に立って、シヅコは私に笑いかけた。
「消えちゃいました」と繰り返して言った。そしてわずかに俯いた。
「ねえ、あぶないよ」
「私が誰かに愛されることってあるんでしょうか」
「あんなに蝶を従えていたのに」
「あれはお客さんです。私にはお客さんしかいないんです。だって私、アイドルだから……」
「降りてきて。どうしちゃったの」
「私が誰かにほんとうに愛されても、もうそれに気づくことができない。蝶がいても、いなくても」とシヅコは呟いた。
「愛してる、私が」
く、とシヅコは私の方を向いた。「嘘」と言った。
「ほんとうだよ。……私、シヅコのことが好きなんだ。ずっと言えなかったけど、でも、ほんとうなんだよ」
「じゃあ蝶を見せて」
私はテ蝶を立ち上げる。灰色になっているアクティブモードのパネルを何度も押して、私から絶対にそれが生まれないのを知る。
「きっと」と操作パネルを震える指で押し続けながら、「ロックされてるんだよ、だから出ないんだ。シヅコ」と私は言った。
「ねえ、降りてきて。信じて」
シヅコは微笑んでいた。その恐ろしいほど明るい審判の中心に立って、「ねえ」と私が言い続けるのを見つめていた。
「嘘です」と彼女は言った。
「シヅコ、信じて」
「……だって蝶がいません」
そのままゆっくりとシヅコは後ろに倒れていった。私がまっすぐに伸ばした手は何もない空間を掴んだ。はるか下の地面に落ちて、彼女の身体からはつぶれた蛹から漏れ出るそれのようにこの上なく悲しい液体が広がっていった。低く、長い、まっくらな悲鳴を私は聞いた。それが自分の声だとはとても思えなかった。
「ああ!!」
自分が上げた絶望の声で目が覚めて、私は桃色に輝く渦のただ中にいることを知った。何もかも恐ろしくて、身体が自由に動かなかった。
「やだ! いやだ!」
よろめきながら立ち上がって、腕を大きく振った。ぐわっと空間がゆがんで、それだけだった。耳の後ろをぎゅうっと押す。何も起きなくて、私は混乱した。
嵐のまんなかで、私はたった一人で立っていた。逃げられなかった。どこにも逃げ道はなかった。私は小さな虫だった。名前のない愛たちによってバラバラに羽を毟られようとする、かわいそうな蝶だった。食いちぎられないように縮込めていた手を、わずかな希望を求めてぶうんと振った。何か固いものにがつんと当たって、私は蝶以外に初めて触れたそれを必死で掴んだ。
それがシヅコだった。
彼女は腕をしっかりと私に絡め、やわらかい身体でぎゅうっと私を抱いた。私たちは床に転がって、お互いのすべてを守るように必死に抱き合った。
私は自分が号泣しているのを知った。熱い液体が彼女の肩のあたりをどんどん濡らしていた。ああ、と言う泣き声は、身体の内側にずしんと響いた。シヅコの耳元でそうしていたから、彼女の中にもそれが響いていたかもしれなかった。
どれくらいそうしていたのか、わからない。
目をひらくと、私たちはいつのまにか離れていた。床に座りこんだシヅコが寝ている私を見つめていた。私はそのまま部屋を見渡した。あたりは静かで、暗かった。シヅコだけがうっすらと輝いているように私には見えた。
「レイちゃん」
ふっと彼女に視線を戻した。一匹の蝶が、シヅコの背後で小刻みな直線を描いて飛んでいるのが見えた。
「ありがとう」と言うと、シヅコは微笑んだ。
彼女はその蝶を見たのだろうか。
うねるような感情に押しつぶされそうになった。シヅコに向かって手を伸ばし、しがみついた。
震える腕で彼女を抱きながら、私は泣き続けた。蝶がいつまでも消えることなく舞っていた。
0 notes
Text
窓際、快晴、風強し / なおかれ(モブ視点)
「ヒナ」
二限目のノートを引っ張り出しているとき、マチに話しかけられた。「イインチョ」と返すと、マチは「委員長はやめて」と顔をしかめた。
「イインチョは委員長じゃん? 二学期連続」
「私がメガネだからってみんな適当に投票するから、そういうイミワカンナイことになるんだってば」
マチはため息をつきながらそれを外して、「コンタクト、怖いんだよなあ……」と赤く細いフレームを睨みつけた。「あたし、イインチョのメガネ好き」と言ったあたしをマチは無視する。
そうは言ってもみんなが適当にマチに投票してるわけじゃないのをマチもわかっている。まともな進学校というのはそういうものだ。マチがどうしたって世話焼きで真面目でうまいこと色んなことを決められるコだってことをみんな知っていて、だから彼女は毎学期けっきょく委員長に選ばれてイインチョと呼ばれはじめる。
あたしは彼女が片手に持っている紙束に目をやりながら「どうかしたの」と聞いてみる。
「北条さんって来てない?」
「んー、たぶんまだ来てない」
あたしの席は一番うしろの廊下側だから、誰が来ていて誰が休みで誰と誰が喧嘩中で誰がひとりぼっちかすぐにわかる。「そっか」と小さな声で言って、マチはあたしの前の席に勝手に腰掛けると憂鬱そうにはああ、と長いため息をついた。
「なんか失敗?」
「そういうわけじゃないんだけど……んんん」
マチは机に突っ伏して、とん、とん、と何回かあたしの脚を蹴った。あたしは彼女の視界の外で微笑みながら、そっと彼女の軽く巻かれた髪の端っこを持ち上げた。
「……ねえ、北条さんってさ」
「うん」
「こわくない?」
「こわくない」
脚を蹴るのが止まって、やがて再開された。とんとんとんとん。あたしの拒否をとがめるように早く、少し強くて、だからかわいらしい。
「……私、委員長だからさー」
「うん」
「四月から北条さんに何回も何回もプリントまとめて渡してるの。でもずうっと、なんていうか、そっけなくて」
「あはは、ちょっとわかる」
マチは顔を上げてあたしを見つめる。「北条さんって――」と彼女が言いかけたとき、あたしははためくカーテンを写すマチの瞳をまっすぐに見ている。そのまま「北条さんってきれいだよね」と彼女はあたしに呟いて、その言葉によってあたしたちふたりともが受ける浅いひっかき傷のような何かをあたしは感じる。
「まあそりゃ、芸能人だし」
「爪の先まですごくかわいい」
「あー校則違反、誰も注意しないよね。かわいいから」
あたしがへらへら笑うと、マチはうつむいた。
「……テレビでいつも明るく笑ってる��とに、そっけなくあつかわれるのは、やりきれない」
そう言って彼女はそのまま黙った。
教室の騒がしさからあたしの机はもっとも遠くにあるから、何もかもがよくわかった。あたしはそっと彼女の手にてのひらを重ねて、やさしく指先を握った。マチの眼差しがあたしの指先を確かめるように撫でていくのがわかった。プリントを握った手にはきゅうっと力が入っていた。
あたしはすっと息を吸って、にこりと笑った。
「ね、マチ。スマブラさあ、小学校のとき一緒にやってたよね」
「……何、急に」
「今もやってる?」
「弟はやってるけど……んー、ごめん。実は今もけっこうやってる」
「じゃあ、やればいいんじゃない?」
「誰と?」
「北条さんと」
マチはあたしに視線を戻して、あたしがこれまで一度も見たことがないような変な顔をうかべて「は?」と言った。
「マチは知らないかもしれないけど、北条さん、スマブラやる相手を探してるんだよ。ゲーム好きな子たちにちょっとずつ声かけてるみたいなんだけど、でもみんな今はイカのゲームやってるから」
「……北条さんが、スマブラ?」
マチは背筋をピンと伸ばすと、顎をつまんでふうむ? みたいな顔をした。
「ぜんぜん想像つかない?」
「ぜんぜん想像つかない」
「あたしも想像つかない」
「馬鹿にしてんの?」
あっはっは、とあたしは笑う。「ほんとだよ。北条さんは、困ってる。一緒にやってる友だちが強すぎるからこっそり練習したいんだって」と頬杖をついた。
そのとき、さあっと風が吹き抜けた気がした。あたしたちのうしろを「おはよ」と言いながら、彼女が通っていったのだった。
「おはよー」とあたしはあいさつを返して、マチは無言で見送った。「行きなって」とあたしは言った。ぽん、とてのひらでマチの手を叩くと、はく、と彼女は口だけ動かした。あたしはこつこつ彼女のちいさな腕時計を指で叩いて「時間」と促した。
それでマチは行ってしまう。
あたしは笑顔で彼女を見送る。マチは北条さんの席にたどり着いて軽いあいさつをしたあと、プリントをさっと渡す。北条さんはいつもの固い表情でそれを受け取る。北条さんはそういう負い目を感じるような瞬間がとても苦手に見える。マチの面倒見の良さには押し付けがましいところがあるから、それで北条さんは少しずつマチのことが不得意になる。
でも次の瞬間、マチがふたことみこと何かを言うと、北条さんは口元を抑えて、全身によろこびがあふれる。あたしはそれで安堵とともに、冬の夜を思わせるような寒々しい気持ちがあたしの中にあらわれたことに気づく。なんとなくその先を見たくなくなり、「さて……」とわざとらしい声を出しながらトイレに行こうと席を立ったとき、「松代さん!」と大きな声があたしのことを呼んで、それを発したのは北条さんで、彼女はまっしろにはためくカーテンの向こう側から太陽の明るさで光りかがやきながら「松代さんも一緒にやろうよ!」と叫んだ。
2 notes
·
View notes
Text
光がすべて / なおかれ
こち、と動き出した鳩時計には光を感じるセンサーがあった。鳩は夜中でも明るければ動作するし、昼でも暗ければ動作しなかった。光がすべてだった。
その部屋に灯った八個の光は電球色に統一され、白いはずの壁はあたたかい春のようすで照らされていた。少しだけ干された夏草のような色をした鳥小屋の中から、鳩はどことなく愉快そうにぱっぽうと声を上げた。時刻が午前四時半になったことを理解すると、奈緒はおもむろに立ち上がり、その夜の就寝前からずっとちいさく鳴っていた音楽のヴォリュームをさらに絞った。曲はリヒャルト・シュトラウスが人生のおわりに書き上げた歌曲のひとつだったが、奈緒はその歌についてなにも知らなかった。ただ少し、今聴くには華やかすぎるかもしれないと感じていただけだった。
奈緒はちら、とベッドの上に目をやる。
ごうごうという暖房の音。
窓際に配置されたクッションの上で二十分ほどぼんやりと過ごしていた奈緒の身体は冷えていた。外気はこの冬初めて零下になろうとしていた。部屋からつづいている、廊下を兼ねたまっくらな台所で奈緒が冷蔵庫をひらくと、やわらかそうな寝間着があおい光に照らされた。また、暗くなる。牛乳が戻され、また、暗くなった。部屋のほうから差す光は微かで、その下で奈緒は慎重にメイプルシロップをカフェボウルへ注いだ。あとはあたためるだけでホットミルクになるそれは電子レンジにかたりと固い音で置かれた。扉が閉じられる。
レンジを操作するためのディスプレイは明るい。
奈緒はそれに照らされたまま、無表情に、「頭、冷えたか」と聞いた。
加蓮は「あたま、ひえたか?」と聞き返した。ぎゅうっと握りしめていたいるかのぬいぐるみをベッドから奈緒の足元へと思い切り投げつけ、「あたまひえたか?」ともう一度繰り返した。いるかはそのまま廊下をすべっていき、玄関のまだ濡れている奈緒のブーツに当たった。奈緒はそれをぼうっと見送った。
「そうだよね、私だけが怒ってるんだもんね」と加蓮は呟くように言った。
奈緒は加蓮に向き直って、
「あたしは怒ってないよ」
「わかってるよ!」
加蓮が悲痛な声で叫び、布団に顔を押し付けたので、奈緒は「静かに……」と囁きながらゆっくりと近づいた。加蓮は今度はオレンジ色をしたイカのぬいぐるみをベッドから拾うと、ふたたび奈緒に投げつけた。それは奈緒の肩をかすめて、壁にぶつかった。
「私だけが怒ってる。私だけが怒ってる! いつも、いっつもそう!」
「加蓮」
「いつからだかわかる?」
ごうごうごう。
「……あたしが、大学に上がってから」
「みじめな気持ちになるの! 奈緒がそうやって、私を、子どもみたいに……」
加蓮はまたうつむいて、毛布を拾うと顔を拭った。
奈緒はついにベッドへとたどり着くと、やさしげな声で、
「心配なだけなんだよ、加蓮」
「しんようがない」
加蓮のうめき声はほとんどが毛布に吸い込まれてしまい、奈緒の耳には届かなかった。奈緒は顔をしかめると、「なんだって?」と聞いた。
加蓮は「私は奈緒に信用されてない」と言った。あまりにもありえないことだったので、奈緒は微かに笑って「まさか」とこたえた。「だったらなんで、だめっていうの?」と顔を上げた加蓮の両目は、冬の海のようにきらめいていた。奈緒はそれがうつくしすぎると思ってこわくなった。それでも、す、と正しく息を吸った。
「さっきも言っただろ」
「もう一度言って」
「明日は大事な模試がある」
加蓮の喉が悲しげに鳴った。「……信用ないんじゃん」
「心配なんだよ」
「それもさっき聞いた」
「身体に負担がかかるだろ」
「私、もうそんなにやわじゃないよ」
「だからさ」
奈緒は半分笑いながら、
「信用ないとかじゃなくて、そんなこと、やってる場合じゃ――」
「どうしてそういうふうに言うの」
加蓮の眉がハの字に寄せられて、「私たちが触れ合うことを、なんでそういうふうに言うの?」と言った。
「そんなにいけないことなの?」と聞いた。
「なんでだめなの?」と、繰り返し質問した。
暖房が自動的に停止すると同時に音楽が止まり、次の曲が呼び出されるための短い時間があった。奈緒の顔に向けられる加蓮の眼差しには全霊が込められていた。それらをしっかり受け止める瞳、はっきりとした鼻梁と、凛々しく意志に満ちた眉を加蓮は感じていた。
奈緒はじっと加蓮を見つめたあと、「これがリハーサルの前日だったら、どうしてた?」と聞いた。
くうっと胸が動揺にうごめいて、こほ、と咳が漏れた。沈黙のうちに新しい曲が流れた。ショパンのピアノに合わせて、加蓮は小さな声で「ずるいよ」と言った。奈緒はみずからの中に溢れようとするあらゆる否定の言葉を退けると、加蓮の手のひらをこれ以上無いほど誠実に握った。
それは苦しみに満ち、汗にまみれていた。
「私、真剣にやってるよ、奈緒」
「うん」
「ずっと、判定、合格圏内のままだよ」
「うん、知ってる」
「先週の公演で、私、センターやったとき――」と言って、あとは言葉にならなかった。奈緒は目に小さな涙を浮かべて「すごいよ、加蓮は」と言うと、そのまま愛する人を抱きしめた。涙混じりに「さっき、蹴って、ごめん」と加蓮が短く謝り、奈緒はすべてが込められたキスで答えた。長いそれが終わって「もう、寝る」と加蓮が言った。奈緒は準備していたホットミルクを諦めて、暖房の温度を上げた。ごうごうという音がまた鳴り出した。
二人は電気を消して、やさしく抱き合った。部屋には深い眠りが満ちた。
午前五時になったとき、鳩は鳴かなかった。
そのとき、光がすべてだった。
0 notes
Text
内臓の色 / かなふみ
大切なものが致命的に失われてしまったとき、ひとが上げる声はけっこう間抜けに響く。そのときの文香が上げた「あ」という悲鳴も相当のものだった。その声は別室でリズムゲームをしていた奏の耳にも届いたので、彼女は「どうしたの?」と言いながら数個のミスと引き換えに停止ボタンを押して文香のいる寝室兼書斎を振り返り、その惨状を見て「わあ」とらしからぬ感嘆の声を漏らした。
文香が三十分ほど前から机に向かっていたのは、来年上梓される単行本の帯文を快諾してくれた友人に礼状を書くためだった。リビングにあるコレクションの棚からウイスキーボトルと下ろしたてのインクをいそいそと取り出すとき、文香の陽気な鼻歌に奏は短く唱和していた。二人が台湾へと旅行したときに購入した特別なときにしか使われないはずの青黒いそれは、今や現れたばかりの暗闇に溶けていく海のように完璧な広がりで床を覆いつつあった。文香に万年筆を引っ掛けられて落ちてしまったガラス製の容器の中では、繰り返し断末魔を上げているかのように僅かな残りが揺れていた。
「……やって……しまいました……」
文香のぼうっとした口元はどこか誤魔化すように子どもじみて緩んでいた。「笑ってる場合!?」と叫んだ奏がキッチンペーパーをくるくると巻取りながら戻ってくるまで、文香は呆然とデスクの前のオフィスチェアにただ座っていた。十分な量を手に取ると、奏は苛立たしげに残りを文香に投げつけた。
フローリングの目地に染み込んでいった黒色がいくらとんとん叩いても全く落ちないのを見て、奏はまっくろになったそれを投げ出すと「もう!」と大声を出して両手の指を広げ、身体の内側で膨れていく怒りをどうすることもできないという感じに振った。長期に渡る撮影に向けた役作りで軽く伸ばし気味にしている髪の毛を苛立たしげにかき上げ、奏はキッと文香を見上げた。
「二回目!」
「……はい……」
「前のとき、私がなんて言ったか覚えてる?」
文香がじいっと奏の顔をただ見ているので、奏の頭にはかあっと血が登って、指先は憤怒に震えた。怒りを感じたときの職業的な反射で口角を少し上げて笑った表情を作り、奏は「お酒を、飲みながら、書くな!」と言葉を区切りながら強い指示をあらわして叫んだ。
「奏さん、奏さん」
「何!?」
額に、ついていますよ、と、文香は自分のおでこを指しながら囁いた。奏はパッと視線を移して大きな姿見に映っている自分の姿を覗き込んだ。感情が昂ぶって、目元には少し涙が滲んでいた。文香の言ったことは正しく、髪の毛をかき上げた時に生え際へと一筋のインクがついていたのだった。奏が一瞬、なぜ私がこのように汚れなければならないのだろうか、これは私がほんとうに人生に求めていたことなのだろうか、とみずからに問いかけたまさにそのときに、文香が一歳を過ぎたばかりの赤ちゃんのように汚れた床へまっすぐに手をつけると、それをそのまま奏の頬にぺたりとつけた。
「……は?」と、奏はこめかみをぴくぴく動かしながら文香を見つめた。
「あはははは」と、文香は白痴のひとのように笑いながら奏を見つめた。
湯船に溜まっていくお湯の音を聞きながら、奏は洗面所の前に上半身裸で立ち、まっくろに汚れた乳房を眺めていた。その身体にはそこら中に点々とてのひらのあとがついていた。ポロックの絵のような柄になったカシミヤのセーターを諦めたようすで床に放り、シンクの縁に手をかけると下を向いて滅茶苦茶に長いため息をついた。
「……お、こって、ます、か?」と、恐る恐るというように廊下の角に隠れながら文香が言ったので、く、と短く笑うと、「こっちに来て」と奏はこたえた。神妙にやってきた文香の頬に向かって、まだ少し汚れている手を差し出しながら「お風呂、一緒に入りましょう」と言ったので、文香は「すみません、でした……」と消え入るような声で謝った。
奏は一瞬不思議そうな顔をすると、「舌、出してみて」と文香に言った。文香は、えうう、といささか長すぎる舌をいっぱいに伸ばし、奏は、くは、と笑って「ハラグロ」と言った。
文香の舌と口腔がきわめて長い夜のようにくろぐろと染まってるのを見て、奏はもう一度、「ハラグロ文香」と、笑いながら言った。
0 notes
Text
焼きそばハロウィンはいかにして無敵のアイドルになったのか(4)
1 https://tmblr.co/ZlZBMe2cy-9bD
2 https://tmblr.co/ZlZBMe2dBfNbl
3 https://tmblr.co/ZlZBMe2dUJ5V-
ごう、という音とともに点滅する文香の顔に向かって、美嘉は「なに?」と大きな声を張って聞き直した。「すみませんでした!」と繰り返した文香の声のあとを追って、たたん、たたん、と軽い音で電車が通り過ぎてゆき、「もういいって言ってるでしょ」と、美嘉は笑みを浮かべて安心させるように言った。騒々しいほどの客車の明るさが去るとあたりは暗くなり、二人の後ろで志希がおもしろくなさそうに小石を蹴った。転がったそれは排水口の暗闇へと吸い込まれていった。
三人はそれぞれ手にトートバックを持って公衆浴場へと向かっていた。バッグの中には着替えとタオルが入っていて、文香は自分のそれを大事そうに両手に抱え直した。彼女のバッグにはあの青い本が今も入っていて、片時もそれを離そうとしないのだった。
「本当に、申し訳ありませんでした……」
「だーかーらー、アタシなんもしてないよ。むしろ怒りすぎちゃってごめんって。文香さんがのぼせちゃってるなんて思ってもみなかった」
文香が顔を赤らめて下を向き、美嘉は苦笑しながらパーカーのフードを少し上げて、歩みを進めた。
「大家さん、テキパキなんでもやってくれてすごかったなー」
「……矢張り、普段から美嘉さんが、周りの人々と良い関係を築いていていらっしゃったので」
「いやいや……それにしてもよくダクトテープなんか持ってたね、志希」
「ふふーん、世の中のすべての故障はダクトテープとハンマーで直せるのだ」
カーディガンからハンマーを出したり引っ込めたりする志希を見て、
「どこから出してくるのよ……」
「ぱかぱぱん、四次元スカート〜」
志希がにゃはは、と笑ってぴらぴらスカートをめくったので、美嘉は真っ白な下着から目をそらしながらもう注意するにも疲れたという声色で「あっそ……」と言って前に向き直った。
数歩歩いて、あっ、と美嘉は重大な事実に気づいたように言った。
「喧嘩してた理由を聞くの、忘れてた」
二人が歩きながら顔を見合わせたのを見て「もう仲直りした?」と美嘉は聞いた。
「いいえ……」と文香が言った。「聞いて聞いて〜」と志希は母親に告げ口をする子どものようすで答え、美嘉の���を捕らえたために「ん?」と美嘉は注意を向けた。文香は慌てて「ちょっ、と、志希さん!」と嗜めると、志希の手を捕まえてその身体を無理にひっぱり、「いたっ、いたたたた。もーっ、なに?」と悲鳴を上げ続ける志希を線路沿いの緑の金網にがしゃんと押し付けた。
秋の少し冷えた空気にぼんやりと光輪をつくる街灯の光で二人の姿は明るく浮き上がっていた。
「何を、美嘉さんに言う気なのですか」
「んんー?」
大きく欠けた月のかたちで楽しげに歪んで見上げる志希の眼を、文香は不快さに満ちた瞳で見下ろした。
「……美嘉さんは、あなたのことを、わかっているのですか」
美嘉に聞こえないような、小さな声で文香はぼそぼそとしゃべった。美嘉は数歩離れた薄暗い路上から文香と志希を見ていたが、微かに不安の滲むその表情に二人は気づいていなかった。
「人同士が完璧にわかりあえるなんて幻想だよね〜?」
「……いい加減に……!」
「美嘉ちゃんは知らないよ」
志希は急に真面目な顔をして言った。早口に、文香に呼応するような微かな声で、
「あたしのママが死んでいったことは知っている。あたしのママが本当のママとは言えないこともうっすらと知っている。でも、それだけ。文香ちゃんのことも言うつもりはないから安心して」
文香は口を微かに開けて何かを言おうとした。しかし、ついにそれを遮るかのように「二人とも……」と美嘉が声をかけながら志希と文香に一歩、二歩と近づいた。
「文香ちゃんさー! あたしのママのこと、わるものあつかいしたの!」と志希が急な大声で言った。
「なっ……」と文香は志希を睨みつけ、美嘉は訝しげに「どういうこと?」と答えた。
カシャリ、と志希は金網から離れながら、
「あたしのママがあたしのことを殺そうとしているところを想像しろって。ママがあたしに、愛情なんか抱いてないってところを想像しろって――」
「志希さん!」
文香は志希を大声で遮り、はっと美嘉の方を振り向いた。美嘉は押し黙って文香のことを猜疑の目で見つめていた。文香は拳をぎゅっと握りしめ、下を向いた。追い詰められた動物が最後の一瞬に力強い反撃をするように、「志希さんだって、私のおかあさまのことを、悪くないと言いました!」と大きな声で言った。
「私のことを守るためだって。全部私のわがままだって。私の、本を、すべて燃やしたひとなのに……」と微かに震える声で続け、そのまま何も言えなくなってじっと美嘉の青いスニーカーを睨みつけた。
美嘉はフーッと疲れた息を吐くと。「志希」と言った。
「文香さんに謝って」
文香は志希の喉がぐっとなる音を聞いて顔を上げた。「なんで!?」と志希は信じられないものを見た顔で美嘉を睨みつけた。ぶん、と腕を振って「あたしのママが! あたしのことを……愛してないところを想えって言ったんだよ!」と美嘉に主張した。美嘉は「アンタ、火事にあった人にそんな喧嘩のふっかけ方はないよ」と言った。
「……それが理由なの……」と志希は、心底から絶望した声をあげた。
「そんなのが理由なの!? おかしいよ!」と繰り返した。
「文香さん」
美嘉は志希を無視して、文香に話しかけた。は、と志希が絶句するのを文香は感じながら、まっすぐに美嘉が自分を見つめているのを見返した。
「やっぱり、警察に行こう」と彼女は言った。
「……いいえ。説明ができないと、先ほど――」
「火事。消し止められたから良かったよね。でもさ」
美嘉は腕を組み、すっと息を吸った。「フツーに考えて責任があると思う。人が死んでた可能性だってあるんだから」
「美嘉さんはあの人の責任を私が担うべきだと、そうおっしゃるのですか」
「違うよ、ただ説明を――」
「おかあさまはと私はもう何の関係もありません」
文香が言って、静けさがあたりを覆った。志希がじっと文香を見つめたまま、怒りの炎が胸から溢れそうなようすで、「なんでそんなこと言うの……」と呟いた。
そのまま三人はしばらくの間押し黙っていた。はるか遠くにある歩行者信号が点滅しているようすが志希の青く潤んだ瞳にてんてんと映っていて、やがてそれは赤になった。拳が握り込まれて、「ねえ……」と、爆発寸前のようすで志希の声が発せられたとき、「妹が昨晩死んだと、おかあさまから、聞きました」と文香が言って、く、と指は緩められた。
眉をしかめて額に指を三本当てると、すぐにそれを離して顎に寄せながら、「どういうこと?」と美嘉は聞いた。文香は視線を落とし、ガードレールの根本をゆっくりと順番に見つめ、やがて「鷺沢の家には、あるものを守るというお役目があって、それで死んだのだと……おかあさまが殺したも同然です」と言った。
「小さな子どもだったのに……かわいい子だったのに、おかあさまがお役目に出して……」
「……ごめん、ちょっと意味がわからないんだけど……」
美嘉は文香の言ったことをとんとんと顎先を叩きながら反芻した。そして、「文香さんは、その『お役目』をなんでやっていなかったの」と聞いた。
「……叔父を頼って、上京したのです」と文香は言った。顔を上げて、美嘉をまっすぐに見た。
「私は鷺沢の家でもともと持て余されていました。家は寺付きで、小さな頃から、お経ばかり読まされていたのですが……私は幾度となく規範を破って、本を拾っては、取り上げられて……。もっといろいろな本が読みたくて、どうしようもなくなったんです。同じように家を出た叔父を頼りました。しかし……」
文香は言葉を区切って、今気づいたばかりのあらたな事実に心が動き、すべてが溢れ出すようにきらきらと目を輝かせた。
「私は本も、アイドルも……本当はおかあさまに許されたくて、ずっと心に刺さった小さな針のような……でも、もう関係が、ないのですね」
「なぜ」
「母は本を燃やしたあと、私を勘当したんです。家には帰らないと言ったから」と言って、文香はふわっと笑った。
「そう……もう私には関係がないんです。つながりが、ないんです。おねがいしなくてもいいんです! 美嘉さん、私はアイドルを続けられるようになったのです。ああ……そうか……きっとすべての本と引き換えにそれが――」
「妹さんの名前は何ていうの?」と、美嘉が文香を遮って言った。いつのまにかその目蓋は閉じ、眉はしかめられ、軽く握られた手が額に添えられていた。一秒、文香は口元で笑ったまま、おさないきょとんとした表情を目に浮かべ、「シロ、と言いますが……」と言った。
「そう」と美嘉は言って、きっ、と顔を上げた。
「シロちゃんのこと、文香さんが殺したようなものじゃない?」と美嘉は静かに言った。
文香はびくりとして、は、と口をひらいた。あの屋上で母親と別れる寸前に放たれた言葉が、再び目の前に現れて言葉を失ったのだった。
「役割があったんだよね、それを文香さんは果たしていなかったということになるよね。姉として妹を守っていなかった。文香さんがずっと一緒にいれば、シロちゃんは死ななかった」
「あの……鷺沢の技は末子が……一番小さな子が受け継ぐ取り決めで、その……なるべく長く技を伝えるために――」
「なんでお葬式にもいかないの?」
「……鷺沢は……多産多死の家系なんです。葬儀などは……あの、美嘉さん――」
「文香さん、シロちゃんのことどうでもいいと思ってない?」
少しずつ傾いていた深皿からついにスープがこぼれ落ちるときのように「ねえ」と志希が切ない声を上げたのと、文香が今にも泣き出しそうな表情を浮かべて「美嘉さん、あなたには、おそらく、お分かりにならないかと……」と呻くように言ったのは同時だった。
美嘉は一見何もかも興味がなくなってしまったという目線を文香に向けたまま、だらんと落としていた腕を腰に当てた。「はいはい」と彼女は冷めた口調で言った。
「アタシ、家ってのがなんなのか知らないんだよね。物心ついたときには施設にいたから、親とか、家族とか、いないしさ」と美嘉は言った。文香が「え……」と漏らした呻き声は、そのあとしばらく三人の真ん中を漂っていた。
「なんで分からないって言うの」と新たに投げかけられた声は、徐々にどうしようもなく膨らんでゆく怒りを隠しきれず、微かに震えていた。
「なんでアタシには分からないって言うの? 親がいなかったらそんなに馬鹿に見えるの?」
「美嘉ちゃん」と、たまらず志希が声を上げると、「志希も志希だよ」と美嘉は志希を睨みつけて言った。志希は、く、と言葉を飲み込んで、黙ってしまった。
「どうせアタシが何も分かんないからって二人でコソコソ話してるんでしょ。分かったよ。もう分かった」
「……違います……」
「分かったってば」
美嘉はいやらしく、にぃ、と笑った。フードをぐっと下げると、その表情は口元を残して影に隠れ、まっくらになった。
「馬鹿らしくなってきた。いいよもうなんでも」
くるりと文香に背を向けて肺に溜めていた息を怒りと共に吐き出した。そのまま文香と志希を置いて、美嘉は線路を渡る陸橋へと向かってゆっくり歩き出した。
かし、と軽い音で金網を掴み、文香は少しずつ下を向いていった。美嘉が着ている黄色のパーカーは徐々にぼやけて視野の外に消え、緑に塗られた路側帯にはやがて短い銀色の糸のようにぽたぽたと涙が落ちていった。ふ、ぐ、と繰り返し現れる嗚咽が呼吸を難しくさせて、きれぎれのそれにはやがてしゃっくりのような響きが混じった。文香は自分の何もかもが恥ずかしくなって、どうにかして消え去ろうとかがみ込んだ。トートバックの中で、美嘉に借りたタオルと共に微かに息づいていた本の存在は忘れられてしまった。立ちふさがった巨大な孤独の壁を追いやるかのように、膝に目頭を押し付けると、圧迫された眼球が篝火のように赤く染まった。そのまま文香は苦しい呼吸だけをひ���すらに続けていた。
そして、やさしく肩を叩くひとがいた。
文香が顔を上げると、そのひとは街灯の天輪を浴びて神々しく立っていた。涙の膜がそこにある光すべてをうっすらと混ぜ合わせていたので何もかもが明るく見えた。彼女が何かを差し出していて、文香はほとんど反射的にそれを取った。「落ち着いたら、追いかけて」と、志希が真剣な目で言ったので、文香はぼうっと痺れた頭で言われたことを理解すると、ゆっくりと頷いた。
たっ、と志希が駆け出していって、文香はそれを見送った。
少しだけ開いたセロファンの袋の中から、半分に切られた石鹸がいたわりに満ちた香りを発していて、文香はすん、と鼻をすすった。
陸橋を登る階段の周囲には街灯は少なく、美嘉はすでにそれを登りきったのか、どこにも姿は見えなかった。たんたんたんというダンス音楽めいた足音と自分の呼吸音を聞きながら、志希は軽く腕を振って階段の上を見上げた。まっすぐに伸びたその眼差しの先には大きな丸い月が出ていて、その眩しさに志希はキッと目を細めた。そしてその光の先を見据え、黄色いパーカーが陸橋の半ばよりもさらに遠くへと歩みを進めていたのを見た。
「美嘉ちゃん!」
志希が必死に上げた叫び声が確実に届いているはずなのに、美嘉は止まらなかった。一人で孤独に先を急いでいるようなその後ろ姿がひどく悲しげに見えて、志希の鼻先につんとする感覚が現れた。それでも、彼女がスピードを緩めることはなかった。志希の走るスピードはいつも遅く、小さな頃はそれでよくクラスメートにからかわれた。しかし、彼女は常に自分の肉体を完璧にコントロールしていたのだった。志希は必ず誰よりも長く走り続けることができたし、必ず自分が設定したゴールにたどり着くことができた。
「美嘉ちゃんってば!」
階段の一段目を右足で踏んだ美嘉を捕まえたとき、激しい勢いでその手は振り払われて、半分の半分に切られた石鹸は陸橋の隅へころんと落ちた。美嘉はそれを目で追ってはっとすると、「アンタ……」と言って志希を軽く見上げた。今や志希の瞳は激しく燃え上がり、彼女のそれよりも上にあった。はっはっはっと短く漏れていた彼女の息は、ぐっと飲み込まれたつばきで途切れ、志希はかがみ込むとその汚れてしまった小さな固まりを拾ってついた土を払った。
美嘉の瞳は罪悪感でいっぱいになり、こちらに向き直った志希から逸らされた。眼下の線路は近くにある駅やその先まで果てしなく伸びていて、どこかにある光源から現れ続ける冷たい光を反射していた。視界にまっすぐ伸ばされた志希の石鹸が入って、美嘉は志希へと激しい勢いで向き直ると、「いらない!」と言った。
「どうせ、志希だって……アタシのこと……分かってないくせに!」
強い口調で言ったあと、志希のまっすぐな視線を受け止めることができなくなって、ふら、と揺れた。ついには目蓋が閉じられて、「アタシが……今朝、ひとりで、どれだけ不安だったか……」と、呟きが漏れた。その言葉があまりにも強い痛みと共に発せられたので、美嘉は今の瞬間いかに自分が自分を嫌悪しているのかはっきりと分かった。自分が情けない、と思ったのだ。情けない、情けない情けない! こんな愚痴を言ってもどうしようもないのに!
自分が情けない!
「ごめん」
はっと目がひらかれて、ばっと志希を見上げた。心遣いの乗せられたその言葉に反して、志希の瞳が怒りに満ちているのをはっきりと感じ、心臓の近くに現れたおそれが美嘉を呆然とさせた。短い間目をつぶっていたせいで、志希は現実の彼女の姿よりも明るくきらめいて見えた。志希は、激怒していた。暴れるたましいがくるくると自由を求めて喘ぐ髪の先々まで行き渡って、背後から彼女を照らす月の光は真っ赤にその輪郭を縁取っていた。美嘉はその震えと気高い光に、燃え上がる炎を想起した。
「ちゃんと聞いてあげて」
「え……」
志希はまっすぐに陸橋のもと来たほうを指差した。
「ちゃんと、文香ちゃんの言うこと、聞いてあげて!」と志希は叫んだ。動こうとしない美嘉の手を掴み、無理やり自分と同じ高さに持ち上げた。すぐ近くでまだ荒く吐かれる志希の呼吸が、その苦しげな合間合間にありったけの願いを乗せていることに美嘉はやっと気づいた。それと同時に、志希が激しい口調で叫んだ言葉の意味が身体の中心を貫いていった。美嘉の手を引いてぴたりと動かないその右腕は、今、陸橋の真ん中よりも少し向こうで跪き、こちらを見ている女性を差していたのだった。
志希は美嘉の手を掴んだまま、たっ、と走り始めた。
道を誤った人は、自分がどこにいるかわからなくなってしまうために、正しい道を見つけるにははじめよりも時間がかかる。しかし美嘉の場合は、志希の力強い足の運びが、とん、と美嘉に軽い最初の一歩を歩ませて、そのまま、たん、たん、と、軽く文香の元へと走ることができた。
跪いていたはずの文香は、美嘉がそこへと辿り着いたときには、みずからの肩を抱きかかえ、道に額を擦り付けんばかりに頭を垂れていた。美嘉はどうすれば良いか分からないまま数秒の間彼女を見ていたが、やがてその場に膝を付いた。
「……お詫びします……先程、美嘉さんに申し上げた、こと……」と、文香は海鳴りに似た低い声で呟いた。
文香さん、と微かな声で投げかけられた呼び名と、伸ばされた手は、志希の手のひらがやさしくその背中に触れたときには受け入れられていたにも関わらず、緩やかに振られた頭で拒絶された。
「でも」
文香はそっとその土から顔を上げた。あらゆるものの底からほんの少しだけ高いところから、美嘉を見上げて、「私がいけないのですか」と問いかけた。
何もかもがその言葉に込められていた。怒りや悲しみとともに、まっくらに塗りつぶされた未来への恐れがあった。それらがないまぜになった色濃い暗黒色に輝く瞳は、ぐ、と美嘉に息を呑ませた。その瞬間、バシィン、という高い音が地響きと共に現われて足元を揺らし、同時に激しい点滅があたり一帯を覆った。フードで守られていた美嘉の頭部は一瞬で暴かれた。ぐるっとゆるやかにすべての世界が自分と文香を中心に回転しだしたことに気づいて、美嘉はそれがなぜなのかを一瞬で悟った。二人の足元で巨大な長い列車が交錯し、運命が回り始めたのだった。万物は二人を軸にして、まるで二台の列車に無理やり回転させられる巨大なひき臼のように回った。天体の運行にも似たそれが大気を揺るがす轟音よりも遥かに大きな声で、「鷺沢の家に産まれたことがそんなにいけないことなのですか!?」と文香が叫んだとき、美嘉はその姿が三歳ほどの小さな女の子にいつのまにか変わっていたことに気づいた。彼女は、よく見知った人物だった。
まさしく彼女は、美嘉自身だった。
物心ついたころ、美嘉はテレビっ子だった。年少だった美嘉のために施設のテレビのチャンネル権は頻繁に与えられ、それは常に歌番組を映していた。美嘉はいつもテレビの中で歌うひとびとの真似をして過ごしていた。彼女が笑うとみなが笑ったし、彼女が踊るとたちまち何人ものひとびとが集まって声援を贈った。先生たちは勇気づけてくれたし、お兄さんやお姉さんは褒めてくれた。しかしある日、汗だくになった美嘉がいつものようにお辞儀をして喝采を浴びたあと、「いつかアタシもテレビに出られるかな!?」と聞いたとき、彼らは一秒ほど、沈黙したのだ。
そのすぐあとに浴びるような激励があった。
大丈夫だよ、必ずなれる、あのテレビの中にいたかわいい子たちのように、美嘉ちゃんなら。
しかし、誰もが本心では一瞬それが信じられなかったということを、美嘉はおさない心で敏感に察知したのだった。この子どもにほんとうにそれができるのかと自問したことを、感じ取ったのだ。
美嘉はそれ以前にも以降にも二度と無いほど激しく泣き叫んで、周囲の大人たちは慌てふためいた。何を与えればいいのか、迷った。それは彼らに与えることができるものではなかった。彼女が泣き叫んだのは、それがいつか美嘉自身の手によって与えられるという事実をうまく信じることができない周囲への怒りのためだった。与えられるべきものは、みずからの力以外では与えられるものではなかったのだ。そのことを美嘉は最初からきちんと分かっていた。
逃れがたい渦の中心で、幻想はバシンと音を立てて去っていき、こちらを睨みつける志希の隣では文香が叫び続けていた。
「私が、本を読み、大学へ行き、アイドルを……アイドルになることを、望むのは、それほどまでに許されないことなのですか!?」と、叫んでいた。
その問いがあまりにも力強く投げかけられたために、ごう、と散っていく火花がはっきりと見えるようだった。青い瞳からはとめどなく涙が溢れ、こころの内側にある激しい信念は彼女が瞬くたびにパッパッと輝いた。その場にいるすべての人々に、文香の偉大なたましいの奥底には、暗い夜空に燦然と輝く星の一柱への想いがはっきりと埋め込まれていることが明らかとなった。
美嘉は一メートルほどあったはずの二人の間の距離を一瞬で詰めて、気づいたときには文香の柔らかな身体を強く抱きしめていた。いつのまにか列車ははるか遠くに消え、あたりは静まり返っていた。文香の微かな泣き声だけが、静寂の薄布が包む平穏を時折裂くように響き渡っていた。
「ごめんね」と美嘉は小さな声で言った。
「ごめん」と繰り返した。文香はうう、と唸りながら美嘉を引き剥がそうとしたが、やがて力なく美嘉を抱きしめ返して、激しく泣き始めた。
「文香さんが信じれば、きっと、何でもできるよ」と、耳元で囁いて、美嘉はさらに強く文香を抱きしめた。ぐ、と美嘉がやさしさを込めて抱けば抱くほど、文香は力強く抱き返した。あらわれた想いの強さに、美嘉の唇は心の動きを映して少し震えた。美嘉にはあまりにも大きなつながりを文香に感じた。彼女がやがて成し遂げるだろう絢爛たる成功を心に描くと、涙が溢れて、美嘉はぐっと一瞬文香の肩口に額を押し付けた。
二人が抱き合っている横で、志希はほうっと息を吐いた。「志希」と言った美嘉が、手のひらを上にして差し出していたので、志希はカーディガンの両方のポケットから小さな石鹸を取り出して、どちらを渡そうか迷ったようだった。美嘉は微かに凹みのできたそれを取って、手のひらに握り込んだ。「手、同じふうにして」と言って、美嘉は志希に縦のグーを作らせた。怪訝そうな顔をした志希に見つめられると、美嘉は「ありがと、志希。最高」と涙声で言いながら、文香を抱きしめたまま、トン、と拳で拳をやさしく突いた。ぶる、と震えて、志希は潤んだ目をきらりと光らせると、心の底から嬉しそうに笑った。
「はー……」
「もう何も起きないで欲しい……心底……」
「……」
三人が料金を払って陸橋下の銭湯に入り込むと、更衣室にも、女湯にも誰もいないようだった。出発前に「ゲーノー人が公衆浴場なんか行っていいの?」と志希が聞いたとき「なんかそもそも潰れかけで人少ないんだよね。アタシはよく行くよー、きもちいいしメイク落とせばばれないばれない」と美嘉はあっけらかんと言った。あまり凝った化粧をしない志希はまあいっかどうでもと思ったし、そもそも化粧というものをしない文香は特になにも考えていなかったのだが、結果として問題は起きようがなかった。
もたもたと上着を脱ぐ志希に「何、恥ずかしいの? ひょっとして〜」と、ブラ姿になった美嘉は茶々を入れたが、面倒臭そうに目を細めた志希に両手でがっつりと胸を掴まれて「ぎゃあ!」と叫んだ。その瞬間高齢の番台に、「お嬢ちゃんたち、ほどほどにね〜」と注意され、二人は「すみません……」「はあーい」と謝ったのだった。
「にゃはー、怒られちゃった」
「……フザケンナ……アイドルの胸を弄んで……お金払え……」
「元はと言えば美嘉ちゃんがわるーい」
ふん、と向こうを向いた美嘉を尻目にずばっと全裸になった志希は、我関せずと服を脱いでいた文香の方へと鼻歌を歌いながら振り返ると、ふつふつと全身に汗を浮かせて真っ青になった。文香の尻の割れ目の少し上で、ゆっくりと揺れる長く細い尻尾にひとり気づいたのだった。きゃっ、という文香の悲鳴に、「ちょっと、静かに!」と振り返った美嘉が見たものは、全裸のまま折り重なって倒れている二人だった。うつ伏せに倒れた素っ裸の文香の尻にぎゅっと抱きついている志希を見て、う、と嫌悪に満ちた表情を浮かべ、「アンタら、マジでなにやってんの」と美嘉は聞いた。
「あははは〜」と笑ってごまかした志希は、「いやー、文香ちゃんのお尻、きもちヨサソ〜って思って……」と嘯いて、文香の腰のあたりに頬ずりをした。美嘉はあやしむようすでそのまま突っ立っていたが、「いい加減にしなさいよ……」と、見てはいけないものを見てしまった母親のようにロッカーに向き直り、アクセサリを外し始めた。ほうっと息を吐いた志希に、文香はいつもと変わらず平静な表情を向けて、「……そんなにきもちいいでしょうか……」と聞いた。すっと真顔になった志希は、今日一番の殺意を込めて文香を睨みつけた。
志希はこそこそとしゃべる。
「文香ちゃん、尻尾出てるよ。なんで最初から尻尾もあるって言ってくれなかったの」
はあ、と生返事をした文香は、ふうむ、とくるくる目を回して、
「猫に尻尾があるのは、当然と言うものでは……」
志希はがくりと文香の腰に顔を落として、「もういいよ……」と呟いた。
右耳からも外されたアンプルの中身を飲み込んで、志希はそっと美嘉から自分の身体で影を作ると、小さく陣を書きながら尻尾の根本を触った。「やっ……あん」と文香がいやらしい響きの声を上げて、「なんなの、そのえっちな声!」と、小声で志希は嗜めた。「で、ですが、我慢できな……くぅ」と悶える文香に、志希は焦ったようすで、しかしゆっくりと黒い尻尾を根本からしごいていった。「んんぅ」と悩ましげな吐息を文香が吐き終わったのと、徐々に透明になっていった尻尾がまったく見えなくなったのと、「ふう」と、志希が安堵の息を吐いたのと、「ひと仕事終えたみたいなため息をつくなっ!」と美嘉が真っ赤な顔で叫んで志希の頭をはたいたのはほとんど同時だった。
「アンタほんと何考えてんの!? 銭湯でそういうことする普通!?」
「だーっ、もう本当美嘉ちゃん超面倒! 処女は黙ってて!」
「だっ、なっ、しょ、処女……じゃないし……ていうか、アイドルが処女とか言うなーっ!」
延々と続く二人の口喧嘩を横目に、ほうっと息をついた文香はタオルで胸の前を覆うと、そっと立ち上がった。目が合った番台に、「ほどほどにね〜」と先ほどと同様に注意され、軽く頭を下げると、ついに掴み合いを始めた美嘉と志希の横をすたすたと歩いて、ガラス戸をからから開け、ぱたんと閉めた。
文香が黄色い洗面器にお湯を溜めていると、打って変わって静かになった二人も現われて両側に座った。
「番台さんがあんなに怒るなんて」
「怖かった」
「志希のせいだからね」
「もういいよそれで……」
石鹸の甘い香りが立ち込めると会話はすぐに打ち切られ、三人は黙々と身体と髪を洗い始めた。文香が真っ先に立ち上がり湯船に向かったとき、足の指先を磨いていた美嘉は「ちょっ……と……」と文香を呼び止めた。不思議そうに美嘉を見た文香に、
「早すぎない?」
濡羽色に煌めく髪をかきあげて「いつも……このくらいです」と、文香は言った。髪の毛をぐるぐるとタオルで巻いた志希が文香の肩を掴んで、「早くはいろはいろー」と急かしたので、文香は軽く会釈して浴槽へと向かった。「え……アタシがおかしいの……?」と、美嘉は自問しながら全体の三分の一も終わっていない身体を洗う工程を再開した。
志希は「あっつう」と言いながらお湯に入り込んでいった。胸元のまっしろな谷間が水を弾き、描かれた幾本もの玉筋が彼女のまたから湯船へと伝い落ちていった。銭湯富士は空から浮き立つように濃い群青で描かれ、手前の松林からは小さな古めかしい型の帆船が西湖を巡ろうと今まさに姿を見せていた。文香はそれを見上げながら「風流なものですね」と誰に向かってとなく言った。壁を見ながら心にしまおうとした雄大な富士の山が、自由なようすで胸のうちに現われたのを見てそう呟いたのだった。「日本人のたましいだね〜、てきとうだけど」と、肩まで浸かった志希が言って、「そうかもしれません」と文香は調子を合わせた。
広い湯船の真ん中で、二人は富士のふもとに身体を寄せ合った。ほう、と息を吐いて「なんだか不思議な気分」と志希は言った。「……つまり?」と文香が聞くと、志希はしばらく湯船に口をつけてぶくぶくと泡を吐いたあと、「――こんなに胸をひらくなんて、思ってもいなかった」とこたえた。
文香がしばらく揺れる水面を見ながら沈黙しているのを見て、志希は膝を抱えると「……大丈夫?」と聞いた。投げかけられた言葉に、文香はふっと笑って、「志希さんは、やさしいですね」と言った。そのまま二人は乱れる水面の下で、本当は静止しているタイルの幾何学模様がさまざまな形を取るのを眺めていた。
――焼っきハッロ焼っきハッロかわいいなー。朝はかなしく昼たいへん、夜はけっこうたのしいのー。
志希は吹き出して、「なにそれ」と言った。文香も笑いながら「てきとうです」と返した。ちゃぷ、と水面を乱して入ってきた美嘉が、「もうほんっとうに怒られたくないから静かに……って言おうと思ってたんけど」と言いかけて湯船に浸かり、「男湯も、人いないっぽい」と笑った。
すうっと志希が息を吸った。
――焼っきハッロ焼っきハッロかわいいよー。夏は焼きそば秋かぼちゃ、冬はいったいなにたべるー。
銭湯のエコーが志希の歌声に軽妙な節をつけた。「なに食べるの?」と聞いた美嘉に、「さあ?」と志希はこぼれ落ちるように笑いかけた。「おでん、七面鳥、おうどん――」と文香がいいかけて「キムチ鍋!」と志希は叫んだ。「鍋は二つ用意して、ひとつは志希専用ね」と美嘉が言った。
「なんだかおなかすいてきた」
「私もです……」
「アタシも! 帰りは別の道で帰ろう。コンビニがあるんだ」
「何を食べましょうか……あんまんはもう置いてありますか?」
「あるある、アタシこないだ食べたよ」
「あたしはピザまんにタバスコ」
「うっわ、マジ?」
三人はひとしきり今日の夜食についてきゃあきゃあと笑い合って、最後に美嘉が歌った。
――焼っきハッロ焼っきハッロかわいいねー。ひとりは魔女でひとりねこー、ラストひとりはあくまだぜー!
「これ、相当いいねー! なんてゆうか、うける気がするー」
「カップリング曲になりませんでしょうか」
「あっはっは、楓さんに言ってみよっか。次のシングルにするってのもおもしろいかも!」
三人は笑い転げて、もう一度最初から歌った。
――焼っきハッロ焼っきハッロかわいいなー。朝はかなしく昼たいへん、夜はけっこうたのしいのー。
――焼っきハッロ焼っきハッロかわいいよー。夏は焼きそば秋かぼちゃ、冬はいったいなにたべるー。
――焼っきハッロ焼っきハッロかわいいねー。ひとりは魔女でひとりねこー、ラストひとりはあくまだぜー!
湯気はもうもうと煙り、無敵になった三人の歌声を遮るものはいなかった。青く輝く富士の山のふもとで、三人はずうっとその短いフレーズを繰り返し歌っていた。永遠に続くかと思われた霊峰の雄大な煌めきはやがてぼやけていくとおぼろげな靄を残して消え去り、幽かに残された光を見つめながら文香は床に敷かれた客用の薄い敷布団の上でひとり呟くように口ずさんだ。ひとりは魔女で、ひとりねこ、ラストひとりは――。
「もう磨き終わったの?」
「……はい」
歯ブラシを咥えた美嘉に聞かれて、文香は眠た��な瞳を向けた。にこっと笑った美嘉は「なんでもかんでも素早いね、意外だった」ともごもご言った。
「習慣ですので……」
手を上げて返事をすると、美嘉はバスルームの段差に腰掛け、キッチンのシンクにうがいの水を吐き出している志希のショートパンツを早くしろと言わんばかりにぺちぺち叩いた。
「あーそうやって邪険に扱うと、あたし自分ちに帰っちゃうよ。明日どうなっても知らなーい」
「ふいまへん、まひやめて」
ぺっと最後の水を吐き出して小物をしまうと、「せまーい!」と叫びながら志希は文香のとなりに飛び込んだ。二人のすぐ横、ベッドの上ではスプリングがびよびよに露出しているマットレスが粗大ごみシールを貼られて悲しそうに佇んでいた。
天井を見ている文香に、「明日が怖い?」と志希は聞いた。文香が志希を見てゆっくりと片手を伸ばすと、志希はその指先を赤ちゃんのようにしっかり掴んだ。口角を上げた独特の笑い方で、志希は何も言わずに頷いた。文香も微笑んで、ゆっくりと頷きを返した。
「志希、スマホの充電は?」
「ダイジョブー」
「じゃあ、電気消すよ」
「はあい」
「はい」
二人の返事と同時に、美嘉は照明を消してもぞもぞ二人の間に潜り込んだ。ほ、と息をついて、「つかれたね」と文香の方を向いて安心させるように笑った。「うあ」と文香が変な調子で返事をし、目を見開いたので、「はい?」と答えた。
ばっ、と文香が美嘉をまたいで馬乗りになり、「身体をひさぎます」と宣言したので、「は?」と美嘉は間抜けなこたえを返し、ぶはっ、と志希は吹き出した。
「ヒサグ……ってどういう意味だっけ……志希?」
「ぐうぐう」
「なにそれ、寝たふり?」
「何もかもお世話になっているのに――」と文香は呟いて、美嘉のパーカー状の寝巻きのボタンのひとつめ、もっともおなかに近いところを外した。「何もお返しできるものがありません」と囁くと、少し冷えた指先がひたっと美嘉の腹を擦ったので、「ちょ、あ、待って待って待ってそういうこと!?」と彼女は慌てふためいた。
文香はわずかな緊張を乗せた微笑みを浮かべて、
「耳学問で申し訳ありませんが、宿代と……思っていただけると……」
「ありえーん!」
美嘉の絶叫を無視すると、文香の身体は少し足側へと寄せられて、口が裾をめくった。ぱ、と離されると、そのままへそのすぐ下あたりを舌が掠めていった。頭を叩いていいものか迷っていた両手がついに「やめてやめて、まじで!」と、文香の肩を押さえつけて引き剥がそうとしたのだが、文香は「……美嘉さんの、おなか、なんだか甘いです……」と、美嘉の腹部から少しも離れようとしなかった。
「くうー! なんか、ヤバイ、ざりざりする! わかった、わかったって、甘いのはたぶん石鹸だって! うわーんめちゃ力強い! 志希助けておかされるー!」
「……くくっ……ふふふっ……ぐうぐう」
「寝たふりはもういいってば! 文香さんもなんでやめてくれないの!?」
「……古来、睦み言に繰り込まれる綾は、複雑で……ことわざにもあるように……いやよいやよも、好きのうちと――」
「ちーがーうー! そーいうんじゃないってばー!」
「あっはっは!」
涙をいっぱいに溜めた目で、美嘉が「笑うなアホー!」と志希に向かって叫んだ声は、アパートの外にまで大きく響いていた。たまたま深夜に犬の散歩に出ていた近所の老人は、その電気の消えた部屋を見上げると「ほどほどにね」と呟いた。犬は少し控えめにわんと鳴いて、大きく真円を描く月へとその鳴き声は吸い込まれていった。
楓がどさりとオフィスチェアに座ると、ゆっくりそれは回転し始めた。そっくり返って、「無理」と呟いた彼女に「そうですかー」とちひろは返答した。楓は天地逆になった緑の事務服を見つめながら、
「何が無理か、聞いてくださいよ」
「鷺沢さんのお母様に何か言われたんですか?」
「そういう細かな話じゃないんです」
フェラーリレッドのファブリックで覆われたヘッドレストから頭を引き起こすと、楓はそのまま瀟洒なデスクへと突っ伏した。「今日も川島さんにドタキャンの電話を……ううっ、『しんでれら』の限定白子鍋……」
「アイドルとプロデューサーの二足のわらじ、やるっていったのは楓さんじゃないですか」
ぐすっ、と楓は鼻をすすって、
「こんなに大変だとは、思いもしなくてえ……もっと説明が事前にあっても……」
「秘密の部署っていうのはたいていそういうものですよ。楓さんだって予算と影響力が欲しくていらっしゃったんでしょう」
しばらくイヤイヤをしながら呻いたあと、楓は顔を上げてすっとデスクのマウスを触り、ふっと灯ったディスプレイが表示し始めた美嘉のレッスン動画を見つめた。早いテンポのステップを、美嘉は汗で額を光らせながら笑顔を崩さずに踏み続けている。「美嘉ちゃんですか?」とちひろが音だけで言い当て、「ええ」と楓は答えた。
「いやー……普通の人間が高みを求め続けるということの難しさについては、理解をしているつもりだったんですが……」
「普通ねー……この業界、普通の人なんて一人もいないと思いますけど……」とちひろが呟き、そのまま会話を終わらせたので、楓は少し悲しそうに彼女を見やった。
コココココッ、という短い連続した打鍵音のあと、「さて」とちひろは拡張現実デバイスを頭から外して立ち上がった。
「あ、ひどい、傷ついた私を無視してお帰りですか?」
「私、ここには仕事できているので」
にこりと笑いかけたちひろに、楓が満点歌姫スマイルをにこーっと返したので、「あ、悪い予感」とちひろは言って座り直した。
「鷺沢さんのお母様から、ちょっと問題のある情報の提供がありまして――」
「世田谷の書店ならさっき処理しましたよ。その件でわざわざ? 守り猫の割に子煩悩な方ですね」
「あ、そうそう、お土産をいただきました。高垣の家とは妙に仲違いが多くてですね、当代から信頼関係をと……文香ちゃんを、くれぐれもよろしくって」
「いやいや楓さん、ご自分で文香ちゃんをスカウトされてたでしょう……たぶんめちゃくちゃ恨まれてると思いますよ」
がさがさと包み紙を広げながら、楓は「そうですよねー」と、丁寧にりんごパイを箱をデスクに置き、早速そのうちの一つを食べ始めた。ちひろは顔をしかめて、「深夜によくそんなもの食べられますね」と言いながらひとつを取り、ハンドバッグにそっと詰めた。半ば機械的に立ち上がり、窓際のウォーターサーバーで紙コップにお茶を用意すると、こと、と楓のデスクに置いた。
「帰っていいですか? 一時回ってるんですけど」
んぐ、と口に頬張ったパイの欠片をそのままに、楓は首を振った。お茶を口に含んで、ほう、と温かい息を吐きながら、「『映画』の件、あったじゃないですか」
「はあ、一応来週から���二スプリントで準備は終わりますが……」
「あれ、明日必要になります」
部屋がしいん、として、ぷああというクラクションがやけに大きく響いた。楓のオフィスは皇居近くのビルにあり、夜でもそれなりの車通りがあった。「はあ?」とちひろは呆れた様子で言った。
「裏取りはしていないんですが、京都のダキニとやらに動きがあったそうで」
ちひろはため息をついて、
「ダキニって国内の筋としては超木っ端ですよ。京都じゃなおさらだし、『映画』への影響なんてゼロだと思いますけど……」
「いやあ、私の世紀末シンデレラ超感覚にビンビン来たんですよね。ダキニダケニ、東京の覇権をいたダキニ来ちゃうぞ〜、なんて」
「や、超感覚はどうでもよくって、この話のポイントは明日……それ今日って意味ですよね、今日の二十四時までに『映画』の技術検証が間に合うわけないってところです。いくら美嘉ちゃんのためでも無理なものは無理です。二スプリントって何営業日分の作業かわかっています?」
「十営業日でしたっけ」
「二十営業日です!」
「あと、深夜ではなく、必要になるのは正午ごろです。あと十時間四十五分ですね」
若干のいらつきを示していたちひろの表情はスッと能面のようになると、逆に満面の笑みを湛えて「お疲れ様でーす」と手を振った。白いエナメルバッグを抱えると、ドアの方へと向かった。
「テンタクルを四十機使えます」
楓の言葉にちひろはぴた、と止まって、「よん、じゅっき……?」と言いながらゆっくりと振り返った。楓は完璧な脚を完璧なかたちに組んで完璧な笑みを浮かべたまま「今日いっぱい、防衛省から三十二機、米軍と、個人的な伝手で民間から四機ずつ借りました」と囁いた。
「物理所在は?」
「全部東京です」
バッグをそのへんに放ったちひろはデスクに腰掛け、デバイスを頭に被り直すと空中をすっと撫でて使用可能なリソースの一覧を可視化した。ぱっぱっぱっと時間差で現れた三群のひしめき合うインスタンスすべてに、紫のネオン効果付きの文字で『テンタクル』とラベリングされているのを見て、「最高……」と呟き、手元のベンチマークツールを試しに幾つかパイプして、激しい勢いで明滅するメトリクスにきゃあ、と叫んだ。
小型のフリーザーから取り出したエナジードリンクをちひろのデスクに置くと、「今日は帰ります。何かあったらご連絡ください」と楓は言って、デスクの上に放り出してあった闘牛を模したエンブレムのついたキーを拾った。
「そうそう、車両課の田所課長が、次に公用車を壊したら十五分以内にアルコール検査を受けろっておっしゃってました」と、ちひろは楓にゴーグル越しに言った。
「芸能四課の高垣課長は、血中アルコール濃度になど縛られない、とお伝えください」と言って、楓はひら、と手を振りながら、執務室のドアを開けた。
「……かっこうよくなんか言ってるようでほんとうにてきとうなんですよねー……」とちひろはぼやきながら、バッグから取り出したハンドクリームを軽く手に伸ばしたあと、拡張ハンドデバイスを取り付けた。画面上に大きく美嘉の動画を出し、パン、と柏手を打って「どうかああはならないでください! ナムナム」と拝んだ。そのまま肩幅ほどに広げられた両手のゆびさきがやさしく仮想ワークスペースに触れると、四十機のインスタンスは乱れた水面のように膨大な量のタスクボックスを吐き出していき、ちひろの視界を埋め尽くした。
2 notes
·
View notes
Text
歯を食べる / しきフレ
「どーかしたの?」と聞いたフレデリカに向かって、志希はおさない子どものように舌をつき出した。少し不健康に白いその上に乗っているものはよく噛まれたガムのようだった。「とえた」と言ったあと、舌をしまって「とれた。ガムで、銀歯」と言い直した。
「ほーう」
フレデリカは雑誌をぽいっとテーブルに放った。本来は数人で座るはずのソファに寝転がっていた志希のおなかをまたぐと、「舌」とやさしく微笑んだ。志希はそのまま従順に深いキスを差し出し、やがてちいさな歯のかけらはフレデリカの口へとうつっていった。
フレデリカはかたいそれを指で摘むと、
「これ、銀かな?」
「や、違うね、セラミック? あー、歯医者さん行くのやだなー……」
志希がぼやくと、ニコリと怪しく笑って、フレデリカはふたたびそれを口に含んだ。志希に顔を近づけると、黄金色に光る髪の毛をさらりと流して、そのまま彼女は小さな声で囁いた。
「これ、アタシが飲み込んじゃったら、コーフンする?」
「あー……ちょっといいかもー……」
「……一緒に他のところも食べられちゃいたい?」
かり、と二人の奥歯と奥歯が擦れる音がフレデリカの口中から鳴ったとき、「ン……」と志希は肯定の響きで呻くと目を閉じた。そして、「家でやれ!」と叫んだ周子が先程放られた雑誌で思い切りフレデリカの後頭部を叩いた。
「にゃはー。ごめんごめん、周子ちゃんいるの忘れてた〜」
「あのね、なんで毎回毎回あたしがいるのにそんな盛り上がれんの? しかもそんな繁殖期丸出しの変態プレイ……猫やめたんやなかったんかい」
「飲んじゃった」
『……え?』
周子と志希が同時に聞き返して、フレデリカは「飲んじゃった、シキちゃんの歯」と涙目でもう一度言った。
「……興奮した?」と周子が聞くと、志希は呆然としながら「少し」と答えた。
0 notes
Text
猫 / かなふみ
冷えすぎたケーキを 冷蔵庫から出しながら
名前を読んでも
返事がなくて
ふと 目をやると
「奏さん、私は実は猫だったのです」という顔で
くうくう丸くなっているので
今日何回目だかわからない
ため息をつき
ポットとマグカップひとつだけを持って
隣に座った
しゃくにさわったので
あなたのお気に入りの棚から
一冊 盗もうとすると
不機嫌そうなうなり声で 呼ばれたので
慌てて謝ろうとしたら
「私は怒っています」という皺が
きれいな眉の間に
寄っていたから
真剣なゆびさきで
伸ばしてやった
0 notes
Text
耳あてつきの帽子 / かなふみ
「よろしかったのですか」と文香が聞いて、「よろしいもなにも、あれじゃあ断れないわ」と笑った。代官山駅から徒歩五分のダンススタジオへと辿り着くのはいつも早すぎて、カフェで遅い朝食を二人で取ることは毎週���取り決めになっていた。ところが今日はいつもと違って、歩道に面した席で注文を出したすぐあとに、顔を赤くして近寄ってきた中学生くらいの男の子が私に手帳を差し出したのだ。「応援しています!」という、去り際の挨拶に、声変わりの気配を感じた。
はあっと指先に息を吐いてあたためた。
「事務所の規程では――」と文香が言いかけて、「あら」とそれを遮った。
テーブルに肘を突き、「規程では、私たち、恋人を作れないはずじゃなかったかしら?」と言ってしまって、私は後悔する。耳が熱くなる。真冬の白い太陽が急に大きくなった気がする。
オープンカフェの暖房がごうごうと音を立てている。
けれど、私は、無敵。
帽子が私の心を守っている。私の動揺を隠す、耳あてつきの帽子。じっと私を見つめる文香から視線を外して、素知らぬ顔で道を行く人々を眺める。交差点でさっきの男の子がこちらを見ていて、振られた手に私は笑みを返した。
その瞬間に、帽子が取り去られる。
あっ、と声を上げて、私は文香を呆然と見つめる。文香は帽子を膝に置くと、にこりともしないで私を見ている。
「やめますか?」
底冷えのする声だった。じとりと背中に嫌な汗が浮いた。さあっと風が吹いて、足元を枯れ葉の一群が掠めていった。帽子を見ながら「やめないわ」と小さな声で答えた。降りた沈黙にどうしていいのか分からず、少しだけ涙が浮かんだ。そのときに、くくっと言う笑い声が文香の口から漏れて、私はもう一度、「ああっ」と叫んだのだ。
「からかったのね!」
「奏さん、真っ赤です!」
「帽子、返しなさい、文香!」
あっはっはと文香が子どものように笑って、私は恥ずかしさで死にたくなる。この地獄のような、かけがえのない朝を、私はどうしてもこの手から離せない。
0 notes
Text
焼きそばハロウィンはいかにして無敵のアイドルになったのか(3)
1 https://tmblr.co/ZlZBMe2cy-9bD
2 https://tmblr.co/ZlZBMe2dBfNbl
鷺沢古書店の裏口が閉じられたとき、世界中のあかりをまとめていた一本のろうそくがふっと微かな風で消えたようにあたりは真っ暗になった。産まれる前に死んだひとがちいさく丸まっているように、文香はその場にしゃがみ込むと息をくうっとひそめた。やがて扉の向こう側で美嘉が立ち上がり、あたりに散らばった荷物をひとつひとつ拾うと肩を落として去っていった。ごめんなさい、と、文香自身にすら聞こえない囁きがそれを見送った。こつ、と小さな音を立てて額が打ち付けられ、文香は現れた痛みに顔をしかめた。とほうもない悲しみを湛えた彼女の顔を正面から見ていたら、きっと美嘉は何をおいても文香をその激痛の海から助け出そうとしただろう。
すんっ、と文香の鼻が鳴った。
土間から上がった文香は、少しよろめいて壁にもたれかかった。壁づたいに小さな部屋を抜け、トイレへと向かった。扉が閉められると、からからとしばらくペーパーが巻かれる音がしたあと、ひそやかだった文香の泣き声はやがて号泣と言えるほどに大きくなって、店の中に響きわたった。物言わぬ本たちだけが彼女の嘆く声を聞いていた。本たちは彼女を慰めるでもなく、ただそっとその場に佇んでいた。彼らは誰かが彼らを読むことをただ待っていた。がりがりと壁をかきむしっていた音が止むと、今度はごん、ごん、と狭いトイレのドアに額の打ち付けられる音が低く鳴りはじめた。夜の嵐が来たときに沖に逃げることができなかった船々が岸壁にぶつかり続けているかのようだった。
数人の女性たちが閉じられたままのシャッターの前を笑い声を上げて通りすぎていき、やがて文香が悲しむ音も同じように消えていった。あたりが静かになってからしばらくすると便器を流す水音が響いた。ぺらぺらに薄いドアを開けて、文香は頬を濡らしたまま現れた。厚ぼったい布地のロングスカートは片手に抱えられ、少しずり下げられたオレンジ色のショーツ姿で、腰のあたりからは黒くしなやかな尻尾が頼りなく伸びていた。
ぐし、と文香は子供のように鼻を片手でこする。
彼女は部屋を抜け、手も洗わずに店へと出た。レジの後ろにあった、長く使われていると思しきすり減ったスツールに腰掛けて、カウンターに突っ伏した。彼女はその椅子の上に下着姿のまま佇んでいた。ヘアバンドをぐっと掴んで取ると、その下からはまっくろな猫の耳が現れた。狭い鷺沢古書店の中で、その耳だけが細かく動いていた。やがてひやりとしていた椅子が文香の下でほんのりと温まったころ、彼女は誰かに呼ばれたかのようにぱっと顔を上げ、まっくらやみの中に立ち並ぶ巨大な本棚の間にその姿を探した。暗さに慣れた目はその闇を青白く撫でていった。彼女の瞳は空に瞬くシリウスのように光っていた。月のない夜に外を歩く人たちをどうにかして助けようとするような、やさしい光だった。
その光には、本たちだけが照らし出されていた。
「私はアイドルを続ける」と、彼女はぽうっと光る、うるんだ目で本たちを見つめた。
「おかあさまにおねがいする」
文香の瞳に照らされて、本たちはざわざわと囁きを返した。それにこたえるかのように「私はがんばる」と、小さな声で呟いた。
よろめきながら、立ち上がった。
洗面所へと戻り、電気をつけた。スカートとヘアバンドを床に放って髪を片手で後ろにまとめると、文香は蛍光灯のあおい光に削り出された自分を鏡の中に見つけてその手を止めた。
どうしたって人間には見えない、その姿を悲しそうに覗き込んでいた。
文香はどこか焦ったようすで歯ブラシの横に置いてある茶色いガラス瓶を手にとり、蓋を開けた。文香の瞳と同じ色で輝く錠剤を手に取ろうとして、やめた。きゅうっと蓋をきつく締めたあと、文香がその瓶を握りしめる力は異様に強かった。まっしろになってしまった自分の指がひどくゆがんでいることに気づかないようすで、文香は鏡ぎりぎりまで顔を近づけると、その瞳をまっすぐに見つめながら自分に言い聞かせるかのように「おかあさまにおねがいする」と言った。
陶器製のシンクの上に薬を持った手がぎゅっと乗せられて、カツンと鳴った。
ごん、と額を鏡に打ち付けた。
「おかあさまにおねがいして大学を卒業する」
ごん。
「おかあさまにおねがいしてなんでも好きな本を読む」
ごん。
「おかあさまにおねがいしてアイドルを続ける」
ごんっ。
「おかあさまにおねがいして、明日のイベントに――」
最後に額を打ち付けたとき、鏡がしゃっと粉々に砕け散って、文香はすっと黙った。ゆっくり頭を鏡から引き剥がすと、前髪に残ったガラス片が照明を反射しながらきらきらと落ちて、シンクの上で空気中の水分が雪になっていってしまうようなちりっという音を立てた。文香はそれを聞いて、自分の願いがすべて凍りついてしまったように思った。まっしろな氷原から目を上げて、きっとどうしたって何もかもが叶わないのだと、割れた鏡に映り込む、ばらばらに壊れてしまった自分自身をじっと見つめながら思った。
どうすればいいのか、わからなくなった。
文香はふい、と踵を返した。床に落ちたスカートとヘアバンド、壊れた鏡と、洗面所の照明、すべてをそのままにして部屋を抜けた。足早に歩いてゆく彼女の双眸はすーっと流れていって、その二つの星々の軌跡を本たちは悲しげに見送った。何しろそれはもっと偉大に輝くことになるはずだったのだ。きい、きい、と規則正しい音を立てて、文香は優しい色合いの木でできた階段を登っていった。丸い尻の上でまっくろな尻尾がふるふると震えていた。眠ってしまおうと思ったのだ。文香はそのまま寝てしまって、明日をまっさらに迎えようと思っていたのだった。
そして彼女が二階のふすまを開けたとき、その隙間からぱあっと溢れ出た圧倒的な太陽の光が彼女の瞳を灼いて、その向こうから「文香」とその名を呼ぶ声が聞こえた。
文香は一度はしかめた目を見開いて、「おかあさま」と呆然とこたえた。
窓の棧に腰掛けた彼女は文香と見た目には殆ど変わらない年頃に見えた。真っ黒なパンツスーツに、文香は喪服の不吉さを感じた。一重のまぶたや著しく短い黒髪、活動的な性格をうつしたその溌剌とした笑みは文香にまったく似ておらず、唯一のその瞳の色だけが彼女たちの血縁をはっきり示していた。
母親は「こちらへいらっしゃい」と文香に言うと、ぎくしゃくとやってくる文香から洋服だんすのほうにその切れ長の瞳をやって、慣れた手付きでスカートとクリーム色のヘアバンドを取り出した。やってきた文香の右手を自分の肩に乗せてやり、彼女を支えながらあたらしいスカートを履かせた。「ありがとうございます……」と言う文香に後ろを向かせて尻尾の流れをなおし、ついで立ち上がると「あら」と言った。肩をやさしく押して畳に座らせた。
「目をつぶって、動かないでね」
女は文香の前髪に残るいくつかのガラス片に気づいたのだった。そっと丁寧にガラスを取り除くと、「もういいわ」と言って文香にヘアバンドを渡した。「相変わらず薬が嫌いなのね」と言って、くっくっとまた笑った。文香が耳を隠している間、彼女はそれをティッシュにくるみながら、目を細めて「思い出した」と言った。
「去年の冬、文香が木の上から落ちてきた雪に埋まったとき、今みたいに雪を払ったわ」
あはは、と笑うと、彼女の短く細い髪の毛はさわやかに揺れた。文香は何も言わずじいっと彼女を見つめていたが、「いつ、いらっしゃったのですか」と聞いた。
母親はテーブルの上の本を取るとぱらっとめくった。その本は壁を埋め尽くす、文香の上京以来の蔵書から二十冊ほど抜かれた本のうちの一冊だった。「六十ページほどかしら」と彼女は言った。そして窓に片脚を乗せて腰掛けなおすと、凄まじいスピードで続きを読み始めた。
「……シロは、息災ですか」
文香の言葉に、母親は答えなかった。顎を拳で支えながら、ただページをぱら、ぱら、と片手でめくる音を響かせていた。文香はそっと立ち上がると、階下に戻ってお湯を沸かした。青白い炎が古めかしいガス台から登っていた。「……おかあさまに……」と小さく文香は言った。その瞳で小さな炎がゆらゆら揺れていた。
淹れられたお茶が母親に飲まれることはなかった。文香はただじっと冷めていくそれを見つめながら、母親が本に満足するのを待った。二十冊を読み終えたときは夕方と言っていい時刻をすでに回り終わっていた。青白い照明の下で、「お腹が空いたわ」と彼女は言った。
「すみません……晩ご��んは、準備が……」
ふ、と笑って、
「あなたの料理に期待なんかしていないわよ。二駅ほど行ったところに美味しいお店があるの」
朗らかに言ったあと、彼女は「いい本ばかりね、文香」と言った。母親に褒められたので、文香は反射的によろこんで固くなっていた肩の力を抜いた。部屋の両側に天井までそびえ立った本棚に一冊ずつ差し込みながら「敵を知るにはとても良い」と彼女は言った。彼女が取った本は偏っていた。ほとんどが世界にあまねくひしめいている大小の宗教をテーマにしていた。そして「文香には早いわ」と、声の調子を変えずに言った。
「毒よ」
とんとん、とみずからの頭を叩いて「あなたの未熟な、精神には」と確信が込められたようすで言った。文香は無表情に、ぼんやりと母親を見上げた。
「経はきちんと毎日読んでいるかしら、文香」
「……読んでいます」
「どうかしら」
母親はすべての本を戻し終わると、取り出しやすい位置に置いてあった別の一冊を取り出してテーブルにぽんと乱雑に放った。その本は表紙に今風のイラストが書かれた少女小説だった。文香は、かあっと顔を赤らめると、下を向いた。怒り、反発と、羞恥が同時に押し寄せたのだった。
「仏典以外を読まないようにすることね」
「……あの」
文香は顔を上げた。眦を決し、必死の嘆願を「私、大学が終わるまで、東京に……」と言いかけて、母親が片方の眉を吊り上げたのを見て続けることができなくなった。「大学は四年制だったわね。終わったとき、あなたはいくつかしら」と聞かれて、それに答えることもなかった。母親は嘆息すると「明さんにあなたを任せるのではなかった。大学だなんて……」と言った。窓際にあった靴箱からエナメルのヒールを取ると、「いきますよ」と促した。文香は黙ってそこからフラットシューズを取り出し、のろのろと履いた。
彼女たちは窓から外に出た。街灯が近くでじいじいと鳴って、文香の沈んだ横顔を照らしていた。
慣れた動きで、二人は屋根から隣家へと飛び移る。少し離れたマンションの壁へとたどり着くと、するすると全身を使ってベランダの側壁伝いに登っていき、屋上の手すりの外に立った。文香は母親の横顔を悲しげに見ていたが、やがて「あの」と言った。
「せめて一年、こちらにいさせてください。……手紙にお書きしましたとおり、今、私は新しいアイドルユニットに所属しています。明日から、大きなイベントが――」
「シロが昨晩死んだの」と母親は言った。
ひゅっ、と文香は息を吸った。ぐら、と揺れて、屋上の手すりをぎしりと掴んだ。「なぜ……?」ときれぎれに言って、母親は何もこたえず、広がる夜景に目を落としていた。
「おかあさま!」と文香は叫んだ。
「鷺沢の技は、末子相伝よ」
「あの子をお役目に出したのですか」
ぽろぽろと大粒の涙が頬を伝っていった。「二歳に、なったばかりの、ちいさな子を……」文香は激しく顔を歪めて、両手で顔を覆った。空いっぱいに広がった星々が残酷な眼差しで二人を見下ろしていた。
「文香」
「……おかあさまが殺したも同然です……」
「文香、私を見なさい」
きっと文香は母親を睨んだ。ぎらぎらとみずから輝く鏃のような青白い瞳が、燃え立つ怒りに満ちて母親を射殺そうとした。
「あなたが総領になったからには、私を受け入れてもらわなければ困るわ」
文香は笑った。涙がまだぽたぽたと落ちて続けているのに、母親を馬鹿にするように笑った。そのほとんど狂ってしまったひと特有の危うさは、汚泥に埋め尽くされた沼の真ん中で蓮の花が痛切な悲鳴をあげているかのような美しさを示していた。
「おかあさまは……」
文香は背中を丸め、膝を折った。重心を低くして、片手の指先を石造りの床につけた。まるで誰かを襲おうとする直前の虎のようだった。服の上から広背筋が緊張で盛り上がっていくのがわかった。
「本気で私が戻ると思っているのですか」と文香は言った。
「安心したわ。鍛錬はきちんと積んでいるのね」
「ふざけるのも大概にしてください!」
母親の組まれていた手の指先が、ぴ、とはるか下を指差した。文香はそれをなにか注意を引くための嘘と取ると、「がう!」と吠えて床を蹴った。その瞬間、その瞬間に、ごうううっ、という激しい音を立てて、鷺沢古書店の二階が内側から爆発するように燃え上がった。文香の横顔を、その熱気が灼いて、彼女は空中で手すりを掴んで勢いを殺し、着地した。しばらく彼女の部屋のすべてに火が点いたのを呆然と見ていたかと思うと、「きゃあーっ!」と叫んで、頭を抱えてその場で一度ぐるっと回った。そのまま「ああ」と呟いて、ばりばりと頭を掻いたかと思うと、ほとんど倒れ込むようにしてその身を空中へと投げ出した。
文香の身体は、母親に支えられた。母親はその腕を思い切り伸ばすと文香の手を掴み、すんでのところで屋上からぶら下げたのだった。彼女はそのまま文香をじっと支えていた。ぼうっと涙を落として、自分を見上げる文香を、顔色も変えずに見つめていた。そして静かに、「私の手を握りなさい」と言った。
「お役目をまっとうしなさい、文香。鷺沢家千年、二百代のお役目を」
文香は母親の言葉に反応を示さず、ただじいっと見上げていた。
「余計なことを頭に浮かべず、私の手を握りなさい」と母親はもう一度言った。「でなければ、二度と鷺沢姓を名乗ることは許しません」
「……おかあさまがシロを殺したんです……」と震える声で文香は言った。「そうね」と母親はあっさりとこたえた。
「けど、あなたもシロを殺したのよ。あなたが家に残ってあの子を支えなかったから、あの子は死んだ」
文香は白痴のひとのように、は、と口をあけた。は、は、は、と、かわいたゆっくりとした笑いが悲しい息とともに漏れた。
「私の手を握って」と母親は言った。ぼうぼうと燃える炎に照らされて、母親の顔は偉大な赤い色に染まっていた。文香は笑いながらじっとその顔を見上げていたが、やがてそっと左手を伸ばして、母親の指を一本一本、自分の右手から剥がした。
「文香」と母親は最後にもう一度、彼女の名前を呼んだ。文香に躊躇なく外された人差し指は、きゅうっと握られた。
そうやって文香はまっくらな闇の中に落ちていった。
足下にあったベランダの縁をとんとんと踏み、勢いを殺しながら文香は降りていった。マンションの土の上に四つ足で着地すると、ごしごしと肩口で顔をこすり、音もなく走って敷地の壁を難なく超えた。集まり始めた通りの人混みを避けて裏庭にたどり着いて、勝手口のノブをばきんと破壊して家に入った。あたりにはめきめきとすべてが壊れていく音が聞こえた。木の天井からはもうもうと白い煙が吹き出していた。文香は洗面所にたどり着き、割れた鏡には目もくれず水でストールをびしょびしょに濡らした。頭からそれをかぶると、人間離れしたしなやかさで階段を登っていった。
二階は地獄のようだった。凄まじい熱気が文香を襲った。顔全体をストールで覆いながら目だけを外に出して、床を這って中に入ったとき、彼女が見たのは燃え上がる二本の火柱だった。彼女の本棚は完全に燃え上がっていた。そこに差し込まれた何かが、きっと激しく熱を発したのだった。その部屋にある何もかもがだめになっていた。文香は魂の底から絞り出されるような唸り声を上げて床に額を打ち付けた。絶望が彼女に襲いかかって、生きる意志のすべてを取り去っていったかに見えた。ストールに吸い込まれていた水気はじゅうじゅうと音を立てて空気の中へと消えていった。
「私の本」
微かな声で囁くと、ごほっと咳をした。文香はなにかに誘われるようにもう一度畳の目から顔を上げた。そのとき、たった一冊、たった一冊のまっ青な本だけがぽつんと目の前に落ちていることに彼女は気づいた。熱でソフトカバーが少し曲がり、泥に浮かんだ泡のような致命的な汚れが浮いていた。あっ、と声を上げて、彼女はそれをひっ掴むと、胸に抱いて丸まった。それは母親がテーブルの上に投げ捨てた、あの少女小説だった。その一冊だけが、何かの拍子に文香の前へと落ちてきていたのだった。胸にあるそれの温もりに、文香はこみ上げるものが抑えきれなくなって、うう、と唸りながら涙をぽとぽと畳へと落とした。
ひゅうう、と苦しそうに息を吸って、ごほごほごほ、と文香は間断なく咳をした。凄まじい熱と煙はもはや文香の四肢から動く力を奪っていた。本棚の片方が倒れ、ごおっという風の巻く激しい音とともに凄まじい熱気が押し寄せた。空中に満ちている火の粉はそのひとつひとつが怒りに震える魂であるかのように激しく踊った。
ごほ、と最後の咳が鳴ったあと、文香は「おかあさま……」と声なく呟いた。赤く染まった目蓋を文香が閉じたとき、涙の膜と消えかかった意識が霞ませた視界に、こちらに差し出される細くやわらかい手が映っていたのが、いつまでも残っていた。
遠くで鳴るサイレンの音で目が覚めた。ずれたヘアバンドの横��ら覗いた耳が、ぴ、ぴ、と忙しな��動いていた。文香はゆっくりと二、三回まばたいたあと、目を見開いてがばっと勢いよく立ち上がり、息を飲んだ。さまざまな人々の希望の光に満ちた、開けた空の下、文香は見知らぬ雑居ビルの屋上に寝ていた。ぐるぐると周囲を見渡し、誰もいないことが分かった。濡れたストールを片手に持ち直そうとして、ふと緑の床に目をやり、そこに一冊の本と茶色の薬瓶が置かれていることに気づいた。
文香はその本と瓶を、両手に持った。青い表紙では、乱れた黒髪の少女がこちらに笑いかけていた。端の焦げたそれをしばらく見ていた文香は、ふ、と顔を上げ、地上を見下ろした。はるか向こうで、鷺沢邸はぼうぼうと燃えていた。いくつもの緊急車両が四方からそこへと向かっているのがわかった。屋根が崩れて、凄まじい火の粉が立ち上るのが分かった。
ぐす、と鼻が鳴った。
文香は「シロ」とむなしくつぶやいた。ぐっと唇を噛みしめると、ああっと叫んで、文香は瓶を持った手を振りかぶると凄まじいスピードで向かいのビルの壁へと投げつけた。ぱあっという音が鳴って、きらきらと光る薬の破片が四方に飛び散った。一瞬の花火の消えていくようすが、凄まじい美しさで文香の胸を打った。
「私が、シロを……」
文香はしばらくそこに佇んでいた。
そして、十月のつめたい風に襲われた。しっかりとそこに立っていたはずの文香は、それでふらりと揺れ、そのまま、落ちた。ビルの室外機に頭を打ち付け、窓枠に肩を強く打った。それでも結局は、すとん、と地上に軽く降り立った。そこはごみごみとした、誰にも顧みられないビルとビルの狭間で、文香はその場に膝を抱えて座り込んだ。
汚水が下着にまで染みていくのにもかかわらず、文香はずっとそこに本を胸にして座っていた。やがて、文香は本を開いた。その普通の少女たちが笑って生きている、何度も何度も読んだはずのその本を文香は読み始めた。本を読んでいるときに、自分自身が何者にも乱されないことを知っていたからだった。
文香はそうやって、みずからを守った。
やがて、それは打ち破られる。やってきた彼女は優しげな表情をまとって、文香の耳を訳知り顔で、母親のように隠してやる。「あたしたちみたいなのが、アイドルだなんて、笑えるよ」と、その少女は言って、「志希さん」と文香はこたえた。志希はポケットから取り出したスマートフォンの電源を入れると、現在地を美嘉に転送して簡単なメッセージを送った。「耳のこと、美嘉ちゃんには内緒だよ」と、唇に人差し指を当てて志希は言った。
息を切らして現れた美嘉が涙声で文香の名前を呼びながらいつまでも抱いているのを、文香は不思議な思いで聞いていた。先ほどまでいた地獄の底は、なんだったのかと思った。自分をまるでふつうの子どものようだと感じた。
ステージライトの猛烈な輝きと激しいリズム音が矢のように頭を横切って、ぎゅっと本を握りしめた手の指がなぜかひどく痛んだ。文香は美嘉の声を聞きながら、微かに顔をしかめていた。
タクシーの運転手は文香の身なりを見るとかなり渋ったが、美嘉による必死の懇願と追加の一万円が効いたのか、最後には根負けして全員を乗せた。シートを汚さないためのコンビニ袋がざりざり音を立てるのが不快で、文香は繰り返し身じろぎをしていた。
タクシーを呼び寄せる前に、美嘉は何度も「警察に、生きてるって言いに行かないと」と文香に主張した。美嘉は現場にいた何人もの消防士が消火もそこそこに家の中のようすを確認しに入っていくのを見たのだった。「私は叔父の家には隠れて住んでいて、いないことになっているのです」と文香が何度言っても納得する様子はなかったが、最後に「母が家に火をつけたので、真実を警察には話せない」と言うと黙ってしまった。あまりにも謎めいた文香の言葉には、想像を超えた異常性の持つ説得力があった。結局、タクシーを呼んだのは志希だった。冷えた文香の手をずっと握っていた彼女は「早くシャワーを浴びせてあげないとかわいそうだ」と言ったのだ。
美嘉のアパートに三人がたどり着いたとき、タクシーを降りてから志希は「下着とか着替え、あるんだっけ?」と言った。「あちゃー」と美嘉は呟いたあと、「もうちょい早く言ってよね……」���鍵を取り出して志希に渡した。
「ちゃちゃっと買ってくるから、お風呂ためときなよ」と美嘉は言って、服のサイズを聞くとコンビニに向かって走り出した。「あたしのぶんもー!」と志希が叫んで、「あほー! もういいよ適当に買ってくるー!」と角を曲がりながら美嘉はこたえた。
「行こ」と促し、志希は文香の手を引いて階段を登った。鍵をあけると「にゃはー、美嘉ちゃんの匂い〜」と、志希はずかずかと部屋の奥まで入り込んで美嘉のベッドの上に倒れた。文香は数歩廊下を歩くと、脱衣所のないバスルームの前に敷かれたマットの上にすとんと座り、また本を開いた。
志希はしばらく美嘉の枕の匂いを吸い込んでいたが、やがて飽きるとその上に仰向けになってしばらく天井を見ていた。
「さっきのさー」
志希は言って、反応がないのを確認した。顔をしばらく持ち上げて文香を見ると、「無視かー」と、また倒れ込んだ。志希は読書中の文香に無視されるのは慣れっこだったので、そのまま目をつぶってむにゃむにゃ言った。数分ごろごろと布団の上で転がってからふと、薄目を開けると、目の前に文香が座ってじっとこちらを見ていたので「んー?」と唸った。
「私の耳を見ても、驚かないのですね」と文香は聞いた。
「文香ちゃん、守り猫だよね? キミたちのことをむかーし見たことがあるからね。三千年くらい前かな、ナイルのほとりのお役所でネズミから書類を守ってた」
文香はくらりと揺れた。「三千年……」と呟いて、その時間の長さがうまく想像できないようだった。
志希は、指折り数えて、
「あっ、自分ちで使ったこともあったかなーっと。経典とか、魔術書とか、とにかく紙を外敵から守ってくれるのは便利だよねー。でもさー」
邪気のない様子でくすくす笑って、志希は「短命なのは困るよね」と言った。文香の肩にはそれですこし力が入ったが、志希はそれには気づかなかった。
「ぽこぽこ代替わりしてくれるから良いんだけど。文香ちゃんはほんとはいくつなの?」
「……次の誕生日に、三歳になります」
「あっはっは、すっごい年齢詐称。わかるよー。あたしは逆だけどねー、アイドルやりたいもんねー」
「……志希さんは、何者なのですか」
「あたしは単なる長生きな錬金術師だよ。一ノ瀬・トリスメギストス・志希でーす。よろしくー」
文香は目を見張って、「ホメロス・トリスメギストス……半神半人の……」と呟いた。
「そうそれそれ。まあ神ってのはいいすぎだし、今はポリメギストスって感じだけどね。何回も何回も生まれ変わっているから」
「定命なのですね」
「いや、呪いだよ。自分に呪いをかけたんだ。死んでも生まれ変わる呪い」
「……それは単なる、輪廻転生の類ではないですか」
「純度が違う」
志希はくるくると指を空中で回した。
「記憶をある程度持ち越せるんだ。それで一切の終わりなく研究できるようになると思った」
文香は冷めた目で「良かったですね」と言った。
「それがさー、結構すぐ飽きちゃったんだよねー。フツーの、充実した人生が送りたいなーってなっちゃった。意外とあたしフツーの人間だったんだな〜って四回目ぐらいで気づいちゃったんだよ。だけど、何もかもがだめだった。あたしは永遠にフツーには生きられなくなった」
「なぜ?」
志希はすっと目を細めて「すべてのママがね、すぐに気づくんだよ。こいつは娘じゃない。あたしがおなかを痛めて産んだ子はこいつじゃない。誰だ! 誰だ! オマエは、誰だ!」と、ベッドを何度も叩きながら恐ろしい形相で叫ぶと、「ってね」と言って顔を緩めた。
「そんな子どもが幸福でいられるわけがない。だからあたしは、ずーっとコキュートスの底にいるの。愚かさのために行われた最悪の刑罰。最近はずーっと『ザ・最大宗教』に追い回されてるしさ。あたしは文香ちゃんみたいにみじかーく生きてフツーに死ねるの、羨ましいんだー」と言った。
文香は押し黙ると、「家に火をつけるような母親が、普通……?」と聞いた。
「でも文香ちゃんは無事だったんでしょ、なにか理由があったんじゃないのー」
「おかあさまは、私を鷺沢の家に戻したいようでした。私の本を、毒だと言って」
「鷺沢の家ってのはあれか、長野だから信州善光寺だ。密教筋のほう?」
「……そうです」
「そっかー。ま、文香ちゃん乱読のクセ強いもんね。守り猫の子供があんなにいろいろ読んでたら、あたしでも身体に毒だとは言うかもな」
文香はむっとして、
「……本は私の、命でした……」
「あのさあ」
志希は少しいらいらした様子で顔を文香に近づけると「本が大事なのはわかるよ? そういう種族の性質だもんね。だけどさあ、あたし、文香ちゃんのママは文香ちゃんを守ろうとして、そこまでやったんだと思う。そんなママなかなかいないって。けっこう根性ある。羨ましい」と言った。
そして、「文香ちゃんはわがままっ子なのかな? かわいいネコちゃん扱いしてほしいワケ?」と、子供をあやすようにこてんと顔を傾けた。
ごるる、と音が鳴った。
それは文香の唸り声だった。静かな部屋の中では、文香の筋肉が戦いに備えて軽く膨らむときに服がみしみしと立てる音は大きく響いた。「おっと……」と志希は言うと、宙空に輝くサインを書き、先程文香の耳を隠すために飲んだマナの残りを使って魔法を操った。指先が放つ緑の輝きが消えると、間髪をいれずに文香が立て膝をつき、ヒュウッと風を切って唸ったその右腕がマットレスを何本ものスプリングごと引き裂いてばちばちばちばちっという音が鳴った。空中で「待った待った待った」と言った志希は軽くベッド際の白い壁、天井を蹴り、すとんと着地すると、「ここ美嘉ちゃんちだから。帰ってくるから!」と叫んだが、志希の方を振り向いて仁王立ちした文香のすさまじい形相に、「あちゃー」という悲鳴を上げた。文香の鼻には怒りのために幾筋もの皺が寄って、その瞳は激しく光り輝いていた。
「何も知らないくせに……」と呟くと、うがう! と叫んで突進した。
志希が横っ飛びに飛んで、今度は壁をすり抜けてバスルームへと逃げると、文香は壁に当たって大きな凹みを作ってから、軽い材質の扉をぶち破って押し入り、その勢いで壁に肩からぶつかったせいで水回りの設備も破壊した。バシャーッと床に広がっていくお湯からもうもうと湯気が立ち上った。志希は尻からバスタブに倒れ込みながら「いたた……」と後頭部をさすったあと、バスタブの縁をまたいで自分を見下ろす文香に向かって、ふ、と笑って「けっこう派手なの履いてるね」と言った。
「美嘉ちゃんカワイソー、守り猫ならもう少し身体を操るのが上手くてもいいと思うな」
すと、と文香は降りて、志希のすぐ近くまで顔を寄せた。「あなたは、魔女のくせに人の心を操るのが下手すぎる」と文香は言って、「人?」と鼻で笑った志希の首にぐっと手をかけた。
「殺せるなら殺してみなよ」
「足の指先から順番にスライスしていきます」
「あ、待ったごめん。痛いやつほんとやめて。魔女裁判、超トラウマなんだよにゃー」
「あなたにも母親がいるのでしょう」
志希はそう言われると急に真面目な顔をして黙った。しばらくして、「どの母親?」と聞いた。
「誰でもいいです。その人が、あなたを殺そうとしているということを思ってください」
「ママは、そんなことしない!」
志希が少しむきになったように言って、二人はそのまま黙りこくった。どぼどぼと床にたまりつつある湯の音がひとしきり響いた。
「……一度だけ、魔女の母親の元に産まれたことがある」と、志希は重大な告白をするように、文香の目をまっすぐに見て言った。
「……あのときだけは、通じ合っているという感じがあった。母親は、いくら子どもを嫌っても殺したりはしない。単に、無視をするだけ」
く、と文香は笑った。「三千年生きていて、よくもそのような……」と言いかけた。そして、湯気の熱気に火照って汗の浮いた顔へ、急激に嗜虐の快楽を湛えて「ああ……」と言った。
「思い出しました」と言って、凄まじい表情で笑った。
「アイザック・ニュートンがルーカス教授職についた次の年、東ヨーロッパからロシアに落ちていった貴人の一家が、東方正教のひとびとに処刑されたという文書を読んだことがあります。母親と娘が魔女だったという話でしたが、その娘は記録によると四歳で、私はそのおさなさに違和感を持ちました……。魔女裁判でそれほど年少の子どもが裁かれた例はとても少ないために、記憶に強く残ったのです。そしてもう一つ」
すうっと息を吸った。
「『借胎の魔女』、非常に若年から恐ろしい魔法を使う人々の総称と言われています。生まれ変わりを使ってそのような偉大さを手に入れていたのではないかという民間伝承です。……私は、今、すべてが完全に繋がった思いでいます。三倍偉大な者……ホメロス・トリスメギストスの伝説も、もとはべつべつの三人の賢者が、後の歴史書によって一人の人物と誤解されたと言う読み方が現在は主流です。しかし、それは間違ってはいなかった。すべては、同一のひとり」
文香はぐうっと口元を志希の耳へと近づけた。「借胎の娘よ、おまえは偽の愛情しかうけたことがない。だからほんとうの母に、幻想を抱く。おまえは私を人ではないと嗤うが、女の腹を借りて産まれるおまえこそ人間なのか?」と囁いた。身を引いて、志希の瞳のなかに何か崩れていくものがないか、探そうとした。
志希の目には涙が溜まっていた。口は一文字に結ばれ、明らかに文香の言葉に衝撃を受けていた。しかし、勝ち誇るかのように口角を上げる文香を見つめてしばらくの間じっと黙ったあと、「ってゆーかさあ。文香ちゃんちょっと勘違いしてない?」と言って、
「あたし、キミの恩人だよ? 誰が耳を隠してあげたんだっけ」
「私は、恩をかけられたつもりは――」
「わかってないなあ!」と志希は大声を出して、文香はびくっと震えると、少しだけ半身を志希から逃した。
「……明日の焼きハロ、耳が隠せなかったらどうやって出るつもりなの……?」と志希は言った。
そのままふたりはざあざあと出続けるお湯と湯気に包まれて、びくともしないまま睨み合っていた。やがて、ぎゃあーっという激しい悲鳴が聞こえて、二人は顔を上げた。
美嘉の足音がどすどすと鳴っていた。帰ってきてすぐに我が家の異変に気づいたのだった。
「なにこれなにこれなにこれ!?」
美嘉は部屋の中を一通り駆け回って被害をすべて確認していた。
「隠れよう」と志希が言って、文香はこくりと頷き、態勢を低くした。志希の乳房の間に顎先を突っ込んだまま、文香は「ま・ほ・う」と口の動きだけで囁いたが、志希が口元でバッテンをつくって「か・ら・っ・ぽ」と返したので、顔をしかめると頭のうえでクルクルパーのジェスチャーをした。
「うわーっ、ここも!?」とバスルームを覗いた美嘉が言った。一瞬で二人がそこに隠れていることを察知して、立ち込める湯気と熱湯に絶望の表情を浮かべながら「アンタたちこれどういうこと!?」と美嘉は浴室に向かって叫んだ。
文香と志希はしばらくの間浴槽の中に隠れていたが、やがてそろーっと二人同時に中から頭を出すと、激しい靄の向こうでカンカンに怒っている美嘉を見上げてから顔を見合わせた。そして『ケンカ、しました……』と声を揃えて言い、うなだれた。
「しんっじられないっ!」と美嘉は叫ぶと、その場の収拾を後回しにして、そもそも人の家に呼ばれたときには、から始まるお説教をごうごうと始めた。志希と文香はバスタブの中に正座してしばらく黙って聞いていたが、志希は数分ほどでそわそわし出すとつん、と文香をつつき、「十三世紀の魔女狩りよりキツい」と文香にだけ聴こえる声で言った。文香は「おばあさまより、こわい……」と、ぐらぐらとした頼りない口調で言うと、熱気に当てられた真っ赤な顔でふらっと反対側に揺れて、そのまま揺り返しで志希の方へと倒れてきた。
「美嘉ちゃんストップストップ! 文香ちゃんがなんかヤバイ!」
「もーっ! アタシはね、ほんとうに志希のそういうてきっとうな言い訳には飽き飽きしてんの! 今日という今日はまっじっでキレたから、覚悟しなさいよね!」
志希は美嘉が湯気の向こうでいっこうに小言をやめようとしないことに気づいて「あれ?」と言った。「なんであたしが……?」と自分に問いかけながら文香に肩を貸すと、ぐっと立ち上がろうとして足を滑らせ、「あ」と言いながらひっくり返った。志希が後頭部を思い切りバスタブにぶつけたガツンという大きな音と「ふぎゃっ!」という悲鳴は、山彦のようにいつまでも響いていた。
1 note
·
View note
Text
焼きそばハロウィンはいかにして無敵のアイドルになったのか(2)
ごうごうと音を立てて裏庭の果樹園が赤く蠢いていた。永遠に収穫されることのなくなったりんごたちは次々に燃え落ちていった。光線を歪めて通すガラス窓がちらちらと女性の顔に炎を落としていた。質素なドレスからむき出しになった上腕を伝い、デスクの上へとおびただしい血が流れていた。その女性はみずから三重四重にナイフで切り口を開いて、金属のボウルに血を溜めていたのだった。ふわりと娘の方を振り向いた彼女のかんばせは、尊い使命を神から与えられて、地獄に遣わされた人の純真を示すヴェールのように白く輝いていた。最も高い天にたなびく雲よりも美しく結われたプラチナ・ブロンド。晴れた日のエーゲ海の上下を混ぜ合わせてしまったような知性に溢れたブルーの瞳。
ボウルから血をおさない娘に何口か含ませると、「絶対に声を出してはだめよ」とその女性は言った。腕の痛みで眉はひどく歪み、額には乱れた前髪が数本張り付いていた。娘はこくこくとうなずいた。母親が言うことを忠実に守るために、口元には両手が当てられて、目には涙が浮かんでいた。母親が「いい子」と言って微笑んだのを見て、ああ、愛しいママ、とその娘は思った。ママが苦しむのを、見たくない。ママが喜んで、嬉しい。
その娘は、かつての志希だった。
そうだ、これはあたしの物語だった、と志希は思った。志希はその鉄臭い液体を口いっぱいに含み、母親の言う通りベッドの下に潜り込むと息を殺した。そこにはカビ臭い本が何冊もあって、それは志希が数ヶ月前にそこに隠したあと、忘れてしまった本たちだった。志希の母親は「いい子だから。きちんと、隠れていてね」ともう一度言いながら、悲痛な表情で彼女の手を握った。血でいっぱいのボウルが横っちょに押し込められた。志希は本の内の一冊を大事に抱えて、ついでボウルを脚の下に隠した。
こく、と血を少しだけ飲んだ。
「ごめんなさい」と彼女は言った。
「許してね。力のない私を許してちょうだい」と、囁いた。
そうして彼女が足早に去っていくのを志希は見送った。
自分の息がうるさすぎて、ごうごうと知恵の実が燃えていく音は遠くなった。
やがて重々しい足音で、数人の兵士たちがやってくる。全員が、統制された動きで部屋を荒らし回った。クローゼットに整然と並んでいたお気に入りのドレスたちは床にぶちまけられ、踏みつけられた。ベッドシーツはめちゃくちゃに切り裂かれ、本棚の本も同様にすべてが投げ捨てられた。がしゃんと窓が割れる騒々しい音がして、家具たちが外に放られているようだった。
志希はそれらをすべて、そのベッドの下の小さな隙間から見ていた。こく、と血を飲む。ボウルの血を口に含めば、まだ少しは、保つはずだった。誰に祈ればいいのか、志希にはもう分からなかった。
そして、母親が戻ってくる。
母親は自分の脚で歩いていない。
つま先はずるずると引きずられている。二人の兵士たちが彼女の両脇をきっと抱えている。そして、彼女は木でできた床に打ち捨てられる。志希の愛したドレスと同じように、本たちと同じように。死の直前、ひどい苦悶に喘いだであろうその美しかった顔や目に、もはや生命のしるしは無く、志希は約束を破って、「ママ」と小さな声で呟きながら、ベッドの下からその死体に手を伸ばした。志希の周囲で、正体のわからない激しい火がぼうぼうっと燃え盛っている気がした。
伸ばされた彼女の手は、炎の向こうで、親しい人にそっと取られた。
「志希」と美嘉は言った。涙で歪んだ視界の奥で、志希は母親の代わりに美嘉を見つけた。
すべてはかつてあった真実が夢に溶けた姿だった。
友愛に満ちた顔には、不安が滲んでいた。ベッドから離れて光るデスクライトだけに照らされて、美嘉の尖った鼻が作る陰翳は、記憶の中の母親のそれに少しだけ似ていたが、おさなさが濃かった。
志希はじっと美嘉の輝く瞳を覗いて、微笑んだ。「泣いちゃった」と、くすくす笑った。そのまま、ぐす、と鼻を啜って、「あー」と意味なく呻きながら人差し指で目の下を拭い、
「美嘉ちゃん台本見てたの? 今何時?」
「一時過ぎ」
「明日も撮影なんだから、早く寝ないとだめだよ」
ふ、と美嘉は笑って、「いつもとなんだか、逆だね」と静かに言った。
そっと美嘉が手を離したとき、志希の手はわずかに空を掻いて、去っていったそれを求めた。求められた美嘉の温もりは、デスクライトをか、ち、とゆっくり消したあと、志希のベッドへと戻ってきた。
志希は美嘉の胸元に抱かれて、少し恥ずかしそうに「ちょっと、美嘉ちゃん」と言った。「お母さんの夢を見ていたの?」と美嘉は聞いた。短く迷って、志希は柔らかな美嘉の胸の中でうなずいた。
「志希のお母さんは、どういう人?」
「……よく、覚えてない」
「そう」
美嘉はそのまま黙って、腕の中の志希の頭を撫でていた。
いつまでも、ゆっくりと撫でていた。
やがて、発作がやってきた。悲しみの発作が作る苛烈な嵐に、志希はほとんど息ができなくなった。ぎゅうっと美嘉のシャツを握りしめて、志希は激しく嗚咽した。その泣き方には、激しい生命の力が込められていた。生きるためには、そうするしかなかった。
「ママ」と、志希は母親を求めて泣き続けた。
結局のところ、志希はそういう星の下を選んで、産まれてしまったのだ。
* * *
何時間も回り続けるように精巧に作られた独楽が回転しているとき、巨大な運動エネルギーを秘めたまま一見静止しているように見える。それと同じように、美嘉は志希の方を向いたあと、口をくっと結んで動かなかった。心中の感情がこれほど苛烈に渦巻いているひとを見たことがなかったから、志希はその熱量の凄まじさに気がつくと、食べかけのゼリーが載っていたスプーンを咥えたまま、動くことができなくなった。
やがて、野生の動物の子どもが襲われた瞬間の母親のように、美嘉は素早く立ち上がると一言も言葉を発さずにベンチから立った。「え」と志希は小さな悲鳴めいた声を上げると、「ゼリー……」と呟いて、手元のそれを大事そうに両手で持ち、そのまま焦ったようすであとを追いかけた。
きめ細かい乾いた土の上を早足で歩く美嘉に小さな歩幅で走って追いつき、志希は「美嘉ちゃん、ゼリー」と言ってそれを差し出そうとした。美嘉は「いらない」と言うと、「着いてこないで」と表情のない声で彼女を拒否した。志希は「う」とひるんで、それでも「美嘉ちゃん……」と呟きながら美嘉の肘をそっと取ろうとした。
ばし、と腕を払われて、志希が持っていたゼリーが土の上にカップごと飛び散った。二人の向いからちょうどやってきた室内犬が低い声で唸りはじめ、その飼い主の子どもは慌てて犬を抱えると、足早に去っていった。
「どうせ、アタシがなんで怒ってるかもわかんないんでしょ」
美嘉に言われて、志希は答えを探そうと必死に頭を巡らせた。志希は半年ほどの彼女との付き合いの中で、何度も何度も美嘉を怒らせたことがあった。ふざけてわざと怒らせたことも、意図せず怒らせたことも、怒っている理由がぼんやりとわかるときもわからないときもあった。しかし今日ほど彼女を怒らせた理由が知りたいと思ったことはなかった。彼女がその魂の底から真剣に怒っていることがわかったからだった。
ほとんど一番に大事な友人にどうしても何かを言わなければならないはずなのに、なんと言っていいのかわからずに志希は下を向いた。
美嘉は、ふっ、と鼻で笑った。「……ごめんねも言わないんだ」と、掠れた声で言って、志希を見���めた。志希は何も言えずに眉を寄せて、何か見るべきものを探し、しばらく地面の上で飛び散ったゼリーが一列の蟻に運ばれていくのをじっとなぞっていた。やがて視野の端をかすめた何かに気づくと、ゆっくりと顔を上げ、その視点は美嘉の手に留まった。
志希は美嘉に駆け寄ると「ちょっと!」と美嘉が振りほどこうとするのに構わず、彼女の手を引いて近くにあった水飲み場まで連れて行った。蛇口を捻って水を出すと美嘉の左手をその下に寄せた。美嘉の手のひらは、文香に倒されたときに傷ついて、皮膚が人差し指の爪ほどの範囲でめくれていた。その傷口に、美嘉は冷たい水が触れたときに初めて気づいたのだった。桃色の皮下組織が乾いた土の下から現れて、「いつっ」と小さな声で美嘉は呻いた。志希は何も言わないまま、大事そうに傷口を水の下で何度か拭うと、綺麗になったその手に顔を近づけてよく確かめてから、美嘉を見上げた。
「なに?」と美嘉が言うと、志希は「バンソウコー、ない」と悲しそうに言った。美嘉はため息をついてタオルハンカチで傷口を拭いながら近くのベンチまで歩いていき、バッグを片手で探ると絆創膏を取り出して志希に渡した。それが自分の親指の付け根へと丁寧に貼られるのをじっと待った。
すべてを終えると、志希はほっと息を吐いた。美嘉は手を引いて「ありがとう」と言った。志希は美嘉におびえているかのように、何も言わずそのまま地面をつま先で軽く擦っていた。
「なんで今日、レッスンに来なかったの」と美嘉は言った。
志希はびくりと身を固くした。数秒のあとにもう一度、拗ねたように土をかき回し初め、やがて「……忘れてた」と一言言った。
はああ、と長いため息を美嘉はついた。
「……ちょっと勘弁してよー、ほんとにもー……あのさ」
美嘉は立ち上がると、ずっと地面を向いていた志希の視線をひらひらと治療の終わった手のひらで遮って上を向かせた。「何回も何回もチャットで言ったでしょ。明後日は最終確認だよー、明日は最終確認だよー! って。志希は全部振り覚えてるかもしれないけど、アタシは不安なの。文香さんは……」
美嘉は一瞬言葉を区切って、何か痛みに耐えるかのような表情をした。志希が不思議そうにそれを見つめているのを無視して、
「文香さんはかなりダンスが不得意だし、三人で合わせる機会はすごく大事だと思ってる。明日からの本番で、失敗しないように」
新たなため息が美嘉の口から音もなく出ていった。
「……ま、ほんとは志希もちゃんと分かってるよね……」
美嘉は志希の青い目を覗き込んだ。「なんで、忘れたの? なにかすごく大事な用事があったの? それでいつもみたいに頭からスポーンって抜けちゃったんでしょ」
はく、と志希の口が動いた。「怒らないから、言ってみな」と美嘉は小さな笑みを口元に浮かべて言った。
長い沈黙があった。
「……マ、ママ、に……呼ばれたの」と、志希は途切れ途切れに言った。
「……どういうこと?」
「……あの、ママ、今日東京に出てきたから、それで……最近はどうしてるのって、何か変わったことない、って、電話で……言われたから……あ……」
志希はベンチに座ったまま、美嘉を見上げていた。彼女の顔が変わっていくのを、どうすることもできずに見つめていた。そして、「死ね」と彼女に言われたとき、もともと白かった顔色はまっしろに変わって、口元は悲鳴の形を作り、首だけが二、三回、静かに振られた。
「馬鹿みたいじゃん」と美嘉は言った。
「アタシ、馬鹿みたいじゃん!」と、叫んだ。絆創膏が貼られたばかりの握りしめられた拳が、ぶるぶると震えていた。
「ほ、ほんとに呼ばれたんだよ! ほんとだよ!」と志希が必死の声で言うと、「アンタアタシにお母さんは死んだって言ったでしょ! それも忘れたって言いたいの!?」と美嘉は叫んだ。
小さく風が吹いて、二人の頭上を覆うクスノキの枝がざあっと揺れた。激しい太陽の光が木々の間から顔を出し、呆然と立ち尽くす志希の姿をつかの間、真実を暴くかのようにぎらっと照らした。怒りのあまりに美嘉の声は震えて、両眼には今にも溢れ出しそうなほど涙が溜まっていた。
「志希、マジ、なんなの? 全部ウソなの? ……沖縄で同じ部屋、泊まってさ、アイドル楽しいね、ずっとやっていきたいねって語って……あの夜……」
光る瞳を残酷な形に曲げて、志希を睨みつけたまま、ぐ、と言葉に詰まり、また口をひらいた。
「アタシだけが本当のこと言ってたの? アタシだけがアンタに騙されて馬鹿みたいに身の上話して……ねえ、志希」
美嘉は笑った。途轍もない悲しみを隠して、涙を零しそうになりながら笑っているので、志希はその凄惨なようすにほとんど耐えられなくなり、く、と唇を噛んだ。
「志希、アタシのこと馬鹿にしてるでしょ」
「してない」
「馬鹿にしてる! アタシの何もかもを、志希は絶対馬鹿にしてる! 馬鹿だ、馬鹿だ、真面目に人生語っちゃって、アイドルなんて真面目にやってって、馬鹿だって!!」
「馬鹿になんかしてない!」
「もういい! 志希なんか死ね!」と言って踵を返すと、美嘉はそのまま早足で歩き始めた。
「……なんでそんなこと言うの……」
志希がそう声をかけたとき、美嘉はついに両腕のすべてを使って志希からは見えなくなってしまった顔を拭った。とうとう溢れ出した涙を、どうにかしようと努めながら、その場から消えゆこうとしているようだった。去っていくその背中を見つめて、「ほんとなのに!」と志希は叫んだ。ぐっと涙をその瞳に湛えて、「あたし、ママいっぱいいるんだもん、ほんとだもん。い、今のママに呼ばれたんだもん!」ともう一度叫んだあとも、美嘉が脚を止めないのを見た。
そして、何もかもが決壊した。
「美嘉ちゃんの馬鹿ー!」と大声で詰ったあと、志希は子供のように泣き出した。嗚咽しながらぽたぽたと地面に落ちていく涙の粒をどうにかしようともせずに、ぎゅっとカーディガンの袖口を握りしめたまま志希は泣いていた。ああーという長い泣き声は公園の隅々まで響いて、遠い通路から脚を止めて彼女を見ている人々が何人もいた。志希はそのまま泣きながら立ち尽くし、葉の間の小さな隙間から漏れる燦然とした光を全身に点々と受けていて、やがてそのままどこかへとふらふら歩き出した。美嘉とは違う道を選び、泣き声のトーンをまったく落とさないまま十メートルほど歩いたところで、早足で戻ってきた美嘉が志希に追いつくと、その両手を握って「ほんとなんだね」と言った。
「ほんとだって、言ってるのに!」と志希は言って、振りほどこうと少しだけ暴れた。
「わかった」
美嘉はもう泣いてはいなかった。しゃくりあげる志希を、前からぎゅっと抱きしめて、後頭部をやさしく撫でながら「ごめんね、信じなくて」と耳元で囁いた。そのまま火を放ち続ける石炭のような志希の感情が落ち着くまで、目をつむって抱き続けていた。
子どもたちの陽気な声が空へと抜けていった。美嘉と志希の二人は疲れ切って、出口近くの噴水の縁に座り込み、一歩も動けずにいた。志希は赤い目をして、ぼうっと噴水がきらきらと落ち始めた太陽の光を反射するのを眺めていた。時折、彼女はきらりと美しく輝いた。美嘉はじっとその顔を見つめながら、
「志希のお母さん……いっぱいいるのね」
さらさらとした水音に、志希は沈黙を乗せて答えた。
「何人いるの、お母さん」
「……わかんない。もう数えてない」
はあーっと、美嘉は呆れてため息をついた。「ちょっとそれホントでしょうね……」と呟いたあと、テレビヒーローの真似をしながら追いかけっこをしている小さな子どもを眺めながら、「アタシにはわからん世界だなー」と言った。
「お母さんと、何の話してたの?」
「今度、焼きハロでやるライブ、インターネットとかで流れるかもしれないよって。だから見てねって」
「おーっ、いいじゃん」
「言おうとして……なんか怖くて、話せなかった」
がくっと下を向いて、「すっぽかされ損じゃん、アタシ……」と、美嘉は軽く笑った。
拗ねたようにずっときれいな水の流れを見ている志希を、美嘉はもう一度見上げた。きっとこの子は、どこかの喫茶店でお母さんと話しているときもこうなんだろうなと思った。目の前で起きていることに、とことん興味のなさそうなその視線。たどたどしい返答。退屈そうにほうっと吹かれる、ただ生きるための微かな吐息。だがその中心で、何かを求めようとする強い願いが燃え盛っているのを、少なくとも美嘉だけはもう知っていた。
「美嘉ちゃんはさー」
「ん?」
「美嘉ちゃんがアイドルやってるのをすごーく見てほしい人っている?」
「んー、このアタシを日本中に見せつけてやろう! とは思ってるけど」
「うまくできてる?」
「どうだろうね」
美嘉はくすくす笑った。「努力はしてるよ。マジで」
「……あたし、アイドルやっててほんとにいいのかなー」
「なんで?」
志希はゆっくりと美嘉の方を向いた。水面が彼女の顔を怪しく照らしていた。
「ママ、あたしがアイドルやってるってこと、知らないんだ」
またそのパターンかー! と美嘉は思った。くうー、と下を向いて、ガシガシ頭を右手でかきむしったあと、
「あのさ、実は文香さんも――」
ぐううう、ととてつもなく大きな音が美嘉の声を遮った。着崩したシャツのおなかのあたりを抑えて、志希は少し悲しそうに美嘉を見た。美嘉はしばらく目をぱちぱちとさせていたが、にこりと笑うと、「アタシの家、行こうか!」と陽気に言った。
「美嘉ちゃんのアパート? 手料理?」
「手料理は正解。アパートは不正解」
美嘉は勢いよく立ち上がると、志希に手を差し出して「行こ」と言った。志希は吊るし売りの人形のように美嘉を見上げたあと、弱々しくその手を取った。
「なんか、幼稚園みたい」と志希は言った。
『児童養護施設 飛翔』と書かれた看板の横の壁に、子どもたちがペンキで描いた絵が連なっていた。志希はそれに顔を近づけながら「美嘉ちゃんはどのへん描いたの」と聞いた。
「その壁建て直したのけっこう最近だから、アタシのはないよ」
「なあんだ」
つまんないの、と言いながら、志希は熱心に横歩きをして、壁をじっと見つめていた。美嘉は腰に手をかけると、ふふ、と笑って、何棟もの宿泊棟へと視線を移した。裏庭で遊んでいるのだろうか、姿の見えない子どもたちの声が建物に反響していて、美嘉は活気を感じた。
「おっ、美嘉ねえじゃん!」
遠くから声をかけられて、美嘉は志希の先から歩いてくる少年のほうを振り向いた。志希もそれに気づいて、壁から離れると美嘉の後ろにさっと隠れた。
「トオル、今部活終わり?」
「そうだよもー、めちゃつかれた」
巨大なバッグを背負い直すと「昨日ぶり〜」と言ってトオルは美嘉に上腕を差し出した。ごつ、とぶつけて「いえい」と二人は親しげに声を合わせた。
「美嘉ねえの友達? こんちは」と、トオルは子供らしさの微かに残る笑顔を志希に向けた。
「トオルは志希の二個下だよ、バドミントンがうまいんだ」と、美嘉が志希に紹介すると、志希は「こんにちは、一ノ瀬志希です」と小さな声で挨拶した。差し出された大きな手を恐る恐る握る。
「志希はねー、アイドル仲間」
「うおー、マジか!」
トオルはぱあっと顔を輝かせると、「一ノ瀬さん、お会いできて感動っす!」と言うと、握ったままの手をぶんぶん振り回した。志希はあうあうと焦ったあと、さっと美嘉の背後にもとのように隠れてしまった。
「ちょっとアンタ、あんま乱暴しないでよ。つうかアタシも一応アイドルなんだけど、なんだと思ってんの?」
「やー、本物はやっぱ全然違うね! めちゃかわいい!」
「あんま調子乗ると彼女に言いつけるよ。昨日ライン交換したんだから」
「すみません、やめてください」
神妙な言葉とは裏腹にあははと笑うと、トオルは口元に手を添えて、小声で「ほんとは初彼女のことみんなに自慢しにきたんじゃないの〜?」と美嘉に囁いた。
「初彼女……」
志希は目を丸くした。数秒ほど固まった美嘉は全身を真っ赤にして「んなわけないでしょ! バカ!!」と叫び、既に宿泊棟のほうまで逃げていたトオルを追いかけていった。
「昨日のお返し〜! 美嘉ねえのアホー!」
トオルが宿泊棟に駆け込むと、はー、とため息をついた美嘉はとぼとぼと戻ってきて「ごめんね、バカで」と志希に謝った。
「美嘉ちゃん、昨日も来てたの? よく戻ってきてるんだ」
「ん? んー、今日はほんとにたまたまだよ。アタシは家が場所的に近いからすぐ来れるっちゃ来れるけど、フツーは一回外に出たら、あんまり戻らないかな」
「なんだか、不思議な家だね」
志希の正直な感想に、美嘉は少しの間黙った。黄金に色を変えつつある太陽光線が、ピンクに染められた髪を掠めて志希の瞳を焼いたので、志希は微かに目を細めた。「そうかもね」と言って、美嘉は猛烈な光の中心で笑い声を上げた。
「さて……チサはどこにいるかな……」
美嘉は志希を促して敷地の中を歩いていった。何人もの子どもたちが美嘉を見つけると親しげに挨拶をして、志希はそのたびにたどたどしく自己紹介をした。女の子たちばかりが遊んでいる場所をいくつか通ったあと、美嘉はついにちいさな図書室の暗がりで、赤い絨毯の床にぺ���りと座って図鑑を読んでいる女の子を見つけた。
「チサ」
図書室の中にはほかに誰もいなかった。からからと引き戸を大きく開けながら、小声で美嘉が彼女の名前を呼ぶと、チサは顔を上げて、「美嘉ちゃん」と嬉しそうに言った。
「あさ、起きたら美嘉ちゃんいなくて、悲しかった」
「あはは、ごめんね。お仕事があって忙しかったんだ」
「そっかー……」
チサは下を向いて、「わがまま言って、ごめんなさい」と言った。「昨日の夜、アタシに帰るなってみんなが言ったこと?」と言いながら、美嘉は靴を脱いで中庭から図書室へと上がった。
「大丈夫、遅刻とかはしなかったから」と、チサの頭をぽんぽんと叩いた。チサは悄然として床を見ていた。美嘉は苦笑いを浮かべながら「さて」と言った。
じゃじゃーん、と、美嘉は大きく手を広げて志希を指し示した。
「アタシが連れてきた、この子は一体誰でしょう!」
「……知らないおねえさん」
「や、まあ、見たことないだろうから、そうなんだけど」
「美嘉ちゃん」
志希も訝しげに美嘉を呼んだ。美嘉は志希に向かって笑みを浮かべ、
「覚えてない? 夏休み子供アイドル相談室で、石鹸のつくり方を聞いてきた……」
あ、と志希は声を出した。
「そうか、キミはあの子か」と、靴を脱ぎながらふふ、と笑うと、急に自信に満ちた態度で図書室に上がった。膝で立って目線を合わせ「こんにちは」と挨拶をすると「一ノ瀬志希です。夏休みのラジオ番組で、キミの質問にこたえたのは、あたしだよー」と言うと、床に置かれていたチサの手にそっと触れた。
チサはぼうっと志希を見ていたかと思うと、ぱあっと顔を輝かせた。「石鹸、できました! あぶないって言われたところは先生たちに手伝ってもらって――」と、流れる川のように喋り始めた。やがていくつかのあらたな質問が溢れ出て、志希はそのひとつひとつに丁寧に答えていった。美嘉は微笑みながら二人のようすを見ていたが、志希に「ご飯作ってくるから」とひとこといい添えて、図書室を出ていった。
中庭を楽しげな長い影が、小さな鼻歌と共に横切っていった。
「ハンバーグ美味しかった? 時間かかっちゃってごめんね」
「ううん。みんなとお話してたから、楽しかったー」
皆に挨拶を済まし、二人は施設をあとにしていた。日はすっかり暮れて、薄暗い中に街灯がぽつぽつと点いていた。志希はカーディガンのポケットからセロファンの袋に包まれたマーブル模様のきれいな直方体を取り出すと、街灯にかざしてほうっと息を吐いた。
「いいなー。それ半分に切ってアタシにもちょうだいよ」
「絶対だめ」
「ええー」
けち、と言いながら、美嘉はとても嬉しそうに笑った。志希は赤く細いリボンを少し緩めて、すっとその香りを鼻腔に満たした。
「ダージリン、ヘーゼルナッツ、ハニー。このブラウンはココアか……」
しばらく余韻に浸ると、大事そうにそれをポケットに戻して、
「きっとこれで身体を洗ったら、お菓子みたいになっちゃう」と言うと、泡だらけになった自分を想像したかのようにふふふ、と笑って、くるっと回った。
「美嘉ちゃん、ありがとう!」と美嘉の目を見て言い、また歩き出した。美嘉は驚いてしばらく立ち止まっていたが、「びっ……くりしたあ。志希がお礼を言うなんて……」と、あとを追った。
「次はごめんねが言えたらもう一歩成長かな……ていうか、元気が戻ってよかったよ」
「んー、どうだろにゃー」
志希は機嫌の良い子どものように大きく手を振って歩く。しかし、目を細められ、口元は薄い冷笑を作っているのがわかった。いつまでも消えないそのアンバランスさがひどく哀れに思えて、美嘉は悲しくなった。
「ママ……ママたちね、きっとみんな、あたしのこと嫌いだと思う」
「……なんで?」
「みんなあたしがほんとうの子どもじゃないということを、おなかの底からよくわかってるんだと思う。だから嫌いなの」
「……そうかなあ」
言葉を区切ると、近くの草むらで秋虫が鳴く声がはっきりわかるようになった。美嘉は次の街灯が自分の身体を照らし始めるところまで黙って歩いた。
「アタシは逆に血縁のことなんて信じてないから、もっと大きなつながりのほうを強く信じてるよ。だから志希は大丈夫だと思うんだけど」
「大きなつながり?」
「愛だよ、愛」
「うっわ」
恥ずかし、と茶化すと、にゃははと笑った。
「まー、よくわからないけど、今日のあたしは、アイドルできてた! すっごく嬉しかった!」
たたっと走って、次の街灯に先にたどり着くと、
「だから、あたし、アイドルを馬鹿になんかしてないよ。美嘉ちゃんのこと、馬鹿になんてしてない」
「もー、わかったから」
その街灯に美嘉が歩み寄ったので、二人はお互いがはっきりと笑っていることを知った。
「早いとこお母さんに言いなよ」
「努力しまーす」
「ったく、保護者の同意書どうやってくぐり抜けたのよ」
「署名のギゾー」
何かを言いかけた美嘉はぴた、と止まって、数秒してから「忘れてたあ……」と座り込んだ。
「なになに、なにかトラブル?」
「今日の練習、文香さんも来なかったんだよ」
「ほほー」
「午後に文香さんち行ったんだけど、『親にやめろって言われたから、アイドルやめる』って言われちゃって」
「あは〜ん、で、それを今の今まで忘れていたと」
志希はふむふむ、と何かを考える振りをしながらくるくると視線を動かしていたが、やがて、「美嘉ちゃんは、馬鹿なのかにゃ?」と言った。美嘉はゆっくり立ち上がると、思い切り振りかぶった拳を志希の頭に振り下ろしながら、「お前が言うなっ!」と叫んだ。
その駅のホームに降り立ったとき、志希はすうっと一息空気を吸い込んで、立ち止まった。「どうかした?」と美嘉が聞いて、志希は首を振ってこたえた。炎が暴れ狂う匂いだ、と志希は思った。どこかでだれかの財産と生命が、燃えているのだ。蛍光灯に照らされながらとんとんと階��を降りていく、志希の顔は暗い。
東口を出ると、美嘉は「ちょっと、とりあえず作戦立てよ、作戦」と言った。
「ファミレスはそこにあるけど、えーと……」と、スマートフォンを取り出して操作していると、志希は「美嘉ちゃん」と遮った。
「文香ちゃんの家って、あっちのほうだったりする?」
「ん、んー? 多分そうだと思うけど……」
志希が指さした方で、空や建物が恐ろしげに赤く照らされているのが美嘉にもわかった。遠く、何台もの緊急車両のサイレンが聞こえた。「行こう」と、微かに不安の滲む声で、美嘉が言って走り出したとき、志希はその場で過去の体験がぐわあっと自分を追い越していくのを感じた。あの燃え盛るりんごの木々、てんてんとボウルに血液が落ちる音、本に生えたかびの臭い、錆びた鉄の味、床に捨てられたママの美しかった瞳が、恐怖に歪んであたしを見ていて、彼女はその口を開き「いい子」と――。
「志希!」と激しい声で呼ばれて、はっと顔を上げた。「くっ」と声を漏らすと志希は美嘉を追って走り始めた。
やがて、二人はその家にたどり着く。
「嘘でしょ……」と美嘉は最後の角を曲がると呟き、志希は「ああ」とその激しさに絶望して、声を上げた。
分厚い人垣の向こうで、鷺沢古書店は燃えていた。屋根は柱を何本か残して既に落ち、二階にあったはずの文香の居室は跡形も無くなっていた。一階の店舗部分からは今もめらめらと恐ろしい勢いで炎が吹き出し、庭木のいくつかはすべての葉を落としていた。太い電線がまさしくちょうど焼け切れて、ばぢん、という何かを切り落としたような音が辺りを裂いていった。何もかもが燃え尽きていく凄まじい臭気が空間を満たしていた。
美嘉がだっと駆け出して人混みをかき分け、そこに近付こうとすると、すぐに警察の張った黄色い規制線に遮られた。開けた周囲をぐるりと見渡し、救急車、消防車、警察車両がすでに到着して、必死の消火活動が行われていることが分かった。
「すみません!」
美嘉はテープを広げようと忙しく働く警察官に声をかけた。「危険だから、少し下がって!」と強く言われた。
「友達が、住んでた家なんです! けが人とか……どうなったのか教えてください!」
「なんだって……近所の人には、持ち主が帰ってこない空き店舗だと聞いたけど」
その警察官が無線でどこかへ連絡し始めたとき、美嘉はぎゅうっと両手を胸の前で組んだ。文香がまだ見つかっていないということがはっきりと分かったからだった。
「お願い……」
美嘉の開ききった目は燃え盛る火宅をじっと見つめ、震える喉からは悲しい祈りが漏れ出た。そうやってぼうぼうと踊り狂う炎が何もかもを奪っていくのを、力無く見守っていた。祈ることしか、彼女にはできなかった。
志希は、そうではなかった。
志希は美嘉が背中を丸めて、全霊で何かに祈っているのを見つめていた。やがて、ふ、と踵を返すと、元来た道を走って戻った。冷たい空気が肺で暖められて、彼女の周りに形無くたなびいていた。いくつもの街灯が、規則的に彼女の冷静な顔を明滅させていた。角へと立つたびに、彼女は、すん、と鼻をうごめかした。
四つの角を曲がり終わると、彼女は人通りの少ない道へと出た。誰も目にすることのない狭いビルとビルの間で、やがて志希は目的のひとを見つけた。
かちゃ、と、ノブが回される音が鳴った。
乱れた呼吸を、ふ、ふ、と戻すように努力して、志希はその奥を見つめながら、ふ、と自嘲気味に笑った。
通る者のいない路地を囲む植木鉢と、枯れた植物の奥、トマソンと化したドアの奥、ブゥーンと低い音で鳴る室外機、ゆっくりと回るガスメーター、なにかよくわからない液体の汚らしい流れと、何年もの間繰り返し捨てられて拾うもののいない缶や瓶のごみのさらに奥に、まさにそこに、文香はいた。
焼け焦げて濡れたストールに身を包んで、服も炭で汚れていた。背を壁にぴたりとつけ、地面に座り込み、小さな空間で彼女は一心不乱に広げた本を読んでいた。角が焼けてしまったその青い表紙のソフトカバーを、文香はまるで数日ぶりの食事をしているかのように、大事そうに一行一行をなぞっていた。志希が目の前に現れたことにも気づかない様子で、時折その文を小さく声に出して読み上げていた。
そして、今や彼女がふつうの人間ではないことは明らかだった。その頭で、猫のような大きな耳が揺れていたからだ。
文香が感覚の一切を集中してその本に身を投じているのに、その耳だけが別個の意志を持っているかのようにく、く、と動いた。志希がちり、と音を鳴らして耳に下がっていたピアスを片方外すと、文香の右耳がこちらの方を向いて、あたかも獲物を凝視する一匹の肉食獣であるかのようにそのまま止まった。志希はピアスについていた小さなアンプル状の装飾をぱきっと砕いて開けながら「キミも、そうだったんだね」と文香に向かって言った。
瓶の中で、ぬらりとした液体が怪しげに揺れていた。
パトカーが一台サイレンを鳴らしながら現れて、志希の姿をばあっと照らした。その光を志希は一瞬眩しそうに見つめて、そのまま猛スピードで通り過ぎていくのを目で追った。
文香のいる谷間に一歩入りこんでから、志希は液体をこくりと飲み干した。志希の身体は、それで仄かな緑色に光り輝きはじめ、両側の壁面を美しく照らした。
ぴちゃ、ぴちゃ、とローファーで汚水を踏みしめて、志希はその隙間のもっとも奥へとたどり着くと、文香の頭をやさしく撫でた。彼女の頭で、ぴ、ぴ、と大きく動いていた耳は、志希が両手でそれをそっと包んで、何事かを唱えながらゆっくりと触っていると、やがて透明になっていき、消えた。
「あたしたちみたいなのが、アイドルだなんて、笑えるよ」と言って、志希はほんとうに笑った。
文香は志希のやわらかな光にようやく気づいたのか、顔を上げると「志希さん」と言った。
猛烈なスピードで近づく電車の前にみずから佇む人は、頭の中が後悔でいっぱいになり、自分がなぜそこにいるのかついには理解できなくなる。それと同じように、文香は何もわからないようすで志希の表情を反射するかのように笑みを浮かべた。口元は笑っているのに、すだれのようにすべてを覆い隠す前髪の奥で、ロシアンブルーのそれのような瞳が彼女の魂を映しているかのように悲しげに瞬いていた。
1 note
·
View note
Text
焼きそばハロウィンはいかにして無敵のアイドルになったのか(1)
糸のように少しだけ開いたカーテンの隙間から朝陽が差していた。三角形に切り取られたやわらかな光の中を、田園を飛ぶ数匹の蛍のようにきれぎれの曲線を描いて埃が舞っていた。深い紫陽花色をしたチェック柄のミニスカートが、まっすぐにアイロンを当てられたシャツ、左右が完全に揃えられた赤いリボンとともに壁にかけられていて、部屋の主である女子高校生の内面を強いメッセージが込められた絵画のように表していた。
最も速い蒸気機関車が、そのペースをまったく乱されることなく東海道を走り続けていたように、その子どもがアスファルトを踏みしめるスニーカーのちいさな足音は正確に一分間当たり百六十回をキープしていた。それは彼女が小さなころから訓練に訓練を重ねてきた人間であることを示していた。太陽が地面に落とす影はすでに硬くなり、朝に鳴く鳥の歓びがその住宅地の道路には満ちていた。はっはっ、という歯切れ良い呼気が少女の胸から二酸化炭素と暖かさを奪っていった。
白いジャージに包まれたしなやかな身体は、湖面の近くを水平に飛ぶ巨大な鳥のそれに似ていた。ベースボールキャップからちらちらと見え隠れする桃色の髪がたった今自由になれば、相当に人目を引くほど美しくたなびいただろう。
ちら、とベビージーを見た視線が「ヤバイ」と言う言葉を引き出して、BPMが百七十に上がった。冷えた秋の空気が肺胞をちくちくと刺すようになったにもかかわらず、彼女の足取りは軽やかなままだった。そのままペースを落とさずに簡素な作りの階段をタンタンタンとリズム良く駆け上がりながら、背負っていた黄色のリュックサックからきらびやかなキーチェーンに取り付けられた部屋の鍵を取り出した。
かちゃり、と軽い音でドアが開いた。
「ヤバイってえ……」
靴が脱ぎ捨てられ、廊下を兼ねたキッチンの冷蔵庫が開かれると同時に、がっちゃんと重々しくドアは閉まった。その家の冷蔵庫は独身者向けの小さなサイズのそれで、天板に溜まった微かな埃が家主の忙しさを示していた。リュックから取り出された小さなタッパーを二つ、彼女は大事そうに冷蔵庫の中段に入れた。若干乱暴にそれが閉められた後、その場には一息に服が下着ごと脱ぎ捨てられた。浴室に荒々しく躍り込むと、曇りガラスの裏側でごろ、と音が響いて、洗い場の椅子が乱雑に蹴り退けられたようだった。
水が身体に跳ね返って飛び散り続ける音は短かった。男子高校生並のスピードでシャワーを終えて素早く黄色のトレーニングウェアに着替えると、彼女は強力なドライヤーで頭を乾かしながら鏡を睨みつけた。凄まじい早さで顔を直し、部屋の隅に立てかけてあったドラムバッグを一度だけひょいっと跳んで深くかけ直すと、小上がりに鎮座していたゴミ袋を掴んで「いってきます!」と誰もいない部屋に叫んだ。
キャップから出された、揺れるポニーテール。土曜日の早朝を走り抜けてゆく足音をゴミ収集車のビープ音だけが追っていた。
少女の部屋には静けさが戻る。
地下鉄の駅を出ると、人混みをすいすいとくぐってきつい坂を下っていった。途中にある寺の横を小さく一礼して通り過ぎ、降りきった先の人通りの少ない路地を抜けていくと、やがてダンススタジオのちいさな立て看板が見えた。軽い足取りで一番下までたどり着き、ふう、と軽く息を吐く。耳から完全ワイヤレスのイヤホンを引き抜いてポケットに突っ込み、「ごめん!」と、笑顔を浮かべたまま身体全体で重い扉を勢いよく開いた。
小さな子どもたちが彼女の頭上を通り過ぎる笑い声と一緒に、白い光が斜めに入り込んで、暗い床を小さく照らしていた。彼女の瞳は、誰の姿も捉えない。
「……あれ?」
「あれ、じゃない」
ばこん、と、現れた女性に横からファイルで強く頭を叩かれ、彼女は悶絶して頭を抱え座り込んだ。
「城ヶ崎……集合時間は何時だ?」
く〜、と唸り声を上げた美嘉は、しばらくしてから「九時」と涙声で言った。
「今は何時?」
「八時五十八分、に、なったところです」
「正解だ。じゃあな、私はデートに行ってくる」
「ちょ、っと。トレーナー!」
美嘉はトレーナーの服を掴んで、「え」と言ったあと「……冗談、ですよね」と半笑いの顔を作って聞いた。上から下までトレーナーの服装を見て、それがいつもの緑色のウェアとは似ても似つかぬ、落ち着いた色合いの秋物であることに気づく。
「失礼だな、私にも急なデートの相手ぐらいいるよ。年収五百五十万、二十九歳、私にはよくわからないのだがシステム系の会社でマネージャーをしている――」
美嘉はうんざりとした顔を浮かべて、
「相手の年収なんて聞いてませんよ。ていうかそうじゃなくて、私たちのレッスンはどうなっちゃうんです?」
「まず第一に、私はいつも五分前行動を君たちに要請している」
「……それは、すみません。朝、用事で家を出るのが遅れてしまって」
「第二に、彼は笑うとえくぼがとてもかわいいんだ。好きな力士は豪栄道」
「彼氏情報はもういいですから……」
豪栄道とトレーナーの共通点を美嘉がまじまじと探していると、「第三に」と言って、トレーナーは指を振った。
「次は三人揃わないとレッスンはしないと、前回宣言したはずだ。案の定だったな」
美嘉は、うわっ、と呻いて「志希のやつ……」とつぶやきながらスマホを取り出して乱暴に操作した。
「先に鷺沢に連絡しろー」と、ヒールを履いたトレーナーは外に出ながら言った。
「あいつ、いつも三十分前に来て長々ストレッチしてるんだ。本番前最後の確認でいきなり無断欠席となると、少し心配したほうがいいかもしれないぞ」
ドアの隙間から微笑んで、「じゃあな」と、一言言うとトレーナーは去った。ぽかんと美嘉は小窓から彼女を見送る。かつ、かつという高い音は、軽やかに去っていった。
おかけになった電話番号は、電源が入っていないか――。
美嘉は携帯から小さく流れる音声を一回りそのままにしてから消し、スタジオの照明をつけないまま日の当たるところへと歩いていった。『い』から『さ』へ大きくスクロールして、窓際であぐらをかく。『鷺沢文香』を押し、耳に当てる。短いスパンで赤いボタンを押す。『鷺沢』赤ボタン。『鷺沢』赤ボタン。『た』にスクロール。
『高垣楓個人事務所』
耳元の小さな呼び出し音を聴きながら「なんで……」と美嘉は呟いた。短いやり取りで、事務員に文香への連絡を頼んだ。
「プロデューサーにも連絡お願いします……いえ、アタシは……はい、残って自主練やります。」
電話を切った後、ふうう、と美嘉は長いため息をついた。一息に立ち上がり、バッグから底の摩耗したダンスシューズを取り出して履くと、イヤホンを耳に押し込んで入念なストレッチを行った。同い年くらいの少女たちが数人、スタジオの横を笑い声を立てながら通り過ぎ、その影が床をすうっと舐めていったが、彼女はそれに目もくれなかった。
床に丁字に貼られたガムテープの、一番左の印に立った。トリオで踊るときのセンターとライト、残りふたつのポジションに一瞬の視線が走り、美嘉は目尻に浮かんだ悔し涙を一瞬親指の背で拭った。
「くそ」
いきなり殴りつけられた人がそうするように、美嘉はしばらく下を向いていた。闘争心を激しく煽る力強いギャングスタ・ラップが彼女の耳の中で終わりを告げ、長い無音のあと、簡素な、少し間抜けと言ってもいい打楽器が正確なリズムで四回音を立てた瞬間、美嘉は満面の笑みを浮かべてさっと顔を上げ、ミラーに映った自分を見つめながら大きく踏み出した。だんっ、と力強くフローリングを踏みしめた一歩の響きは、長い間その部屋に残っていた。
「おはようございます……」と挨拶をしながら、美嘉がその部屋に入っていくと、「あら、めずらしい」とパイプ椅子に座っていた和装の麗人が彼女を見て笑った。その人が白い煙草を咥えているのを見て、美嘉は「火、つけます」と近寄りながら言った。
「プロデューサー、煙草吸うんですね」
「いやですねえ、二人きりのときは楓と呼んでくださいと、このあいだ申し上げたじゃないですか」
「……楓さん、ライター貸してください。アタシ流石に持ってないんで……」
こりこりこり。
煙草が軽い音を立てながら楓の口の中に吸い込まれると、こてん、と緑のボブカットが揺れ、「はい?」と返事が返った。���草と思っていたそれが菓子だったことが分かって、美嘉はがくりと頭を垂れた。
「ええと、ライターですか……あったかしら……」
「……からかってるんですか?」
「まさかまさか」
楓がココアシガレットの箱を差し出すと、美嘉は「いらないですって……」と顔をしかめて言った。
「今日は、打ち合わせ?」
「はい、次のクールで始まる教育バラエティの……楓さん、ちひろさんから連絡行きましたか」
「はいはい、来ましたよ。文香ちゃん、大丈夫かしら」
「……軽いですね」
「軽くなんか無いですよ」
ついつい、と手の中のスマホが操作され、「私の初プロデュース、かわいい後輩ユニットなんですから、応援ゴーゴー。各所からアイドルを引き抜きまくって、非難ゴーゴー!」と、画面を見せた。『高垣楓プロデュースユニット第一弾! コンビニコラボでデビューミニライブ』と大きく書かれたニュースサイトの画面には、『メンバーは一ノ瀬志希、城ヶ崎美嘉、鷺沢文香』と小見出しがついていた。びきっ、と美嘉の額に音を立てて青筋が現れ、「だったら」と美嘉は言った。
「ほんっと、真面目に仕事してくださいよ! なんなの、『焼きそばハロウィン』っていうユニット名!」
「ええ〜かわいくないですか、焼きハロ」
「ユニット名は頭に残ったら成功なの! ニュース見たら一発で分かるでしょ、記者さんも訳わかんなくなっちゃって、タイトルにも小見出しにも使われてないじゃん! ていうか百歩譲ってハロウィンは分かるとして、焼きそばってどっからきたの!!」
「以前、焼きそばが好きだっておっしゃっていたから……」
「え、そんなこと言ってましたっけ」
「沖縄の撮影に三人で行ったとき、一緒に食べておいしかったーって」
「……あれ、たしかに……はっ、いやいやいや、丸め込まれるところだった。好物をユニット名にしてどうすんの」
「美嘉ちゃんには対案があるんですか?」
「た、対案?」
いきなりプロデューサー業を完全に放棄して頬杖をしながらがさがさとお菓子かごを漁る楓に、美嘉は「対案……」と呟いて顎を触った。は、と思いついて「たとえば、志希がセンターだから、匂いをモチーフに『パフュー(ピー)』とか、あと……秋葉原でイベントやるし、そうだ、三人の年齢とかを合わせちゃって『エーケービー(ピイィー!)』とか、あーもうさっきからピィピィうるさい! なんなんですかそれ!」
「フエラムネですよ。あっ、今の若い子はご存じないですか」
「アッタッシッがっ、しゃべってるときにはちゃんと聞いてよ、アンタが考えろって言ったんでしょ! ていうか文香さんのこと、早く何とかしなさいよ!」
「ははあ」
ごり、と、ラムネを噛み砕くにしては大きい音が楓の口内から立てられた。美嘉は激昂から一瞬で冷めて、口元に小さな怯えを浮かばせた。月と太陽とを両眼に持ったひとはそれらをわずかに細め、もう一つラムネを口の中に放り込んだ。
「焼きハロ、私はリーダーを誰かに頼みましたよね。誰でしたっけ」
「……アタシ、です」
ごり。
「トレーナーさんからも話を聴きましたよ。なんでも志希ちゃんは、初回以来一度もレッスンに現れていないとか」
「あれは! ��の……志希は、前の事務所のときからずっとそうで……」
ごり。
「ふうん、美嘉ちゃんはそれでいいと思ってるんですね」
楓がゆらりと立ち上がり、美嘉に近寄った。彼女が反射的に一歩大きく下がると、壁が背後に現れて逃げ場が無くなった。フエラムネをひとつ掴み、楓は美嘉の少し薄い唇にそれを触れさせた。真っ赤に染まった耳元にほとんど触れるような位置から、楓の華やかな口元が「開けて」と動いて、美嘉がわずかに開けたそこにはラムネがおしこめられた。ひゅ、と一瞬鳴ったそれに、楓は満足そうに微笑むとテーブルに寄りかかった。「口に含んでもいいですよ」と楓が言った。美嘉は少し涙の浮かんだ目で楓を睨むと、指を使ってそれを口に入れた。
「私は高垣楓ですから」
テーブルを掴んでいる指で、楓はとんとんと天板を裏側から叩いていた。「傷つかないんですよね、残念なことに。何が起きても」とほんとうに少し残念そうに言った。
「だから、あなた方が失敗しても、私は特に何も思わない。たとえばコンビニのコラボレーションが潰れても、私は特に怖くない。少しだけ偉い人に、少しだけ頭を下げて、ああ、だめだったのかあ、と少しだけ感慨に浸るんです。でもあなた方はきっと、違いますよね」
美嘉の口の中で、こり、と音が鳴って、
「……何が言いたいんですか?」
「自信がないの? 美嘉ちゃん」
質問に質問を返されて、しかし美嘉はもうたじろがなかった。「最高のユニットにしてやる」と自分に言い聞かせるように呟くと、「なんです?」と楓は聞き返した。
「何も、問題は、ない。って言ったんですよ」
パン、と楓は手を叩いて、「ああ、よかったあ」と、言った。
「今日はもうてっぺん超えるまでぎっちり収録ですし、困ったなあ、と思ってたんですよね。明日の店頭イベント、よろしくお願いします」と、微塵も困っていない顔で言った。
「文香さんち、いってきます」と宣言し、美嘉はトートを抱え直した。行きかけた彼女は楓に呼び止められて、投げつけられたココアシガレットの箱を片手で受け取った。
「さっきはちょっといじめちゃいましたけれど……」と楓が言葉を区切ると、美嘉は心底嫌そうな顔をして「はあ」と言った。
「ほんとうにどうしようもなくなったら、もうアイドルを続けていられないかもしれないと思ったら、そのときはちゃんと私に声をかけてくださいね。す〜ぱ〜シンデレラぱわ〜でなんとかして差し上げます」
「もう行っていいですか。時間無いので」
恒星のように微笑んで、楓は「どうぞ」と言った。美嘉がドアを開けて出ていくと。入れ替わりにスタッフがやってきて「高垣さん、出番です」と声をかけた。
立ち上がりながら、ふふ、と笑うと、「楽しみだなあ、焼きハロ♫」と楓は呟いた。
だん、だん、と荒々しいワークブーツの足音が廊下に響いていた。「いらないっつってるのに……ていうか、一本しか残ってないじゃん。アタシはゴミ箱かっつうの」と独り言を言いながら、美嘉は箱から煙草を抜いて口に咥えた。空き箱はクシャリと潰されて、バッグへと押し込められた。
「あーっ、くそ!」
叫んで、ココアシガレットを一息に口の中へと含む。ばり、ばり、ばり、という甲高い音を立て、ひどく顔をしかめた美嘉の口の中で、それは粉々に砕けていった。
「すみませーん」
美嘉は三度目の声をかけ、ドアベルをもう一度押した。鷺沢古書店の裏庭にある勝手口は苔むした石畳の先にあり、彼女はそこに至るまでに二度ほど転びかけていた。右手に持っていたドラッグストアの袋を揺らしながら側頭部をぽりぽりとかいて「……やっぱり寝込んでるのかなー」と心配そうに小さな声で呟いたとき、奥から人の気配がして、美嘉の顔はぱっと輝いた。
簡素な鍵を開けたあと、老いた猫が弱々しく鳴くときのような蝶番の音を響かせて、顔をあらわしたのは果たして鷺沢文香だった。「文香さん」と美嘉は喜びを露わにして言った。
「無事でよかったー! なんだ、元気そうじゃん」
美嘉は鷺沢のようすを上から下まで確かめた。ふわりとしたロングスカートに、肌を見せない濃紺のトップス。事務所でも何度か見たことのあるチェックのストールは、青い石のあしらわれた銀色のピンで留められていた。普段と変わらぬ格好とは裏腹に、前髪の奥の表情がいつになく固い事に気づいて、美嘉は「……文香さん?」と聞いた。
「ご迷惑をおかけして、申し訳ありません」と、文香は頭を深々と下げた。
どこか寒々しい予感に襲われ、美嘉は「あ……」と、不安の滲む声を漏らした。はっとすべてを消し去り、いつもの調子に戻して、
「今日のレッスン? もういいっていいって。連絡が無かったのはだーいぶあれだったけど、ま、志希のせいで無断欠席には慣れちゃったっていうか、慣れさせられたっていうか――」
「そうでは、なくて……」
文香は言葉に詰まった。合わない視線はゆらりと揺れて、隣家で咲き誇るケイトウの花を差していた。燃え盛る炎のように艶やかなそれを見ながら「アイドルを、やめようと思います」と彼女はゆっくりと言った。がっと両腕を掴まれて、文香は目の前で自らの内側を激しく覗き込もうとする黄金の瞳に眼差しを向けた。
「なんで!!」
美嘉が叫ぶと、文香はふら、と揺れた。陽が陰り、そこからはあらゆる光が消えた。産まれた冷気を避けるかのように、ち、ち、と小鳥が悲鳴を上げながら庭から去っていった。
「向いて、いないと、思いました」と、苦しそうに彼女は言った。
「突然で、ほんとうに、申し訳ありません……楓さんには、後ほど、きちんとお詫びをしようと――」
「嘘」
「……嘘では、ありません。自分が、古めかしい本にでもしがみついているのがふさわしい、惨めな人間――けだもの、虫の一匹だと、あらためて思い知ったのです」
「何があったの、だって」
美嘉は文香から一歩離れると、心の底から悲しそうな表情を浮かべた。
「あんなに……嬉しい、嬉しいって、新しいことを発見したって、何度も何度も言ってたのに!」
「間違いでした」
「何があったんだってアタシは聞いてるの!」
「もともと何も無かったんです!」
文香がこれまで聞いたこともないような大声を出したので、美嘉は呆然と立ちすくんだ。「すべてがまぼろしだったのです! ステージの上の、押し寄せる波のように偉大なあの輝きも!」と文香は一息に言って、興奮を抑えるようにしばらく肩で息をしながら美嘉を見つめていた。やがて、「まぼろしだったのです、あの胸の、高鳴りも……」と、悄然として言った。
「……なぜ」と美嘉は言った。その反転がなぜ起きたのか理解できないようすで、美嘉はただ文香を睨みつけて質問を繰り返した。
長い沈黙のあとに、「家に、呼び戻されました」と文香は言った。美嘉は唖然として「どういうこと」と聞いた。
「親の同意がないままアイドルをやってたから、やめろって言われたって、そういうことなの?」
文香はうなずいた。
「未成年者は保護者の同意書提出があるはずじゃん」
「あれは、東京の叔父に書いてもらいました」
「……だって、大学だってあるし、文香さんトーダイでしょ。そういうの、全部捨てて、帰ってこいって言う……そういうことなの?」
「そうです」
「そんなの、家族じゃない」
美嘉が断固とした調子で言うと、文香は口を一文字に結んだ。そのようすを見ながら「家族じゃない、おかしいよ」と美嘉は言った。
「だって、アイドルも、学校も、全部夢じゃん。自分が将来こうなりたいっていうのを、文香さん自分の全部を賭けて頑張ってたじゃん。アタシずっと見てたよ。すごいな、ほんとうにすごいなって、思ってたよ。ねえ」
文香の瞳をまっすぐに見つめて、美嘉は手を差し伸べた。
「全部捨てる必要なんてない、大丈夫だから」
青い海のようなそれに吸い込まれそうになりながら、美嘉は一瞬の煌めきをそこに見つけて、笑いかけた。文香が恐る恐るといった様子で、ゆっくりとその手を取ったとき、微笑みを浮かべた彼女の口元は「そう……分からず屋の家族なんて、捨ててしまえば――」と囁いた。「う」と小さな悲鳴を上げて、文香は手を振りほどくと、どん、と彼女の肩を両手で押し、庭土へと倒した。あっ、と倒れ込んだ美嘉は、文香を見上げ、「美嘉さんは、鷺沢の家を知らないんです!」と、文香が絶叫するのを聞いた。美嘉の眉はみるみるうちにへの字に曲がって、
「知らないよそんなの! アタシに分かるわけないじゃん!!」
ぐ、と文香の喉は、嗚咽するような音を立てて、やがて、ふううと長い息が吐かれた。
「……さようなら」と、短い別れの言葉で、ドアは閉められようとした。「待って!」と美嘉が呼びかけたときにその隙間から見えた、雨をたたえた空のようにまっしろな文香の顔色が、美嘉の目には消えゆく寸前のろうそくのようにしばらく残っていた。
どさ、と重い音を立てて、その白い袋は金網で作られたゴミ箱へと捨てられた。美嘉はよろめく足取りですぐ横のベンチに向い、腰を下ろした。眼の前には公園に併設された区営のテニスコートがあり、中年の男女が笑いあいながら黄緑色のボールを叩いていた。
美嘉はイヤホンを耳に押し込むと、ボールの動きを目で追うのをやめてうつむいた。両手を祈りの形に組み、親指のつけ根を皺の寄った眉間に押し当てた。受難曲の調べが柔らかく彼女の鼓膜を触り終わったあと、シャッフルされた再生が奇跡のようにあの四回の簡素なリズムを呼び出して、今朝何度もひとりで練習したあの曲が鳴り始めた。美嘉は口をとがらせ、ふ、と微かに息を吐きながら顔を上げた。そしてテニスコートの男女が消え、自分の周りにひとりも人がいなくなったことを見つけた。
空はまっ青に晴れ、柔らかな光が木々の間から美嘉に差していた。そのやさしさをぼうっと受け止めながら、美嘉は立ち上がってゴミ箱から先ほど投げ捨てた袋を拾った。冷えピタやいくつかの薬、体温計を自分のバッグに移し、二つのフルーツゼリーをこと、こと、と静かにベンチの横に置いた。
曲はサビに差し掛かり、いつの間にか美嘉は鼻歌でそれを小さく歌っていた。てんてんと指で指してみかんとぶどうからぶどうを選びとると、蓋を開けてプラスチックのスプーンを突き立てた。
口に入るかどうかわからないくらいの大きさでそれをすくい上げて、飢えた肉食動物のような激しさでがぶりと食いついた。
歌い始めたときにはもうこぼれていた大粒の涙が、収め切れなかったゼリーの汁と一緒におとがいへと伝って、ぽとぽとと太ももに落ちた。
泣くときに必ず漏れるはずの音を、美嘉は少しも立てなかった。涙を拭いすらしなかった。たまに「あぐ」という、ゼリーを口に入れるときに限界まで開いた顎の出す音だけが、緑の葉が擦れるそれと共にそっとあたりに響いていた。食べ終わると同時に曲が終わり、美嘉はイヤホンを引き抜いた。ほうっと息を吐いて、ぐすっと鼻を啜った。涙のあとが消えるまで頬のあたりをハンカチでごしごし擦り、そのまま太ももを拭くと、鏡を出して顔を軽く確認した。
そして、は、と後ろを向く。
ベンチの背越しに伸ばされた腕がゼリーを取って、「これ食べていいやつー?」と聞きながら蓋を開け、返事を待たずにスプーンですくい取った。
「志希」と、呆然と美嘉は言った。
「ん?」と、ゼリーを口いっぱいに頬張りながら志希は言った。
4 notes
·
View notes
Text
ミステリアスアイズ
一事が万事、という言葉を最初に耳にしたのは、たしかダンスレッスンのあとだった。燃え上がるような太陽を見つめながら渋谷の交差点に立っていたとき、「奏さんと一緒に過ごしていると」と、文香は往来に消え入りそうな声で言った。
「あなたのすべてが、私の身体に染み込んでゆき……糧となるような心地がします」
私は文香の方へと振り返った。彼女の語る言葉を聴き漏らさぬように集中していたから、何も言えなかったのだと思う。「一事が万事、私を成長させるのです」と言って文香が夕陽に溶けるように笑ったので、私は火照る顔の赤さがごまかしきれていればいいなと感じて、小さく微笑んだ。
次にその言葉を聞いたのは、電話に出たプロデューサーがこれまでに見たこともないような厳しい顔をしたあと、窓の外に目をやりながら二言三言その相手と話して電話を切ったあとだった。私は彼につられまっすぐに並ぶ飛行機へと目をやり、ふうー、と長々つかれた彼のため息を聞きながら「どうか、した?」と聞いた。
「二十秒ほどくれ、奏。考えをまとめる」と彼は言った。空港に響くいくつかのアナウンスが私たちの間を流れゆき、私はコツ、コツと音を立てて二歩ほど彼に近寄った。トラブルの香りに、さきほどまでの高揚した気分が、消え去るようだった。初めての海外、映画の準備期間、トップスターとの共演――。
「高垣さんに何かあったの」
「……そうだ……」
私は軽くパニックになる。理性が働いて、気持ちを落ち着かせるために深呼吸をした。
「遅刻、しているのは……事故、とか?」
「事故と言えば事故だ」
彼は先程よりも長いため息をついたあと「パスポートを失くしたそうだ」と言った。
私ははんぶんほど笑って、「は?」と彼に答えた。「え」と言ったあと、
「でもなぜ、それを、飛行機が出る二時間前に、電話で?」と、なにもかもがどうしようもないと分かりながら言った。
「海外ロケはさすがに動かせないが、そっちは二週間後だから再発行が間に合う。だが悪いな、マリブは無しだ。伊豆あたりに変更することにするよ」
プロデューサーは手の中のスマートフォンのロックを外して、どこかに電話をかけ始めた。私は数歩後ずさって、そこにあった座席にどさりと座った。
「しんじられない」と、口をついて言葉が出た。
「奏」とプロデューサーが通話口を抑えて私を呼んだ。顔を上げると、プロデューサーは微かに笑って「おぼえておくといい」と言った。
「高垣楓と過ごしていると、一事が万事、この調子だ」
朝陽の中で私に笑いかける彼に目を向けながら、私は「はは」とつられて笑った。
2 notes
·
View notes