Text
嘘つきのナイチンゲール
嘘世界ノースディンのおはなし。嘘予告の情報だけで書いたので、ちょっぴりノスクラっぽいかもしれない。 かなり幅広く捏造しています。最初から最後までALL捏造。何でも許せる方向け。 ただひたすらに暗いです。
※死を匂わせる描写あり
***
「嘘つきのナイチンゲール」
その日のことは、いまでもよく思い出せる。
あの祝福された夜のことを。
わたしの指を握るちいさな手は、どこまでも無垢で純粋で。わたしはおまえが──どうか冬の寒さに、空虚な氷に囚われることなく生きてほしいと、そう願った。
その手が、愛らしいその手が凍えてしまわないように。そう在ろうと誓った。
***
吐く息が白い。トランシルヴァニアでもあるまいに、ひどく寒い。
──吹雪の悪魔が?
笑わせる。そう鼻を鳴らし、立ち上がろうとして……ノースディンはその力も残されていないことを、頭の隅で認識した。血の通う感覚がすでに、ない。
手ひどくやられてしまったようだ。
胸を衝く弾丸はかろうじて氷で縫い留めてはいるが、もはや薄氷のようなノースディンの身体は、少し力を入れれば容易く壊れてしまいそうな状態だった。自分の心臓がひび割れていくかのような感覚に、ノースディンは思わずうめく。それがまだ脈打っているかどうかすら、いまではもう怪しかった。
──愚かな。
投げだされたままの身体を雪に沈め、浅く息を吐く。ありったけの能力を駆使して応じたため、木々は重みを持って撓垂れ、あたりは一面の銀世界へと変貌を遂げていた。何もない。まるで冬を切り取ったような世界の中で、ノースディンはひとり思い出す。腹が立つほど澄んだ海をたたえた蒼の瞳と、嘲笑うように高鳴ってみせたあの心臓を。己をなげうってまで、あの人間を生かした愛弟子を。わたしに報復するために?
自分はいま、嘲るような笑みを浮かべられていると、ノースディンは思ったに違いない。
なんて愚かな。人間に肩入れするなんて。ノースディンは内心で吐き捨てた。脆弱で、潰しても潰しても現れる虫のような、どうしようもなくみじめな存在だとお前はあの方の近くでよく見ていたはずだろうに。か弱くて、儚くて、すぐに死んでしまう。どのみち我々を置いてゆく生き物だということを、お前は知っていたはずだろうに。
我々は止まらない。止められない。昼の末裔は、悉く滅ぼすしかないと、お前の祖父も、父も――。
人間と馴れ合うなど、あまつさえ退治人などと! お前はあの方の嫡孫。白銀の狼の嫡男。奴らは我らの悲願を阻むものどもだというのに。
こんなことになるとは思っていなかった。警告したつもりだったが。
喉がひゅっと締まり、ノースディンは咳き込んだ。
わたしみたいになるな、と。
……そうとも。
かつてただ一度、愚かにもわたしはお前と同じことを願った。そっと瞼を閉じて、ノースディンはその裏に黒衣の姿を浮かべる。あのころは、お前もまだ小さくて、いまよりもずっと泣き虫だった。人間に強い思い入れなどはなかったが、あの男がわたしを退治しにきてから──それも悪くはない、と考えていた。
そうだ。奇しくも、彼も退治人だった。
ノースディンの胸のあたりがキシっという音を立てた。
しかし、望んだ未来は来なかった。あの方は──。
すべての昼を赦さないとあの方が言うならば、ドラウスが肯定したならば、わたしもそうしよう。
遠くから見ていようと決めた城下の者たちを雪の下に埋めた。正体を知らずとも、わたしによくしてくれた者たちの子孫を、手にかけた。
それでいいのだと信じていた。信じたかっただけかもしれない。後にはもう引けなかった。人間との対立は深くなる一方だろう。我々が撒いた種だ。だからこそ、わたしはあの子を人間から遠ざけようとした。
なんてひどい師だろう。傷つけまいとそう誓ったのに、結果だけ見れば、わたしはあの子を殺したのだ。
努力はしたんだ、ドラウス。頑張ったんだ、わたしなりに。だが、わたしではあの子を連れ戻せなかった。
これはその代償だ。
ああ、なのに。なぜ、わたしの心はこんなにも穏やかなのだろう。
これで終わりなのだとわかっているのに、とても愉快な心地がする。呼吸もままならなくなった肺の音を鳴らしながら、ノースディンは虚空に向けて高らかに笑った。
こんなふうに笑ったのは何世紀ぶりだったか。
これでお前を傷つけることもない。もう、自分を殺し続けることもないのだ。そう思うと、暗くなりはじめた視界とは裏腹に、晴れやかな気分になった。
やれることはやったのだ、ノースディン。それでも変えられないというのなら──あの子はそうあるべきなのだろう。
もしかすると、どこかで喜んでいたのかもしれない。あの子が自身と同じような未来を望んでいることを。ノースディンは力なく笑った。
ドラルク。わたしの指を握った小さな手。お前の歩む道は、苦難で舗装されている。わたしにもこの先の未来がどうなるか、少しも検討がつかない。それでもどうか、と願わずにはいられない。
傍で見てやれないのが……残念だが。愚かな師匠から不出来な弟子へ、最後の課題を出そう。
その手でお前の大事なものを、守りなさい。
「……」
鼓動が遠い。
ピシ、ピシ、と亀裂の入るような音が、かすかに耳に届く。このまま雪に溶けるのだろう。それでいい――それでいいのだ。「吹雪の悪魔」には相応しい最期だ。もう、疲れた。
かつての願いは叶わない。あの子は行ってしまった。わたしはどこにも帰れない。自分を欺き、夢を捨てられずに一族を欺き……。許されるのは、永遠の白銀へ沈むこと。
嗚呼。もしも神がいるというのならば、どこにも行くことのできないわたしに、どうか裁きを。朽ちる前にただ一度でいい。
――クラージィ。
動かせない唇が音のない名前を紡ぐ。
わたしたちは、いったいどこで誤ってしまったのだろうな。
***
サクリサクリと、雪を踏む音がした。
音はどんどんとノースディンの方へと近づき、やがて止まる。
「あれ。そこにいるのはもしかして吹雪の野郎?」
遠くに聞こえたのは、ノースディンが望んでいた声ではなかった。
――そうだな。お前は、わたしの手の届かないところに行ってしまったのだから。
ハハッという笑い声をかすかに感じながら、あの子に読み聞かせた物語を思う。オスカーワイルドの小さな鳥。
わたしにお似合いの結末だと、ノースディンは微笑んだ。
0 notes
Text
アッサムに溺れる不凋花
13巻156死のあとくらいのノースディンのお話。クラノスなんだかノスクラなんだか……想像におまかせします。 ALL捏造。何でも許せる方向け。
***
「アッサムに溺れる不凋花」
我ながら、よくそんな言葉が出てきたなと思う。
ぎちぎちに締め上げられた、わけのわからないハイレグ衣装との格闘を終えてから数刻。椅子に沈み込みながら、ノースディンは淹れたばかりのアッサムにそっと口をつけた。
街に完全に溶け込み、あまつさえ腹を下しそうな格好をしてまで自分の魅了を跳ね返した弟子を思い出すと、思わず口がほころびそうになる。もっとも、催眠に耐性を付けたのはノースディン自身だったのだが、その成長にいままでの「がんばり」が少しだけ報われたと感じて、彼は満足な気持ちになろうとしていた。
しかしささやかな高揚感も、ドッと押し寄せてくる疲労すら跳ね返すように、彼の思考は恐ろしいほどに冴えていった。
香色の水面に、男の面影が映る。
白いものを髪に混じらせ、手にも目元にもしわを刻んだ男は言った。
「わたしはきっと、きみと同じところへ行くだろう、ノースディン」
こぼされた言葉が、変わらない響きでノースディンに語りかける。悪魔祓いだったはずの男は、こうしてたびたびわたしの屋敷に足を運んだ。
「飽きもせず、吹雪の悪魔がいれた茶を飲んでいるんだからな、当然だ」。自分とよく似た声がそんな風に茶化すと、ハハ、と朗らかな笑い声が耳の奥で響いた。
きみの屋敷を初めて訪れた日が懐かしい。まるで昨日のようだ、と男が笑う。その時から何年も、何年も、わたしはそのたびに彼を淹れたての茶で迎えてきた。目元に刻まれるしわは、出会うたびに増えていった。
「それならよければ会いに来てくれ。今度はわたしがきみをもてなそう。スコーンでもつくって」
茶化したのは本心ではなかった。
不意に向けられたその言葉に、ノースディンは向き合うことができていなかった。
ややあって答えたのは、「わたしは死なん」という、ほんの少し気分を害したように見せかけた自分の声だった。
そうだったな、と男は目を細めた。「きみにはきみの生き方がある。考えるだけおかしな話だ」
色褪せることのない声色の男が、水面越しにノースディンを見つめてほほ笑んだ。
そういえば、あの子は元気にしているか?
無邪気に問いかけられる質問。ゆらゆらとさざ波をたてはじめた香色の水面に、ひとつ、ふたつと波紋が広がった。
「ハハ、ははは!」
そう。まったくおかしな話をしたものだ!
われわれは死なないし、その話題はおよそ吸血鬼に相応しくない。それに、黒装束を脱いでなお弱いものを助けて回っていた彼が、我らと同じところへいけるわけがないのだ。われわれは決して天上の楽園などに足を踏み入れることはできない。たとえ、いつかもしわたしが本当に、生に飽くことがあったとしても─。
『われわれは天上の国からほど遠い存在だが』。
ノースディンはひとしきり声を上げて笑った。
やけくそ混じりのどこか悲鳴にも似た笑い声を聞く者はいない。
弟子の成長への喜びが、同時に胸をちりりと焼いていた。更に生意気に成長した、そしてすこぶる元気にしていると言いたいのに。
「お前はそこにいないだろう」
誰もいない静寂の中で、ノースディンは顔を覆った。
0 notes
Photo

***
王の館も英雄の住処も、分け隔てなく死は扉をたたく。
なんぴとたり��も逃れられぬ。
“ There is no escape “
0 notes
Text
響け届よ声の音
HADES二次。伝令の神サマとカロンさんの突貫やっつけ短い恋の話 何でも許せる人へ 。
***
「届け響けよ声の音」
豊穣の女神が永遠の冬で世界を閉ざしたり、容赦ない雷霆を落としたりしていたぼくたちが、人間を置いて──いや、人間がぼくたちの下から巣立って、ずいぶんと経つ。
雷を落としたとしても、人間たちはそれすら便利なものに変えてしまうから、いまや神々はすっかりお役御免。
太陽を運ぶヘリオスはまだ忙しなく毎日馬車を走らせてるけど、誰もそんなことは気にしない。二百年くらい前にはまだ似たようなものがあったような気もしたけど、いまはもっと速くておっかないものがひっきりなしに駆けていく。
まあ、ぼくの方が速いんだけど。プロメテウスなんかは手を叩いて喜んでいるかもね。そもそもの材料を与えたのは彼だから。
そのぼくはといえば──最近はちょっと仕事がなくなったって感じ。数百年まえくらいまではまあまあ働いたけどさあ。何千年も経って、人も変わった。時代はもう英雄を望まないし、英雄が現れることもない。必要ないんだ。つまり、ぼくもわざわざ冥界まで赴くこともないということ。ザグくんも念願叶えちゃったし、偽ってたぶん、あんまり危険なこともできないし。
のんびり隠居でもしようとおもってるんだよね──ディオニュソスのところのネクタルをたんまりちょろまかしてさ。だってぼく、そういうの得意だから。でも、ぼくは伝令役。それなりにやっぱりまだ働かされてるよ。人間たちがぼくたちを忘れたとしても、まだぼくたちはささやかに暮らしてるわけで、それならぼくもいったりきたりしなきゃいけない。なにせ相変わらずぼくたちは気まぐれだから。こんな杖まで持たされてるんだし……で、そのついでにちょっと人間の耳元で何かしら適当なことを囁くのが、最近のブーム。もちろんたいていの人間は聞こえないから、もしもぼくの愚痴がきこえたひとは幸運だよ──。
ひととおり走り回って、一息つくか(神様だけど)とおもった僕のカバンに見慣れない郵便物がいつの間にか入っている。もう羊皮紙とかパピルスとか、そういうのじゃないんだよね。ずいぶんと洒落た形の手紙は、ぼく以上に"こちら"と"あちら"を行ったり来たりしてる誰かさんじゃないと思いつかない。
まわりくどいな、普通に送ってきなよ。手に取ると、何もせずとも封がピット音を立てて切れる。なになに……「恋せぬことはつらいもの。恋するもまたつらいこと」。
なんだそれ!
やたら叙情的な文章が、当代ではきっと見ることもないできないぼくたちの字で書かれてる。いま、こんなの誰も書かないもんね。彼、ほとんど言葉らしい言葉を言ってくれることはないのに。だからなのかな、彼は冥府きっての詩人になれるだろう。内容は近況報告だけど、ときどき本心が静かに滲んでいた。
なんてことをしてても、思わず顔をほころばせていたぼくの耳にはどこかで金属の鳴る音がしっかりと聞こえてくる。あー、誰かぼくの不名誉な像に硬貨を投げたのか?
どうも、立派なものがついたぼくの像に硬貨を投げつけると、ぼくがお告げをくれるとかいう占いがあるみたいなんだけど、恥ずかしい過去を見せつけられてる感じでなんだかしょっぱい気分になっちゃうよ。まだぼくがヘマをやらかしちゃったときの像が残ってることにも驚くけど、まだそんなことをやろうとしている人間がいることには、やっぱり驚く。そういう人間たちのおかげで、ぼくたちまだやっていけてるといえば、それはそうなんだけども。
さて、いいことあったし、今日は真面目な事を言ってみるか。
そっと風にのせて短く言葉を紡ぐ。
「会いたいよ」
あの子、ずいぶんと期待してるみたいだけど、何を言うかはぼくの勝手。まあ、その様子じゃ聞こえてないよね。でも、確かに届いてるってぼくにはわかる。
ちなみに、お嬢さん。この硬貨は将来きみがステュクスの川をわたるときの"渡し賃"になります。
だからみんな、忘れちゃだめだよ。たとえ石や別の何かで舗装しても、その下には確かに底が続いているんだからね。
それは、このぼくが一番よく知ってるんだから。どの神様よりも、きっとね。
0 notes
Text
インヴェルノの星
ノスとウス準備号。 氷笑卿の過去170%捏造。書きたいところだけを書いたので、すぐ終わります。何でも許せる方向け。
***
「インヴェルノの星」
春。麗しく咲き誇る花の女神が、全ての命を芽吹かせる時。
美しい季節。花が咲き、小鳥が歌う。もう一度手を取り合うことができればと、幾度も夢に見たもの。
わたしがわたしであるかぎり、訪れない泡沫の夢。
お前が滅ぼしたのだ。この地を。我々を。
わたしを弾劾する声が、罵る声が、幾度となくわたしを刺す。つららのように鋭い刃は溶けることがない。
花が咲き、小鳥が歌う、美しい季節? そんなもの。そんなもの。そんなもの。
「忌むべき子」。「何故こんなことを」。「なんてひどい」。「どうして」。
──お前が殺したのだ、ノースディン。
どうして、母様。どうして、父様。あなたの希望になりたかっただけなのに。
「は、」
いくら叫んでも、どれだけ抗おうとも、この声はどこにも届かない。氷はただ、私の声を跳ね返すのみ。
わたしは冬だ。冬そのものだ。冷たい氷の季節。全ての命が眠り、雪の下に閉じ込められる。死神のように刈り取り、生まれる命が言祝がれることはない。わたしにできることは、ただ奪い続けるだけ。
ああ──願わくば、この呪われた身に、春など与えられませんよう。いずれわたしは、それすらも葬り去るだろう。その資格を、わたしはもう持ち合わせないのだから。
二度とこの地に花など咲くまい。
わたしはそういうものなのだ。そしてこれから先も──そうであらねばならない。
***
「『一夜にして氷に覆われた悲劇の街。樹氷の森!』。ここを観光地にでもするつもりなんでしょうか、彼らは」
トランシルヴァニアの北。かつて存在した……いまはどこまでも広がる冷たい大地に足を踏み入れ、ドラウスは道すがら聞いた人間の会話を、悪趣味だ、と吐き捨てた。
その隣を歩く彼の父親が、喜色を含んだ声で「見て。いっぱい雪合戦できそう」と答える。その表情は動かない。
「お父様。遊びにきたんじゃないんですよ」
嘘か真か冗談か。ほぼ9割の確率で本気で言っている父親を諫めて、ドラウスはため息をつく。目を離した隙に本当に雪像とかつくりそうなので、たまったものではない。このままでは一族全員で生き残りをかけた雪合戦など企画されかねないが、そもそもここまでやってきたのには、きちんとした理由があった。
「つい最近までここは」
すぐにその顔色が変わる。眼下に広がる、ガラスのような街を見てドラウスは声を失った。
そこでは水も、草木も、花も、そして──暖炉の炎さえも氷の下に縫い止められ、活動していたものすべてが時をなくしたまま、月明かりの下で冷たい光を放っていた。豊かな葉をつけ、実りの時期を待つ葡萄たちは、収穫されることなく覚めない眠りにつく。
つい最近まで、そこは美しい場所だった。小さくとも逞しく生きる、穏やかな地だった。
「見事だ」
そう言った竜の真祖が、変わらないその表情をほんの瞬きの間──曇らせたことに、ドラウスは気づかなかった。
***
ゾッとするような感覚が背筋を駆け抜ける。こんなものは経験したことがない。それは否応なくわかる、本物の畏怖。
誰かがやってきた。推測するまでもない。隣の若い男は誰だ?いや、そんなことはどうでもいい。
あれが、話に聞く竜の──。なぜ、こんなところまで。
「こわい」。少しでもそう思ってしまったことに気づいた時には、もう遅かった。恐怖が、瞬く間に空気を冷やしていく。
ああ、そんな。だめだ、だめだ。頼む。お願いだから!
わたしは駆け出した。あたりはみるみるうちに灰色に染まっていき、身を切り裂くような氷の風が唸りを上げ��めていた。見つかってしまう。うなだれた砂糖細工の森を走りながら、少しでも遠くへ、遠くへとわたしは必死だった。差し向けられた侮蔑の視線を、かけられた糾弾の言葉が浮かぶ。まただ。このままでは、また、わたしは。
──呪われたこの身が、いったいどこへ行けるというのだ? この世界にはわたしの居場所など、どこにもないというのに。
がむしゃらに走り、領地の端にある洞窟の奥へと駆け込んだ。膝をかかえ、落ち着けと何度も自分に言い聞かせながら、長く震えていたかと思う。相手はただの高等吸血鬼ではない。話に聞いたあの竜の真祖。わたしを探していることは確かだった。こんなところに隠れたところで、やりすごせるはずがない。見つかるのは時間の問題だっただろう。
激しさを増す風の中に聞こえてくる。雪を踏み、氷を割る音が、近づいてくる──わたしを殺しにきたのか。
死ねというのなら、犯した罪の重さに、わたしの命が見合うことを祈った。やはりわたしは生まれてくるべきではなかったのだと、そう突きつけてやるために。
やがて足音は止まり、最後に漆黒の大きな竜がこちらを見た。目が合う。だが喉をひゅっと鳴らしたわたしの耳に最初に聞こえたのは、別の声だった。
「お父様! 会話をしてください!」
そう言ったのは、あの若い男だった。男が喋ると、不思議と場の空気がやわらかくなった。2番目に聞いたのは竜の真祖の言葉だったが、これはカウントしないでおく。「めんご。緊張しちゃって」と彼は若い男に謝っていた。
そして結局、わたしに初めてかけられた言葉は侮蔑でもなく、糾弾でもなく──。
「ヘロー、少年。おヒマ?」
そんな、気の抜けた言葉だった。
0 notes
Text
宵闇のストレンジャー
書きたいところだけを書いたノスとウスの雰囲気だけのおはなし。
「夜のストレンジャー」の続きとして書いたもの。すぐに始まってすぐに終わります。
舞台はおなじく20sのアメリカ。御真祖さまに頼まれて別荘の内見に、はるばるルーマニアから出てきた白銀の狼と、その親友の話。
***
「宵闇のストレンジャー」
戦勝に沸き、華やかな夜が近づく摩天楼の国。
これだけの人がいる国では、狭い路地で人とすれ違うことなどあまりにも普遍的なことであり、誰もそれを疑うことなどしないだろう。ドン、とすれ違いにドラウスに誰かがぶつかったとしても、それは特段おかしいことなどではない。
しかし、「どこ見て歩いてるんだよ!」と吐き捨てられたノースディンの目の色が変わるのは、早かった。
「待ってくれ、ノース!」
すぐにドラウスの制止の声が飛んだが、ノースディンの耳には入らない。
「なんだ……?!」
走り去ろうとした相手が、突然動かなくなった自分の体に困惑した表情を見せた。
「礼儀を知らない愚か者が。腹の足しにもならん」
空気を震わすような声が路地に響く。
「盗ったものを出せ」
ノースディンは時代の潮流について、ドラウスよりも幾許か理解があった。彼にとって路地裏の闊歩は格好の標的になることであり、不自然すぎる衝突は”ちいさな犯罪”の常習だった。
「何も盗ってない!」
見かけにして10歳くらいの少年がガタガタと震え出したのは、決して恐怖だけが理由ではない。いまや路地裏の気温は、ロンドンの冬に近づくほど下がろうとしている。
「威勢のいい坊やだ」
嫌味をたっぷり含んだ言い方だった。外見上は人の形であっても、彼らは古の吸血鬼。この少年が対峙している存在は、まぎれもなく夜を統べるものだった。「われわれから物を盗むなど、ましてやあろうことか彼の懐から頂戴しようとするなど、愚かにも程がある」。ノースディンの声色は、いっそう冷たいものとなった。
「残念だが、夜はお前に味方はしない」
「ひッ」
「ノース!」
見かねてドラウスが声を上げ、太腿まで凍りついたところで、少年はようやく黒い財布を差し出してきた。上質な皮のそれは、まさしくドラウスの財布であった。
フンと鼻を鳴らし、少年から財布を奪うと、ノースディンはドラウスに財布を差し出す。
「用心しろ、まったく」
しかしドラウスは、このややお人好しの白銀の狼は、素直にその財布を受け取ることができなかった。
「これはわたしの財布じゃないよ、ノース」
ノースディンの顔に驚きの色が広がったのは当然のことだ。
「ドラウスおまえ、何を言って」
「だからノース、彼を離してやってくれ」
「ドラウス!」
財布は間違いなくドラウスのものだった。しかしドラウスは財布の受け取りを拒否し、あろうことか少年を庇おうとしている。語気をやや荒げてノースディンは親友を嗜めたが、ノースディンは彼の親友にめっぽう甘い。
「頼む。お願いだ」
寂しそうにドラウスが笑うのなら、溜飲を下げざるを得なかった。
ノースディンが眉間にしわを刻むと、少年の下半身を縫いとめていた氷は、パンっという音をたて、バラの花びらが落ちるようにほろほろと砕けていった。
「……」
「引き止めてすまなかった。わたしのじゃなかったようだから──これはきみに返そう」
まだ眉間に皺を寄せているノースディンの隣で、ドラウスはつとめて穏やかにそう言ったが、突然自分を襲った、人でない何かの強い力に恐怖した少年がようやく与えられた隙を逃すわけがない。
「あっ」
ドラウスが声をかける前に、少年はフラフラと立ち上がり、そのまま財布を受け取ることもなく走り去っていった。
「行ってしまった……」
行き場のなくした財布をしまいながら、ドラウスは走り去る少年を見送った。
当然、一息おいてノースディンのお説教が始まる。
「あほウス!なぜ逃した」
親友の厳しい声に、ドラウスはぴょんとはねた耳のような癖毛を、しおしおぺたり、と伏せた。
「わかっているよ、ノース」心なしか一本だけ飛び出したアホ毛もしなしなとしているように見えた。「けど、まだ子供なんだよ」
「貧相な子どもが一人、いったい何だというんだ?」
ノースディンはドラウスの言葉を一笑に付した。
「あんなのはスリの常習犯だ。いまさら哀れみを与えたところで、彼らにとって我々は所詮いいカモでしかない。こちらの好意など土足で踏みにじってくる」
「わかっているさ」
しょんぼりとしたまま、ドラウスがつぶやく。
ドラウスは財布を盗られたわけではなかった。それを知っていて、あえて財布を盗らせたのだ。
ドラウスとて世間知らずなわけではない。何百年も生きている分、前から歩いてきた少年の置かれている環境は、容易に想像できた。しかしそれが小さな罪だとしても、置かれた場所は、彼の罪ではない。ドラウスはそう思っていた。
少年のおびえた顔を見てドラウスの脳裏に浮かんだのは、彼のいくぶんか大きくなった息子の顔だった。
「ドラウス。わかっていないんだ、おまえは」
ノースディンは怒っているわけではなかった。ただ心配で仕方がない。
「あの子供ひとりを助けたところで、世界は簡単には変わらない。この先、あのような境遇の子供はどんどん増えていく。わかるか? 東の風はまだ吹いているんだ」
より人と関わることの多いノースディンは、人間の醜さをよく知っていた。だからこそ、ノースディンは人間の何がいったいどんな結果を引き起こすのか、その見当が付けられた。その醜さにドラウスが巻き込まれてしまうこと。それこそノースディンが最も許せないことであり、どんな手を使ってでも忌避すべきことだった。
「でもノース。だからって子供に手を差し伸べてはいけない理由はないんだろう?」
「わたしは、おまえのその優しさがお前自身を殺しやしないか不安なんだ。バカウス」
0 notes
Photo

『夜のストレンジャー』
20sのアメリカ。御真祖さまに頼まれて別荘の内見に、はるばるルーマニアから出てきた白銀の狼と、その親友の話。
***
「見てくれ、ノース!
弾んだ声がする。
「あれ息子のお土産にしていい?」
抗議の声は、そのすぐ隣から飛んできた。
「ダメだ。あとにしろ」
隣を歩くノースディンのその視線は、手元の紙に注がれている。
「我々の目的を忘れたわけではあるまい」
花が咲き、春をとどめたかのような市場を夜の紳士たちが歩く。
「ドラルク喜びそうなのになあ」
ドラウスが心持ちしょんもりしてみても、親友の表情はかわらない。
「ドラウス、さっきも言ったが今日は」
「"蒸気船ウィリー"を見に行くんだろ?」
ワクワクした表情でドラウスが答える。
「ドラウス!」
ノースディンが呆れたように一喝すると、「すまない……冗談だよ」とドラウスのぴょんと飛び出した前髪がしおしおとしなだれた。ノースディンはこれに弱かった。少しだけ絆されそうになるのである。
「ノースと出かけるの久しぶりだったから」
ウッと言葉につまりそうになるノースディン。そう困ったように笑われてしまうと、もう太刀打ちできない。天性の人たらし。その威力はノースディン自身がいちばんよく知っていることだ。
「御真祖様の別荘の内見。そうだろ」ドラウスがふうとため息をついた。
ノースディンとて鬼という訳ではない。ドラウスの好奇心を否定するつもりもない。しかしドラウスが彼の息子へのお土産を選ぶには、かなりの時間が必要になるという事実がある。(そしてノースディンには罪悪感がある。)
花の間を歩きながらドラウスがぼやく。
「なんでおれたちがジジイの代わりに行かなきゃいけないんだろう」
「あの方にも何か考えあってのことだろう」
それについては、ノースディンには少しだけ心当たりがあった。もしものことがあったら──情勢を省みるに、それは当たらずしも遠からずだろうと。かなりの年月を自分の父親に振り回されてきたドラウスは、ただの趣味だよ、と独り言ちる。
「なんて面倒なんだ、くそ」
「そうだ。だからこんな話はとっとと終わらせて、空いた時間をうんと楽しみに行こうと言っているんだ。そうだろ」
おなじくらい竜の真祖に振り回されてきたノースディンは知っている。面倒ごとはすぐに片付けるに限るのだ。ドラウスの顔はぱっと明るくなった。
「そうだな!」
戦勝に沸く今、華やかな夜はそこに近づいている。フォードが道の傍に止まれば、着飾った女性が下りてくる。燕の紳士たちはそれをエスコートして享楽の世界に繰り出していく。
さースディン!という親友の声を聞きながら、ノースディンは苦労人特有の、心配とやや安堵の混ざったため息をそっとつき、そして夜に生きる二人の紳士もまた、連れ添って200年前よりも明るくなった世界に飛び出して行くのだった。
1 note
·
View note
Photo

***
「おれには無理だよノース……できっこないよ」
舞踏会の当日。ピスピスと鼻を鳴らしながら、ドラウスはそんなことを言ってべそをかいた。
「顔見知り程度で、喋ったこともない令嬢と──踊れやしないさ!」
「それでもやるしかないんだ、ドラウス」彼の親友が勇気づけるように言う。
「招待客の顔ぶれを見たか? お前が最初のダンスを踊るんだぞ」
舞踏会のダンスは、招待客の中で一番地位の高い男性が先鋒を務めると決まっていた。
「自信を持て。落ち着いてやれば絶対にできる」
「しくしく……。おれは嗅ぎたばこの灰……」
石橋をたたきすぎて粉砕してしまうドラウスは、このゾーンに入るとしばらく立ち直れない。しかたないな、まったく……。
ほら、とノースディンがドラウスの手をとる。
「まだ幕が開くまで時間がある。確認くらいならできるだろう。わたしが霊条約をやるから」
「エーン」
いいから泣くな、と言われると、しょんぼりとしながらもドラウスはちょっとだけ笑った。
「ありがとう」
「舞踏会が不安で仕方がないウスと、その親友の話」
1 note
·
View note
Photo

***
昨晩のことよ。わたし──そう、わたし、とても素敵な方に出会ったの。
とても月の綺麗な夜だったわ。どこにいてもわかるくらい、背丈の大きな殿方で、名前は、ええと、名前は何だったかしら……。ええ、そう、不思議なの。わたし、確かにあの人の名前を聞いたのよ。不思議な言葉だったけど、素敵な響きだと思った。そしたら、カドリールが始まって……そう、わたしは確かに言葉を交わして──おかしいわね。あんなに素敵な紳士なら、忘れることなんてあるはずないのに。
でも──昨日のことなのに、いまはもう、顔すら思い出せないの。
もしかしたら、わたし、幻覚を見たのかもしれないわ。ワインを飲みすぎたのかもね。
でも、ひとつだけしっかりと覚えているの──。
その人からは、夜の匂いがしたわ。
「こっそりヒトの舞踏会に参加していた若御真祖様のおはなし」
0 notes
Text
嘘つきの小夜啼鳥
ちいさなドラちゃんと氷のような師匠のおはなし。ほんのりノス→ウス風味。ほんとのほんとに何でも許せる方向け。
***
「嘘つきの小夜啼鳥」
ノースディンおじさまはうそつき。
ノースディンおじさまはうそつき。
ほんとは、あんなこと言う人じゃないのに。いまのおじさまは別人みたい。
でも知ってる。ノースディンおじさまがうそつきだってこと。
だって、わたしが泣いても、絶対になぐさめてくれないのに。わたしがどこで泣いていても、かならずわたしを見つけるんだもの。
ノースディンおじさまは、とってもうそつき。
一人前の吸血鬼になるためには、これくらいできて当然だ、っておこるのに。いつまでも、うだうだと、わたしの失敗した理由をあげてる。
本当にうそつき。
ひどいことばかり言うのに、わたしが困ったとき、どこからでもすぐやってくるんだから。
くそったれ! 師匠の嘘つき!
頼んでもないのに、誕生日には絶対なにか部屋に置いてあるんだ。お前なんかにボトルの味はわからん、無駄になるだけだって言ってたくせに。
師匠の嘘つき!
ちゃんとおいしいなら最初からそう言ってくれればいいのに! だったら最後まで完食するな。人のことシェフかなんかと思ってないか?
腹立つ! こんなとこ絶対に出て行ってやる!
ああ、ひどい人。
「不出来な弟子」だと、わたしを呼ぶくせに、わたしのことを「一族のできそこない」と呼ばない。
お父さまの息子なのに、お祖父様の孫なのに。
いつも、失敗ばかりのわたしを叱りつけるけれど。部屋は寒くなるけれど。できそこないとは、一度だって言わないんだから!
そういえば嘘がお上手な人だった。お父様のことだって──大好きなのに。師匠はなにも言わない。
まるでオスカーワイルドの白い鳥。
それなら、かなわないと知っていながらも啼きつづける、あの白い鳥でいればいい。
はあ~~~~~~~……。
あンッッのロートル髭。
いらんって言ったにもかかわらず、ご丁寧にもこんな高そうなスーツを送ってきて。
まるで七五三だな!とか煽ってきやがったくせに。人のこと何歳だと思ってるんだ? ハァーーこれだから老眼は!
お父様に言って返品しようとしたら「次の表紙撮影の衣装を贈りたかったんだが、わたしはセンスが壊滅的だから、代わりにノースに行ってもらったんだ!」って、なんだそれ。
お父様もお父様。ちくしょうアンニャロメ、いつ会計済ませたんだ。ふざけんな髭。おせっかい髭。
余計なものまでポンポン送ってくるな。S-falの取っ手の取れる鍋とか……べ、別にほしかったわけじゃないんだからね! 今年もご丁寧に誕生日ぴったりに送ってきて。いったい何百年続けるつもりなんだよ。
うっせーわ鍋くらい自分で買うわ。
突然シンヨコまで押しかけてくるし──でもあれは惜しかったな。もう少しで、あの! いけ好かない髭のボンテージ姿が拝めたっていうのに。もったいないことした!
あーやだやだ。あんな顔しやがって。老婆心だかなんだかわからんが、くだらん理由でいらんことをするな。顔を見に来たかっただけって素直にそう言え。まわりくどいにもほどがある。
アンタは昔からそう。お父様のことだってそう。
気づいていないって思っているんだろうが。残念だがな、そんなことはずっと昔から知っているんだ。自分の気持ちを氷漬けにして。減らず口のクセに、しおらしいマネなんかして。エルサだってちゃんと城から出てきたぞ。ゲルダの涙なんていらないって言うんだろ。でも、アンタのそのバラは棘だらけだ、師匠。自分で作った棘だ。そのバラを胸に抱きしめたまま、永遠に血を流し続けるっていうのか。
アンタは昔っからそういう人だ。だからわたしが何を言ったって、変わることはない。そんなことは知っているのさ。だからこちらはせいぜい毒を吐かせてもらうんだ。あんたが自分に素直になるまでな。
ああ、いやだ。あんなケツでホバリングしてるような女たらしの心配をするなんて。
この嘘つきのナイチンゲール。
一生痔になってろ! バーカ!
0 notes
Text
プリマヴェーラの葬送
花の香りがする氷笑卿の昔話。
ノス→ウス。捏造150パーセントでお届けするので、本当になんでも許せる方向けです。

「プリマヴェーラの葬送」
春。美しい季節。
麗しく咲き誇る花の女神が、全ての命を芽吹かせる時。
私はそんなものとは無縁だったが、もちろん、そのことについて自分を哀れんだことはない。
冬は辛く冷たい氷の季節。全ての命が眠り、雪の下に閉じ込められる。生まれる命が言祝がれることはない。
私とはそういうものなのだ。そしてこれから先も──そうであれと思っている。
***
ある時、お前からは花の香りがする、とドラウスに言われた。
昔の話だ。
なんのことかわかるはずもない。自覚はなかったし、自分から最も遠いものだと思っていた花の香りなど。凍らせることしかできない私にとっては、考えたこともなかった。
初めは別の吸血鬼の仕業かと疑った。しかし、やはり思い当たるものがない。
一過性のものだと思っていたが、私からは変わらず花の香りがしていたようで、いつもドラウスは決まって「いい香りだ」と言っていた。鼻が利くのはオオカミに変化することが多い故か、それとも血のなせる技か。真実はわからない。
「お前はいつもそう言うが、一体どんな香りなんだ」
「そうだなあ」
鼻をスンスンといわせたドラウスは、その時は「バラの香り」と言った。
ちょうどその頃あたりから、私はドラウスの相談相手となっていた。
当時のドラウスは、名門の嫡男という責務を自分に課して、いつも苦しんでいた。そのぶん、完璧にしたいが故に失敗した時の落ち込みはひどいものだった。
ドラウスが突然私を呼び出す時は、決まってなにか悩んでいることがある時だ。
「ノースはなんでもわかるんだなあ」
いつもそんなことをドラウスはぼやいた。
「当たり前だろ。お前のことなんてお見通しだからな」
私はフフンとでも笑っていたのだろう。
***
思い当たる節はなかったが、なんとなく考えていたことがある。
私の中で何か──そう。おそらく、花が咲いているのではないか。
おかしなことだと笑うだろう。だが思いつくことはそれくらいだった。
もちろん物理的なものではない。実体を持つものではない。だがその花は、初めてドラウスに会った時から、そして、その友人になった時から──自分の中にずっと咲いているのだ。
それを裏付けるかのように、花の香りは、私の感情に合わせて変化した。
バラだけではなくアザレアや、ミモザに。モモやスミレに。そしてある時はリナリアに。
それらを経て、ようやく私は確信に至った。私の中でその花のつぼみが膨らむ度に、美しい花をつけて咲き誇るたびに……おそらく。
私には永久に関係のないものだと思っていた春を、与えてくれたドラウスを。冷たい冬に、初めて手を差し伸べてくれたあの男を──想うたびに。
おかしな話とは思うが、そんなことがあったのだ。
でも、ドラウス。私はお前のことなどお見通しだから。
この美しい季節が、長く続かないということも、よくわかっていた。
***
「春だなあ」
バラに水をやるドラウスがのんびりと言う。彼の城の庭では、いままさに花開かんとするバラたちが、水のドレスを纏って美しく着飾りはじめていた。
季節の移り変わりなど、我々にとっては些細なことだ。長く時を生きる、我々にとっては。
「最近、お前から少しも花の香りがしないから、春だってすっかり忘れていたよ」
ノース、あれやめたのか?突然ドラウスにそう言われても、知らない体をつらぬく。
「何の話だ」
「前はバラの香りがしたのに」
俺アレ好きだったのになーとドラウスは残念そうに言った。
今では「そんなこともあったかもしれない」という認識にとどめるのみだ。確かに、お前から「花の香りがする」と言われていたか。しかし、それはとうの昔に、私から最も遠いものへと還っていった。
私は自分の手であの春を葬ったのだ。口付けを落として──もう何百年も前に永遠の眠りを贈った。
そうすることが彼の幸せになるということを理解していたし、そうするべきだ、と私自身が判断したのだ。後悔は──ないと言うべきなのだろう。だから、後悔はない。
それは、お前がくれた花がまだ美しく咲き誇っていた頃の話。二度と春は訪れないし、花がこれ以上咲くこともない。凍ったままの大地に花は咲かない。
「でも今日はなんだか甘い匂いがする……」
「そうか?」
「うん、この匂いは知ってるぞ」
「ほう。一体どんな香りなんだ」
「そうだなあ」
ドラウスは鼻をスンスンといわせると言った。
「ヘリオトロープ!」
「……よくわかったな」
嬉しそうに笑ってドラウスが言った。
「ミラさんが前に育てていたんだ!」
私はそっと目を伏せた。
「レディからの貰いものだったかな。いいオードトワレだ。腐らせておくのは勿体ないだろう」
私の言葉をうけて、ノースは本当に女性との付き合いが上手だなあとドラウスが言った。その言葉はまるで冷たい無機物に反射したかのように、空虚な響きで。
ああ、ドラウス。お前はずっと変わらないでいておくれ。どうかいつまでも気づかずにいておくれ。
私の中で咲き誇っていたあの花が、深い氷の下で美しいまま、とこしえに訪れない春を夢を見ていられるように。
それでいいのだよ。それが私の幸せだから。
「ところで 、また何か問題か?」
そう尋ねると、ドラウスはベアッと奇声を上げて明後日の方向に目を泳がせた。
「いや、そんなことはないぞ!いつも通り私は完璧だ」
手がもじもじしている。嘘くさいにも程があるのではないか。
「それで?私は何をすればいい」
なお追求すると、やがてドラウスはしょんぼりと肩を落とし、「わたしはゲボです」と泣いた。
ドラウスが突然私を呼び出す時は、決まってなにか悩んでいることがある時だ。
「ノースは本当になんでもわかるんだなあ」
困ったように笑ってドラウスが言う。
私はフフン、と笑った。
「当たり前だろ。お前のことなんてお見通しだからな」
*ヘリオトロープの花言葉
" 献身的な愛 "
0 notes
Text
明日からのてがみ
ヘル+真くらい。
ヴァン・ヘルシングがある夜の日に見た不可思議な夢と、それから。
何でも許せる方向け。170%捏造。

「明日からのてがみ」
"目を開けると、別世界にいた"。
月や地底への旅行を夢見る時代だとしても、こんなことを言っても信じてくれるかどうかは��問だが。
しかしおかしなことも起きるもの。
「なんだこれ」それが、わたしの第一声だったと思う。
わたしはいつも通り寝床にもぐりこんだだけなのに、立ち尽くした場所は見知らぬ場所。
馬車の代わりに、カブトムシのような何かがものすごい速さで駆け抜け、通りを歩く人の波は、みな一様に薄い板のようなものをつついたり、耳に当てて喋り、せかせかと、せわしく通り過ぎていく。
なじみのない言葉。見たことも想像もできない異様なもの。明らかにアムステルダムではない。ましてやハンガリーなわけがない。そして──ルーマニアでもない。アイツなら喜びそうだが、それは別世界と呼ぶに相応しかろう。
しかし不思議なことに、自分の目で見て歩いて探索するごとに、どうもすべてが幻とは思えないほど、その世界は現実味を帯びているように感じた。名前はシンヨコハマとかなんだとか。わたしがいるはずの場所から離れているにも関わらず、そこには変わらず吸血鬼がいて、そして退治人がいる。
ただ少し違ったのは、この場所では吸血鬼と人間が半ば共存して生きているということだった。
これは、わたしに大きな衝撃と驚きをもたらした。わたしが生きている世界では、想像もできないようなことだった。補足する、捕食される関係に横たわる溝はあまりにも深く、だからこそわたしは──隠し通さなければならないと、そう決意したのだったが。
わたしを拾ってくれた青年は、退治人をしていると言っていた(まだ若いのに、なんとも立派なことだ)。
そして、吸血鬼と同居していた。
どこかアイツを思い出すような吸血鬼と。夕飯の話をして、小言を言い合って、軽口をたたいていた。
随分と奇妙な既視感を覚えたわたしが、ここが自分がいる世界の未来の場所なのではないのか、と確信をもったのは、その時だった。
そうか、そうなのか。遠いどこかで、こうなる日が来るということなのか。
そう思うと、ああ──なんだかとても──安心した。わたしは退治人なのに。それは喜びだった。理由はわかっている。
彼らは、我々に本当によく似ていた。
もちろんそれは同時に──わたしはこの時代に生きることはできない、ということも示していた。どうしてわたしが名乗っても、誰もが微妙な反応をしたのか。これがその答えだったのだろう(意外とつらかったシング)。
それでも、喜ぶべきだと思ったのは──お前が一人じゃないとわかったから。
見たんだ、お前の姿を。ずいぶんと歳をとったようだが、ロンドンでなくとも相変わらず人を巻き込んで。あれはお前の孫か──道理で。お前の息子にそっくりだ。
変わらなかったな、お前は。誰も知らなかったわたしの名前を、お前だけが呼んでくれたよ。
その隣に立てないことが、ほんの少しだけ──寂しい。けれど、思わず口元が緩んでしまった。ああ、これなら、と。
だから、D。これを読むころ、きっとわたしは──
次の一文をタイプしようとしたところで、声がかかった。
「ごはんできたよ」
「いま行く」
そう返事して、わたしはタイプライターのキャリッジをガシャリとスライドさせた。
「なあ、D」
「なに?」
椅子に座ってコーヒーをすすると、どこで焼いたのか、アイツがバケットをすすめてくる。
思わず出そうになったその言葉を、わたしはコーヒーで喉の奥に流しこんだ。「いや──なんでもない」
それ以上アイツは聞いてこなかった。
焼きたてのバケットを頬張る。やっぱりうまい。──吸血鬼なのにな。
「うまいよ」
表情の変わらないアイツの目が細められたのがわかった。
「そう?よかった」
──結局のところ、目が覚めたときにはわたしは元の世界に帰ってきていて、相変わらずアイツはいたし、コーヒーの香ばしい香りは、すぐにわたしの鼻腔をついた。けれどもそれは、私をどうしようもなく安心させて。
あのすべてが現実になるとしても、その時代を渇望したとしても──やはりわたしには、いま生きているこの時が、アイツと笑っているこの時代が、愛おしいということなのだ。
最後の行を打ち終える。
宛名は書かない。だがおそらく、わかってくれるだろう。蠟を落として、封をしたら、これは銀行の金庫に預ける。
次に金庫が開くのは、わたしがこの世を去って、それから十分の時が過ぎてから。そしてその時には、何も詮索せずに、ただ"ある住所"にこの手紙を送ってほしい。そう書き添えて。
これを読むころ、きっとわたしはお前の隣にいないだろうが、どうか──
言葉に出してしまえば、それが呪いになるとわかっているから、わたしは続いていく先の時代にそれを託す。
こんなものなくったって、わたしがいなくなったって、ただこれからも、あの"いつか来るかもしれない時代"で楽しくやってくれること。それが昼の子としての、そして不本意ながら友人としての──わたしが望むことだ。
***
さわっと風が凪ぐ。
いつ訪れても、ここには静寂が満ちている。
「またこちらにいたのですか」
お父様。後ろに立ったドラウスが声をかける。
返事を返すことのない墓標が、みるみるうちに花で飾られた。ずっと一緒にいれない分、たくさん咲かせても罰は当たらない。きっと。
「見つかっちゃった」と言うと、ドラウスはため息をついた。「お父様は、いつもここにいますね」。
そうなのだろうか。あまり自覚はないが。
そう?と聞くと、ハッキリとした口調で答えが返ってくる。
「そうです」
まさか、自覚しておられないので?と聞かれたが、気にしたことない、と言って頭を振っておいた。
アイビーが、柔らかい風に揺れている。
「やはり、思い出すのですか」
ドラウスが口を開く。ちらりとこちらの表情を盗み見るその表情は、やや心配しているように見えた。
"人間のご友人を"とドラウスは言わなかったが、それはきちんと伝わっている。
「うーん」少し考えてから、口を開く。
「そうじゃないといえば嘘になるけど、そうかと言えば、少し違う」
そっと墓碑に手を触れる。
「忘れたことなどないから」
愛おしむように冷たい石の表面を撫でる。
だから、思い出そうとしたことはないよ。そう言うと、恐る恐るドラウスが尋ねてきた。
「……寂しくなることはないのですか」
きまりが悪そうな顔で待っている。少し置いてから「そうだな」と返答した。
昼の子の一生は花のよう。瞬く間に、移り行く季節と共に、通り過ぎていく。
「我らと昼の子は生きる場所が違う。お前も知っているように」
結局は彼も──わたしを置いていってしまった。
わたしが彼と過ごせた季節は、あまりにも短くて。ひとり残されたわたしにもたらされたのは、永遠に続く灰色の季節で。
「消えてしまいたい日もあるよ」
思わずそうこぼすと、ドラウスが息を呑んだのがわかった。
「お父様──」
青ざめているドラウスに気づいて、あわてて手を振る。
「大丈夫、大丈夫」
勝手に死んだりしないから。
死んだとしても──我々は同じ場所には行けないのだ。その国に足を踏み入れることは、おそらく叶わない。それで彼に会えるのならば、わたしはとうの昔にそうしたことだろう。でも。
「死んじゃダメって言われたから」
「誰にです?」
その質問には、「ないしょ」。そう答えるだけにとどめた。
首を傾げたものの、こころなしドラウスはホッとしたような表情を見せる。
安心した?と聞くと、知りませんと言ってむくれたドラウスに、笑みがこぼれる。
ある日届いた、宛名のない手紙。けれど、手にした時から何となくわかっていた。色褪せたその手紙を開かずとも、送り主が一体誰なのか。
今よりもっと"面白いもの"がたくさんあるはずだから、良い時代になっているだろうから。
「だから死ぬな」。そこにはそう書いてあった。
それが酷なことだと知っていて、精いっぱいの理由を列挙しているのが何とも愛おしかった。吸血鬼なんて信用できないってあれほど言っていたのに。きみは──ずっと、最期まで──優しい人間だった。だからね。
ゴデチアが、さわさわと笑うように揺れる。
「もう少し生きてみるよ」
わたしは自信をもってそう口に出すことができたのだ。明日から今へ。過去から未来に届いたきみの声にこたえるために。
センニチコウが月明かりに煌めいて、紫と赤が混ざったようなその色に、わたしは自分の孫と、その愉快な友人のことをちらりと思い出す。
「だって、まだ面白いものがたくさんあるもの」
きみが教えてくれたように。
「……」
しばしの沈黙の後に耳に捉えたのは、深く深くついたため息と、呆れきった声。
「ぜひともそうしてください」
私には荷が重すぎますので。そうボヤいて声の主は疲れたように肩を落とした。
0 notes
Text
星月夜の子守唄を君に(後)
失踪した御真祖様を探しに行くヘルシングおじさんのお話。 150パーセント捏造でお送りします。ヘル+真くらいぼやぼや。 前編はこちら。

「星月夜の子守唄を君に(後)」
アムステルダム中央駅からロッテルダムまで出て、港から船便でイギリスに入ったわたしが初めにしたことは、アイツの屋敷を訪ねることだった。
リバプールから更に陸路でピカデリーの方へと向かい、グリーンパーク付近で降りると、妙な懐かしさを感じた。
吸血鬼のいる屋敷と聞けば、石の壁で囲まれた暗くて、埃っぽくて、じめじめした場所を想像するだろうが、実際はそうではない。流行りのヴィクトリアン様式で建てられた、普通の屋敷だ。ガーデニングが好きだったらしく、玄関前の植え込みが非常に丁寧に手入れされていた。
廊下を抜けてキッチンに併設されたサンルームから中庭に出ると、美しい緑が目に飛び込んでくる。月の綺麗な夜は、そこで2人して大酒をかっ食らったものだ。
今回は合鍵を持ち合わせていないが、さて──
ドアノブに手をかけると、簡単に屋敷の扉は開いた。不用心だな。それとも、わたしの来訪を見越してか。
わたしは一通り部屋を見回って屋敷を出ると、セントジェームズパークでアヒルにエサをやりながら、夜になるのを待った。
手紙には消印も住所もなかったが、あの手紙はただの便箋ではなかった。よく見ると薄い透かしが入っているもので、試しに陽にかざしてみると、ある模様が浮かび上がった。それがイギリス王室の紋章だったのだ。おそらく土産として路上で売られているものだろう。そんなものが手に入りやすいのは、女王陛下がおわすお膝元──すなわちロンドンだと踏んだ。
そこまでたどり着いたのはいいが、詳細な場所までは把握できてはいない。ここを選んだのは、正直に言うと賭けの面が強かった。
それでも、自分の中にあった何らかの自信が確実なものになったのは、視界の端に、同じようにアヒルにエサをやる背の高い紳士をとらえた時だった。
「おい」
そう声をかけると、背の高い紳士はすっとこちらを向いた。
「何か用ですかな?」変わった訛りの英語で男はそう答えた。
トップハットをかぶり、全身を黒で固めた若い紳士だった。目元が見えないようにサングラスをかけている。髪は赤毛だった。
一見すれば、アイツとはかけ離れてるように見えるが──
「お前、影がないぞ」
夕陽に照らされた男の足元には、影一つ落ちていなかった。
「あれ。ミスっちゃった」
すっとぼけたような、聞きなれた声がしたかと思うと、瞬きの間に男の髪は赤から艶やかな黒へ、若者から口ひげをたくわえた男性へと姿を変えた。
「……どうしてわかったの?」
手紙の主である”D”──アイツは、後ろめたいような顔をして言った。
「手紙だ。こんなものが売ってるのは、バッキンガム周辺だろう」
予感が確信へと変わり始めたのは、屋敷を訪れた時だ。キッチンの棚には相変わらずいい酒が揃えてあったし、植え込みも中庭も、綺麗に手入れされていた。机の上の万年筆のインクは乾ききっていなかった。それは、長い間放っておいていて維持できる状態ではない。
「さがさないでって言ったのに」
「さがしてくれって言われたんだよ」
お前の息子に。そう言うと、アイツはそう……とだけ言って、再びアヒルに餌を投げた。
「なんでいなくなった?」
「家出」
「随分と長い家出だな」
目を合わせようとしない。そういう時は決まって何か隠している時だった。
「1度も会いに来なかったな」
「そうだね」
「お前がいなかったせいで、本が返せなかった。1年も」
「そうだね」
「……」
返事はない。
並んでアヒルに餌を投げる。黒いアヒルだけが、やけにわたしの餌に食いついた。
ちらりと横を見て、少しも変わらないアイツの表情にふうとため息をつく。
「俺のことをどう思おうが構いはしないが、家に帰れ。お前の家族が困ってる」
そう言うと、今まで黙りこくっていたアイツが急に口を開いた。
「きみに会うのが、こわくって」
──うん?
突然飛び出した言葉は、思わず同じ言葉を口に出してしまう程の衝撃だった。
「うん?」
なんだって?
わたしが素っ頓狂な声を上げても、アイツはこちらを見なかった。
代わりにポツリ、ポツリと、言葉が紡がれる。
内容はこうだった。「いつか来るきみとの別れが怖くなった」と。
吸血鬼と人間の間には、どんなに努力しても、足掻いても、ひっくり返せないものがある。それが寿命というものだ。
それが辛くなった、と。
「きみと友人になって、毎日がどんどん色鮮やかに、眩く煌めいていく度に──同じだけわたしは、自分自身の運命を思い知るようになった」
長い間忘れていたものだった。初めて得たものだった。そう言ってアイツは目を細めた。
「ただ、寂しくて」
「……それで、姿をくらませたのか?」
わたしが尋ねると、うん、と言ってこっくりと頷いた。
「そうすれば、いずれ来る運命の酷さも、少しは和らぐだろうと」
なんだそれ……
「……俺はてっきり……俺のことは、もうどうでもよくなったのかと」
「わたしがそこまで酷い男に見える?」
「さあな」
お前たちのことは、よくわからん。そう返すと、少しだけアイツの口角が上がったような気がした。
ちょっと安心してる自分が悔しかった。
「でもきみは、吸血鬼にはならないでしょ」
「だろうな」
「昼の子は、みんなわたしを置いていく」
最後の餌を投げてポツリとつぶやく。ゆらゆらと動く水鏡に、その姿は映らない。
「だが──それが人間ってやつだ」
一人きりで水鏡に映る自分の姿を見ながら、わたしはつぶやいた。
「俺たちは死ぬ。それは避けられない」
教鞭をとってる身として、それは誰よりもよくわかっているつもりだ。
そうして次の世代へと渡していくことで我々は時代を紡いでいく。忙しなく動いて、止まることは出来ない。それが人間だ。少なくともわたしはそう思っている。
「できない」
「知ってる」
あきらめたような、素っ気ない返事だった。
陽が傾き始め、ぽつぽつと、セントジェームズパークの街灯に暖かい光が灯り始めた。
何か気の利いた言葉をかけてやるべきなんだろうが、いまのわたしには、うまく言葉にできる自信がなかった。
「俺は」
急にむずがゆくなった頭をガリガリとかく。
「大変不本意なことだが──お前のことを、友人だと思ってる」
ぱっとアイツの顔が明るくなったのがわかった。しかし、その意味を悟ってか、すぐに元の表情に戻ってしまう。仕方がないな、まったく。
「だからお前とは、吸血鬼だとかそういうことじゃなくて──1人の人間として付き合いたいんだ」
お前が俺を退治人という言葉でくくらなかったように。
そうだろ、とアイツの顔を見ると、視線が合った。それもほんの少しの間で、そっとアイツは視線をそらせた。
本心だった。いずれ遺していく側の者として、何を言えるわけでもないが。
「…………」
何も言わずにいたアイツは、やがて観念したように肩を落とすと、「きみって、ずるいよね」とそっと呟いた。
「なんとでも言え」
わたしはフンと鼻を鳴らした。こっちはわざわざアムステルダムから、大学に嘘までついてお前を探しに来たんだ。この間にもどんどん仕事が貯まってきていると考えると、正直げんなりする。
「それに──それですべてが終わるというわけじゃないだろ」
死んだからといって、いなくなったからといって、世界から消えてしまうわけではない。
誰かの記憶として、誰かの思い出としてずっと遺る。わたしは、東洋や熱砂の国に伝わるような、"廻る"思想について思い出していた。
「お前は俺よりもずっと長く生きる。でも、そうすればいつか……」
別の形なのか、それとも直接会えるのかはわからないが──いずれにせよ。それでも、こんなにも不思議と神秘が根付く世界なのだから。
「また会えるかもしれない」
「……」
「少し、夢を見すぎているのかもしれないが」
妙な沈黙が続いたので、慌てて誤魔化す。ガラにもないことを言ってしまったかもしれない。しかし、それもまた本心だった。大変不本意ではあるが。
「それでいいのか、我が友──ヘルシング」
しばしの沈黙の後、夜の香りを纏う真摯な声が、わたしに問いかける。
水面には宝石のような光が浮かび始めていた。それは手を伸ばせば、掬えるかもしれないほどで。
わたしの答えは決まっていた。
「俺は、それでいい。D」
「……そう」
そっと目を伏せて、アイツはそれ以上何も言わなかった。
わたしは、それで良いのだと思った。明日には元の調子に戻っているだろう──そんな予感がわたしには確かにあった。
***
陽はとうの昔に傾き、あたりはすでに宵闇に包まれていた。アイツの"お得意"の時間だ。
「見ろよ、ほら」
2人で見上げると、我々の頭上でたくさんの星が美しく輝いていた。ロンドンは煙で燻ってる場所だと思っていたが、こんなにも美しい星が見られるとは。そして、何よりも。
「なんて綺麗な月なんだ」
あわい光を降らしながら、ロンドンを見下ろす月。いつかの時に見た、そう──あの月と同じように綺麗な月が、夜の海に浮かんでいる。
「月に行ってみる?」弾んだ声でアイツが言った。「連れてくよ」
「バカ言うなよ。そんなこと、ヴェルヌの頭の中でしか出来やしないさ」
「そう?でも、月なら──」
月なら。アイツは何か言おうとしたが、そうだねと小さな声でつぶやいただけで、結局その先は言わなかった。
月世界旅行なんて、まさに夢のような話だ。あと何世紀も巡らなければ、とても人類では到達できそうにもない。
「だが……うん。そうだな、もし本当に連れて行ってくれるって言うのなら──」
わたしは少し考えてから、「お前と月旅行っていうのもいいかもしれん」と言って笑った。それも悪くはないだろう。本当にそんなことができれば、だが。
「……うん」
慈しむように瞳を細めて、夜を統べる竜がうなずく。
「本当に──きれいだね」
そんなことを口にして、ようやくアイツは笑った。
***
「せっかくの美しい夜だ。満喫しないのはもったいない。お前のとこで飲み直そう」
セントジェームズパークを後にしてピカデリーのほうに向かう道すがら、わたしはアイツの背中を叩きながら酒のことばかり考えていた。
「きみ、もう私のワイン開けてるでしょ」
「なんだ、やっぱりいたんじゃないか、お前」
実は3日ほど、あの屋敷に厄介になった。ここで張っていれば帰ってくるのではと踏んだからであって、決して酒がうまかったからとか、ホテルの予約を忘れたからとか、そういうことではない。
一度も帰ってこなかったので空振りに終わったと思っていたが──アイツの神出鬼没な性質は、今に始まったことではないか。
「うまい飯も食いたい!」と言うと、じゃあ、何か作ろうか、とアイツは笑った。
結局のところ──やっぱり何をどう取り繕っても、わたしはアイツの友人であることが、楽しいのだろう。
いずれ訪れる未来の自分を救うために、いますぐ大学に戻ることもできたが、カバンにつめてきた本は返しにいかねばならない。借りたものは返さねば。そう、仕方なく返しに行かねばならないのだ。なにより、せっかくもぎとった休暇なのだから……
「次はコナンドイルが読みたいんだが」
「全部あるよ」
「そりゃ、ありがたい」
しばらくは、ご褒美だと思って騒がしい休暇を楽しもう。その真実を知っているのは、この美しい夜だけなのだから。
0 notes
Text
星月夜の子守唄を君に(前)
失踪した御真祖様を探しに行くヘルシングおじさんのお話。 150パーセント捏造でお送りします。ヘル+真くらいぼやぼや。後編はこちら。

「星月夜の子守唄を君に(前)」
アムステルダム大学の研究室で、膨大に積み上げられた資料を確認してる頃だ。夜の帳がすっかり落ち切った深夜12時頃。研究室の扉をノックする音があった。
この時間に来る生徒は珍しいというわけでもないが、私には少しの"勘"があった。人間ではない。
「どなたです?」私がそう聞くと、扉の外から声がする。
「夜分遅くに申し訳ない。火急の用事があってうかがった」
男の声だ。そっと音を立てぬように6連の銃に手を伸ばす。もしものことがあってはならない──扉越しで会話を試みる。
「火急の用事とは?」私が声をかけると、なぜかためらうような声が返ってきた。
「父のことで……」
「父?」
おや?なんだか聞いたことがある声だぞ。
それから扉の外の訪問者は、すまなさそうな声でこう言った。
「お父様のことで、相談がある。人間の方」
わたしの名前はヴァン・ヘルシング。アムステルダムのしがない教授であり──吸血鬼退治人である。
***
「アイツがいなくなった?」
そう言うと、夜に棲む客人は返答代わりにしゅんと肩を落とした。なぜこの男は、人の部屋で紅茶を飲んでいるのか。
いなくなったのは他でもない、かつてわたしが派手にやりあった、あの吸血鬼──だというのだ。厄介である。話を聞くと、もう1年は戻ってきていないと言われた。
「お父様が突拍子にいなくなるのは日常茶飯事だが、ここまで日を空けられることは今までなかった」
我々としては、ありがたいことなのだが──とそう付け加えながらも、「ぶっちゃけた話、わたしには一族をまとめ上げられる自信がない」と彼は言った。
「このような時代だし、我々もこの先どうなるかはわからない。一族内で決めるべき事項がいくつか浮上してきている。決定権をもつお父様にこれ以上城を空けられると」
変わらず我々と彼ら吸血鬼の間には深い溝があり、いまだに拮抗状態が続いていた。嫡孫のことも聞いている。あれこれと対応しなければならないことがあるのだろうが──なぜこの男は、人の部屋で優雅に紅茶を飲んでいるのか。ティーカップがウェッジウッドのなのが妙に鼻につく。
「それで、お父様のいそうな場所に心当たりはないか、お聞きしようとこちらにうかがった次第で」
「どうして私のような者のところに。便宜上は退治人だとお父様とやらに聞かされているはずだが」
「お父様からは、貴公は我が父の友人だとうかがっている」
アイツ!そんなこと言いふらして……
「残念ながらアムステルダムにもどってからも、一度も顔を見てはいない」
すまない、というと客人は、一息置いてからウエーンと泣きだした。
なんだか、妙な予感はしていた。
借りていた本を返しに、城に行った時のことだ。いつもならこちらから赴く前に飛び込んできそうなアイツが、少しも現れないのでおかしいなと思っていたら──留守です、と。開口一番、一族の者にそう言われた。噂の"白銀の狼"──彼の一族の嫡男である。日が悪かったと何度か改め直したが、やはりその都度、留守だと言われた。
そんなことを繰り返してるうちに、私は大学の方に呼び出され、アムステルダムに戻らねばならなくなった。アイツのことだから、ふらりとそのうち現れるだろう。その時に改めて本は返せばよい──そう思いながら、気が付けばもう1年が経ってしまったのだという。
その嫡男殿は、いま研究室のソファで膝を抱えながら「わたしはゴミ!」と自暴自棄になりながら泣いている。
「わかったから、ドラウス殿」ハアと私はため息をつかざるを得なかった。「アイツが行きそうなところを考えてみるから、今日のところは帰ってくれ」
「エーン」
「見つけたら連絡するから!」
「ウエーン」
彼はまだピスピスと泣いていたが、こちらはロンドンで走り回っていた時期のツケが溜まりにたまっている。正直なところさっさとそれを片付けたかったので、アイツの息子には早急にお引き取り頂いた。
──いなくなっていたのか、アイツ。
先ほどまで客人が座っていたソファに沈み込むと、ようやく得た小休止に、1日の疲れがドッと押し寄せてきた。
いなくなっただって?わたしはてっきり……。興味がなくなったのかと、そう思っていた。長く生きる彼らにとって、私の存在など、ほんの一握りの砂でしかないのだし。それにしても……。
「一体どこにいったんだ」
人のことをほっぽっておいて。いや、別に寂しいとかそういうことではない。とにかく今はこの貯まった仕事を片付けねば。そうしたら、少しはアイツを探しに行ってもいいのかもしれないが──友人という言葉が、ずっとわたしの耳朶をくすぐっている。
その次の日だった。私のもとに「さがさないでください」と書いた手紙が届いたのは。
Dとだけ書かれた署名、それはわたしの重い腰を上げさせるには十分だった。
***
結局、貯まった仕事を片付けるまでには、結構な日数を擁してしまった。
めんどくさいあれこれをしっかり収めたのち、わたしは退治人としての仕事を名目に、大学側に長い休暇を申請した。これでも”ここ”では名の知れたほうである。大学側も簡単に却下はできまい。
さて。休暇をとったはいいが問題は、アイツの行き先である。ドラウス殿に電報を打ったところ、南米の別荘や日本の方にはいないということだった。
大学を留守にできる日数にも限りがある。いとも簡単に世界中を移動できるような相手を、闇雲に探すことはできない。一体どこに行ったというのか。
そもそも、なぜアイツを探すなんてことを考えたのか。向こうの方が圧倒的にこちらを探しやすいだろうに。こちらが骨を折って走り回る必要などないだろう。
しかし、��んな手紙を寄越されたからには──手紙?
そうだ、手紙。一体あの手紙はどこから送ってきたものなんだ?わたしは机の上の本をひっくり返しながら、急いでアイツからの手紙を探した。手紙は、積み重なった本と本の間から見つかった。住所はおろか、消印もなかった。何の変哲もないただの白い便箋だったが、果たして本当にそれだけだろうか──?
わたしは急いで駅に電話をかけ、本日午後発の電車のチケットを予約した。旅行鞄に借りたままの本も一緒に詰めると、コートをひっつかんで研究室から飛び出す。ようやく居場所に目処がついた。
向かう先は、ロンドン。
我々が初めて対峙した地である。
0 notes
Text
ビブリオテーカが告げる春
ドラルクがロナルドくんと出会う少し前くらい。 御真祖様と秘密の部屋の昔話。
120パーセント捏造。「ビブリオテーカに眠る春」と対になるおはなしです。

「ビブリオテーカが告げる春」
「ううー寒い。なんでこんな山奥なんかに城をわざわざ建てたんだウチの一族は」
トランシルヴァニアの深い山の奥。切り立つ崖の上。そこには、吸血鬼が出ると噂されている城があるという。
地元でまことしやかに伝えられてきたその城に、かつての主だった吸血鬼が今宵、舞い戻ろうとしていた──という感じに書くと、「なんかカッコイイ導入」みたいで聞こえがいいが、ただの帰省である。
遡ること数日前。その日、ドラルクはひさびさに「ヤサシンクリード2」をプレイしようと意気込んでいたはずだった。
そのドラルクがなぜトランシルヴァニアに帰省しているのか?
簡潔に言うと、「実家で逃走中やろ」という電話が、ドラルクの祖父からかかってきたのである。
逃走中?ヤバイオハザードの間違いでは?
当然、ドラルクは乗り気になれなかった。小5のウルトラマン、小さめのゴジラなどと称されるお祖父様の思い付きに付き合って、無事でいれたことが今まで一度でもあっただろうか。
それでもゲームの話題には好奇心を抱かずにいられないドラルクは、初代QSの1000万台モデルをあげるから、というお祖父様の誘惑に抗うことができなかった。チョロい。
こうしてドラちゃん一生の不覚!などとぼやきながらも、結局ドラルクは実家に帰省することになってしまった──これが事の顛末である。
そしていま、一族を巻き込んだ、もはや無理ゲーと化したろくでもない逃走中がようやく終了し 、満身創痍のドラルクは、城の中をトボトボと歩いていた。
***
「お祖父様どこにいるのかなあ」
もはや枯れ柳のようにしおしおのドラルク。
ただでさえ疲れているのに、こんなに広い城の中をあてもなく逍遥するなどという自殺行為をしているのは、スマブラ大会のあと、「QS取りに行ってくる」と行ったきりお祖父様が全く帰ってくる気配がないからだった。
「とりあえずお祖父様の部屋で待つとしよう……」ドラルクは呟いた。そのうち見つけてくれるだろう。ドラルクは2階へと続く階段を上る。
相変わらずお祖父様は世界中を飛び回っているようで、その部屋は美しいもの、珍妙なもので──前に見た時よりも──更にあふれかえっていた。よく言えば退屈しない場所だが、その中にエレベーターに呪いをかけちゃう系やばみざわな人形が見受けれらても、ドラルクは見なかったふりをした。
しかし今日は、足を踏み入れた時から、何か奇妙な違和感を感じる。なんだろう。
その正体はすぐわかった。部屋の奥、マントルピースの後ろの壁が、スライドしていたのだ。これはいやでも気づく。
「エッ」
こんなことが偶然に起こるものだろうか?──ところがどっこい、起こるのである。ここはジョークジョークアベニュー。
「ま、まさか私はパーセルマウス持ち?!組み分けはスリザリンか?!」
エクスペリアームズ!ドラルクは恐る恐るスライドした壁の先に進んだ。バジリスクが襲ってこないことを祈る。お祖父様ならやりかねん、南米でチュパカブラハントしてくる人だもの!──そうドラルクは思ったが、その先にあったのは、バジリスクなどというおどろおどろしいものとはまったく無縁の場所──美しい図書室だった。
「なんだ、ここは……」
城の中にしてはめずらしく白で統一された室内。金の植物がやわらかく部屋を飾っている。隠し部屋らしくこじんまりとはしているが、天井が高く作られており、壁にはそれに近づかんと本が並ぶ。
螺旋状の階段は、ゆっくりと弧を描いて2階の本棚へ誘い、繊細な細工をしたキャビネットには、バカラなどのグラスが綺麗に並べられていた。
本の種類はさまざまで、小説から学術書まで、割となんでもあった。吸血鬼とは縁のなさそうなものが多い印象だ。
「うわーストランドマガジン全部そろってる」
1887年11月号のビートンのクリスマス年鑑まで、お祖父様は所持していた。なるほど、この先ウン世紀はホームジアン諸君を悩ますことになるだろう。
部屋の内装からしてすでに200年近くは経っているだろうに、陽が入らないという環境もあるだろうが──よく見ると、本の状態がすこぶる良い。手に取ってわかることだが、埃も積もっていない。部屋中に掃除が行き届いてるようだ。
奥には暖炉とマントルピースがあり、その前にはサイドテーブルがひとつ──それを挟むように2つの革張りの椅子が静かに佇んでいた。おそらく、お祖父様がマメに掃除をしているのだろうが──それにしても、この部屋は一体……
「おや?」
サイドテーブルの上に何か置かれている。そっと手に取ると、よく使い込まれた、年季の入った丸い眼鏡だった。うん?とドラルクは首をかしげた。
はて、この眼鏡、どこかで──
「ドラルク」
それは、ちょうどドラルクが記憶の糸を手繰り寄せようとしていた時だった。突然響いた声にびっくりしてドラルクが砂になる。もう少しで丸眼鏡を落として割るところだ。すんでのところで最悪の結末を回避して後ろを振り返ると、そこには待ち人、お祖父様が立っていた。
「お、お祖父様!」
ようやく帰ってきた。ちがう、そうじゃない。ドラルクは眼鏡を元の位置に戻しながら、わたわたとした。勝手に部屋に入ったことがバレてしまったのだ。まずい!
わざとじゃないです、ちょっと好奇心を刺激されてしまって、と急いであれこれ理由を挙げへつらう。しかしお祖父様は特に表情を変えないまま、いや、怒ってないよと手をヒラヒラさせる。
「はい、これ言ってたQS」
「あっ、えっ」
本当に怒っていないのか……?お祖父様の表情は変わらない。
「あ、ありがとうございます」
ドラルクは、ぎこちなくお祖父様から黒い箱を受け取った。しかし、濃い青のQS本体を確認して、すぐに生唾を飲む。これがあの、幻とさえ言われる、初代QSの1000万台モデルなのだ──オークションにも出回らないという……先ほどの心配はどこへやら。ヒュー!血が滾っちゃう!
いやあ、長生きはするものだなー!と、ひとしきりQSにはしゃいでから、ドラルクは図書室のことをようやく思い出した。そうだ、この秘密の部屋の話を聞かねば。
「しかし、いい部屋ですな」
お祖父様の表情が、ぴょんっと明るくなった。
「そうでしょ」
「ええ」
ドラルクが尋ねる前にその答えは自ずと返ってきた。
「友人の部屋」
「ご友人の?」
「そう」
「ほー。お祖父様の友人の部屋……」
お祖父様の友人にしては、ずいぶん真面目そうな……
これ全部ですか?とドラルクが聞くと、お祖父様はそうだよ、と言ってこっくんこっくんとうなずいた。これ全部そうなの?!
「もともとは私のものだったけど──使わないから、あげちゃった」
「はあ……」ドラルクは目をしばたたかせた。「随分と博学なご友人だったようですな」
「うん」
彼は学者だった、とお祖父様は言った。
「楽しかったなあ」そうぽつりと呟いた声が、風に乗って消える。それは明るい響きを含んだ、めずらしく優しい声だったが、それは瞬きの間のこと。
「それより、これから広間でスマブラやらない?プロジェクター買った」お祖父様は、すぐにいつもと変わらない調子に戻って言った。
ドラルクは、お祖父様に友人のことを聞くタイミングをすっかり逃してしまった。そうなればもう、すばやく返事をするのみである。
「あ、いえ、わたしはジョンのパンケーキを焼かねばなりませんので」
考えてる場合ではない。ドラルクが自分に言い聞かせたその間、わずか0.03秒。フラグは全力で回避する。修学旅行の夜であっても、そんな無茶をするやつはいないだろう。
「そっか」
お祖父様はそれだけ言って、それ以上は勧めてこなかった。
「いつかお前も、お前を必要とする誰かに出会うよ」
帰り際に、お祖父様はドラルクにそう言ったが、その言葉の意味も、ドラルクにはピンとこなかった。
だから、信じあい、許しあう心を忘れないで──って、何の話だろう?
お祖父様が深紅の瞳を細めた理由も、まるで、何か眩しいものを見るように微笑んだ理由も、ドラルクにはいまいちよくわからない。
「はやく帰ってヤサシンクリードやろうっと」
ドラルクがその本当の意味を知るのは、もう少し後になってからの話である。
そして、お祖父様がそう言った数年後。
「任しときな。夜明けまでにカタつけてやるぜ!」
宵闇に浮かぶ城を見上げながら、銀の髪、青い瞳を夜の下で煌めかせ、赤いコートの男が不敵に笑うのだった。
2 notes
·
View notes
Text
ビブリオテーカに眠る春
ドラルクがロナルドくんと出会う少し前くらい。 御真祖様と秘密の部屋の昔話。
120パーセント捏造。「ビブリオテーカが告げる春」と対になるおはなしです。
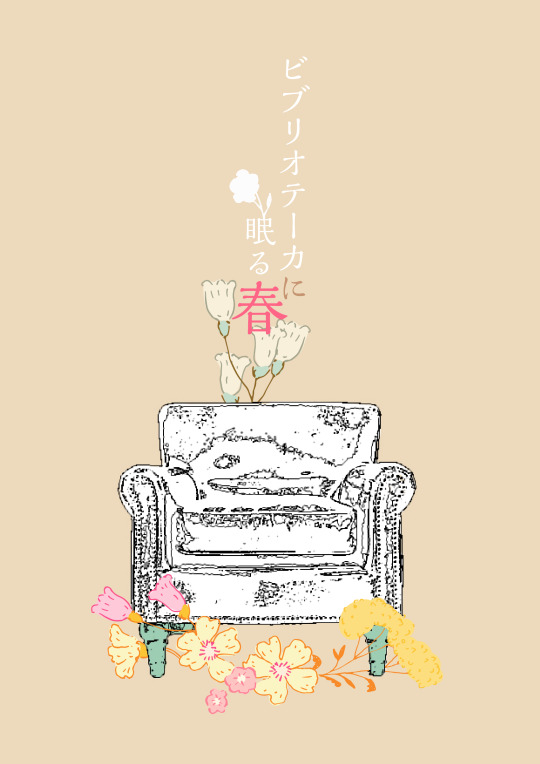
「ビブリオテーカに眠る春」
友は学者だった。
「この本!とっくの昔に廃版になったものだろう!?」
本棚から古い小説を取り出しながら、そう声を弾ませていた。それなりの量を揃えているはずなのに、友はこの図書室からすぐに、お目当ての本を探してきた。
「そういうの好き?」そう尋ねると、今度は勢いよく否定された。
「いや!決して好きというわけではない。決して!」
「じゃその本はあげる」
「えっ」
つい先ほどまで全力で否定していたのに、いいのか?!と輝いた友の瞳を今でも覚えている。
理由はなかった。ただ、流行っているというので購入をしていただけ。
「なんだ?何を見てる」
思わず目を細めてしまう。おかしかったからではない。あまりにもまぶしくて、きらきらしていたものだから。
「なんでもないよ」
きみが本当に楽しそうだったから、もっと見ていたくて。
ああ──なんてないものが、ふとしたことで輝き始める。その美しさ。理由を与えられれば、世界はこんなにも色鮮やかに変わる。意味を見出せなかったものでさえ──
いくつもの理由を拾い上げながら、きみの隣にいれたら──そう思った日のこと。
***
QSどこにおいたっけ。
懸賞に当たったのは、随分と前のことになる。とはいえ、それは昼の子の世界の話であり、我々のような夜のものには些細なことにしかならない。幾つの夜と朝を繰り返したかなどは、とうの昔に気にしなくなった。
しかし人間の生み出すものは、いつだって興味深く、そして面白い。それはいくら時が移ろっても、変わらないことである。
横浜スタジアムを貸し切って大画面でスマブラをするなどしたら、もっと面白くなるのではないだろうか。
扉を開く。秘密結社っぽくて素敵でしょ、というと友は「秘密結社はどうかと思うが」と呆れていた。この図書室は、友に贈ったものだ。辞退されたが──その割には、頻繁に本を探しに来ていた。だから、この部屋は彼のもの。そう決めた。
あまりにも辛気臭い場所だったので、せめて明るくしようと内装は白と金に塗り替えた。本は友が好きそうなものを、たくさん集めた。趣味で集めていたものもあったが、流行りのものならとりあえずなんでも買ってみた。
朝まで2人で読み耽って、難しい話をして、いいお酒を少しあけて──少しではなかったかもしれない。よくまあ、あれほど飲めたものだ。私は酔うことを知らなかったけれども──暖炉で薪がはじけるぱちぱちという音が恋しい。
いいや。QSはあとで探そう。
向かって右の椅子をひと撫でして思う。私の孫にも、友人ができると思う?
ドラルクは──今はひとりと1匹で、あの城に住んでいるけども、本当は毎日エンジョイ!というわけには、いっていないのだと思う。
時代の潮流の中で、仕方ないことではあったけど──幼いころから1人にしてしまいがちだった。人と付き合うことを厭うようで、その実、あの子はそれを諦めている。後ろめたい気持ちはないといえば、それは嘘になる。
しかし、我々はいつまでも彼の在り方に干渉してはいられない。ドラウスはなかなか、そう割り切れないようだが──いっそ誰かが、あの場所からあの子を連れ出してくれるといいのだけど。
ドラルクにもできるだろうか、きみのような友人が。たとえ立場が、生きる世界が違っても、笑えるような友人が。
今だってまだ、世界は眩く輝いている。それは、あの時、あの場所、あの瞬間にきみがくれたもの。きみが去っても、何も変わらない色彩。同じ景色を、わたしはあの子にも見せてあげたい。なぜって──感じ方はそれぞれかもしれないけど──きっと、楽しいはずだから。
サイドテーブルに笑いかけてみる。返事はないけれど、それでいい。
いつかあの子が、あの子を必要とする誰かに出会うその日が来ることを、祈っている。
ね、アルミニウス。ああ、本当に──
「楽しいね、友よ」
さあ、今日も張り切って掃除をしようか。
0 notes
