#花尾かくれ念仏洞
Text
iFontMaker - Supported Glyphs
Latin//Alphabet// ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789 !"“”#$%&'‘’()*+,-./:;<=>?@[\]^_`{|}~ Latin//Accent// ¡¢£€¤¥¦§¨©ª«¬®¯°±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ Latin//Extension 1// ĀāĂ㥹ĆćĈĉĊċČčĎďĐđĒēĔĕĖėĘęĚěĜĝĞğĠġĢģĤĥĦħĨĩĪīĬĭĮįİıIJijĴĵĶķĸĹĺĻļĽľĿŀŁłŃńŅņŇňʼnŊŋŌōŎŏŐőŒœŔŕŖŗŘřŚśŜŝŞşŠšŢţŤťŦŧŨũŪūŬŭŮůŰűŲųŴŵŶŷŸŹźŻżŽžſfffiflffifflſtst Latin//Extension 2// ƀƁƂƃƄƅƆƇƈƉƊƋƌƍƎƏƐƑƒƓƔƕƖƗƘƙƚƛƜƝƞƟƠơƢƣƤƥƦƧƨƩƪƫƬƭƮƯưƱƲƳƴƵƶƷƸƹƺƻƼƽƾƿǀǁǂǃDŽDždžLJLjljNJNjnjǍǎǏǐǑǒǓǔǕǖǗǘǙǚǛǜǝǞǟǠǡǢǣǤǥǦǧǨǩǪǫǬǭǮǯǰDZDzdzǴǵǶǷǸǹǺǻǼǽǾǿ Symbols//Web// –—‚„†‡‰‹›•…′″‾⁄℘ℑℜ™ℵ←↑→↓↔↵⇐⇑⇒⇓⇔∀∂∃∅∇∈∉∋∏∑−∗√∝∞∠∧∨∩∪∫∴∼≅≈≠≡≤≥⊂⊃⊄⊆⊇⊕⊗⊥⋅⌈⌉⌊⌋〈〉◊♠♣♥♦ Symbols//Dingbat// ✁✂✃✄✆✇✈✉✌✍✎✏✐✑✒✓✔✕✖✗✘✙✚✛✜✝✞✟✠✡✢✣✤✥✦✧✩✪✫✬✭✮✯✰✱✲✳✴✵✶✷✸✹✺✻✼✽✾✿❀❁❂❃❄❅❆❇❈❉❊❋❍❏❐❑❒❖❘❙❚❛❜❝❞❡❢❣❤❥❦❧❨❩❪❫❬❭❮❯❰❱❲❳❴❵❶❷❸❹❺❻❼❽❾❿➀➁➂➃➄➅➆➇➈➉➊➋➌➍➎➏➐➑➒➓➔➘➙➚➛➜➝➞➟➠➡➢➣➤➥➦➧➨➩➪➫➬➭➮➯➱➲➳➴➵➶➷➸➹➺➻➼➽➾ Japanese//かな// あいうえおかがきぎくぐけげこごさざしじすずせぜそぞただちぢつづてでとどなにぬねのはばぱひびぴふぶぷへべぺほぼぽまみむめもやゆよらりるれろわゐゑをんぁぃぅぇぉっゃゅょゎゔ゛゜ゝゞアイウエオカガキギクグケゲコゴサザシジスズセゼソゾタダチヂツヅテデトドナニヌネノハバパヒビピフブプヘベペホボポマミムメモヤユヨラリルレロワヰヱヲンァィゥェォッャュョヮヴヵヶヷヸヹヺヽヾ Japanese//小学一年// 一右雨円王音下火花貝学気九休玉金空月犬見五口校左三山子四糸字耳七車手十出女小上森人水正生青夕石赤千川先早草足村大男竹中虫町天田土二日入年白八百文木本名目立力林六 Japanese//小学二年// 引羽雲園遠何科夏家歌画回会海絵外角楽活間丸岩顔汽記帰弓牛魚京強教近兄形計元言原戸古午後語工公広交光考行高黄合谷国黒今才細作算止市矢姉思紙寺自時室社弱首秋週春書少場色食心新親図数西声星晴切雪船線前組走多太体台地池知茶昼長鳥朝直通弟店点電刀冬当東答頭同道読内南肉馬売買麦半番父風分聞米歩母方北毎妹万明鳴毛門夜野友用曜来里理話 Japanese//小学三年// 悪安暗医委意育員院飲運泳駅央横屋温化荷開界階寒感漢館岸起期客究急級宮球去橋業曲局銀区苦具君係軽血決研県庫湖向幸港号根祭皿仕死使始指歯詩次事持式実写者主守取酒受州拾終習集住重宿所暑助昭消商章勝乗植申身神真深進世整昔全相送想息速族他打対待代第題炭短談着注柱丁帳調追定庭笛鉄転都度投豆島湯登等動童農波配倍箱畑発反坂板皮悲美鼻筆氷表秒病品負部服福物平返勉放味命面問役薬由油有遊予羊洋葉陽様落流旅両緑礼列練路和 Japanese//小学四年// 愛案以衣位囲胃印英栄塩億加果貨課芽改械害街各覚完官管関観願希季紀喜旗器機議求泣救給挙漁共協鏡競極訓軍郡径型景芸欠結建健験固功好候航康告差菜最材昨札刷殺察参産散残士氏史司試児治辞失借種周祝順初松笑唱焼象照賞臣信成省清静席積折節説浅戦選然争倉巣束側続卒孫帯隊達単置仲貯兆腸低底停的典伝徒努灯堂働特得毒熱念敗梅博飯飛費必票標不夫付府副粉兵別辺変便包法望牧末満未脈民無約勇要養浴利陸良料量輪類令冷例歴連老労録 Japanese//小学五〜六年// 圧移因永営衛易益液演応往桜恩可仮価河過賀快解格確額刊幹慣眼基寄規技義逆久旧居許境均禁句群経潔件券険検限現減故個護効厚耕鉱構興講混査再災妻採際在財罪雑酸賛支志枝師資飼示似識質舎謝授修述術準序招承証条状常情織職制性政勢精製税責績接設舌絶銭祖素総造像増則測属率損退貸態団断築張提程適敵統銅導徳独任燃能破犯判版比肥非備俵評貧布婦富武復複仏編弁保墓報豊防貿暴務夢迷綿輸余預容略留領異遺域宇映延沿我灰拡革閣割株干巻看簡危机貴揮疑吸供胸郷勤筋系敬警劇激穴絹権憲源厳己呼誤后孝皇紅降鋼刻穀骨困砂座済裁策冊蚕至私姿視詞誌磁射捨尺若樹収宗就衆従縦縮熟純処署諸除将傷障城蒸針仁垂推寸盛聖誠宣専泉洗染善奏窓創装層操蔵臓存尊宅担探誕段暖値宙忠著庁頂潮賃痛展討党糖届難乳認納脳派拝背肺俳班晩否批秘腹奮並陛閉片補暮宝訪亡忘棒枚幕密盟模訳郵優幼欲翌乱卵覧裏律臨朗論 Japanese//中学// 亜哀挨曖扱宛嵐依威為畏尉萎偉椅彙違維慰緯壱逸芋咽姻淫陰隠韻唄鬱畝浦詠影鋭疫悦越謁閲炎怨宴援煙猿鉛縁艶汚凹押旺欧殴翁奥憶臆虞乙俺卸穏佳苛架華菓渦嫁暇禍靴寡箇稼蚊牙瓦雅餓介戒怪拐悔皆塊楷潰壊懐諧劾崖涯慨蓋該概骸垣柿核殻郭較隔獲嚇穫岳顎掛括喝渇葛滑褐轄且釜鎌刈甘汗缶肝冠陥乾勘患貫喚堪換敢棺款閑勧寛歓監緩憾還環韓艦鑑含玩頑企伎忌奇祈軌既飢鬼亀幾棋棄毀畿輝騎宜偽欺儀戯擬犠菊吉喫詰却脚虐及丘朽臼糾嗅窮巨拒拠虚距御凶叫狂享況峡挟狭恐恭脅矯響驚仰暁凝巾斤菌琴僅緊錦謹襟吟駆惧愚偶遇隅串屈掘窟繰勲薫刑茎契恵啓掲渓蛍傾携継詣慶憬稽憩鶏迎鯨隙撃桁傑肩倹兼剣拳軒圏堅嫌献遣賢謙鍵繭顕懸幻玄弦舷股虎孤弧枯雇誇鼓錮顧互呉娯悟碁勾孔巧甲江坑抗攻更拘肯侯恒洪荒郊貢控梗喉慌硬絞項溝綱酵稿衡購乞拷剛傲豪克酷獄駒込頃昆恨婚痕紺魂墾懇沙唆詐鎖挫采砕宰栽彩斎債催塞歳載剤削柵索酢搾錯咲刹拶撮擦桟惨傘斬暫旨伺刺祉肢施恣脂紫嗣雌摯賜諮侍慈餌璽軸叱疾執湿嫉漆芝赦斜煮遮邪蛇酌釈爵寂朱狩殊珠腫趣寿呪需儒囚舟秀臭袖羞愁酬醜蹴襲汁充柔渋銃獣叔淑粛塾俊瞬旬巡盾准殉循潤遵庶緒如叙徐升召匠床抄肖尚昇沼宵症祥称渉紹訟掌晶焦硝粧詔奨詳彰憧衝償礁鐘丈冗浄剰畳壌嬢錠譲醸拭殖飾触嘱辱尻伸芯辛侵津唇娠振浸紳診寝慎審震薪刃尽迅甚陣尋腎須吹炊帥粋衰酔遂睡穂随髄枢崇据杉裾瀬是姓征斉牲凄逝婿誓請醒斥析脊隻惜戚跡籍拙窃摂仙占扇栓旋煎羨腺詮践箋潜遷薦繊鮮禅漸膳繕狙阻租措粗疎訴塑遡礎双壮荘捜挿桑掃曹曽爽喪痩葬僧遭槽踪燥霜騒藻憎贈即促捉俗賊遜汰妥唾堕惰駄耐怠胎泰堆袋逮替滞戴滝択沢卓拓託濯諾濁但脱奪棚誰丹旦胆淡嘆端綻鍛弾壇恥致遅痴稚緻畜逐蓄秩窒嫡抽衷酎鋳駐弔挑彫眺釣貼超跳徴嘲澄聴懲勅捗沈珍朕陳鎮椎墜塚漬坪爪鶴呈廷抵邸亭貞帝訂逓偵堤艇締諦泥摘滴溺迭哲徹撤添塡殿斗吐妬途渡塗賭奴怒到逃倒凍唐桃透悼盗陶塔搭棟痘筒稲踏謄藤闘騰洞胴瞳峠匿督篤凸突屯豚頓貪鈍曇丼那謎鍋軟尼弐匂虹尿妊忍寧捻粘悩濃把覇婆罵杯排廃輩培陪媒賠伯拍泊迫剝舶薄漠縛爆箸肌鉢髪伐抜罰閥氾帆汎伴畔般販斑搬煩頒範繁藩蛮盤妃彼披卑疲被扉碑罷避尾眉微膝肘匹泌姫漂苗描猫浜賓頻敏瓶扶怖附訃赴浮符普腐敷膚賦譜侮舞封伏幅覆払沸紛雰噴墳憤丙併柄塀幣弊蔽餅壁璧癖蔑偏遍哺捕舗募慕簿芳邦奉抱泡胞俸倣峰砲崩蜂飽褒縫乏忙坊妨房肪某冒��紡傍帽貌膨謀頰朴睦僕墨撲没勃堀奔翻凡盆麻摩磨魔昧埋膜枕又抹慢漫魅岬蜜妙眠矛霧娘冥銘滅免麺茂妄盲耗猛網黙紋冶弥厄躍闇喩愉諭癒唯幽悠湧猶裕雄誘憂融与誉妖庸揚揺溶腰瘍踊窯擁謡抑沃翼拉裸羅雷頼絡酪辣濫藍欄吏痢履璃離慄柳竜粒隆硫侶虜慮了涼猟陵僚寮療瞭糧厘倫隣瑠涙累塁励戻鈴零霊隷齢麗暦劣烈裂恋廉錬呂炉賂露弄郎浪廊楼漏籠麓賄脇惑枠湾腕 Japanese//記号// ・ー~、。〃〄々〆〇〈〉《》「」『』【】〒〓〔〕〖〗〘〙〜〝〞〟〠〡〢〣〤〥〦〧〨〩〰〳〴〵〶 Greek & Coptic//Standard// ʹ͵ͺͻͼͽ;΄΅Ά·ΈΉΊΌΎΏΐΑΒΓΔΕΖΗΘΙΚΛΜΝΞΟΠΡΣΤΥΦΧΨΩΪΫάέήίΰαβγδεζηθικλμνξοπρςστυφχψωϊϋόύώϐϑϒϓϔϕϖϚϜϞϠϢϣϤϥϦϧϨϩϪϫϬϭϮϯϰϱϲϳϴϵ϶ϷϸϹϺϻϼϽϾϿ Cyrillic//Standard// ЀЁЂЃЄЅІЇЈЉЊЋЌЍЎЏАБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯабвгдежзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюяѐёђѓєѕіїјљњћќѝўџѢѣѤѥѦѧѨѩѪѫѬѭѰѱѲѳѴѵѶѷѸѹҌҍҐґҒғҖҗҘҙҚқҜҝҠҡҢңҤҥҪҫҬҭҮүҰұҲҳҴҵҶҷҸҹҺһҼҽҾҿӀӁӂӇӈӏӐӑӒӓӔӕӖӗӘәӚӛӜӝӞӟӠӡӢӣӤӥӦӧӨөӪӫӬӭӮӯӰӱӲӳӴӵӶӷӸӹӾӿ Thai//Standard// กขฃคฅฆงจฉชซฌญฎฏฐฑฒณดตถทธนบปผฝพฟภมยรฤลฦวศษสหฬอฮฯะัาำิีึืฺุู฿เแโใไๅๆ็่้๊๋์ํ๎๏๐๑๒๓๔๕๖๗๘๙๚๛
see also How to Edit a Glyph that is not listed on iFontMaker
#FAQ#ifontmaker2#Symbols#Dingbat#Cyrillic#Greek#Coptic#thai#character set#character sets#list#language
5 notes
·
View notes
Text
ミニ講座 第14回 「ぼろぼろの草子」
暮露と文学 其の三!
「ぼろぼろの草子」で暮露の実体を探る!
今回もお二方の論文を参考にさせていただきました。ですのでほとんど論文の解説です。恋田知子氏の本には貴重な奈良絵本の写真まで載ってます。論文を公開してくださっている恋田氏、保坂氏の論文を残して下さった山田氏にまずは感謝です。
「17世紀における虚無僧の生成」 保坂裕興
「ぼろぼろの草子」考 宗論文芸としての意義 恋田知子
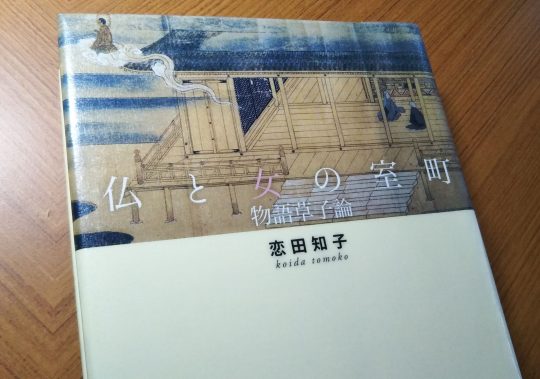
因に近年、主に中世史研究の立場から暮露の実態解明の一助として色々な研究者から言及なされている。
細川涼一著「ぼろぼろ(暮露)」『中世の身分制と非人』1994年
原田正樹著「放下僧・暮露に見る中世禅宗と民衆」『日本中世の禅宗と社会』1998年
黒田日出男著「ぼろぼろ(暮露)の画像と『一遍聖絵』絵画史料の可能性を求めて」1991年
さて本題!
【ぼろぼろの草子】(1232年頃)とは、
明恵高弁(みょうえこうべん)(鎌倉時代前期の華厳宗の僧。京都栂尾 とがのおの高山寺開山)が書いたとされる。1232年没した遺言によって披見(ひけん)が禁止されていて1338年にたまたま発見されたといわれている。
ネズミが袋を齧ったためとも言われています。ちょうど「ぼろぼろの草子」が書かれてから100年後に発見されたんですね。今からで言うと、明治時代のものが発見されたような感じですね。
「読むな」と書いたものを死後残すのは一体何の為なのでしょうか??? それとも生きてるうちに誰かに読まれたら困るから、書いておいて忘れて死んじゃったとか???
恋田氏によると、現在のところ古写本はなく、すべて近世以降のものだそうですが、写本、版本は大学の図書館、国会図書館、個人蔵含め、何冊かあり、題名も「暮露暮露艸紙」「古今残葉」「柿袋」「空花論」「観音化現物語」「明恵上人革袋」などまちまちです。
尚、蓮華坊は保坂氏、蓮花坊は恋田氏と、漢字が違います。
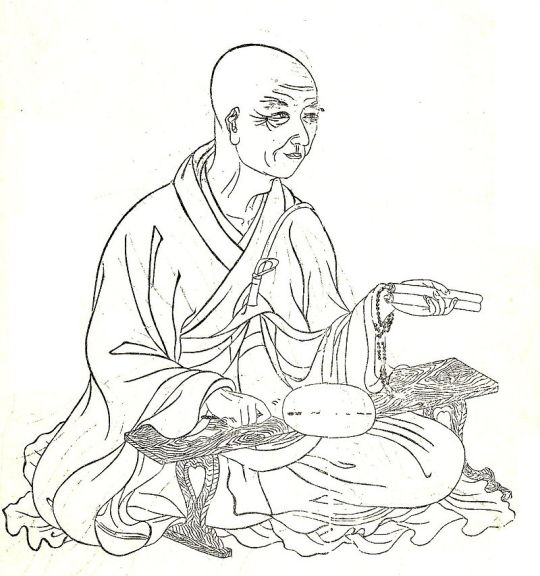
(明恵上人)wikipediaより
物語は、都の油売女が、「見めあしき事たとゆべきなき」虚空坊と、「たまのごときなる」蓮華坊という対照的な二男児を生んだが、母没後に破産し、兄虚空坊は暮露に、弟蓮華坊は念仏者になり諸国を遊行行脚した後、浄土宗と天台・禅系統の教義に関する問答を交わし消え去るという物語で、兄弟は大日、阿弥陀の化身であったと結ぼれるものである。内容の大半は問答形式で暮露が念仏者を論破していく様が描かれ、最後の部分でそれは「玄妙殊勝(優れている)の法門」であり、暮露の本地は「大日如来」であると結ばれている。
虚空坊が有様たとふべき事なし。かみはそらに生あがり、色くろく、たけたかく、誠に夜叉鬼王のごとく、悪人をころすこと数をしらず。(中略)彼の虚空坊の長さは七尺八寸。力は六十五人が力、絵かき紙衣に黒袴きて、一尺八寸の打刀をさし、ひるまきの (1) 八角棒を横たへ、一尺五寸のたかあしだはきけり。同様なる暮露々々三十人引具(ひきぐす)して諸国を行脚するに、見聞く人惶(おそ)れて、かりそめにもゆきあはんといふものなし。しかれどもひがごと (2) せず、夜はふすまを引かつぎ座禅するなり。東西南北をのこさず一見し、五逆十悪三宝誹謗のものをみては我敵よと心得て打殺しに捨てにけり。善をなすものをば是非をいはず又けんどん (3)のものには布施の心を示し、瞋恚(しんい・怒り)のものには慈悲の心をふくめ、愚癡(ぐち)のものには智慧をさづけ、驕慢者(きょうまん)には恭敬の心を教へ、放逸(なまけること。 仏道に励まないこと)の者には摂心(散乱する心を一つに摂むる)をしらしめ、懈怠(ケタイ)の者には精進戒を授け、破戒の者には持戒を授く。
(七尺八寸は236センチ!デカい!そして高下駄一尺五寸 45センチの高足駄はいくらなんでも高すぎるだろう!とつっこみたくなります。)
【ひるまき】柄や鞘の補強・装飾目的で表面に螺旋状の模様が蛭が幹ついたようにみえることから。平安時代から幕末まで。
【ひがごと】道理に合わないこと
【けんどん】ケチ、思いやりが無い
五逆十悪三宝誹誘→とにかくものすごい悪いヤツで仏教心のない人のこと。
【五逆】五つの最も重い罪
【十悪五逆】ありとあらゆる悪行
【三宝】とは、仏教における「仏・法・僧」と呼ばれる3つの宝物を指し、仏陀と法と僧のこと。この三宝に帰依し、その上で授戒することで正式に仏教徒とされる。

恋田知子著「仏と女の室町・物語草子論」より
「観音化現物語」1678年刊 柳沢昌紀氏蔵
(こんな貴重な絵が存在したとはこれを見つけた時は驚きました。暮露、そのままの通りの絵じゃん!ひるまきの八角棒振り回して念仏坊主を追いかけてる!)

(一遍上人聖絵)国立国会図書館より
こちらも暮露。
虚空坊の風体は、黒田日出男氏が指摘された『一遍聖絵』等に見える暮露の姿と一致し、「五逆十悪三宝誹誘の者をみてはわれ敵よと心得て打殺し捨にけり」とする様は、「徒然草」(1330)第百十五段等にみえる放逸無慚の暮露の様相とも重なる。
<虚空坊と蓮花坊の宗論>
兄弟は諸国を遊行した後、三条東洞院で再会する。
鉦を首にかけ、念仏を唱える蓮花坊に対し、虚空坊は「愚療の念仏申がにくさに打殺んと思なり」と述べ、「大小乗は行ずるものの心によれり」、「実の浄土といふは首をふり足を踊り、顛倒するをばいわず。心念無所を浄土といふなり」と蓮花坊の念仏を批判する。これに対して蓮花坊は、虚空坊の主張を認めるものの、「髪は空へ生あがり、紙衣に画かき黒袴に打刀高履ひる巻の棒、是何仏弟子の形かや。殊女つれて簾中(れんちゅう・貴婦人)と名付寵様更に心得ず」と、仏法者としてふさわしからぬ風体や妻を伴うことについてただすのである。
このような二人の争論には、顕密側からなされる融通念仏者・禅宗系下級宗教者に対する批判との、方法上の類似が認められる。本作品における宗論は、中世前期に旧仏教側から新仏教に対して盛んに行われた批判を前提とした上で、その批判の論点・内容を巧みに取り込み、虚空坊ら新仏教の下級宗教者たちの問答にすりかえるという構造になっているのである。実際的な記録としてではなく、いわば擬似的に仮構された宗論とすることができよう。
このように「ぼろぼろの草子」は、虚空坊と蓮花坊との宗論という形をかりで、中世前期に盛んになされた旧仏教側の批判とそれに対する反論を擬似的になしてみせたものと見なすことができるだろう。(恋田)
虚空坊・暮露の実体 → <三学>を実践修行する仏教者
三学とは、仏道の修行者が必ず修めなくてはならない最も基本的な修行で、戒学・定学・慧学の三をいう。戒学は、悪を止め、善を修し、戒律を守って規律ある生活を保つこと。定学は、禅定を修して心の散乱を鎮め、心を落ち着かせること。慧学は、その戒学と定学とに基づいて真理を知見し、智慧を獲得することを意味する。
<仏教思想>
御邊は何衆の人ぞ。答云、是大圓覺宗のものなり。
→『円覚経』の宗門=「圓覺宗」の者、つまり唯心論の華厳宗系仏教者であることを表明。この点はこのテクストが華厳宗の明恵に寄託されたこと、本地(本来の姿)が大日如来(毘盧遮那仏)とされたことにも合致している。
因に、
”ぼろ””ぼろぼろ”の語源は彼らが一字金輪呪(いちじきんりんじゅ)「ボロン」を連続して誦(しょう)したことによるという。(「七十一番職人歌合・新日本古典文学大系」より)
【一字金輪】…仏様のトップグループを仏頂尊ぶっちょうそんといいます。そのトップグループの頂点に立つのが一字金輪=大日如来です。
深い瞑想の境地に至った如来が説いた一字の真言ボロン(भ्रूं [bhrūṃ])を神格化したものである。
ご真言 一字金輪呪 (ナマサマンダボダナン ボロン)
問云、圓覺宗とは何を行するや。答云、行する事あらば何の圓覺宗とかいはん。圓覺といふは邊際もなし、只我心即如此(かくのごとく)といへり
→またここでは「行」を否定しているが、明恵らは、戒・定・慧の<三学>を堅持したトータルな<行>を行い、定学だけが念仏や坐禅として自立した「行」を採らなかった。(保坂)
「師もなく不思量にして不進不退」と述べている点からも
異類異形の巷間の禅僧として、放下や自然居士らに共通するものと把握できる。(恋田)
【不思量】一切の思量分別を停止すること。考えることの徹底した否定。

(因に私が描いた兄・虚空坊と、弟・蓮華坊のイラスト)
『ぼろぼろの草子』は虚空坊と蓮花坊との宗論という形をかりて、中世前期に盛んになされた旧仏教側の批判と、それに対する反論を擬似的になしてみせたもの、すなわち宗論文芸とみなすことが出来る。(恋田)
「一遍聖絵」の、徳江氏、黒田氏の指摘によると、異類異形の巷間の禅僧として放下や自然居士に共通するものとされていますが、明恵上人による「ぼろぼろの草子」ではまた禅宗ではなく華厳宗であり、少々混乱しますが、これは宗論文芸ということで落ち着きたいと思います。
ともかく、大日如来派と阿弥陀如来派に別れたわけですね。
元は同じなのにね〜。
そして暮露は江戸時代にはいると自然に消滅していきます。
ああ、失われた職業というやつです。
今巷で虚無僧なんかやってますと、一体自分はどっちなんだろうと思います。
完全に過去の形態なんだけれど、一度無くなったものだから、新しいと言えば新しい。そして既存の仏教団体に属していない。どうしても虚無僧というより、暮露のような気分になるんです。
それが私の強い暮露愛につながるのでしょうか。
そして、
この現代にも、禅宗を否定する宗派が、尺八を吹いている虚無僧を攻撃して来るわけです。
噓みたいですがホントの話。
元をたどれば同じなのにね〜。
これから虚無僧する皆さん、彼らは暮露みたく、いきなり打刀で切りつけては来ませんが、論争でやってきますから気を付けて!
逃げるが勝ちですよ🎵
...
0 notes
Text
老いてこそ V
花鳥誌2019年10月号より転載

句誌「太白」代表
吉岡 乱水
浦上崩れ
二十六聖人像の並ぶ長崎の西坂の丘。太白一千号出版記念会の折、坊城俊樹先生、田鶴の水田むつみ主宰を迎え、太白会員揃って、この丘を吟行した。
二十六聖人とは、一五九七年二月五日豊臣秀吉の命令により長崎に連行され磔刑に処せられたカトリック信者たちである。
吟行の折、五島から訪れた四五人のシスターたちが磔像にひざまづいていた。世界遺産になるとのニュースにこの地を訪ねずにはおれなかったのだ。
シスターの春愁ひては磔像へ 坊城俊樹
いち早く気付かれた先生。また志津子さんも
磔像に跪坐のシスター風薫る 吉田志津子
昔、聖徒たちは、京都に於いて耳を削がれ、市中引き回しの上、長崎で処刑されることになった。中に十二歳の少年がいた。そのルトビコ茨木を哀れみ、キリシタンの教えを捨てれば助けると持ちかけたが、この世の束の間の生と永遠の命は取り変えられないとルトビコは従容として処刑に付いたという。
磔像にをさなご二人鳥雲に 松本洋子
二人とは、中国人を父とする十三歳のアントニオとの二人を指す。西坂の丘は宣教師のみならず信徒六〇〇人以上の処刑の禍々しい、いや神聖な丘だ。
江戸幕府になっても、鎖国とカトリックの禁教は、国家統制の政策として踏襲された。島原の乱を境にさらにこの政策は強められ、幾多の厳しい取り締まりが展開された。「崩れ」である。「崩れ」とは、「鎖国」体制下の江戸幕府の潜伏キリシタンの一斉検挙のことで、「浦上崩れ」は殊によく知られている。
禁教令偲ぶ遺構にある秋思 高比良映子
浦上以外にも大村や天草の崩れもあった。
八坪の牢獄なりし木の実落つ 松尾みちこ
これは大村市、鈴田牢獄を詠んだものである。
キリシタン崩れの山の時雨かな 松尾みちこ
山の中腹にある洞窟に潜んでいた信者が一斉検挙された。その遺跡を詠んだ句である。一六五七年(明暦三年)の調査、その翌万治元年の再調査の結果の大量捕縛である。「郡崩れ」という。
一八〇五年(文化二年)天草島内での五千人に及ぶ一斉検挙、いわゆる天草崩れもある。
転ぶとは棄教すること絵踏帖 福田洋子
「絵踏み」をさせ、踏まなければ「転び」つまり棄教と転向を迫る。今も擦り減った板踏絵が遺されている。血や涙がどれほど流されたかを偲ばせる。
ことに長崎浦上の崩れは、規模が大きい。
浦上一番崩れ、一七九〇年(寛政二年)仏像建立の費用負担拒否からくるキリシタンの一斉捜
査。
浦上二番崩れ、一八二四年(天保十三年)密告による逮捕事件、証拠不十分で釈放。
浦上三番崩れ、一八五六年(安政三年)ただし、この件はキリシタンの教えと知らなかったことによって生じた「異宗事件」として処理され、キリシタンの存在を公式には認めなかった。
一八六七年(慶応三年)キリスト教を信仰した浦上村の民が大浦天主堂に赴き、プチジャン神父に浦上のキリスト教信者たることを証し、多くの潜伏キリシタンの存在が明るみに出て、江戸幕府の指令により大量に捕縛された。引き続き明治政府もキリスト教禁止政策を引き継ぎ、厳しい処分案を練ったが、外国の反発を懸念、各藩への預託案を採用した。
三重・広島・山口・岡山・鳥取・高知・愛知・島根・鹿児島・名東(徳島県)・兵庫・香川・和歌山・石川・奈良・愛媛などに分散預託。苦難の長道行であった。
政府は一八七三年キリシタン禁制の高���を撤廃帰村させること���なる。帰村数一九三〇人、家有りのもの一一六四人、家無し七六六人。四〇パーセントほどが家無し状態であった。(浦上村調査に拠る)
一八七九年(明治十二年)、浦上の小聖堂を築いた。大浦天主堂から神父を招き、一八八〇年(明治十三年)庄屋高谷家の跡地(キリシタン弾圧時代の信徒が絵踏みを強いられた因縁の場所)を買い取り、仮聖堂を建て、一八九五年(明治二十八年)起工、一九二五年(大正十四年)正面ドームまでやっと完成。それから僅か二十年後、原爆で天主堂も壊滅した。
浦上は原爆投下の中心地、どれほどの信徒が犠牲になったことか。これを比喩的に浦上五番崩れと言うが、そんなことで済ませられることではない。
佇めば身も凍つるなり聖廃墟 吉岡乱水
浦上の想像も絶する悲劇の歴史を想い、原爆に崩れ落ち今なお丘下に半ば埋もれた旧教会のドームの廃墟に暗澹と首を垂れた。
今の長崎は、この大きな悲劇の堆積の上に危うく、存在している。スマホに溺れ、飽食にかまけての今、歴史を忘れ、目をつぶり踊る世情を憂えている。
0 notes
Text
石
先日友人が、宮古の海岸で拾ったという小さな石を土産にくれた。四条イノダコーヒの奥、正装の老人が集まる赤く暗い席の片隅で。それは緑がかった不思議な灰色をしていた。これな、撫でてると落ち着くねん、と彼女。ただの石ころと言ってしまえばそれまでだが、今までもらった土産のなかでは一番嬉しかった。話を聞けば、震災の爪痕がまだ生々しく残る町で人々はみな明るかったとのこと。居酒屋「栄子」の栄子さんは店内の襖を指さし、腰あたりの高さに引かれた茶色い線をなぞりながら言ったそうだ――これ、つなみ。全てを楽しげに語る彼女はみずみずしい記憶そのものだった。ライブペイントの仕事で呼ばれたらしいが、それ以外も満喫できたようだ。海岸は今回もらったような石で埋め尽くされていたという。海と浜がひとつづきになって、春の太陽につぶつぶときらめく景色が目に浮かんだ。もらった石は仕事場のデスクの上に置いていて、気持ちを鎮めたいときにそっと触れている。ひんやりつるつるしていて、凪いだ海が指先から、時化た胸のなかにそっと入ってくる。そうしてぼんやり石を見つめていた時、それ何ですか? と隣席の同僚に聞かれた。友人の土産ですよと返したら、いい人ですね、と一言。そうなんです。いい石をくれる友人はなかなかいないのでとてもありがたい。ちなみに彼女の苗字には石の字が入っている。その他にも石が名前に付く友人は三人いて、みな私にいい思い出をくれる。やはり石と友人は大切にしよう。
*
石といえば、私は小学生時代はちょっとした鉱物マニアで、いつのころからか近所の地学会館に出入りするようになっていた。そしてそこで売られている奇石をなけなしの小遣いで買ったり、公園で拾った珍しい柄の石を持ち帰ったりしては家で眺めるのが好きだった。一年ほどかけて黄鉄鉱やヘマタイト、水晶、黒曜石、方解石、蛍石、トルコ石、テレビ石、砂漠の薔薇などを手に入れ、触りながらその美しさにうっとりしていた。アンモナイトや縞瑪瑙もあった。砂岩や珪石、桜石、石英、大理石など目立たないものも持っていた。ところが確か小学六年の時である。夏休みの自由研究の発表で、集めた石を教室の後ろに展示したところ、すぐに誰かに盗まれてしまった。綺麗なものばかりがなくなっていた。当時のショックと悲しみは今でも忘れがたい。最後まで誰かが名乗り出ることも目撃者もないまま事件は忘れ去られた。私は誰が盗ったかわかっていたので悔しかった。結局、その犯人は後に別件で社会的制裁を受けることとなったため、それで恨みは晴れた。一時は頑張っても無駄だと悟った私に代わり、今やそいつが賽の河原のシシュフォスというわけである。事件以降、私は鉱物に対する熱意を失った。ただ、本当の鉱物マニアにならなくてよかったなとも思う。薄暗い研究室で顕微鏡を覗き続けていたら、私の場合は、今に輪をかけてひどい石頭になっていただろう。それでも未だに石には反応してしまうのだが。
*
なぜ人は石を集めるのだろうか。その心理の根底には、石への無意識な信仰があるように思える。人は原始、巨岩を崇拝した。そこにどこからともなく神が降りてくるのだという。依り代となった岩は、日本では磐座(いわくら)と呼ばれる。神山や三輪山の頂には注連縄を張られた岩があり、山自体が信仰の対象となっている。京都の岩倉には、山住神社という岩そのものを祀った社があり、当地名の発祥となった。アボリジニのウルルやイギリスのストーンヘンジなどもそうで、神聖な地とみなされている。私は、崇拝といえば人を象ったものや社殿など偶像へのそれがまず真っ先に思い浮かぶが、そういった技術以前の対象は人そのものを含む自然物の他になかっただろう(人の手による簡素な道具をそこに加えるとすれば、時代がやや下ってからのことかと思う)。確かに、背丈を超えるような大きさの岩には存在感がある。いや、「感」などという曖昧なものではなく、厳然たる存在がそこに鎮座する。その重みには、物理的な理由以外の動かしがたさがある。その変化は、人間のライフタイムでは測り知ることができない。何があっても頑なその姿に、人は父祖のような威厳を見たのではないか。そしてそこに自らの理想を重ね合わせたのではないか。古代人の考えは推測するよりほかないものの、じっさい岩には人を引き付ける力があり、そんな岩のかけらは、釈迦の遺骨を刻んだ仏舎利のように、物神のひとつになり得る。小石をポケットに入れる行為は、自分の分身たる守り神に守ってもらうことなのだろう。時々取り出しては、変わることのない自分の礎を思い出すために。
*
ある時、鴨川の源流を探りたいと思って、愛車のシクロクロスを走らせて友人と雲ケ畑へと入った。岩屋山のふもとから祖父谷川を遡上し、舗装がなくなったので自転車を置いて徒歩で登る。その途上、狭まる川の向こうの崖に小さな滝を発見したので、真夏の登山で体が火照っていた私たちは、水を浴びようと石を渡り、対岸にたどり着いた。滝の下は踊り場のようになっていて、大人ふたりが立てるほどの広さがあった。薄っぺらいスニーカーでなんとかよじ登り、じゃぶじゃぶと頭から水をかぶって喉を癒す。その時、ふと目の端に何かを感じ私は横を向い���。すると苔むした岩肌には顔ほどの大きさの穴がぽっかりと開いていた。穴の奥は暗く、何かが潜んでいるような気がした。ちょっと怖いな、と友人は言った。私も、なぜかずっとは見ていられなかった。しばらくして、この内部の闇を静めるためにできるのは、洞の中に小石を置くことだと思った。言語以前の狂気を発し続ける、おどろおどろしいその口に舌を与え、いっそ祠にしてしまおう。そうすれば、自分に相対する無に意味が生まれ、祈りの所在がはっきりするだろうと考えたのだ。おそるおそる小さな丸石を置き、私たちはそこを後にした。そうしてところどころから湧く沢に源流を見定めたのち、迷いつつさらに北上していると知らぬ間に北山最高峰の桟敷ヶ岳に到達していた。山頂には惟喬親王がそこから都を眺めたと伝えられる岩がある。近くにあったベンチで小憩し、大反響するやまびこを楽しんでから、次の道を決めあぐねていたところ、京北側から登ってきたという人に出会った。地図を持っていないことを話すと、自殺行為ですねと言われ、丁寧に帰り道を教えてくれた。あとでわかったことだが、その先の京北へと続く道の名は石仏峠というそうだ。一度消失し近年になって再発見された幻の峠だという。考えてみれば、彼はひょっとすると何かの化身で、私たちが祀ったのは石仏のひとつだったのかもしれない。そして石を洞に祀っていなかったら彼の言う通りになっていたのかもしれない。空想としては面白いが、少しぞっとした。果たしてあの石はまだあるのだろうか。
*
試験勉強に倦み疲れ、誰の考えも援用せずに美について思案していたら、龍安寺の石庭が頭のなかに現れた。あの庭の魅力は石の配置で、どの角度から見てもある石が他の石を隠してしまい、一度に全十五個の石は見えないようになっている。また、短辺にある塀が手前から奥に向かって低くなるという、遠近法の錯視を利用した作庭がなされており、庭の形は白銀比の長方形になっている。作庭者が不明のため、石の配置の意味するものについては諸説ある。虎の子渡しの故事にちなむとか、禅の精神を示すとか、どこからどう飛躍したのかという感じだが、宇宙を表すとかいわれている。初めは私も宇宙なんぞ言いすぎだろうと笑っていた。しかし、考えを巡らせるほどに実はそれが解釈として正しいのではないかと思い始めた。というのも、もしその意図が本当であれば、一見ランダムながらごく適切に配置された石の群れは、あるがままにあるこの宇宙の一瞬とそのまま照応するからだ。私たちは何かしらの必然性があって存在しており、降り積もってゆく数々の「今」には確かな理由があるのだ。さらに、作庭者が不明であることにも宇宙発生の秘密とどこか共通するところがある。そうすると石庭とはいわば、四次元風景を切り取った三次元の写真ということになるのではないか。こんなことを言いながらも当時は石庭を画像でしか見たことがなかった。この仮説を確かめるべく、暇な私は龍安寺に向かった。鏡容池を囲む見事な回遊式庭園を過ぎて方丈に入り、いよいよ庭へ。観光客や修学旅行生でごった返すなか、なんとかぎゅうぎゅうに詰めて縁側の端に座る。人の声がうるさい。座禅や観想などできるわけがなかった。喧噪の中でぼんやりと見た石庭は石庭であった。けっこう広かった。ふーん、という感じで私はじっとしていた。試しに目をつぶってみると、なんとなく自分が見えない石のひとつになったような気がした。小一時間いて感じたのはたったそれだけであったが、それこそが宇宙なのだと自分を納得させて帰った。おそらくそれはあながち間違いではなかっただろう。常に、宇宙は容易く、世界は難しいのだ。
*
上賀茂神社から少し下ったところにある大田神社には、カキツバタで有名な沼(沢)がある。尾形光琳の絵の題材にもなったといわれる場所だ。ここの水は雲ケ畑から地下を通って湧いていて枯れることがないとか、水の中に踏み入れると足が腐るとかいう伝説がある。紫の花が一斉に咲く毎年五月には多くの人が見物に押し寄せるが、それ以外の時期は白茶けた地味な水辺で、あまり人もいない。私は秋から冬ごろにこの沼を見るのが好きだ。こぢんまりとした侘しさがそこにはある。大学生の時は自転車で社家町を抜けてよく訪れていた。楕円形でごく浅い沼の中央には、土が盛り上がってできた島がぽつんとあり、草木に覆われている。山から注がれる水の流入口には「蛇の枕」と呼ばれる石がちょこんと顔を覗かせている。昔はこの石を叩いて蛇を怒らせ、雨乞いの儀式をしていたという。このあいだ、その島のことを考えていると、それが何やら亀のように思えてきた。水から浮かび上がって甲羅の天日干しをしている。頭はどこかわからないが、尾の部分には水の流れがあり、そこには蛇がいる――。ここまで考えて私はひらめいた。とするならば、この構造はまさしく玄武の姿そのものだと言える。玄武とは亀の甲羅と頭を持ち、尻尾が蛇になっている神獣のことで、都の北方を守護しているとされる。東には青龍、西には白虎、南には朱雀が相当し、合わせて四神と呼ばれる。調べてみると、上賀茂神社には玄武が祀られているという話があった。私は意外な象徴を発見して驚いた。これは偶然か必然か。水のようにさらさらした想念が途端石のように固くなった。興奮のあまりその観念を詩に書いた。なかなかうまくできたと思う。しかし真実はどこにあるのだろうか。蛇はいつからか人前に出てくることもなくなり、石に首をもたせかけてずっと眠っている。
*
これを書きながら寝た次の日の朝に、夢をいくつも見た。そのうち三つほどはまだ思い出せる。じっさいは夢にも満たない露のようなものだったが、その味は濃かった。起きると岩肌がしっとりと濡れていて、予想以上に高く上がった太陽に黒く濡れ輝いているのを見つけた。
0 notes
Text
2017年、心に残った出来事・ベスト5【車中泊女子の全国縦断記】
「もう12年も旅して、飽きるでしょ?」と聞かれることもありますが、地元であっても未だ知らない名所があるものです。ふだん通らない道を走ってみるだけでも、様々な発見があります。 その1【歴史をめぐる】 筆者の地元、熊本県菊池川流域〜福岡県・筑紫平野は、古墳をはじめ遺跡の宝庫。何日もかけて遺跡・史跡めぐりをしました。写真の【切通しの石仏群】は筆者の地元・菊池市のお隣、山鹿市菊鹿町にあります。クルマで30分程度の場所であるにも関わらず、今春までまったく知りませんでした。 作られた当初(大正3年)は八十八体の石仏があったそうですが、現在は三十体ほどしか残っていません。もっと古い時代からの道が近くを通っているのに何故わざわざ巨大な岩山(岩隈山)を切り崩して道を作ったのかも謎です。 横穴墓群、古墳群、城跡…。縄文・弥生時代など遠い時代、自分とはまったく関係ないことのようですが連綿と現代まで繋がっているのだなぁと感慨にふけった春でした。 その2【神社めぐり】 福岡県東峰村にある宝珠山 岩屋神社で毎年4月の第2土・日に執り行われる【岩屋まつり】、土曜日は雨で断念しましたが、メインイベントでもある日曜日の紫橙(さいとう)大護摩供養・火渡り神事を見ることができました。 国指定重要文化財・岩屋神社本殿は、権現岩(写真)の窪みを利用して造られた彦山山岳修行の第3窟。およそ1500年前の継体天皇25年(521)、中国・北魏からの渡来僧「善正」が修行場「日子山(ひこさん/彦山・英彦山)」を開山した翌年に『宝珠山宝泉寺大宝院』として開かれたのがはじまりとされています。 宝珠山には、欽明天皇8年(547)、突然の霊光とともに空から「星の玉」(つまり隕石?)が降って来たという伝説があり、その〝宝珠石〟は今も本殿内に祀られています。 鎖場に次ぐ鎖場を超えて奥社への修験道も踏破したし、山が好きで山岳信仰に惹かれる筆者にとって多いに意義ある1日となりました。 神社が好きな理由のひとつには、境内の自然がゆたかであることも大きいです。 写真は山形県西村山郡朝日町にある浮島(浮嶋)稲荷神社。神池・大沼は、天武帝9年(681)、山岳修験者である役小角(えんのおづぬ)によって発見されたと伝えられています。大小様々な「浮島」は風もないのに動くといわれており、とても神秘的な場所です。大沼の散策路は一周約30分、筆者が訪れた10月下旬は紅葉も素晴らしかったです。 記憶に新しい、三峯神社の「白」い「氣」守りをいただいたことや、出雲大社で迎えた「神在月」なども特別な思い出です。 その3【野生動物との出逢い】 かれこれ20回は訪れている北海道ですが、さすが「でっかいどう」と称されるだけあって未踏の地がまだまだあります。サクラマスが遡上することで有名な「さくらの滝」(北海道斜里郡清里町)も、そのひとつでした。サクラマスの遡上シーズンは7〜8月中旬。お盆休み頃が最後のチャンスです。 今年は台風の影響で巨大な倒木が行く手を阻み、こんな高さの滝を遡上するなんて無理ではないかと固唾をのんで見守りました。結局、上り切るところは見られなかったのですが、何度もジャンプし滝に挑み続ける姿に感動しました。 然別風穴地帯(北海道河東郡鹿追町)でナキウサギを間近に見ることができたのもラッキーでした。ナキウサギは氷河期の生き残りといわれ、岩場を住処としています。警戒心が強く、すばしっこいので鳴き声は聞こえても姿を捉えるのは至難の業。毎年のように大雪山を登山していますが一度も見たことがありませんでした。初めてカメラにバッチリ収めることができて、嬉しいというよりも呆然としてしまいました(笑) 然別湖には観光遊覧船があり、カヌー、カヤックなどアウトドア体験も豊富です。時間と体力があれば東雲湖トレッキングも楽しめますし、【ホテル風水】の展望大浴場で日帰り入浴もできます(1,000円)。 北海道を代表する野生動物といえばキタキツネ、エゾシカ、そしてヒグマです。過去、何度かヒグマを見たことがありますが、今年は知床ウトロの岩尾別川でヒグマがサケを補食し、そのおこぼれを狙ってオジロワシ親子が群がるシーンを見ることができました!(カラスもいますが…) しかし、遠すぎたうえに三脚を持っていなかったので、写真がボケてしまっているのが何とも悔しい。 その4【金比羅山火口展望台(洞爺湖展望台)】 洞爺湖および有珠山を中心として伊達市・豊浦町・壮瞥町・洞爺湖町を含む、日本で最初の世界ジオパーク【洞爺湖有珠山ジオパーク】。 西山山麓火口には【西山山麓火口散策路】と【金比羅火口災害遺構散策路】という2つの散策コースがあるのですが、実はこの2つの散策路の間に【金比羅山火口展望台(洞爺湖展望台)】が存在するにも関わらず観光パンフレットには載っていません。知らずに登って来る観光客も多く(筆者もその一人)、前述の2ヶ所が無料なのに対しこちらは有料であることからトラブルにもなりかねず、改善してほしいところです。 金比羅山火口展望台の料金は1,000円と少��値が張りましたが、クルマ1台につき5名まで同料金なのでグループで見に行けば安く感じます。金比羅山火口の火口湖もバッチリ見えるし、眼下には洞爺湖、湖の向こうには羊蹄山までも一望できる絶好のロケーションでした。洞爺湖も幾度となく訪れていますが、隠れスポットを見つけた喜びはひとしおです。 管理人さんに交渉して車中泊させていただけたので、洞爺湖温泉街の夜景や花火も満喫できました。この日は薄曇りなうえ満月だったので星空は見えなかったのが残念。来年にはキャンプ場としてのオープンを予定しているそうなので、また利用したいです。 その5【湯西川ダム ダックツアー】 ふだんは自然が好きで観光地やレジャー施設などにはあまり行かないのですが、水陸両用バスでゆく【ダックツアー】にはハマりました! 栃木県日光市湯西川温泉地区の観光センター【湯西川水の郷】から発着、湯西川ダムを見学したあと水陸両用バスに乗り換えダム湖を遊覧(ダム見学とダム湖遊覧の順番は、便により交互になっています)。乗り物好きには「水陸両用バス」というだけでテンション上がりますね。 ダックツアーは東京・お台場、大阪、長野・諏訪湖、長崎・ハウステンボスでも運行しています。来年は、お台場ダックツアーも体験してみたい! というわけで、次回は「2018年に行ってみたい場所ベスト5」をお送りします。 (松本しう周己) 【関連記事】 2017年、行ってよかった日本の風景・ベスト5【車中泊女子の全国縦断記】 https://clicccar.com/2017/12/27/543132/ あわせて読みたい * 2017年、行ってよかった日本の風景・ベスト5【車中泊女子の全国縦断記】 * 戌年最強のパワーアイテム!? オオカミを祀る三峯神社の白い氣守り(埼玉)【車中泊女子の全国縦断記】 * 寒い日はやっぱり温泉ですよね。日本有数の炭酸泉・長湯温泉で温まりませんか(大分)【車中泊女子の全国縦断記】 * チバニアンに続け!? 世界でたった3ヶ所しかない「世界三大奇勝」が徳島県阿波市にあるって知ってますか?【車中泊女子の全国縦断記】 * 竹田城跡だけじゃない。あの空中都市・マチュピチュを思わせる風景が大分にあった【車中泊女子の全国縦断記】 http://dlvr.it/Q7vYTN
0 notes
Text
●●禅(ぜん) ★虚無僧(こむそう)
本文を入力してください
●●禅(ぜん) ★虚無僧(こむそう)
虚無僧 http://w01.tp1.jp/~sr10031313/images/yjimage-5.jpeg
今ここに生きて有る命の真実 この真実を禅では本来の自己という。
本来の自己を表わす業が座禅である。
が禅の心得だそうです。
日本曹洞宗の祖・道元は、ただひたすら坐ることに打ち込む
只管打座(しかんたざ)を唱えている。
タダ座って只管打座(しかんたざ)
「只管」は、ただひたすら。「打座」は、仏教で、座禅すること。
簡単なようで難しい。
昔聞いたのではヨガのように瞑想しなさいとは言わないようだ。
虚無僧が禅宗からの派生とは知らなかった。
子供の頃に深編み笠で回ってくる虚無僧は少し怖かった。
今ではほとんど見かけることもない。
少し形は違うけれども普通の編み笠でも良いようだ。
深編み笠で回って来るので
あの編み笠の中の顔が下からのぞいても見ることは出来ない。
だから怖かったのかも知れない。
子供の頃見かけた虚無僧は正式の服装して腰に印籠を下げていたかな。
脇差しは無論していなかった。
遠い懐かしい風景が目に浮かぶ。
★禅 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/禅
禅(ぜん)は大乗仏教の一派であり、南インド出身の達磨が
中国に入り教えを伝えて成立したとされている。
中国禅は唐から宋にかけて発展したが、明の時代に入ると衰退 していった。
日本に純粋な禅宗が伝えられたのは鎌倉時代であり、
室町時代に幕府の庇護の下で発展した。
明治維新以降は、日本の禅が世界に伝えられた。
日本禅宗24流 曹洞宗 3派 臨済宗 21派
★虚無僧(こむそう)http://bit.ly/wbnKtX
禅宗の一派である普化宗の僧であり、剃髪しない半僧半俗の存在である。
普化宗は中国(唐)の普化を祖とし、日本には臨済宗の僧・心地覚心が中国に渡り、
普化の法系の張参に竹管吹簫の奥義を受け、張参の弟子「宝伏」ら
4人の居士を伴い、1254年(建長6年)に帰国し紀伊由良の興国寺に
普化庵を設けて住まわせたことに始まる。
「古くは、『こもそう(薦僧)』ということが多く、
もと坐臥用のこもを腰に巻いていたところからという。」
虚無僧の様相については、
「尺八を吹き喜捨を請いながら諸国を行脚修行した有髪の僧」
とされており、
「多く小袖に袈裟を掛け、深編笠をかぶり刀を帯した。」
虚無僧はじめは普通の編笠をかぶり、白衣を着ていたが、
江戸時代になって徳川幕府によって以下のように規定された。
托鉢の際には藍色または鼠色の無紋の服に、男帯をまえに結び、
腰に袋にいれた予備の尺八をつける。
首には袋を、背中には袈裟を掛け、頭には「天蓋」と呼ばれる深編笠をかぶる。
足には5枚重ねの草履を履き、手に尺八を持つ。
旅行時には藍色の綿服、脚袢、甲掛、わらじ履きとされた。
なお、よく時代劇で用いられる「明暗」と書かれた偈箱(げばこ)は、
明治末頃から見受けられるようになったもので、
虚無僧の姿を真似た門付芸人が用いたものである。
江戸時代には、天皇家の裏紋である円に五三の桐の紋が入っており、
「明暗」などと書かれてはいなかった。
江戸期においても偽の虚無僧が横行していたが、
偽虚無僧も皇室の裏門を用いていたようである。
★曹洞宗の公式サイト http://bit.ly/Akqm83
★臨済宗・黄檗宗の公式サイト http://bit.ly/zNTYq2
★曹洞宗大本山永平寺 第78世貫主 宮崎奕保禅師
(道号・法諱) 栴崖奕保(せんがい えきほ).
(禅師号) 黙照天心禅師. (もくしょうてんしんぜんじ).
(生誕) 明治34年(1901)11月25日. 平成20年(2008)1月5日. (世壽). 108歳.
https://youtu.be/SRezHZsNOI8
宮崎奕保禅師の禅のお話し 2018/04/02
★これが永平寺だ!永平寺曹洞宗大本山永平寺 2011/10/31
https://youtu.be/PLE7Jta6k74
★新日本風土記「永平寺」道は無窮なり悟りても猶行道すべし 2019/05/10
https://youtu.be/RgIdPQjUZNU
修行というのは何かのためにやるのではない、生活そのものが修行なのです。
★Zen Dogen the Zen Master
https://youtu.be/4T0QbAQXQV4?list=PL8447A93C7DCA0141
http://bit.ly/xJuE8h
http://bit.ly/wAOnLq シナ語?英語字幕
http://bit.ly/z7L2Mq
http://bit.ly/x7n4HI
http://bit.ly/xzWb5k
http://bit.ly/ys5HMV
http://bit.ly/zL8KzG
http://bit.ly/ytDjpH
http://bit.ly/y5OVN5
★財団法人禅文化研究所 http://www.zenbunka.or.jp/
★人 間 禅 道 場 http://bit.ly/z5mtOX
明治の初頭に山岡鉄舟、中江兆民らの先覚者が、当時鎌倉円覚寺管長の今北洪川禅師(白隠禅師より8世)を拝請し、社会人のための禅会として人間禅教団(旧名両忘協会)は創設されました。
★大安禅寺 http://www.zazen.or.jp/
福井県は松平家ゆかりのある、花しょうぶの美しいお寺です。
★禅文化歴史博物館 | 駒澤大学
https://www.komazawa-u.ac.jp/facilities/museum/
禅文化歴史博物館情報/開館時間.
駒澤大学 禅文化歴史博物館 (駒沢キャンパス内)
〒154‐8525 東京都世田谷区駒沢1-23-1
入館無料平日 10:00~16:30(最終入館16:15まで).
お問い合わせ先駒澤大学禅文化歴史博物館事務室.
TEL:03-3418-9610
★坐禅 - Wikipedia http://bit.ly/x1D7Hp
日本曹洞宗の祖・道元は、ただひたすら坐ることに打ち込む只管打座(しかんたざ)を唱えている。
★坐禅のやり方(初心者) - 禅-Zen
http://zen.halfmoon.jp/zazenn.html
坐禅 やり方、基礎知識.
はじめに
坐禅に関しては、最初は何やらとっつきにくいものではないかなあと思います。
個人で自宅でもできるものだとは思いますが、最初はお近くの座禅会などで、
正しい坐禅をご教授していただくのがよいかと思います。
また、一人ではなかなか時間に流されてしまいがちになってしまいますが、
座禅会などはまわりの方々もいらっしゃるので、集中度がちがって
くるような気がします。
ただいきなり座禅会などで、初めてのことが多いと、頭がこんがらがって
しまうかもしれないと思い、初めてこれから坐禅に挑戦したい・興味がある
という方向けとして、坐禅の簡単な組み方の説明を載せてみます。
(世の中にはいろいろととても素晴らしい坐禅の方法の説明サイトや書籍があると思います。本サイトでうまく伝わらないかもしれません。ご不明点とうありましたら別サイトや書籍をお調べになる、座禅会で直接ご指導を受けてみるなどの方法もあります。)
★自宅で座禅、呼吸整える http://bit.ly/wN7tUC
背筋を伸ばし下腹に力
邪念を払い心穏やか
座禅にはともすれば厳しい修行のイメージがつきまというが、寺院が主催する座禅会では若い女性の姿も目立つようになってきた。「気分が引き締まった」との感想に加え、「美容と健康にもいい」といった声も。とかくストレスのかかる現代社会。自宅での日常生活にも、座禅のエッセンスを取り入れてみよう。
★座禅の仕方 http://bit.ly/wU0CQw
禅とは「禅那」と言いサンスクリット語のdhyanaの音訳で、静慮とか思惟とか
思量するという意味があり、古代インド仏教から伝わる瞑想法です。
座禅は安楽の法門とさえ言われるように、その座法はおしゃか
さまのお悟りの姿に見るごとく身体の最も安定した形です。
その座禅とは、静座(せいざ)をして座禅の三要素である
調身・調息・調心による身体を調え、呼吸を調え、心を調えることによって
精神の統一から本来的に備わる真実の自己(仏性)の自覚にあります。
その過程における精神医療的効果や禅定における集中力や不動心や忍耐力の
養成の効用面が広く知られ、企業研修などに活かされています。
・ぜんな 【禅那】 〔梵 dhyāna〕
禅。禅定。
・せい りょ【静慮】
( 名 ) スル
心を落ち着けて静かにおもいをめぐらすこと。
・しい【思惟】
( 名 ) スル
① 考えること。思考。しゆい。 「其しいする所甚だ卑下にして/明六雑誌 19」
② 〘仏〙 「しゆい(思惟)」に同じ。
③ 〘哲〙 「思考(しこう)② 」に同じ。
・しりょう【思量】
・しれう 【思料】
( 名 ) スル
いろいろと考えること。おもんぱかること。思慮。
「客人ならんと思量せしかば小腰を屈めて前掛けに手を拭ひ/新粧之佳人 南翠」
★はじめての座禅指導.WMV 2011/01/24
https://youtu.be/sUOJaJh-tIw 平成23年1月22日 座禅講座
★尺八・虚無僧 http://bit.ly/zk5LXg
虚無僧は普化宗の徒で、出家者として全国を行脚していました。
しかし、お坊さんのように剃髪していたわけではなくまた、お坊さんでもなく 、
徒として所属していたようです。
そして、基本的には武士(浪人)が虚無僧に なれる条件でした。
だから、適当な仕官口が見つかると、再び還俗したようです。
中には、黒沢琴古のように指南役として尺八を教えることを専門に、
江戸などで、一般のお弟子を取っていたようです。
と言っても、これは、庶民の音楽とは 無縁でした。
商業都市が形成され、一般大衆(といっても所謂、中流以上の人でしょうね。 )
の生活と時間に余裕が出来てくると、文化も多様化してきました。
それでも、尺八は庶民には高嶺の花だったのでしょう、と言うのも、
男伊達と 言えば尺八をカッコよく手にした歌舞伎絵が多くあるからです。
庶民の憧れのカッコだったんでしょうね。
いつも、かっこいい男は、少しやくざっぽくて、楽器の一つでも
粋に奏するものです。
しかし悲しいかな、多くの、真の芸術家はそんなにカッコ良くはありません。
いつも、生活の塗炭にもがき苦しんでいるようです。
・還俗 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/還俗
還俗(げんぞく)とは、僧侶になった者が、戒律を堅持する僧侶であることを
捨て、在俗者・俗人に戻る事をいう。
「復飾」(ふくしょく)とも。
自らの意志で還俗する場合と、教団側から還俗させられる場合がある。
日本では、律令「僧尼令」における刑罰の一つでもあった。
武士・公家の家督や棟梁、氏長者といったものを相続していた当主が亡くなり、謀反防止のためなどの理由で出家していた子弟・縁者などが相続して家名を
存続させる目的のものもあるなど、背景はさまざまである。
また、宮門跡となって入寺得度(出家)した親王が再び皇親に戻り、
宮家を継承することもあった。
特に幕末維新期にはその数は増えていった。
★虚無僧研究会 http://bit.ly/yRfoEp
★虚無僧(こむそう) [ 日本大百科全書(小学館) ]
尺八を吹きながら家々を回り、托鉢(たくはつ)を受ける僧。
薦(こも)僧、菰(こも)僧というのが本来の呼び名で、
諸国を行脚(あんぎゃ)して遊行(ゆぎょう)の生活を送り、
雨露をしのぐために菰を持ち歩いたからである。
ぼろを身にまとって物乞(ものご)いしたので、
暮露(ぼろ)とも梵論字(ぼろんじ)(梵論師)ともよばれた。
普化(ふけ)僧ともいう。
普化宗は禅宗の一派で、中国の唐代の普化和尚(おしょう)を始祖とし、
法燈(ほっとう)国師覚心(かくしん)が宋(そう)から日本に伝来したという。
覚心は紀伊国(和歌山県)に興国寺を開山し、宗旨も広まり多くの流派ができた。
虚無僧寺としては、
京都の明暗寺、
下総(しもうさ)小金(こがね)
(千葉県松戸市)の一月寺(いちがつじ)、
武蔵(むさし)青梅(おうめ)
(東京都青梅市)の鈴法寺(れいほうじ)などが著名であった。
普化宗では、心を虚(むな)しくして尺八を吹き、虚無吹断を禅の至境とした。
近世初期には武士以外の入宗(にっそう)を認めず、
また幕府も自由の旅を許すなどの特典を与えたが、
浪人や無頼の徒が身を隠す手段に利用し、乱暴をはたらくなどの弊害が続出した。
普化宗は1871年(明治4)に廃宗となり、88年に京都に明暗教会が設立されたが、
虚無僧は宗教から離れ、尺八修業の方便か物乞いの手段かになって影を潜めた。
僧とはいいながら半僧半俗で、
多くは有髪(うはつ)で、
天蓋(てんがい)と称する深編笠(ふかあみがさ)をかぶり、
着流しで、首から袈裟(けさ)と頭陀袋(ずだぶくろ)をかけた。
手甲(てっこう)・脚絆(きゃはん)なども着けた。
古くは草鞋(わらじ)を履いたが、江戸時代の中ごろから
高下駄(たかげた)を履くようになった。
出没自在、腕のたつこと、無頼性など、不思議な魅力をもつところから、
時代劇では善玉としても悪玉としても、しばしば脇役(わきやく)として登場する。
[ 執筆者:井之口章次 ]
★虚無僧で遊ぶ http://bit.ly/zJqy6i
目次
虚無僧で遊ぶ
TRPGで虚無僧を使う
参考文献
★虚無僧 - AIRnet
http://www4.airnet.ne.jp/sakura/blocks_menu/conjyaku_04/komuso.html
【虚無僧】
虚無僧の歴史は古く,七百年以上前にさかのぼる。
法燈国師によって開かれた臨済宗法燈派「興国寺」(和歌山県由良町)は
虚無僧の本山として名高い。
東福寺(臨済宗)の心地覚心(1207~1298)が,
建長元年(1249)入宋,建長六年に弟子四人を連れて帰国,
紀州由良に興国寺を立てた。
興国寺の中に普化庵を建て弟子を住まわせたが,この流れの中から
京都白川に明暗寺が作られることになっていくのである。
禅宗が栄えて,禅宗の中の普化宗は紀伊,伊勢,志摩を中心に
末寺百四十三ヶ寺を数える関南第一禅林(箱根の関より南の
禅宗の寺の第一に数えられるという意味)と言われた。
「・・・大門から入ると二十三坊の坊舎が左右に建ち四十六坊もあった・・・」
と古い文献にあり,当時全国から多くの学僧が集まり”学問の府”の偉容を
誇っていたが,信長・秀吉に焼かれてこれらの堂塔はことごとく消失した。
★【妙音】虚無僧の行進曲【手の内ご無用】 2010/06/04
https://youtu.be/RlybT_mfNNo
2010年6月、高岡市の国泰時総本山で行われた虚無僧による行進の風景です。
禅宗のお寺である国泰時総本山では外部の宿泊者の受け入れもしており、
また、リクエストをすれば、日帰りで座禅を組むことができます。
お寺の周りは竹の子の名産地で、竹の子料理店が軒を連ねており、
シーズンには行楽客で賑わいます。
★honkyoku for sampled bassoon 法竹
https://youtu.be/FboLa83-AA0
★本曲(本曲、「オリジナル曲」)は、屈従と呼ばれる日本の虚無僧が演奏する尺八またはほっちく音楽です。コムソウは、13世紀には早くも啓蒙と施しのために本曲を演奏しました。本曲とは、水前の練習です。この練習を始めたフケ派は19世紀に存在しなくなりましたが、今日では多くの本曲の口頭で書かれた血統が現在も続いていますが、音楽は現在コンサートやパフォーマンスの設定でよく練習されています。
★竹音空間(ちくおんくうかん)|竹楽器製作者:遠藤健二|法竹(ほっちく)
https://otomoribeat.wixsite.com/chikuon
竹音空間では、法竹(ほっちく)と呼ばれている素朴な尺八(地無し尺八、地無し管)を製作しております。
法竹は真竹で作ったシンプルな縦笛ですので、竹が持つ本来の音色が出ます。
尺八古典曲の音色は日本の豊かな自然の中で生まれました。
尺八古典曲の音色は日本の豊かな自然の中で生まれました。
尺八古典曲は音楽的でありながらも自然の様を
写し取ったような表現もあり音楽の枠にはおさまりきらない幅があります。
それは、もともと日本人が鳥や虫の声、自然の音を音楽と同じように親しみ聴いて来たから
ではないでしょうか。素朴な竹から奏で出る竹音には、そんな日本の音楽の原点があると思います。
★尺八癡人街頭表演(捨てられた町`)(悲情的城市)
http://www.youtube.com/watch?v=4wwhSlV0ALk&feature=related
★虚無僧 法竹 虚鈴 Komuso Hocchiku KyoRei 2011/04/08
https://youtu.be/8LcG-n1_Zko
by 関家悠也(Sekiya Yuya)
★尺八 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/尺八
尺八(しゃくはち)は、日本の木管楽器の一種である。
リードのないエアリード楽器に分類される。
中国の唐を起源とし、日本に伝来したが、その後空白期間を経て、鎌倉時代から
江戸時代頃に現在の形の祖形が成立した。
「尺八」の名で呼ばれてきた楽器は複数あり、狭義には現在使用されている
普化尺八(ふけしゃくはち)を指す。
現行の普化尺八は、伝説では9世紀ごろに唐の禅僧普化の弟子張伯が
虚鐸(きょたく、こたく)として発明し、1254年に心地覚心が日本に持ち帰り、
1400年ごろに虚無(楠木正勝)が広めたという伝承があるが、
史実として確実に遡れるのは17世紀までである。
名称は、標準の管長が一尺八寸(約54.5cm)であることに由来する。
語源に関する有力な説は、『旧唐書』列伝の「呂才伝」の記事によるもので、
7世紀はじめの唐の楽人である呂才が、筒音を十二律にあわせた縦笛を作った際、
中国の標準音の黄鐘(日本の十二律では壱越:西洋音階のD)の音を出すものが
一尺八寸であったためと伝えられている。
演奏者のあいだでは単に竹とも呼ばれる。
英語ではshakuhachiあるいは、Bamboo Fluteとも呼ばれる。
真竹の根元を使い、7個の竹の節を含むようにして作るものが一般的である。
上部の歌口に息を吹きつけて音を出す。
一般的に手孔は前面に4つ、背面に1つある。
尺八に似た楽器として、西洋のフルートや南米のケーナがある。
これらは、フィップル(ブロック)を持たないエアリード楽器である。
★尺八について(歴史)|公益財団法人 都山流尺八楽会
http://www.tozanryu.com/introduction/shakuhachi/shakuhachi01/
尺八ってどんな楽器?
尺八は真竹(まだけ)の根に近い部分を7節使うのが一般的です。
しかし近年は廉価な木製、プラスチック製の尺八もあります。
標準管の長さは一尺八寸(約54cm)で、一尺八寸管、略して八寸管とも
呼ばれています。半音(一律)刻みでいろいろな長さの尺八がありますが、
一尺八寸管以外によく使われるのは、一尺六寸管です。
尺八の長さと音程の関係は短いほど音が高く、長いほど低い音が出ます。
同じエアリード楽器に分類される楽器としては「リコーダー」「フルート」「オカリナ」などがあります。
●尺八の歴史をさかのぼってみよう
・古代尺八(雅楽尺八)の伝来
・一節切(ひとよぎり)尺八の普及
・虚無僧の登場
「慷月調」作曲の前年、明治35年(1902)11月
奈良で撮影した虚無僧姿の流祖(右)
http://www.tozanryu.com/introduction/shakuhachi/shakuhachi01/images/image05.jpg
・尺八ってこんな楽器です! http://www.tozanryu.com/introduction/summary/
竹で作られた管楽器です。中国(唐時代)から伝来したものが始まりとされ、楽器の長さ(一尺八寸)がその名の由来とされています。他の楽器には無い奥深い音色を奏でることができます。
・「都山流」は国内最大と言われる尺八の流派です
120年以上続く尺八の流派です。尺八には様々な流派があり、都山流は「流祖中尾都山」が明治29年(1896)に大阪にて創始しました。現在は京都に本拠を置き、若手からベテランまで多くの著名な演奏家を擁し、教授資格を持つ師匠は約4000名に及びます。平成28年(2016)に創立120年を迎えることができました。
0 notes
Text
七福神巡り、多くの参拝者にぎわう 県内各地15カ所を紹介 七つの災難が免れ、七つの幸福が授かる
埼玉新聞 https://this.kiji.is/452623335831651425?c=39546741839462401 参拝すると七つの災難が免れ、七つの幸福が授かるといわれる七福神。県内各地にも恵比寿、大黒天、毘沙門天、弁財天、福禄寿、寿老人、布袋尊の七福神巡りが設けられ、新年になると多くの参拝者でにぎわう。中にはスタンプラリー形式や甘酒の無料配布など、楽しみながら巡れるところも。新春のまちの空気を感じながら巡り、健康や長寿などを願ってみては。 ■三郷七福神 厄除け銀杏がお出迎え 三郷市内の全24寺院が参加する三郷七福神めぐり。「彦成めぐり」「八木郷戸ケ崎めぐり」「早稲田めぐり」と三つのコースがあるのは全国的にも珍しく、ウオーキングを兼ねて歩いて回る人も。彦成コースの安養院境内には、樹齢600年の「厄除大銀杏」の大木があり、その銀杏の実を正月に食べれば1年間災いから逃れられるとされている。 来年1月1日~7日までの7日間は七福神めぐりスタンプラリーを実施。スタンプ台紙は各寺院で販売している。 問い合わせは、三郷市観光協会事務局の市商工観光課(電話048・930・7721)へ。 ■日光街道すぎと七福神 料理や買い物ツアーも すぎと七福神は東武線杉戸高野台、東武動物公園、姫宮駅を拠点に、古利根川に沿いに福正院、永福寺、全長寺、宝性院、延命院、来迎院、馬頭院を巡る。 七福神巡りと共にうなぎや和菓子、そばや地酒など、地元のグルメを楽しんでほしい。年明けにはガイドと料理、ショッピングを盛り込んだ七福神ツアーも。来年1月19、26の両日は徒歩で(参加費1人2千円)、2月2日はタクシーで(同4千円)で。 問い合わせは、すぎと七福神事務局宝性院(電話0480・32・0342)か、杉戸町観光協会(電話0480・32・3719)へ。 ■くりはし八福神 ふるさと自慢のコース 通常の七福神に吉祥天を加えた「くりはし八福神」。コースは埼玉ふるさと自慢100選に入選し、年明けのJRの「駅からハイキング」にも指定されている。 約10キロ2時間半ほど、平坦で気軽に楽しめる点が人気だ。JR宇都宮線、東武日光線栗橋駅を起点終点に、栗橋宿の街並み、昔ながらの田園地帯を歩く。足を延ばして、八坂神社や栗橋関所跡碑、静御前墓所など、地域の名所・旧跡を訪れることもできる。御朱印押印期間は来年1月3日~15日午前9時~午後4時。 問い合わせは、久喜市観光協会(電話0480・21・8632)へ。 ■草加宿七福神 宝船も加えた寺社巡る 日光街道の宿場町として栄えた旧町地区にある7カ所の七福神に宝船を加えた8カ所の寺社を巡る。歴史情緒あふれる町並みを歩きながら、布袋尊の回向院や毘沙門天の東福寺など、七福神巡りを楽しむ。 来年1月1日~7日までスタンプラリーを実施。スタンプ台紙は各寺社のほか、草加駅構内、市物産観光・情報センターで配布する。開催時間は午前9時~午後4時まで。1日はお休み処草加宿神明庵で、3日は東福寺境内でいずれも午前10時から甘酒の配布を行う(なくなり次第終了)。 問い合わせは、草加市観光協会事務局の市文化観光課(電話048・922・0151)へ。 ■小江戸川越七福神 蔵造りの街並み味わう 小江戸川越七福神はJR、東武の川越駅や川越市駅を起点にするコースがある。全行程は約6キロ。途中には蔵造りの街並みや時の鐘、菓子屋横丁などがあり、至るところで江戸情緒や城下町の面影を感じながら回ることができる。 7カ所全ての寺には、地中に埋められた甕(かめ)の中に水滴音を反響させてその音を楽しむ「水琴窟(すいきんくつ)」を設置。それぞれの音の違いを楽しむこともできる。絵馬など、オリジナル七福神グッズの販売も行われている。 問い合わせは、小江戸川越七福神霊場会(電話049・222・6151)へ。 ■武蔵野七福神 台紙手に日帰りコース 飯能、入間、所沢市の寺社を巡る七福神。武蔵野の自然を満喫しながら電車、バスを上手に乗りこなし、日帰りで回れるコースとなっている。 効率よく七福神を巡るなら、円泉寺(福禄寿)から飯能恵比寿神社(恵比寿)、観音寺(寿老人)、浄心寺(毘沙門天)と飯能市内の寺社を回り、入間市の円照寺(弁財天)、長泉寺(大黒天)、所沢市の山口観音(布袋尊)へと参拝するのがモデルコース。 台紙の色紙にご朱印(1回100円)を集めながら7寺社を巡るのも楽しい。 問い合わせは、山口観音(電話04・2922・4258)へ。 ■与野七福神 開運願う仮装パレード 与野七福神は、さいたま市中央区の本町通り周辺を徒歩約2時間で巡る人気コース。日光街道岩槻への脇往還の宿場として栄えた街の名残を今も感じられる。 同区本町東の氷川神社(福禄寿)をスタート。冬至祭で知られる一山神社(恵比寿神)から天祖神社(寿老神)、御嶽社(弁財天)、円乗院(大黒天)、円福寺(布袋尊)、鈴谷大堂(毘沙門天)でゴールする。各寺社の押印受付は元日~3日の午前9時~午後4時。3日午前11時半からは「七福神仮装パレード」も行われる。 問い合わせは、与野七福神奉賛会の岩崎さん(電話048・853・9798)へ。 ■武蔵越生七福神 梅の郷で甘酒たしなむ 「梅の里」として知られる越生町。武蔵越生七福神は越生駅の西側一帯に点在する。起伏に富んだ約13キロのコースは、豊かな自然を体感しながら七つの寺院を巡る趣向だ。周辺には越生梅林や自然休養村センターもある。 来年1月4日に開催される「新春武蔵越生七福神めぐり」は法恩寺を出発し、全洞院までを巡る。ゴール会場の東上閣駐車場では甘酒の無料配布や福引を楽しむことができるほか、干支(えと)のオリジナル缶バッジがプレゼントされる。 問い合わせは、越生町産業観光課(電話049・292・3121)へ。 ■武州川口七福神 早春をつげる安行寒桜 川口市で七福神と言えば、外せないのが安行原の深い緑に隠れた密蔵院(川口駅東口から峯八幡行バスで終点下車)の大黒天だ。 550年の歴史を誇り、本尊は平安時代の地蔵菩薩という。堂々とした黒門は幕末の江戸で薩摩藩のものを移築したと伝える。本堂への真っすぐの石畳を歩けば歴史の空気を感じることができる。早春に咲く安行寒桜でも名高い。 武州川口七福神は密蔵院のほか、戸塚の西光院(弁財天)、東本郷の傑伝寺(恵比寿様)、元郷の正覚寺(布袋様)、本町の錫杖寺(福禄寿)、南町の吉祥院(毘沙門)、宮町の正眼寺(寿老人)。ともに地域との絆、歴史を誇る。 問い合わせは、川口観光物産協会(電話048・228・2111)へ。 ■武州本庄七福神 徒歩3時間で全て巡回 武州本庄七福神はJR本庄駅北口に点在する10寺院に設置。銭洗い弁財天は慈恩寺、大正院、佛母寺の3カ所、大黒尊天は城立寺と普寛霊場の2カ所にそれぞれある。 全工程は約4キロで、3時間もあれば徒歩で巡れる。本庄駅から大正院(銭洗い弁財天)―円心寺(福禄寿)―開善寺(布袋尊)―慈恩寺(銭洗い弁財天)―普寛霊場(大黒尊天)―安養院(毘沙門天)―佛母寺(銭洗い弁財天)―金鑚神社(恵比須尊)―泉林寺(寿老人)―城立寺(大黒尊天)を巡るコースがお薦め。 問い合わせは、本庄市観光協会(電話0495・25・1174)へ。 ■深谷七福神 北から南へ市内を横断 深谷七福神は、旧深谷市内を南北に横断しているのが特徴。どの寺にも秋の七草が植えられている。 JR深谷駅を起点とする全工程は約22キロ。距離が長いので、車やバスを利用する人が多い。同駅出発なら瑠璃光寺(大黒天・ハギ)―泉光寺(恵比寿天・オミナエシ)―正伝院(毘沙門天・クズ)―惣持寺(弁財天・オバナ)―全久院(寿老人・フジバカマ)―宝泉寺(福禄寿・キキョウ)―一乗寺(布袋尊・ナデシコ)と北から南下するのはいかがでしょうか。 問い合わせは、瑠璃光寺(電話048・571・1945)へ。 ■秩父七福神 1市4町、根強い人気 秩父七福神は秩父札所34カ所観音霊場とは異なる古刹(こさつ)寺院で構成され、秩父、長瀞、皆野、小鹿野、横瀬の1市4町に点在し、総距離は約56・1キロ。歴史は40年以上で、根強い人気を誇る。 熊谷方面からは今月8日にシンボルの「多行松」が伐採された長瀞の総持寺(福禄寿)が出発点。皆野の大浜円福寺(大黒天)、小鹿野の鳳林寺(毘沙門天)と続く。秩父は田村円福寺(寿老人)、惣円寺(弁財天)、金仙寺(布袋尊)の3カ所で、横瀬の東林寺(恵比寿)が最後だ。 問い合わせは、秩父七福神会事務所の総持寺(電話0494・66・2665)へ。 ■武州寄居七福神 露座に光る豪快な存在 武州寄居七福神は寄居町の寄居、用土、男衾駅周辺の5カ寺にある。ご神体を露座で祭り、御像の大きいのが特徴。各寺でご朱印を集められ、色紙は千円で授与されている。 一回り約25キロ。存在感あるのが蓮光寺の布袋尊で高さ約4・5メートル(台座含める)、幅約3メートルと豪快な笑顔で福を招き、福禄寿も設置。極楽寺は高さ約3メートル(同)の毘沙門天と高さ約2・7メートル(同)の弁財天がある。 ほかの七福神は恵比寿神(常楽寺)、寿老尊(長昌寺)、大黒天(常光寺)。 問い合わせは、寄居町観光協会(電話048・581・3012)へ。 ■行田忍城下七福神 名所旧跡を一緒に堪能 「行田忍城下七福神」は1周約20キロ。忍城址や埼玉古墳群など、行田の名所旧跡を見学しながら楽しみたい。 花で有名な遍照院(福禄寿)、難病封じの行田八幡神社(大黒天)、大仏様の大長寺(毘沙門天)、縁起の良い寺名の宝積寺(恵比寿)、三重塔がある成就院(寿老人)、弘法大師作の弁財天を祭る遍性寺、利根大堰(ぜき)近くの興徳寺(布袋尊)で構成。七福神絵図(千円)は7寺社で、スタンプ巡り用の宝船台紙(200円)は行田八幡神社、大長寺、成就院、興徳寺、遍照院で販売している。 問い合わせは、連絡事務所の「忍藩堂」(電話048・577・8058)へ。 ■北本七福神 日本一のおみくじ好評 2015年9月に北本市高尾の阿弥陀堂に布袋尊が建立され、七福神がそろった。「北本七福神」はJR北本駅をスタート。ゴールまでの行程約12・8キロのお薦め散策コースがある。 寿老人が祭られている須賀神社では、日本一大きいとされる八角形のおみくじが300円で引ける。このおみくじを目当てに来る人は多い。 1月13日午前9時半~午後3時まで、新春「北本七福神めぐり」が行われる。各所でのご朱印は300円。スタンプラリーは無料で、スタンプを7個集めると先着800人に記念品がもらえる。 また各所ではおしるこや、まんじゅうなどのおもてなしがある。 問い合わせは、北本市観光協会(電話048・591・1473)へ。 埼玉新聞 https://this.kiji.is/452623335831651425?c=39546741839462401
0 notes
Text
明かりは乱闘で割れてしまったらしい。一部の机の上と床の片隅にさあっと硝子の粒が春の霜みたいに張っていた。通りの光だけを採る粉屋は半端に暗い。
「さて、じゃあ授業を始めます」
形だけはいつも通り、なつめが教壇に立って教室を見回した。
春は両手を前に携えて思い詰めながら壁際に立ち尽くしている。隣に翳島が腕を組んで凭れている。彼の表情はなにか普段と違う事態が起きるとときどき読み取れなくなる。
図々しいことに部屋の真ん中を占めて、魔性のごとき少年が長机に肘をついている。
誉が持ち掛けた勝負の、封切りの場だった。
「今日はお客さんを迎えての対談だ。誉」
誉、となつめは呼んだ。極力感情を排したような声で。
「君が知りたいことは、何?」
「はい」
すうっと片手が挙がる。挑戦者の少年。
「やはり古今東西、学徒の議論といえば神にきまっているだろう。なつめくん、君の育ちなら信仰を持っていておかしくない。実際どうなんだい、君にとって神は、在るのか、無いのか」
春は思わず翳島の横顔を仰いだ。青年は気づかないのか無視したのか、春のほうは見なかった。
信仰、神、という言葉に並んで、なつめの育ちの話が出た。誉は何を指して言っているのだろうか? なつめの家のことを、春はいまだ聞いたことがなかったのだ。なつめはいつも、授業を終えるとどこかに帰っていく。けれどその行き先を不思議と尋ねたことがない。聞く必要がない、あるいは聞いてはいけないことのような気がして。
翳島は知っているのだろうか。二人で旅をしてきたのだから、決まった家があるのじゃないはずだ。
「結論から言おう」
なつめは言った。部屋の空気が張り詰めていて、びんと春の鼓膜が震えた。
「神というものは在るよ。信じる人にとってはまちがいなく」
「へぇ?」
なつめの声に迷いはなかった。誉が伺うように瞳を細くした。
「信じる人に、とは?」
「それより先に、だ。誉」
鉾先が鋭利に返る。
なつめはゆっくりと狙いを定める目つきをしている。
「君にとって神とは何だ?」
そうだ、と春は思った。彼が持ちかけた議論の題目は酷く抽象的だ。
誉は唇を持ち上げた。
「不死であり、永遠、万物の父」
「それは文字通りの意味でそれが神だということか?」
「それ以外にどんな神がある?」
二人の視線が互いを睨み据えた。春は無意識に口元を押さえた。そのやり取りから、剥き出しの言葉の塊がぶつかりあって散らばり落ちるような気がしたのだ。
何の話だろう、と春は考えた。神。少年たちの言う神とはなんのことであるか。不死、永遠、万物の父。それが日本古来の神道で祀っている神のことではないのは神奈神社の巫女である春にはすぐに肌でわかった。
詳しくはないけれど知る限りそれは、西洋から来た神さまのことである。
その正体を、誉がなつめに問うているのだ。奇妙な状況だ。誉は仏門の僧服を着ているのに。
「なつめさんは……」
出しかけた小声を隣から遮られた。しいっと指を立てた翳島だ。その意図が分からなかったけれど、眼鏡越しの真剣な眼光を見て春はぱたんと口をつぐんだ。
ぽかりと空虚なままの胸の洞が疼いた。少年たちは何の土俵で戦っているのか。
春は何も……知らない。
「この世には」
となつめは言った。なつめの双眸がぎらぎらしている。
「説明できないことが無数にある。それを説明しようとするのがぼくら学徒だ」
「へえ」
ひとまず傾聴の姿勢を示すよ、とでも言いたげに誉は肘を突く。なつめはようやく普段の「授業」を思い出してきたようである。
かんッ、と白墨が鳴った。
「ケプラーの法則を知っているか」
なつめが黒板に文字を書いた。小学校の廃棄品のお下がりを春たちで貰ってきたものだ。
「天体の運動に関する基礎概念だ。近代天文学はここから始まる」
「俺はきみたちのそういうやつは不得手でね。教えてくれよ」
誉は応じて首を振った。きみたちの、と言ったのは春や翳島というよりもなつめとその性格に似たたくさんの学徒たちを示しているように思われた。生徒役の従順な態度になつめはまだ目玉を奇妙に光らせたまま頷いた。
「簡単に説明しよう」
なつめの手が円を描く。
「『惑星は太陽を焦点の一つとする楕円軌道を動く』」
白墨の線に合わせて、春の頭の中をぐるんと木星だか火星だかの像が回った。
「春、これは何だい」
自分に問いかけを振られているのだと、春は遅れて気が付いた。思わずすこし腑の抜けた声で答えた。
「第一法則……」
「そう。ケプラーの第一法則」
春も習った。これくらいのことは一年足らずで覚えていた。なつめが夏に冬に星を見上げては語る宇宙。
惑星は太陽の周りを疾駆している。その莫大な質量に近づいたり離れたりを繰り返しながら。それは春にとっても印象的な事実だった。宇宙に思いを馳せるとき、自分まで星になったように感じることがある。
なつめはこちらから目を離した。
「じゃあ、第二法則は?」
彼の手がすいと動く。陽だまりの空気をその肌が白く反射して遮る。
「翳島」
「『惑星と太陽を結ぶ線分が単位時間あたりに動く面積は一定である』」
翳島は棒暗記した教科書を読むように感情のいっさいない声で息継ぎせずにそう言った。春よりももちろん彼のほうが正確に知識を持っている。
「面積速度一定の法則だ」
「正解。それが第二法則」
なつめは特段の満足を生徒たちに示すこともなくそう言った。細い手がふたたび日影をうごめいた。黒板のうえにかつかつと文字が増えた。春が答えたもの。翳島が答えたもの。図にも複数本の線分が書き足されて、三角に似た扇形がいくつか切り取られた。春はそういうものなら見分けることができる。軌道上を動いた惑星が太陽を見つめる視線を示しているのだ。
「それから、最後は少し複雑だからぼくが自分で書こう。『惑星の公転周期Tの二乗は、楕円軌道の半長軸aの三乗に比例する』。惑星が遠ければ遠いほど、その惑星が太陽を周回するのには時間がかかるということだ。聞いてくれれば、それぞれの性質を求める方法も教えよう。だけどひとまず、今の問題は、この式自体の意味するところを解明することではない。
わかるかい、つまり、定式化できるんだ。
宇宙には法則がある。遠い宇宙に、たった三行で書き表してしまえるような法則をケプラーは見つけたんだよ」
なつめの目が輝き始めていた。
大丈夫だ、と春は思う。
同じ光ではあっても、最初に誉を迎えたときのなつめと、ここにいるなつめは違った。春の知っている通り教卓に立っているなつめは、いつもの星の輝きに戻っていた。夜みたいな色の黒板の前に立つ星。北斗星みたいにぶれずに先を示す星だ。
「ヨーロッパはこのときどういった状態だったと思う。誉?」
一周して、なつめの視線が客人に戻った。けれどさっきまでみたいな不安感は春にとってはもうない。
「近世だね」
と誉は言う。彼はどこまで歴史を知っているのだろうか。
「ルネサンスだ。文芸復興」
「少し古いかな。エル・グレコなら悪くはない」
楽しそうになつめの双眸がまばたく。エル・グレコは受胎告知の作家だ。
「一七世紀は、ヨーロッパにとって圧倒的に危機の時代だった。戦争。内乱。飢饉。世界的な寒冷の波が当時ユーラシア大陸を襲ったと言われている。気候はいつの時代だって重大な歴史の決定要因だった。寒きは草を枯らせ、食を細らせて人を歪めるんだよ。その証拠に、歴史上の最も陰惨な事件のいくつかはこの時代に起こった」
誉がくすくすと笑った。なんだか心当たりでもあるみたいな笑い方だった。
「魔女狩り」
「分かってるんじゃない」
陽射しのまっさらな白が彼らの輪郭を飛ばして春の目に映りにくくする。春は思わずまぶたを細くして会話の続きをかいま見ようとした。
「その中でね、ケプラーは星を見た」
チカッと、明かりが弾けたのが見えるようだった。
白墨が黒板を鳴らした。
「悲しい事件が起こっていたのと、惑星運動の法則が定められたのが同じ時代のこと。科学は、暗闇を照らす人の手の灯火だ。そうは思わないか」
春は陶然とした。なつめの言葉を聞くのはいつだって疾走する列車に乗るような心地だった。
ずっと聞いていたい。ほんとうにずっと聞いていたら、なんだかおかしくなってしまうのはおぼろげに知っているけれど。
はん、と一方で誉が鼻を鳴らした。聞き手がつい忘れる本筋に、強引に全員の意識を引き戻していく。
「じゃあ、きみにとっては科学こそが光で、それより前にあったものは冥盲というわけか。神も暗闇。さっき魔女狩りの話が出たね。じゃあ信仰は、なつめ、罪なき魔女を狩らせる悪者か?」
「まさか。よく聞いてくれよ」
なつめはめげない。少年の手が軽やかに踊る。
「ぼくが言いたいのはね、ケプラーは神学者だったってこと」
春はそれを聞いて横から目をぱちくりした。
天動説、というものを聞いたことがある。地球は動いていないのであって、回っているのは空の方だ。これに反する説を唱えた科学者は地位を追われた。なぜなら神の作った大地は静止していなければならないからだ。
ケプラーの話は、神の教えにまっこうから反しているように思われる。
彼が神学者だったならなら、なぜ。この先の話は、春も知らない。
「ケプラーはたとえ表面的に聖書に反していたとしても、真理の究明を行うことこそが信仰だと考えた。彼の信念はね、『神の作った宇宙は美しくあるべきだ』だったんだ。ケプラーの師匠にブラーエっていう人がいるんだけど、このブラーエも、当時としては珍しくないカソリック教徒だ。ブラーエは、火星の運動の解明をケプラーに託した。なんて言ったと思う? より���しく、より神にふさわしく在るように、世界の謎を解いてほしいと。そうなんだ。国立天文台で星を見た人々にとって、神さまは、世界の基盤だった」
なつめが客人の瞳を真っ直ぐに覗き込んだ。
「言いたいこと、わかる?」
「わかるともさ」
誉は薄く笑みを浮かべたままふわりと首を傾げた。なつめの横顔を照らす光が誉の髪にも木漏れ日模様を作っている。
「世界の仕組みを、科学で解明したとしても、その仕組みをそう定めたものを、神と呼ぶことには何の矛盾も生じない」
あぁ、と空気の残滓に胸を鳴らしながら、春は思った。
誉が正確にとらえた、なつめの話す言葉が、目の前を照らしていた。いつものように、遠いものと遠いものをその手に捕まえて、一瞬のうちに鮮やかに結び合わせる言葉。
春はこの言葉が大好きだった。黒板の前を跳ねる白い手が大好きだった。誉がどんな野望を抱いてこの粉屋に入ってきたのかはわからない。だけど、と春は思う。
この言葉に、彼の紡ぐ物語に、人は頭を垂れなかったら嘘なのだ。
なつめに勝てる人間なんて、この京都いっぱいを見渡したって一人もいない。
そうでしょう、ねえ、あなたも。
胸が詰まる。
明るい視界の真ん中を、体勢を変える黒い僧衣がすうっと横切っていく。
「きみもそれを『神』だと思っているわけ?」
「というのは?」
「『きみ自身も、世界の謎を謎と定めた力を神と呼ぶのか』ってことさ。ケプラーやブラーエの話じゃなくてさ?」
「そこまで言う必要があるかい?」
なつめは小さく笑った。
「信じる人にとって、そこに神のはたらきはある。それだけでいいだろう?」
「それじゃあなつめ」
誉の言葉の、色が変わった。
「問題だ。たとえば聖母像を抱いて崖から飛び込んだ女がいたとする。彼女は教義に反して穢れた女で、教会が彼女にそうすることを命じた。当人の女も、それで己の罪が清まるのなら良いと納得して死んだらしい。
それが啓示の結論だったとしたら、それは救いか、それとも破滅か?」
不吉なたとえだった。
春は眉をひそめて誉を見つめた。悪趣味な問いかけを口にした少年は、粉屋の薄い陽だまりの真ん中で薄く笑んでいる。
「見方によるよ」
なつめもやや不可解な顔をしていた。初めてそこで、なつめは話の流れを見失ったような表情をしたのだった。
「そのときの人々にとっては、どんなに悲しくても罪が清まるのなら救いだったかもしれない。彼らにとって神は在ったのさ」
「別の質問をしよう」
誉は答えを出さない。あくまで自分の裁量で話を進めてしまう。
「それじゃあ、信じる人たちが神の力と信じたところに、別の理由が見つかったらきみは教えてあげる? たとえば、天空じゃなくて地球が動いていた、みたいなことさ」
なつめがすこしの間黙った。
「それも場合によるだろう。事実の過誤で誰かが不利益を被るなら教える。そうでなければわざわざ本人たちに特別に伝えることはない」
「ふーん」
何が楽しいのか、誉はずっとにこにこしていた。
「きみは言ったね。『世界の説明できないことを説明しようとするのが学徒だ』って。そしてこうも言った、世界の仕組みを科学で解明し、その仕組みをそうと定めたものを神としても矛盾しないって」
なんだか不安な香りがした。春は思わず背中を硬くしながら二人のやり取りを交互に見守った。
「俺にはこう聞こえるんだよね。『まだ自分たちが説明できない事象のすきまには、特別に仮の説明として別の力を認めてやってもいい』って」
かたん、と、なつめが白墨を置いた。
その音をひどく乾いた音に感じた。春の呼吸が浅くなっていた。翳島は相変わらず微動だにしない。一瞬空の上を薄い雲が過って、粉屋に差す明かりの強さを変える。
話の内容は遠回しで、いったい何を見据えて議論が行われているのか春には判然としなかった。
なのに、はっきりと思う。流れが変わった。
春の聞きたくない話に、少しずつ部屋の温度は遷移していた。
「そこまで言ってないよ」
なつめは空気を振り払うように笑って言った。
「すでにわかっていることにだって、ときには人は救いを求める。花の花びらの枚数で恋人の気持ちを量ったりだとかね。それが一体くだらない行いか? 人が思いを託す場所として、信仰は尊い。ぼくはそう思うよ」
「『人が思いを託す場所』」
誉が鸚鵡返しにする。機械で打った文章を読み上げたみたいな声色。
「信仰は人にとって、さまざまな念慮を受け止めてくれるという意味で実益ある思想である。そういうこと?」
「何か間違ってる?」
なつめがふいに語尾を奪い取るように勢い込んで言った。その頬がわずかに紅潮していた。驚くくらい子供っぽく見える態度で唇を結んでいる。
「ぼくは確かに古くは神やもののけの領域とされてきた分野を解明しようとしている。だけどそうしたものを考え出してきた人の営みそのものを否定しようなんて思わないって、そう言っているんじゃないか」
「間違ってるだなんて、言ってないじゃないの。俺は絶対そんなこと言わないよ」
誉はけたけたと笑い声をあげた。その声が悪鬼じみて聞こえて春はがんと突然の頭痛を感じた。
「『そうしたものを考え出してきた人の営み』! そうさ、俺はそういうきみと話しにきたのさ。ねえ仁路なつめ、あんたとずっと話したかった」
その喋り方が、いつの間にかずいぶんあけすけになっていた。
誉がすいっと手を差し出した。その手に虎目石の数珠が絡みついているのを見て春はどこか気圧された。この少年は少なくとも形の上僧侶なのだ。
「人が神やもののけを考え出してきた。これがきみたちの思想だ」
説話を読むように言う。もう片手も差し伸べる。
「神が人を作り恩寵ではぐくんできた。これがたとえば、さっきの聖書の思想」
両手に概念を携えて較量するように、誉は笑う。
「さて、どっちが正しい?」
「どっちもだ」
迷いなく、なつめは言った。少し急いだような言い方だった。
「世界をとらえる枠組みは人によって違うんだ。間違い探しで勝負するものじゃない」
「ふん! そういうことにしておこうかね」
誉は笑った。凄惨な鬼のようにどくどくしく見えた。
「頭ではそんなふうに考えてるってことか。言葉の隙間から出るものはどうだか知らないけど。まあそれならいいんだよ、俺は少なくともきみがそう思う限りは何も言うつもりはない――」
春は無意識に後ろに手を伸ばして机の紙束を掴んでいた。
ずっと黙って聞いているばかりだった翳島がちょっと驚いたように物音に振り向いて春のほうを見た。春はそれに構う余裕はなかった。
「帰ってちょうだい!」
喉をつんざいて、口から叫び声がほとばしり出た。
春がそれに気づいたときにはもう自分の手が勝手に動いて手当たりしだいに握ったものを大きく振りかぶっていた。誉に向かってばさばさと古い紙やら乾いた筆やらを投げつけた。ぴょんと両手をひっこめた誉は人畜無害な子犬みたいな顔をして春をまばたきとともに見つめた。
「春ちゃん、お怒りかい?」
「帰ってちょうだい! 帰って! 出てって」
繰り返しながら喉が擦り切れる気がしてぜえぜえと息を吐いたら隣から大きな手のひらが伸びてきて肩を捕まえられた。春は続けて投げつけようとしていたインク瓶を空中で携えたまま無理に動きをとめた。翳島が諫めるような目をして春の腕を支えている。
「品のないことはやめろ」
「でも、だってっ、あの人が最初に喧嘩をけしかけてきたんじゃない! 翳島さんだって腹を立ててたはずだわ。ごろつきを送り込んで殴らせたんだって! それがこんなふうに座らせておくなんて間違ってるわ。最初から、追い返せばよかったのに、追い返したかったのに、来なければ……」
悔し涙が滲んで春は必死で奥歯を噛んで押しとどめる。春の居場所だったあたたかい粉屋を、踏みにじっている誉が許せなかった。
姫さまがいたらこんなとき、背中にふわりとけはいを香らせて落ち着かせてくれるのに、と春はひどく喪失を感じた。姫さまはどこにいったのだろう。姫さまならこの話をどんなふうに聞いたのだろう。春には理解できないことが多すぎた。教えてほしかった。
「泣くな、春」
「泣いてないわ」
ここで泣いたらまるで一人だけお子さまの癇癪そのものだ。敵のいる前でそんな姿を絶対に見せるわけにはいかない。
鼻をすすってきっと前を向いた。誉が軽い動作で席を立っていた。いつの間にかその黒い僧服姿が春の正面の数歩先にいる。
「御大層な送り出しをありがとうだね」
「茶化さないで」
見据える。睨みつける。視線で少しでも春の強さを伝えようとする。春は最初からこの少年を一瞬でも歓迎したことはない。
「あなたの神さまなんかわたしにはどうだっていいんだわ」
敵意を込めて少年の持ち掛けた論題を突き刺してやる。
誉はわざとらしく驚いたみたいににやついて目をぱちくりした。
「春ちゃん、なんか勘違いしてないだろうね」
「なに?」
「俺の格好見なよ。仏の門徒だよ。神さまの話は一般論。別に細かい話はいいんだけどさ。俺があっちの神信じてたらかえってこの話持ってこなかったよ。中から来る言葉はいつだって信用ならないものだからね」
何を言っているのか知らないが誉は十分信用ならない。彼の信仰が仏門だというのが彼の無粋さになんの関係があるのか。
黙って睨み返す春に音もなく近寄って、誉の手がぽんと春の胸元を突いた。春は目をぱちくりした。
「それから、きみもきみ自身にもっと誠実になるべきだと思うね」
正面で見ていたのに接近を許した。
自分への驚きが先に立って、聞いた言葉はよそごとのように響いた。意味をとらまえる前にぼんと心臓が爆発するように空気をいっぱいに取り込んだ。生命が冬の終わりに息吹をいっぱいに持ち上げるように、身体に燃え上がったような気がした。
春は思わず声を漏らした。
「あっ」
胸の空洞になっていた場所に知っているけはいが芽吹いた。正確にはそれは戻ってきたのだ。
『ぷはぁっ』
姫さまが、息を吹き返した。
春はぶわっと真っ赤になって自分の胸を押さえた。動揺やら昂奮やら、ずっと不安だったものへの安心と、色んな感情が一緒くたになって言葉が出なかったのだ。身体のない姫さまは久しぶりに家に辿り着いたように春の胸の中に疲れたようなけはいを溜めていた。『春』耳馴染んだ声が言う、『すまなんだ』
春は今になってぶるぶると抑えきれない涙が込み上げてくるのを感じていた。
「ねえっ、姫さま、今まで何がっ…………」
『説明はまたにさせよ。わらわも休みたい……』
「おいっ、てめぇ!」
至近で荒々しい声がして、春はびくっと顔をあげた。
幸い、というより当然のこと、その声はもちろん春に向けられたものではなかった。誉の背中に翳島が怒っていたのだ。僧服の少年はとっくに粉屋の入り口を出て、明るい三条の表通りに駆け出していた。
「止めるかい? まだ何か話し足りない?」
楽しそうにくるりと回る少年は言う。
「談義なら俺はいつでも付き合おう。俺自身の世界観で語って聞かせたっていいよ。今回はきみたちばかりに語らせてしまったからね。というより主になつめくんか。いや実に申し訳ない。翳島暁蔭(あきかげ)、だったっけきみは。きみもなかなかに面白い解釈を持っていそうな気がするんだよね。もしかしてきみのほうが賢いかもしれないとさえ思う。俺は賢い人間は好���だよ、愚かなのと同じくらいにね。ねっ、春ちゃん」
丸い瞳が春をとらえてにっこりと三日月を描いた。
「桜が散る前にまた会いたいな」
浮つくくらい気障な言葉。
「可能なら一回り大きくなって来てくれるととても嬉しい」
翳島が耐えかねたようにがんと踏み出して戸口の柱木を叩いた。
びいん、と建物全体が共鳴した。春は首をすくめて思わず目を閉じた。ひらひらと片手を振った誉はまるで遊ぶ途中の子供のように小さな背中で駆けていく。
その背中が見えなくなるまで、全員が黙っていた。
翳島がゆっくりと拳を下ろした。静かだった。
「まぁ、悪い夢でも、全員で見たんだろうと思おうや」
低い声だ。冗談にしてしまうには、粉屋の状況は奇妙に過ぎた。割れたランプ、乱れた机、少年が座っていた後に散らばった紙の束。
「あいつ、また来やしねえかな。このまま来やがらねえなら、こっちから関わってやる義理は二度とないんだが。なつめ、拠点を移すなり、色々考えるか。ここはちょっとあいつらのお膝元に近え気がするな。なつめ?」
軽い声で翳島は続けて、床に散らばったごみくずを拾いあつめるために腰を曲げた。なつめが付き合わないので、翳島はすこしして黙っている少年に向けて頭を持ち上げて呼びかけた。
日が動いて完全に影になった黒板のもとに、仁路なつめは古樹にでもなったように黙然と、身動きせずに佇んでいた。
その瞳がすこし憂えげに見えて、春は一歩歩み寄りかけた。
「なつめさん……」
呼ぶ前に、
「もう一回、話したいな」
なつめが言った。
翳島が度肝を抜かれた拍子に机の一つに肘をぶつけた。動いた机がごとごとと音を立てた。
「おいなつめ」
頬の青たんと一緒に痛々しい顔をして、翳島は机を挟んだままなつめに迫る。春もほとんど息をとめたままなつめの顔を見つめていた。少年は春たちのほうを見やることはなく、どちらかといえばぼんやりとさっきまで僧侶の少年が座っていた席のあたりをじっと見つめている。
まだ、議論の続きを考えているような顔だった。
「頭がいいと思ったんだ。ぼくとはきっと違う視点を彼は持っている」
「だからって……っ」
ここで声をあげたのは春である。だからってもう一回話したいなんて。だってあの人とても失礼な態度を取っていたのよ。だけど春のその言葉はうまく口から出なくて春は唇をごにょごにょさせた。失礼な態度だったのは、はて、具体的にはどの発言がそうだっただろうか。
「春や翳島は巻き込まなくてもいい。冬子も」
今は居合わせない仲間の名前をなつめは後ろから一つ付け足した。疎外されたようで春はかえってもやもやする。
「だけど、ぼくはもう一度、確認してみたい……」
姫さまのけはいがすっと胸の奥から出てきた。
その意図は分からなかったけれど、時を同じくして、なつめの茫洋とした瞳がようやく今現在に焦点を合わせた。はしばみ色の瞳がゆっくりと春を視界の真ん中に収めた。
「そうだね、春。……ぼくの『家』に来る?」
黙って春はなつめを見つめ返した。
それは議論のはじめに提示された春の知識の空白部分だった。なつめは春が置いてけぼりになっていたことを気にしてくれていたのかもしれなかった。
隣で机に手を突いていた翳島が、何やら言おうとして一度口を開けた。けれど何も言わなかった。姫さまのけはいが背中を包んでいた。
春が小さく頷くと、なつめが笑った。
次≫
もくじ
0 notes
Text
北九州平尾台の噂!魅力を語ります!
北九州平尾台の噂!魅力を語ります! 遊びいきてー!!
ども!ぽいずんくっきーMiです!
今回は国の天然記念物にも指定されています花崗閃緑岩(かこうせんりょくがん)からなる
平尾台について注目です!!
鍾乳洞等もあるので夏場は涼しいスポットですね!
映画のロケ地に使われる事も多い場所ですが色んな噂があります!
スポンサードリンク
心霊現象の噂
この噂は色々ネットに出ていますよね!その他の話はココから→北九州コレットの話
私も過去、バンドをしていた時に深夜、仲間と出かけた時。
道路に足首から下が道路にあったとか、カーブミラーに人が写るとか
首だけが地面から出ていたとか、さまざまな噂がありますよね!
確かに、北九州での数少ない峠でもあり走り屋的な人はよく事故をしたって話も聞きますね。
ガードレールがチョコチョコ変なとこで新しく変わってたりしてますからね。
平尾台内にある千仏鍾乳洞(せんぶつしょうにゅうどう)もパワースポットとしても有名ですよね!
View On WordPress
0 notes
Photo

【旅の記:博多ツアー2017年冬⑰高傳寺】
さ、この日も結構歩いています。。高傳寺にやってまいりました。曹洞宗の寺院で山号を恵日山、高傳禅寺とも言います。ご本尊は釈迦如来。1552年に龍造寺家家臣だった鍋島清房が創建。以後、佐賀藩鍋島家の菩提寺となっています。明治4年鍋島家11代直大により点在していた龍造寺・鍋島両家の墓所を集めて整備しました。
龍造寺家は肥前佐賀の国人で九州千葉家に仕えていたが、室町時代千葉氏に代わって北九州の守護となった少弐氏似る仕える。その後龍造寺家兼の時代に実力をつけていって大内氏に通じ、1535年少弐氏を裏切り自害に追い込み、大内氏庇護のもと独立、戦国大名となる。しかし主家裏切りと下剋上の恨みを買い、少弐氏重臣たちの調略により一族を多く殺され、一時壊滅的な状況に。生き残った家兼は筑後の蒲池鑑盛の厚い庇護を受け再起、大内氏の力を背景に家兼の後を継いだひ孫の隆信が龍造寺本家の家督も継承する。1551年大内義隆が家臣・陶晴賢の謀反で斃れると、後ろ盾を失い家臣の裏切りに会い、再び筑後柳川城城主蒲池鑑盛に身を寄せる。1553年蒲池氏の助けを借りて肥前を奪還し、その後は勢力を拡大。かつて主家であった少弐氏を完全に滅ぼし、肥前の国人を次々と下して1562年ころまでに東肥前を支配する。この急速な勢力拡大は周辺の大名を震撼させ、豊後の大友宗麟もこれを危険視し肥前に侵攻するが、龍造寺家家臣で義兄弟でもある鍋島直茂が安芸毛利氏に大友領への侵攻を要請して撤退させ、大友氏再度の侵攻も直茂の夜襲によって撃退する。これ以降直茂の存在はとても大きなものとなる。
これ以降、大友氏の圧力は完全に排除できなかったものの着実に力を蓄え領土を拡大、1578年有馬氏を下して肥前の統一を果たす。その年大友宗麟が耳川の戦いで島津義久に大敗すると、混乱に乗じて大友氏の領国を席捲、国衆たちを服属させて戦国大名となる。1581年には隆信と直茂が図り、大変お世話になった蒲池鑑盛の息子・鎮漣を肥前に誘い出して誅殺し柳川を制圧した。(鎮漣には島津家への内通があったようですが、お世話になったのにあまりにもひどい仕打ち、、という話にはなったようです)鍋島直茂は筑後の国政を担当することになるが、この頃調子に乗っていた隆信が直茂を疎んじ、離れた筑後を任せたとも言われる。しかしこの蒲池氏殺害は諸将の離反を招き、1584年龍造寺家の興隆を警戒していた島津氏が龍造寺から離反した有馬氏に協力して沖田畷の戦いが起こり、この戦いでなんと隆信は陣中討ち死にをしてしまう。戦場からかろうじて落ち延びた直茂は、一度は自害しようとするが、家臣に止められて肥前まで退き、隆信の息子・政家を補佐して島津家とのよりよい条件での講和を取り付ける。しかし島津氏に恭順すると見せかけて、早くから中央の豊臣秀吉に通じ、九州征伐がはじまるといち早く島津氏とは手切れとし、立花勢とと共に龍造寺勢も先陣を担って大いに働いた。
秀吉に高く評価された鍋島直茂は龍造寺氏とは別に所領を安堵され、政家に代わり国政を担うようになり、朝鮮出兵でも龍造寺家臣団を率いて参加する。
1600年関ヶ原の戦いでは、最初息子の勝茂が西軍に参加するが、直茂は東軍勝利を予測して、尾張方面の穀物を買い占め目録を家康に献上。関が原本戦前には勝茂を戦線から離脱させている。さらには近隣の西軍諸将の居城を攻め、久留米城を攻略、立花宗重の柳川城を降伏開城させた。一連の行動により家康から肥前国佐賀35万7千石は安堵されることとなる。
龍造寺政家の子・高房は幕府に対して実権回復を働きかけるが、幕府は鍋島直茂・勝茂の龍造寺からの禅譲を認め、また隆信の弟たちもこれを支持した。このことで直茂を恨んだ高房は直茂の養女である夫人を殺し、自殺を図った。直茂は隠居していた政家に「おうらみ状」という、高房を非難する書状を送る。高房は再度自害に及び死去した。。
その後、直茂は龍造寺家への敬意を表しながらも鍋島氏の藩統治を強固なものにしていった。しかし、直茂は龍造寺家への遠慮があってか藩主の座に就くことはなく、息子勝茂が初代藩主となっている。
1618年、直茂は耳にできた腫瘍による激痛の中悶死したとされ、これは高房の亡霊の仕業ではないかと噂されたそうです。。

鐘楼。

釈迦堂。

立派な山門!

ご本堂。受付で住職さんが丁寧に対応してくださり、本堂の電気もつけてくれました。

当時には日本最大級の涅槃図があるそうですが、残念ながら公開はしていない時期でした。。

大隈重信がこどものころに登って老僧に怒られたという槙の木。大隈の用命にちなんで八太郎槙と呼ばれる。やんちゃだったんだなぁ。

義祭同盟を中心となって結成した枝吉神陽の墓と、その弟でもあり外務卿を務めた副島種臣のお墓があります。書家としても有名な種臣は江藤新平の墓碑銘を手掛けた。

本堂裏手には龍造寺・鍋島氏のお墓がずらりと!

明治に入り西洋化がすすみ、廃仏毀釈の風潮のなかで11代直大は両家のお墓を集めて整備したという。。

梅の時期はとてもきれいだそうです。


0 notes
Text
各地句会報
花鳥誌 令和3年6月号
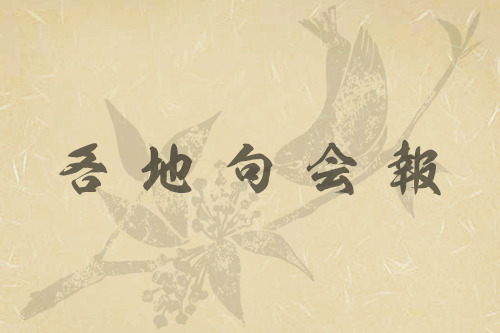
坊城俊樹選
栗林圭魚選 岡田順子選
………………………………………………………………
令和3年3月3日
立待花鳥俳句会
坊城俊樹選 特選句
川原の景色を替へる猫柳 世詩明
一生を投げ打つ如く嚔かな 同
冴え返る明智神社の石仏 ただし
段ボール迷路の遊び春立ちぬ 同
夜な夜なに表はれくるや雪女 輝 一
楤の芽を楤の木撓め採りにけり 誠
(順不同特選句のみ掲載)
………………………………………………………………
令和3年3月4日
うづら三日の月
坊城俊樹選 特選句
三姉妹雛に劣らぬ顔に見ゆ 喜代子
水温み何か動めく川の底 都
古雛のどこかやつれて品のあり 同
雪音のそれらしき音春きざす 同
(順不同特選句のみ掲載)
………………………………………………………………
令和3年3月5日
花鳥さざれ会
坊城俊樹選 特選句
飾られてふと笑み給ふ女雛かな かづを
故山笑む遠嶺は未だ覚めずとも 同
三月の鳥語艶めく故山かな 同
雛の世に及びし人の世の流転 雪
春愁か考へてゐる横顔か 同
古鍬にくさび打ち込み春耕す 匠
石仏の頭巾乾ける四温かな 同
三月や恐竜の吠えまろやかに 数幸
三月やクレーンアームの手の捌き 同
雛の間をちらと横切る男の子かな 笑
足裏に春芽の息吹はたと受く 同
ランドセル春のジャンケン沈下橋 天空
(順不同特選句のみ掲載)
………………………………………………………………
令和3年3月6日
零の会
坊城俊樹選 特選句
ふつくらと日当たる乙女椿かな 小鳥
春の池ぐちやぐちやにスワンボートかな 和子
落つる時少しあからむ椿かな 三郎
ひたひたと岸をゆたかに春の水 悠紀子
春禽と真正面よりみつめ合ふ 久
切り株の洞に雨水の匂ひかな 要
マネキンの裸身をなぞりゆく春日 順子
子の櫂に春の一日を委ねをり 久
落椿白より赤の朽つる日に 和子
岡田順子選 特選句
銭洗ひ丁か半かよ春の水 きみよ
橋渡りしはとしあつ師かと亀の鳴く 瑠璃
水温むちよつと先行きや神田川 荘吉
白き空吸ひこむやうに鳥帰る 三郎
切り株に集め積まれし落椿 小鳥
古着屋の中東の香の春ショール きみよ
武蔵野や鳥の繋いでゆく木の芽 千種
鳥交るベンチに人はものを食ふ 和子
少女うつむき三椏の花嫌ふ 俊樹
スワンボートを漫画にしたる霞かな 同
ひらり乗る赤い自転車受験果つ 光子
(順不同特選句のみ掲載)
………………………………………………………………
令和3年3月8日
武生花鳥俳句会
坊城俊樹選 特選句
忠魂碑あたり群がる土筆かな 世詩明
鳥帰る網を繕ふ人の上を 清女
ものの芽に狭庭の月日始まれり 信子
古墳群一叢侘し筆の花 世詩明
春蘭の秘めたる恋の色に咲く 中山昭子
指先に血を騒がせて土筆摘む 世詩明
鞦韆に二人腰掛け黙の刻 中山昭子
雛納む鬢のほつれを撫で申し みす枝
涅槃会や朱唇輪袈裟の六地蔵 世詩明
無人駅それからの道つくづくし 同
雪吊の男結びの解き難し ただし
光秀の駆けたる道の犬ふぐり 清女
(順不同特選句のみ掲載)
………………………………………………………………
令和3年3月8日
なかみち句会
栗林圭魚選 特選句
山焼くや旬日にして利休色 怜
医薬門くぐれば春の水の音 和魚
雨戸繰る芝生青むと思ふ朝 怜
ほし鱈の炙りて尾びれ香ばしき 貴薫
木洩れ日の影やはらかき菫草 三無
落日に白木蓮のかがやきて 迪子
信濃路に虚子の句碑ありこぶし咲く 同
水温む蛇口の水も柔らかし 史空
黄水仙声高らかに話す人 ます江
凜として月光纏ふ花ミモザ 同
(順不同特選句のみ掲載)
………………………………………………………………
令和3年3月9日
萩花鳥句会
リハビリに縮緬手作りお雛様 祐子
薄化粧の少女ミモザを抱へ来し 美恵子
精霊の海へ十年涅槃西風 健雄
言葉では感謝しきれぬ卒業生 吉之
鳥帰る水面に白き羽根二本 陽子
青き踏み幼児二人の鬼ごつこ ゆかり
稚児走る河津桜に染めし頰 明子
伐られたる古木の椿より新芽 克弘
(順不同特選句のみ掲載)
………………………………………………………………
令和3年3月12日
鳥取花鳥会
岡田順子選 特選句
島浦の遊具に少女初桜 栄子
黄水仙俯く顔を上げさせて 史子
馬酔木咲き石灯籠に垂れきし 同
番号で呼ばれる廊下春寒し 佐代子
面差しの失せし弁天蝶を呼び 都
湖を駆け来る綺羅よ春時雨 美智子
風紋の襞より雲雀転げたち 悦子
夕東風や遊覧船はドック入り すみ子
(順不同特選句のみ掲載)
………………………………………………………………
令和3年3月13日
芦原花鳥句会
坊城俊樹選 特選句
真昼間の一人の時間犬ふぐり よみ子
暁は春雪洞の灯をともし 依子
失せし物こつと現る春の風 よみ子
(順不同特選句のみ掲載)
………………………………………………………………
令和3年3月13日
札幌花鳥会
坊城俊樹選 特選句
右打者のライト方向春一番 のりこ
春水をふはりとゆらす真鯉かな 清
サンバ打つ雪解雫や倉庫群 雅春
春待ちて大地踏みしめたき足裏 同
葬り終へゆつくり帰る雪解道 慧子
(順不同特選句のみ掲載)
………………………………………………………………
令和3年3月16日
伊藤柏翠俳句記念館
坊城俊樹選 特選句
椿落つ太郎冠者てふ良き名にて 雪
炬燵猫人の機嫌に拘らず 同
春満月西行偲ぶ野の明かり みす枝
万蕾の膨らむ音や山笑ふ 同
早春賦歌へば少女なりし頃 玲子
耳たぶに三月の風そよと來て 和子
枯れし木に炎のやうな牡丹の芽 英美子
春塵や嫁ぎゆきたる娘のピアノ 同
目鼻なき狐の嫁入り雛飾り ただし
橋梁の浦の越路や海おぼろ やす香
陽の落ちて瞑想深し座禅草 同
啓蟄や村を出て行く次男坊 世詩明
妻に云ふ言葉探しに青き踏む 同
(順不同特選句のみ掲載)
………………………………………………………………
令和3年3月17日
福井花鳥句会
坊城俊樹選 特選句
菜の花の畑の先に滑り台 千加江
蒼天へ梅の一枝に花二輪 同
はだら雪見えて母娘にある禁句 清女
春立つと雀は軒に鳴きたがる 雪
美しく止りて春の鳥となる 同
夢に見し椿此の世の色ならず 同
春愁のこけしの一重瞼かな 同
案外な男のくれし桜貝 同
(順不同特選句のみ掲載)
………………………………………………………………
令和3年3月21日
風月句会
坊城俊樹選 特選句
騎馬像や辛夷に太刀を振り下す 幸風
春雨に旧き薬舗の濃き匂ひ 貴薫
料峭の軒触れ合へる神仏 千種
春雨にけぶる漆喰薬舗かな 慶月
日のにほひまとひて雨の桜かな 幸子
栗林圭魚選 特選句
春雨に旧き薬舗の濃き匂ひ 貴薫
春光の逆立つ川を遡り 千種
茅葺きの春の嵐を吸収す 慶月
太古の樹春雨にぶく光り落つ ます江
せせらぎに木五倍子の花の鎖垂れ 三無
日のにほひまとひて雨の桜かな 幸子
里桜武蔵国原見晴らして 久子
武蔵野や仄かに香る木の芽雨 三無
(順不同特選句のみ掲載)
………………………………………………………………
鯖江花鳥俳句會
坊城俊樹選 特選句
男ふとつらつら椿てふ一語 雪
竜の鬚こぼしてをりぬ竜の玉 同
地虫出づ大きな顔に覗かれて 同
老人と認めぬをとこ春の風 上嶋昭子
地に還るまでのくれなゐ落椿 同
土筆摘む老女の中に棲む少女 信子
金泥の胸の大きな寝釈迦かな ただし
春灯や女横顔エゴイズム 世詩明
立子忌や続く愛子忌女どち 同
(順不同特選句のみ掲載)
………………………………………………………………
枡形句会
栗林圭魚選 特選句
ままごとの客人として雛あられ ゆう子
芳墨の古寺の扁額弊辛夷 幸風
手のひらの小さき折雛緋色して 美枝子
鰐口の連打に応へ木の芽吹く 百合子
ぎつしりと野の香の詰まる蓬餅 三無
てんでんに句碑の梅訪ふ親しさよ 文英
大川の流れ華やぐ桜東風 秋尚
大空に向けて蹴り上ぐ半仙戯 幸風
陽子姉の形見の雛今年また 多美女
強東風に硝子戸軋むそば処 三無
(順不同特選句のみ掲載)
………………………………………………………………
さくら花鳥会
岡田順子選 特選句
風を読む浜の男の子やいかのぼり 登美子
春来たる駅前恐竜空に啼く 令子
鳥群るるまだ白がちな春山に あけみ
紙雛のいつの間にやら数増えて 裕子
花雪洞の寄付の名俳句教室と 令子
晴の窓雪解雫の影流れ 紀子
山門へ敷き延ぶ筵草萌ゆる 令子
(順不同特選句のみ掲載)
………………………………………………………………
九州花鳥会
坊城俊樹選 特選句
山桜なべて浄土の風はらむ 佐和
春泥の古鏡のごとき光かな 睦子
温む水こはさぬやうに鷺下りる 孝子
失敬と手を上げ君は鳥雲に 美穂
散る花の音も気づかず彷徨ひて かおり
軒端まで流れてきたる冬銀河 佐和
鳥帰る記憶の道を迷ひけり 美穂
真つ直ぐに生きし柩よ梅真白 成子
解かれある上がり框の花衣 かおり
春泥を跳び損ひし子へ呪文 美穂
迷ひこむ少年老いし冬木立 佐和
天上のこゑ雲雀野は古墳趾 志津子
しばらくはシテの桜でありにけり 睦子
寄す波も消えゆく波も鳥曇 かおり
春の泥行きつ群れゆく鳥けもの 同
(順不同特選句のみ掲載)
………………………………………………………………
0 notes