Text
東京レインボープライドにアマゾンとマクドナルドとの協働中止を要請します~イスラエルのアパルトヘイト・ジェノサイドに加担する企業とは決別を~
NPO法人東京レインボープライド御中
LGBTQ+とアライのみなさま
東京レインボープライド(TRP)は3/15に「パレスチナ・イスラエルをめぐる現状に関するお問い合わせについて」という声明を発表しました(*1)。これは、現在5か月を超えて激化しているガザ・ジェノサイドを非難し、これに加担しない意思を表明するために、イスラエル大使館やアパルトヘイト支援企業からの協賛は受けないことを明らかにしたものだと思います。
しかし、現状では、これは事実に反する虚偽となってしまっています。
わたしたちフツーのLGBTをクィアする等からの公開質問状や多くの問い合わせに言及した上で「特定の企業や大使館からの協賛はございません」と述べられていますが、問い合わせの第一義的なポイントはBDS対象企業(*2)であったにもかかわらず、まさにそれに含まれているアマゾン(*3)とマクドナルド(*4)からの協賛がホームページに掲載されているからです。ゆえに上記の記述は明らかに間違っており、現実に実行されていないものとなっています。
TRPは公開質問状に「回答拒否」をしましたが(*5)、これまで、わたしたちや多くの人がTRPに対して問い合わせ・要請をおこなったのは下記のことです。
2013年以来11年間にわたって続けてきたイスラエルのアパルトヘイトや戦争犯罪への共犯と決別すること。
ピンクウォッシングを終わらせること、つまりプライド・パレードを虐殺のノーマライゼーション/プロモーションの場として利用させないこと。
そのために同国大使館やアパルトヘイト支援企業(BDS対象企業)から協賛を受けるのをやめること(とりわけ近年協働が続いてきたアクサとヒューレット・パッカードを蓋然性の高い主要なターゲットとして)。
ところが、TRPはそうした問い合わせ・要請の趣旨を捉え損ねたのか、あるいは評判への配慮のみにしかもあまりに限定的な留意しか払わなかったためか、きたるTRP2024でも共犯を続けて重大な人権侵害から利益を得ることを「次世代につなげていく」道を取ろうとしています。それは「すべての人たちの人権が守られる社会を実現するために」と言うTRPにとって、まったく不本意なのではありませんか。
■■■ TRPへの要請 ■■■
(1). 「すべての戦争、虐殺、暴力や弾圧に反対しています。また、多くの命が失われている現状に対して強い憤りを感じています」との言葉が本当の思い、真実であるならば、ジェノサイドを支援しているマクドナルドとアマゾンからの協賛をTRPが受けることはできようはずもありません。すぐに、これらの協賛を取りやめることを決定し、その手続きに入ってください。
(2). 以上述べたように、「お問い合わせを頂いている特定の企業…からの協賛はございません」との記述は事実に反するものとなっており、「すべての戦争、虐殺、暴力や弾圧に反対」「強い憤り」という記述も虐殺加担企業が協賛に含まれている現状と矛盾したものとなっています。そのため、(1)の協賛取りやめが実現するまでのあいだ、TRP法人サイトの虚偽を含む声明文を削除するよう求めます。
3/31(日) までにこれらの要請へのご回答をお願いします。(お尋ねなどありましたら、気軽にご連絡ください。)
■■■ みなさまへの呼びかけ ■■■
ガザそしてパレスチナでの虐殺・占領を一刻も早く止めるために、東京のプライドをその共犯から決別させるために、もう一度、みなさんの声をTRPに届けてください。
【TRP公式ウェブサイト (問い合わせ)】 https://tokyorainbowpride.com/contact/
【TRP公式Twitter/Xアカウント】 @Tokyo_R_Pride
#共犯と決別する回答を
#TRPはアマゾンとの協働中止を
#TRPはマクドナルドとの協働中止を
#ジェノサイドにプライドはない
2024年3月17日
フツーのLGBTをクィアする
フェミニズムとレズビアン・アートの会
(*1) https://tokyorainbowpride.org/news/20240315/2042/
(*2) https://bdsmovement.net/Act-Now-Against-These-Companies-Profiting-From-Genocide
このリンクはすでに昨年12/28公開質問状で示しており、当時からアマゾンもマクドナルドもBDS対象企業に含まれていました。そして、1月初めにはマクドナルドに対する世界的なボイコット・キャンペーンの促進が呼びかけられています。
(*3) https://www.notechforapartheid.com/
アマゾンについては12/28公開質問状でも圧力をかける対象であることに注意喚起していました。
(*4) https://bdsmovement.net/Boycott-McDonalds
(*5) https://feminism-lesbianart.tumblr.com/post/740022720990953472/trp2024-noresponse
---
PDF版はこちら。https://drive.google.com/file/d/11cV05SHD7_196Hv2kXPU0SzHkIPQaCAV/view

#trp#open letters#pinkwashing#フツーのlgbtをクィアする#bds#2024#palestine#israel#no pride in occupation#共犯と決別する回答を#TRPはアマゾンとの協働中止を#TRPはマクドナルドとの協働中止を#ジェノサイドにプライドはない
2 notes
·
View notes
Text
NPO法人東京レインボープライドが公開質問状に「回答拒否」。みなさんの声をTRPに届けてください!!
“お世話になっております。お問い合わせいただいた件、お返事が遅くなり申し訳ございません。弊団体は基本的に個別のアンケートやお問い合わせに関しては、回答しておりませんのでご了承ください。
いただきましたご意見は、今後の運営の参考にさせていただきます。
この度は貴重なご意見を賜りありがとうございました。”
――NPO法人東京レインボープライド事務局
回答期限から1日遅れた1月19日、去る12月28日に送付した「東京レインボープライド2024へのイスラエル大使館とBDS対象企業からの協賛についての公開質問状〜植民地主義と民族浄化・ジェノサイド共犯と決別するために〜」に対して、TRPから上記のとおり「回答拒否」の返信がありました。
100日を超えたガザ・ジェノサイドを目撃してもなお、TRPは、これまで11年間ピンクウォッシングに加担し続けた過ちを認めず、人権侵害の共犯を続けるつもりなのでしょうか?
TRP2024のテーマのページに掲げられている、
「多様な誰もが公平に、そして自分らしく幸せに暮らせる未来のために」
という言葉は、本当に実践するつもりなどない「ただのお題目」に過ぎないということなのでしょうか?
https://tokyorainbowpride.com/news/notice/35939/
ガザそしてパレスチナでの虐殺・占領を一刻も早く止めるために、東京のプライドをその共犯から決別させるために、みなさんの声をTRPに届けてください。
#共犯と決別する回答を
#TRPはアクサから協賛を受けないで
#TRPはヒューレット・パッカードから協賛を受けないで
#ボイコット・アパルトヘイト国家イスラエル
#ジェノサイドにプライドはない
【TRP公式ウェブサイト (問い合わせ)】 https://tokyorainbowpride.com/contact/
【TRP公式Twitter/Xアカウント】 @Tokyo_R_Pride

15 notes
·
View notes
Text
東京レインボープライド2024へのイスラエル大使館と
BDS対象企業からの協賛についての公開質問状
〜植民地主義と民族浄化・ジェノサイド共犯と決別するために〜
NPO法人東京レインボープライド 御中
貴団体の長年にわたるLGBTQ+権利運動への貢献に敬意を表し、感謝申し上げます。
きたる2024年においても、プライドに集うことを心待ちにできることは多くの人にとって大きな喜びにつながるものと思います。
1994年の東京での最初のパレード以来、プライドは良くも悪くも大きな成長を遂げてきた観がありますが、その過程で、東京レインボープライド(TRP)が、立ち上げから間もない2013年から東京五輪開催を控えた2019年までの7年間にわたり、イスラエル大使館の協賛を受け続けてきたことを振り返らないわけにはいきません(*1)。当時、すでに「イスラエルのピンクウォッシング」が活動家・研究者などに知れわたっている状況になっていたにもかかわらず、同大使館のブース出展やステージ登壇、広告掲載などを通じてTRPはピンクウォッシングに協働し続けました。このことは、長年のパレスチナの人びとの苦難を敢えて無視するのみならず、イスラエルによる暴虐・戦争犯罪に敢えて加担し、それを常態化させ加速させることにほかなりませんでした。そして、現在、2023年10月7日以来、とめどもなくガザ地区(人口の半分が子ども)と軍事占領下のパレスチナ全土に襲いかかっているイスラエル国家によるジェノサイドと民族浄化(殺戮、傷害、破壊、強制移住、集団飢餓、非人間化)につながる役割を果たしてしまったと認めざるをえないのです。
イスラエルによる犯罪への加担を看過・許容した人びと、止めることができなかった人びと、わたしたちは、その責任の重大さを痛感せねばなりません。同時に、これを終わらせるために行動を起こす必要があります。
この大きな失敗をしっかりと踏まえ、二度と繰り返さないために、今こそ、貴団体がその立場を鮮明にするべき時ではないでしょうか。
大量虐殺者の側に立つのか。土地を追われ、財産を奪われ、殺されている者の側に立つのか。
人権運動に連なる団体として、あまりに自明のことかと思います。
貴団体は、ウェブサイトでこう述べています。
「多様な誰もが公平に、そして自分らしく幸せに暮らせる未来のために、私たちはあきらめない。」
……多様性・自由・平等をもとに謳われたその「幸せに暮らせる未来」は、誰かを踏みつけた上に築かれたものであってはならないはずです。LGBTQ+の生と権利は、西側先進国の特権などではなく、日本を含めたグローバルな先住民の権利運動や入植者植民地主義抵抗運動との連帯を強めなくてはならないでしょう。
「これまで積み重ねてきた歩みをみなさんと共に振り返り、しっかりと次世代につなげていく、そんな機会にしたいと考えています。」
……現在地までを「共に振り返り、しっかりと次世代につなげていく」ために、わたしたちは、貴団体に対し、以下、2点を質問させていただきます。
(質問1)TRPは、2020年〜23年においては、イスラエル大使館の協賛やブース出展などは受けていないものと認識していますが、これは間違いないでしょうか。
また、2024年において、そして、イスラエル国家がパレスチナの占領・アパルトヘイトを終結させるまで、たとえ先方から協賛の申し出があったとしても受けることはないと誓約してくださいますか。
(質問2)これまでの取り返しのつかない失敗をあがない、二度と繰り返さないための方法、その一歩として、「Queers in Palestine」(*2)からの要求に応答することが可能です。その第1項は、「イスラエルの資金提供を拒否し、イスラエルのすべての機関との協力を拒否し、BDS運動(*3)に参加してください。」という要求です。
TRPが2017年〜23年に協賛を受けたアクサ(AXA)、2020年・21年・23年に協賛を受けたヒューレット・パッカード(HP/HPE)は、パレスチナの市民社会からボイコットが呼びかけられている企業です。AXAとHP/HPEにとって、TRPはよい評判を得るための絶好の機会ですが、それで血塗られた手を拭うことはできません。ジェノサイドと共にあるプライドなどありえず、TRPがピンクウォッシングに協力すれば、プライドを売り渡し、パレスチナ殺戮に手を染めるに等しい事態となります。日本と世界のLGBTQ+コミュニティーズを背景に得てきた力を持つTRPが、両企業からの協賛を絶つことには重要な意義があります。パレスチナのクィアと人道の危機からどうか目を背けないでください。
2024年において、そして、AXA、HP/HPEがイスラエルのアパルトヘイト政策を支援してパレスチナでの人権侵害から利益を得ることをやめるまで、たとえ両企業から協賛の申し出があったとしても受けることはないと誓約してくださいますか。
ジェノサイドと民族浄化、占領暴力を終わらせる行動の輪に加わってください。
事態の緊急性が高いため、恐れ入りますが、2024年1月18日までにご回答いただけますよう、お願いいたします。
お尋ねなどありましたら、気軽にご連絡ください。
なお、この質問状は送付と同時に公開させていただきます。
2023年12月28日
フツーのLGBTをクィアする
フェミニズムとレズビアン・アートの会
足立・性的少数者と友・家族の会
レインボー・アクション
(*1) わたしたちは、この間、毎年なんらかの形で批判を行い、2016年、18年、19年にはイスラエル大使館協賛にかんする抗議文を発出してきましたが、これに対し残念ながらイスラエル大使館とTRPから一度も応答はありませんでした。
https://feminism-lesbianart.tumblr.com/tagged/trp
(*2) https://queersinpalestine.noblogs.org/post/2023/11/08/87/
「パレスチナのクィアからの解放へ向けた要求」(日本語あり)
声明に賛同署名できます。脱植民地化解放運動に積極的に関与することが必要です。
(*3) https://bdsmovement.net/Act-Now-Against-These-Companies-Profiting-From-Genocide
南アフリカ共和国のアパルトヘイトを終わらせた国際連帯運動にならい、BDS=ボイコット・ダイヴェストメント(投資引き上げ)・サンクションズ(制裁)を呼びかける国際キャンペーン。
AXAのボイコットについては → https://bdsmovement.net/axa-divest
HP/HPEのボイコットについては → https://bdsmovement.net/boycott-hp
https://bdsmovement.net/BoycottHP-GazaGenocide-Update
(TRPが協賛を受けた日本ヒューレット・パッカードはHPE系の企業です。HPブランドの企業・製品・サービス全てがボイコット対象です。)
なお、近年にTRPが協賛を受けてきたアマゾン(Amazon)、Disney、Airbnb、Googleも、現在、圧力をかける対象となっています。
-----
PDF版はこちら。https://drive.google.com/file/d/1OXBOBd9rTU2lq0RXhcVX7Eg_Bfbt5Tpr/view

2023年1月20日追記:NPO法人東京レインボープライドからの返信https://feminism-lesbianart.tumblr.com/post/740022720990953472/trp2024-noresponse
10 notes
·
View notes
Text
バトラー『アセンブリ』オンライン読書会

■ テキスト:ジュディス・バトラー 著、佐藤嘉幸、清水知子 訳『アセンブリ―行為遂行性・複数性・政治―』 (青土社, 2018) http://www.seidosha.co.jp/book/index.php?id=3126
Judith Butler, Notes Toward a Performative Theory of Assembly (Harvard UP, 2015) https://www.hup.harvard.edu/catalog.php?isbn=9780674983984
■ 日程:2020年11月23日月曜日から、月曜日と金曜日、全7回*
午後7時30分~9時30分 (日本標準時)
*2020年11月23日 (月), 27日 (金), 30日 (月), 12月4日 (金), 7日 (月), 11日 (金), 14日 (月)
■ 開催方法:Zoomミーティングを使います。
追記:資料の共有や読書会参加者同士の交流を目的としてSlack (https://slack.com/) を使用します。Slackには登録せず/参加せず、Zoomでの読書会のみ参加することも可能です。 (2020/11/17)
■ 参加費:無料
■ 申込み方法:
- こちらのページから 名前とメールアドレス、参加予定日 (複数選択できます) を登録してください。名前は 「名」(First Name) の欄が必須項目になっています。 Zoomに参加するときの名前、またはご自身が呼ばれたい名前を入れてください。この登録フォームで主催者 (janis) だけでなくZoom社に情報が送られます。https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZYlceGupz0uGNEBZPvgq162V6CL7U8Psb4Z
- 自動でZoom社から参加リンクが送られます。 各回20人くらいまで。(2020/11/30変更 登録者数が多くなってきたので手動承認に切り替えました。)
- 性別・性自認・性指向・国籍・学歴・障害の有無など不問。
- 分からないこと、不安な点があれば janis までメールをください。 [email protected]
■ 進め方:この読書会では、2015年に発行されたJudith Butler の Notes Toward a Performative Theory of Assemblyという本を1回1章ペース、計7回で読みます。日本語翻訳は、2018年に 『アセンブリ―行為遂行性・複数性・政治―』 というタイトルで佐藤嘉幸と清水知子の共訳が青土社から出ています。 テキストは図書館等で借りるなどしてご自身で用意してください。
毎回最初の30分程度は内容を確認し、できるだけ何が書かれているのかを理解した上で、残りの時間で気がついたところや考えたこと、疑問に思ったことを音声と文字チャットを使用して共有します。
参加前に読み終わってなくてもかまいませんが、どの言語版でもいいので、できる範囲で少しでも予習してくると楽しいですよ。
ディスカッションは日本語(音声と文字チャット)の予定です。 カメラは全員オフです。入室時は参加者の マイクをオフにします。進行は音声で、参加は文字チャットのみでもできます。
参加者の方には、各回ごとに文字チャットで自己紹介+αをお願いします(おなまえと参加理由、加えて感想や質問があればそのときに)。
■ 企画意図 (2020/11/24追記):
2018年夏以降、日本語圏のTwitter上で加速したトランス排除的なフェミニズム言説は、2020年11月までに相当広範に普及してしまっています。 わたしは 、こうした状況への抵抗の足がかりとして、 日々の騒乱から少し離れて、尊厳が脅かされない場で、すでにあるトランスやクィアのフェミニストたちの言葉を、他の人たちとともに読むことに政治的な意義があると考えています。
FLAでも2020年2-3月は米国のトランス・ポリティクスについての本を、また8月には英語圏の反トランス・フェミニズム批判の本を読みました。近年のグローバルなトランス排除的な言説の急激な増加は、とくに1990年代以降カトリック教会や右派が国境を越えて展開してきた反「ジェンダー・イデオロギー」運動とつながっているので、10月にはその現状をまとめて伝える報告会も開きました。
ところで、集会にしろ、デモにしろ、こういった催しにしろ、集まりの目的はあり、それに多くの参加者は賛同して集まります。企画者は必ず目的を表明します。FLAのような小さなグループでやるときは、そうした言葉を伝えること、インターネット上に痕跡が残ることの意義もあるでしょう。
けれども、先日の反「ジェンダー」運動についての報告会のときに60人ほどの申込者の方たちが書かれた理由からわたしが読み取ったのは、テーマそのものや内容についての関心からだけでその人たちが申し込んできていないということでした。(おそらくこの2年ほど日本語圏インターネット上で増悪しているトランス差別の影響が大きいですがそのことに限らず) いまのこの現状において何らかの切迫した事情、この報告会に時間を割くだけの事情があり、あるいはこういう機会にある集まりに参加すること自体の意味がその人にあったと考えた方が、納得がいくように思えたのです。
何か人が集うときは、その中身は当然大事だし、企画意図も大事です。企画者が誰なのかも、その空間がどういう風に運営されるのかも大事です。無視していいわけがない。けれども、人が集まること自体の意味が、そこに集まることを躊躇するときにも、それが可能ではないときにすら、やはりあるように思います。
それで、そうしたことがテーマになっている『アセンブリ』の読書会を、2020年11月にすることにしました。
今回はこの「企画意図」の部分が事前に書けず、そのために限定的にしか広報ができませんでした。第1回 (2020/11/23) はすでに終了していますが、11月24日現在まだ申込みは可能です。
■ スケジュール:
11/23 (月)
序論
Introduction
11/27 (金)
第一章 ジェンダー・ポリティクスと現れの権利
1. Gender Politics and the Right to Appear
11/30 (月)
第二章 連携する諸身体と街頭(ストリート)の政治
2. Bodies in Alliance and the Politics of the Street
12/4 (金)
第三章 不安定(プレカリアス)な生と共生の倫理
3. Precarious Life and the Ethics of Cohabitation
12/7 (月)
第四章 身体の可傷性、連帯の政治
4. Bodily Vulnerability, Coalitional Politics
12/11 (金)
第五章 「私たち人民」――集会(アセンブリ)の自由に関する諸考察
5. “We the People”—Thoughts on Freedom of Assembly
12/14 (月)
第六章 悪い生の中で良い生を送ることは可能か
6. Can One Lead a Good Life in a Bad Life?
最終更新日:2020年11月30日 手動承認に切り替え (残席わずか)、 11月24日 企画意図を追記、11月17日 Slack使用予定を追記
#study group#judith butler#notes towards a performative theory of assembly#アセンブリ#zoom meetings#queer theory#2020#online events
2 notes
·
View notes
Text
オンライン報告会:英語圏トランス差別言説と反「ジェンダー」運動の現状
2020年10月15日:新規申込みは締め切りました。
日時:2020年10月16日 (金) 19.30~21.00 (JST) [1.5時間]
方法:Zoomミーティングを使用します
参加費:無料
報告者:janis (フェミニズムとレズビアン・アートの会 (FLA))
近年の英語圏反トランス言説と、グローバルに展開されている反「ジェンダー・イデオロギー」運動の現状を日本語でまとめて報告します。
当日はこちらのリンク集にある英語の文献等を参照します。(日本語の紹介記事や翻訳があるものには★星印からリンクがついています。https://transinclusivefeminism.wordpress.com/link-english/
また「アンチ・ジェンダー」のタグがついた記事は、今回のテーマに関連して参考になると思います。
申込・詳細はこちらから (Googleにログインする必要があります)。
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScCLWZlUIixg2j8WB9xVfWkEb-ZtJaIo9DARm7hDKalLC5hzQ/viewform?usp=sf_link
問い合わせは janis (at) selfishprotein.net (janis) まで。
【企画詳細】ナショナリズムとレイシズムが増悪する文脈において、過去10年バチカンを中心にキリスト教右派がグローバルに展開してきた反「ジェンダー・イデオロギー」運動が、各地での強権的な政権の長期化や極右勢力の主流化とともに、非常に活発になっています。(ここでのナショナリズムとレイシズムの増悪というのは、ホロコースト否認論や反ユダヤ主義、イスラモフォビア、反移民感情の高まりを指します。 )
反「ジェンダー・イデオロギー」運動※は、性別二元制を前提とする異性愛規範をベースに、近代の核家族制度を守るべき価値とする世界的なキャンペーンです。
※ 反「ジェンダー・イデオロギー」運動について参考情報:
Gillian Kane. 2018. ‘Gender ideology': big, bogus and coming to a fear campaign near you. Guardian. 30 Mar. https://www.theguardian.com/global-development/2018/mar/30/gender-ideology-big-bogus-and-coming-to-a-fear-campaign-near-you
Mallory Moore. 2019. Gender Ideology? Up Yours. Medium. 24 Jan. https://medium.com/@Chican3ry/gender-ideology-up-yours-470575a5311a
この運動は、これまでから「ジェンダー理論」や「ジェンダリズム」「ジェンダー・イデオロギー」といった用語を、こうした価値観に対立する攻撃対象を粗雑にまとめるサンドバッグ的に利用し、セクシュアル&リプロダクティブ・ライツ/ヘルスを侵害し、LGBTQ+の存在そのものを否定してきました。
こうしたなか、トランスナショナルなネットワークに支えられたフェミニズムへのバックラッシュにあらためて注目し、警戒をいっそう強める連帯の動きもあります。https://blogs.lse.ac.uk/gender/category/anti-gender/
念のために書きますが、国家/宗教/資本の権力に織り込まれた非規範的なセクシュアリティやジェンダーのあり方への排除や殲滅を企てる規制は、一般的にフェミニストの価値観と相容れないとされる「右翼」の政治に限定されているわけではありません。とくに主流のフェミニズムにおいて議論の前提とされる次元に存在し、それゆえに繰り返し問われ続け、フェミニスト自身が抵抗する必要のあることと、本企画者は考えています。
今回の報告会は、英語圏の情報を整理し、右派と一部のフェミニストによるトランスジェンダーの権利に対する攻撃に注目します。そしてこの文脈での反トランス言説や反「ジェンダー・イデオロギー」運動の現状を、日本語で共有することを目的としています。
事前のアンケートで比較的関心の高かった、反トランス・フェミニストと宗教保守とのつながりや、反セックスワーク/反人身売買・フェミニズムや商業的代理出産の完全廃絶を目指すフェミニズムと反トランス運動とのかかわり、哲学分野でのトランス排除運動、女性のリプロダクティブ・ライツ/ヘルスとの関係といったあたりにも触れることができればと考えています。また企画者自身のここ数週間の関心から、デジタル空間における「真実」をめぐる議論や情報操作について話すことになるかもしれません (あるいはいつになるか分からないですが、次の機会になるかもしれません) 。
上記内容に、ご関心のある方は、ぜひご参加ください。
【関連情報】有志のフェミニスト研究者からなるTIF.jpによる「トランスフォビアへの抵抗とトランスインクルーシブなフェミニズムのためのリソース集」ウェブサイトにはトランス排除にかんする分析や資料をまとめたリンク集(日本のと英語圏のもの2種類があります)含め、今回のトピックについて参考になりそうな記事や論文などが掲載・紹介されています。こちらもご活用ください。https://transinclusivefeminism.wordpress.com/
更新日時:2020年10月18日 終了しましたが、 TIF.jpの 「アンチ・ジェンダー」のタグがついた記事 へのリンクを追加しました。10月15日 新規申込みを締め切りました。10月12日 参考記事追記。10月11日 「企画詳細」追記。
#anti-trans feminism#heteroactivism#online events#events#2020#LGBTQ#anti-gender movements#trans inclusive feminism#online seminar
4 notes
·
View notes
Text
Phipps オンライン読書会
2020年7月25日追記:満席になりました。現在参加申込は受け付けていません。

#MeToo に代表されるような、主流フェミニズムの反性暴力運動において、誰が何を マスメディアとソーシャル・メディアに 「投下し」、誰のどんな感情がかきたてられているのか。
強い怒りの政治は何を導き、何を不問にするのか。
ある種のフェミニズムを駆動し持続させ表舞台に乗せ続けるのは、どのような力学なのか。そうした運動は何を照射し、何を捨象し、何を隠蔽し、何を殲滅しようとしているのか。
■ 日程:
2020年8月7日(金)、11日(火)、14日(金)、18日 (火) [全4回]
午後7時30分-9時20分
■ オンライン (Skype音声+文字チャット)
★詳細は参加者の方に送ります。
■ 費用:無料
■ 定員:各回10人まで。
■ テキスト(文献が手に入りづらい場合はお気軽に連絡をください):
Phipps, Alison. _Me, not you: the trouble with mainstream feminism._ Manchester, UK: Manchester University Press, 2020. https://manchesteruniversitypress.co.uk/9781526147172/
著者ブログで最初の2章 (Introduction & Chapter 1) がサンプルとして公開されています。第1回 (8/7) で読む箇所です。
https://genderate.wordpress.com/2020/05/07/free-sample-of-first-two-chapters-of-me-not-you/
著者による各章の概要紹介はこちら。
https://genderate.wordpress.com/books/mny/
■ 進め方:
この学習会では2020年に発行されたAlison Phippsの"Me, not you: the trouble with mainstream feminism"という英語の本を1回2章ペース、計4回で読みます。
毎回最初の30分程度は内容を確認し、できるだけ何が書かれているのかを理解した上で、残りの時間で気がついたところや考えたこと、疑問に思ったことをシェアします。
日本語の簡単な概略を用意します。英語力は問いません。参加前に全部読み終わってなくてもかまいません。でも、できる範囲で少しでも予習してくると楽しいですよ。
ディスカッションは日本語(音声ベース、必要に応じて文字チャット)の予定です。
テキストが手に入りづらい場合はお気軽にお問い合わせください。 janis(at)selfishprotein.net
■ 参加方法など:
- 参加を希望する日の前日夜7時までにjanisまで連絡をください。
- 第1回 (8/7)、第2回 (8/11)、第3回 (8/14) は続けてでも1回だけでも参加できます。
- 第4回 (8/18) はその前までに1回以上出席した人のみ参加できます。
- 性別・性自認・性指向・国籍・学歴・障害の有無など不問。
- 読書会に参加されない方に当日配布資料はお渡ししていません。
- 分からないこと、不安な点があればメールをください。
■ 参加希望される方は次の項目についてお一人ずつメールで教えてください。
メールアドレスは janis(at)selfishprotein.net
—– (参加希望メール内容ここから)——
・ なまえ (法律上でも通称でもかまいません。メールのやりとりのためのなまえ)
・ メールアドレス
・ Skype ID (取得済みの場合)
・ 参加希望日 (今のところの参加予定;どの回に来られそうですか?)
8/7, 8/11, 8/14, 8/18
・ この読書会のことをどうやって知りましたか?
・ 本は持っていますか? 購入する/図書館で借りる予定等はありますか?
(参加前にテキストが手に入らない場合は相談してください。)
・ 何か要望などあればどうぞ。
—– (参加希望メール内容ここまで)——
■ 企画意図:
前回に引き続き、2018年半ば以降日本語圏ツイッター上での「フェミニスト」によるトランス女性差別発言が急増している文脈を踏まえての企画です。この間、日本語圏ツイッターのトランス排除言説を追っている人たちは、英国や米国、カナダ、韓国といった日本国外でのトランスジェンダーの人びとが直接影響を受ける制度についての議論や、とくに英語圏の著名なフェミニストやフェミニズム親和的な人たちによるトランスフォビックな発言が日本語圏の議論に強い影響力を持っていることにすでに気づいていると思います。
今回は、日本語圏トランス排除/反セックスワーク・フェミニズムに影響を与えている大きな流れの一つである、英語圏の議論を学ぶ企画です。
扱うテキストはトランス排除や反セックスワーク、反移民、反黒人といった時事的で複合的なテーマと事象を扱いながら、英語圏を中心とした世界的な影響力のある主流フェミニズムがもつ人種主義・植民地主義を分析・批判するものです。
英語としてそこまで複雑なわけではないのですが、背景知識が少し必要です。分からないことは、お互い補いあって、学べればと思います。
■ 著者とテキストについて:
著者のAlison Phippsは、英サセックス大学教員で専門はジェンダー研究。研究者かつアクティヴィストとして過去15年性暴力の問題に取り組んできた経験をもとに本書の主流フェミニズム分析は書かれています。
_Me, Not You: the trouble with mainstream feminism_ は英語圏の主流フェミニズムが白人至上主義と不可分な関係にあることを分析しています。タイトルは性暴力告発の声として使われている "me, too" (わたしも!) という言葉のもじりで、そうしたマスメディアで取り上げられやすいフェミニズムが "me, not you" (わたしのことだ、あんたじゃない!) とでも言いたげな、特権的な白人女性たちの排他的で処罰志向の運動になっていることを指摘するものです。
主流フェミニズム内の白人性に着目すること自体は新しい試みではありませんが、グローバルに再び勢いを増している右派の言説やバックラッシュが、著者自身を含めた特権的な白人フェミニストたちが拠って立つ「政治的白人性」を接続点として、主流フェミニズムの運動と組み合わさるという分析 (第3章) は、ジェンダーと人種や階級の交差性に注意しながら、フェミニズムのもつ可能性をより深く掘り下げて考える手がかりとなりそうです。
本書ではまた「トランス排除的ラディカル・フェミニズム (trans exclusionary radical feminism)」が、「ラディカル・フェミニズム」の伝統に位置する理由や「階級としての女性」がどういうロジックで成り立つのかについても明晰な説明がされています (第2章)。主流フェミニズムが必然的に「付随的」とするダメージを周縁化された諸集団にもたらす、戦争機械として分析される一方 (第5章)、本書はその多くをブラック・フェミニストや有色のフェミニストたちの仕事に負っています。ブラック・フェミニストたちは交差しあう諸システムにあらがうことをベースにした、オルタナティブな蓄積と政治を発展させてきました。これらの蓄積は本書とその読者が展望するフェミニズムとその分析や行動のための豊かな枠組みを提供してくれるものです (第2章)。
■ スケジュール:
8/7
■ 序章 Introduction (1) ◆ 「主流派フェミニズム」とは何か。 What is ‘mainstream feminism’? (5) ◆ 複数の問題系が交差するなかでの性暴力 Sexual violence in the intersections (7)
■ 第1章:右傾化する世界におけるジェンダー Chapter 1: Gender in a right-moving world (12) ◆ 女性への戦争 The war on women (16) ◆ 「ジェンダー・イデオロギー」戦争 The war on ‘gender ideology’ (21) ◆ 「女性の安全」を武器にする Weaponising ‘women’s safety’ (26) ◆ 数あるたたかいの交差性 The intersectionality of struggles (31)
8/11
■ 第2章: わたしのことだ、あなたじゃない Chapter 2: Me, not you (35) ◆ 「フェミニズム」は白人女性のもの ‘Feminism’ is for white women (37) ◆ ホワイト・フェミニズムのなかの性暴力 Sexual violence in white feminism (41) ◆ 監獄フェミニズム、植民地主義フェミニズム Carceral feminism, colonial feminism (46) ◆ フェミニズムのべつの伝統 A different tradition (49)
■ 第3章:政治的白人性 Chapter 3: Political whiteness (57) ◆ 「わたしは何もかもだ」―政治的白人性のナルシシズム ‘I’m everything’ – narcissism in political whiteness (61) ◆ 傷つけられた自己としての白人的自己 The white self as wounded self (67) ◆ 白人の女性性と、性化された脅威 White femininity and sexualised threat (72) ◆ 「統制を取り戻す」―白人性の権力への意志 ‘Taking back control’ – the white will to power (76)
8/14
■ 第4章:憤怒/炎上のエコノミー Chapter 4: The outrage economy (82) ◆ 憤怒/炎上のパフォーマティヴィティ The performativity of outrage (85) ◆ 投資/傾注としてのトラウマ Trauma as investment (90) ◆ 大文字の他者を追放/駆逐する Pricing Outhers out (96)
■ 第5章:戦争機械としてのホワイト・フェミニズム Chapter 5: White feminism as war machine (109) ◆ 怒りの(誤)利用 The (mis)uses of anger (112) ◆ けっきょく誰の怒りなのか? (わたしの、あなたじゃなくて) Whose anger is it anyway? (or Me, Not You) (116) ◆ 戦争機械としてのホワイト・フェミニズム White feminism as war machine (120) ◆ 意志するのか意志されるのか、殺すか殺されるか Will or be willed, kill or be killed (128)
8/18
■ 第6章:フェミニズムと極右 Chapter 6: Feminists and the far right (113) ◆ (戦略的)神聖な同盟 (Un)holy alliances (136) ◆ 反動的なフェミニズムと/あるいは保守主義 Reactionary feminism and/or conservatism (140) ◆ 火に油を注ぐ Pouring fuel on the fire (146) ◆ 資本主義-植民地主義的メンタリティーとしての反動的フェミニズム Reactionary feminism as capitalist-colonial mentality (151)
■ 終章 Conclusion (161)
###
(最終更新:2020年8月15日 スケジュールのところに章と節のタイトルとその日本語訳を追記しました。/ 2020年7月25日 受付はいったん終了しました。)
#study group#metoo#me not you#2020#feminism#black feminism#racism#colonialism#alison phipps#racial capitalism
1 note
·
View note
Text
#広河隆一氏とデイズジャパンに責任履行を求めます〜BDS japan有志ステートメントに賛同します

[写真:2019年4月28日東京レインボープライドに出展したイスラエル大使館ブース前で行った、アパルトヘイトとピンクウォッシングに反対する抗議のスナップから。中央で掲げられている黒い旗にピンクの文字で “lgbtq against pinkwash”]
フェミニズムとレズビアン・アートの会 + プロジェクト「フツーのLGBTをクィアする」は、BDS japan有志による下記ステートメントに賛同します。
-----
広河隆一氏とデイズジャパンの事件について謝罪・慰謝賠償による責任履行と二次加害行為の終結を求めます
BDS japan有志
2020/06/25
わたしたちは、広河隆一氏と株式会社デイズジャパンによる性暴力、セクシュアルハラスメント、パワーハラスメント、労働搾取事件を受け、何よりもまず、加害を被られた多くの方々に、連帯の意思を表明し、尊厳への敬意を捧げ、被害から回復されますことを第一に願っております。そのためにも、またこういったハラスメントが日常化している日本社会を変えていくためにも、共に考え、取り組んでいきたいと思います。
広河氏、そしてデイズジャパンは、イスラエルによる入植型植民地主義とパレスチナ占領支配、戦時性暴力、権力による圧政・腐敗などの惨状とそこに生きる人々を取材報道しながら、同時に、その構図をなぞって、自らの身の回りで性的加害と人権侵害を繰り返していたことが、被害者らによる告発記事やデイズジャパン検証委員会報告書により明らかになりました。報告書は、広河氏らがこの深刻な加害の現実を直視して、重大な責任を担い、明確に謝罪し、被害者に慰謝賠償するべきであると勧告しています。広河氏とデイズジャパン経営陣は、そうした責務を最大限果たし、誠意をもって被害者の方々への損害賠償・慰謝の措置等にあたるよう求めます。
報道によれば、法手続き的には、複数の被害者がデイズジャパン社に対し損害賠償を請求しており、これを受けて同社が破産申請を行ったため、6月に東京地裁で債権者集会が予定されているとのことです。同社が可能な限りの誠実な対応を取るよう注目するとともに、非常に憂慮されるのは、広河氏が前述のような責務を未だに全く果たそうとしていない現状です。
広河氏は、仕事を通じて築いてきた地位や名声に乗じ、長期に渡り複数の被害者を苦しめ、周囲はそれを黙認・隠蔽してきました。そして今、広河氏本人による加害否認や責任回避という二次加害が起こっています。さらに、そうした不正義に居直る広河氏を擁護し、それに同調・加担するような団体や関係者も出現してしまっています。
広河氏が真摯に反省しない態度を取り続けている一因として、わたしたちパレスチナ問題と関わってきた者や、彼の周囲の人々の社会的沈黙(暗黙の容認、彼の言動に内心批判的ではあるが声を上げる気運が乏しいこと、彼と関係を断つことで終わりにすること、無関心等)も挙げられると思います。それが彼に居直りの余地を与え、構造を温存し、二次加害の発生にも繋がることになっていはしないか、わたしたちも自戒を込めて本声明を出すことにしました。わたしたちは、被害者の方たちの尊厳が守られる社会の実現を願う者として、性暴力・人権侵害を許さず、再発防止に取り組む土壌作りを呼びかけたいと考えます。
事件は、そして、その背後にある家父長制や性差別、権威主義や「大義」の硬直化といった構造的問題は現在進行形であり、他の社会運動や業界・職場においても無縁ではなく、よりよい未来を築くための課題として存在しています。世界的に見てもジェンダーギャップ指数順位が著しく低い日本では、性差別に対する闘いはまだまだこれからも続きます。この事件で傷ついた方々の苦しみが無駄にならないよう、日本がすべての人々にとってより住みやすい社会となるよう、わたしたちは性差別・性暴力・ハラスメントをなくすべく、これからも声を上げて行きたいと思います。
BDS japan有志
[連絡先:bdsjplus☆gmail.com (☆を@に入れ替えてください)]
-----
【参考情報リンク】
中川聡子 |「謝罪も説明もない」 セクハラ加害者の「逃げ得」に憤る被害者 デイズジャパン破産 (毎日新聞 統合デジタル取材センター) 2020/3/25 https://mainichi.jp/articles/20200324/k00/00m/040/180000c
田村 栄治 | “性暴力”広河隆一氏が設立した“人権団体” 大物写真家たちはなぜ守ろうとするのか (文春オンライン) 2020/4/28 https://bunshun.jp/articles/-/37498
広河隆一氏とデイズジャパン経営陣の人権侵害を忘れない会 https://donotforgetvictims.blogspot.com/
#bds#days japan#statement#support#bdsjapanplus#hirokawa ryuichi#bds japan#広河隆一氏とデイズジャパンに責任履行を求めます#フツーのLGBTをクィアする#endorsement
0 notes
Text
活動記録リンク (2001~2014年)
2001年から2014年まで (Tumblrブログを始めるまで) のフェミニズムとレズビアン・アートの会 (Feminism and Lesbian Art working group: FLA) の活動記録リンクです。
2014
■ ワークショップ 「LGBTとは?」とは?/「ゲイシティ」とは?とは?
(第1回 2014/12/22、第2回 2015/1/12)
http://selfishprotein.net/cherryj/2014/AgainstPinkwashingTokyo.html
■ ワークショップ 「ガザと映画祭とパレードと」その2 (2014/12/1)
― イスラエルに抗議してボイコットするとする.
対するはモノなのか、人なのか.
この運動は〈私たち〉の表現と自由を奪う検閲なのか. ―
http://selfishprotein.net/cherryj/2014/TokyoIsraelPalestine2.html
当日配付資料 http://selfishprotein.net/cherryj/2014/BDS_Workshop_20141201.pdf
■ ワークショップ 「ガザと映画祭とパレードと」(2014/10/4)
http://selfishprotein.net/cherryj/2014/TokyoIsraelPalestine.html
当日配付資料 http://selfishprotein.net/cherryj/2014/SchulmanReview_20141004.pdf
■ 乳がん啓発キャンペーンをテーマにしたドキュメンタリー映画
"Pink Ribbons, Inc." 上映会 (2014/9/27)
http://selfishprotein.net/cherryj/2014/PinkRibbonsInc.html
■ サラ・シュルマン「イスラエル/パレスチナとクイア・インターナショナル」読書会 (2014/6/20-8/29)
―イスラエルによるパレスチナ占領とプライドイベント支援の政治について批判的に考えるために
http://selfishprotein.net/cherryj/2014/Schulman.html
参考:企画のきっかけとなった東京レインボーウイーク冊子『WHO?』 (2014/4) の該当ページ http://selfishprotein.net/works/201404TokyoRainbowWeek_4-5_20-23.pdf
2012
■ 「家族」をめぐる経験と制度を考える読書会 (虹色組合/FLA共催「クイア目線で読む戸籍」関連企画) (2012/2/15-4/4)
http://selfishprotein.net/cherryj/2012/KazokuSG.html
2011
■ ワークショップ:クイア目線で読む戸籍 (2011/10/30)
http://selfishprotein.net/cherryj/2011/Koseki.html
■ ソンタグWS ウィークエンド版 (第24回ウーマンズ・ウィークエンドにて)(2011/9/23)
■ 第5回アートQキャラバン 『AQFF*がやってくる!!!』(協力) (2011/7/2)
*アジアン・クイア映画祭(Asian Queer Film Festival [http://www.aqff.jp/]
■ 第4回アートQキャラバン 『創り手に会いたい!』(協力)(2011/3/5)
■ 第3回アートQキャラバン ソンタグをめぐる問いのいくつか (2011/2/19)
―なぜ彼女はレズビアンなのか、あるいはレズビアンではないのか
http://selfishprotein.net/cherryj/2011/Sontag_ArtQCaravan.html
■ ソンタグ『隠喩としての病い・エイズとその隠喩』 読書会 (アートQキャラバン関連企画) (2011/2/2-3/9、6/8)
http://selfishprotein.net/cherryj/2011/Sontag_Illness.html
2008
■ 「クイア経済学」英語読書会 (2008/9/25-12/4)
http://selfishprotein.net/cherryj/2008/JacobsenZeller.html
2007
■ Blau, Ferber, & Winkler "Economics of Women, Men, and Work" 読書会 (2007/4/22-9/2)
http://selfishprotein.net/cherryj/2007/bfw.html
2006
http://selfishprotein.net/cherryj/2006/indexj.htm
■ 2003~2006年 FLA・いらつめ活動報告 http://selfishprotein.net/lesart/jap/categories/fla.shtml
■ ファンドレイジング・パーティ (2006/7/8)
手をつないで 街へ出よう
LGBT共同作業の可能性
―アクティヴィズムとスタディーズ―
http://selfishprotein.net/cherryj/2006/fundraising.html
■ Hammond "Lesbian Art in America : A Contemporary History"読書会 (2006/4/4-25)
http://selfishprotein.net/cherryj/2006/hammond.html
2005
http://selfishprotein.net/cherryj/2005/indexj.htm
■ Weston & Rofel "Sexuality, Class and Conflict in a Lesbian Workplace" (1984) 読書会 (2005/3/29-4/12)
http://selfishprotein.net/cherryj/2005/weston-rofel.html
■ Califia. "Public Sex: the Culture of Radical Sex"読書会 (2005/8/1-10/10)
http://selfishprotein.net/cherryj/2005/califia.html
■ Tipping the Velvet 上映会 (2005/10/24)
http://selfishprotein.net/cherryj/2005/tpvt.html
■ 無買デーパーティー (2005/11/26)
http://selfishprotein.net/cherryj/2005/bnd.html
2004
http://selfishprotein.net/cherryj/2004/indexj.htm
■ 『ララミー・プロジェクト』上映会 (2004/1/4)
http://selfishprotein.net/cherryj/2004/lpp.html
■ レズビアンセックスのお勉強会 (2004/1/6-27)
http://selfishprotein.net/cherryj/2004/sexws.html
■ “Tipping the Velvet” 上映会 (2004/3/20、4/24)
http://selfishprotein.net/cherryj/2004/tpvt1.html
http://selfishprotein.net/cherryj/2004/tpvt.html
■ A.リッチ「強制異性愛とレズビアン存在」読書会 (2004/2/8-4/11)
http://selfishprotein.net/cherryj/2004/rich.html
■ 性暴力サバイバー&女性パートナーのためのワークショップ (2003/10-2004/10)
http://selfishprotein.net/cherryj/2004/ssaws.html
2003
http://selfishprotein.net/cherryj/2003/indexj.htm
■ bell hooks "Feminism is for everybody" 学習会 (2003/9-11)
http://selfishprotein.net/lesart/jap/2003/030926a.shtml
2002
http://selfishprotein.net/cherryj/2002/indexj.htm
2001
http://selfishprotein.net/cherryj/2001/indexj.htm
#feminism and lesbian art working group#fla#records#archives#links#events#study groups#workshops#2001#2002#2003#2004#2005#2006#2007#2008#2009#2010#2011#2012#2013#2014#pinkwashing#israel#feminism#queer#palestine#iratsume#about
0 notes
Text
Normal Life読書会

変更:3月5日からはオンラインでの開催です。参加を希望される方は、メールで前日午後7時までにご連絡ください。
Normal Life読書会
―行政の暴力、批判的トランス・ポリティクス、法の限界―
[印刷用PDF]
■ 日程:
2020年2月20日、27日、
3月5日★、12日★、19日★、26日★
木曜日 午後7時-8時50分
★3月5日、12日、19日、26日は午後7時30開始
■ 場所:
東京ウィメンズプラザ1階交流コーナー (3/5はオンラインに変更)
渋谷駅 宮益坂口から徒歩12分
表参道駅 B2出口から徒歩7分
都バス (渋88系統) 渋谷駅から2つ目 (4分) 青山学院前バス停から徒歩2分
東京都渋谷区神宮前5-53-67 〒150-0001
http://www1.tokyo-womens-plaza.metro.tokyo.jp/outline/tabid/136/Default.aspx
■ 費用:
資料コピー代実費各回50円まで。
■ 定員:
各回10人まで。先着順。
■ テキスト(文献が手に入りづらい場合はお気軽に連絡をください):
Spade, Dean. _Normal Life: Administrative Violence, Critical Trans Politics, and the Limits of Law._ Durham, NC: Duke University Press, 2015. https://www.dukeupress.edu/normal-life-revised
初回2/20に読むPrefaceとIntroductionについては、PDFが出版社サイトで無料で公開されています。(2020年1月23日現在)
https://read.dukeupress.edu/books/book/99/Normal-LifeAdministrative-Violence-Critical-Trans
■ 進め方:
この学習会では2011年に初版、2015年に増補改訂版が発行されたDean SpadeのNormal Life: Administrative Violence, Critical Trans Politics, and the Limits of Lawという英語の本を1回1-2章のペースで読んでいきます。
毎回最初の30分程度は内容を確認し、できるだけ何が書かれているのかを理解した上で、残りの時間で気がついたところや思いついたことをシェアします。
日本語の簡単な概略を用意します。参加者の英語力は問いません。参加前に全部読み終わってなくてもかまいませんが、できる範囲で少しでも予習してくるとより楽しいですよ。
ディスカッションは日本語です。
テキストが手に入りづらい場合はお気軽にお問い合わせください。 janis_cherry(at)selfishprotein.net
■ 参加方法など:
- 参加を希望する日の前日夜7時までにjanisまで連絡をください。
- 1回だけでも続けての参加もできます。
- 多くて8人くらいの集まりになる予定です (テーブルの大きさ的に)。
- 「見学」 (沈黙) というのはなしです。
(実際は会場の都合で、覗き見&立ち聞きできます。お気軽にどうぞ。)
- 性別・性自認・性指向・国籍・学歴・障害の有無など不問。
- 申し訳ありませんが、読書会に参加されない方に当日配布資料はお渡ししていません
(今回の読書会に参加して欠席回の資料も必要な場合はその都度ご相談ください)。
- 分からないこと、不安な点があればメールをください。
■ 参加希望される方は次の項目についてお一人ずつメールで教えてください。
メールアドレスは janis_cherry(at)selfishprotein.net
—– (参加希望メール内容ここから)——
・ なまえ (法律上でも通称でもかまいません。メールのやりとりのためのなまえ)
・ メールアドレス
・ 参加希望日 (今のところの参加予定;どの回に来られそうですか?)
2/20, 27, 3/5, 12, 19, 26
・ この読書会のことをどうやって知りましたか?
・ 本は持っていますか? 購入する/図書館で借りる予定等はありますか?
(参加前にテキストが手に入らない場合は相談してください。)
・ 何か要望などあればどうぞ。
—– (参加希望メール内容ここまで)——
■ 企画意図 (2020/2/7):
主催者は、2007-9金融危機とオキュパイ以降の、経済的不平等と国家/政府の再分配機能 (不全) に焦点を当て、「新自由主義」を批判してきたフェミニズム内部の (おそらくは無自覚な) トランス/クィア消去の問題を考えたいと思ってきました。
今回の読書会は、Space between Us読書会で明示的に中心的な問題であった、少数者への差別や抑圧を条件づけている前提を問いただすことを継続し、著者が提起してきた批判的トランス・ポリティクスによる抵抗の可能性を考えます。
https://www.youtube.com/watch?v=OU8D343qpdE
主催者個人の関心はこういったものですが、2020年2月という、このタイミングなので2018年半ば以降日本語圏ツイッター上での「フェミニスト」によるトランス女性差別発言が急増している文脈を踏まえ、日本でのトランスジェンダーの人びとをめぐる状況や問題についても話をしたいと思っています。
■ テキストについて (2020/2/7):
著者のトランス・アクティヴィストで弁護士で大学教員でもあるDean Spadeは1977年生まれ、低所得かつ/あるいは有色の、トランスジェンダーやインターセックス、ジェンダーノンコンフォーミング (ジェンダー規範に合わせない) である人たちのために 無料の法律サービスを提供する非営利コレクティヴ、Sylvia Rivera Law Project (SRLP) https://srlp.org/ を2002年に創設しています。
本書Normal Life: Administrative Violence, Critical Trans Politics, and the Limits of Law はこの30年、いわゆる「新自由主義」の下でトランス・ポリティクスに何が起こってきたのかを辿り、法的承認や包摂への要求を超えて、現在の国家/政府・市民社会・安全保障・社会的平等をめぐる論理そのものを変革しようとする本で、副題にある批判的トランス・ポリティクス (critical trans politics) は、1980年代後期から始まったアクティヴィストや法学研究者たちの運動である、批判的人種理論 (Critical Race Theory) の蓄積を足場にしていることを示しています。
Normal Life でSpadeは反差別法や反ヘイトクライム法といった法律の制定がトランスジェンダーの人権を守るのだという一般的な理解を考えなおそうとします。ここで問題にされているのは、そうした法律と同じ法制度の下で、とくに行政の領域において、法がトランスジェンダーの人びとの集団としての脆弱さを構築し再生産していることです。
単なる手続きに過ぎず中立的な営みと考えられがちな行政で、〈標準とされること〉や〈決まりになっていること〉こそが、異なる諸集団を構造的に不安定な状況におき、生きることそのものを含めたその人たちの人生のチャンスを (ときに負の方向に) 分配してしまっているのではないか。Spadeが依拠するのは米国の事例ですが、戸籍制度をめぐる問題や、入管施設での長期収容問題を含めた入国管理のあり方など、日本の文脈でも同様の問題提起は有効でしょう。本書でSpadeはトランスの人びとの生に非常に重大な影響を与えている法や政策の具体的な問題領域を三つあげ (a. 身分証明、b. 施設 (シェルターやグループホーム、拘置所・刑務所、トイレ)、c.医療ケアへのアクセス)、これらの問題について論じていきます。
ちなみにSpadeは2016年関西クィア映画祭で日本語字幕版が公開された2015年のドキュメンタリー『これがピンクウォッシュ! シアトルの闘い』 (Pinkwashing Exposed: Seattle Fights Back!) https://kansai-qff.org/2016/program_pinkwashing.shtml の監督でもあります。(日本語字幕つきではないオリジナルのバージョンは無料で公開されています。英語字幕等表示させることができます。https://pinkwashingexposed.net/2015/05/06/watch-pinkwashing-exposed-seattle-fights-back/)
■ スケジュール:
2/20
Preface ix-xvi
Introduction: Rights, Movements, and Critical Trans Politics 1-19
https://read.dukeupress.edu/books/book/99/Normal-LifeAdministrative-Violence-Critical-Trans
2/27
1. Trans Law and Politics on a Neoliberal Landscape 21-37
2. What's Wrong with Rights 38-49
3/5
2. What's Wrong with Rights (cont.) 42-49
3. Rethinking Transphobia and Power—Beyond a Rights Framework 50-72
3/12
3. Rethinking Transphobia and Power—Beyond a Rights Framework (cont.) 67-72
4. Administering Gender 73-93
3/19
5. Law Reform and Movement Building 94-116
Conclusion: "This Is a Protest, Not a Parade" 117-138
3/26
Afterword 139-161
2015年出版以降のトランスをめぐる政治について
(最終更新: 2020年3月12日 3/19以降についてもオンライン開催の旨、追記しました。)
youtube
#dean spade#trans politics#queer studies#2020#gender studies#law#study group#normal life#pinkwashing
1 note
·
View note
Text
Feminist, Queer, Crip 読書会
クィア障害学シリーズ (by 井上) ということで、2017年の Crip Theory 読書会に引き続き、武蔵大学 (江古田) での読書会です。
2019年9月20日スタート、毎週金曜夜、11月まで続きます。
読書会案内の印刷用PDFはこちらです。
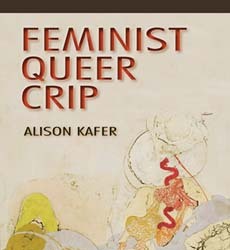
・・・告知文ここから・・・
Feminist, Queer, Crip 読書会
――時間の障害学、アクセシブルな未来に向けて
Alison Kafer は Feminist, Queer, Crip (2013, Indiana University Press) において、近年のクィア・スタディーズを活気づける「時間」に関する考察を批判的に障害学に接続し、「未来」をめぐる議論がいかに健常身体的/健常精神的な異性愛を自然なものとして再生産しているかを論じています。
そして、障害の脱政治化に抵抗し、もっとアクセシブルな未来を想像するために、障害とフェミニズムとクィアの連合の政治が不可欠であると主張します。
本書の焦点はアメリカに当てられていますが、本書で取り上げられる生殖医療、不妊手術、出生前診断、障害とテクノロジー、公共空間における障害者やトランスジェンダーの排除といった問題は、日本においても決して対岸の火事ではありません。
この読書会では、お配りする資料をもとにまずは Feminist, Queer, Crip で何が述べられているのかを日本語で丁寧に確認し、その上で疑問点や日本の文脈との相違や応用可能性などについて話し合いたいと思っています。
1回のみ、一部の回のみの参加も可能です。
■ 日時:2019年9月20日~11月15日
毎週金曜19時~21時(全9回)
■ 会場:武蔵大学6号館1階6102
*11月1日のみ7号館1階7113になります。ご注意ください。
https://www.musashigakuen.jp/access.html
東京都練馬区豊玉上1-26-1
西武池袋線・江古田駅より徒歩6分、桜台駅より徒歩8分
都営大江戸線・新江古田駅より徒歩7分
西武有楽町線・新桜台駅より徒歩5分
■ 使用言語:日本語(テキストは英語)
■ 参加費:無料
■ ファシリテーター:井上(武蔵大学大学院人文科学研究科博士前期課程)
■ 申込:必要
初めて参加を希望する日の正午までに、お名前(通称でもかまいません)と、連絡がとりやすいメールアドレス(複数でもかまいません)と、参加予定日を、readcriptheory(at)outlook.jp(井上)あてにお送りください。
所属や学歴、出自、年齢、障害の有無、性別、性自認、性指向など一切問いません。
会場は車いすでアクセス可能、近くに多目的トイレがあります。
配布資料の拡大や筆談など可能な限り対応します。ご不明な点は上記アドレスまでお気軽にお問い合わせください。
■ テキスト:Kafer, Alison, 2013, Feminist, Queer, Crip, Bloomington and Indianapolis: Indiana University Press.
http://www.iupress.indiana.edu/product_info.php?products_id=806824
参加を希望する方でテキストが手に入りにくい場合は、ご相談ください。
■ 予定:
9/20
Introduction: Imagined Futures (1-24)
9/27
1 Time for Disability Studies and a Future for Crips (25-46)
10/4
2 At the Same Time, Out of Time: Ashley X (47-68)
10/11
3 Debating Feminist Futures: Slippery Slopes, Cultural Anxiety, and the Case of the Deaf Lesbians (69-85)
10/18
4 A Future for Whom? Passing on Billboard Liberation (86-102)
10/25
5 The Cyborg and the Crip: Critical Encounters (103-128)
11/1*
6 Bodies of Nature: The Environmental Politics of Disability (129-148)
11/8
7 Accessible Futures, Future Coalitions (149-169)
11/15
全体を振り返って
*11月1日のみ武蔵大学7号館1階7113で行います。ご注意ください。
・・・告知文ここまで・・・
印刷用PDF http://selfishprotein.net/works/FeministQueerCrip_StudyGroup_2019.pdf
3 notes
·
View notes
Text
TRP2019へのイスラエル大使館の後援・ブース出展に抗議します
NPO法人東京レインボープライド 御中
駐日イスラエル大使館 文化広報/TRP担当 様
ヤッファ・ベンアリ駐日イスラエル大使 様
東京レインボープライドTRP2019へのイスラエル大使館の後援・ブース出展に抗議し
国際法違反・人権侵害とそのノーマライゼーションをただちに終結するよう要求します。
東京レインボープライドは、2013年以降、7年間にわたって、イスラエル大使館から後援を受け続けています。これは、イスラエル国とTRPによる「ピンクウォッシング」にほかならず、東京・日本に生活するクィア市民として強く抗議します。
イスラエルは、1948年以来、パレスチナ人に対する民族浄化・暴力的人権侵害を71年間にわたって続けており、違法占領・入植型植民地政策や人種差別体制(アパルトヘイト壁建設・国民国家法を含む)および戦争犯罪について、国連を含む国際社会から厳しく非難されています。また、世界中に散在する550万人のパレスチナ難民の帰還権(国連総会決議194号)の一日も早い実現が求められています。
その暴虐ぶりから人々の目を逸らすために、はりぼてのゲイフレンドリー・アピールによって自国のイメージ塗りかえを図るイスラエルの広報外交政策は「ピンクウォッシング」、すなわちLGBTの権利の冷笑的な悪用としてつとに批判されています。東京・日本のLGBTQコミュニティと広告代理店に利益が流れ込む一方で、パレスチナ人からは身体や土地や水や電気や生きるために必要な資源が日々強奪され破壊され続けるのです。
報道されているように、1948年に現イスラエル領から追放されてきた難民およびその子孫が住民の75%を占めるパレスチナ・ガザ地区では、故郷への帰還と封鎖解除を求めて、昨年3 月30日から「帰還大行進」と呼ばれる平和的デモが始まりました。この民主的な非武装デモに対し、イスラエル軍は銃撃やガス弾を浴びせ、パレスチナ保健省によれば、今年4月半ばまでに271人が殺害され、16,656人の負傷者が病院で手当を受けています。1年を超えた今も、ガザ市民は、故郷から追い出され帰還権をもつ我々は存在するのだという形で抗議活動を行い、もうこれ以上、パレスチナを見捨てておかないように、イスラエルにやめさせるように、むきだしの身体を現すことで国際社会と世界の人々に要求しています。イスラエルは戦争犯罪の上塗りをするのでなく、平和と人権への義務を果たすべきです。
東京レインボープライドは、今年のテーマ趣旨で「人種差別撤廃」を求めて1963年に米国で行われた「ワシントン大行進」へのオマージュを語っています。にもかかわらず、このように基本的人権を求めるパレスチナ人に対して日常的に武力弾圧を行い、現在このときも「帰還大行進」参加の市民を殺傷しているイスラエルの大使館ブースを出展させるとは、まさに人種差別への加担そのものであり、暴力常態化の共犯にほかなりません。
わたしたちは、東京レインボープライドに対するイスラエル大使館からのスポンサーシップとブース出展をただちに中止することを要求します。
2019年4月28日
フツーのLGBTをクィアする/フェミニズムとレズビアン・アートの会
[email protected]
PDF版 http://selfishprotein.net/works/2019TRPIsraelLetter.pdf
1 note
·
View note
Text
"queers in black" at Tokyo Rainbow Pride 2019
呼びかけ〜ピンクウォッシングにプライドはない
2019年4月28日(日) 13時〜14時(コアタイム)
東京レインボープライド
「イスラエル大使館」ブース前スタンディング/非暴力哀悼ビジル
(原宿側のメインゲート前、一番端のブース)
↓代々木公園会場マップ(イスラエル大使館=パープル136番) https://tokyorainbowpride.com/assets/file/booth_map.pdf
*黒っぽい服装でお集まりください。
*プラカード持参歓迎。とくにコールなどを行う予定はありませんが、スピーチ、パフォーマンス、交流など、ご自由にご参加ください。
*数分だけでも構いません。上記コアタイムには呼びかけ人らがいます。28日(日)・29日(月)の都合のいい時間に一人からでも行えるアクションです。
【参考】http://womeninblack.org/action/
*下の画像のPDF版はここからダウンロードできます。http://selfishprotein.net/works/nopinkwash.pdf
【ネットプリント予約番号】 31950977(セブンイレブンで印刷できます)

東京レインボープライドは、2013年以降、7年間にわたって、
イスラエル大使館から後援を受け続けています。
イスラエルは、パレスチナ人に対する民族浄化・暴力的人権侵害を
71年間にわたって続けており、アパルトヘイト(人種隔離)体制を敷いている国。
その暴虐ぶりから人々の目を逸らすために、
はりぼてのゲイフレンドリー・アピールによって
自国のイメージ塗りかえを図るイスラエルの広報外交政策は
「ピンクウォッシング」、すなわちLGBTの権利の冷笑的な悪用として有名です。
東京・日本のLGBTQコミュニティと広告代理店に利益が流れ込む一方で、
パレスチナ人からは身体や土地や水や電気や生きるために必要な資源が
日々強奪され破壊され続けます。
イスラエルとともにわたしたちが盗んでいるのです。
この共犯に屈し、自ら隷従し続けることを、まだ選び続けるのですか?
パレスチナ・ガザ地区では、故郷への帰還と封鎖解除を求めて、
昨年3月末から「帰還大行進」と呼ばれる平和的デモが始まりました。
この民主的な非武装デモに対し、イスラエル軍が銃撃やガス弾を浴びせていることは、
日本のメディアでもときおり報道されてきました。
今年4月半ばまでに271人が殺害され、16,000人以上が負傷させられていますが、
1年を超えた今も、なぜ抵抗は毎週連日続けられているのでしょうか。
故郷から追い出され帰還権をもつ我々は存在するのだという形で抗議活動を行い、
もうこれ以上、パレスチナを見捨てておかないように、イスラエルにやめさせるように、
むきだしの身体を現すことで国際社会と世界の人々に要求しているのです。
東京レインボープライドが、人種差別国家イスラエルの暴力常態化に毎年加担しているのに、
今年のテーマ趣旨で、「人種差別撤廃」を求めて1963年に米国で行われた 「ワシントン大行進」へのオマージュを語っていることは恥ずべき欺瞞であり、
記憶の盗用、解放運動への冒涜でしかないのではないでしょうか。
この国にも性差別、人種差別や国籍差別、軍事主義、経済的収奪がはびこっている今、
パレスチナにおける人権と正義ある平和のための闘いに連帯して、
誇りをもって「ピンクウォッシング」拒否を表明し、イスラエルとの共犯を終わらせよう。
[呼びかけ]フツーのLGBTをクィアする
http://feminism-lesbianart.tumblr.com
https://twitter.com/lgbtq_luna
2019年4月26日更新:プラカ印刷用のPDFリンクと【ネットプリント予約番号】 31950977(セブンイレブンで印刷できます)情報を追記しました。
2019年4月28日更新: プラカ印刷用のPDFリンク はそのままですが、1箇所脱字があったので、画像とPDFを訂正版に差し替えました。最初にアップしたものは「すべて」と「ひと」の間の「の」が抜けてました! ごめんなさい!!
#pinkwashing#フツーのLGBTをクィアする#call for action#trp2019#trp#2019#bds#no pride in occupation#lqbtq against pinkwash#puraka
1 note
·
View note
Text
4/20「TRP2019イスラエル大使館ブース出展を考える」勉強会
「TRP2019イスラエル大使館ブース出展を考える」勉強会
■ 日時:2019年4月20日(土) 14時〜16時頃
■ 場所:東京ウィメンズプラザ1階交流コーナー
(「渋谷駅」宮益坂口から徒歩12分、「表参道駅」B2出口から徒歩7分)
http://www1.tokyo-womens-plaza.metro.tokyo.jp/outline/tabid/136/Default.aspx
《テキスト記事》*事前に読めてなくても大丈夫です。
3-Mar-2019 "How Eurovision has turned into a ‘pinkwashing’ opportunity for Israel – the LGBT+ community should boycott it" by Haneen Maikey and Hilary Aked (いかにしてユーロビジョンはイスラエルにとってピンクウォッシングの機会に変わったのか - LGBT+コミュニティはボイコットするべきだ)
https://www.independent.co.uk/voices/eurovision-israel-lgbt-rights-pinkwashing-palestine-a8804851.html
“The narrative that Israel welcomes LGBT+ self-expression while in the rest of the Middle East queers face relentless persecution, constructs a false opposition”
(「中東の他の国々ではクィアたちは容赦ない迫害に直面するが、イスラエルはLGBT+の自己表現を歓迎する、という語りは偽の対立を構築している」)
----------
きたる4/28-29に開催される東京レインボープライド2019に、今年もイスラエル大使館ブースが出展することが発表されてしまいました。 https://tokyorainbowpride.com/booth/
イスラエル大使館 「テルアビブは今年、ユーロビジョン・ソング・コンテストを迎え入れます。そのユーロビジョンを2週間前に控えた4月28日(日)と29日(月)、イスラエルブースは再びTRP2019に帰ってきます!たくさんのプレゼントやイスラエルの音楽を用意して、皆さんをお待ちしております。6月14日にテルアビブで開催される、世界最大規模のプライドパレードの雰囲気を一足先にお楽しみください!」
日本ではほとんど馴染みのないユーロビジョンが欧米系国家ステイタスの徴として言及されています。昨年優勝したイスラエル代表は、コメントで翌年開催地を「エルサレムで!」と言ったのですが(動画最後の3時間43分過ぎあたり)、さすがにそれはなくテルアビブに決まり、現在アーティストや放送局などにボイコットを呼びかける国際的BDS運動が続いています。
Eurovision Song Contest 2018 - Grand Final - Full Show
https://youtu.be/4AXTB-iShio?t=13380
BOYCOTT EUROVISION IN ISRAEL AND TEL AVIV PRIDE! http://www.pinkwatchingisrael.com/portfolio/boycott-eurovision-in-israel-and-tel-aviv-pride/
Tell Madonna to Choose Freedom(ぜひご署名ください!)
https://secure.everyaction.com/rWBQiL9XHkC_7ePCEHOiAw2
今回は、テキスト記事の内容を日本語で確認しつつ、ピンクウォッシングへの対抗アクション、ボイコット運動について話し合います。参加無料。どうぞお気軽にご参加ください。
1 note
·
View note
Text
Spaces between Us 読書会
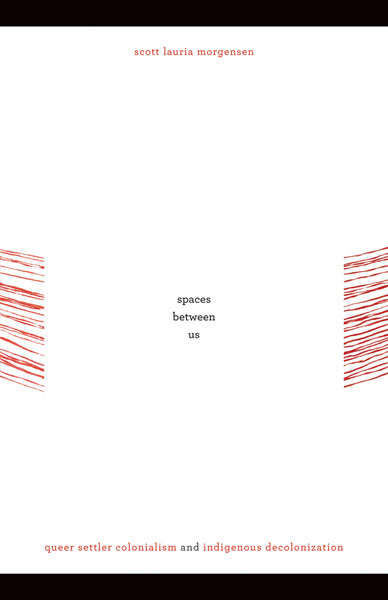
■ 日程:
2019年2月13日、27日、
3月6日、13日、27日、
4月3日、10日、1日 (月)、6日 (土)、9日 (火)、
4月15日 (月)、 23日 (火)、5月7日 (火)、20日 (月)、28日 (火)、
6月3日 (月)、 10日 (月)、25日 (火)、
7月2日 (火)
午後7時-8時50分
■ 場所:
東京ウィメンズプラザ1階交流コーナー
渋谷駅 宮益坂口から徒歩12分
表参道駅 B2出口から徒歩7分
都バス (渋88系統) 渋谷駅から2つ目 (4分) 青山学院前バス停から徒歩2分
東京都渋谷区神宮前5-53-67 〒150-0001
http://www1.tokyo-womens-plaza.metro.tokyo.jp/outline/tabid/136/Default.aspx
■ 費用:
資料コピー代実費各回50円まで。
■ 定員:
各回10人まで。先着順。
■ テキスト(文献が手に入りづらい場合はお気軽に連絡をください):
Morgensen, Scott Lauria, 2011, Spaces between Us: Queer Settler Colonialism and Indigenous Decolonization (Minneapolis, MN: University of Minnesota Press)
https://www.upress.umn.edu/book-division/books/spaces-between-us
■ 進め方:
この学習会では2011年に発行されたScott Lauria Morgensen の "Spaces between Us: Queer Settler Colonialism and Indigenous Decolonization" という英語の本を1回1章のペースで読んでいきます。
毎回最初の30分程度は内容を確認し、できるだけ何が書かれているのかを理解した上で、残りの時間で気がついたと��ろや思いついたことをシェアします。
日本語の簡単な概略を用意します。参加者の英語力は問いません。参加前に全部読み終わってなくてもかまいませんが、できる範囲で少しでも予習してくるとより楽しいですよ。
ディスカッションは日本語です。
テキストが手に入りづらい場合はお気軽にお問い合わせください。 janis_cherry(at)selfishprotein.net
■ 参加方法など:
- 参加を希望する日の前日夜7時までにjanisまで連絡をください。
- 欠席される場合は、当日直前でもかまいませんのでご連絡ください。
- 1回だけでも続けての参加もできます。
- 多くて8人くらいの集まりになる予定です (テーブルの大きさ的に)。
- 「見学」 (沈黙) というのはなしです。
(実際は会場の都合で、覗き見&立ち聞きできます。お気軽にどうぞ。)
- 性別・性自認・性指向・国籍・学歴など不問。
- 申し訳あ���ませんが、読書会に参加されない方に当日配布資料はお渡ししていません
(今回の読書会に参加して欠席回の資料も必要な場合はその都度ご相談ください)。
- 分からないこと、不安な点があればメールをください。
■ 参加希望される方は次の項目についてお一人ずつメールで教えてください。
メールアドレスは janis_cherry(at)selfishprotein.net
—– (参加希望メール内容ここから)——
・ なまえ (法律上でも通称でもかまいません。メールのやりとりのためのなまえ)
・ パソコンのメールアドレス
・ あれば携帯電話のメールアドレスまたは番号 (当日連絡用)
・ 参加希望日 (今のところの参加予定;どの回に来られそうですか?)
2/13, 27, 3/6, 13, 27, 4/1, 4/6, 4/9, 4/15, 4/23, 5/7, 5/20, 6/3, 10, 25, 7/2
・ この読書会のことをどうやって知りましたか?
・ 本は持っていますか? 購入する/図書館で借りる予定等はありますか?
(参加前にテキストが手に入らない場合は相談してください。)
・ 何か要望などあればどうぞ。
—– (参加希望メール内容ここまで)——
■ 企画意図とテキストについて (2019年2月25日追記):
企画の理由の一つは、2010年代の日本語圏でLGBTブームといわれるなかで、そのLGBTを語ることを可能にしている文脈が、その前の歴史や、目指すべき先進性を前提とする考え方と、どのようにつながっているのか、あるいはつながっていないことになっているのかを、考えてみたいと思ったからです。
本書が扱うのは、直接には日本の話ではありません。北米のクィアとアメリカ州の先住の人びとについて、入植型植民地主義の研究を踏まえ、再考するものです。ここで「入植型植民地主義」と訳す、settler colonialism は、ある土地から人びとが別の土地への定住を目的として移動し、その人たちが入植していく際に、もともと住んでいた人たちの土地を奪い、その過程で先住民をしばしば虐殺し消滅させるだけでなく、そのことを自然化して、新たに植民者の社会を作りあげていく、そのような構造のことです。こうした入植型植民地主義の特徴は、先住民が自然に消滅していくように*みえる*ことにあります。settler colonialism の訳語は「入植型植民地主義」以外にも「殖民植民地主義」や「セトラー・コロニアリズム」などいくつかあるようです。
本書で著者のMorgensenが目指すのは、〈クィア〉をそう成らしめている条件を問いただすことです。
「著者は、先住民フェミニストと先住民クィア批評家たちを継承し、その条件が説明されるまで確かめられないであろう白人至上主義の入植型植民地主義によって制定された一つの位置として、〈クィア〉 を理解する。ここでの議論は『インターセクショナル』というより系譜学的なものとなる。問題は、白人の、特権階級の、入植型植民地主義のナショナルな継承者たちが、クィアが語られる際の中心におかれつづけてきたこと、ではない。問題は、そのような説明の範疇から引き出されるすべての結論には、誰がそこから排除されているのかを説明できないだけでなく、*含まれている*すべての人びとを説明することもできないということなのだ。なぜなら、白人至上主義の入植型植民地主義のもとでのクィアネスについての唯一可能な説明は、その条件を問いただすものでしかないからである。」(25-6)
このような問題の立て方を学びたいと思ったのは、2013年から東京レインボープライドへのイスラエル大使館ブース出展をきっかけにピンクウォッシングの問題に取り組んできたなかで、そのピンクウォッシングという批判の文脈で使われている(ピンクに象徴されるLGBTフレンドリーな文化政策などが覆い隠しているという)「入植型植民地主義」の意味がほとんど通じていないようにみえることに、もどかしさを感じているというのがあります。
政治化されうることと、政治化されることすらなく、政治化されること自体が問題とされることの境がどのように引かれているのか、それによって何が起こっているのか、この読書会ではそうしたことを考えられたら、と思っています。
■ スケジュール(2019年6月25日更新):
2/13
Introduction
2/27
Part I. Genealogies
1. The Biopolitics of Settler Sexuality and Queer Modernities
3/6 3/13
(1. cont.) from page 45
2. Conversations on Berdache: Anthropology, Counterculturism, Two-Spirit Organizing
3/27
(2. cont.) from page 77
Part II. Movements
3. Authentic Culture and Sexual Rights: Contesting Citizenship in the Settler State
4/1
(3. cont.) from page 99
Race and Coalition in the National gay and Lesbian Task Force (99)
4/6
(3. cont.) from page 110-
4/9
(3. cont.) from page 119
4. Ancient Roots through Settled Land: Imagining Indigeneity and Place among Radical Faeries
4/15, 4/23, 5/7, 5/20, 5/28, 6/3, 6/10. 6/25
5. Global Desires and Transnational Solidarity: Negotiating Indigeneity among the Worlds of Queer Politics
7/2
6. “Together We Are Stronger”: Decolonizing Gender and Sexuality in Transnational Native AIDS Organizing
Epilogue
(最終更新日:2019年6月25日 スケジュール更新)
5 notes
·
View notes
Text
周縁化と沈黙に抗う――BDSと「反ユダヤ主義」学習会
イスラエル政府は過去においてもまた現在も、イスラエル内外のユダヤ人という多様な集団を単独で代表する存在ではありません。けれども、パレスチナ市民社会からの呼びかけを受け世界中で拡大するイスラエル政府のアパルトヘイト体制批判である、BDS (ボイコット、資本撤退、制裁) の運動を「反ユダヤ主義 (antisemitism)」と混同する攻撃は根強くあります。このような混同がBDSへの「批判」として利用される時代的な背景としては、 白人至上主義やイスラモフォビアが問題化されづらい一方で、欧州やアメリカ合衆国での、極右による排外主義的なユダヤ人差別の扇動やユダヤ人を含めたエスニック・マイノリティをターゲットにした憎悪犯罪の増加があります。
参考:
"Anti-Semitism on the political left" (11 Jan 2017)
https://www.aljazeera.com/programmes/upfront/2017/01/anti-semitism-political-left-170111153859304.html
"Web extra: Is boycotting Israel anti-Semitic?" (23 Dec 2016)
https://www.aljazeera.com/programmes/upfront/2016/12/web-extra-boycotting-israel-anti-semitic-161223090003247.html
今回の学習会では、2018年12月に来日を控えた2人の米国在住フェミニストの言葉を通し、対イスラエルBDS (ボイコット、資本撤退、制裁) の運動に対する「反ユダヤ主義」言説がどのように展開されており、それに対してどのような反論がなされているのかを、反植民地主義・反レイシズム・反ヘテロセクシズムの立場から学びます。
■ 日程:2018/11/25(日)午後2時, 12/2(日)午後2時, 12/10(月)午後7時 (各回2時間、全3回、単発参加可)
■ 場所: 東京ウィメンズプラザ 1階交流コーナー
渋谷駅 宮益坂口から徒歩12分
表参道駅 B2出口から徒歩7分
都バス (渋88系統) 渋谷駅から2つ目 (4分) 青山学院前バス停から徒歩2分
東京都渋谷区神宮前5-53-67 〒150-0001
http://www1.tokyo-womens-plaza.metro.tokyo.jp/outline/tabid/136/Default.aspx
■ 参加費:資料代実費 (各回50円まで)/予約申込み不要
■ 進め方:
この学習会では反植民地主義・反レイシズム・反ヘテロセクシズムの立場から、Judith ButlerとNoura Erakatのスピーチや文章をみんなで読みます。
毎回最初の30分程度は内容を確認し、できるだけ何が書かれているのかを理解した上で、残りの時間で気がついたところや思いついたことをシェアします。
日本語の簡単な概略を用意します。参加者の英語力は問いませんし、全部読み終わってなくても大丈夫ですが、テキストやビデオはできる範囲でちょっとでも予習してくるとより楽しいですよ。
ディスカッションは日本語です。
12/2と12/10に扱うテキストが手に入りづらい場合はお気軽にお問い合わせください。 janis_cherry(at)selfishprotein.net
■ 参加方法など:
- 事前に各回指定のテキストを読み (ビデオを見て) ご参加ください。予約申込みは不要です。各回とも当日直接お越しください。
- 1回だけでも続けての参加もできます。
- 多くて8人くらいの集まりになる予定です (テーブルの大きさ的に)。
- 「見学」 (沈黙) というのはなしです。
(実際は会場の都合で、覗き見&立ち聞きできます。お気軽にどうぞ。)
- 性別・性自認・性指向・国籍・学歴・英語力など不問。
- 分からないこと、不安な点があればメールをください。問い合わせはjanisまで。janis_cherry(at)selfishprotein.net
■ スケジュール:
第1回:2018年11月25日(日) 午後2時-4時
テキスト:"Judith Butler’s Remarks to Brooklyn College on BDS" (February 7, 2013) https://www.thenation.com/article/judith-butlers-remarks-brooklyn-college-bds/
2013年2月、米国ニューヨーク市立大学でBDSを支持するJudith Butlerと、BDSキャンペーンの共同創始者であるOmar Barghouti のパネルが企画された際、市の後援を取りやめるよう圧力がかかりました。そうした圧力への抗議を経て開催されたパネルでのButlerによるスピーチです。
第2回:2018年12月2日(日) 午後2時-4時
テキスト:Butler, Judith. "Foreword" In On Antisemitism: Solidarity and the Struggle for Justice, Jewish Voice for Peace, vii-xiii. Chicago, IL: Haymarket Books, 2017. https://www.haymarketbooks.org/books/1065-on-antisemitism
ビデオ:Jewish Voice for Peace. "Judith Butler on BDS and Antisemitism", Filmed [Aug 2017]. Youtube video, Posted [Aug 2017]. https://www.youtube.com/watch?v=B9gvj3SvcDQ
Jewish Voice for Peace (JVP) は1996年にカリフォルニア州立大学バークレー校の学部生たちが自主的に立ち上げたイスラエルとパレスチナの平和運動団体で現在は全米に60以上の支部を持つ草の根団体です。2017年に『反ユダヤ主義について――正義への連帯とたたかい』というアンソロジーを出版しました。今回読むのはメンバーの一人でもあるJudith Butlerが寄せた序文になります。またビデオは同時期にJVPの企画で発表されたものです。

第3回:2018年12月10日(月) 午後7時-9時
テキスト:Erakat, Noura. "Arabiya Made Invisible: Between Marginalization of Agency and Silencing of Dissent" In Arab and Arab American Feminisms: Gender, Violence, and Belonging, edited by Rabab Abdulhadi, Evelyn Alsultany, and Nadine Naber, 174-183. First Paperback ed. Syracuse, NY: Syracuse UP, 2015. http://www.syracuseuniversitypress.syr.edu/fall-2010/arab-arab.html
アラブ人とアラブ系アメリカ人のフェミニズム(複数形)をテーマに編纂されたアンソロジーから一編を読みます。Noura Erakat によるこの文章はアラブ女性やモスリム女性のアイデンティティについての偏狭なステレオタイプに対抗し、ラディカルな反シオニストとしては退けられるなかで、著者自身がパレスチナ人法学生のアクティヴィストとして行為性を発揮してきたプロセスが描かれています。学習会のタイトルはこの文章の副題から取りました。

関連のお知らせ:2018年12月15日に、パレスチナBDS民族評議会の「多田謠子反権力人権賞」受賞発表会があり、それと同時に14日(大阪)・16日(東京)にBDS japan発足集会が企画されています。それぞれの会で学習会の3回目で扱う文章を書いた、ヌーラ・エラカート (Noura Erakat) さんのスピーチがあります。https://bdsjapan.wordpress.com/
印刷用PDFはこちら。
(2018年11月21日更新:タイトル他マイナーチェンジ、PDF追加)
#study group#judith butler#noura erakat#bds#on antisemitism#jewish voice for peace#feminisms#anticolonialism#antisexism#antiracism
1 note
·
View note
Text
2018レインボー・リール東京での『テルアビブの女たち』上映について
【レインボー・リール東京での『テルアビブの女たち』上映について
ブランド・イスラエル効果/ピンクウォッシングに気をつけてください】
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2102482616686635&id=1890621221206110
https://twitter.com/lgbtq_luna/status/1014042853062791168
今年も第27回レインボー・リール東京(東京国際レズビアン&ゲイ映画祭)が開催されることは喜ばしく、尽力されている方々に感謝と敬意を捧げたいと思います。
今回、2014〜17年には上映されることのなかったイスラエル映画が再び登場しています。わたしたちは、『テルアビブの女たち』上映について、ブランド・イスラエル効果、およびピンクウォッシングには留意が必要であることに注意を喚起します。
BRAND ISRAEL
https://bdsmovement.net/cultural-boycott#tab1
(1) イスラエル・フランス映画となっているこの作品は、Palestinian Campaign for the Academic and Cultural Boycott of Israel (PACBI)のガイドラインに照らして、資金調達と「ブランド・イスラエル」への貢献について疑問があり、グレーゾーンにあります。
PACBI Guidelines for the International Cultural Boycott of Israel
https://bdsmovement.net/pacbi/cultural-boycott-guidelines
イスラエルに対する国際的なカルチュラル・ボイコットのPACBIによるガイドライン(2014年7月版)[仮訳]
https://note.mu/selfishprotein/m/mef9daeab60ac
(2) 従来、同映画祭でイスラエル作品が上映される際には、イスラエル大使館の後援を受けていましたが、今回はどういう経緯によるものかフランス大使館(およびアンスティチュ・フランセ日本)の後援のみが付けられています。よって、本作品上映はボイコットの対象とはなりません。
(3) また、原題Bar Baharや英語タイトルIn Betweenにない「テルアビブ」や「女たち」という語が入る『テルアビブの女たち』という日本語タイトルが付けられ宣伝されることの政治性、「ゲイ・シティ」として売り出されている「テルアビブ」を舞台とし表題に掲げる映画が「セクシュアル・マイノリティの人たちの育んできた豊かなカルチャー」を謳う「レインボー・リール東京」で上映されることには、「ブランド・イスラエル」との接続、ピンクウォッシングとの親和性があります。
(4) なお、今回『傷���という南アフリカ作品が上映されますが、監督のジョン・トレンゴーヴはパレスチナのクィアからの呼びかけに答えて2017年のテルアビブ国際LGBT映画祭への参加をとりやめたという経緯がありますので、参考にしてください。
https://bdsmovement.net/news/award-winning-south-african-filmmaker-cancels-participation-israeli-lgbt-film-festival
(5) 映画祭スポンサーについては、ソフトバンクは、イスラエル企業への出資・協業を推進していますので、警戒してください。
ソフトバンク、イスラエルのサイバー攻撃防御技術スタートアップCybereasonに1億米��ルを出資
http://thebridge.jp/?p=241540
ソフトバンク、イスラエルのInuitiveとAI/IoT分野で協業
https://japan.cnet.com/article/35111368/
ソフトバンク、3Dセンサのイスラエル企業「Vayyar」とIoT分野で協業
https://japan.cnet.com/article/35112535/
2018年7月3日
フツーのLGBTをクィアする
http://feminism-lesbianart.tumblr.com
[email protected]
#フツーのlgbtをクィアする#pinkwashing#information#bds#in between#rainbow reel tokyo#tokyo international lesbian and gay film festival#tilgff#statements
2 notes
·
View notes
Text
The Right to Maim 読書会
2018年8月18日更新:次回の範囲を少し変更。次回8月20日は、117ページからChapter 3の終わりまでと、Chapter 4をカバーします。
2018年8月6日更新:スケジュールを変更しました。8月27日はキャンセルで、9月3日、10日 (予備日) に延長しました。

■ 日時:
2018年7月2日(プレミーティング)、9日、23日、30日 (中止)、
8月6日、13日、20日、27日 (中止)
9月3日 (追加) 、10日 (追加)
月曜日 午後7時-8時50分
※7月16日はお休み
■ 場所:
東京ウィメンズプラザ 1階交流コーナー
渋谷駅 宮益坂口から徒歩12分
表参道駅 B2出口から徒歩7分
都バス (渋88系統) 渋谷駅から2つ目 (4分) 青山学院前バス停から徒歩2分
東京都渋谷区神宮前5-53-67 〒150-0001
http://www1.tokyo-womens-plaza.metro.tokyo.jp/outline/tabid/136/Default.aspx
■ 費用:
資料コピー代実費各回50円まで。
※7/2の資料はありませんので無料
■ 定員:
各回10人まで。先着順。
■ テキスト(文献が手に入りづらい場合はお気軽に連絡をください):
7/2 (この回は事前申込不要/当日配布資料なし)
Chen, Mel Y. 2011. "Toxic Animacies, Inanimate Affections." GLQ: A Journal of Lesbian and Gay Studies 17 (2-3): 265-286.
7/9~8/27 9/10 (延長)
Puar, Jasbir K. 2017. The Right to Maim. Durham: Duke University Press.
https://www.dukeupress.edu/the-right-to-maim
PrefaceとIntroductionはPDFで公開されています。
https://www.dukeupress.edu/Assets/PubMaterials/978-0-8223-6918-9_601.pdf
■ 進め方:
この読書会では2017年に出版されたJasbir Puarの"The Right to Maim" (直訳すると『傷つける権利』) という英語で書かれた本をみんなで読みます。
7/2プレミーティングでは、Mel Chenの2011年の論文"Toxic Animacies, Inanimate Affections."を読みます。7月9日以降は、Introductionを後ろにまわして"The Right to Maim"を1回1章くらいのペースで順番に読んでいきます。
読書会は毎回最初の30分程度は内容を確認し、できるだけ何が書かれているのかを理解した上で、残りの時間で気がついたところや思いついたことをシェアします。
7/9以降は日本語の簡単な概略を用意します。参加者の英語力は問いませんし、全部読み終わってなくても大丈夫ですが、テキストはできる範囲でちょっとでも予習してくるとより楽しいですよ。
ディスカッションは日本語です。
テキストが手に入りづらい場合はお気軽にお問い合わせください。
■ 企画理由:
この本でPuarは、ディサビリティではなくディビリティという概念を出してきているのですが、この概念でなければ議論できないことがいったい何なのかについて、わたしはそこまで説得されていません。難しいから理解できていないだけというのもあるとは思うのですが、いまのところの理解では、これが現状を正当化するロジックとして機能しやすいのではないか、と警戒しているからです。
同時に、具体的な暴力による軍事占領や入植者植民地主義やアパルトヘイトへの抵抗としての、反ピンクウォッシングの活動があるとしたら、それはどういうものになるのかを考える上で、このテクストを読むことは助けになるとも思っています。
もう一つの企画理由は、これまでの活動履歴にあります。イスラエルの「ピンクウォッシング」については、2013年の東京レインボープライドでのイスラエル大使館ブース出展以来、考え対抗する活動をしてきました。「フェミニズムとレズビアン・アートの会」としてTRPや大使館宛に意見を伝えたり、「フツーのLGBTをクィアする」というプロジェクトで、勉強会やイベントを企画したり、それ以前から日本国内外で展開されてきたパレスチナ連帯運動とつながったりもしてきました。
たとえば2015年、日本の複数の市民団体が連名でピアニストの上原ひろみさんへ宛てた、イスラエルでのコンサート中止を要請する書簡には、フェミニズムとレズビアン・アートの会も賛同しています。
ですが、この要請文については納得がいかないまま、出してしまった部分が実はあります。
上原ひろみさん宛てのお手紙はこちらから全文が読めるのですが
http://d.hatena.ne.jp/stop-sodastream/20151023/1445604839
その中に、ボン・ジョヴィのイスラエルでのライヴに対し、元ピンク・フロイドのベーシストであるロジャー・ウォーターズが送った書簡を引いた箇所があります。
参照記事原文:
Roger Waters to Jon Bon Jovi: "You stand shoulder to shoulder with the settler who burned the baby"
https://www.salon.com/2015/10/02/roger_waters_to_jon_bon_jovi_you_stand_shoulder_to_shoulder_with_the_settler_who_burned_the_baby/
(引用ここから)
でも、上原ひろみさん、あなたに読んで欲しい記事をひとつ選ぶなら、脚を射ち砕かれたサッカー選手の記事です。ふたりのうちのひとりは両脚に1発ずつの銃弾、もうひとりは、左脚に7発、右脚に3発、そして左手に1発、11発の銃弾を受けています。通常なら命を狙うところ(ガザに対する空爆では、やはりナショナルチームメンバー3人が殺戮されていますが)、サッカー選手故に、故意に脚に銃弾を集中させたと見えないでしょうか、二度とサッカーができない事を嘆き悲しみながら生きるよう強いる悪意で。
上原ひろみさん、想像してみてください。あなたが指を射ち砕かれたらと、それもピアニスト故に、と。どうぞ、彼らの嘆きに思いを馳せてください。そして、イスラエルがアパルトヘイト政策を放棄するまで、イスラエルでのコンサートに参加しないと決意してください。
(引用ここまで)
ここは、攻撃する側のロジックにいったん乗るような形で、それぞれの人が殺されて死んでしまうことや爆撃による怪我の痛みそのものというより、障害をもって生きつづけることへの一般的な恐怖を利用し、特定の攻撃方法の残虐さをあぶりだしつつ、そこへの加担をしないように訴えるという論理が使われています。
この箇所で、わたしたちが乗ってしまったのは、本当に攻撃する側にしかないロジックなのか。わたしは、そうではないように思っているし、わたしたちがすでにそのロジックの中にいるのであればなおさら、これに対抗するとはどういうことなのかを、考え続けていかなければならないと思っています。そのために、今回の読書会は企画しました。
■ 参加方法など:
- 参加を希望される方は前日7時までにメールでご連絡ください。
- 欠席される場合は、当日直前でもかまいませんのでご連絡ください。
- 1回だけでも続けての参加もできます。
- 多くて8人くらいの集まりになる予定です (テーブルの大きさ的に)。
- 「見学」 (沈黙) というのはなしです。
(実際は会場の都合で、覗き見&立ち聞きできます。お気軽にどうぞ。)
- 性別・性自認・性指向・国籍・学歴など不問。
- 申し訳ありませんが、読書会に参加されない方に当日配布資料はお渡ししていません
(今回の読書会に参加して欠席回の資料も必要な場合はその都度ご相談ください)。
- 分からないこと、不安な点があればメールをください。
問い合わせはJanisまで。janis_cherry(at)selfishprotein.net
■ 7/9以降参加希望される方は
次の項目についてお一人ずつメールで教えてください。
メールアドレスは janis_cherry(at)selfishprotein.net
—– (参加希望メール内容ここから)——
・ なまえ (法律上でも通称でもかまいません。メールのやりとりのためのなまえ)
・ パソコンのメールアドレス
・ 当日連絡用のメールアドレスまたは番号があれば
・ 参加希望日 (今のところの参加予定;どの回に来られそうですか?)
7/9、7/23、8/6、8/13、8/20、9/3、9/10 (スケジュール変更後の開催予定)
・ この読書会のことをどうやって知りましたか?
・ 本は持っていますか? 購入する/図書館で借りる予定等はありますか?
(参加前にテキストが手に入らない場合は相談してください。)
・ 何か要望などあればどうぞ。
—– (参加希望メール内容ここまで)——
■ いまのところの予定:
7/2
(文献が手に入りづらい場合は連絡を/事前申込不要/当日配布資料なし)
- Chen, Mel Y. 2011. "Toxic Animacies, Inanimate Affections." GLQ: A Journal of Lesbian and Gay Studies 17 (2-3): 265-286.
7/9以降の文献
(文献が手に入りづらい場合は連絡を/事前申込必要/当日配布資料あり・コピー代実費かかります)
- Puar, Jasbir K. 2017. The Right to Maim. Durham: Duke University Press.
7/9
Preface: Hands Up, Don't Shoot! ix
ちなみにPrefaceとIntroductionはPDFで公開されています。
https://www.dukeupress.edu/Assets/PubMaterials/978-0-8223-6918-9_601.pdf
7/23
1. Bodies with New Organs: Becoming Trans, Becoming Disabled 33
7/30 8/6
2. Crip Nationalism: From Narrative Prosthesis to Disaster Capitalism 63
8/6 8/13
2. Crip Nationalism: From Narrative Prosthesis to Disaster Capitalism 88-end
3. Disabled Diaspora, Rehabilitating State: The Queer Politics of Reproduction in Palestine/Israel 95
8/13 8/20
3. Disabled Diaspora, Rehabilitating State: The Queer Politics of Reproduction in Palestine/Israel 117-end
4. "Will Not Let Die": Debilitation and Inhuman Biopolitics in Palestine 127
8/20 9/3
Postscript: Treatment without Checkpoints 155
Introduction: The Cost of Getting Better 1
8/27 9/10
予備日&まとめ
問い合わせはJanisまで。janis_cherry(at)selfishprotein.net
(最終更新日:2018年8月18日 次回8/20の範囲変更。)
2 notes
·
View notes