#エルダースクロールズ
Text
エドワード王 二巻
昔日の王の一代記、二巻
ファーストホールドでの再会
エドワードは赤い空に目を覚ましました。太陽は西の山々に上ったばかりです。彼らは各面が炎に輝く塔のすぐそばに来ていました。ドラゴンは急に方向を変えて近くに飛び、炎の長い息を吐き出しました。彼らが突然高度を下げると、塔の頂上で何度か光が点滅しました。エドワードのお腹はとても変な感じでした。彼はため息をついて身体を動かすと、モラーリンが右手でエドワードを抱けるように体をずらしました。彼は身体を伸ばしてあくびをしました。
「もうすぐだ。クリスタルタワーからファーストホールドまでは馬で数日だが、アカトシュは1時間以内に連れて行ってくれると思う」
「塔には寄らないの?アイリック―」
「軽々しくその名前を使うんじゃない。私にさえもだ。アーチマジスターは向こう何日かは戻らない。ユニコーンは風の兄弟分で、同じぐらい早く旅をする。荷物があってもな。だが、ドラゴンが飛ぶほどじゃない。エルフの故郷がドラゴンの帰還の始まりを迎えているのがわかるだろう。人類の幸運を祈るんだな」
エドワードの視線は深い森の中と、無骨な丘をさまよいました。人のいる印は見えませんでした。「きれいだね」彼は謙虚に言いました。「でもハイロックほどじゃないや」忠誠心からそう付け加えましたし、それは事実でした。「街も、村も農場もないの?」
「ファーストボーンは森の奥深くに住まっている。彼らは大地を引き裂かないし、新しく植えもしない。だがオーリエルが差し出すものは喜んで受け取る…そしてお返しをする。ああ、成長するものの青臭いにおいだ」
確かに、その空気はエドワードが父のカップからすすったことがあるワインと同じような感じがしました…「お腹空いた」
「そうだと思った」少し体を動かし、モラーリンの左手が小さな葉っぱの包みを取り出しました。浅黒い手は大きくて力強く、人にも動物にも見えませんでした。エドワードは嫌悪しながらその手を見つめ、やがてその手に触れないように極めて慎重に包みを取りました。モラーリンが身体を強張らせるのがわかり、エドワードを抱く手が少しその力を弱めました。エドワードは自分の行動を恥ずかしく感じました。この状況で気を悪くさせるのは、親切でも賢明でもありませんでした。モラーリンは簡単に彼を落とすことができるのです。「僕お風呂に入りたいけど、君もだよね」彼はぎこちなく言いました。モラーリンがわざと彼の反応を誤解してくれたことを、エドワードは知っていました。「ああ、私はとても汚れている」エドワードがケーキをかじると、それは見た目よりずっとおいしいことを証明しました。「母さまはそんな風に僕を見ていたよ―少なくとも、そうだった。でも多分、僕はまずお風呂に入るべきだよね?」
「お前はその選択の必要はないと思うが。ああ、やっとだ!」ドラゴンはその翼を広げて空に舞い上がり、巨大な炎の固まりを吐き出すと、広い空き地に降り立ちました。着陸は急角度で、大きな衝撃がありました。エルフたちが急に現れて、彼と、やっと目を覚まして半狂乱でぐるぐる走り回り、エドワードの足元で喘ぐシャグに腕を伸ばしました。
銅の色の炎のような髪をした背の高いエルフが、礼儀正しく彼らに挨拶しました。「ご機嫌麗しゅう、我が王よ。ご婦人がお待ちかねです。エドワード王子、ファーストボーンの地へようこそおいでくださいました。我が民に成り代わり、歓迎申し上げます。ここでのご滞在が心地よく、実りあるものでありますように」
モラーリンは恭しく頷きました。「ありがとう。わが女王は十二分にお待ちになった。すぐにお目にかかろう」エドワードの肩に置いたモラーリンの手が、彼を見たこともないほど大きな木に導きました。その幹は空洞で、中に入ると上に導かれました。開口部にはさらに階段があり、丈夫な枝に橋が架かっています。彼らは大きなひさしがついた、部屋のように椅子とチェストがしつらえられた台に着くまで、それに沿って前に進みました。金色の肌の女性が彼らに微笑みかけ、手招きをして立ち去りました。背が高くほっそりした、蒼白い肌の黒い髪の人間の女性が彼らに歩み寄りました。彼女の眼はエドワードを捉えていました。エドワードだけを。
「どうしていなくなっちゃったの!」その叫び声は彼の深いところから現れ、彼の全身に響き渡りました。その声は彼の数歩手前で彼女を立ち止まらせました。今度は彼女の目がモラーリンを見上げました。彼はエドワードが聞いたことのないような厳しい調子で言いました。「お母様に敬意を持ってお話をなさい、無作法な子だ!」その瞳の一瞥の衝撃で、彼の目に水が溜まりました。
アリエラは素早く彼に近寄り、両手を彼の胸に置きました。「おかえりなさい、旦那様。あなたと息子を無事に私の下に連れてきてくださったノトルゴを称えましょう」
「竜たちの盟主と盗賊さんにも感謝いたしますわ。彼らなしでは私のぼうやをあれ以上きれいに連れてくることはできませんでした。アーチマジスターもうまくことを運んでくださったのね」モラーリンの浅黒い手がそっと優しく彼女の腕に置かれました。彼は落ち着いて幸福そうに笑いました。でも、彼の胸に置かれた両手は、彼を労わるようでもあり、障壁を作っているようでもありました。
「私は本当に恵まれているわ。でも、息子と話すのは久しぶりなのです。二人だけなら、もっと話がしやすいかもしれません」
モラーリンの笑顔がさっと消えました。「3人でいるより2人の方が言葉が見つけやすいと?まあ、そうかもしれないね。時にはね、奥さん」彼は踵を返して去って行きました。橋が揺れて軋みましたが、彼の足は少しも足音を立てませんでした。
アリエラは彼の背中を見ていましたが、彼は振り向きませんでした。エドワードは、また彼の敵に苦痛を与えたことで、好奇心と満足感と後悔が混ざったような気持がしました。「エドワード、私の坊や。ここにきて座ってちょうだい」
エドワードはその場に立っていました。「お母さま、僕は何年も待って、答えを求めて何リーグも旅をしました。僕はもう待ちません。一歩だって動きません」
「何と言われていたの?」
「父が客の名誉を信頼しながら夜眠っている間に、魔法の助力を得て最も卑劣な方法で誘拐されたと」
「お父さまがそう言ったのね。モラーリンは?」
「完全に自分の意思で来たと言いました。あなたの言葉で聞きたいのです」
「私がなぜあなたのお父さまの下を去ったか、どうしてあなたを連れて行かなかったのか、どちらが聞きたいですか」
エドワードは間を置いて考えました。「母上、僕は本当のことが聞きたいんです。ですから、僕は本当のことを知らされなければいけません。あなたが僕を置き去りにしたことを。もう一つの方は、僕は知っていると思います。あなたがそれ以上に、またはほかに話したいと願わない限り、僕はわかっているだろうし、わかると思います」
「真実ですか?真実とは、それを理解している者から独立して存在するたった一つのものではありませんよ。でも、あなたに私の真実を話しましょう。そうすればきっと、あなたは自分の真実にたどり着くでしょう」
アリエラは静かにクッションのおかれた椅子に歩いて戻り、姿勢を正しました。ルビーの色をした小鳥がすぐそばの小枝に停まって、彼女の穏やかな声に伴奏をつけました。
「私の両親が私の結婚を故郷の習慣通りに決めてしまったのです。私はコーサイアを愛していませんでしたが、初めは彼を尊敬していましたし、良い妻でいようと努めました。彼は私を気にかけもしなければ、世話もしてくれませんでした。ですから、彼は私の尊敬を失い、手をかけてもらえない植物が枯れていくように、私は毎日少しずつ死んでいたのです。あなたといる時だけが私の幸福でしたが、コーサイアは私があなたを軟弱にすると考えました。『女みたいに』と彼は言いましたわ。そうして、あなたの3回目の誕生日のあと、私は毎日たった1時間だけ、あなたと過ごすことが許されました。あなたの泣き声を聞きながら、何も考えられずに座って泣いていました。ようやくあなたが泣き止んで私を求めると、私の心は空っぽになりました。私は護衛を一人か二人しか付けずに、長い時間一人で散歩をして、馬に乗るのが癖になりました。そんな時、モラーリンがやってきたのです。彼はロスガー山脈にある黒檀の鉱山を欲しがっていました。彼が使いたがっていた土地は、私の持参金の一部でした。彼は私たちの民に彼の技を喜んで教えてくれましたし、ダークエルフが作った武器を差し出してさえくれました。そのお礼に、私たちの民はゴブリンを遠ざける彼の手助けをして、ハイロックに彼の民の植民地を作ることを許したのです。コーサイアは土地には興味がありませんでしたし、本当に武器をとても必要としていました―最上のものでしたからね―ですから、彼はその申し入れを喜んだのです。話し合い、決めるべきたくさんの細かい事柄があって、その交渉への干渉が私にも降りかかりました。コーサイアはダークエルフを嫌っていましたし、タムリエルで最も優れた戦士として既に名声を得ていたモラーリンに嫉妬していたのです。
「でも、モラーリンは熟練の戦士以上の人でした。彼は読書家で、太陽の下にあるものすべてに興味を持っています。ヤー・フリーとジム・セイから教えを受けたように歌い、演奏することもできました。彼は、私が夢でしか会えないと思っていた、それ以上のお相手でした…誓いますわ。私たちは二人とも外にいるのが好きで、話し合いは乗馬と散歩の間でしたが、いつも彼の部下とコーサイアの部下が一緒でした。すべてが整った時、コーサイアは条約を祝って大きな宴会を開きました。ハイロックのすべての貴族がやってきて、他の地域からもたくさんの人たちが訪れました。最後に、酔っぱらったコーサイアが血でなければ洗い流せないような侮辱の言葉を漏らしました。私は他の貴婦人たちととっくに席を立っていましたから、それが何だったのかは知りません。でも、私はコーサイアがそのような言葉をため込んでいることを知る程度には、個人的に充分聞いてきました。モラーリンは決闘を申し込み、それまでに彼がウィットを取り戻すかもしれないと、コーサイアに昼までの猶予を与えました。
「そしてモラーリンが独りで私の部屋に来て、何が起きたかを話してくれました。『奥様、彼はあなたの弟君を決闘相手に選ぶだろうと思います。いずれにせよ、もう二度と関わることのできない血の河が、私たちの間に流れるでしょう。私はあなたの愛なしで生きていくことはできます。だが、あなたに憎まれることには耐えられない。共に来てください。妻として、あるいは名誉ある客人として、それはあなたの選択です。そして、ご親族の代わりに、あなたは血の代価として貢献なさるでしょう』
「そして、月明かりの下で、恐れおののいて、眠っている貴婦人たちのそばで、私は彼を愛していることを知ったのです。彼なしで生きて行けるかは疑わしかったけれど、それでも、あなたをそれ以上に愛していたの!『息子は』私は囁きました。『置いては―』『奥様、選ばなければなりません。お気の毒ですが』わかるでしょう、エドワード?もし留まれば、私の弟の死が―彼の無垢な若い血が流れるのです。あるいはあなたのお父さまの血が!あるいは、そんなことは起きないと思っていたけれど、私の愛する人の血が流れたかもしれません。モラーリンの戦闘技術はそれだけでも優れていましたし、この類の出来事には、彼は同じくらい優れている魔法の力も借りるでしょう。『連れて行けますわ』でもモラーリンは悲しげに首を振りました。『私にはそんなことはできない。父と子を引き離すことは、私の名誉に反する』
「愛する者を一人ぼっちにする、私は義務には慣れていました」アリエラは誇らしげに言いました。「あなたを父親から、あなたの大好きなおじさまから盗んで行けばよかったでしょうか?そして、おそらくコーサイアは生き残り、この件で私を責め、私を遠くにやってしまう言い訳にしたはずです。コーサイアは私がいなくなれば喜ぶだろうと考えました。彼が本当に武器を欲しがっていることは知っていました。あなたと過ごす時間を得るために、それで取引することもできると私は考えました。モラーリンが私を見ずに立って待っている間、すべてが私の中を駆け巡っていました。
「マーラ様、正しい選択をお助け下さいと私は祈りました。『本当に私を妻にしたいのですか?私は―私は厄介ごと以外何ももたらしませんのよ』
『アリエラ、私はあなたを妻に迎える。私が求めているのはあなた自身だけだ』彼はマントを脱ぎ、布団を引き剥がしながら私の体を包みました。
『モラーリン、待って―これは正しいことかしら?私がしようとしていることは?』
『奥様、もし間違いだと考えているなら、私はここに立ってなどいない!あなたに与えられた選択肢の一つは、私には最も正しいことに思えます』彼は私を抱き起して、馬に運んでいきました。そうして、私は彼のマントだけを身に着け、彼の前に座って馬に乗り、あなたのお父さまの家を去ったのです。野蛮な喜びと悲しみが混じって、自分がどう感じているかわかりませんでした。これが、私の真実です」
エドワードは静かに言いました。「でも、彼は結局、僕とお父さまを引き離した」
「本当に渋々だったのです。そして、ドラゴンが、本当には、あなたとお父さまの心は既に離れてしまっていると言ったからです。何リーグかだけのことです。これはあなたの安全を保つ方法なの。モラーリンはここに来ることを決めるのは、あなたの自発的な決断であるべきだと言いました。それと同じに、戻りたい時に戻っていいのですよ」
「モラーリンは僕をただ連れて行こうとした!アイリ―その、アーチマジスターが同意しなきゃいけないって言ったんだ」
「彼は忍耐強い性質ではないのです。そして、彼はコーサイアを傷つけてしまわないか不安でした。彼がその議論をどこかほかの場所で続けられると考えていたことは間違いありません」
「肝っ玉の小さい王だって呼んだんだ。そして笑ったよ。どうして?ダガーフォールの人の肝臓はエボンハートの人のより小さいの?第一、それに何の関係があるの?父さまはとても怒ってた。きっと戦いたかったと思うな。でも、父さまが僕を嫌ってるのは本当だよ。わかってるんだ。でも、わかりたくなかった。だからそうじゃない風にふるまっていたんだ。モラーリンはそうじゃないと思うけど」
「ええ」
「でも、彼は嘘をついた。彼は僕の父親だって言おうとしてた。わかるんだ」
アリエラは頭を後ろにそらせて、鈴を転がすような声で笑いました。彼は遠い記憶からそれを思い出し、背中がぞくぞくしました。「もしあなたにそう思ってもらえたら、きっとものすごく、心からそう言いたかったに違いないわ。彼はいつでもせっかちなの。そして、彼は誓いの下では決して嘘をつかないし、愛するものを傷つける嘘はつかないわ」
「僕のことを愛してなんかいないよ。僕のことを好きでさえないんだ」
「でも、私は愛しているのよ、私の大切な坊や。あなたは―」エドワードは彼女が大きくなった、と言おうとしているのだと思いました。大人たちはいつでも彼の成長を見てそう言うのです。一週間前に会ったばかりでも。奇妙なことに、年のわりに、彼は小さかったので。彼女はその代わり、「私が考えていた通りだわ」と母の深い満足を湛えて言いました。
「彼はあなたのことを愛してる。でも彼は使いっぱしりの小僧じゃないと言った。でも、あなたは彼がそうみたいに下がらせた」
アリエラの顔と首が真っ赤になりました。
「確かに、私は召使いに格下げされたようだね」うず高く食べ物が積まれたお盆を持って、モラーリンが静かに入ってきました。「椅子を取ってくれないか、少年。私が給仕役をやれるなら、お前も給仕役をやれるだろう。お前はお腹が空いているだろうし、妻が私の欠点の残りの部分を話す前に戻った方がいいと思ったのでね。それを挙げ連ねるのにほとんどまる一日かかるから」彼は鎧を脱いで風呂を浴び、細いウエストの周りに銀のサッシュを巻いて、洗い立ての黒いジャーキンとズボンを着ていました。でも黒い剣は、彼の横で揺れていました。
「まあ、なんてこと。小さな軍隊がお腹いっぱいになるほどの食べ物を持っていらしたのね。それに、私は朝食を済ませましたの」アリエラは小さな手でエルフの腕に触れ、愛撫するように下に滑らせて彼の手を握って力を込めると、それをまだほてっている首に持ち上げ、唇でその手をなぞりました。彼女の美しさに向かい合う浅黒い肌に居心地の悪さを感じながら、エドワードは素早く目を逸らしました。
「これは私用と、少しは坊やのためにね。でも、ご相伴してくれると嬉しいよ。君は痩せてきている。私にとっては針みたいだ、本当にね」彼女の黒い巻き毛の束を指に巻き付け、軽く引っ張ってにやりと笑いました。それから、食べ物に移ると、人間がするように指で食べるのではなく、小さな銀色の武器で飢えた狼のように襲い掛かりました。その食べ物は―素晴らしかったのです。エドワードはもう何も入らなくなるまで食べました。
「立ち聞きしていたんだが」彼は思慮深そうにもぐもぐと言いました。彼は食べている間、モラーリンの欠点を口の中でもそもそと挙げ続けていました。そして、もっと早く大きな声で言えばよかったことがわかりました。
「ゼニタールよ、坊や、君たち人間は、個人的な話を木の上全体に聞こえるような大きな声で叫んでも、私が耳に綿を詰めて聞かないでいてあげると期待しているのかね?」彼は大きなとがった耳をとんとんと叩きました。エドワードは急いで何を話したか思い出そうとしました。嘘をついたと言いました。ああ、なんてことでしょう。彼が聞いていませんように。
「それで、私は嘘つきなんだって?坊や」ヴァー・ジル、彼に救いの手を、エドワードは溺れ死ぬような気持がしました。このエルフは心を読めるのかしら?彼はそれが父親が彼に使った侮辱の言葉ではないことを願いました。「僕―僕は、そのことを考えていると思ったって意味で言ったんだ。口ごもったもの」エドワードは喘ぎました。彼はものごとを悪い方に転がしていました。
「たぶん、私は思い出そうとしてたんだよ…」皮肉っぽい響きが戻ってきました。
「僕のことなんか好きでもないくせに!」エドワードが大きな声で言いました。
「だからって、本当の父親がお前に主張するのを止めることになるようには思えないね」
「モラーリン、やめて!」アリエラが遮りましたが、エルフは片手を上げて彼女を黙らせました。
「わからないんだ」エドワードがちらりと見ました。
「どうしてあんなことを言ったんだね?」
「わからない―ロアンが言ってた―ことなんだよ―そして、僕はちっとも父さまに似てないんだ。みんなそう言うよ。そして話をやめてしまうの」
「言ってたこと―とは何だね?言いなさい、坊や!」
「二人が若かったころ、どれほど母さまがおじさまのことを好きだったかって。母さまが連れていかれたあと、彼がどんなに悲しんで怒ったかって。弟じゃなくて恋人みたいだったって彼女は言った。とってもかわいらしくそう言ったけど、何か他の意味があるみたいだった。口に出すのがとても汚らわしい何かだよ。他の時には、あの人は僕がとてもエルフっぽく見えるって。僕が結婚したあととても早く生まれたことも。あの人の一人目の息子みたいじゃなかったって」
モラーリンは跳び上がりました「何だって!戻ってあの女狐の首を絞めてやる!人間は―」彼は悪態をかみ殺しましたが、その赤い瞳は怒りに燃え上がり、筋肉がはちきれるように膨らんで、髪は逆立っていました。「お前はエルフと人間の子供には見えない。私が母上に出会ったのは、お前が母上のおなかに宿ってから4年後だ。どうやらロアンはどちらの嘘を使いたいのか決めかねたのだろうね。だが、近親姦などと!私ができないなら、ケルが代わりに鉄槌を下しますように」背の高いエルフは怒り狂って部屋の中を歩きました。カジートのようにしなやかで、片手は剣の柄を撫でています。その台が揺れて、少し下がりました。
「エドワードに比べれば、彼女は自分の息子たちに大望を持っている。疑問なのは、彼女の話を信じる者がどれほどいるかだ。彼を殺させる計画をしているなら、充分ではないだろう」アリエラのなだらかな眉に小さなしわが寄りました。「あのね、私は彼女を嫌ったことはないのよ。彼女もそう。あの方は私の立場を欲しがっていて、私はエドワードを救うために喜んで譲ったわ」
「僕に王様になってほしいんだね。そうしたら黒檀の鉱山を持てるから」エドワードはパズルを解きました。
「まあ、黒檀なんてどうでもいいの。おそらく彼が手に入れるでしょうし。あなたのお父さまがお亡くなりになったら、ロアンの子供たちと協力するより良いチャンスを持っているの。彼らには感謝する十分な理由がありますし、いい取引よ。そうは言っても、彼らの両親のことを考えると、契約にサインするのに充分なほど、自由に口が利けるかどうかは見込み薄だけれど」
「それじゃ、なぜ?僕のこと好きでもないのに」
「マーラ、お助けを!人を『好き』と思うことは人間の概念だ。ある日、彼らはお前を好む、次の日は好まない。火曜日にはまたお前のことを好んで戻って来る。私の妻は私に対してそうするが、彼女が私を好きじゃない時でも私を愛していると言うよ。彼女がどちらもしない日と、リアナの騎士団に加わる話をする時以外はね。そんな時は、私は彼女が正気に戻るまで狩りに行く」
「大げさね、そんなの一度しかなかったし、よく知っているくせに」
「回復期間は大いに楽しんだのを覚えているよ。もっとあってもいいかもね」二人はお互いににやりと笑いました。
「だけど、どうして僕に王様になってほしいの?」エドワードは食い下がりました。
「言っただろう、それはアカトシュの意思なのだ。それと、アーチマジスターのね。私は遠乗りに付き合っただけさ。彼らに聞いてごらん」
「アーチマジスターに会ったら聞いてみよう」
「素晴らしい考えだ。我々と北に旅立つ前に、お前は2、3週間タワーで過ごすことになるだろう」
「それだけ?」
「お前の母上と私と一緒に冬を過ごす計画がそんなに嬉しくないかね?」
「そんなことは…ないです。でも、アイリックと一緒に行くって言ったんだ」お前じゃなくて、口に出さなかった言葉が、二人の間にありました。
「そうなるだろう、そのうちね。今、そこでの数週間は、魔法の訓練を始めるのにちょうどいいだろう。私はお前に呪文を教えてやれる。だが、お前は強くならなければならない。お前の体が心に追いつかなければいけないんだ。それはアーチマジスターの意思なのだよ」
「戦闘の魔法?僕は他のことを勉強したいな。獣の呼び出し方、癒し方、そして浮き方…」
「それも学ぶだろう、必ずね。それと、お前は戦士は癒せないと思っているのか?それはお前がいちばん最初に学ぶ呪文だ。だが、王は戦い方を知らねばならない」
「得意じゃないんだ」
「ドラゴンの歯だよ、坊や!まさにそれがお前が学ばねばならない理由だ」
「もしできなかったら?」
「お前は勇気があって、澄んだ頭を持っていて、魔法を学ぶ潜在的な力がある。それは大抵の者が持っている以上のものだ。残りの部分は私が教える」
エドワードの頭が、不慣れな賞賛にぐるぐる渦を巻きました。「僕が?本当に?君が?」
「お前はお父上の愚かな王宮の者たちがドラゴンとユニコーンの前に丸腰で向き合って、アーチマジスターとタムリエルの英雄に、彼らの正義を要求すると思うのかね?正義だって!そんなものを前にしたら、彼らはどうにか慈悲を請うのが関の山さ、それだって疑わしいが、口が利けるものならね」
「僕、そんなことした?したのかなあ?」エドワードはすっかり驚いてしまいました。彼は知らなかった、考えたこともなかったと付け加えたいと思いました。
「ああ、したとも。そして、それはここからモロウィンドに向けて歌われる行いだ。私はそのバラードを作曲しよう―昼寝をしたらすぐにね。ドラゴンの背中の上ではあまりよく眠れないんだ」
「僕とシャグに眠りの魔法をかけたね!」
「そして城の他の者にもだ。友人に手伝ってもらってね」
「うわああ。宙にも浮けるの?見せてくれる?」
「そう急ぐな。私はドラゴンの背中に一晩中とどまっているように、動きを固める魔法を全員にかけていたんだ。休むまではマッチを使わずにろうそくに火を灯すこともできないよ」
「ああ、わかった。それでも僕は、戦士よりもアーチマジスターみたいになりたいな」
「はっ!アーチマジスターが戦えないなんて、そりゃニュースになるな!彼がお前に杖の扱い方を見せる時間があることを願うよ。初期の訓練には最適の武器だ。そして彼以上の講師は望めない。さあ、お前が前に見た四人の中で、誰が一番優れていると思う?」
エドワードは数分の間、慎重に考えました。「僕の判断は本当に粗末だけど、それでもよければ、タムリエルのチャンピオンって称号を使う人が一番優れているはずだと思う。でも、アーチマジスターは君の魔法の先生ではないの?そして武器の扱いもよく訓練されているみたいだ。だから、誰が勝っているか?ドラゴンの炎と爪と歯に太刀打ちできる人間がいるかな?それに、とても足が速くて、尖った角と蹄があること以外、僕はユニコーンのことは何も知らないんだ。とってもおとなしかったし。それで、君が尋ねたその質問には、正しく答えられそうにないんだ」
「いい答えだ、坊や!単体の近接戦闘ならユニコーンは簡単に勝てる。人間も、ドラゴンでさえ、あんなに早く一撃を当てられないし、炎で焼くこともできないし、魔法や属性の力も効かない。その蹄は致命的で、その角は一度触れただけで、どんな敵でも殺してしまう。角自体は燃えてなくなってしまうけれどね。それでも、一番強力なのは、それをすぐに再生できることだ。
「そして、4人のタムリエルの英雄は、互いに戦えばおそらく敗者になるだろうが、その称号は馬鹿げた自慢ではない!モラーリンは一流であることに慣れていない。結果として、私の行儀作法は苦しんでいるかもしれないがね」
「わが王よ、あなたには心から感謝申し上げます。あなたは僕に偉大な栄誉と貢献を与えてくださいました。ご恩返しできることがあれば、致しましょう。僕の乱暴な言葉と不躾をご容赦ください。僕は粗野で粗暴な中で暮らしてまいりました。そして、僕には父がないようです。あなたをそう呼ぶことをお許しいただけない限りは」エルフは少年に手を差し出し、彼はその手に自分の手を置きました。エドワードの味気ない気分はすっかり消え…まるで魔法のように…思考が彼の心を漂います…すると彼は手を離して、モラーリンの腰にしがみつきました。エルフの手は黒い髪を撫で、薄い肩を掴みました。
「ありがとう、奥さん。結婚からたった5年で、君は私に9歳のすばらしい息子を贈ってくれた。非凡で、本当に…魔法のようだ」
2 notes
·
View notes
Text
放置スカイリム

僕はエルダースクロールズのスカイリムが大好きですねん。
もう発売から10年位経ちますが、
いまだにmodを入れたり消したりして
やっている。
スカイリムが支持される理由としては色々あるだろうが、
僕が一番好きなのは、クエストの内容だ。
クエストがたくさんあるゲームはよくあるが、
その殆どは
狼に困っているの!狼を15引き狩ってきて!
とか
トマトをみかけたら4つ持ってきてくれ。
とか
なんで初対面の人にそんなこと頼むの?
みたいな面白くもないもので埋められることが多い。
スカイリムのサブクエストは無数にあるが、
単純なものはほとんどない。
非常に難しい判断を迫られて、
どれを選んでも後味が悪いようなもの、
取り返しがつかないような結果になるものばかり。
だからこそプレイは慎重になるし、
その慎重さは、オープ��ワールドで
ロールプレイングをするときに、
没入の手助けになる。
要するに、
実際のじぶんならどうするか!?
という感情が、世界をリアルにする。
スカイリムの肝はここだと思っていて、
それ以外はオマケだ。
なので、その肝を分解して、再構築し、
きちんと味わえるようなゲームを作れば、
スカイリム好きに響くのではないか。
そこでやりたいのは、
モバイルの放置ゲームだ。
スカイリムの基本的な流れは、
よくあるお使いゲームだ。
クエスト受ける
→目的地に行く
→なんか事件起こる
→判断する
→結果
→またクエスト受ける
これの繰り返し。
であれば、2~3つめの、
「なんか起きる」→「判断する」という部分以外を、
ほぼ自動にして、放置しても進むようにすれば
手軽にスカイリムの肝を味わえると思った。
クエストを受ける
マップで目的地を決定
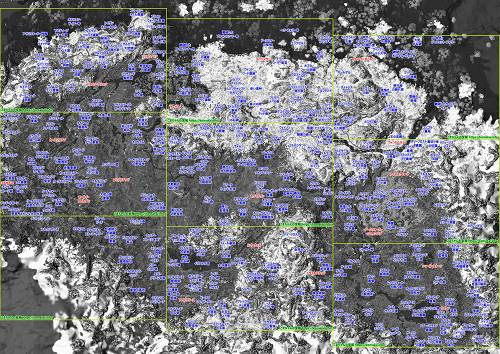
そこまで自動で移動する。
ここで時間がかかるが、ゲームを閉じていても進行する。
そして目的についたら、事件が起きていて、
プレイヤーは選択する。
そして結果を得る。
目的地につくまでの道中はあまり重要ではないので
移動時のグラフィックは適当でよい。
(自動生成された道を進んでいくだけでいい)
※もちろんこの道中でも、
なにかイベントが発生することはある。
これを繰り返してクエストを進めていく、
半放置RPGを作りたい。
実際のプレイ感を想像して、次回もう少し詳しく
書いてみよう。
1 note
·
View note
Text
@KotobaNoriaki(コトバノリアキ@単行本第②巻 好評発売中!)
@silverclock96 他にもエルダースクロールズ等の洋ゲーでも
常に勇者はChampion訳なので
英語圏では明確に一単語一訳ですねぇ
Twitter Web Appから

0 notes
Video
youtube
#27【RPG】The Elder Scrolls V Skyrim【スカイリム】
オープンワールドRPG「The Elder Scrolls V Skyrim(エルダースクロールズV スカイリム)」続きをプレイしています。
カジートでプレイしています!!
【The Elder Scrolls V Skyrim エルダースクロールズV スカイリム 再生リスト】
https://www.youtube.com/playlist?list=PLh8m2ie4qTAXYISCSugWaYhoNeBif6ZuK
【yosum58 Youtube Channel】
https://www.youtube.com/user/yosum58
1 note
·
View note
Text
【TES6】エルダースクロールズの続編が遅れる理由はTESオンラインと継続的なスカイリムの繁栄を守る為? 米経済誌フォーブスの見解
先週ベセスダのE3プレカンがあり、TESシリーズのファンから見れば、TESの新作(TES6)について何の発表もないであろう事は予想はされてはいたけども、少々残念な結果ではありました。 それで、ベセスダ・ゲームスタジオはTES6はいずれは製作するであろうけど、しかし、その前に新作2本の製作を抱えている…と言う現状も伝えられて来て、それでも「なぜこれほどTES6の製作を後回しにするのか?」 アメリカの経済誌のフォーブスのサイトに一つの見解記事が出たので、それを訳しておきます。…
View On WordPress
1 note
·
View note
Text
【悲報】スカイリムに続く超期待作『エルダースクロールズ6』、発売するのは「PS5」や新型Xboxが出てからになる模様他
ニュースが更新されました。
Source: News人
View On WordPress
0 notes
Text
エルダースクロールズ6が発表される!その内容は?
「エルダースクロールズ6」の発表というニュースがネット上を駆け巡っています
ベセスダの公式だそうです
広大なフィールドのみの映像で、具体的なタイトルや舞台の土地の名前は全く分かっておりません
映像を観ると雪が無く、緑に多めの大地ですね
そしてフィールドも広そうです
Youtubeの公式チャンネルにコメント殺到
6月13日の時点でベセスダの公式チャンネルにはコメントが殺到し、2万3千を超えています
動画見た人のコメントの中からいくつかピックアップしてみましょう
こりゃハプニングだ!
やった!!
待てねぇ
なんてことだ!泣いてるぜ
このゲームがリリースされた日は、私が仕事を辞めた日だ
スカイリムでのサイドクエストバグが発生するような事はしないでくれ
ハイロッ…
View On WordPress
0 notes
Text
【速報】スマホで遊べる『エルダースクロールズ ブレイズ』が発表!!クオリティすげえええええ!
続きを読む
Source: オレ的ゲーム速報
View On WordPress
0 notes
Text
エドワード王 八巻
昔日の王の一代記、八巻
ワイルダーランド
ヴァレンウッドの旅は楽しいものでした。ほとんどの場所で昼間は晴れて、夜間は涼しい気持ちの良い天候が続きました。彼らの馬の足元に、舞い落ちる朱色や茜色、金色や緑の明るい色の葉っぱが降り積もってカーペットを作っていました。ヴァレンウッドは、曇りがちで急峻な森林の多いハイロックとはとても違っていました。北の国境に着いた時、振り返ったエドワードの目には、ほとんど丸裸で、栄光を失ってしまったような木々が見えました。彼らの前には、数えるほどしか木が生えて���ない、丘がうねる広大な緑の土地が広がっていました。それは永遠に続いているように思えました。
「エドワード、これがワイルダーランドだ」モラーリンが言いました。「気をつけるんだぞ。気持ちのいい土地に見えるが、この辺りを治める方法を知る王はいない。皆互いのやり方を否定している――人間より悪いものもいる。ここではタムリエルのすべての種族がいて、衝突している。身を守るんだ、ことによればな」
彼らの旅は、ちょっとした事件とともに、それから数日続きました。カジートの盗賊団が夜に彼らのキャンプに這い寄ったこと以外は。彼らはたやすく撃退されました。シルクが一人を倒すと、残りは叫びながら逃げて行きました。大人しいウッドエルフの少女、ウィローは彼らの後ろに向かって弧を描くように火の玉を投げました。街道はありませんでした。互いに交差し、どこにも続いていないように見える小路ばかりでした。
力強く馬を飛ばして二週間ののち、彼らは土地が途切れるボウルのような形の丘に着きました。収穫物が積まれた畑は整っているようでしたが、そこにいた人々は覇気がなく、ぼろをまとっていて、友好的ではありませんでした。宿についての質問も、ただ肩をすくめて困ったような顔をされただけでした。その時、武装した一団が現れて、用件を言えと要求しました。モラーリンがモロウィンドに向かっていると答えると、何も盗まずに早く行ってしまえと言われました。
「通過できただけで充分だ」モラーリンが静かに言いました。
「あの田舎者たちに誰か礼儀作法を教えるべきだ」普段は穏やかなマッツが唸りました。
「それなら、留まってエチケットの学校でも開いてみるか」モラーリンが言いました。「ああいう悪党のために講義をしてやるには、私の人生は短すぎると思うがね。空の具合が気に入らないな、あれはあの村人よりも邪悪に見える。町で運試しをしてみようか」
町は木の柵で囲まれ、丈夫な門がありました。彼らを見渡すと、衛兵が入場を拒絶しました。「人間だけだ、エルフ。下等な仲間を連れて去れ」
「わかった。アリ、マッツ、エドワード、お前たちがここで暖かく迎えられることを保証しているようだ。我々はどこか雨宿りできる場所を探すよ」
アリエラは、この門に足を踏み入れた途端、嵐が来る前にみんなファーストホールドに吹き飛ばされるのが目に見えるようだと皆に言いました。そこで彼らは町を迂回し、砦らしきものの中にある岩壁を備えた堀を渡りました。北に延びている 近くの道の脇に、大きな納屋がある小さい家があります。どちらも粗末な修繕しかしていないように見えましたが、モラーリンはドアをノックして納屋で眠らせてもらえるかを尋ねるのに、アリエラとエドワードを行かせました。あとの者たちは道で待っていました。
年かさの女性がノックに応えて出てきました。彼らに会って喜んでいるようでした。「泊まりたいんですって?話し相手ができてうれしいですよ。納屋で寝なくたってかまやしませんよ、奥様。空いている部屋がありますからね。私はオラ・エンゲルスドッターと言います」アリエラは待っている仲間たちに合図をしました。女性は眼をすがめて彼らの方を見ました。「ご主人とお友達がいなさるの?ええ、それじゃみんな寄り集まっていましょう。その方が暖かいでしょうからね。火にスープの鍋が掛けてあるんですよ。一週間分の食事ですけど、どうかお気になさらず。まだ作れますよ」
「夫はエルフですの」
「そうなんですか?あの方はあなたと息子さんの面倒をよく見なさっているように見えますね。豚みたいによく太って。あの人たちを連れておいでなさい。私の孫娘にも、こんな風に気にかけてくれる方がいるといいのにねえ」
客人のもてなしに金を払わせなければならないほど困窮していないと言って、オラは支払いを拒否しました。その夜の物語と歌の楽しさで充分だと言いました。雨漏りの最悪の事態を避けるために、鍋と皿が置かれていました。彼女はその位置を熟知していました。雨戸と扉をしっかりと閉め、屋根が全部飛んでいかないかと怯えるような嵐が荒れ狂う中、彼らは暖炉の周りに集まって、とても楽しく過ごしました。
「奥様、教えてくださいな」オラがアリエラだけに囁きました。「あの方は本当にあなたに良くしておられる?あの方はとても大きくて、とても黒いのね」
「本当に良くしてくれますのよ」口は真面目そうな形を保っていましたが、アリエラの目は笑っていました。
「ああ、それはいいことですよ。あの方が大きくて黒いものだから、ちょっと男爵を思い出してしまって。あの人は孫娘のキャロンをさらって行ったんです――それに、あの子を手厚く扱ってくれやしません。あの人は――あの人はあの子を傷つけるんです、奥様。そして、あの子は逃げ出すこともできやしないんです。どこに行けるって言うんです?」オラの目に涙が浮かんで、使い古されて親しみのあるしわに沿って頬を流れ落ちて行きました。
女主人が就寝のために部屋に引き取ったあと、アリエラは彼女が話したことを皆に繰り返して聞かせました。
「その子を助け出そう」ビーチが言った。「怠惰な生活で腐っちまう」
「賛成!」シルクとウイローが即座に言いました。
マッツが同意を示して唸りました。ミスとスサースは興味があるように見えました。
モラーリンは疑わしげ��した。「我々はタムリエルのすべての間違いを正すことはできないよ。この男爵は村人に避難所のようなものを提供しているのだし。よそがいいと思えば、彼らは出ていくだろう」
「賛成」ミスが言いました。「盗賊を遠ざけてるから、そいつは楽しみのために村人から盗むのかもな」
「それで、彼を引きずり降ろすのかね?代わりになる誰かがいるだろう。あるいは、よそ者がやって来て、根こそぎ持って行かれるさ」
「この不潔な何かに勝るものはない」マッツが言いました。
「そういうことね」嵐は過ぎ去ったようでした。アリエラは戸口に行って、雲が素早く行きすぎる東の月を見上げました。一つの大きな輝く青い星が、月の近くに浮かんでいました。「ゼニタールがタムリエルの近くにいるわ。モラーリン?」
「明日ここの屋根を修繕しようと思っていた、それが公正ならね」彼女が炎のそばに戻ってくると彼は言いました。「少なくとも、大仕事だよ。一夜の宿にしてはね――違うか?」
「彼女なりに……私に助けを求めたのよ……そして私――風の中にゼニタールの声を聞き、今夜の雨の中に彼の手を感じたの」
「君の試練、というわけだね、奥さん」
アリエラは頷きました。笑ってはいませんでした。彼女は煙突がある隅でモラーリンと一緒に身体を丸め、少しの間囁き合って笑いました。エドワードは眠っていました。朝になると、彼はビーチとウィローが新しいこけら板を置くのを手伝いに屋根の上にやられました。モラーリンは手紙を書いて、夕食の時間に間に合うように、徒歩で男爵に持っていくようにと、マッツに言い付けました。
「女の子のために彼に挑戦するつもりなんだね!」エドワードがにやりと笑いました。「でも彼は戦うかな?それに、僕たちがいなくなったら、またその子を取り返すんじゃない?」
「いや、彼は私を町に入れなかったから、代わりにお前の母上は彼を我々の家に招くことを考えたんだ」モラーリンはシグネットリングで手紙に封をしてマッツに渡しました。
「わあ。でも、おうちまでは遠いんじゃない?」エドワードはこの救出劇が差し迫ったものでないことに、少しがっかりしました。でも、彼には8人の人間だけで砦を奪おうなんて、とても筋の通ったこととは思えませんでした。たとえそれがモラーリンの仲間たちであってもです。多分、あの歌は彼らの行いを大げさに言っているのでしょう。
モラーリンはにやりと笑ってエドワードの髪をくしゃくしゃと撫で、質問をやめて屋根に行き、母上の心配をしなさいと言いました。モラーリンとミスは一緒に歩いて出発しました。アリエラは狩りに行ったのだと言いました。夕飯時になっても、彼らは戻ってきませんでした。アリエラはエドワードに心配はいらない、あとで会えるから、と言いました。
女主人にお別れを告げたのは、日が沈んでからかなり時間が経ったときでした。彼らは馬を全部連れて行き、砦の北側の壁の近くの木立に置いていきました。アリエラはエドワードに馬と一緒に待っていたいかと尋ねました。エドワードがどこに行くのかと訊きた。
「私たちは砦に入ってオラのお孫さんを取り戻すのよ。質問は駄目です、エドワード。あなたが来るなら、私と一緒にいて、言われた通りのことをなさい。堀はレビテトで渡るの。私は泳がなきゃだめね。渡り終えたら塀をよじ登るのよ。中に入ったら、私についてきて、できるだけ音をたてないようにして」
エドワードはぽかんと口を開けて、母と他の仲間たちを見ました。彼ら6人でどうやって砦を襲うというのでしょう?3人の女性と、2人の男性と、男の子が1人で?壁の上には衛兵がいるでしょうし、中にはもっといるでしょう。マッツも一緒に中に入るだろうけど、と彼は考えました。でも、モラーリンとミスはどこに?
堀では恐ろしいことがありました。エドワードは抗議しかけましたが、それからその方がいいと考え直しました。スサースが最初に堀に滑り込みました。小さな水音とシューッという声がして、水面が静まりました。アリエラが水の中に入りました。他の者たちは宙を浮いて渡りました。
「ロープがある」ビーチが壁を探りながら言いました。3本のロープがありました。エドワードとビーチとスサースが最初に上に上がりました。アリエラ、ウィロー、シルクがそのあとに続きました。モラーリンとミスが上で待っていました。二人の衛兵は荒れ果てた建物の上で穏やかにいびきをかいていました。
「どう―」エドワードが言い始めると、母が片手で彼の口をぴしゃりと叩いたのがわかりました。他の場所の壁の上にいる衛兵が大きな声で呼びかけ、エドワードは心臓が止まりそうになりました。ミスが何かを叫び返すと、どしどしという足音が遠ざかって行きました。
仲間たちは静かに階段を下りて、影のように中庭を横切りました。砦の中に入る扉には、衛兵が一人もいませんでした。通路の中は不気味なほど静かでした。彼らは堂々とした扉のところで身を屈め、壁にぴったりと身体をつけました。中の声が聞こえます。か細い、ゾッとするような泣き声がして、静かになりました。モラーリンがそのあとに続いた静寂に向かって口笛で短い曲を吹きました。ドアが大きく開き、彼らは中に駆け込んで、猛烈な勢いで驚いていた衛兵の上に身体を投げ出しました。
エドワードがトゥースを手に最後に中に入りました。彼は一番近くにいた衛兵の脇腹に突き刺して、ビーチが頭への一撃でとどめを刺しました。マッツはずっと中にいました。扉を開けたのはマッツだったのです。彼の斧が一人の衛兵の頭を割り、それから内側のドアに向かって振り抜きました。アリエラとウィローが外側のドアに素早くかんぬきを掛けました。モラーリンの敵はとても若い男でした。彼は大きなダークエルフを一目見ると、彼の剣を床に捨てて跪き、慈悲を請いました。
モラーリンは汚らわしいものを見るような目で彼を見て言いました。「ゼニタールによろしく言ってくれ。エボンハートのモラーリンが慈悲を推奨していたとな。お前のような者に対しては、私には持ち合わせがない」彼は若い衛兵の喉を切りました。モラーリンの革鎧に血が吹きかかりました。彼の犠牲者は床に倒れ、ゴボゴボと恐ろしい音をたてています。燃えるような酸味がエドワードの喉にせり上がってきましたが、彼は固唾を呑んで目をそらしました。
控えの間の中にいた衛兵たちは処刑されましたが、ドアの外では怒号と足音が轟いて、ドアに体当たりする音が聞こえました。エドワードは母のあとについて、巨大なベッドに鷹が羽を広げるような形で縛り付けられた裸の少女を除いては誰もいない、奥の部屋に行きました。彼女の眼が彼らを見つめていました。
アリエラが彼女の肩を押さえている間に、仲間たちが彼女の縄を切って自由にしてやりました。「おばあさまが私たちをよこしなさったの。男爵はどこ?」
少女は本棚を指さして、アリエラにしがみつきました。彼女はエドワードより大きくもなく、年もそう変わらないように見えました。彼女の胸は膨らみ始めたばかりです。彼女の体はみみずばれと血と紫色と黄色の打撲で覆われていました。アリエラは自分のマントで彼女を包みました。ビーチが彼女を抱き上げました。ミスの指先が本棚を探っています。カチリという音がして、横に滑りました。彼は慎重に中に入りました。他の者たちがあとに続くと、秘密の扉が彼らの後ろで閉じました。
「それはただのねじ穴だと思う」ミスが言いました。「だけど、罠を仕掛けてあるだろう。間違いない」
「じゃあ、気をつけて」アリエラが言いました。「急ぐことはないわ。男爵は戸口で客の見送りをする準備をしてるでしょう、いい主人の常識みたいにね」
細い通路が左側に開けました。ミスは雷の矢を打ち込みました。床は骨でいっぱいです。人間の骨です。小さな頭蓋骨が空っぽの目で見つめていました。「彼を殺すことを楽しむことにするよ」モラーリンが言いました。
「駄目よ!」アリエラが抗議しました。「私の試練です、私が殺すの!」
モラーリンが彼女の方を振り向きました。「アリエラ――」
「私はアリエラの手によって死んだと歌われたいの!彼と対決する権利を主張しますわ、我が王よ」
「私に任せるんだ、歌は君の言った通り歌うから!彼は君の二倍はあるんだぞ。権利のために私と戦いたいのかね?」エルフは彼女に向って身を屈めました。彼は彼女の頭一つ分余計に身長がありました。
「必要ならね」アリエラは彼を撫でて通り過ぎ、腕につけた盾を鳴らしました。そして走り出すと、彼女のショートソードを抜きました。
モラーリンは彼女を掴みましたが、掴み損ねて彼女のあとを走って追いかけました」彼の大きな体は低くて狭い通路で引っかかりました。不用意に壁にぶつかると、彼の魔法のシールドから火花が飛びました。
「二人とも、早く」ミスが前方で叫びました。「お前らのためにやつを取っておくとは約束してないぞ」
「モラーリン」エドワードが彼の後ろを走りながら喘ぐように言いました。「母さまにやらせないつもりなの!」
「させるさ!どうやって止められるか教えてくれるのか?私は提案を受け付けるぞ。実際に彼女と戦うには知識が不足している」彼は半分怒っていて、半分は面白がっているように見えました。
「た、多分あいつはもう逃げちゃってるよ」
「ないな。彼は我々と一緒にここに閉じ込められたんだ。さっき反対側から出口を見つけてミスが男爵には開けられない鍵をかけた」
「じゃあ、麻痺させよう。父さまは運べる」
「彼女は盾を使ってる。他にも効果はあるが、あれは呪文を跳ね返すんだ。私はただ自分を麻痺させるだけだし、私は運ぶには不便だ。彼女は大丈夫さ。あれはすばらしい盾だ。とても強い魔法を使える。アイリック本人が細工をしたんだよ」
「今晩、鍵にちょっとした問題がおありかな、男爵?」前方からミスの声が聞こえました。彼らは広い部屋に出てきました。そこでは、男爵が巨大なドアの隣のスイッチを虚しく引っかいていました。
「彼には必要ないでしょう」アリエラが鼻で笑いました。仲間たちは彼女の周りに半円状に広がりました。男爵は背中を扉につけて戦う間合いを取りました。彼は大男で、マッツほどの大きさがありました。そして、彼はマッツが持っているのと同じくらい大きな斧を抱え、ブレストプレートと兜を身に着けていました。彼はモラーリンを指さしました。
「9対1だ。お前のような黒い悪魔たちからのオッズを期待しているぞ」モラーリンはグループの後ろにいましたが、男爵は彼をリーダーに選び出しました。なぜかみんなそうするのです。
「ウェイトでアドバンテージを取るのがお好みなのだろう?だが、妻が戦いたいそうでね。お前の魅力に抗えないと見える。私もだ。招待への返事を待ち切れなくてね。だから代わりに来てやったぞ」
「俺があの女を負かしたら、残りのお前らが俺を殺すのか?はっ!その値打ちはあるかもな」彼はアリエラを冷酷な黒い瞳で見つめながら付け加えました。
アリエラは恐ろしい微笑みを見せました。彼女の黒い髪は肩の辺りで奔放に揺れ、彼女は輝いているようです。「男爵、お前はこの女を打ち負かすことはできないでしょう。ですが、もしできるなら、どこにでもお行きなさい。今夜、お前は私だけのものです。皆に誓います、ゼニタールに懸けて!もしまかり間違って彼が私を殺したら、私の幽霊が墓まで、その先も彼を追い立てるわ」彼女の声は予想よりも楽しそうでした。エドワードは震え始めました。
「ゼニタールに懸けて!」
男爵は笑いました。「信じられんな。だが俺のコレクションにまた女が加わるわけだ。その女にそんなに飽きてるのか、エルフ?」
「そんなに彼女を恐れているなら、代わりに私とやる方がいいか?」エドワードの心が、どこか深いところでかのエルフが正しいことを理解しました。男爵の虚勢にもかかわらず、彼はアリエラを恐れていました。エドワードは彼らとともには誓いませんでした。彼はしっかりと杖を握り締めていましたが、足は床に根を張っているようでした。
男爵は再び笑って、答え代わりにアリエラに強力な一撃を繰り出しました。でも、それは彼女の盾に傷もつけずに跳ね返されました。彼女が魔法でシールドを張っていることがわかると、彼の目が見開かれました。アリエラは踊るように脇に避け、彼の腕を切りました。彼女は敏捷でしたが、彼はどうにか多くの攻撃を当てることに成功しました。もし彼女のシールドが切れ…エドワードには最後まで考えませんでした。
彼女の盾の効果を消すことばかり考えて、彼が体を開いていたため、彼女は彼の足に何度も攻撃を加えました。彼女は打撃を低く保って、足を鈍らせ、血を流させようとしていました。その間中、彼が死んだら玉を抜いてやると言いながら、彼女は彼の男らしさをあざ笑って挑発していました。猛烈な一撃が彼女を後ろに下がらせました。彼女の盾が光ると、消えてしまったのです。
男爵は彼女の頭を一撃で割ろうとして斧を高く構えました。彼女は腕を後ろに引き、細身のショートソードを敵の目のにまっすぐ投げ込みました。彼は斧を取り落として叫びながら膝をつき、両手を顔に這わせました。アリエラは前に進み出て、彼の脳に深く貫通するほど、痛烈に剣を突き刺しました。身をよじり、痙攣させながら、彼は倒れました。
「よくやった、奥さん!」
「私にはすばらしいトレーナーと、いい甲冑師がいますもの!」アリエラは笑って、やがて頭を戻し、こぶしを握り締め、両手を挙げて言葉ではない勝利の叫びを上げました。
「お前のおかげだ!」モラーリンはシルクを掴むと荒々しく抱きしめて大きな音をたててキスしました。「お前が彼女に教えてくれた、いかしたトリックのおかげだよ、シルク」
「私のトレーナーさんを口説くのをやめて下さったらありがたいんですけど、旦那様!」細身のアダマンティウムの剣を慎重に拭いながらアリエラが言いました。
「私が?口説くって?怒っていないだろうね……それに、君の盾はまだ魔力がある。私はただ感謝しただけだよ。次に会った時はアイリックにキスしよう」
「本当に死んだの?」戦闘の間中、キャロンは目をつぶってビーチにしがみついていました。今の彼女はアリエラを――畏敬のまなざしで見つめていました。エドワードは適切な言葉だと考えました。エドワードも何か同じことを感じていたのです。恐怖に近いものでしたけれど。
「充分死んでいるわ」アリエラは、まだかすかにぴくぴくと動く身体を満足気に見つめながら言いました。少女は近寄り、彼の隣に膝をつきました。彼女は石を持ち上げると、泣きながら、何度も何度も彼の顔にぶつけました。彼女がそれを終えると、スサースが彼女に治癒の呪文をかけました。ミスが鍵を開けて外に出ると、馬を置いて行った場所のすぐ近くでした。
彼らは少女を母親の家に送り届け、彼女を冒涜しようとする人間には誰にでも、もし彼女が傷つけられたら、ゼニタールの番人たちが戻って来ると言うように、と教えて立ち去りました。まごついた老女は孫娘を抱きしめました。彼女が別れの挨拶をすると、夫の面倒を見るようにとアリエラに耳打ちしました。
「あら、そうしますわ」アリエラは言いました。「そうしますとも」
*******
彼らが休憩のために足を止め、アリエラが話をしようとエドワードの方に行きましたが、彼はとても疲れていて、ただただ眠りたいと抗議しました。息子に必要とされていない時は、君を必要としている夫に会えるだろうと言いながら、モラーリンが彼女を引き離しました。二人は火を囲む輪の外に出て行きました。エドワードは目を覚ましたまま起きていて、二人の小さな、鼻を鳴らすような音を聞いていました。それは、珍しいことではありませんでした。最初は気になりました。「眠れないよ、二人ともうるさいんだもん」ある夜、彼は抗議しました。「ねえ、何してるの?」その言葉は仲間たちから忍び笑いを引き出しました。「少なくとも、眠る振りぐらいできないのか?」モラーリンが平静を装って尋ねました。「僕は今、どうしてダークエルフがよく一人以上子供がいるのかわかったよ。僕がわからないのは、どうやって人間がこんなにいっぱい増えたかってことだ」モラーリンとアリエラは、その夜彼に嘘をつくために戻ってこなければなりませんでしたが、彼が眠ったふりをしたあとは、他の夜と同じようにしていました。
その騒音はあまりにも身近なものだったので、その夜の冒険の映像が彼の心の中で明滅するのを防ぐことができず、まるでそれらが再び本当に起こっているように、生き生きとしていました。彼は自分のデイドラが餌を食べ、それを止められないのを感じていました。不公平だ、と彼は考えましたが、自分のデイドラに餌をやり、それでも神々とともに歩むというモラーリンの言葉の意味を理解し始めていました。ゼニタールとともに。
モラーリンがアリエラを抱えて戻ってきました。彼は彼女を優しく下ろしてから、エドワードと彼女の間に横になりました。
「女でいるということは困難に違いないね」彼は優しく言いました。「彼女を見ていると大変だ。ただ見ているだけでね」
エドワードは頷きました。
「私はそれについてよく尋ねたものだ、彼女に」モラーリンは続けました。「彼女はそれがどんなに大変か教えてくれたが、今晩まで知らなかった。彼女が勝つことは知っていた。ゼニタールが彼女とともにあって、男爵にはデイドラしかいなかったからな。それでも、見ているのはとても辛かった。彼女は10回のうちの9回を使った。そして、もし失敗すればあの盾にはさらに使い道がある……彼が疲れ切ってしまう前に、消耗を回復したかもしれん」
「僕もそのことを考えていたの……そしてあの衛兵…彼は命乞いをした?」
「わかっているよ。だが、彼は同じ言葉を聞いていた……毎晩毎晩な。それでも彼は男爵の手下であり続けた」
「大抵の男は父さまみたいに強くないんだよ。自分でもどうしようもなかったんじゃない?」なぜ彼は、もう死んでしまった男の弁護をしているのでしょう?彼の心はその夜の出来事を、良くも悪くも違う結果になったかもしれないと何度も繰り返し考えていたのです。
「あのように腐った魂のような邪悪を目にしたのに、ただ見ているだけで何もしないなどとは……マッツは持っている値打ちなどない私の片手を持ったままだったかもしれないな。それに、若者にとってはさらに悪い。今夜のようなことを経験させて済まなかった」
「僕の魂は腐っちゃった?」
「苦虫を噛み潰したような気持ちだろう、みんなそうだ。だが、治るよ」
「今治せる?」
「もちろんだとも」モラーリンは彼を腕の中に引き寄せて寝返りを打ち、エドワードが両親の間で横になれるようにしました。アリエラは眠ったまま彼女の両腕を彼に回しました。エドワードの鼻で、彼女の強い女性の香りと、モラーリンの麝香の暗い���パイスの香りが混じりました。
「母さま、とても怒ってた」エドワードは囁きました。彼はまた同じような気持ちで母を見られるようになるかしら、と考えました。きっと、モラーリンもその安心感を求めていて、それを求めるには充分賢明だったのでしょう。
「彼女は女だ。他者に対するああいう類の傷は、彼女の心の琴線に触れる」彼は言いました。
どのぐらい?少年はその質問を口に出せるわけがないことを察しました。
「お前の父上は怪物ではない。だが、彼女は自分のことを気にもかけない男に嫁いだ。そして、彼の下から去ることができなかった。お前の種族にはよくあることだが、だからと言ってそれが耐えることをたやすくはしないと私は思うよ」
「じゃあ、母さまにもデイドラがいるの?」エドワードは悲しげに尋ねました。
「それについては本人と話さなければいけない」
「今日のはほんとには公正な戦いじゃなかった。母さまはシールドがあったし、彼にはなかったもの」
「公正な戦いは闘技場のためのものさ、坊や。お前は狼やヘルハウンドが何も持っていないからって、武器も呪文も鎧もなしに戦うのかい?私は使うだろうな」
「男爵が死んじゃって、キャロンとオラはどうなるの?それに他の村の人たちも。」
「私が予言者マルクに見えるかね?わかるわけがない。春までここにいて、今夜我々が焼いた畑に何が育つかを見ることはできる。私は留まる気も、耕す気もないがね。私には私の、手入れすべき畑がある――聞いたかい、ノルドの農夫みたいじゃないか。鉱山の方がもっと私らしいな」彼はあくびをしました。
「他のみんなはあとのことは考えてなかった。父さまは考えてた」
「私は王だよ。それが仕事さ」
2 notes
·
View notes
Text
【速報】TES世界のカードゲーム『エルダースクロールズ レジェンズ』、 PS4、Xbox One、ニンテンドースイッチでリリース決定!!
Source: ナゲット
View On WordPress
0 notes
Text
#9【糞ゲーもぐもぐ】格闘ゲームはいかが?ベテランコンバット!
【ちゃんねる登録⇒http://urx3.nu/As9p】
次:https://youtu.be/cK7hltQZank
前:https://youtu.be/9dSsEVQm7dI
クソゲキラーまーやの小姑(の様にブツブツ文句言いながら)実況です。愛すべき糞ゲーを毎週実況プレイします。
今週のゲーム:VETERAN COMBAT
http://store.steampowered.com/app/351420/
まーやツイッター
https://twitter.com/MayaPcgamer
◇再生リスト◇
【MOD】まーやのエルダースクロールズ【スカイリム】
[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=videoser…
View On WordPress
0 notes
Text
スカイリムSwitch版の最新情報まとめ!ジョイコンやamiiboにも対応!
スカイリムSwitch版の最新情報まとめ!ジョイコンやamiiboにも対応! | 攻略大百科
現在開催されているゲームの一大イベント「E3」において、Switchの新作ゲームに関する情報が公開されました。 タイトルは「ザ エルダースクロールズ V: スカイリム」。Switchの発表当初から話題を集めてきたタイトルですが、ようやく具体的な情報が出てきましたね。 Switch版「ザ エルダースクロールズ V: スカイリム」の概要 世界的ヒット作 「ザ エルダースクロールズ V: スカイリム」は、2011年に通常版が、2016年にスペシャル版が発売された作品です。通常版の売上が3ヶ月ほどで1000万本に達し、世界的な大ヒットを記録した超大作です。 オープンワールドタイプのアクションアドベンチャーゲームであり、自由度の高い冒険が最大の魅力です。美しいビジュアルも評価が高い部分のひとつです。 [citation…
View On WordPress
0 notes
Text
エドワード王 九巻
昔日の王の一代記、九巻
幸運
エドワードはモラーリンの背後に膝をついて、エルフの手の中のカードが見えるように前かがみになりました。彼は炎から離れて座っていたので、人間の目には暗かったのです。でも、モラーリンはエドワードに手の内を見ることを許してくれる唯一の仲間でした。他の参加者はビーチ、ミスとマッツで、エドワードは彼らに不運をもたらしました。モラーリンは本当には運の問題ではないと言いましたが、そう思う人たちの目には、エドワードの表情が手札を反映しているように見えるのです。今はビーチとマッツにとってはエドワードを見るには暗すぎましたし、モラーリンがミスの視界から彼を遮っていました。それでも、モラーリンのコインの山はエドワードが後ろに陣取ってから小さくなっていました。でも今回、彼はいい手を引きました。エドワードにはそれが見えました。マッツの番です。彼は考え込んでいました。
「震えているじゃないか」モラーリンが言いました。「暖かい服は持っていないのかい?何か見繕ってやらなければね。さ、それじゃこっちに来て私のマントに入りなさい。持ちたければカードを持っても構わないよ」風は凍り付くようで、激しさを増していました。彼らは北の方にいて、新年が近づいていましたから��エドワードはモラーリンの腕と毛皮のマントの中の避難所の提案を受け入れ、彼のそばに座りました。
「手持ちのカードだけでやろうと思う」マッツがようやくそう言って、コインの山を賭け場に押し出しました。そして突然決意を固め、もう少し加えました。「よし」
「手を下げるんだ、エドワード���見えているよ」
「僕たちよりいい手なんかないよ!」エドワードが抵抗しました。
「エドワード!」モラーリンが唸りました。
「さて、俺がどうやってわかったと思う?」彼の賭け金に見合うコインを出さない限り、マッツはカードを見せる必要はありませんでした。
「見てたんだ。静かに。ああ、いいぞ。父親ってものがこんなに甘くなるなどと誰も教えてくれなかった」彼はマッツの賭け金に見合うほとんど全部のコインを賭け場に押し出して、エドワードが手札を見せました。
「おや」マッツが言いました。「友よ、そんなことしなくてもよかったんだぞ。坊主にタダで見せてやったのに」
「この汚らわしいノルドめ」モラーリンが憎々しげに言いました。「カードを出して私の金を持って行け、この手に勝てたらな。私がこのゲームの指南を受けなきゃいけないかどうか、見てみようじゃないか」
「残念だな」マッツがニヤッと笑いました。「俺を馬鹿にせずに寛大な申し出を受け入れていればねえ」マッツは『淑女たち』と呼ばれる完璧な手を披露しました。
「挑発は侮辱とよく似ている。マッツ、その手は王子が見る価値があると言えなくもないね。5人の美しい淑女たち!互いにあまり好意を持っていない彼女らをまとめて見かけることはそうないからな」
「どうしてわかったの?」エドワードが詰問しました。
「ああ、そのうちわかるだろう」モラーリンが歯を剥き出して笑いました。「いくつかは自分自身のために学ぶことになるだろうね。それもゲームの一部だよ。だが覚えておきなさい、誰かがそれ以上の手を持っていれば、いい上がり手に価値はない」
「ごめんなさい」エドワードは悲しそうにほとんど残っていないコインを見ました。
「いいんだよ。幸運の神が彼の肩に乗っているこんな夜にマッツと遊ぶのはばかげているし、私についていた神はもうベッドにいるはずのブレトンの王子のせいで逃げてしまったからね。最後には、彼が私を身ぐるみ剥いだというわけさ。もう寝なさいってことだよ」
「興覚めだな」マッツが不平を言いました。「サイが訪ねてくるのは毎晩のことじゃないし、俺は彼が来てくれて楽しんでたんだぜ」
「来た時と同じようにさっさと帰って行くさ。サイはお前の好みじゃないよ、マッツ」
「俺がいちばんよく知ってるんだぜ?いや、謝ることはない。心配してくれて嬉しいよ。完全に不当ってわけでもないが、誘惑には十分気をつけてる。サイのお恵みがどれだけ頼りにならないかも、どれだけ気まぐれかもな。俺は信頼を置いている友達としかやらないんだ」
「それじゃ、おやすみ」モラーリンとミスは、マッツとビーチとエドワードを火のそばに残して、もう眠っている者の仲間に加わりに行きました。ダークエルフの生来の睡眠習慣は、日中5、6時間眠って、真夜中に2、3時間昼寝をするというものです。今、彼らは旅行中ですから、夜にだけ眠ります。これはミスとモラーリンにとっては困難な調整で、それに合わせるには魔法を使わなければなりませんでした。エドワードは夜営のために足を止めてすぐ、みんなが夕食の用意をしている間に少し眠っていました。結果として、今は目が冴えているのです。ビーチはあくびをしていました。マッツは他の人より寝る必要がないようでした。
「サイのことを教えて、マッツ。僕、初めて聞いたんだ。幸運の神がいるなんて知らなかった。幸運は、ただ起きるものだって思ってたの」
「お前はブレトンだからな、わかるよ。ブレトンは説明のつく、はっきりして筋が通ってて、順序立ってることが好きだ。だから、他も同じさ。お前もわかってるだろう。大抵の神々はそんな感じなんだ。神が決まりを作って、人はそれに従って神に敬意を払う、そしたら彼だか彼女だかがお恵みを与えてくれる。そして、もっと決まりをよく守って、もっと神を敬ったら、もっといいお恵みがある。こういう決まりごとを常に守るのは簡単なことじゃない。それに、ある神の決まりを守ろうと思ったら、他の神の決まりを破らなきゃいけないかもしれないけど、それは自分次第だ。でな、サイはそんなんじゃないんだ。彼はデイドラじゃないが、確かにデイドラみたいな側面がある。例えば、彼を崇めすぎると、彼は完全にそいつを見放す。『サイの副作用』って呼ばれてるよ。神の存在を求める圧倒的な欲望だ。俺の親父はそれで苦しんでた。哀れな男さ。その病気は、ただの神への存在の欲望以上のもんだったよ。それに苦しむやつらは神のお恵みの継続的な証拠を求めるんだ。だから、やつらは際限なく博打を打つ。勝つためじゃない。あいつらは勝つことで、負けるまで博打を打ち続けるんだ。それで、やつらはまた博打ができるようになるために、賭け金を吊り上げるのにやらなきゃいけないことをやるのさ。
「ああ、恐ろしいもんだよ。おっかないよ。俺の親父はそのせいで俺を奴隷として売った。あとになって、一番上の姉ちゃんも売った。それで、また借金ができた時、珍しく正気になった瞬間に自分に何が起きたかを知って、自殺したんだ。家族に、自分自身に何てことをしたのかってな。もちろん、売られた時の俺はちびっ子だった。わからなかったよ。怠け者か馬鹿か言うことを聞かないからか、自分が何かしくじったせいで遠いところにやられたんだ、もし自分がもっといい子なら、こんなことにはならなかったって考えた。それはオーリエルのやり方だ。子供たちに両親を尊敬して、そこから学ばせるためだ。だけど、尊敬に値しない両親ってのがたまにいる。まあ、あれは病気のせいだっておふくろは言ってたけどな。赤痢や癩病にかかったのと同じように、彼のせいだとは思ってない。俺はおふくろの言い分を信じるけど、時々、まだ俺のせいだったって気がするんだ。まあ、お前は運が悪いって言うかもな。だけど、サイは俺にモラーリンを授けてくれたし、あれは本当に幸運な日だった
「ぶん殴ってるやつにぶん殴るのをやめさせるように頭の中に命令を出してくれる神なんかいるか?タムリエル中の他のエルフは、胸糞が悪くて顔をそむけるか、馬鹿な人間を笑って見物するのに立ち止まるかだ。2人のダークエルフのガキに4人のノルドだ。しかも、俺が受けてる仕打ちが当然だって全員知ってる。俺は泥棒か人殺しだったかもしれないんだぜ。俺は泥棒だったんだろうなって思う。自分を盗んだんだ、言ってみればな。
「モラーリンは、なんであんなことをしたのか説明できないって言ってた。その日はケンカしたくて仕方なかったし、モロウィンドの奴隷捕獲人を見ても癇癪を押さえるのに何の役にも立たなかったって。だから言うんだ、サイのおかげだって。だけど、神の声に耳を傾けたのはモラーリンだ。
「サイの手を自分の肩の上に感じるのがすげえことなのは間違いない。最高の馬に乗るとか、愛そのものみたいなことだ。いつもの苦痛に満ちた生活じゃなくて、自分が世界と一つになって、なんでも思い通りになって、すべてが自分の味方なんだ。頭がよくなくても、男前じゃなくても、親切じゃなくても、頓智が利かなくてもいい、ものごとが全部自分の思った通りになる。なんか間抜けなことをしても関係ない。それは行われるべきだった適切なことに変わっちまう。それが幸運だ。幸運に生まれ付いたやつがいて、そうじゃないやつがいる。なんでかはわからない。大抵みんな、時にサイの存在を感じるんだろうな。お前はどうだい?」
エドワードはかぶりを振りました。彼はマッツが何を言っているのかわかりませんでした。
「まあ、強欲みたいなことだと思うよ、この、サイの副作用ってやつはさ。なあ、ただ辺りに撒き散らすたくさんの幸運があって、何人かが全部それを持って行ったら、残りのやつらには何も残らない。今夜みたいに、俺が最後に勝ったけど、他のやつらは負けなきゃいけなかった。みんながサイと一緒に勝てるわけじゃない。他の神々はそうじゃないし、そうである必要もない。まだわかんないだろうな。サイの話を聞きたいか?」
エドワードは頷きました。マッツは心根のいい男ですが、普段はとても口数が少ないのです。エドワードは、どちらかというと彼が愚かなせいだと思っていました。カードゲームのマッツの幸運は、彼の口を軽くしたようでした。そして今になって、彼が口に出す以上にいろいろなことをたくさん考えているのを、エドワードは理解しました。
*******
昔々、人々が今より少なくて、狼がずっと多かった頃、今のスカイリム地方の中央にある沼地に、ジョセアという名の若い未亡人が住んでいた。彼女はごく普通の女で、賢くもなければ見目好くもなかった。彼女は滑らかな茶色の髪と温かい茶色の瞳で、鼻が低く、身体と同じ丸い顔をしていた。彼女は田舎の農夫の一人娘として生まれた。両親は彼女が17歳の時に腸チフスで世を去った。その後まもなく彼女はトムと結婚した。陽気な性質で、浮気がちな屈強な若い木こりだった。彼女がすぐに身ごもると、彼の注意は他に移った。赤ん坊が生まれる少し前、彼は殺された。地元の金細工師が家に帰ると、ハンサムな木こりが妻とベッドの上にいるのを見つけ、彼の背中にナイフを突き立てたのだった。
トムの死は、ハートの日に起きた。赤ん坊は男の子で、その4か月後の年央の月の間に生まれた。近所の女性2人がお産を手伝い、一人は数日彼女の家に留まった。その後、彼女は1人でできる限り子供の世話と家事に明け暮れた。
暁星の月のある夜、まぐさ桶で眠っている赤ん坊を置いて、ジョセアは家の外の小さな納屋に雑用をしに出て行った。風が吠えていた。彼女はマントをしっかりとかき寄せなければならなかった。牛の乳しぼりをして餌をやり、豚と鶏にも餌をやった。納屋を出て激しい吹��の中に歩き出した時のことだ。風が激しく吹き上げ、彼女は納屋から少し離れて道のそばにある家さえ見えなくなった。それでも彼女は自信に満ちて家の方に歩いて行った。
彼女は生まれてからずっとこの家に住んでいるし、こんな突然の激しい嵐に会ったことはない。とはいえ、この辺りのことは隅から隅まで知っていた。彼女の足元には2インチほど雪が積もっていた。彼女がどうやら家を通り過ぎてしまったに違いないことを把握するまで、彼女は時折風に抗った。彼女は向きを変えて自分の足跡をたどろうとした。再び家を目指す前に納屋に行けば、少なくとも温まれるからだ。しかし、あまりに多い降雪が彼女の足跡を目の前で消してしまい、彼女は迷ってしまったし、とても寒かった。
ジョセアはそれでもあきらめなかった。家と納屋でなければ、玉石でも木でも道でも何か目印になるものに行き会う希望を持って進んだ。彼女の手足は濡れて感覚が鈍っていた。眉とまつげには霜がつき、厚着をしていなかったために骨の芯まで冷え切っていた。
「ティミー!ティミー!!」彼女は子供の名を呼んだ。赤ん坊が目を覚まして泣けば、その声を追えることを期待していた。凍り付く空気を吸い込みながら、彼女は立ち止まって耳を澄ましたが、風が吠える音しか聞こえなかった。風の音、あるいはそれ以上の何か?灰色の影が彼女の前に現れ、細めた黄色い目で彼女を見つめていた。巨大な灰色狼だった。
彼女は心臓が止まりそうになった。なすすべもなく一人で家の中に横たわる子供と、家の外で死んだ母親のことを考えると、彼女の目に涙が浮かんだ。なんて不運なのだろう、安全な場所のすぐそばで死ぬなんて!不運。だが、彼女はずっと不運だった。自分が知る中で最も不運な女だった。その考えが彼女を訪れたのは数日前だったかもしれない。彼女は疲れ切って膝をついた。狼は彼女の前に座り、その頭を後ろに振って、恐ろしい遠吠えをした。
狼の群れの前には何の役にも立たない棒きれか石を探して、彼女の凍えた指が雪の中を必死で探った。もう一つの黒い影が、渦巻く白い雪の中から現れた。彼女は狼狽して後ろに飛びすさった。この影も灰色だったが、背が高くて二本足で、灰色のマントを着てフードをかぶっていた。その手袋をした手が伸び、狼の頭をぽんぽんと軽く叩いた。彼女の悲鳴は喉のところで止まった。
「恐れる必要はない、お嬢さん。危害は加えない、決してだ。あなたは子の母かね?」
彼女はぼんやりと頷いた。風が唸りを上げる中で、彼の声は深みがあり、親切で、澄んでいた。しかし、彼女の眼は彼の恐ろしいお付きに向いた。
「恐れる必要はない」彼は繰り返した。「ここにいるわが友グレランが、無事に我々を導いてくれよう。あなたがここで夜を過ごしたいのでないのなら」彼の手が彼女の手に伸びて助け起こすと、彼女はその腕にもたれかかって、彼のそばでよろめいた。
ようやく彼女の家の戸口に着くと、彼は言った。「ここに留まって嵐をやり過ごしたい。構わないだろうか?」
彼女に断れるだろうか?男も狼になり得るが、仮にそうでも、答えとしてとにかく否定は受け入れないだろう。「ど、どうぞ、入ってください。わた、私、やかんをひ、火にかけっぱなしで、今頃は空っぽに違いないわ」彼女は呆けたように言った。
「私は中に入ったのだ。戸を叩いても応えがなかったのでね。そして、赤ん坊が一人で眠っているのと、やかんが沸き立っているのを見つけた。やかんは火から下ろしておいたが、赤ん坊はそのままにしておいた。母親が遠くに行っていないのはわかっていた。それでグレランを探しにやったのだよ。運が良かったが、私が常に周囲の者に幸運をもたらすとは限らない」
彼がフードを後ろにずらすと、彼女は彼が長身で青白い顔をしていて、銀色の髪と瞳を持っていることがわかったが、若者の顔をしていた。彼の顔つきは残忍そうではあるものの、銀色の目は優しげで、口元は穏やかだった。「私の馬も今晩は避難所が必要になろう。彼にも手を差し伸べてもらえるだろうか?」
彼が馬をつないでいる間、彼女は濡れた服を着替えて彼らのためにささやかな夕食をこしらえた。スープとパンとチーズ、それにエルムルートのお茶だった。皿に盛り付けると、彼女は粗末な返礼を詫びた。
「いやいや、これは私のやったこととは比べ物にならないごちそうだ!」彼は微笑んで、むさぼるように食べた。グレランは火のそばに寝そべって、時折ひと口投げてくれる主人をずっと見ていた。「彼が昨夜たくさん食べたのは、ここの鶏たちには幸運だったね。さもないと、あなたから一匹買わねばならない羽目になっていた」
「いいえ、いいんです」彼女は抗議した。「本当にお世話になったし、分けてあげられるものがあるのが嬉しいんです」その時、赤ん坊が身じろぎをして泣き出した。そして彼女は彼を抱き上げ、濡れたおむつを替えて乳を含ませた。
「ご主人は?」
彼女は一瞬口ごもった―見ず知らずの人間に、自分がいかに孤独で、守られていないかを話すべきではないという考えが頭をよぎったのだ―そして、本当のことを話した。
「悲しい話だ、本当にね」彼は言った。「だが、彼はあなたに端正な子を遺した。そして、あなたはここで極めて快適に見える」彼の目が質素なひと部屋きりの小屋を見回した。まぐさおけと、彼女の母が縫ったキルトのカバーが掛かった羽毛布団のベッドが片方の端に、もう片方には石組みの暖炉、中央には父が作ったテーブルと椅子がある。はしごの上には、彼女が子供の頃に眠っていた屋根裏がある。突然、この簡素な部屋が、彼女には宮殿のように見えた。彼らは温かく、からっと乾いて、満たされたお腹で過ごしている。本当に、これ以上何を願えるだろう?
「ええ、おっしゃるとおりですね。結局、私って運がいいんだわ。それじゃあ、あなたのことを何か聞かせてもらえませんか?」
「ある意味、私はあなたより幸運に恵まれていない。私は放浪者で、そのように生まれ付いた旅の何でも屋だ。大抵のことはできるがね。結婚したことも、子供を持ったことも、私の馬が引いているワゴン以外に家を持ったこともない。一つのところに長くとどまったこともない。両親は私をサイと名付けたが、大抵の者は、私をラッキーと呼ぶ」
「それなら、ラッキーと呼びますね。だって、あなたは本当に私にとって幸運だったもの」
彼は立ち上がって背伸びをし、テーブルから食事の残りを片付けた。洗い桶に銅のやかんから水を注いで皿を洗い、乾かした。彼女は男がこのようなことをするのを見たことがなかった。授乳が終わり、彼らは暖炉の前のラグの上で赤ん坊と遊んだ。その間、彼は旅の中で行き合った不思議ですばらしい土地や人々の話をした。すると、彼女は再び自分の生活がとても狭苦しく、色あせたものに思えた。1、2時間して赤ん坊が飽きてむずかると、彼女は赤ん坊を膝の上に乗せて、眠るまで歌を歌って聞かせた。まぐさおけに彼を寝かせると、うさぎの毛皮でできた祝い旗で温かくくるんだ。
暖炉に戻ると、ラッキーは彼女に手を伸ばし、少しの間言葉もなくその手を握っていた。やがて互いに抱き合い、むさぼるような口づけをした。彼らは服を脱ぎ、恥ずかしげもなく並んで身を横たえ、揺らめくばら色の炎の光の中でお互いの体を愉しんだ。彼は彼女の胸と太ももの、腹と臀部の丸さを愛おしみ、りんごのように瑞々しいと言った。彼のやせて筋肉質な真っ白い身体と絹のような髪に、彼女も同様に魅了された。彼女はトムを愛していたし、彼との快い時間も知っていたが、この見知らぬ男に感じたものとは比べ物にならなかった。
朝、彼女はいつものように赤ん坊の泣き声でベッドで目を覚ました。ラッキーはそこにはおらず、彼は鮮やかな夢だったに違いない、と彼女は考えた。するとドアが開いて閉まり、そこにいるようにと手で示して、服を着こんだ彼が彼女に歩み寄った。彼は彼女の唇にキスをして、それから赤ん坊を連れて来て、乳を飲むのを見ていた。「一度知ってしまった歓びを覚えていないのは、まったく残念なことだ」
「でも、私たちの歓びはまだ思い出せる」そう言うと、彼女は自分の大胆さに頬が染まるのがわかった。「彼は私をなんて淫らな女だと思ったに違いないわ!」彼はそう言って、彼の冷たい手を彼女の火照る頬に添えた。
嵐は夜のうちに��ぎ去ったが、道には雪が降り積もっていて、馬がラッキーの小さなワゴンを引くにはあと数日かかることは明白だった。そのワゴンは明るい色で塗られ、葉っぱと蔓と花が赤と青と緑と黄色で描かれていた。車輪は赤、スポークは黄色だった。帆布の幌にも青地に白いふわふわした雲が描かれていた。ジョセアはそのワゴンがとても好きだったが、灰色づくめの静かなラッキーには奇妙な取り合わせだった。
ラッキーは彼女のためにいくらかの働きをした。道具や蝶番、家庭用品を修繕し、今年使い切れなければ来年に置いておけと言って、彼女のための薪を作った。彼は1週間留まり、雪融けが来て凍結し、道路にはわだちがあったが、旅には適していた。彼は朝日の中で互いに見つめ合い、彼は彼女が自分に飽きていないのなら、もう1日か2日留まっても支障はないだろう…と言った。彼女は飽きてはいなかった。
その1週間後、ラッキーは彼女に一緒に来ないかと言った。彼女はその質問に嬉しさで跳び上がったが、彼女は人生のすべてを過ごした小さな家を見渡して、自分の国と村と赤ん坊のことを考えた。そして、「私は行けないわ。旅をしたいとは思わないし、この子を連れて行って宿無しの子供のようにはしたくないの」
ラッキーの青白い顔に痛みが閃いたが、彼はただ頷いて馬に手綱をつけ、彼女にお別れの口づけをした。涙が彼女の目に溢れて、けばけばしいワゴンの色が滲んだ。
雪とみぞれと雨が降る薄明の月はゆっくりと過ぎたが、あの日彼女にラッキーをもたらしたような嵐はやってこなかった。時折ドアを叩く音がすると、彼女の心臓が高鳴って身体をビクンと震わせたが、それはいつも、彼女が売っている干した薬草を求めに来た、ただの村人だった。蒔種の月の最初の晩、彼女は聞き覚えのあるワゴンの軋みを聞いた。彼女はドアに駆け寄り、明かりが灯ったような表情で、彼の腕の中に飛び込んだ。
「長くはいられない」彼は言った。「ただ通りがかっただけだ―」そのごく短い間、二人が交わした言葉はそれだけだった。
春が来て、クロッカスが雪の下から顔をのぞかせた。ラッキーは彼女の庭にすっかり踏みすきをかけた。物見高い隣人たちが訪ねてきたが、彼女が彼について何も知らないことがわかった。彼女は彼らに卵と―彼女の鶏はとてもよく卵を産んだ―干した薬草と、祖母のレシピから作った錬金薬を売った。それは頭痛とリウマチにとてもよく効いた。彼らは疑念を持ちながらも、庭仕事にラッキーを雇い入れた。
決してどこに行き、いつ戻るとも言うことなく、ラッキーは彼女の下を訪れては去る生活を続けたが、数日以上離れていることはほとんどなかった。彼は愛の言葉をささやくことはなかったが、いつでも同じ激しさで彼女を愛した。ジョセアの丸いお腹はさらに丸みを増し、ティミーを離乳させて牛乳を飲ませた。ラッキーの旅は短くなり、頻度も少なくなった。国中が繁栄した。一番年かさの者さえ、その年以上の収穫を思い出せなかった。薪木の月に、ジョセアは銀色の髪と、矢車草の色の目をした美しい女児を生んだ。ラッキーが彼女を抱くと、喜びが彼の全身から溢れ出して、燃え上がる白い炎のように見えた。
2 notes
·
View notes
Text
エドワード王 十一巻
昔日の王の一代記 十一巻
ロスガー山脈のふもと、レイヴン・スプリングと呼ばれる小さな村の、狭いけれど快適な宿屋で、コンパニオンたちは、一晩を過ごしました。翌朝彼らは東に向かう旅を再開しました。スカイリムとハマーフェルの国境に向かううねる丘を越え、次の2晩は澄んだ初夏の晴れた空の下でキャンプを張りました。彼らが旅を再開した3日めの朝、モラーリンは道の北側の斜面を見て、皆に南西に面している高い牧草地に通じる切り込みがあるのを見るように言いました。一団が突き出した岩の周りを曲がった時、ほぼ同時に全員がそれに気づきました。
シルクとビーチが適切なルートの偵察と、今夜のキャンプ地を探すために先行しました。黄昏までには、彼らは草地までの半分近くの道のりを終えていましたが、翌朝まだいくつかの崖を登らなければなりませんでした。もう一度キャンプを張る頃合いだと意見が一致しましたが、幸いにも翌日のお昼時にはピクニックができそうでした。
翌日の正午、それは年央の月5日の土曜日でしたが、アカトシュともう一匹のドラゴンが加わった仲間たちは、ドラゴンの村の草が生い茂る斜面で腹ばいになっていました。この二匹目のドラゴンはアカトシュよりも小さく、雌のように見えました。性格上、アカトシュはただそのドラゴンをデビュジェンと紹介しただけで、それ以上の説明はありませんでした。二匹のドラゴンは、人類たちと礼儀正しくおしゃべりをしながら自分たちの過去を懐かしんでいましたが、少し経つとデビュジェンは飛び去り、優雅に空を弧を描いて飛び、少し離れた草の茂った野原にいる雄の子牛に飛びかかりました。
アカトシュはこれに対するエドワードの反応を観察していて、そしてたずねました。「なぜしり込みをしたのだね、エドワード?このところデビュジェンは食べていなかったし、ただお前たちが今しがたしていたのと同じ振る舞いをしていたのに」
エドワードは少し微笑んで答えました「僕たちの食事はあんな風に野蛮じゃないと思うんです」
アカトシュは笑顔を返しましたが、やがて返答しました。「それはいい警告だ。我らは、同じというより似ているだけだという」
エドワードは口を閉じて真昼の太陽に目を細めました。それからドラゴンに向き直りました。「アカトシュ―どうしてあなたの村にこの場所を選んだのですか?」
「さて、山の中にあり、高さも十分で、我らにふさわしい。その上、家畜を育てるのに充分に平坦だ…鹿のための木もある…そして、我らすべてにとって、非常に防衛的だ。ここには人間が牧場と農場を作る場所もあるし、エルフたちは断崖の端の厚く茂った木々の中なら極めて快適だ。崖の表面を囲む坑道は、内部の鉱山にある我らのねぐらへの通路になる。全体として、多くの生き物の種族を含んだこのような実験を行うには、理想的な場所だ。その上、南西に面していることで、小さな生物たちを気温の低い月の間の要素から保護するのに合理的な暖かさも供給される」
エドワードが答えました。「真ん中に建物が集まっていない村って言う概念に慣れるのは難しいけど―多分、将来は発展するでしょうね。少なくとも、会議や社交のためのいくつかの建物は。それに、ここはきれいな夕陽が見られると思うな」
ドラゴンはまた笑って、そして答えました。「まったくそうだ。だが、ドラゴン族の中でそんなことに興味を持つのは我だけだ。そして、それは我らがこの場所を選んだ時には正当な考慮のうちに入っていなかった」それからもの思わしげに、「そのうちのいくつかを表す言葉を組み合わせられればいいのだが。数え切れないほどやってみようとしたが、結果はあまり…立派なものではなかった」と言うと、元気な調子に変わりました。「話は変わるが、人類のために会議場を建てるつもりにしている。取引と物々交換のための店を何軒かも」
モラーリンがぶらぶらとやって来て、腰を下ろして尋ねました。通常人類がドラゴンたちに見せる敬意の欠落は特筆すべきものでした。「こんなおかしな実験をしようなんて、何に憑りつかれたんだね、アカトシュ?」
ドラゴンは思慮深そうに間を置いてから答えました。「我が常に分析してきたように、この場合、ドラゴンの行動の歴史と言えるかもしれぬ。新しいオーレリアンの神々に対する抵抗の長い闘争は明らかに無駄なものであったが、我らがそのことを理解し、受け止めるには何世代もの時間を要した。そして、我らの次の様式は、互い同士からさえ孤立することであった。また、他のあらゆる存在からの侵入に対する抵抗でもあった。例外は、夫婦となり我らの種を再生産することだった。然りながら、その一つの活動を別にして、我らは我らの貴重な私生活を守るために戦ったのであるし、我らが特に頑固な種族であること以外には、何の正当性もなかった」
エドワードが言いました。「なら、理由がなくなってしまったずっと後も、その様式を維持してきたんですか?」
アカトシュは少し恥ずかしそうに見えました。彼は鼻をすするように言いました。「我はその通りのことを言ったと思う。我らだけがその餌食になる感傷的な生き物ではないのだ」
「アーチマジスターが多くの行動は生まれつきだって言ってました」エドワードが言いました。
モラーリンが彼に笑いかけました。「そして生まれつきの行動様式は、状態が変わるとゆっくりと変化する長命の種に顕著な問題なのだよ。お前たち短命種の人間以上に、我々エルフたちはそのせいで苦しんでいる。命は変化し、それに抵抗することになるにもかかわらず、我々がものごとをそのままにしておくのが好きな理由だ。ドラゴンはさらに長く生きる。エルフよりも長くだ。そして、結果として繁殖も遅い。しかし、社会的環境に生まれた変化が、良かれ悪しかれドラゴンの行動にどんな影響を与えるかは、誰にもわからないのだよ」
この時にはアリエラも会話に加わって、そして観察していました。「デイドラはドラゴンの行動に長らく喜んでいるに違いありませんわね」
アカトシュが答えました。「おそらくそうだろうが、我はこの提案のようなものとともに我らの…女王に接触を試みた。なぜなら、我らが種族として停滞状態に陥っていることは明らかのようであるし、我ら自身に活力を与えるために、この殻を破らねばならぬゆえに」
この時には、仲間たちは皆、声が聞こえる場所に座っていました。そしてマッツが尋ねました。「女王の許可が必要だったんですか?それと、いろんな種族との間にたくさんの困難を抱えてた?」
「許可はこの場合、極めて正確ではないな、マッツ。我らが存在している、それはなおさら、彼女が情報を手にできるように、我には彼女に伝える義務があったのだ。例を挙げるなら、他のドラゴンは軍事的な知識を求めて我を訪れる。従うことは準備を整えておくことと同一の哲学だ」
マッツはにやりと笑って言いました。「つまり、『念のため』ってことですか?だけど、エルフと人間については?」
「ああ、我が人類の王と淑女は、異なる姿かたちと習わしに対する敬意と忍耐の非凡な例となっておる。彼らはわが年若きブレトンの友エドワードと我とともに、寛大にも知識と技術を分け合ってくれる、ああ、私がここでの定住を試みるよう説得した鍛冶職人と鉱夫たちを貸し出してくれたモラーリンに感謝しているよ。ブレトンは、そうだな、多くのブレトンは、それが利益をもたらす限りは、長い間何事も徳を持って行ってきた。そして、そこから知識と技術を得ている。ノルドは個人の栄誉を渇望し、栄光がここで生産されたミスリルの鎧と武器をすばらしく利益のあるものにする―貴族以外には売らないことを主張するようになったアリエラは、まったくの天才であったよ―探索が新しいトンネルを開き、経路を提供してくれた―我らドラゴンが必要とするものに」アカトシュは少しずる賢そうに微笑みました。ドラゴンが何を必要としているかについて、彼はとても寡黙でした。「ビーチとウィローが、彼らの民にウッドエルフがここで歓迎されることを広めてくれている。ゆえに、長らく古来のハイロックのふるさとを追われた者たちが、この丘に戻ってきている」
「幸い俺は今公爵だから、ミスリルを着ることと持つことを保証されてる。あと二つばかり手に入れられたらなあ!だけど値段のせいで諦めなきゃいけないかも―」マッツが言いました
「諦めたらミスリルを手に入れられないぞ」モラーリンが指摘しました。
「俺の息子と娘はどうなんだ?その子たちのために、お前に土下座でもするか?」マッツが憤然として言いました。「俺の膝と呼吸がひと頃ほどじゃないのは認めるよ。どういうわけかここに残りたい誘惑に駆られてるのは事実で、俺は今ここにいる。だが、俺はまだ何にだって自分の斧を振るえるぜ!」
ミスが楽しそうに歯を見せて笑いました。「ノルドは勘定できないもんな。だからあいつらは利益でなく名誉と栄光を求めるんだ。名誉と栄光ってやつはあんまり多すぎて、人が指で数え上げるには向いてないからな。マッツ、もしお前が39歳だったら、俺が会ったか会ってみたいと思ってる人類の中で一番でかい10歳の人間だよ!」
「だけど、それなら探検も鍛冶もしないやつには何の利益があるんだ?」マッツが旧友を無視してこだわりました。「俺はこんな…別格の存在のすぐそばに住むのを怖がるやつがいっぱいいると思ったもんだ」最初の部分を言う時に、マッツは狡猾そうに笑いました。
「そうだな、一方ではその『別格の存在』の姿は、確実に手厚く守られていることを意味する。それに、この一帯は驚くほど肥沃で、作物がよく育つ…そして、彼らは我らのための肉を供給してくれるが、我らの食糧が占める割合は、彼ら自身が消費する分の五分の一だ。我らはまた、我が長らく疑念を持っていたことを発見してもいる―3組の種が組み合わさった場合、それぞれが孤立していると考える時よりも、より効果的に戦う―それは、それぞれの種が他の弱点を補強あるいは打ち消すからだ。少なくとも、ごく短期間でこの辺りのゴブリンが劇的に数を減らしていることは確かな事実だよ」
「その通りだ」エドワードが返事をしました。「モラーリンがモロウィンドでそう証明したよね」
「少しばかり友の助けを借りてね」モラーリンが認めました。「賞賛は享受するし、彼らが設定した基準よりも私が少々上のレベルにいるのは事実だが―時にそれは基準以上に標的のような気がするよ!」
彼の発言に笑いの波が応えました。エドワードはこだわります。「アカトシュ、あなたと他の仲間がここにいて、僕は自分の国の国境の守りが厚くなったと感じるけど、スカイリムは国境を西に動かす必要性に駆られる気がするはずだと思うの」
アリエラが尋ねました。「他のドラゴンたちにここに移ってくるよう説得するのは簡単でしたの?」
「実際に最も困難だった��は、我らの宝を新しいねぐらに���ぶことだった」アカトシュは怠惰な微笑を見せながら答えました。「蓄積した金属と、宝石や貴金属が役に立たないとわかると、すべてがうまく運んだ」でも、次にもっと深刻そうに言いました。「本質的に、我は他のドラゴンに個人的に近づかねばならなかったし、この考えには利益があると、彼らを…説得せねばならなかった。ここでもまた、我らのうちでも特に孤立した2、3の同類を説得してしまえば、ことを運ぶのか楽になった。しかし、この辺りに住んでいるのはたったの9体なのだ…そしてここには実際にあと2、3体分の場所しかない。今後の展開を見ずばなるまい」
アリエラが気が付いたように言いました。「今のドラゴンの行動を、神々と女神たちがとても好意的に捉えているのではないかと思いますわ」
「そうかもしれないな、アリエラ。だが、再び言うが、これはそのためではないのだ。しかも、彼らはまだ我らの長い敵対を覚えているかもしれぬ」
ビーチが恭しく尋ねました。「それより、この村の名前は何なのですか?」
アカトシュは嘆息して、やがて返答しました。「結論が出ることがないのではと恐れている。それぞれの種がそれについて意見を決めたゆえ。おそらく、最初の建設期間が完了すれば、そのような問題に関してさらに熟考できるだろう」
ビーチが応えました。「それは正しいことには思えません―どこにでも名前があるべきでは?」
ウィローがくすくす笑って言いました。「私たちにはそうだろうけど、ドラゴンがどう思うかなんて誰にもわからないわ。それに、人間とエルフは名前のスタイルだけじゃなくて、その詳細でも口論になるのは確実よ」
モラーリンがひどく劇的な調子で割り込みました。「エルフがとんでもなく頑固だと言っているのではないだろうね!?」そして議論は、彼らの中でひとしきりの笑いと揶揄の中に溶けてゆきました。
やがて、アカトシュが言いました。「我は『セクション22』という名が好ましい」
ビーチが彼を見つめました。「アカトシュ、詩作の難しさはよく知っていますよ。率直な意見を申し上げてもよろしいですか?それは私がこれまで聞いた中で最悪の村の名前です」
アカトシュは突発的にため息をついて、急いでビーチに詫びました―人類は、ドラゴンのため息は非常に不快で、時に本当に危険であることを発見しました。「ならば、我の意図がどう違うかわかっているのだな。我にとってはこれは大変意味があり、最も適切なのだ。『セクション16』ならもっといいのかね?違う?それなら、『セクション』という言葉が引っかかっているのかね?それは『砦』や『リーチ』や『峡谷』や『支配地』と比べてどう劣っているのかね?」
エドワードが言いました。「でもね、アカトシュ。名前は意味があるべきだと思うんです。少なくとも、人間はそう考えているよ。この場所を『22』にするなら、その前の21個のセクションがないと」
「本当?」アカトシュが言いました。「なぜだね?すべての数字は等価ではないのかね?一つの場所と他を区別するのに役に立つ。例えば、『グリーンヴェールズ』という村がいくつもあるかもしれん。そのような村を4つ知っている。『22』という数字は、魅力的だ…審美的にも。同様に、何らかの『意味』がある―少なくとも我には」
モラーリンが言いました。「アカトシュ卿は、我々が言うところの『内輪ネタ』を楽しんでいるんだと思う。私はドラゴンにそんなに無分別に教えたのだろうか―」
「モラーリンが分別がないなんて糾弾した人間がいるかしら?」シルクが言いました。
少しして、エドワードがアカトシュに尋ねました。「ちょっとだけ一緒に戦いのゲームをしてくれる?僕、ゲームの盤と駒を持ってきたんだ」
モラーリンが遮りました。「残念だが、アカトシュと私は今晩いくつかの件で話し合わねばならない―それに、お前はどうしたってまた負けるよ」彼は好ましい笑顔で付け加えました。
エドワードが返答しました。「だけど、僕は誰にだって勝てるんだよ…アカトシュ、僕があなたに勝つことがあるかしら?」
「ないね、エドワード、我に勝つことはないだろう」そしてアカトシュはエドワードの驚いた表情に少し混乱しました。そして、急いで心のこもった笑顔を見せました。
「あまり如才ない答えじゃなかったですね、アカトシュ。だけど、どうして僕は絶対に勝てないの?」
「我がお前よりずっと長い間やってきたからだ、エドワード。そして我が続ける限り、お前が追いつけることはないだろう。その上、このゲームは我が『有限の問題』と考え始めているもので、この類のものは最も簡単に解決できるものだ」
「その『有限の問題』ってのはどういうことです、アカトシュ?」マッツが尋ねました。
「起こりうる行動と結果を数えることができる問題ということだ、マッツ。このゲーム盤には81マスしかない、そして両軍は正確に27駒、それぞれの駒が特定の動きをする、そういうことだよ」
「だけど、そのゲームは本当の戦闘に似てるんじゃ?」スサースが尋ねました。
「いや、学習するにも、どのように戦闘を終わらせるかを考えるにも非常に良い練習になる―だが、我がエルフの射手は決して疲れることがないし、我がマスターメイジは常に私の求めることをする。現実の戦闘でそんなことはまず起こらぬ」
モラーリンが同意するように頷き、からかうようなずる賢さで尋ねました。「では、無限の問題の例は?」
「まさに現実の戦闘…だがまた、私にとっては詩が無限の問題だ」
「でも、すべての詩は分析できますわ、アカトシュ」アリエラがたしなめるように言いました。
「無論だ―だがそれは書かれたあとのこと。我はそれを書くという行いを決定し、あるいは固定することができぬ。だが…それは、創造する行いだ。もし我が詩を書き始めたら…可能性は数多くある」そして苦々しげに、「我は最初の1行を越えたことがない。なぜなら、1行目に書き込めるすべてのものを想像し始めるからだ…」と言いました。
2 notes
·
View notes
Text
イェフレ
神、イェフレの性質に関する黙想
エルフの村人が独りでその地を歩き、木々と星々の間の力の歌を歌う時、歌い手イェフレは彼らとともに歩んでいる。イェフレは森林の自然に注意を払い、せせらぎと小川の水音を楽しんだ。鳥たちに季節の歌を歌うことを教えたのも、川にきらきら光る音楽を教えたのもイェフレだった。過ぎし日々の夏の暖かい夜、彼の歌を聞くために、木々が自ら彼の近くに移動したと言われている。エルフの最初の偉大なバラードが作られたのはこの時であった。それを生んだのは、イェフレの生み出す生き生きとした音楽と、自然と損なわれていない森のバラードに戯れた森の若者だった。事実、彼は歌と森の神として信仰されている。
ヴァレンウッドでは、イェフレは深い森のある場所に寺院と祭壇を備えた主な森の神であると考えられている。エルフの言い伝えには、歌の才能を持って生まれた者は、イェフレ直々に祝福されているというものがある。伝説では、彼は自然と、とりわけ森に親しみを持つウッドエルフを祝福していると伝えている。ほとんどのウッドエルフがイェフレを信仰している。
彼の自然の美への熱意はサマーセットに彼を導いた。彼は巨大な海鳥に歌うことを教え、浜辺で砕ける波を囁きと力の歌に形作った。その歌で、砂浜や小川、河川や滝であっても、水から遠い場所にいても、イェフレはすべてを見、すべてを聞いているとハイエルフは言う。さらに、歌を教えてくれた返礼に、鳥たち自身がイェフレのために見張りをしているとも、イェフレはその島の美しさに見合う美しさで、ハイエルフを祝福しているとも言われる。
ダークエルフたちは、イェフレが最初の日の前に大地を歩き、星の光の下でとても美しい歌を編んだので、星自らが感動のあまり揺れたという伝説を持っている。この時と同じ星が、夜と闇の歌を思い出してまだまばたきしている。彼の影響力ゆえに、すべてとは言わないまでも、ほとんどのエルフの吟遊詩人はイェフレに敬意を払っている。
ものごとの自然の理が、ヴァレンウッドとサマーセット島のイェフレ寺院の基本である。イェフレが許さない一つのことは、ものごとの自然の理を有害に操作することである。
1 note
·
View note
Text
エドワード王 一巻
ダガーフォールを発った昔日の王の一代記
昔々、世界が芽吹きの季節だった頃のお話。レッドガードがタムリエルに来る前、そして偉大なセプティム朝が生まれる前。でも、ゴブリンがドワーフたちをハマーフェルから追い出したあとのこと。ダガーフォールのコーサイア王と、彼の妻ウェイレストのアリエラ女王の間に、息子のエドワードは生まれました。
ダガーフォールの深い青の海を見下ろす、風がよく通る丘の上にある王宮の果樹園で、幼い少年が横になってう���うとしています。ダガーフォールの秋にはつきものの霧は吹き散らされて、空はどこまでも深い青さを湛えていました。若き王子エドワードにとって、このような瞬間は稀少でした。彼が知っている他の貴族たちが話し相手を切望しているように、彼はひとりの時間を切望していましたから、今日の午後は、何日もそのためのはかりごとに費やした結果なのです。家庭教師は今頃彼が武術の課外授業に出ていると信じていましたし、武術の先生は狩りの師範と鹿を追いかけていると信じていて、狩りの師範はエルフの言葉を勉強していると思っていました。父親は、若い妻と息子たち、貴族の生活のプレッシャーに手一杯で、彼がどこにいるかも知りませんでしたし、気にも留めていませんでした…
落ちてきたりんごが頭をかすめ、彼は薄い灰色の目を開きました。鼻の中に甘い、すえたようなにおいがしています。彼はため息をついて空の青を見上げました。どうして物は上に上がらずに落ちてくるんだろう?ずっと空を見上げ続けていると、空に向かって落ちて行くような気持になるでしょう……黒い虹彩の縁が大きくなるにつれて、彼の眼は潤んで瞳孔が開きました。彼は体重を失って、漂って……、もう一つりんごが落ちてきて、彼の耳を掠めると、彼は地面にどさっと落ち、最初はあばらを、次に頭をぶつけて大きな声を出しました。絹糸のような笑い声が響きました。エドワードは驚いて口をぼんやり開けたまま、ぶっきらぼうに座って辺りを見回しました。10フィートほど離れたところに 馬に乗った 二人の男がいて、石から削り出したようにじっとして、ひたすら彼を見つめていました。王子というものは、そう簡単に怖がってはいけないのです。たとえそれが紳士的な心を持った類の相手であっても。でも、エドワードはこの二人組のような人たちを見たことも、想像したこともありませんでした。一人は金色の肌と目をして、金の縁取りがついた白い服に身を包み、またがっているのは(エドワードが瞬きをしても、それは消えずにまだそこにいました)ユニコーンなのです!ユニコーンの隣にいるのは金色の竜で、翼を行儀よく畳んでいました。そして彼の背中には、黒いチェインメイルを着て、身体の横にロングソードを提げた男が乗っていました。彼ははげ頭で、黒い顔に赤い目が光っていました…それに彼のとがった耳……「君たちはエルフだ!一体――!」
「彼は賢い子だ」ダークエルフは皮肉っぽい声をしていました。彼が完璧なブレトンの言葉を話していることに、エドワードは気が付きました。残りの部分がどこかおかしいようだと思ってはいたものの、彼の心はまだちゃんと動いていました。
「そうみたいだね。ほぼ彼自身の力だけであれをやったんだ。訓練を受けていない子供にしてはすごいな。私は彼が――集中するのをほんの少し手伝っただけさ」ハイエルフもブレトンの言葉を話しましたが、ためらいがちで、少し歌うような訛りがありました。エドワードの家庭教師が、エルフたちは人間の発音が得意でないと言っていました。
エドワードの視線は居心地のいい場所を見つけかねて、素早く彼の前の4つの存在に移りました。彼は手短に、ただひたすらに、これが夢であってほしいと願いました。彼の心は疑問と要求で湧き立っていたのです。すると突然、彼の舌が自由に動くようになりました。「だけど、僕はちっとも集中なんかしてなかった!僕の先生たちはみんな、僕が苦手だって――」エドワードは顎を固く引き締め、そして、はたとこのような者たちと言い合いをするのは賢明な振舞いではないかもしれないことに思い至りました。
でも、金色のエルフは完璧に白い歯を見せながら、口を大きく開けて笑いました。「確かにね」彼は、エドワードの肌に心地よい疼きを感じさせる、温かな寛大さを滲ませていました。それは、もうずっと前にいなくなってしまった母と一緒にいた時に感じたものでした。しかし、もう一人のエルフは無表情でした。まるで、エドワードの魂を突き刺すように、その赤い瞳で穴が開くほど彼を見つめていました。
「モラーリン!お前はモラーリン、魔女の王だな!」彼は立ち上がって、ダークエルフと向かい合いました。「お前は僕の母さまを盗んだ!父さまがお前を殺してくれる!」
「その通りだ。だが彼はどうかな?お父上を呼んで確かめてみようではないか?」ダークエルフは姿勢を正し、その眼をさらに輝かせました。小さな湯気の固まりがドラゴンの鼻から飛び出しました。彼のお供の体の周りに、輝くオーラが現れました。エドワードは、護衛を呼ぶつもりがないことはわかっていました。なぜ彼らが殺されなければならないのでしょう?この二人は何でも――できるように見えました。本当に突然、彼の恐れが消えました。もし彼らが自分を傷つけるためにここにいるなら、もうとっくにやっているのです。でも、やり場のない怒りの感情は残されたままでした。彼らが母親をさらったのです。そして今、――
「なぜここにいるんだ?」彼は強い口調で尋ねました。
「エドワード、私たちと一緒に来ないか?」ハイエルフが口を開きました。彼の声はそよ風のように涼しげで、火のそばにいるように暖かく、竪琴の調べを聞いているようでした…
少年は立ち尽くしていました。自分自身の楽しみのために、一緒に行くと言いたくて仕方がなかったのです。もし母に会えるなら、と尋ねたいと思いましたが、その代わりに「父さまが―」彼は呻きました。
「間違いなく君を恋しがるだろうねえ」モラーリンの言葉の奥には皮肉がこもっていました。その声は、冬の太陽に溶け落ち、弾けるつららを思わせました。でも、彼の眼には飢えのようなものがありました。あるいは、切望でしょうか?
彼の父親は彼を恋しがらないでしょうし、彼はそれを知っていました。恥ずかしさが少年の中を��け巡りましたが、彼は顔を上げて恐れげもなく、肩幅の広いエルフの顔を見ました。「お前は僕の父親なのか?」エドワードはこの問いかけでエルフの皮肉にお返しをしたつもりでしたが、彼の手は、まるでその一部のように耳に這い寄っていました。寛大な赤毛の父に似ず、彼は癇癪もちでした……ロアンは彼によくエルフのようだと言っていました。
重苦しい沈黙が続き、エドワードはモラーリンが彼の質問を言葉通りに受け止めたものの、彼が次に言うべき言葉を見つけようがないことを感じ取りました。彼は都合のいい答えを言うのでしょう。ですが――。
「いや」残念そうな声でした。もちろん、嘘をついているのかもしれません。でも、エドワードは深い安堵を感じました。
「母さまは他に――息子がいる?」急に、エドワードはそんなものがいないこと、その質問がダークエルフを傷つけることを知りました。それは嬉しいことです。
「ことによると、お前の母親は死んだかもしれん。お前の知ったことではないようだが」ダークエルフの細い鼻が、まるでエドワードが悪臭を放っているように歪み、口の周りの皺が深くなりました。
彼女は死んでいませんでした。エドワードは知っていたのでしょう。モラーリンの軽蔑は、辛辣で不正なものでした。「母さまがお前たちを僕のところによこしたのか?」
「私を使いっぱしりの小僧だとでも思っているのか!」彼はぴしゃりと言うと、連れに向かって話しました。「彼を捕まえて行こう。あとのことは空いた時間に話せばいい」
金色のエルフは片手を上げました。「抑えろ、いとこ殿」そしてエドワードに言いました。「さて、坊ちゃん、一緒に来るかい?」
若い人間に飢えたエルフたちが人間の子供をさらうという恐ろしい話が、巷間で語られていました。
「僕は君の名前も知らないんだ」エドワードが急場をしのぐように言いました。
「ここでの生活がそんなに好きなのかな?」
エドワードは遠くの王宮を見ました。その上に気だるげに旗がなびいています…城下の街、輝く湾、遠くの山々を。「ダガーフォールが好きだ」
「ああ、戻ってきて治められるだろう、エドワード王子。私はアイリック・ハラド・エガン、アーチマジスターだ。誓ってもいい」モラーリンは振り返って、エルフの言葉で厳しく抗議しました。ドラゴンは小さな炎を吐きましたが、ユニコーンは動じませんでした。その金色の目はまっすぐにエドワードを見つめていました。「ユニコーンはいかなる嘘も許さないよ」その言葉は、母の声となって彼の心に漂いました。
「アーチマジスター、アイリック・ハラド・エガン、一緒に行くよ」
「君はモラーリンの方に乗ってもらわなきゃいけない。アカトシュ卿はこの――必要性に同意してくれている」エルフはドラゴンに向かって、手で払うような仕草をしました。
当然、彼はユニコーンに触るには適していませんでした。「じゃあ、それでいい。僕の――僕の犬は連れて行けないよね?」彼はどこにいるのでしょう?シャグはいつも彼のそばにいたのです。草の上で眠っていました!のんびり屋のシャグったら。エドワードは膝をついて彼に触れました。エルフの言葉の過熱した議論は続いています。その間にドラゴンが炎で草を焦がしました。モラーリンが鞍から降りて、さも嫌そうにシャグを拾い上げました。「よろしい、だが、アカトシュの忍耐には限りがあることを警告しておいてやる。さあ、乗れ」
「アカトシュ卿、あなたのご厚意に心から感謝いたします。このご恩に報いることができるなら――」
「できるさ」モラーリンが割って入りました。彼はエドワードのベルトを掴み、ドラゴンの背中に投げ上げました。エドワードはドラゴンの首と翼の間に座り、眠っているシャグは彼の前でだらりと横になっていました。「ここには充分な場所が――」エドワードが口を開くと、ドラゴンが彼の下で身体を動かして大きくなりました。エドワードが驚いて体をぐっと引きました。ドラゴンは本当に、とても大きくなりました。モラーリンは鎧の効果で大きく飛んで、彼の後ろに陣取りました。ユニコーンは9フィートの壁を華麗に飛び越えました。ドラゴンは大きな羽根を伸ばして屈みこむと、大空へと飛び上がりました。乗り手たちは大きく揺れました。エドワードにはわからないエルフの言葉でダークエルフがぼそぼそと何かを言うと、彼らは安定しました。羽根は力強く空気を叩き、ドラゴンは砦の上を低く旋回してゆっくりと高度を上げて行きました。今になって人々が走り寄ってきて、指をさして大声で何か言っています。エドワードは年老いた世話係を見て、手を振って叫びました。「さよなら!さようなら!きっと戻ってくるから……!」世話係が叫びながら近くにいた人の腕を掴んでいる間、弓兵が撃った矢が虚空を通り過ぎて行きました。コーサイア王は裸に戦の装備を着て駆け付け、大声で叫んで拳を振り回しました。「この悪餓鬼め、戻ってきなさい!お前の無価値な命の一インチに至るまで鞭打ってやるぞ!モラーリン、降りてきて当たり前の人間らしく私と戦え」
モラーリンの大きな笑い声は、寺院の鐘のように澄み切って響き渡り、砦中に流れました。彼は叫びました。「喜べ、俺はやらんぞ!肝っ玉の小さいちっぽけな王め!」ドラゴンはむしろだるそうに旋回して、大きな炎の固まりを吐き出しました。矢はその金色のうろこに当たっても傷つけることなく、チリンと音を立てて堕ちました。「母さまに会いに行くの!」エドワードは下に向かって叫びました。継母と、彼女の赤毛の息子たちは顔を上げることもしません。ロアンは毛皮の縁取りをしたローブを両手でかき寄せましたが、その髪は風になびくままになっていました。モラーリンのものではない四組の目が、怒りと憎しみで細められ、きらきらと光っていました。エドワードは手を振るのをやめ、両手でシャグをしっかりと抱きしめました。モラーリンの鎧を着た腕は、彼の腰のところに収まっていました。エドワードは彼の方に倒れ込み、本当に久しぶりに、そして初めて、本当に安心した気持ちになりました。弓兵たちは射撃をやめ、ほとんどの者たちは王族を見ていました。王は怒りに身を躍らせていました。巨大なドラゴンの翼はより激しく空気を打ち、彼らは海を越えて南を目指して飛んでいきました。
「エボンハートに行くんじゃないの?」少年は辺りを見回してモラーリンを見上げました。「お母上がサマーセットのファーストホールドでお前を待っている、小さな王子さま」
「なぜ僕をさらうのにこんなに長いことかかったの?」
「めんどくさい子だな。ユニコーンとドラゴンがエルフや人間の命令を聞くと思っているのか?お前の母上は完全に自分の意思で私のところに来たが、お前を連れてくることはできなかった。父親の部下がすぐそばでお前を守っていたからな。力ずくでお前を連れて行くのに、自分の国を荒れ地にさせるか?彼女はお前が安全に、面倒を見てもらっていると思っていた…そして、彼女は絶望したのだ。これはドラゴンの計画だった」
午後に起きたすべての驚くべき出来事の中でも、これは最も驚異的なことでした――彼の家族の誰一人そんなことはないのに、ドラゴンが彼に興味を持っているなんて。でも、自分の意思で、とエルフは言いました。完全に、自分の意思で、と!
「お前は大きな出来事の中心なんだよ、坊ちゃん。お前の仕事は、王になる準備をすることだ――お前の民のような者たちが聞いたこともないような王にな。我々の仕事は、お前を手助けすることだ。さあ、眠りなさい」
エドワードの精神を、続々と眠気の波が襲います。「でも――」彼はモラーリンに母親のことを聞こうとしたのですが、最後の波はとても大きく、彼の上で弾けると、彼は暗い炎を吐く夢に滑り込んで行きました。
1 note
·
View note